サイズが 480KB を超えています。500KB を超えると書きこめなくなるよ。
聖書 Part9
▼ページ最下部
地球人類社会において、四書五経こそは、ここ2500年の長きにわたって、わざわざ
特筆するまでもないほどに標準的な聖書としての、その地位を守り続けてきている。
その理由は、四書五経が「社会統治の聖書」であるからで、その他の用途に
用いられる諸々の聖書一般と比べれば、書物活用の場でもある世の中全体を司る
聖書である点において、やはり別格級の存在意義を持っているからでこそある。
夏・殷・周の三代に渡る古代中国の治世のあり方を、春秋時代に孔子が五経として体系化し、
その孔子自身や弟子や亦弟子(孟子含む)の言説を取りまとめた四書がさらに朱子に
よって権威化された。両者を合わせて「四書五経」というが、四書五経は宋代に定型化された
儒学正典の代表書というまでのことで、これに漏れた「孝経」「周礼」「儀礼」「大載礼記」「国語」
などの儒書も、四書五経に勝るとも劣らない聖書として扱ってもまったく差し支えないもの
となっており、四書五経を含むこれら全ての聖書が、実際に天下国家全土における治世を
実現していく上でのマニュアルとなるに相応しいだけの、十分な度量を備えている。
実際に、当時世界最大規模の国力を誇った漢帝国や唐帝国や宋帝国、
死刑一つない治世を実験した平安朝や、識字率世界最高を誇った江戸の日本
などにおいて、四書五経に代表される儒学の聖書こそは、権力者から庶民に
至るまでの、「必須の教養」としての扱いを受け続けていたのだった。
四書五経の記述に基づくような治世が実現されて後に初めて興隆する、儒学以外の高度な文化
というものもまた別に多くあり、むしろそちらのほうが治世実現後の世の中における「花形」
としての扱いを受けたりもする。唐代における詩文芸の興隆や、宋代における禅仏教の興隆、
平安時代における密教文化や女流文芸の興隆、江戸時代における武芸文化や演劇文化の興隆などが
その好例であり、そのような人々を楽しませることにかけてより秀でている文化の興隆を実現する
「縁の下の力持ち」としての役割をも儒学は担って来たから、必ずしも目立つ存在ではなかった
せいで、あまり人々にその偉大さを意識されることすらないままでいることが多かったのだ。
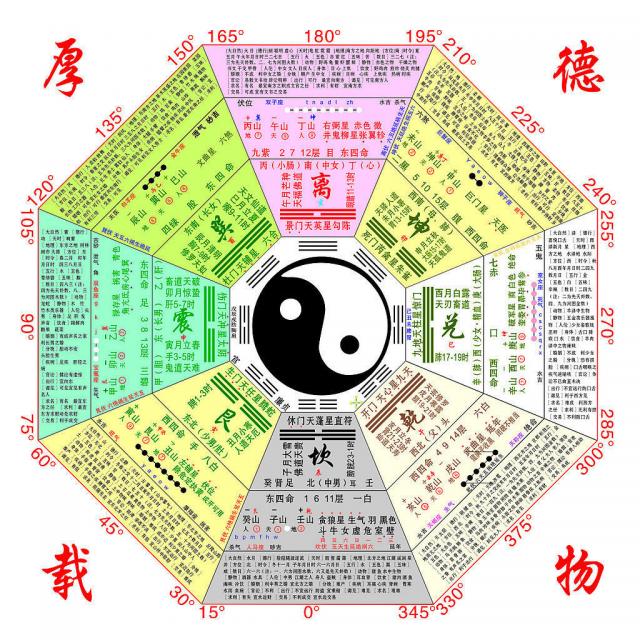
特筆するまでもないほどに標準的な聖書としての、その地位を守り続けてきている。
その理由は、四書五経が「社会統治の聖書」であるからで、その他の用途に
用いられる諸々の聖書一般と比べれば、書物活用の場でもある世の中全体を司る
聖書である点において、やはり別格級の存在意義を持っているからでこそある。
夏・殷・周の三代に渡る古代中国の治世のあり方を、春秋時代に孔子が五経として体系化し、
その孔子自身や弟子や亦弟子(孟子含む)の言説を取りまとめた四書がさらに朱子に
よって権威化された。両者を合わせて「四書五経」というが、四書五経は宋代に定型化された
儒学正典の代表書というまでのことで、これに漏れた「孝経」「周礼」「儀礼」「大載礼記」「国語」
などの儒書も、四書五経に勝るとも劣らない聖書として扱ってもまったく差し支えないもの
となっており、四書五経を含むこれら全ての聖書が、実際に天下国家全土における治世を
実現していく上でのマニュアルとなるに相応しいだけの、十分な度量を備えている。
実際に、当時世界最大規模の国力を誇った漢帝国や唐帝国や宋帝国、
死刑一つない治世を実験した平安朝や、識字率世界最高を誇った江戸の日本
などにおいて、四書五経に代表される儒学の聖書こそは、権力者から庶民に
至るまでの、「必須の教養」としての扱いを受け続けていたのだった。
四書五経の記述に基づくような治世が実現されて後に初めて興隆する、儒学以外の高度な文化
というものもまた別に多くあり、むしろそちらのほうが治世実現後の世の中における「花形」
としての扱いを受けたりもする。唐代における詩文芸の興隆や、宋代における禅仏教の興隆、
平安時代における密教文化や女流文芸の興隆、江戸時代における武芸文化や演劇文化の興隆などが
その好例であり、そのような人々を楽しませることにかけてより秀でている文化の興隆を実現する
「縁の下の力持ち」としての役割をも儒学は担って来たから、必ずしも目立つ存在ではなかった
せいで、あまり人々にその偉大さを意識されることすらないままでいることが多かったのだ。
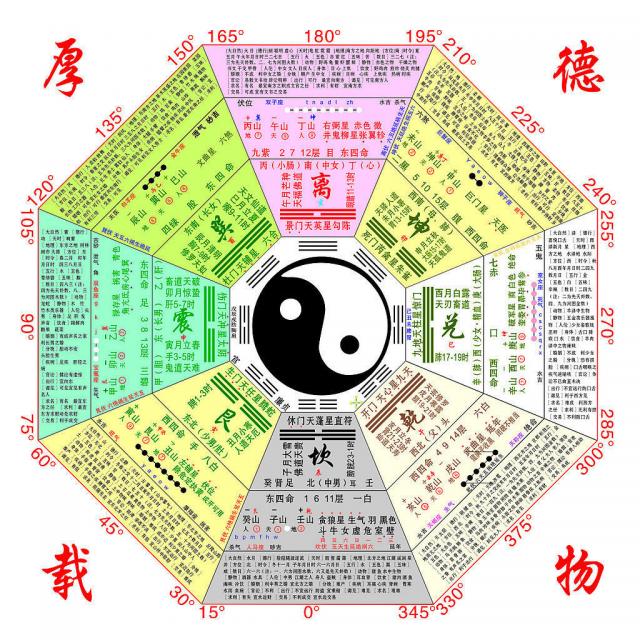
実際に、全世界を穏便に統治できる程もの度量があればこそ、儒学は治世実現後の世の中においてまで
そんなに自己主張に専らであったりしない。キリスト教なんざは、ただ世界征服を目指すだけで、
征服後の世の中はかえって最悪の争乱や破滅に陥れてばかりだから、そんな度量は一切持てず、
「征服したことに意義があった」みたいながなり立てを行うことで、自分たちの有害無益さ
に対する文句を騒音によって打ち消すことを、延々と試み続けていかなければならない。
儒学は決してそんなことはなく、その教学の優良さによって、着実に世の中をマシ以上な
治世へと導いて行くから、治世実現後には殊更な自己主張も控えて、乱世再来を防ぎ止める
ための義務的な儒学の勉強を人々に促す程度の粛々とした態度でいるようになるのである。
自分たちが縁の下からクリエートする世の中こそは最大級の治世をも獲得できるのだから、
儒者が自分たちから理念面での社会統治者としての立場を譲ったりすることを是とするわけもない。
法家心酔者の始皇帝に生き埋めにされた儒者や、乱世の荒波に飲まれて打ち首にされた吉田松陰などが、
儒学による社会統治の譲渡などを進んで容認していたような事実も当然ないわけで、儒学に基づく
統治が叶わない世の中において、仕方なく外野に甘んじるということはあっても、決して好き好んで
治世の企画者としての自分たちの立場が追われることなどを欲していたりはしないのである。
「滅国を興し、絶世を継ぎ、逸民を挙げれば、天下の民、心を帰せん」
「すでに滅びたような国も興し、絶えた家も受け継がせて、世捨て人も取り上げるようにすれば、
天下の人々もみな心から帰服するだろう。(乱世の支配者としての立場を受け継いだりするよりは、
乱世のせいで絶えてしまったような家を受け継いで復興させていくほうが、遥かに重要であろう。
ちなみにこれは周代の言葉であり、この直前に乱世をもたらしてしまった殷朝が滅亡している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・堯曰第二十・二より)
そんなに自己主張に専らであったりしない。キリスト教なんざは、ただ世界征服を目指すだけで、
征服後の世の中はかえって最悪の争乱や破滅に陥れてばかりだから、そんな度量は一切持てず、
「征服したことに意義があった」みたいながなり立てを行うことで、自分たちの有害無益さ
に対する文句を騒音によって打ち消すことを、延々と試み続けていかなければならない。
儒学は決してそんなことはなく、その教学の優良さによって、着実に世の中をマシ以上な
治世へと導いて行くから、治世実現後には殊更な自己主張も控えて、乱世再来を防ぎ止める
ための義務的な儒学の勉強を人々に促す程度の粛々とした態度でいるようになるのである。
自分たちが縁の下からクリエートする世の中こそは最大級の治世をも獲得できるのだから、
儒者が自分たちから理念面での社会統治者としての立場を譲ったりすることを是とするわけもない。
法家心酔者の始皇帝に生き埋めにされた儒者や、乱世の荒波に飲まれて打ち首にされた吉田松陰などが、
儒学による社会統治の譲渡などを進んで容認していたような事実も当然ないわけで、儒学に基づく
統治が叶わない世の中において、仕方なく外野に甘んじるということはあっても、決して好き好んで
治世の企画者としての自分たちの立場が追われることなどを欲していたりはしないのである。
「滅国を興し、絶世を継ぎ、逸民を挙げれば、天下の民、心を帰せん」
「すでに滅びたような国も興し、絶えた家も受け継がせて、世捨て人も取り上げるようにすれば、
天下の人々もみな心から帰服するだろう。(乱世の支配者としての立場を受け継いだりするよりは、
乱世のせいで絶えてしまったような家を受け継いで復興させていくほうが、遥かに重要であろう。
ちなみにこれは周代の言葉であり、この直前に乱世をもたらしてしまった殷朝が滅亡している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・堯曰第二十・二より)
えらく高評価だけど、本家である中国がなぜこの体たらく?
ヴァカにかまうと。。。><
「体たらく」も何も、完全に実力で世界を席巻しにかかってんじゃねえか。
ただ、そのあり方が今の日本などにとっては好ましくないだけで。
「国際協調」なんてものが単なる偽善に過ぎないことも、
中国人は長年の実地経験から知り抜いている。
諸国を統べる帝王を立てないことには、国同士での仲良しや仲違いが、
政商や縦横家にとっての格好の餌食になるだけでしかないとも知っている。
そうとも知らず、日米安保なんかに頼りきりでいる今の日本のほうが、
現実の外交セオリーを全く解さない愚か者の集まりとなっている。
ただ、そのあり方が今の日本などにとっては好ましくないだけで。
「国際協調」なんてものが単なる偽善に過ぎないことも、
中国人は長年の実地経験から知り抜いている。
諸国を統べる帝王を立てないことには、国同士での仲良しや仲違いが、
政商や縦横家にとっての格好の餌食になるだけでしかないとも知っている。
そうとも知らず、日米安保なんかに頼りきりでいる今の日本のほうが、
現実の外交セオリーを全く解さない愚か者の集まりとなっている。
職種別の社会的な害益の度合いでいえば、
君子士人(権力道徳者)>農業従事者≧必需工業従事者>無職≒0>ガラクタ工業従事者≧商業従事者>犯罪者>権力犯罪者
(0以上は世の中にとって有益無害、0以下は世の中にとって有害無益)
で、人としての貴さについても、この不等号に基づく順列が当てはまる。
社会的な常駐が倫理的に許されないのは犯罪者と権力犯罪者で、これらは一方的な撲滅の対象となる。
常駐が禁止まではされないが、色々と社会的な制限を受けなければならないのがガラクタ工業従事者と商業従事者で、
これらも放任が過ぎると犯罪者並みの害悪をもたらす場合がある(特に商売人が政商として権力犯罪に走る場合が多い)。
社会的な制限どころか、保護すらされて然るべきなのが農業従事者や必需工業従事者で、国を挙げてのそれらの
事業の振興が、着実な国力の発達にも結び付く。古来から重農主義であり続けてきた日本や中国などの東洋諸国が、
重商主義であり続けてきた西洋との経済競争で優位に立てたのも、そのような根本からの国力の養生があったればこそ。
君子士人は、上記のような措置を講ずる世の中の統治者たち自身のことであり、その働きが見事で
あったからには、それこそ神さま仏さまに準ずるほどもの畏敬の対象とされていかなければならない。
社会的に言って、有益無害の極致と有害無益の極致に該当するのが、権力道徳者(君子士人)と権力犯罪者であり、
片や神仏にも準ずる尊重の対象とされるべきである一方、片や最底辺の下流(子張第十九・二〇)として賤しむべき存在である。
全くの即物的な概算に基づいて生ずる貴賤の隔絶なのだから、これを迷信的な判断などとして退ける余地も、どこにもないといえる。
君子士人(権力道徳者)>農業従事者≧必需工業従事者>無職≒0>ガラクタ工業従事者≧商業従事者>犯罪者>権力犯罪者
(0以上は世の中にとって有益無害、0以下は世の中にとって有害無益)
で、人としての貴さについても、この不等号に基づく順列が当てはまる。
社会的な常駐が倫理的に許されないのは犯罪者と権力犯罪者で、これらは一方的な撲滅の対象となる。
常駐が禁止まではされないが、色々と社会的な制限を受けなければならないのがガラクタ工業従事者と商業従事者で、
これらも放任が過ぎると犯罪者並みの害悪をもたらす場合がある(特に商売人が政商として権力犯罪に走る場合が多い)。
社会的な制限どころか、保護すらされて然るべきなのが農業従事者や必需工業従事者で、国を挙げてのそれらの
事業の振興が、着実な国力の発達にも結び付く。古来から重農主義であり続けてきた日本や中国などの東洋諸国が、
重商主義であり続けてきた西洋との経済競争で優位に立てたのも、そのような根本からの国力の養生があったればこそ。
君子士人は、上記のような措置を講ずる世の中の統治者たち自身のことであり、その働きが見事で
あったからには、それこそ神さま仏さまに準ずるほどもの畏敬の対象とされていかなければならない。
社会的に言って、有益無害の極致と有害無益の極致に該当するのが、権力道徳者(君子士人)と権力犯罪者であり、
片や神仏にも準ずる尊重の対象とされるべきである一方、片や最底辺の下流(子張第十九・二〇)として賤しむべき存在である。
全くの即物的な概算に基づいて生ずる貴賤の隔絶なのだから、これを迷信的な判断などとして退ける余地も、どこにもないといえる。
聖書信仰はこの、即物的な観点に即して最悪級の賤しさを帯びる「権力犯罪」という所業の推進を企図したもので、
それにより「ただの犯罪者は救われないが、自分たちに限っては救われる」という事態の実現を目指した。
権力犯罪を推し進めることでこそ、ただの犯罪者のような断罪の対象にはさせないという暴挙の押し通し、
それも確かに多少は通じることもあったが、最終的には絶対に通じなくなる。そして本当に通じなくなったのが、今。
この頃まで権力道徳の認知も覚束ないでいた極西の部落社会で、権力道徳の対極であるが故に劣悪な所業の極みでもあることが
明らかとなる、権力犯罪の存在性もまた即物的には察知されることがなかった。その故に、そこに宗教的な幻想までをも抱いて、
権力犯罪を推進すればこそ、ただの犯罪者は罪になっても、自分たちは罪を免れられるかのような妄想にも陥ってしまった。
そのような連中によってこそ捏造されたのが新旧約聖書で、即物的な観点に基づけば、それは「権力犯罪聖書」だとも言える。
民間犯罪以上にも害悪度の極まる権力犯罪を推進するための聖書だったのだから、当然それが免罪の対象となるわけもない。
そうだと知ってて信仰や実践したのなら極刑の対象にすらなるし、そうとも知らず信仰や実践をしてしまったのだとしても、
十分な反省や活動自粛などが必須となる。幻想を晴らして即物性に帰ればこそ、そうせざるを得ないと断じるほかはない。
「即物性に過ぎる宗教こそはカルト」みたいな物言いがされることもあるが、むしろ即物的な観点に即して不正である
宗教こそが特筆してカルトであり、即物的に見て問題がない宗教こそは正統である。宗教と即物性を乖離させようとするのも
カルトの策謀であり、むしろ正統な宗教こそは、カネやモノへの取り扱いに対する監査を恐れたりする必要もないのである。
それにより「ただの犯罪者は救われないが、自分たちに限っては救われる」という事態の実現を目指した。
権力犯罪を推し進めることでこそ、ただの犯罪者のような断罪の対象にはさせないという暴挙の押し通し、
それも確かに多少は通じることもあったが、最終的には絶対に通じなくなる。そして本当に通じなくなったのが、今。
この頃まで権力道徳の認知も覚束ないでいた極西の部落社会で、権力道徳の対極であるが故に劣悪な所業の極みでもあることが
明らかとなる、権力犯罪の存在性もまた即物的には察知されることがなかった。その故に、そこに宗教的な幻想までをも抱いて、
権力犯罪を推進すればこそ、ただの犯罪者は罪になっても、自分たちは罪を免れられるかのような妄想にも陥ってしまった。
そのような連中によってこそ捏造されたのが新旧約聖書で、即物的な観点に基づけば、それは「権力犯罪聖書」だとも言える。
民間犯罪以上にも害悪度の極まる権力犯罪を推進するための聖書だったのだから、当然それが免罪の対象となるわけもない。
そうだと知ってて信仰や実践したのなら極刑の対象にすらなるし、そうとも知らず信仰や実践をしてしまったのだとしても、
十分な反省や活動自粛などが必須となる。幻想を晴らして即物性に帰ればこそ、そうせざるを得ないと断じるほかはない。
「即物性に過ぎる宗教こそはカルト」みたいな物言いがされることもあるが、むしろ即物的な観点に即して不正である
宗教こそが特筆してカルトであり、即物的に見て問題がない宗教こそは正統である。宗教と即物性を乖離させようとするのも
カルトの策謀であり、むしろ正統な宗教こそは、カネやモノへの取り扱いに対する監査を恐れたりする必要もないのである。
「殷民に辟在りて、予れを辟せよと曰うも、爾じ惟れを辟する勿れ。予れを宥せと曰うも、爾じ惟れを宥す勿れ、
惟れ厥の中をせよ。汝の政に若わず、汝の訓えに化せざること有らば、辟して以て止めよ。辟あらば乃ち辟せよ」
「民の内に罪を犯した者が有った場合、本人が有罪を認めたからといって重罰を科すのでも、無罪を主張するから
といって罰を科さないのでもいけない。常に中正を心がけ、おまえ自身の為政に従わず、教化に服さないことが
あれば、それこそを罰して過ちを未然に食い止めよ。それでも罪を犯した者がいれば、厳酷な罰を科すがいい。
(罪の有無や科刑の軽重は正式な為政者こそが自主性を以って判断すべきことであり、干渉の余地はどこにもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・君陳より)
惟れ厥の中をせよ。汝の政に若わず、汝の訓えに化せざること有らば、辟して以て止めよ。辟あらば乃ち辟せよ」
「民の内に罪を犯した者が有った場合、本人が有罪を認めたからといって重罰を科すのでも、無罪を主張するから
といって罰を科さないのでもいけない。常に中正を心がけ、おまえ自身の為政に従わず、教化に服さないことが
あれば、それこそを罰して過ちを未然に食い止めよ。それでも罪を犯した者がいれば、厳酷な罰を科すがいい。
(罪の有無や科刑の軽重は正式な為政者こそが自主性を以って判断すべきことであり、干渉の余地はどこにもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・君陳より)
男女関係でいえば、夫唱婦随であるほうが子宝にも恵まれて家庭円満でもいられたりする一方、
カカア天下のほうは女が多産を嫌がったり、家族関係が険悪化したりと色々な問題を生じさせてしまう。
それは、本質的な自律者である男が、依存者である女を十分な主導下に置くことが本末の正立となる一方、
依存者である女が主導的となることが本末の転倒になってしまうからで、それ以上に不思議な理由などはない。
車にしろ船にしろ、一方向に前進しやすいように作られるのが基本で、バックも一応はできるにしても、
一時的な後退だけを念頭に置いていて、常にバック走行し続けることなどを念頭においてはいない。
特殊な構造でもない自転車やバイクなどは、足をつかなければバックはできないようになっているし、
飛行機にいたっては飛行中のバックからして不可能で、エンジンの逆回転なども着陸時のブレーキなどと
してのみ用いられる。そして、こんな乗り物の例などを挙げるまでもなく、人間自身の身体構造からして
眼前に向かって前進していくことが歩行の基本となるようにできている。身体構造がクラゲやウニのような
全方向的な構造にはなっていないから、その人間が乗用することを目的とした乗り物なども自然と、
一方向に向かって進むことが便利となるように設計されていくようになっている。
夫唱婦随が人間自身や乗り物の前進であるなら、カカア天下は後退であるといえ、飛行機でもない限りは
後退だってできなくはないが、常に後退し続ける状態でいたのでは、人間や車や船といえども無理を来たすもの。
男女関係に限らずとも、一方が自律者でもう一方が依存者であるような関係が本末正立的であったり本末転倒的で
あったりすることは、人間や乗り物の前進や後退に譬えられるもので、後退が絶対に不可能なことでまであるとは
限らないにしても、常に後退をし続けるのでは無理を来たすという法則もまた、そのまま当てはまるのである。
カカア天下のほうは女が多産を嫌がったり、家族関係が険悪化したりと色々な問題を生じさせてしまう。
それは、本質的な自律者である男が、依存者である女を十分な主導下に置くことが本末の正立となる一方、
依存者である女が主導的となることが本末の転倒になってしまうからで、それ以上に不思議な理由などはない。
車にしろ船にしろ、一方向に前進しやすいように作られるのが基本で、バックも一応はできるにしても、
一時的な後退だけを念頭に置いていて、常にバック走行し続けることなどを念頭においてはいない。
特殊な構造でもない自転車やバイクなどは、足をつかなければバックはできないようになっているし、
飛行機にいたっては飛行中のバックからして不可能で、エンジンの逆回転なども着陸時のブレーキなどと
してのみ用いられる。そして、こんな乗り物の例などを挙げるまでもなく、人間自身の身体構造からして
眼前に向かって前進していくことが歩行の基本となるようにできている。身体構造がクラゲやウニのような
全方向的な構造にはなっていないから、その人間が乗用することを目的とした乗り物なども自然と、
一方向に向かって進むことが便利となるように設計されていくようになっている。
夫唱婦随が人間自身や乗り物の前進であるなら、カカア天下は後退であるといえ、飛行機でもない限りは
後退だってできなくはないが、常に後退し続ける状態でいたのでは、人間や車や船といえども無理を来たすもの。
男女関係に限らずとも、一方が自律者でもう一方が依存者であるような関係が本末正立的であったり本末転倒的で
あったりすることは、人間や乗り物の前進や後退に譬えられるもので、後退が絶対に不可能なことでまであるとは
限らないにしても、常に後退をし続けるのでは無理を来たすという法則もまた、そのまま当てはまるのである。
自律的な者と依存的な者との関係を、夫唱婦随のような良好な関係とするための道具となるのが上下の序列で、
上位に置かれた自律者が下位に置かれた依存者を一方的な統制の対象とする上での、増強剤的な役割を果たす。
別に、車をバックで走行させ続けるようなほどものカカア天下的な悪癖が根付いてしまっている
のでもない限りは、上下関係のあてがいによる夫唱婦随への矯正までをも必要とはしないわけで、
むしろ依存者こそが自意識過剰によってわがままを甚大化させてしまっているような所でこそ、
自律者と依存者との間に上下関係をあてがうことまでもが必要となってしまうのである。
無闇に上下関係をあてがったりするよりも、「自律者と依存者の関係は夫唱婦随が正則、カカア天下が逆則」
という認識を広めていくことのほうがあって然るべきで、それにより、車を前進させること程にも夫唱婦随を
当たり前なこととして受け止め、延々とバックさせ続けること程にもカカア天下を異常なこととして受け止める
ようになれば、わざわざ上下関係を徹底してまで夫唱婦随を強制したりする必要もなくなるのである。
「自律者と依存者の関係は夫唱婦随が正則、カカア天下が逆則」
これは、ただそうであるというまでのことで、そこにまで疑問を唱えたとしても仕方のないこと。
それはあたかも、「なぜ車はバックし続けるように作られていないのか」という疑問を抱くことに
大した意味がないのと同じようなもので、夫唱婦随であるべき人間関係も、丸ごと一つの車であるようなもの。
男女関係も一つの車、父子関係や君臣関係、官民関係なども一つの車。そこに主従の転倒をあてがったりするのは、
前進する目的で作られている車にバックを強要し続けるような暴挙になってしまうと考えたならば、
いかにそのような試みが不毛なものでしかないことかもまた、明らかになるだろう。
「所謂西伯善く老を養うとは、其の田里を制して之れに樹畜を教え、其の妻子を導きて其の老を養わしむればなり」
「『文王はよく老人を養った』とあるが、これは文王が田地を整理して人々に植樹や牧畜の行い方まで教え、
それぞれの妻子までをも老人への養護に務めるように導いたからである。(本人の優遇ではなく、善行へと導いた)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・二二より)
上位に置かれた自律者が下位に置かれた依存者を一方的な統制の対象とする上での、増強剤的な役割を果たす。
別に、車をバックで走行させ続けるようなほどものカカア天下的な悪癖が根付いてしまっている
のでもない限りは、上下関係のあてがいによる夫唱婦随への矯正までをも必要とはしないわけで、
むしろ依存者こそが自意識過剰によってわがままを甚大化させてしまっているような所でこそ、
自律者と依存者との間に上下関係をあてがうことまでもが必要となってしまうのである。
無闇に上下関係をあてがったりするよりも、「自律者と依存者の関係は夫唱婦随が正則、カカア天下が逆則」
という認識を広めていくことのほうがあって然るべきで、それにより、車を前進させること程にも夫唱婦随を
当たり前なこととして受け止め、延々とバックさせ続けること程にもカカア天下を異常なこととして受け止める
ようになれば、わざわざ上下関係を徹底してまで夫唱婦随を強制したりする必要もなくなるのである。
「自律者と依存者の関係は夫唱婦随が正則、カカア天下が逆則」
これは、ただそうであるというまでのことで、そこにまで疑問を唱えたとしても仕方のないこと。
それはあたかも、「なぜ車はバックし続けるように作られていないのか」という疑問を抱くことに
大した意味がないのと同じようなもので、夫唱婦随であるべき人間関係も、丸ごと一つの車であるようなもの。
男女関係も一つの車、父子関係や君臣関係、官民関係なども一つの車。そこに主従の転倒をあてがったりするのは、
前進する目的で作られている車にバックを強要し続けるような暴挙になってしまうと考えたならば、
いかにそのような試みが不毛なものでしかないことかもまた、明らかになるだろう。
「所謂西伯善く老を養うとは、其の田里を制して之れに樹畜を教え、其の妻子を導きて其の老を養わしむればなり」
「『文王はよく老人を養った』とあるが、これは文王が田地を整理して人々に植樹や牧畜の行い方まで教え、
それぞれの妻子までをも老人への養護に務めるように導いたからである。(本人の優遇ではなく、善行へと導いた)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・二二より)
 「你じに拄杖子有らば、我れ你じに拄杖子を与えん。
「你じに拄杖子有らば、我れ你じに拄杖子を与えん。 你じに拄杖子無くんば、我れ你じの拄杖子を奪わん」
「おまえが参禅修行者用の杖を持っているようならば、俺もおまえに杖を与えよう。
おまえ自身が杖を持っていないようならば、俺はおまえから杖を奪ってやろう」
(「無門関」第四十五則・芭蕉拄杖より)
上の禅書からの引用は、これ自体はスレの主旨に違うことも承知の上で、あえて持ち出してみたもの。
というのも、禅仏教こそは自力作善の聖道門の正統もいいとこで、庶民が生半な覚悟でかじったり
すべきでないものの最たるものでもあるから。だから芭蕉和尚も、参禅の資質のある者とない者とを
これ程にも冷厳に篩い分けたのだという一つの実例を、まず挙げておきたかったというまでのこと。
自力作善の仏門が上記ほどもの徹底した差別志向を敷いていればこそ、他力本願の浄土門は
徹底的な平等志向で、親殺しや仏門毀損にすら及ばなければ、誰でも念仏によって救われるとしている。
救われた先にあるとされる「無量寿経」中の極楽浄土なども、金銀財宝が散りばめられた豪華絢爛たるもので、
かえって聖道門の経典である「華厳経」おける仏国土の描写などよりも、即物的な豪華さに満ちたものとなっている。
(華厳経の仏国土にも即物的な描写はあるが、尽十方にかけてそのような描写が為されている頻度はかえって少ない)
参画者を極度に制限する禅門の寺こそは質素素朴である一方、百姓町人から屠殺人まで誰でも入信可である
浄土門の寺こそは、キンキラキンの宝飾が尽くされてもいる。仏門はかくの如き差別志向や平等志向それぞれの
善用によって、出家者たち自身が政治に直接携わらないうちからの、社会風紀の健全化に務めていく。
儒者の政治参画に基づく社会統治も、決してこの傾向を否定するものではない。仁徳に適うのなら粗末な衣食住も
楽しみに変わるという一方(述而第七・一五)、殷帝国の帝王として放辟邪侈の限りを尽くしていた紂王こそを
「下流(子張第十九・二〇)」とも断じている。富が吹き黙りやすい権力者の界隈こそは清貧を旨とするべきであり、
自分たちもそのような道徳的な権力者となることを目指しているわけで、仏者とはその手段が異なるにしても、
全体社会における富の偏在を、全身全霊を挙げて是正していこうとしている点では、全く共通しているといえる。
差別を>>6に挙げたような純正な職業別の害益度に即して徹底し、権力者といえども徳治者であり得た場合にのみ貴ばれ、
一躍権力犯罪者と化した場合には、即刻の自決も辞されなかった。武士が主な在俗信者であった禅門でも、できの悪すぎる
出家者を穴埋めや簀巻きの川流しにするなどして、武士が自らの勤めに励む上での鑑となるようにも振る舞っていた。
儒学自体からは多少話しが逸れたが、仏門が貧富ではなく精進修行の資質の有無にかけての差別を徹底することで、
社会全体における富の偏在を是正する役割を果たしていた事例を挙げてみた。それは、儒学統治とは志しが
一致するものだから、儒学を統治理念とする君子士人による世俗支配に協力する役割をも果たせていた。
一方で、富める者と富まざる者との格差を大いに開かせて已まない資本主義的な統治と、仏門の活動とは
決して相容れないものだから、資本主義が流入して来た明治以降の日本で仏門は徹底して弾圧され、
為政者の精神的な拠り所や、標準的な学問教育の主導者としての役割などは、ほぼ奪い去られることとなった。
多少「取材」の対象にできるぐらいのことはあったとしても、今の世の中の統治者は、仏門の活動をうまく
自分たちの為政の助けにしていくこともできやない。無理に参禅などを志してみたところで、自分たち自身のやってる
ことが金満政治以外の何物でもないから、多少経歴に箔を付けるための「ごっこ遊び」程度の意味合いしか持ち得ない。
仏門が儒学統治の味方たり得ても、金満政治の味方たり得たりまではしない。これもまた一つの正しい差別だといえる。
楽しみに変わるという一方(述而第七・一五)、殷帝国の帝王として放辟邪侈の限りを尽くしていた紂王こそを
「下流(子張第十九・二〇)」とも断じている。富が吹き黙りやすい権力者の界隈こそは清貧を旨とするべきであり、
自分たちもそのような道徳的な権力者となることを目指しているわけで、仏者とはその手段が異なるにしても、
全体社会における富の偏在を、全身全霊を挙げて是正していこうとしている点では、全く共通しているといえる。
差別を>>6に挙げたような純正な職業別の害益度に即して徹底し、権力者といえども徳治者であり得た場合にのみ貴ばれ、
一躍権力犯罪者と化した場合には、即刻の自決も辞されなかった。武士が主な在俗信者であった禅門でも、できの悪すぎる
出家者を穴埋めや簀巻きの川流しにするなどして、武士が自らの勤めに励む上での鑑となるようにも振る舞っていた。
儒学自体からは多少話しが逸れたが、仏門が貧富ではなく精進修行の資質の有無にかけての差別を徹底することで、
社会全体における富の偏在を是正する役割を果たしていた事例を挙げてみた。それは、儒学統治とは志しが
一致するものだから、儒学を統治理念とする君子士人による世俗支配に協力する役割をも果たせていた。
一方で、富める者と富まざる者との格差を大いに開かせて已まない資本主義的な統治と、仏門の活動とは
決して相容れないものだから、資本主義が流入して来た明治以降の日本で仏門は徹底して弾圧され、
為政者の精神的な拠り所や、標準的な学問教育の主導者としての役割などは、ほぼ奪い去られることとなった。
多少「取材」の対象にできるぐらいのことはあったとしても、今の世の中の統治者は、仏門の活動をうまく
自分たちの為政の助けにしていくこともできやない。無理に参禅などを志してみたところで、自分たち自身のやってる
ことが金満政治以外の何物でもないから、多少経歴に箔を付けるための「ごっこ遊び」程度の意味合いしか持ち得ない。
仏門が儒学統治の味方たり得ても、金満政治の味方たり得たりまではしない。これもまた一つの正しい差別だといえる。
「夏の暑く雨ふるに、小民惟れを曰いて怨み咨く。冬の祁いに寒きに、小民亦た惟れを曰いて怨み咨く。
厥れ惟れ艱いかな。其の艱きを思いて、以て其の易きを図れば、民乃ち寧し。嗚呼、丕いに顕らかなる
かな文王の謨。丕いに承けんかな武王の烈。我が後人を啓き佑けて、咸な正しきを以て欠くること罔し」
「夏は暑くて多雨だと決まっているのに、庶民はそれにすら怨み嘆こうとする。冬がひどく寒いのも
分かりきっていることなのに、これまた庶民はいちいちそんなことに嘆く。なかなか察し難いところだが、
その察し難い所までよく察して、(日々の生活に追われている庶民たち自身はなかなか気づかない)飢寒
の害のような本当のところの困窮までをも衣食の充実などによって補ってやったならば、民たちも安んじる。
(これも文王の代からの政治的手法なわけだが、)ああ、なんと文王のお考えはあきらかなることだろう。
武王もまたそのような偉業を見事に受け継ぎ、我々のような後代の者までをも啓蒙し助けて、正しく
ないところがないようにしてくれる。(この文王が編み出した政治的手法は聞くにあきらかではあるが、
愚昧な庶民たち自身があきらかに気づけないような部分に至るまでの配慮に基づく。生活ある民衆たち
自身こそを啓蒙して政治的な主導者の立場に置こうとする、民主主義の不能性をも示唆している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・君牙より)
厥れ惟れ艱いかな。其の艱きを思いて、以て其の易きを図れば、民乃ち寧し。嗚呼、丕いに顕らかなる
かな文王の謨。丕いに承けんかな武王の烈。我が後人を啓き佑けて、咸な正しきを以て欠くること罔し」
「夏は暑くて多雨だと決まっているのに、庶民はそれにすら怨み嘆こうとする。冬がひどく寒いのも
分かりきっていることなのに、これまた庶民はいちいちそんなことに嘆く。なかなか察し難いところだが、
その察し難い所までよく察して、(日々の生活に追われている庶民たち自身はなかなか気づかない)飢寒
の害のような本当のところの困窮までをも衣食の充実などによって補ってやったならば、民たちも安んじる。
(これも文王の代からの政治的手法なわけだが、)ああ、なんと文王のお考えはあきらかなることだろう。
武王もまたそのような偉業を見事に受け継ぎ、我々のような後代の者までをも啓蒙し助けて、正しく
ないところがないようにしてくれる。(この文王が編み出した政治的手法は聞くにあきらかではあるが、
愚昧な庶民たち自身があきらかに気づけないような部分に至るまでの配慮に基づく。生活ある民衆たち
自身こそを啓蒙して政治的な主導者の立場に置こうとする、民主主義の不能性をも示唆している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・君牙より)
何事も言えばその通りになる、富士山も相模湾に「飛び込め」と言えばそうなるという考えは。
いわゆる「馬鹿」の考えだ。鹿も「馬だ」と言い張れば馬になるとする、馬鹿の考え。
馬鹿の考えも、絶対に実現が不能だとは限らない。人間が空を飛ぶなんてのも200年前には馬鹿の
考えることだったが、今や飛行機が飛べることに疑念を呈している人間のほうが恐怖症扱いである。
「馬鹿と天才は紙一重」というが、発想の実現が可能なのが天才な馬鹿で、
実現は不能だが発想だけが奇天烈なのが単なる馬鹿だといえる。こんな、
あまり天才にとっても好ましくないような言い方をするのも、天才だからといって
世の中に好影響を及ぼすとも限らないから。馬鹿みたいな発想を実際に発明や研究などによって
実現した結果、機関銃や核兵器みたいな大量殺戮兵器までもが編み出されたわけだから、
決して天才だからといって手放しに褒め上げていればいいなんてこともないのである。
天才や馬鹿である以前に、人としてわきまえておかなければならない諸法実相の絶対法則というものがある。
そこを疎かにしてまでの発想の実現の試みは、馬鹿だけでなく、天才のそれまでもが有害な影響をもたらす。
だからそもそも、奇抜な発想によって常識を覆してしまおうとするような試み全般に一定の歯止めをかける
べきなのであり、それでも有益無害ゆえに実現していける発想だけを温存するようにすべきなのである。
いわゆる「馬鹿」の考えだ。鹿も「馬だ」と言い張れば馬になるとする、馬鹿の考え。
馬鹿の考えも、絶対に実現が不能だとは限らない。人間が空を飛ぶなんてのも200年前には馬鹿の
考えることだったが、今や飛行機が飛べることに疑念を呈している人間のほうが恐怖症扱いである。
「馬鹿と天才は紙一重」というが、発想の実現が可能なのが天才な馬鹿で、
実現は不能だが発想だけが奇天烈なのが単なる馬鹿だといえる。こんな、
あまり天才にとっても好ましくないような言い方をするのも、天才だからといって
世の中に好影響を及ぼすとも限らないから。馬鹿みたいな発想を実際に発明や研究などによって
実現した結果、機関銃や核兵器みたいな大量殺戮兵器までもが編み出されたわけだから、
決して天才だからといって手放しに褒め上げていればいいなんてこともないのである。
天才や馬鹿である以前に、人としてわきまえておかなければならない諸法実相の絶対法則というものがある。
そこを疎かにしてまでの発想の実現の試みは、馬鹿だけでなく、天才のそれまでもが有害な影響をもたらす。
だからそもそも、奇抜な発想によって常識を覆してしまおうとするような試み全般に一定の歯止めをかける
べきなのであり、それでも有益無害ゆえに実現していける発想だけを温存するようにすべきなのである。
馬鹿と天才は全くの別種なのではなく、発想が奇抜であるという点では全くその本質を同じくする。
ただ発想が奇抜なだけの「大多数の馬鹿」という負け組の中に、奇抜な発想を現実化する能力や資金を得た
「一部の天才」という勝ち組がいるのがキリスト教社会で、大半の一般人が地獄を天国だとも勘違いする最悪の
蒙昧に陥れられていればこそ、そこからの脱却を希望する若干名の人間が天才としての成功をも企てようとする。
誰しもがキリスト教徒級の蒙昧に踊らされている世の中でもないのなら、そもそも誰しもが諸法実相の了解
からなる一定の安楽にも与れていられるものだから、わざわざ天才や秀才としての成功などを企てようとする
ようなもの自体がそんなに生じない。仮に天才が生じたところで、関孝和や平賀源内のように適当な範囲の
成功に止めて、天才として世の中を席巻するような不埒な企てにまで及んだりすることはないのである。
馬鹿の妄動に一定の歯止めをかけるべきなのはもちろんだが、天才を天才だからといって無条件に
褒め称えるような風潮にもいい加減、幕を引かなければならない。天才であってもサイコパスであるような
人間に世界を支配されるよりは、凡才でも純朴で分別の利く人間が世の中を統治していくほうが、まだ
全体社会においてもたらされる損害以上の利益の度合いも高まるというもので、少なくとも、天才か凡才か
などという査定基準を、善人か悪人かという基準以上にも優先していいようなことは、もう決してないのである。
ただの小百姓の末子でいながら「皇帝になる」という大志を抱き、ほとんど文盲なままに帝位を目指し、
実際に皇帝となってみたなら、官職者や富豪には厳しくとも庶民には優しい、理想上の主君となった
漢の高祖劉邦のように、むしろ無知で純朴な中にこそ陰徳を養っていたような人間も実際にいるわけだから、
天才だからといって称えるのと同時に、無知や凡才だからといって侮るようなことも控えられていかなければならない。
ただ発想が奇抜なだけの「大多数の馬鹿」という負け組の中に、奇抜な発想を現実化する能力や資金を得た
「一部の天才」という勝ち組がいるのがキリスト教社会で、大半の一般人が地獄を天国だとも勘違いする最悪の
蒙昧に陥れられていればこそ、そこからの脱却を希望する若干名の人間が天才としての成功をも企てようとする。
誰しもがキリスト教徒級の蒙昧に踊らされている世の中でもないのなら、そもそも誰しもが諸法実相の了解
からなる一定の安楽にも与れていられるものだから、わざわざ天才や秀才としての成功などを企てようとする
ようなもの自体がそんなに生じない。仮に天才が生じたところで、関孝和や平賀源内のように適当な範囲の
成功に止めて、天才として世の中を席巻するような不埒な企てにまで及んだりすることはないのである。
馬鹿の妄動に一定の歯止めをかけるべきなのはもちろんだが、天才を天才だからといって無条件に
褒め称えるような風潮にもいい加減、幕を引かなければならない。天才であってもサイコパスであるような
人間に世界を支配されるよりは、凡才でも純朴で分別の利く人間が世の中を統治していくほうが、まだ
全体社会においてもたらされる損害以上の利益の度合いも高まるというもので、少なくとも、天才か凡才か
などという査定基準を、善人か悪人かという基準以上にも優先していいようなことは、もう決してないのである。
ただの小百姓の末子でいながら「皇帝になる」という大志を抱き、ほとんど文盲なままに帝位を目指し、
実際に皇帝となってみたなら、官職者や富豪には厳しくとも庶民には優しい、理想上の主君となった
漢の高祖劉邦のように、むしろ無知で純朴な中にこそ陰徳を養っていたような人間も実際にいるわけだから、
天才だからといって称えるのと同時に、無知や凡才だからといって侮るようなことも控えられていかなければならない。
「孔子衛に在りて、葬を送る者有り。夫子之れを観て曰く、善きかな喪を為すや、以て法と為すに足れり、小子之れ
を識せと。子貢曰く、夫子何ぞ善みすること爾かるやと。曰く、其の往くや慕うが如くし、其の反るや疑がうが如しと。
子貢曰く、豈に速やかに反りて虞するに若かんやと。子曰く、小子之れを識せ、我れ未だ之れを行う能わざるなりと」
「孔先生が衛国に滞在しているとき、葬送に参列する者がいた。先生はこれを見て言われた。『見事な服喪の仕方だ。
規範とするに足るものだから、よくそのあり方を記録しておきなさい』 弟子の子貢は問うた。『どこがそんなに
模範的なのでしょうか』 先生『葬儀に参列する時には未だ故人を慕っているようでいて、退くときにもまだ故人が
亡くなったことが信じられないような疑わしい態度でいるところがだ』 子貢『どうして速やかに退いて、斎宮でその
霊魂を祭ることがより模範的ではないのでしょうか』 先生『これも記録しておきなさい。私には到底できやしないが』
(生きていようが死んでいようが、人間の霊魂と身体とを妄りに分裂させて捉える気になれないのがまともな人情と
いうもの。そのような人情に欠ける子貢の意見も孔子は全くの非とはしなかったが、自分には到底できないともいった。
そして今の日本でも、没後四十九日目に法要によって死者の霊を送り出すなど、人情に適った葬礼が行われている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓上第三より)
を識せと。子貢曰く、夫子何ぞ善みすること爾かるやと。曰く、其の往くや慕うが如くし、其の反るや疑がうが如しと。
子貢曰く、豈に速やかに反りて虞するに若かんやと。子曰く、小子之れを識せ、我れ未だ之れを行う能わざるなりと」
「孔先生が衛国に滞在しているとき、葬送に参列する者がいた。先生はこれを見て言われた。『見事な服喪の仕方だ。
規範とするに足るものだから、よくそのあり方を記録しておきなさい』 弟子の子貢は問うた。『どこがそんなに
模範的なのでしょうか』 先生『葬儀に参列する時には未だ故人を慕っているようでいて、退くときにもまだ故人が
亡くなったことが信じられないような疑わしい態度でいるところがだ』 子貢『どうして速やかに退いて、斎宮でその
霊魂を祭ることがより模範的ではないのでしょうか』 先生『これも記録しておきなさい。私には到底できやしないが』
(生きていようが死んでいようが、人間の霊魂と身体とを妄りに分裂させて捉える気になれないのがまともな人情と
いうもの。そのような人情に欠ける子貢の意見も孔子は全くの非とはしなかったが、自分には到底できないともいった。
そして今の日本でも、没後四十九日目に法要によって死者の霊を送り出すなど、人情に適った葬礼が行われている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓上第三より)
徒善や徒法を自分たちで捏造することによって、それに反する小罪や偽悪を働くものを
徹底して糾弾し、それによって自分たちが企てる本物の大悪から衆目を逸らさせる
というのが、古来からの権力犯罪者やカルト犯罪者の罪悪推進上の常套手段となっている。
ユダヤ教の、割礼(包茎手術)を行わない者を神の意向に違う罪人として糾弾し、
「聖絶」の対象にすらしようとも憚らぬ姿勢などもその最たるものであり、徒善や徒法が
「神の啓示」などとして祭り上げられた場合の度し難さを示した極例ともなっている。
一方で、イスラム教における豚肉食や飲酒の禁止もまた、神託の名目で実定されている
傍目には徒法にすら思えかねない戒律である。実際、飲酒が厳禁されているためにこそ、
日本など以上にも喫煙や麻薬の服用が許容されていたりするといった問題も呈しているわけだが、
ただ、これらの戒律は異教徒に危害を加えることを正当化する言い分に用いられることまでは
少ないことからも、割礼や同性愛の禁止といった戒律を守らない異教徒を迫害の対象にすらする
ユダヤ教やキリスト教のあり方よりは、随分とマシな範疇に止まっているといえる。
アブラハム教圏には、善因楽果悪因苦果の自覚的な把捉に即した、自明な善悪の分別というものがない。
全ての規範は超越神が定めるものであり、自分はそれに服従するだけの存在でしかないと考えて
いる点では、ユダヤもキリシタンもイスラムも全くその様相を同じくする。その上で、神からの
啓示であるとされる善悪の分別や法定が、自明な分別から大幅に乖離してしまっているのが
ユダヤ教やキリスト教であるのに対し、「当たらずといえども遠からず」という
程度の範囲に止まっているのがイスラム教であるといった程度の違いがある。
徹底して糾弾し、それによって自分たちが企てる本物の大悪から衆目を逸らさせる
というのが、古来からの権力犯罪者やカルト犯罪者の罪悪推進上の常套手段となっている。
ユダヤ教の、割礼(包茎手術)を行わない者を神の意向に違う罪人として糾弾し、
「聖絶」の対象にすらしようとも憚らぬ姿勢などもその最たるものであり、徒善や徒法が
「神の啓示」などとして祭り上げられた場合の度し難さを示した極例ともなっている。
一方で、イスラム教における豚肉食や飲酒の禁止もまた、神託の名目で実定されている
傍目には徒法にすら思えかねない戒律である。実際、飲酒が厳禁されているためにこそ、
日本など以上にも喫煙や麻薬の服用が許容されていたりするといった問題も呈しているわけだが、
ただ、これらの戒律は異教徒に危害を加えることを正当化する言い分に用いられることまでは
少ないことからも、割礼や同性愛の禁止といった戒律を守らない異教徒を迫害の対象にすらする
ユダヤ教やキリスト教のあり方よりは、随分とマシな範疇に止まっているといえる。
アブラハム教圏には、善因楽果悪因苦果の自覚的な把捉に即した、自明な善悪の分別というものがない。
全ての規範は超越神が定めるものであり、自分はそれに服従するだけの存在でしかないと考えて
いる点では、ユダヤもキリシタンもイスラムも全くその様相を同じくする。その上で、神からの
啓示であるとされる善悪の分別や法定が、自明な分別から大幅に乖離してしまっているのが
ユダヤ教やキリスト教であるのに対し、「当たらずといえども遠からず」という
程度の範囲に止まっているのがイスラム教であるといった程度の違いがある。
イスラム圏における豚肉食の禁止は、間接的に女色の貪りの抑制にも寄与した。そのような
慣習の一切ないキリスト教圏では、同性愛への蔑視を横目にした男女の交わりの過激な推進すらもが
半ば横行し、いい女を抱くためにこそ男が無闇やたらに富を貪るようなことまでもが常態化してしまった。
それと比べれば、女色の貪りに一定の制限がかけられている一方、別に同性愛の禁止などがあるわけでもない
イスラム圏における大半の男たちの経済感覚のほうが至ってまともなもので(石油メジャーの手下と化した一部の
富豪などを除く)、自分たちが外界に強いている経済的疲弊なども、こちらは皆無にも等しいものとなっている。
神からの啓示名義の実定法などに依存したりするよりは、罪福の承諾に基づく自明な善悪の分別を
利かせていくに越したことはないが、残念ながらそれが叶わない範囲においても、比較的道義に
適った実定法によって人々が吉方へと導かれたり、著しく道義に悖った悪法によって人々が破滅に
陥れられたりするようなことがある。聖書信仰とイスラムの隔絶などもまさにその実例で、これから
致命的な破滅に陥る欧米聖書圏と比べての、ムスリムたちの「幸い」さが明らかなものとなっている。
むろん、「不幸中の幸い」という意味の「幸い」であって、超越神への信仰依存を本旨とするアブラハム教
全体としては、利益以上の損害をもたらしてしまったと断ずる他ないわけだから、老若男女官民の誰しもが
他社への依存によって生きていこうとすることなどが、決して善いことなどではなかったとも断ずるしかない。
慣習の一切ないキリスト教圏では、同性愛への蔑視を横目にした男女の交わりの過激な推進すらもが
半ば横行し、いい女を抱くためにこそ男が無闇やたらに富を貪るようなことまでもが常態化してしまった。
それと比べれば、女色の貪りに一定の制限がかけられている一方、別に同性愛の禁止などがあるわけでもない
イスラム圏における大半の男たちの経済感覚のほうが至ってまともなもので(石油メジャーの手下と化した一部の
富豪などを除く)、自分たちが外界に強いている経済的疲弊なども、こちらは皆無にも等しいものとなっている。
神からの啓示名義の実定法などに依存したりするよりは、罪福の承諾に基づく自明な善悪の分別を
利かせていくに越したことはないが、残念ながらそれが叶わない範囲においても、比較的道義に
適った実定法によって人々が吉方へと導かれたり、著しく道義に悖った悪法によって人々が破滅に
陥れられたりするようなことがある。聖書信仰とイスラムの隔絶などもまさにその実例で、これから
致命的な破滅に陥る欧米聖書圏と比べての、ムスリムたちの「幸い」さが明らかなものとなっている。
むろん、「不幸中の幸い」という意味の「幸い」であって、超越神への信仰依存を本旨とするアブラハム教
全体としては、利益以上の損害をもたらしてしまったと断ずる他ないわけだから、老若男女官民の誰しもが
他社への依存によって生きていこうとすることなどが、決して善いことなどではなかったとも断ずるしかない。
「天下の礼は、始めに反るを致すなり、鬼神を致すなり、和用を致すなり、義を致すなり、讓を致すなり。
〜此の五者を合わせて、以て天下の礼を治むるや、奇邪にして治まらざる者有ると雖も、則ち微かなる」
「天下に通用する礼節としては、物事の根本をよく見据えること、先祖の神をよく祭ること、万民の和合と
財の充実を図ること、道義を尽くすこと、謙譲を尽くすことの五つがある。この五つの礼節を天下全土に
向けて敷けたなら、奇行や邪侈に走って収拾の付かない者がまだいたとしても、あくまで少数派にとどまる。
(こういう大切なことのみを記録して、放辟邪侈の推進などを元から記録しない姿勢からして優良なのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭義第二十四より)
〜此の五者を合わせて、以て天下の礼を治むるや、奇邪にして治まらざる者有ると雖も、則ち微かなる」
「天下に通用する礼節としては、物事の根本をよく見据えること、先祖の神をよく祭ること、万民の和合と
財の充実を図ること、道義を尽くすこと、謙譲を尽くすことの五つがある。この五つの礼節を天下全土に
向けて敷けたなら、奇行や邪侈に走って収拾の付かない者がまだいたとしても、あくまで少数派にとどまる。
(こういう大切なことのみを記録して、放辟邪侈の推進などを元から記録しない姿勢からして優良なのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭義第二十四より)
「醜夷に在りて争わず(既出)」「同等の立場にある者同士では争わない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・曲礼上第一より)
罪を犯しているものに対して、同様の罪を犯しているものが裁きを講ずるというのでは、話にならない。
だから古来から儒学でも「修己治人」ということが言われてきたし、己れの無為自然によってこそ、
蛮行争乱に走るものを安静に連れ込む道家のあり方なども、一種の修己治人の提唱となっている。
修己治人であればこそ、容易かつ爽快に相手を降伏させられるといった法則もまた存在する。
合気柔術は、他の格闘技などとちがって自分から攻撃を仕掛けない。自分自身は平和主義を守り通す一方、
自分に攻撃を仕掛けてきた相手の攻撃力をうまく絡め取り、相手を捕縛や転倒などの状態に追い込む
ことを旨とする。自分から相手に攻撃を仕掛ず、また相手が本気で攻撃を仕掛けてきた場合にのみ、
合気技は見事にかかる。かける側に十分な技量があって、なおかつ上記のような条件すら整っていれば、
相手が雲を突くような大男で、自分が婦女子ほどの体格の持ち主でしかなくとも、確実に技がかかる。
「修己治人+相手にのみ決定的な落ち度」という条件すら整っていれば、何も柔術技巧に限らずとも、
様々なシチュエーションにおける合気技の法則の適用が可能となる。自分自身が権力犯罪を行わないことに
かけての徹底的な修身に勤め、逆に相手が重権力犯罪まみれの大悪人だったりするのなら、たとえ自分が
乞食も同様の分際でいて、相手が大軍を擁する大帝国の長であろうとも、まるで合気技が極まるかのごとく、
完璧かつ爽快に相手をねじ伏せることができる。これは孟子が梁恵王章句上・五でもすでに述べていることで、
ここではその発言が合気の法則に叶っているが故に、爽快な実現までもが可能であることを指摘したまでのことである。
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・曲礼上第一より)
罪を犯しているものに対して、同様の罪を犯しているものが裁きを講ずるというのでは、話にならない。
だから古来から儒学でも「修己治人」ということが言われてきたし、己れの無為自然によってこそ、
蛮行争乱に走るものを安静に連れ込む道家のあり方なども、一種の修己治人の提唱となっている。
修己治人であればこそ、容易かつ爽快に相手を降伏させられるといった法則もまた存在する。
合気柔術は、他の格闘技などとちがって自分から攻撃を仕掛けない。自分自身は平和主義を守り通す一方、
自分に攻撃を仕掛けてきた相手の攻撃力をうまく絡め取り、相手を捕縛や転倒などの状態に追い込む
ことを旨とする。自分から相手に攻撃を仕掛ず、また相手が本気で攻撃を仕掛けてきた場合にのみ、
合気技は見事にかかる。かける側に十分な技量があって、なおかつ上記のような条件すら整っていれば、
相手が雲を突くような大男で、自分が婦女子ほどの体格の持ち主でしかなくとも、確実に技がかかる。
「修己治人+相手にのみ決定的な落ち度」という条件すら整っていれば、何も柔術技巧に限らずとも、
様々なシチュエーションにおける合気技の法則の適用が可能となる。自分自身が権力犯罪を行わないことに
かけての徹底的な修身に勤め、逆に相手が重権力犯罪まみれの大悪人だったりするのなら、たとえ自分が
乞食も同様の分際でいて、相手が大軍を擁する大帝国の長であろうとも、まるで合気技が極まるかのごとく、
完璧かつ爽快に相手をねじ伏せることができる。これは孟子が梁恵王章句上・五でもすでに述べていることで、
ここではその発言が合気の法則に叶っているが故に、爽快な実現までもが可能であることを指摘したまでのことである。
ただ合気法則に即して大帝国全体を屈伏させるともなれば、ただ「何もしない」ばかりでもいけない所がある。
重権力犯罪まみれによってこそ成り立っていた、秦帝国や米英帝国などの後を継いで、跡地を有効に
実効支配していくからには、それに見合っただけの自分自身の政治的素養が必要となる。なおかつ
その政治能力が権力犯罪をやらかすことではなく、権力道徳を実践していくことにかけて有効でないのなら、
自分自身までもが秦楚や米英の二の舞三の舞に陥ってしまうことになるから、それでもいけない。
結局、老荘並みの無為自然志向と、孔孟並みの徳治の素養、さらには孫呉並みの兵法の素養があることでやっと、
秦や米英が崩壊した後の天下を十分に統治していくことが可能となる。それは決して、一人の人間にばかり
全てを要求すべきような代物ではないので、道術に長けていた高祖劉邦が、兵法にかけては張良や韓信を
頼りとしたり、礼楽にかけては陸賈や叔孫通を頼りにしたりしたような分業がある程度可能であってこそ、
万億の民を湛える大帝国の長期に渡る泰平統治が可能ともなっていくものなのでもある。
修己治人に即して悪逆非道を討つ、それは実際可能なことだし、実現できたならこれ程にも爽快なことはない。
できた所で面倒くさそうだ、今より悪い世の中になりそうだなんて不安が、現代社会にドップリ浸かって
しまっている人間には生じてしまうのかもしれないが、まず、修己治人に基づく勧善懲悪は楽しい、楽しい上に、
確実に今よりもマシ以上な世の中の到来が見込める。そこに魅力を感じることができて初めて、誰も彼もが
罪悪まみれで収拾も付かない時代のつまらなさにも気づき、よって収拾の目処が立っていくのでもある。
「吾れ未だ己れを枉げて人を正す者を聞かざるなり。況んや、己れを辱めて以て天下を正す者をや」
「私も、自分が邪曲でいながら他人を正せた者などを未だ一人も知らない。ましてや、自分を辱しめることで
世の中を正せた者ともなれば、なおさら聞いたこともない。(不正まみれで誰しもがお互いを正し合うことも
覚束なくなっているからといって、イエスのような辱めを受けることでどうにかなるなんて道理もない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・万章章句上・七より)
重権力犯罪まみれによってこそ成り立っていた、秦帝国や米英帝国などの後を継いで、跡地を有効に
実効支配していくからには、それに見合っただけの自分自身の政治的素養が必要となる。なおかつ
その政治能力が権力犯罪をやらかすことではなく、権力道徳を実践していくことにかけて有効でないのなら、
自分自身までもが秦楚や米英の二の舞三の舞に陥ってしまうことになるから、それでもいけない。
結局、老荘並みの無為自然志向と、孔孟並みの徳治の素養、さらには孫呉並みの兵法の素養があることでやっと、
秦や米英が崩壊した後の天下を十分に統治していくことが可能となる。それは決して、一人の人間にばかり
全てを要求すべきような代物ではないので、道術に長けていた高祖劉邦が、兵法にかけては張良や韓信を
頼りとしたり、礼楽にかけては陸賈や叔孫通を頼りにしたりしたような分業がある程度可能であってこそ、
万億の民を湛える大帝国の長期に渡る泰平統治が可能ともなっていくものなのでもある。
修己治人に即して悪逆非道を討つ、それは実際可能なことだし、実現できたならこれ程にも爽快なことはない。
できた所で面倒くさそうだ、今より悪い世の中になりそうだなんて不安が、現代社会にドップリ浸かって
しまっている人間には生じてしまうのかもしれないが、まず、修己治人に基づく勧善懲悪は楽しい、楽しい上に、
確実に今よりもマシ以上な世の中の到来が見込める。そこに魅力を感じることができて初めて、誰も彼もが
罪悪まみれで収拾も付かない時代のつまらなさにも気づき、よって収拾の目処が立っていくのでもある。
「吾れ未だ己れを枉げて人を正す者を聞かざるなり。況んや、己れを辱めて以て天下を正す者をや」
「私も、自分が邪曲でいながら他人を正せた者などを未だ一人も知らない。ましてや、自分を辱しめることで
世の中を正せた者ともなれば、なおさら聞いたこともない。(不正まみれで誰しもがお互いを正し合うことも
覚束なくなっているからといって、イエスのような辱めを受けることでどうにかなるなんて道理もない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・万章章句上・七より)
民主化や廃仏毀釈によって、君子士人としての活動や、本格的な仏門帰依の余地がすでに
絶やされてしまっている現今の日本社会においても、それらが実際に可能であった江戸時代以前の
世の中を慕う者がいて、それらの人々こそは今という時代を嘆かわしい時代だとも受け止めている。
それは確かに、多少の倫理意識によってそう思うという程度でしかない場合もあり、本当に当時の世の中に
回帰するとなれば躊躇すらしてしまうようなものだったりもする。一方で、本当にかつての世の中こそを
心から楽しかったもの、つまらなくなかったものとしてその本質から憧憬し、まるで美女や美食を欲する
ようにして、当時の世の中への回帰こそを自然に選択してしまうほどもの心持ちでいるものもいる。
「高高として上に在りと曰うなかれ、厥れ士の上に渉降したまい、日に監みて玆に在り」
「高々としてとても自分たちが手の届かないところにばかりあるなどと思うな。日々
神霊たちは天と人との間を昇降して、監査を加えつつここにすらあるものだと思え」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・頌・周頌・閔予小子之什・敬之より)
上のような心持ちで、150年以上前の世の中にすら生気がかった思いを馳せてみれば、確かに
実感からの正しき世の心地よさに与ることができる。深く歴史や礼制を学びすらすれば、誰にでもそれは
可能なことだし、自らの先祖が当時の世の中で重職を担っていたりしたのなら、なおさら実感も容易となる。
そしてその心地よさの実感に即して、実際に己と人と世とを律して行ったならば、たとえ君子階級や聖道門が
絶やされた世の中といえども、何度でも仁徳に満ちた聖賢の統治する世の中へと立ち戻らせていくことができる。
さんざん言っている通り、それはあくまで「楽しいからこそ」実施されていくに越したことはないのであり、
いい加減世の中が破滅に陥れられてどうにもならないから嫌々反正していくというのでは、望みが低すぎる。
絶やされてしまっている現今の日本社会においても、それらが実際に可能であった江戸時代以前の
世の中を慕う者がいて、それらの人々こそは今という時代を嘆かわしい時代だとも受け止めている。
それは確かに、多少の倫理意識によってそう思うという程度でしかない場合もあり、本当に当時の世の中に
回帰するとなれば躊躇すらしてしまうようなものだったりもする。一方で、本当にかつての世の中こそを
心から楽しかったもの、つまらなくなかったものとしてその本質から憧憬し、まるで美女や美食を欲する
ようにして、当時の世の中への回帰こそを自然に選択してしまうほどもの心持ちでいるものもいる。
「高高として上に在りと曰うなかれ、厥れ士の上に渉降したまい、日に監みて玆に在り」
「高々としてとても自分たちが手の届かないところにばかりあるなどと思うな。日々
神霊たちは天と人との間を昇降して、監査を加えつつここにすらあるものだと思え」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・頌・周頌・閔予小子之什・敬之より)
上のような心持ちで、150年以上前の世の中にすら生気がかった思いを馳せてみれば、確かに
実感からの正しき世の心地よさに与ることができる。深く歴史や礼制を学びすらすれば、誰にでもそれは
可能なことだし、自らの先祖が当時の世の中で重職を担っていたりしたのなら、なおさら実感も容易となる。
そしてその心地よさの実感に即して、実際に己と人と世とを律して行ったならば、たとえ君子階級や聖道門が
絶やされた世の中といえども、何度でも仁徳に満ちた聖賢の統治する世の中へと立ち戻らせていくことができる。
さんざん言っている通り、それはあくまで「楽しいからこそ」実施されていくに越したことはないのであり、
いい加減世の中が破滅に陥れられてどうにもならないから嫌々反正していくというのでは、望みが低すぎる。
いま現在、本当に世界を破滅に陥れてしまっているユダヤ系やキリシタン系の権力犯罪者たち自身は確かに、
窮地に追い詰められて仕方なく反正するということを主体とするしかないだろう。ただ、それらの人間は
反正の主導者ではなく、反正の取っ掛かりを作るものとなるに過ぎないのでもあり、撥乱反正と事後の
泰平統治を主導していく者であるなら、それを心から楽しんでいけるぐらいの心意気がなければならない。
古えからの知恵にも適った正善を、自他に向けて推進していくことにかけて大きな楽しみを抱けるぐらいで
あって初めて、本当に世界史上にも名高い聖王にも肩を並べるほどもの帝業すらをも成すことができる。
というのも、確かに歴史上の聖王こそは、善政を尽くすことを心から楽しんでいたようでもあるから。
自らが善政を行うための口実としての瑞祥を求めて、方々での祭祀に明け暮れた前漢の武帝なども、
「これによって龍が現れて自分を天上へと連れて行ってくれるのなら、妻子など履物を脱ぎ捨てるように
捨て去ってもいいのに」と言ったという(「漢書」郊祀志参照)。ここには、本当に龍が現れることへの渇望
以上にも、祭祀事業そのものを心から楽しんでいたことからなる余裕が垣間見られる。家庭を捨てて寺に入る
仏者のあり方なども、俗世での楽しみこそが全てである現代の人間からすればやせ我慢じみたものにすら
思われかねないが、むしろそこにこそ常楽我浄があるものだから、出家を志す者もかつては多かったのだ。
正善ゆえ、浄業ゆえの楽しみこそはまた別にあるのだと確信し、そこに邁進していける者こそが、
本当にそこに到達できるのであり、嫌々ながら仕方なくなどという者は始めからお呼びでない。
やる気もないような奴は修行用の杖を持っていない内からその杖を奪ってしまおうとは>>11にもある通りだ。
窮地に追い詰められて仕方なく反正するということを主体とするしかないだろう。ただ、それらの人間は
反正の主導者ではなく、反正の取っ掛かりを作るものとなるに過ぎないのでもあり、撥乱反正と事後の
泰平統治を主導していく者であるなら、それを心から楽しんでいけるぐらいの心意気がなければならない。
古えからの知恵にも適った正善を、自他に向けて推進していくことにかけて大きな楽しみを抱けるぐらいで
あって初めて、本当に世界史上にも名高い聖王にも肩を並べるほどもの帝業すらをも成すことができる。
というのも、確かに歴史上の聖王こそは、善政を尽くすことを心から楽しんでいたようでもあるから。
自らが善政を行うための口実としての瑞祥を求めて、方々での祭祀に明け暮れた前漢の武帝なども、
「これによって龍が現れて自分を天上へと連れて行ってくれるのなら、妻子など履物を脱ぎ捨てるように
捨て去ってもいいのに」と言ったという(「漢書」郊祀志参照)。ここには、本当に龍が現れることへの渇望
以上にも、祭祀事業そのものを心から楽しんでいたことからなる余裕が垣間見られる。家庭を捨てて寺に入る
仏者のあり方なども、俗世での楽しみこそが全てである現代の人間からすればやせ我慢じみたものにすら
思われかねないが、むしろそこにこそ常楽我浄があるものだから、出家を志す者もかつては多かったのだ。
正善ゆえ、浄業ゆえの楽しみこそはまた別にあるのだと確信し、そこに邁進していける者こそが、
本当にそこに到達できるのであり、嫌々ながら仕方なくなどという者は始めからお呼びでない。
やる気もないような奴は修行用の杖を持っていない内からその杖を奪ってしまおうとは>>11にもある通りだ。
夏殷周の三代にわたる最古層の中国文化を春秋時代に孔子が易詩書礼楽春秋の六経として編纂し、
孔子やその後継者である儒者たちも、その忠実な継承に務めていた。秦始皇帝の犯した焚書坑儒によって
「楽経」の全てと「書経」の大半が焼失し、今では五経にまで目減りしてしまっているが、やはり
できる限り古代文化の忠実な継承に儒者たちが務め続けようとして来たことには変わりない。
古代文化そのものは忠実に継承した上で、その実用に応用を利かせるというぐらいのことは当然あった。
秦帝国の覇業を継ぐ形で王業を打ち立てた漢帝国においても、天神を祭るための檀などの装飾に浮ついて
華美なものがあったために、それを廃止したと「漢書」郊祀志下にある。しかもそれが古代の礼制に適って
いないからではなく、すでに遺失している礼制を近代人が我流で焼き直したものだからというわけで、
これはかえって、古代文化の偉大さを尊重するがためにヘタな真似を控えようとした事例にあたるといえる。
日本でも、中国とは違った気候風土に合わせて、供儀に獣肉ではなく魚介類を用いるなどの応用が利かせられた。
これも「東鄰の牛を殺すは、西鄰の禴祭(質素な祭)に如かず」という「易経」既済・九五の記述にも即していて、
中国古来の礼制に即しているわけではないにも関わらず、かえって中国文化の根幹たる易には即したものとなっている。
必ずしも、古代の中国文化そのものをそのまま復古するというのでもなく、それなりの応用は利かせる、
それでこそ単なる復元志向以上にも、温故知新を本旨とする儒学の理念にも叶った実績を上げられたりもする。ただ、
それが決して基本的なあり方なのではなく、できる限り古来のあり方に倣って、あきらかに新規な措置を講じたほうが
最善となる場合に限ってそちらを選択するというのが基本なわけで、「五経の記録に一切従わないことが最善となる」
なんてことは当然あり得ない。そこまで五経が劣悪極まりない反面教師カルトの鑑だったりすることもないのだから。
孔子やその後継者である儒者たちも、その忠実な継承に務めていた。秦始皇帝の犯した焚書坑儒によって
「楽経」の全てと「書経」の大半が焼失し、今では五経にまで目減りしてしまっているが、やはり
できる限り古代文化の忠実な継承に儒者たちが務め続けようとして来たことには変わりない。
古代文化そのものは忠実に継承した上で、その実用に応用を利かせるというぐらいのことは当然あった。
秦帝国の覇業を継ぐ形で王業を打ち立てた漢帝国においても、天神を祭るための檀などの装飾に浮ついて
華美なものがあったために、それを廃止したと「漢書」郊祀志下にある。しかもそれが古代の礼制に適って
いないからではなく、すでに遺失している礼制を近代人が我流で焼き直したものだからというわけで、
これはかえって、古代文化の偉大さを尊重するがためにヘタな真似を控えようとした事例にあたるといえる。
日本でも、中国とは違った気候風土に合わせて、供儀に獣肉ではなく魚介類を用いるなどの応用が利かせられた。
これも「東鄰の牛を殺すは、西鄰の禴祭(質素な祭)に如かず」という「易経」既済・九五の記述にも即していて、
中国古来の礼制に即しているわけではないにも関わらず、かえって中国文化の根幹たる易には即したものとなっている。
必ずしも、古代の中国文化そのものをそのまま復古するというのでもなく、それなりの応用は利かせる、
それでこそ単なる復元志向以上にも、温故知新を本旨とする儒学の理念にも叶った実績を上げられたりもする。ただ、
それが決して基本的なあり方なのではなく、できる限り古来のあり方に倣って、あきらかに新規な措置を講じたほうが
最善となる場合に限ってそちらを選択するというのが基本なわけで、「五経の記録に一切従わないことが最善となる」
なんてことは当然あり得ない。そこまで五経が劣悪極まりない反面教師カルトの鑑だったりすることもないのだから。
その記述に一切従わないでいてこそ最善となるような反面教師カルトの聖典があったとして、しかもそれが何十万文字
という大部に上っていたとする。そんなもの無視するに越したことはないが、残念ながら押し付けられたりもする形で
その内容を知らされてしまったとする。それでいて一切その記述に従わないためには、ただ「こんなものはダメだ」
という反発意識を持つぐらいではどうにもならない。その記述にいかに従わないでおくかに関する体系的な知識こそが
必要ともなるが、その知識が五経や四書の中にはあるとした所で、新約聖書の中にあるようなことも決してない。
新約の教義が、「旧約の教義は一切従わないでいてこそ最善となる反面教師カルトの教義である」という正しい
認識を前提に提唱されたものなどでは決してないから、新約が旧約の毒性を中和できているようなことも全くない。
あたかも四書が五経の注釈書として編纂されたようにして、新約もまた旧約の応用書として作られたものであり、
五経と違って、旧約のほうは改善の余地もないほどに極悪非道の教義の塊でしかないものだから、それを多少いじる
ぐらいのつもりで捏造された新約の教義もまた、旧約に尾ひれをつけた程度のものとしかなり得なかったのだった。
最初の誤りは、新約ではなく旧約にある。旧約が五経ぐらいにマシな教学を湛えていたなら、そこに付け足される形で
作られた新約もまた、四書並みにマシな内容になっていただろう。五経の自学自習によって聖人君子へと大成した
孔子ほどまでは行かずとも、イエスもまたもうちょっとマシな人間ぐらいではいられたことだろう。人間の運命は
必ずしも環境によって決まるものではないにしろ、環境がある程度その運命を左右してしまうのも確かなことだ。
「男女の別有りて、而る後に夫婦義有り。夫婦義有りて、而る後に父子親有り。
父子親有りて、而る後に君臣正有り。故に曰く、昏礼は、礼の本なりと」
「男女の差別があって後に初めて、夫婦の関係に義が生ずる。夫婦の関係に義があって後に初めて、父子の関係に親しみ
が生ずる。父子の関係に親しみがあって初めて、君臣関係も正しくなる。故に結婚こそはあらゆる礼節の根本ともされる」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・昏義第四十四より)
という大部に上っていたとする。そんなもの無視するに越したことはないが、残念ながら押し付けられたりもする形で
その内容を知らされてしまったとする。それでいて一切その記述に従わないためには、ただ「こんなものはダメだ」
という反発意識を持つぐらいではどうにもならない。その記述にいかに従わないでおくかに関する体系的な知識こそが
必要ともなるが、その知識が五経や四書の中にはあるとした所で、新約聖書の中にあるようなことも決してない。
新約の教義が、「旧約の教義は一切従わないでいてこそ最善となる反面教師カルトの教義である」という正しい
認識を前提に提唱されたものなどでは決してないから、新約が旧約の毒性を中和できているようなことも全くない。
あたかも四書が五経の注釈書として編纂されたようにして、新約もまた旧約の応用書として作られたものであり、
五経と違って、旧約のほうは改善の余地もないほどに極悪非道の教義の塊でしかないものだから、それを多少いじる
ぐらいのつもりで捏造された新約の教義もまた、旧約に尾ひれをつけた程度のものとしかなり得なかったのだった。
最初の誤りは、新約ではなく旧約にある。旧約が五経ぐらいにマシな教学を湛えていたなら、そこに付け足される形で
作られた新約もまた、四書並みにマシな内容になっていただろう。五経の自学自習によって聖人君子へと大成した
孔子ほどまでは行かずとも、イエスもまたもうちょっとマシな人間ぐらいではいられたことだろう。人間の運命は
必ずしも環境によって決まるものではないにしろ、環境がある程度その運命を左右してしまうのも確かなことだ。
「男女の別有りて、而る後に夫婦義有り。夫婦義有りて、而る後に父子親有り。
父子親有りて、而る後に君臣正有り。故に曰く、昏礼は、礼の本なりと」
「男女の差別があって後に初めて、夫婦の関係に義が生ずる。夫婦の関係に義があって後に初めて、父子の関係に親しみ
が生ずる。父子の関係に親しみがあって初めて、君臣関係も正しくなる。故に結婚こそはあらゆる礼節の根本ともされる」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・昏義第四十四より)
悪を為さず、罪を犯さない所にこそ「浩然の気」とか「常楽我浄」とかいった風に呼ばれもする
根本からの安楽があり、罪悪を積み重ねれば積み重ねるほどその安楽からは遠ざかる。
最悪、まるで全身に激痛の走る大やけどを負いながら生きさせられるほどにも、
心底からの精神的苦痛と共にしか生きられないようなザマにすら陥ってしまう。
だから悪人や罪人ほど、その表情や言行にも、どこか歪んだものが垣間見られもする。
浩然の気や浄楽我浄のような根本からの精神的安楽に与れている人間はといえば、
心持ちから仏像や菩薩像のような穏やかな表情でいられるもので、生きることに何の無理もない。
無理がないからと言って死に絶えるのでもなく、寿命や運命の限りにおいて命を保ちもする。
個体としての生死以上にも、善因楽果や悪因苦果の因果応報こそは普遍的なものであり、
命を失う前から悪業輪廻を脱するということも結構、できなくもないことである。
ただ、誰しもが悪因苦果を生前から抜け出した有余涅槃の境地にいるよう世の中というのも、
やはり稀有なことで、悪因苦果の苦しみを罪悪の積み重ねに付随する快楽の貪りで
紛らわそうとする悪循環に陥ってしまった悪人などが多少は生じてしまったりもするのが、
大規模な都市社会における常であるといえる。そこで、誰しもが抜業因種の常楽我浄
などには与れないうちから、道徳統治によってそのような人種を減らしていく措置が講じられる。
それが常々ここで私論なり引用なりを書いている儒学に基づく統治でもあり、儒学統治によって
誰しもが有余涅槃の常楽我浄に与れるとまでは決して言えず、せいぜい徳治を心がける為政者
の中に、孟子のような浩然の気を自覚する人間が多少生ずる程度のことが期待できるだけである。
誰しもの有余涅槃すらをも実現しようとした仏教という教学自体、すでに野心的なものだった。
人間は欲望や悪念に流れてしまいやすい生き物で、それ故の悪因苦果への陥りもむしろ常態的なもの。
そこに出家修行までをも導入しての悪業輪廻からの解脱を促そうとしたのは、相当に野心的な思いが
あったからで、故に「仏教ぐらいは誰でも帰依してて当然」なんてことまでが言えるわけでもない。
根本からの安楽があり、罪悪を積み重ねれば積み重ねるほどその安楽からは遠ざかる。
最悪、まるで全身に激痛の走る大やけどを負いながら生きさせられるほどにも、
心底からの精神的苦痛と共にしか生きられないようなザマにすら陥ってしまう。
だから悪人や罪人ほど、その表情や言行にも、どこか歪んだものが垣間見られもする。
浩然の気や浄楽我浄のような根本からの精神的安楽に与れている人間はといえば、
心持ちから仏像や菩薩像のような穏やかな表情でいられるもので、生きることに何の無理もない。
無理がないからと言って死に絶えるのでもなく、寿命や運命の限りにおいて命を保ちもする。
個体としての生死以上にも、善因楽果や悪因苦果の因果応報こそは普遍的なものであり、
命を失う前から悪業輪廻を脱するということも結構、できなくもないことである。
ただ、誰しもが悪因苦果を生前から抜け出した有余涅槃の境地にいるよう世の中というのも、
やはり稀有なことで、悪因苦果の苦しみを罪悪の積み重ねに付随する快楽の貪りで
紛らわそうとする悪循環に陥ってしまった悪人などが多少は生じてしまったりもするのが、
大規模な都市社会における常であるといえる。そこで、誰しもが抜業因種の常楽我浄
などには与れないうちから、道徳統治によってそのような人種を減らしていく措置が講じられる。
それが常々ここで私論なり引用なりを書いている儒学に基づく統治でもあり、儒学統治によって
誰しもが有余涅槃の常楽我浄に与れるとまでは決して言えず、せいぜい徳治を心がける為政者
の中に、孟子のような浩然の気を自覚する人間が多少生ずる程度のことが期待できるだけである。
誰しもの有余涅槃すらをも実現しようとした仏教という教学自体、すでに野心的なものだった。
人間は欲望や悪念に流れてしまいやすい生き物で、それ故の悪因苦果への陥りもむしろ常態的なもの。
そこに出家修行までをも導入しての悪業輪廻からの解脱を促そうとしたのは、相当に野心的な思いが
あったからで、故に「仏教ぐらいは誰でも帰依してて当然」なんてことまでが言えるわけでもない。
あたかも大火事を大水で消し止めたり、大水を湛えた消火栓を常備しておいたりするようにして
仏教もまた嗜まれるものであり、最低限の火消しに務める儒学などと比べれば、その受容が相当に
おおがかりなものともなる。正式な権力機構でもない寺などに布施や寄進をしたりすることからして
自然ではないことであり、それよりは年貢や税金を納めることのほうがごく当たり前なことだともいえる。
あたかも、悪因苦果をカルト信仰によって増長させることと同じぐらいに、信教の形式によって
悪因苦果を断滅しようとした、仏教もまた極度に人口的な代物であり、そこは無宗教的な考え方が
浸透している現代人などからすれば異質に思われても仕方のない部分だといえる。ただ、その異質な
ほどもの人工性が断悪修善にかけて専らである点は、悪逆非道にかけて専らであったりするよりも
確実にマシなことであるといえ、そこはカルト宗教などと同等に扱ってはならない部分だといえる。
人の心理面からの断悪修善や悪逆非道を促すことで、実際に国家社会レベルでの慶福や災禍を
もたらし得るのが宗教というものであり、「宗教なんか何の価値も無い」というのは誤った認識である。
ただ、宗教には正の価値がある場合と負の価値がある場合があって、悪因苦果こそを増長する
カルト宗教などが有害無益極まりないものであることもまた間違いないので、宗教だからといって
何でも手放しに容認していてもいいなんてこともないのもまた、間違いのないことなのである。
「人小罪有りて眚に非ず、乃ち惟れを終えて自ら不典を作し、
式て爾じをせば、厥の罪小なること有るとも、乃ち殺さざる可からず」
「人が過失でない罪を犯して、なおのこと不法を為す意欲が旺盛であるようならば、たとえ軽罪と
いえども処刑しないわけにはいかない。(罪そのもの以上にも、罪を犯して已まぬ心の不埒さを罰する)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・康誥より)
仏教もまた嗜まれるものであり、最低限の火消しに務める儒学などと比べれば、その受容が相当に
おおがかりなものともなる。正式な権力機構でもない寺などに布施や寄進をしたりすることからして
自然ではないことであり、それよりは年貢や税金を納めることのほうがごく当たり前なことだともいえる。
あたかも、悪因苦果をカルト信仰によって増長させることと同じぐらいに、信教の形式によって
悪因苦果を断滅しようとした、仏教もまた極度に人口的な代物であり、そこは無宗教的な考え方が
浸透している現代人などからすれば異質に思われても仕方のない部分だといえる。ただ、その異質な
ほどもの人工性が断悪修善にかけて専らである点は、悪逆非道にかけて専らであったりするよりも
確実にマシなことであるといえ、そこはカルト宗教などと同等に扱ってはならない部分だといえる。
人の心理面からの断悪修善や悪逆非道を促すことで、実際に国家社会レベルでの慶福や災禍を
もたらし得るのが宗教というものであり、「宗教なんか何の価値も無い」というのは誤った認識である。
ただ、宗教には正の価値がある場合と負の価値がある場合があって、悪因苦果こそを増長する
カルト宗教などが有害無益極まりないものであることもまた間違いないので、宗教だからといって
何でも手放しに容認していてもいいなんてこともないのもまた、間違いのないことなのである。
「人小罪有りて眚に非ず、乃ち惟れを終えて自ら不典を作し、
式て爾じをせば、厥の罪小なること有るとも、乃ち殺さざる可からず」
「人が過失でない罪を犯して、なおのこと不法を為す意欲が旺盛であるようならば、たとえ軽罪と
いえども処刑しないわけにはいかない。(罪そのもの以上にも、罪を犯して已まぬ心の不埒さを罰する)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・康誥より)
罪を罪と見定めることができず、まるで息をするようにして罪を犯すように
なってしまった人間ほど不幸なものも他にない。そこに浩然の気や常楽我浄がない
のはもちろんのこと、知らず知らずの内からの多大なる精神的苦痛をわずらい続ける。
潜在的な苦痛からなる自暴自棄によって、まるで当たり前のことのように悪念を抱き、
自分がそのようなものだから、誰しもが悪念の塊であるかのように思い込み、以って、
世の中全体を悪にまみれた暗黒の世であるかのようにも勝手に思い込むようになる。
すると、もはや自分並みに不幸であるのが世人のデフォルトであるかのようにすら考える
ようになり、自分自身が特定して不幸者であることに気づく余地すらをも取り去ってしまう。
この当たりに、致命的な道理の見失いがあり、地獄餓鬼畜生の三悪趣に自らが堕する
機縁までもが生じてもいる。もはや仏の声も聞こえず、聞こえた所で何を言ってるのかも
分からない、それ程にも、自分自身の思考回路の歯車が不正な方向へと一律して回転するように
なってしまっているものだから、そこからの脱却ももはや不可能に等しいものとなってしまっている。
そこから立ち直っていくために、長い長い道のりを必要とすることは、もう何度も書いた。
そこに多大なる試練が待ち受けていることも、最悪の場合こそを想定しつつ書いてきた。
ただそれは、思考の歯車が不正な方向へと最高速度で回転し続けているうちから始まるものではない。
不正な方向への歯車の回転が止まるとまで行かずとも、減速し始めるぐらいのことがあってから
始まるものであり、もうそれぐらいの所にいる人間は聖書圏の内にも多いだろうが、
未だ最高速度での不正回転を続けている人間もまた、やはり多いはずである。
なってしまった人間ほど不幸なものも他にない。そこに浩然の気や常楽我浄がない
のはもちろんのこと、知らず知らずの内からの多大なる精神的苦痛をわずらい続ける。
潜在的な苦痛からなる自暴自棄によって、まるで当たり前のことのように悪念を抱き、
自分がそのようなものだから、誰しもが悪念の塊であるかのように思い込み、以って、
世の中全体を悪にまみれた暗黒の世であるかのようにも勝手に思い込むようになる。
すると、もはや自分並みに不幸であるのが世人のデフォルトであるかのようにすら考える
ようになり、自分自身が特定して不幸者であることに気づく余地すらをも取り去ってしまう。
この当たりに、致命的な道理の見失いがあり、地獄餓鬼畜生の三悪趣に自らが堕する
機縁までもが生じてもいる。もはや仏の声も聞こえず、聞こえた所で何を言ってるのかも
分からない、それ程にも、自分自身の思考回路の歯車が不正な方向へと一律して回転するように
なってしまっているものだから、そこからの脱却ももはや不可能に等しいものとなってしまっている。
そこから立ち直っていくために、長い長い道のりを必要とすることは、もう何度も書いた。
そこに多大なる試練が待ち受けていることも、最悪の場合こそを想定しつつ書いてきた。
ただそれは、思考の歯車が不正な方向へと最高速度で回転し続けているうちから始まるものではない。
不正な方向への歯車の回転が止まるとまで行かずとも、減速し始めるぐらいのことがあってから
始まるものであり、もうそれぐらいの所にいる人間は聖書圏の内にも多いだろうが、
未だ最高速度での不正回転を続けている人間もまた、やはり多いはずである。
多少そういった、未だ救いの見込みも立たないような人間のいる内から、社会規模での改悛を始めて
いったとしても、決して見切り発車などということにはならない。キリスト教支配下にあるような
世の中だけでなく、儒学統治下にある世の中であったって、多少の奇邪が蔓延る可能性があることは
>>19の礼記からの引用などからも知れたことである。せいぜい、最悪級のカルト犯罪が権力機構から
完全に払拭されるなどすらすれば、世の中全体での改悛を始めていく下地としては十分であり、場末で
怪力乱神への妄想を膨らませるものがあるぐらいのことは、まだあっても仕方のないことだといえる。
漢代初期の郊祀対象にも、冤罪の神(族纍)を祭るなどということがあったようで、
多少はキリスト信仰にも似ていなくはない。後世、先祖への祭祀などは強化されていった一方で、
あまりにも奇異に過ぎるような怪神邪神への郊祀は徐々に撤廃されていったようで、文化の
有機性というものを貴ぶからには、多少奇異なものも寛容の対象としていくべきなのである。
それにしたって、聖書信仰はもはや根絶せざるを得ない。それは、聖書信仰があまりにも政治権力と
癒着しての悪逆非道に走りすぎたからで、ただ文化的に異様であるからというばかりのことではない。
ただ異様であるというだけなら、前漢で族纍が祭られたようにして、聖書の神ですら未だ祭られる
余地もあったわけだが、世俗権力を侵しすぎたがためにこそ、その権利ももはやなくなってしまった。
根絶の対象としていかざるを得ないが、未だ聖書信仰に基づく不正な思考の高速回転を減速させる
ことすらできないでいるものも未だ数多い、という現状で社会規模での改悛を始めていく。聖書信仰
自体は根絶の対象としていかざるを得ないにしろ、未だ聖書中毒に陥ったままでいてしまっている人々
をも決して無下には扱わず、きっといつかは立ち直れるものとして長い目で見てあげなければならない。
根絶はやはり不可避であるにしても、こちらで勝手に、そこに亡びの美学すら見出してやればいいのだ。
いったとしても、決して見切り発車などということにはならない。キリスト教支配下にあるような
世の中だけでなく、儒学統治下にある世の中であったって、多少の奇邪が蔓延る可能性があることは
>>19の礼記からの引用などからも知れたことである。せいぜい、最悪級のカルト犯罪が権力機構から
完全に払拭されるなどすらすれば、世の中全体での改悛を始めていく下地としては十分であり、場末で
怪力乱神への妄想を膨らませるものがあるぐらいのことは、まだあっても仕方のないことだといえる。
漢代初期の郊祀対象にも、冤罪の神(族纍)を祭るなどということがあったようで、
多少はキリスト信仰にも似ていなくはない。後世、先祖への祭祀などは強化されていった一方で、
あまりにも奇異に過ぎるような怪神邪神への郊祀は徐々に撤廃されていったようで、文化の
有機性というものを貴ぶからには、多少奇異なものも寛容の対象としていくべきなのである。
それにしたって、聖書信仰はもはや根絶せざるを得ない。それは、聖書信仰があまりにも政治権力と
癒着しての悪逆非道に走りすぎたからで、ただ文化的に異様であるからというばかりのことではない。
ただ異様であるというだけなら、前漢で族纍が祭られたようにして、聖書の神ですら未だ祭られる
余地もあったわけだが、世俗権力を侵しすぎたがためにこそ、その権利ももはやなくなってしまった。
根絶の対象としていかざるを得ないが、未だ聖書信仰に基づく不正な思考の高速回転を減速させる
ことすらできないでいるものも未だ数多い、という現状で社会規模での改悛を始めていく。聖書信仰
自体は根絶の対象としていかざるを得ないにしろ、未だ聖書中毒に陥ったままでいてしまっている人々
をも決して無下には扱わず、きっといつかは立ち直れるものとして長い目で見てあげなければならない。
根絶はやはり不可避であるにしても、こちらで勝手に、そこに亡びの美学すら見出してやればいいのだ。
「囚を要して多罪を殄戮し、亦た克く用て勧む。無辜を開釈して、亦た克く用て勧む」
「囚人の罪状をよく調べて、罪ある者は厳格に処刑したために、人々も善を勧めるようになった。
もちろん罪なき者は即座に放免もしたために、これまた人々が善を勧めるようにもなった。
(犯罪聖書には『誰も善を為せない』という類いの記述が多々見られるが、これも無罪放免の
重罪人が方々に蔓延ってしまっていたからでこそある。罪を犯しても無罪であるようなら
人々は勧善を滞らせ、冤罪者を平気で罰するようであっても、やはり勧善を渋るものである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・多方より)
「囚人の罪状をよく調べて、罪ある者は厳格に処刑したために、人々も善を勧めるようになった。
もちろん罪なき者は即座に放免もしたために、これまた人々が善を勧めるようにもなった。
(犯罪聖書には『誰も善を為せない』という類いの記述が多々見られるが、これも無罪放免の
重罪人が方々に蔓延ってしまっていたからでこそある。罪を犯しても無罪であるようなら
人々は勧善を滞らせ、冤罪者を平気で罰するようであっても、やはり勧善を渋るものである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・多方より)
この世には世襲であったほうがいい職業と、そうでない職業との両方がある。
世の中を営んでいく上で最も根幹的なものにあたる職業ほど世襲であったほうがよく、
あってもなくてもどちらでも構わないような瑣末な職業ほど世襲である必要がない。
世襲を基本とすべき職業であっても、倅が極度の出来損ないであったりした場合には
他人に業務を引き継がせるようにすべきこともある。堯や舜が自らの子息に帝業を
継がせなかったり、豊臣の天下を徳川が放伐したりしたことなどもその例だといえる。
というような例外もあった上で、やはり人間社会というのは、総体的には
世襲を基本としていくべきものだともいえる。それはこの「礼記」からの引用
http://bbs77.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/thought/133655801...
などを読んでみても窺えることで、社会的な活動が世襲に即することこそは、
日月星辰の運行にすら人間の営みを合致させる程にも、普遍的なものとなるのである。
世の中が総体的に、世襲に基づく社会運営を貴べなくなってしまっているようなら、
そのような世の中は必然的に乱世ともなっている。堯→舜→禹と禅譲が行われた頃の
中国も伝承上からして乱れていたとされているし、信長→秀吉→家康という天下取りの
継承によって戦国時代の争乱が収拾されたこともまた、未だ記憶に新しいところである。
ただ乱世に世襲などには構っていられなくなるだけでなく、世襲すら一旦は打ち棄てて
までの個々人の実力勝負によってこそ、乱世自体の決着が付けられたりもするのである。
世襲による事業の継承と、個人による実力の発揮とは、ちょうど陰と陽の関係にあり、
どちらが完全に欠けても世の中が成り立つようなことはない。総体社会における
世襲制の普遍性を諾う者といえども、個人としての実力の研鑽を怠ることまでをも
良しとしたりしてはならず、血筋上で恵まれた立場にあるか否かにかかわらず、
それぞれの領分に即した実力の研鑽に励んでいくべきであることには変わりない。
世の中を営んでいく上で最も根幹的なものにあたる職業ほど世襲であったほうがよく、
あってもなくてもどちらでも構わないような瑣末な職業ほど世襲である必要がない。
世襲を基本とすべき職業であっても、倅が極度の出来損ないであったりした場合には
他人に業務を引き継がせるようにすべきこともある。堯や舜が自らの子息に帝業を
継がせなかったり、豊臣の天下を徳川が放伐したりしたことなどもその例だといえる。
というような例外もあった上で、やはり人間社会というのは、総体的には
世襲を基本としていくべきものだともいえる。それはこの「礼記」からの引用
http://bbs77.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/thought/133655801...
などを読んでみても窺えることで、社会的な活動が世襲に即することこそは、
日月星辰の運行にすら人間の営みを合致させる程にも、普遍的なものとなるのである。
世の中が総体的に、世襲に基づく社会運営を貴べなくなってしまっているようなら、
そのような世の中は必然的に乱世ともなっている。堯→舜→禹と禅譲が行われた頃の
中国も伝承上からして乱れていたとされているし、信長→秀吉→家康という天下取りの
継承によって戦国時代の争乱が収拾されたこともまた、未だ記憶に新しいところである。
ただ乱世に世襲などには構っていられなくなるだけでなく、世襲すら一旦は打ち棄てて
までの個々人の実力勝負によってこそ、乱世自体の決着が付けられたりもするのである。
世襲による事業の継承と、個人による実力の発揮とは、ちょうど陰と陽の関係にあり、
どちらが完全に欠けても世の中が成り立つようなことはない。総体社会における
世襲制の普遍性を諾う者といえども、個人としての実力の研鑽を怠ることまでをも
良しとしたりしてはならず、血筋上で恵まれた立場にあるか否かにかかわらず、
それぞれの領分に即した実力の研鑽に励んでいくべきであることには変わりない。
世襲制の肯定の仕方としては、上記のようなあり方が理想で、世の中のあり方一般の
理想形としても申し分がない。世襲制も実力主義もあるべきだとした上で、若干だけ
世襲のほうが実力よりも優先されるべきだという程度に考えるのが最も正しい。両方
ありとしたところで、実力主義を極端に世襲よりも優先させようとしたりするのでは
いけないし、世襲を全否定して完全な実力主義でいたりするのもなおさら不可である。
このあたり、相当に高度な中正論でもあり、極端から極端に走るたわけ者には
なかなか理解し難い話であるにも違いない。要は、「世襲を完全否定してまでの
実力主義一辺倒に走ったりはするべきでない」と言っているわけだが、「じゃあ
実力主義全否定で世襲を全てにするんですか?」などと天邪鬼の極論主義者は返して
来たがるに違いない。そんなこと一言も言ってないのは、上を読んで理解すれば
分かる通りで、極論主義者だから読んでみたって意味が分からないというのなら、
もはやそちらが上知と交わらぬ下愚であると断ずる他ない。別にこちらが説明を
渋っているわけではなく、そちらがあまりにも愚かであるが故に、最善の説明すら
理解できないというまでのことなのだから、こちらが怨まれる筋合いもないというものだ。
「少くして父無き者を之れ孤と謂う。老いて子無き者を之れ独と謂う。老いて妻無き者を之れ矜と謂う。
老いて夫無き者を之れ寡と謂う。此の四者は、天民の窮して告ぐる無き者なり。皆な常餼有らしむ」
「年少でありながら親のない者を弧といい、老いて子のない者を独といい、老いて妻のない者を矜といい、
老いて夫のない者を寡という。この四者は天に仕える民の内では特に困窮して寄る辺もないものなので、
食糧などの支援を行う。(天民なら、老いて子がない運命にも素直に従って、王制による支援を受ける)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・王制第五より)
理想形としても申し分がない。世襲制も実力主義もあるべきだとした上で、若干だけ
世襲のほうが実力よりも優先されるべきだという程度に考えるのが最も正しい。両方
ありとしたところで、実力主義を極端に世襲よりも優先させようとしたりするのでは
いけないし、世襲を全否定して完全な実力主義でいたりするのもなおさら不可である。
このあたり、相当に高度な中正論でもあり、極端から極端に走るたわけ者には
なかなか理解し難い話であるにも違いない。要は、「世襲を完全否定してまでの
実力主義一辺倒に走ったりはするべきでない」と言っているわけだが、「じゃあ
実力主義全否定で世襲を全てにするんですか?」などと天邪鬼の極論主義者は返して
来たがるに違いない。そんなこと一言も言ってないのは、上を読んで理解すれば
分かる通りで、極論主義者だから読んでみたって意味が分からないというのなら、
もはやそちらが上知と交わらぬ下愚であると断ずる他ない。別にこちらが説明を
渋っているわけではなく、そちらがあまりにも愚かであるが故に、最善の説明すら
理解できないというまでのことなのだから、こちらが怨まれる筋合いもないというものだ。
「少くして父無き者を之れ孤と謂う。老いて子無き者を之れ独と謂う。老いて妻無き者を之れ矜と謂う。
老いて夫無き者を之れ寡と謂う。此の四者は、天民の窮して告ぐる無き者なり。皆な常餼有らしむ」
「年少でありながら親のない者を弧といい、老いて子のない者を独といい、老いて妻のない者を矜といい、
老いて夫のない者を寡という。この四者は天に仕える民の内では特に困窮して寄る辺もないものなので、
食糧などの支援を行う。(天民なら、老いて子がない運命にも素直に従って、王制による支援を受ける)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・王制第五より)
何でもかんでも人の言うこと為すことの反対を行こうとするのは「天邪鬼」で、
そんなんじゃ社会生活もままならないから、ほとんどの人間が子供の内に
天邪鬼ばかりでいることは卒業して、大人へと成長していく。
ただ、大人になっても人の言うことを素直には聞かないぐらいのことは当然あって、
普通それは「頑固」と呼ばれ、行き過ぎると「頑迷」と呼ばれ、共感を得られる範囲だと
「反骨」と呼ばれたりする。世の中に反骨が受け入れられる場合もあるのは、実際に
反骨者の言い分のほうがどう聞いてみても筋が通っているぐらいに、世の中の側の常識や
風潮のほうが総出で歪んでしまっていたりすることがあるからで、ちょうどこの「反骨」
という言葉も、ある種の形而上的な革命論に即して提唱された言葉ともなっている。
歪んだ世の中で、自分が正論に即しようとするから反骨にもなり得るのであって、世の中
のほうが正しいのにもかかわらず、自分が間違いに拘泥して反抗的であったりするのなら、
これはただの反社会主義者である。そのような人間が生じてしまうのを未然に防ぐのが
正規教育の使命でもあり、天邪鬼が至当な反骨に結び付くこともあるのを考えてみるなら、
天邪鬼一般以上にも、上記のような反社会主義こそが優先的に矯正されるべきものだといえる。
それなりに正善さを保っている世の中であれば、過ちに拘泥しての反抗主義などを
未然に防ぎ止めていこうとする自浄作用が働くものだが、世の中が総出を挙げて
濁悪にまみれきってしまっているようならばそうも行かず、世人が世人であるにも
関わらず、適当な理由で世の中に反目することを競い合うようなザマにすら陥ってしまう。
イエスが生存していた頃のイスラエルやローマ帝国もそのような極度の濁世だったから、
イエスの他にもヨハネのようなカルト教義を触れ回るならず者が併存していたのである。
そんなんじゃ社会生活もままならないから、ほとんどの人間が子供の内に
天邪鬼ばかりでいることは卒業して、大人へと成長していく。
ただ、大人になっても人の言うことを素直には聞かないぐらいのことは当然あって、
普通それは「頑固」と呼ばれ、行き過ぎると「頑迷」と呼ばれ、共感を得られる範囲だと
「反骨」と呼ばれたりする。世の中に反骨が受け入れられる場合もあるのは、実際に
反骨者の言い分のほうがどう聞いてみても筋が通っているぐらいに、世の中の側の常識や
風潮のほうが総出で歪んでしまっていたりすることがあるからで、ちょうどこの「反骨」
という言葉も、ある種の形而上的な革命論に即して提唱された言葉ともなっている。
歪んだ世の中で、自分が正論に即しようとするから反骨にもなり得るのであって、世の中
のほうが正しいのにもかかわらず、自分が間違いに拘泥して反抗的であったりするのなら、
これはただの反社会主義者である。そのような人間が生じてしまうのを未然に防ぐのが
正規教育の使命でもあり、天邪鬼が至当な反骨に結び付くこともあるのを考えてみるなら、
天邪鬼一般以上にも、上記のような反社会主義こそが優先的に矯正されるべきものだといえる。
それなりに正善さを保っている世の中であれば、過ちに拘泥しての反抗主義などを
未然に防ぎ止めていこうとする自浄作用が働くものだが、世の中が総出を挙げて
濁悪にまみれきってしまっているようならばそうも行かず、世人が世人であるにも
関わらず、適当な理由で世の中に反目することを競い合うようなザマにすら陥ってしまう。
イエスが生存していた頃のイスラエルやローマ帝国もそのような極度の濁世だったから、
イエスの他にもヨハネのようなカルト教義を触れ回るならず者が併存していたのである。
孔子や孟子が活動していた春秋戦国時代の中国も相当な濁世で、権力者がお互いに
私利私欲のための覇権ばかりを競い合っていたのみならず、その権力者に追従しての
邪説異学を捏造する名家や縦横家、法家などの異端の思想家が数多跋扈してもいた。
そんな中で、古来からの正統な礼学を継承し復興しようとしていた、孔孟に
代表される古代の儒者は、当時の世相からいえば反骨者の部類だったとも言え、
そこにもやはり、ある種の天邪鬼的な要素が備わっていたのだとも推測できる。
孔子も、再三述べている通り、母子家庭育ちの妾腹の私生児という不遇に生まれているし、
孟子も、母親の賢母としての逸話は残っているのに、父親の経歴はほとんど不詳といった
いびつな家系に生まれ育っている。そのような複雑な境遇が本人たちに儒者としての大成を
志させた可能性がなくもないと言えるが、その選択は決して間違ったものではなかったから、
天邪鬼志向も反骨者としての体裁に止まり、大学者としての立場を揺ぎ無くさせられもした。
そういった好例もあるからには、「天邪鬼そのものを全否定すればいいというものでもない、
天邪鬼すら反骨として善用できる場合があるのだから、天邪鬼が度し難い反社会主義に
発展してしまう場合に限って駆逐の対象にすべきだ」ということが結論付けられもする。
天邪鬼の全否定に基づく、反骨志向までものひとしなみな駆逐が、市井での横議すら許さぬ
恐怖政治にすら発展しかねないものだから、この当たりのさじ加減は慎重でなければならない。
「鄙夫は与に君に事う可けんや。其れ未だ之れを得ざるや、之れを得んことを患え、既に之れ
を得れば、之れを失わんことを患える。苟くも之れを失わんことを患えば、至らざる所無し」
「つまらない性根の人間とは共に主君にお仕えすることもできない。何かまだ得られない
ものがあればどうやってそれを得ようかと腐心し、一旦ものを得れば今度はそれを失わない
ことにばかりを腐心する。得たものを失わないことにばかり腐心するあまり、なりふりすら
構わなくなるのだから。(利害得失第一な者は君子たるには値しない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・陽貨第十七・一五より)
私利私欲のための覇権ばかりを競い合っていたのみならず、その権力者に追従しての
邪説異学を捏造する名家や縦横家、法家などの異端の思想家が数多跋扈してもいた。
そんな中で、古来からの正統な礼学を継承し復興しようとしていた、孔孟に
代表される古代の儒者は、当時の世相からいえば反骨者の部類だったとも言え、
そこにもやはり、ある種の天邪鬼的な要素が備わっていたのだとも推測できる。
孔子も、再三述べている通り、母子家庭育ちの妾腹の私生児という不遇に生まれているし、
孟子も、母親の賢母としての逸話は残っているのに、父親の経歴はほとんど不詳といった
いびつな家系に生まれ育っている。そのような複雑な境遇が本人たちに儒者としての大成を
志させた可能性がなくもないと言えるが、その選択は決して間違ったものではなかったから、
天邪鬼志向も反骨者としての体裁に止まり、大学者としての立場を揺ぎ無くさせられもした。
そういった好例もあるからには、「天邪鬼そのものを全否定すればいいというものでもない、
天邪鬼すら反骨として善用できる場合があるのだから、天邪鬼が度し難い反社会主義に
発展してしまう場合に限って駆逐の対象にすべきだ」ということが結論付けられもする。
天邪鬼の全否定に基づく、反骨志向までものひとしなみな駆逐が、市井での横議すら許さぬ
恐怖政治にすら発展しかねないものだから、この当たりのさじ加減は慎重でなければならない。
「鄙夫は与に君に事う可けんや。其れ未だ之れを得ざるや、之れを得んことを患え、既に之れ
を得れば、之れを失わんことを患える。苟くも之れを失わんことを患えば、至らざる所無し」
「つまらない性根の人間とは共に主君にお仕えすることもできない。何かまだ得られない
ものがあればどうやってそれを得ようかと腐心し、一旦ものを得れば今度はそれを失わない
ことにばかりを腐心する。得たものを失わないことにばかり腐心するあまり、なりふりすら
構わなくなるのだから。(利害得失第一な者は君子たるには値しない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・陽貨第十七・一五より)
「其の相い侵奪する者有れば、之れを罪して赦さず」
「お互いの財物を侵奪し合っているような乱れた界隈があれば、それら全体を有罪と見なして赦さないようにする。
(お互いに許し合っているとしたところで、そのような界隈の存在自体が社会全体の風紀を乱すことになるから)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・王制第六より)
何でもかんでも自分たち同士でだけは許容しまくり、寛容や和解しまくりの
なあなあでやって来た、キリスト教圏だとか日本の財界だとか警察だとかいった
集団全体が、最終的に「世界で最も許されざる集団」とも化してしまった。
個人や小集団としての自由率と、全体社会における自分たち自身の責任履行率というのは反比例的な
関係にあり、両者の釣り合いを取っていくのが仁者である一方、個人や小集団としての自由を捨て去って
までの利他に励むのが真っ当な出家修行者である。この二つは決して敵対的な関係にはなく、かつての
日本社会における公家や武家と仏門のように、全く共存が可能なものとなっている。一方、この二つと
決定的な敵対関係にあるか、もしくはより劣位なものとして扱われざるを得ないものとして、社会的責任を
放棄してまでの身勝手な自由を求める個人や小集団といったものがあり、これを無制限に自分たちの内
でだけは許容し続けてきたのが欧米キリスト教圏であったり、今の日本の財界や警察界であったりする。
キリスト教圏や日本の腐敗権力とは逆に、個人の自由を徹底的な制限下に置いている社会として、
今の中国社会などがある。あくまで庶民が徹底的な制限下に置かれているだけで、制限する側に
回っている共産党員などは相当な好き勝手が許されているようでもあるから、決して中国の全部を
褒められたりしたもんではないが、公的責任を蔑ろにしてまでの個人の好き勝手を自分たちが無制限に
許容し続けてきた結果、世界中に飢餓や戦乱といった陰惨なしわ寄せを及ぼしてしまっている
資本主義社会などと比べれば、中国も世界に及ぼす悪影響を相当に抑えられたほうともなっている。
「お互いの財物を侵奪し合っているような乱れた界隈があれば、それら全体を有罪と見なして赦さないようにする。
(お互いに許し合っているとしたところで、そのような界隈の存在自体が社会全体の風紀を乱すことになるから)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・王制第六より)
何でもかんでも自分たち同士でだけは許容しまくり、寛容や和解しまくりの
なあなあでやって来た、キリスト教圏だとか日本の財界だとか警察だとかいった
集団全体が、最終的に「世界で最も許されざる集団」とも化してしまった。
個人や小集団としての自由率と、全体社会における自分たち自身の責任履行率というのは反比例的な
関係にあり、両者の釣り合いを取っていくのが仁者である一方、個人や小集団としての自由を捨て去って
までの利他に励むのが真っ当な出家修行者である。この二つは決して敵対的な関係にはなく、かつての
日本社会における公家や武家と仏門のように、全く共存が可能なものとなっている。一方、この二つと
決定的な敵対関係にあるか、もしくはより劣位なものとして扱われざるを得ないものとして、社会的責任を
放棄してまでの身勝手な自由を求める個人や小集団といったものがあり、これを無制限に自分たちの内
でだけは許容し続けてきたのが欧米キリスト教圏であったり、今の日本の財界や警察界であったりする。
キリスト教圏や日本の腐敗権力とは逆に、個人の自由を徹底的な制限下に置いている社会として、
今の中国社会などがある。あくまで庶民が徹底的な制限下に置かれているだけで、制限する側に
回っている共産党員などは相当な好き勝手が許されているようでもあるから、決して中国の全部を
褒められたりしたもんではないが、公的責任を蔑ろにしてまでの個人の好き勝手を自分たちが無制限に
許容し続けてきた結果、世界中に飢餓や戦乱といった陰惨なしわ寄せを及ぼしてしまっている
資本主義社会などと比べれば、中国も世界に及ぼす悪影響を相当に抑えられたほうともなっている。
結局のところ、どちらも両極端であることには変わりなく、キリスト教圏や日本の腐敗権力ほどにも
個人や小集団の身勝手を無制限に許容し続けるのも許されざることだし、逆に今の中国社会ほどにも個人の
自由が徹底的な制限下に置かれているのも由々しきことである。ちょうど両者はコインの裏表のようなもので、
個人や小集団の身勝手を無制限に許容するような派閥があればこそ、個人の自由を一律して徹底制限するような
派閥も呼応的に発生してしまっている。今の中国だけでなく、イスラム圏もその原初から、キリスト教圏の
身勝手さに反発する形で生じて来たものであり、一日五回の礼拝や執拗なほどもの女性差別、飲酒や豚食の
厳禁といったその規律の厳しさも、あくまでキリスト教やユダヤ教に反発して生じて来たものでこそある。
キリスト教圏級の個人や小集団の身勝手の許容とは一切無縁だった、かつての東洋社会の様相などを鑑みるに、
確かに個人や小集団の自由が無制限だったりはしなかった一方で、イスラム圏や今の中国ほどにも、個人の自由が
徹底して制限されていたようなこともない。漢代や唐代の中国だとか、江戸時代の日本だとかでも、個人利益の
収集を生業とする商業が徹底して統制されていたようなこともないし、性風俗の取り締りが極端に厳しかったり
したこともない、ただ、一部の有志が出家修行者としての浄行に励むことで、修己治人の強化版となる形で世相の
防腐にも一役買っていたりしたこともあり、ただ取り締まりが緩かったというばかりのことではないともいえる。
目指すべくはそのような、個人的自由と公共福祉の釣り合いが絶妙に取られている世の中でこそあり、
個人や小集団の自由ばかりを無制限に許容する世の中でもなければ、それらを徹底的に制限する世の中でもない。
自由と公益の釣り合いの取れた世の中の実現を画策していく人間にとって、無制限な自由の許容を求めるものと、
徹底的な自由の制限を強いるものと、いずれもが味方とはならない。そのような人間ばかりが多数群がって
しまっている現代社会において、即座に自分の味方となってくれるような人間もそう多くはないということを
わきまえた上で、なおのこと志しの実現を目指していかなければならないのだから、まさに前途多難だといえる。
個人や小集団の身勝手を無制限に許容し続けるのも許されざることだし、逆に今の中国社会ほどにも個人の
自由が徹底的な制限下に置かれているのも由々しきことである。ちょうど両者はコインの裏表のようなもので、
個人や小集団の身勝手を無制限に許容するような派閥があればこそ、個人の自由を一律して徹底制限するような
派閥も呼応的に発生してしまっている。今の中国だけでなく、イスラム圏もその原初から、キリスト教圏の
身勝手さに反発する形で生じて来たものであり、一日五回の礼拝や執拗なほどもの女性差別、飲酒や豚食の
厳禁といったその規律の厳しさも、あくまでキリスト教やユダヤ教に反発して生じて来たものでこそある。
キリスト教圏級の個人や小集団の身勝手の許容とは一切無縁だった、かつての東洋社会の様相などを鑑みるに、
確かに個人や小集団の自由が無制限だったりはしなかった一方で、イスラム圏や今の中国ほどにも、個人の自由が
徹底して制限されていたようなこともない。漢代や唐代の中国だとか、江戸時代の日本だとかでも、個人利益の
収集を生業とする商業が徹底して統制されていたようなこともないし、性風俗の取り締りが極端に厳しかったり
したこともない、ただ、一部の有志が出家修行者としての浄行に励むことで、修己治人の強化版となる形で世相の
防腐にも一役買っていたりしたこともあり、ただ取り締まりが緩かったというばかりのことではないともいえる。
目指すべくはそのような、個人的自由と公共福祉の釣り合いが絶妙に取られている世の中でこそあり、
個人や小集団の自由ばかりを無制限に許容する世の中でもなければ、それらを徹底的に制限する世の中でもない。
自由と公益の釣り合いの取れた世の中の実現を画策していく人間にとって、無制限な自由の許容を求めるものと、
徹底的な自由の制限を強いるものと、いずれもが味方とはならない。そのような人間ばかりが多数群がって
しまっている現代社会において、即座に自分の味方となってくれるような人間もそう多くはないということを
わきまえた上で、なおのこと志しの実現を目指していかなければならないのだから、まさに前途多難だといえる。
「曾子曰く、上其の道を失いて民散ずること久し。如し其の情を得ば、則ち哀矜して喜ぶこと勿かれ(既出)」
「曾子の言葉。『世の中の支配者までもが道理を見失って、民たちも気が緩むようになってからすでに久しい。
もし犯罪の実情をつかんだりした時には、ただ哀れむばかりで、決して喜んだりしてはならない』」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子張第十九・一九より)
上の曾子の言葉など、個人犯罪の責任をお上に転嫁したものにすらなっていて、今の世の中などでは
決して聞き入れられるようなものじゃない。いやなことを「世の中のせい」にすることほど不毛なことも
他にないとされ、何もかもを本人自身の責任とするのが潔いこととして無制限に推奨されている現代。それは、
お上が完全に世の中の統治責任を放棄しているがための、プロパガンダすらをもかませられているが故の世論
なのでもあり、本来は上記ほどにも、被支配者の責任すら支配者が負うようであってしかるべきなのである。
被支配者たる庶民が、為政者と自分たちの関係を「親と子」の関係のように捉えて、まるで親に保護された
子供のようでいるようなことがあったって、別に構わないのである。確かにそれ以上にも、為政者などあってなき
もののように民たちが思っていられながら、それなりに世相も治められているような無為自然の統治がより優良なもの
であるには違いないが、お上から下民に至るまで誰しもが勝手気ままのやりたい放題でいるせいで、世の中が破滅に
見舞われるぐらいなら、まだ責任あるお上が民たちを子供のような保護下に置く統治のほうがマシであるといえる。
無為自然のうちから民たちを善導する無為自然の統治は、まだまだ今の世の中で実現していくのも難しいものだ。
それほどにも官民上下の分け隔てない放辟邪侈が蔓延してしまっている世の中だから、一時の強権支配すらかませない
ことには世相を十分に穏健化させることもできそうにない。ただ、そんなものは当然すぐに取り払われるべきで、
その後に官民が親子のような関係となる作為的統治が敷かれ、それに基づく民度の底上げに連動して、徐々に
無為自然の統治へと移行していくというのが、乱世を治世へと反正する手順としてはごく無難な定石になるといえる。
「曾子の言葉。『世の中の支配者までもが道理を見失って、民たちも気が緩むようになってからすでに久しい。
もし犯罪の実情をつかんだりした時には、ただ哀れむばかりで、決して喜んだりしてはならない』」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子張第十九・一九より)
上の曾子の言葉など、個人犯罪の責任をお上に転嫁したものにすらなっていて、今の世の中などでは
決して聞き入れられるようなものじゃない。いやなことを「世の中のせい」にすることほど不毛なことも
他にないとされ、何もかもを本人自身の責任とするのが潔いこととして無制限に推奨されている現代。それは、
お上が完全に世の中の統治責任を放棄しているがための、プロパガンダすらをもかませられているが故の世論
なのでもあり、本来は上記ほどにも、被支配者の責任すら支配者が負うようであってしかるべきなのである。
被支配者たる庶民が、為政者と自分たちの関係を「親と子」の関係のように捉えて、まるで親に保護された
子供のようでいるようなことがあったって、別に構わないのである。確かにそれ以上にも、為政者などあってなき
もののように民たちが思っていられながら、それなりに世相も治められているような無為自然の統治がより優良なもの
であるには違いないが、お上から下民に至るまで誰しもが勝手気ままのやりたい放題でいるせいで、世の中が破滅に
見舞われるぐらいなら、まだ責任あるお上が民たちを子供のような保護下に置く統治のほうがマシであるといえる。
無為自然のうちから民たちを善導する無為自然の統治は、まだまだ今の世の中で実現していくのも難しいものだ。
それほどにも官民上下の分け隔てない放辟邪侈が蔓延してしまっている世の中だから、一時の強権支配すらかませない
ことには世相を十分に穏健化させることもできそうにない。ただ、そんなものは当然すぐに取り払われるべきで、
その後に官民が親子のような関係となる作為的統治が敷かれ、それに基づく民度の底上げに連動して、徐々に
無為自然の統治へと移行していくというのが、乱世を治世へと反正する手順としてはごく無難な定石になるといえる。
良くも悪しくも、今という時代は官民が親子のような関係として受け止められているような時代じゃない。官なんて
民の使いっパシリぐらいにしか思われていない今という時代に、さも自分をみなしごか迷える子羊のように考える
者がいたとして、さらにそのような人間が架空の邪神などへの帰依にこそ親子に比肩する関係を認めたりしたとする。
そしたらそれが、官民こそを親子の関係に比肩させようとする撥乱反正の試みを妨げる大きな障壁ともなってしまう。
官民を親子のような関係にして行くこと自体、過渡的な措置ではあるが、それすらをも不能と化してしまっているが
故に、後々に講じられる無為自然の善導統治への移行すらもがまったく滞ったままにさせられてしまうのである。
親子関係というのは、世俗の内側の家庭関係である。それに比肩させられる崇敬対象となる神仏としては、
第一に先祖の祖霊があり、その他では主君の先祖などが挙げられる。そうでもないような神仏一般というのは、
あくまで超俗の帰依対象とすべきもので、それらを決して親子の関係などに比肩させたりすべきではない。
どこの馬の骨とも知れないような不審な神と、自分との関係を親子関係に見立てたりされたのでは、
官民上下の関係を親子に見立てることを妨害することにすらなってしまうためよろしくない。だからこそ、
基本としては超俗的な神仏を祭る宗教のみが、応用的な宗教としても公認されてしかるべきなのである。
「学は及ばざるが如くするも、猶お之れをを失わんことを恐る」
「学問は(昔の聖賢や優れた先生先輩などに)なかなか追いつくこともできないぐらいの心持ちでいながら、
なおかつ今までに学んで来たことを失ってしまわないかと恐れるぐらいの慎重な心持ちで為すべきである。
(安易に他者にあやかってそれで終わりみたいな邪義を触れ回られては、正学にとっての迷惑ともなる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・泰伯第八・一七より)
民の使いっパシリぐらいにしか思われていない今という時代に、さも自分をみなしごか迷える子羊のように考える
者がいたとして、さらにそのような人間が架空の邪神などへの帰依にこそ親子に比肩する関係を認めたりしたとする。
そしたらそれが、官民こそを親子の関係に比肩させようとする撥乱反正の試みを妨げる大きな障壁ともなってしまう。
官民を親子のような関係にして行くこと自体、過渡的な措置ではあるが、それすらをも不能と化してしまっているが
故に、後々に講じられる無為自然の善導統治への移行すらもがまったく滞ったままにさせられてしまうのである。
親子関係というのは、世俗の内側の家庭関係である。それに比肩させられる崇敬対象となる神仏としては、
第一に先祖の祖霊があり、その他では主君の先祖などが挙げられる。そうでもないような神仏一般というのは、
あくまで超俗の帰依対象とすべきもので、それらを決して親子の関係などに比肩させたりすべきではない。
どこの馬の骨とも知れないような不審な神と、自分との関係を親子関係に見立てたりされたのでは、
官民上下の関係を親子に見立てることを妨害することにすらなってしまうためよろしくない。だからこそ、
基本としては超俗的な神仏を祭る宗教のみが、応用的な宗教としても公認されてしかるべきなのである。
「学は及ばざるが如くするも、猶お之れをを失わんことを恐る」
「学問は(昔の聖賢や優れた先生先輩などに)なかなか追いつくこともできないぐらいの心持ちでいながら、
なおかつ今までに学んで来たことを失ってしまわないかと恐れるぐらいの慎重な心持ちで為すべきである。
(安易に他者にあやかってそれで終わりみたいな邪義を触れ回られては、正学にとっての迷惑ともなる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・泰伯第八・一七より)
極刑級の大罪を犯しておきながらまんまと逃げおおせているような人間こそは、まさに
「死んでいるも同然の人間」であるといえる。捕まって処分されようがされるまいが
善を為す生の楽しみ>死の無苦楽>悪を為す生の苦しみ
であり、あまりにも大悪を為しすぎたがために一生善楽に与る見込みも立たなく
なってしまっている人間ともなれば、さっさと死んで「己れの生存という悪業」
を絶つに越したこともないことにすらなってしまっているのである。
では、悪を為すわけでもなければ善を為すわけでもない無為の状態にある人間は
どうなのかって、別に無為だからといって死並みに無苦楽であるとも限らないのである。
世の中がどこもかしこも罪悪にまみれて、「行動即犯罪」という程にも作為に罪業が
必ず伴ってしまっているのであれば、自分が無為であることそれ自体が善行にすらなる。
だから、何もしないでいるだけで善を為す楽しみにも与れたりする。一方で、世の中の乱れが
相応に抑制されて、善を為すことだってそれなりに出来なくもないようになってから未だ
何も為さないでいるともなれば、今度は無為であることそれ自体が悪行にもなってしまう。
故に、何もしないでいることに後ろめたさなどからなる苦しみが付きまとうようにもなる。
何をしていようが何もしていまいが、人間は生きている以上は生きている。
何もしないでいることすらもが世の中との関係によって善行扱いとなったり、
悪行扱いとなったりもする。ただ生きているというだけですでに多少の活動であり、
それを死と同等のものなどと考えるのも、大雑把に過ぎることだといえる。
「死んでいるも同然の人間」であるといえる。捕まって処分されようがされるまいが
善を為す生の楽しみ>死の無苦楽>悪を為す生の苦しみ
であり、あまりにも大悪を為しすぎたがために一生善楽に与る見込みも立たなく
なってしまっている人間ともなれば、さっさと死んで「己れの生存という悪業」
を絶つに越したこともないことにすらなってしまっているのである。
では、悪を為すわけでもなければ善を為すわけでもない無為の状態にある人間は
どうなのかって、別に無為だからといって死並みに無苦楽であるとも限らないのである。
世の中がどこもかしこも罪悪にまみれて、「行動即犯罪」という程にも作為に罪業が
必ず伴ってしまっているのであれば、自分が無為であることそれ自体が善行にすらなる。
だから、何もしないでいるだけで善を為す楽しみにも与れたりする。一方で、世の中の乱れが
相応に抑制されて、善を為すことだってそれなりに出来なくもないようになってから未だ
何も為さないでいるともなれば、今度は無為であることそれ自体が悪行にもなってしまう。
故に、何もしないでいることに後ろめたさなどからなる苦しみが付きまとうようにもなる。
何をしていようが何もしていまいが、人間は生きている以上は生きている。
何もしないでいることすらもが世の中との関係によって善行扱いとなったり、
悪行扱いとなったりもする。ただ生きているというだけですでに多少の活動であり、
それを死と同等のものなどと考えるのも、大雑把に過ぎることだといえる。
西洋と違って、東洋では人文学的な考察にすら数理的な体系を盛り込む。数学で0が
一つの数字として見なされるのと全く同じようにして、無為すらをも一つの活動として捉える。
それに基づいて無為自然を尊ぶ道家思想や、不動を至尊のものとする仏教が提唱されたのでもある。
無為を尊ぶ道家や出家隠遁を決め込む小乗仏教だけでなく、世俗での善行を旨とする儒家や
大乗仏教においても、無為を一つの人間のあり方として尊重する大前提がやはり備わっていて、
故に「悪いことをするぐらいなら何もしないでいる」ぐらいの分別は付くようにもなってる。
権力腐敗きわまって善行など全く覚束なくなっていた戦国時代の中国で、道家も無為自然を尊ぶ
ことを提唱していたし、仏教が興隆して文化的にも最盛期を迎えていた頃のインドにおいてこそ、
未だ積極的な善行に励もうともしない上座部に反発して大乗仏教が興隆されたりもしたように、
そこでは無為そのものを「活きたもの」として、時宜に即して臨機応変に捉えていたことが窺える。
要は、人文学と数理学を融合させて常にものを考えてきたというぐらいのことなわけで、それすら
をも怠ってきたような界隈が存在していることのほうが、むしろ間抜けに過ぎていたのだといえる。
「于嗟、闊れるに、我と活きず。于嗟、洵かれる、我と信ぜず」
「ああ、かつては固く誓い合ったのに、もはや共に生きることもできない。
ああ、もはや遠ざかってしまった、もはや信じることもできない。
(『信』という作為に生きた心地を得るということがある。それは必ずしも悪いことではない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・邶風・撃鼓より)
一つの数字として見なされるのと全く同じようにして、無為すらをも一つの活動として捉える。
それに基づいて無為自然を尊ぶ道家思想や、不動を至尊のものとする仏教が提唱されたのでもある。
無為を尊ぶ道家や出家隠遁を決め込む小乗仏教だけでなく、世俗での善行を旨とする儒家や
大乗仏教においても、無為を一つの人間のあり方として尊重する大前提がやはり備わっていて、
故に「悪いことをするぐらいなら何もしないでいる」ぐらいの分別は付くようにもなってる。
権力腐敗きわまって善行など全く覚束なくなっていた戦国時代の中国で、道家も無為自然を尊ぶ
ことを提唱していたし、仏教が興隆して文化的にも最盛期を迎えていた頃のインドにおいてこそ、
未だ積極的な善行に励もうともしない上座部に反発して大乗仏教が興隆されたりもしたように、
そこでは無為そのものを「活きたもの」として、時宜に即して臨機応変に捉えていたことが窺える。
要は、人文学と数理学を融合させて常にものを考えてきたというぐらいのことなわけで、それすら
をも怠ってきたような界隈が存在していることのほうが、むしろ間抜けに過ぎていたのだといえる。
「于嗟、闊れるに、我と活きず。于嗟、洵かれる、我と信ぜず」
「ああ、かつては固く誓い合ったのに、もはや共に生きることもできない。
ああ、もはや遠ざかってしまった、もはや信じることもできない。
(『信』という作為に生きた心地を得るということがある。それは必ずしも悪いことではない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・邶風・撃鼓より)
「君子にして不仁なる者有らんか。未だ小人にして仁なる者あらざるなり(既出)」
「君子であっても不仁な者はいるが、小人でいながら仁者たり得た者はいない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・七より)
未だ自分が仁ならざる小人や君子だろうとも、仁を目指すぐらいのことはできる。
ただ当然、仁を目指すぐらいであるのなら、自分が未だ小人止まりであるのを恥じたり、
未だ仁ならざる君子止まりでしかないことに憤ったりするものである。決して自分が不仁者止まりで
あることに安んじきったりはせず、いかにして不仁者としての自己を超克していくかを企て続けて行く。
もちろん、そんなことを一切目指さないというのも、一つのあり方である。
戦国時代のような寸分の徳行も為し得ない時代に、未だ孟子のような徒労同然の仁政の試みを続けるよりは、
もはや荘子や列子のような放り投げを決め込んでの自重に務めておくのも一つの手だと言える。
ただ、この場合には自分自身が何らかの社会的優遇を受けたりするようなことも全く欲したりはせず、
腐敗まみれな権力機構との関わりなども一切絶って、権力犯罪者たちの自滅をもただ静観するばかり。
儒家などにも特有の権力への野望に対して批判的であるからには、それぐらいの潔さでもいるのである。
上記二つのあり方ならいいわけだが、自分が小人でありながら富貴栄達を目指すとなれば、
それこそ眉をひそめざるを得ないような試みと見なす他なくなる。近来の民主主義社会ではそればかりが
礼賛や推進の対象となって来たわけだが、その結果は「人類滅亡寸前」という現状を見ての通りである。
「君子であっても不仁な者はいるが、小人でいながら仁者たり得た者はいない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・七より)
未だ自分が仁ならざる小人や君子だろうとも、仁を目指すぐらいのことはできる。
ただ当然、仁を目指すぐらいであるのなら、自分が未だ小人止まりであるのを恥じたり、
未だ仁ならざる君子止まりでしかないことに憤ったりするものである。決して自分が不仁者止まりで
あることに安んじきったりはせず、いかにして不仁者としての自己を超克していくかを企て続けて行く。
もちろん、そんなことを一切目指さないというのも、一つのあり方である。
戦国時代のような寸分の徳行も為し得ない時代に、未だ孟子のような徒労同然の仁政の試みを続けるよりは、
もはや荘子や列子のような放り投げを決め込んでの自重に務めておくのも一つの手だと言える。
ただ、この場合には自分自身が何らかの社会的優遇を受けたりするようなことも全く欲したりはせず、
腐敗まみれな権力機構との関わりなども一切絶って、権力犯罪者たちの自滅をもただ静観するばかり。
儒家などにも特有の権力への野望に対して批判的であるからには、それぐらいの潔さでもいるのである。
上記二つのあり方ならいいわけだが、自分が小人でありながら富貴栄達を目指すとなれば、
それこそ眉をひそめざるを得ないような試みと見なす他なくなる。近来の民主主義社会ではそればかりが
礼賛や推進の対象となって来たわけだが、その結果は「人類滅亡寸前」という現状を見ての通りである。
最低最悪の選択肢に対する代案というのは、ほぼ必ず二つ以上は挙げられるものだ。最低最悪
よりも多少マシである代案と、そのマシよりもさらに向上的である代案との二つ、あるいはそれ以外。
実物の代替として儒家や道家や仏教などの理念を掲げてみたりもするが、どれを抽出する場合にも、
「こうであればまだマシ」「こうであればもっといい」というような評価と共に提示されていくもの。
ただ一つの代替だけを提示してくれたほうが分かりやすいということもあるかもしれないが、
極端から極端に走る性向を持ち越したままでは、また最低最悪に落ち込む危険性も高いままだから、
代替を一点ばかりに絞ることもあまりしようとはしないのである。最低最悪を抜け出した先に
あるものがまた一極的であったりはせず、多様的であることにこそ慣れていくべきなのだから。
孔子や釈迦が、東洋思想宗教史上でも至尊の聖賢だったことは間違いないが、さりとて孔子が
歴史上に唯一無二の儒者であるわけでもなければ、釈迦が唯一無二の仏者であるわけでもない。
その功績が天地万物に恒久普遍の道理や真理の把捉であればこそ、その後光に与っての後続の
儒者や仏者として大成したものが、孟子や朱子や竜樹や空海のようにいくらでもいるわけで、
アブラハム教などに特有の「唯一絶対」という志向はそこでは通用しないのである。思想哲学や
宗教の内から「英雄たちの群雄割拠」とでもいったような様相を呈しているのが、最低最悪から
一段も二段も上った先にある領域なわけだから、それを解せるだけの男らしさもまた必要になるのである。
「邦君の妻、君之れを称して夫人と曰う。夫人自ら称して小童と曰う」
「国君の妻は、主君が呼ぶ場合には『夫人』という。夫人本人は自称で『こわっぱ』という。
(夫人の謙りとしては『こわっぱ』という自称もありである。大丈夫の謙り方ではないが)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・季氏第十六・一四より)
よりも多少マシである代案と、そのマシよりもさらに向上的である代案との二つ、あるいはそれ以外。
実物の代替として儒家や道家や仏教などの理念を掲げてみたりもするが、どれを抽出する場合にも、
「こうであればまだマシ」「こうであればもっといい」というような評価と共に提示されていくもの。
ただ一つの代替だけを提示してくれたほうが分かりやすいということもあるかもしれないが、
極端から極端に走る性向を持ち越したままでは、また最低最悪に落ち込む危険性も高いままだから、
代替を一点ばかりに絞ることもあまりしようとはしないのである。最低最悪を抜け出した先に
あるものがまた一極的であったりはせず、多様的であることにこそ慣れていくべきなのだから。
孔子や釈迦が、東洋思想宗教史上でも至尊の聖賢だったことは間違いないが、さりとて孔子が
歴史上に唯一無二の儒者であるわけでもなければ、釈迦が唯一無二の仏者であるわけでもない。
その功績が天地万物に恒久普遍の道理や真理の把捉であればこそ、その後光に与っての後続の
儒者や仏者として大成したものが、孟子や朱子や竜樹や空海のようにいくらでもいるわけで、
アブラハム教などに特有の「唯一絶対」という志向はそこでは通用しないのである。思想哲学や
宗教の内から「英雄たちの群雄割拠」とでもいったような様相を呈しているのが、最低最悪から
一段も二段も上った先にある領域なわけだから、それを解せるだけの男らしさもまた必要になるのである。
「邦君の妻、君之れを称して夫人と曰う。夫人自ら称して小童と曰う」
「国君の妻は、主君が呼ぶ場合には『夫人』という。夫人本人は自称で『こわっぱ』という。
(夫人の謙りとしては『こわっぱ』という自称もありである。大丈夫の謙り方ではないが)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・季氏第十六・一四より)
詭弁や概念に人間の社会規範を司らせることも、仏説上の方便などとしてであれば害に
なるとも限らない。諸行無常や諸法実相や因果応報といった原則上の絶対真理に即して
提唱される方便であれば、悪人正機並みに詭弁的なものであろうとも、確かな回向となる。
上記のような仏法上の絶対真理であるとか、人間道徳とかに決定的に反したりしない限りでの
詭弁なら方便や冗談の域に止まるけれども、そこを逸脱した詭弁になると、途端に甚大な害悪を帯びる。
そしてそのような逸脱的な詭弁の流布すらをも承認するのが「宗教」という枠組みでもあるから、仏教なども
宗教の内ではあるにしろ、宗教という枠組みをもうこれ以上無制限に容認してやってていようなこともない。
「宗教」とか「思想」とか「哲学」とか、教学一般を指す言葉の下に何もかもを容認することからして
「雑家」という異端思想に基づくのであり、今ではそれが「自由主義」の名の下に奨励されてもいる。
雑家の著名人としては、秦帝国の宰相であり始皇帝の実父でもあった呂不韋がいるが、その呂不韋の
学術姿勢たるや、儒家といわず道家といわず法家といわず名家といわず墨家といわず、当時の代表的な学派を
適当に寄せ集めてごちゃ混ぜにしたというばかりのもので、その集大成の書とされる「呂覧(呂氏春秋)」も、
歴史資料としての価値は多少あったところで、思想哲学書としての価値には全く乏しいものとなっている。
日本仏教の宗派としては雑家的な側面の色濃い天台宗も、その創始の頃から真言密教には一目置かされて、
平安末期ごろからの僧団腐敗も著しいものとなり、総本山である比叡山を下りての独立的な布教に務めた
法然や親鸞や栄西や道元といった名僧こそは、浄土門や禅門などの専門流派を興隆させもしたのだった。
雑家は雑家で一つの学派ないし教派であり、そこに学者や宗教家のあり方の全てを還元するようでは、
かえって学問や信教全体がのっぺりとした味気のないものと化してしまう。学術であれば、宗教ですら
あれば即座に保護するというような姿勢で以って、みそもくそも一緒くたに教学全体を奨励した挙句に、
数多の宗教嫌いや学者嫌いを発生させての、教学文化全体の衰退を招いてしまうことともなる。
なるとも限らない。諸行無常や諸法実相や因果応報といった原則上の絶対真理に即して
提唱される方便であれば、悪人正機並みに詭弁的なものであろうとも、確かな回向となる。
上記のような仏法上の絶対真理であるとか、人間道徳とかに決定的に反したりしない限りでの
詭弁なら方便や冗談の域に止まるけれども、そこを逸脱した詭弁になると、途端に甚大な害悪を帯びる。
そしてそのような逸脱的な詭弁の流布すらをも承認するのが「宗教」という枠組みでもあるから、仏教なども
宗教の内ではあるにしろ、宗教という枠組みをもうこれ以上無制限に容認してやってていようなこともない。
「宗教」とか「思想」とか「哲学」とか、教学一般を指す言葉の下に何もかもを容認することからして
「雑家」という異端思想に基づくのであり、今ではそれが「自由主義」の名の下に奨励されてもいる。
雑家の著名人としては、秦帝国の宰相であり始皇帝の実父でもあった呂不韋がいるが、その呂不韋の
学術姿勢たるや、儒家といわず道家といわず法家といわず名家といわず墨家といわず、当時の代表的な学派を
適当に寄せ集めてごちゃ混ぜにしたというばかりのもので、その集大成の書とされる「呂覧(呂氏春秋)」も、
歴史資料としての価値は多少あったところで、思想哲学書としての価値には全く乏しいものとなっている。
日本仏教の宗派としては雑家的な側面の色濃い天台宗も、その創始の頃から真言密教には一目置かされて、
平安末期ごろからの僧団腐敗も著しいものとなり、総本山である比叡山を下りての独立的な布教に務めた
法然や親鸞や栄西や道元といった名僧こそは、浄土門や禅門などの専門流派を興隆させもしたのだった。
雑家は雑家で一つの学派ないし教派であり、そこに学者や宗教家のあり方の全てを還元するようでは、
かえって学問や信教全体がのっぺりとした味気のないものと化してしまう。学術であれば、宗教ですら
あれば即座に保護するというような姿勢で以って、みそもくそも一緒くたに教学全体を奨励した挙句に、
数多の宗教嫌いや学者嫌いを発生させての、教学文化全体の衰退を招いてしまうことともなる。
この世界、この宇宙の物事というのは、一元的よりは二元的であるもののほうがほとんどである。
太陽が地上に熱エネルギーをもたらすと共に、月が斥力によって波浪を起こすなどすることで、
地球の生態系も初めて成立している。人間も男と女に性が分かれているのが健全な状態で、
両性具有や性的不具こそは奇形ともなっている。にもかかわらず学問や信教に限って、それそのものが
一元的なものとしてこそ尊ばれたり、その内部破損が無制限に容認されたりすることのほうが
異常なのであり、その内側においてある種の差別が生じたりするほうがかえって自然なのである。
要は、学問や宗教のうちでも、特に正統なものが尊ばれて異端なものが賤しまれるといった程度の
篩い分けがあってしかるべきだということで、学問全般、宗教全般を無制限に奨励する雑家的なあり方を
もう少し控えていくようにすべきだというわけだけども、そのためには、「自由主義」もまた「雑家の美化」
でしかないという認識をもう少し広めていくようにしなければならない。「学問の自由、信教の自由が
閉ざされる」といえば後退的に聞こえるけども、「雑家の独り勝ちが控えられる」といえばむしろ前進的に
聞こえるわけで、そう捉えることで、後退志向までもが深刻化するようなことがないようにすべきなのだ。
「昊天の孔だ昭らけきに、我れ生を楽しむ靡し。爾を視るに夢夢たれば、我が心は惨惨たる」
「晴れ渡る空の下でも、私は少しも生きてることが楽しくない。主上の心が晴れやらぬようなら、
我が心も惨め極まりないものでしかない。(自分が死ぬからではなく、主君を喜ばせられないからこそ、
生きてることが全く楽しくないほどに惨め。この自己中を排した性根からの高潔さを見習うべきだといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・蕩之什・抑より)
太陽が地上に熱エネルギーをもたらすと共に、月が斥力によって波浪を起こすなどすることで、
地球の生態系も初めて成立している。人間も男と女に性が分かれているのが健全な状態で、
両性具有や性的不具こそは奇形ともなっている。にもかかわらず学問や信教に限って、それそのものが
一元的なものとしてこそ尊ばれたり、その内部破損が無制限に容認されたりすることのほうが
異常なのであり、その内側においてある種の差別が生じたりするほうがかえって自然なのである。
要は、学問や宗教のうちでも、特に正統なものが尊ばれて異端なものが賤しまれるといった程度の
篩い分けがあってしかるべきだということで、学問全般、宗教全般を無制限に奨励する雑家的なあり方を
もう少し控えていくようにすべきだというわけだけども、そのためには、「自由主義」もまた「雑家の美化」
でしかないという認識をもう少し広めていくようにしなければならない。「学問の自由、信教の自由が
閉ざされる」といえば後退的に聞こえるけども、「雑家の独り勝ちが控えられる」といえばむしろ前進的に
聞こえるわけで、そう捉えることで、後退志向までもが深刻化するようなことがないようにすべきなのだ。
「昊天の孔だ昭らけきに、我れ生を楽しむ靡し。爾を視るに夢夢たれば、我が心は惨惨たる」
「晴れ渡る空の下でも、私は少しも生きてることが楽しくない。主上の心が晴れやらぬようなら、
我が心も惨め極まりないものでしかない。(自分が死ぬからではなく、主君を喜ばせられないからこそ、
生きてることが全く楽しくないほどに惨め。この自己中を排した性根からの高潔さを見習うべきだといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・蕩之什・抑より)
己れの悪行からなる自業自得の悪因苦果は、まず本人自身の内面からの苦しみとして結実する。
その苦しみを解消していくために必要となるのが死刑を含む懲罰なわけだから、たとえ
世界中を権力犯罪まみれにして、犯罪者に対する十分な処罰が行き届かなくなるような
状態を拵えてみた所で、それで「悪因苦果」という因果応報が全く揺らぐわけでもない。
それでは、悪因苦果の苦しみを麻薬中毒なりカルト洗脳なりの陶酔によって紛らわしてみれば
どうかといって、それにより自分自身の身体や身辺や世の中の側の破綻を招くことになるわけで、
内面からの苦しみを紛らわそうとしたぶんだけ、それが外面からの破綻による苦しみと
なって蓄積されるという、因果応報の保存律が完全に確立されたままであり続ける。
大乗小乗にかかわらず、仏教は唯心主義であり、まず心が如何にあるかを問題とするけれども、
それは心が川の源流であるのに対し、モノが末流であるような関係に両者があるからで、心すら
しっかりと修め抜いたなら、それによって全てのモノすらもが統御されることをも見越しているからだ。
その慧眼が実際に真実にも即しているから、悪因苦果の苦しみも適切な処罰を介さない限りにおいて、
心の内面から外的な物質に至るまでの全ての領域において、必ず保存されたままであり続けるのである。
————
仏教や道家の提示するものは、体裁上からして「真理」だった。
「これが真理です」として提示したものを、信仰対象や定立対象とする門派であった。
ただ、その手法が科学的分析に即しておらず、どこまでも直観的なものでしかなかったから、
科学至上主義の裏側で肥大化してしまっている極度の懐疑主義に基づいて、現代人などには仏教や道家が
真理として提示するものも「過渡的な真理」か何かのようにすら思い込まれるようになってしまっている。
しかし、真理はどこまでいっても真理である。仏者や仙人による最原初の把捉方法が直観的なもので
しかなかったにしろ、真理であるものは真理だったのであり、真理ゆえに抗うこともできないのだ。
その苦しみを解消していくために必要となるのが死刑を含む懲罰なわけだから、たとえ
世界中を権力犯罪まみれにして、犯罪者に対する十分な処罰が行き届かなくなるような
状態を拵えてみた所で、それで「悪因苦果」という因果応報が全く揺らぐわけでもない。
それでは、悪因苦果の苦しみを麻薬中毒なりカルト洗脳なりの陶酔によって紛らわしてみれば
どうかといって、それにより自分自身の身体や身辺や世の中の側の破綻を招くことになるわけで、
内面からの苦しみを紛らわそうとしたぶんだけ、それが外面からの破綻による苦しみと
なって蓄積されるという、因果応報の保存律が完全に確立されたままであり続ける。
大乗小乗にかかわらず、仏教は唯心主義であり、まず心が如何にあるかを問題とするけれども、
それは心が川の源流であるのに対し、モノが末流であるような関係に両者があるからで、心すら
しっかりと修め抜いたなら、それによって全てのモノすらもが統御されることをも見越しているからだ。
その慧眼が実際に真実にも即しているから、悪因苦果の苦しみも適切な処罰を介さない限りにおいて、
心の内面から外的な物質に至るまでの全ての領域において、必ず保存されたままであり続けるのである。
————
仏教や道家の提示するものは、体裁上からして「真理」だった。
「これが真理です」として提示したものを、信仰対象や定立対象とする門派であった。
ただ、その手法が科学的分析に即しておらず、どこまでも直観的なものでしかなかったから、
科学至上主義の裏側で肥大化してしまっている極度の懐疑主義に基づいて、現代人などには仏教や道家が
真理として提示するものも「過渡的な真理」か何かのようにすら思い込まれるようになってしまっている。
しかし、真理はどこまでいっても真理である。仏者や仙人による最原初の把捉方法が直観的なもので
しかなかったにしろ、真理であるものは真理だったのであり、真理ゆえに抗うこともできないのだ。
重大なのは、本当に真理か道理か、はたまた無理であるのかということで、その捉え方や
流布の仕方が分析的か直観的かなどということではない。扱い方が直観的であっても真理は真理だし、
道理も道理であり、直観的であればこその汎用性も加味されて、分析的に取り扱う場合以上もの
有用性すらをも帯びていたりする。易学などもその典型例であり、決してその論及姿勢が科学的に
厳密だったりすることはないが、だからこそ権力道徳の実践などにも即座に応用できるようになっている。
科学的、分析的な手法にも存在意義があるとするなら、それは、自分たちの手法が非科学的であるに
ことかけて、真理や道理に違う誤謬を、あたかも真理や道理であるかのごとく触れ回る邪教邪学の虚偽を
厳密に暴き尽くすことだといえる。それにより、探求姿勢は直観的だったのであっても、本物の真理や道理を
取り扱っていた教学の信用性をも取り戻させることである。それは結局、科学的手法の現時点における大家でも
ある西洋社会が、自分たちの文化的源流である聖書信仰の虚偽性を暴き尽くすことに尽きるわけで、それにより、
自分たちの危害によってくそみそに信用性を貶められてしまった仏教や道家や儒家のごとき優良教学の権威をも
元通りに復元するのである。つまり、自分たちのもたらした迷惑を自分たちで回収するというまでのことだ。
「罪、死にも容れられず」
「罪が刑死によって寛容することすらできない程にも極大化してしまっている。
(『万死に値する』という、一身の生死をも超えた罪の受け止め方。東洋にはあるが西洋にはない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句上・一四より)
流布の仕方が分析的か直観的かなどということではない。扱い方が直観的であっても真理は真理だし、
道理も道理であり、直観的であればこその汎用性も加味されて、分析的に取り扱う場合以上もの
有用性すらをも帯びていたりする。易学などもその典型例であり、決してその論及姿勢が科学的に
厳密だったりすることはないが、だからこそ権力道徳の実践などにも即座に応用できるようになっている。
科学的、分析的な手法にも存在意義があるとするなら、それは、自分たちの手法が非科学的であるに
ことかけて、真理や道理に違う誤謬を、あたかも真理や道理であるかのごとく触れ回る邪教邪学の虚偽を
厳密に暴き尽くすことだといえる。それにより、探求姿勢は直観的だったのであっても、本物の真理や道理を
取り扱っていた教学の信用性をも取り戻させることである。それは結局、科学的手法の現時点における大家でも
ある西洋社会が、自分たちの文化的源流である聖書信仰の虚偽性を暴き尽くすことに尽きるわけで、それにより、
自分たちの危害によってくそみそに信用性を貶められてしまった仏教や道家や儒家のごとき優良教学の権威をも
元通りに復元するのである。つまり、自分たちのもたらした迷惑を自分たちで回収するというまでのことだ。
「罪、死にも容れられず」
「罪が刑死によって寛容することすらできない程にも極大化してしまっている。
(『万死に値する』という、一身の生死をも超えた罪の受け止め方。東洋にはあるが西洋にはない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句上・一四より)
「小人は壯を用い、君子は罔を用う。貞なれどもあやうし。羝羊藩に触れて其の角を羸しましむ(この一文既出)。
〜貞しければ吉にして悔い亡ぶ。藩決けて羸しまず。大輿の輹も壯なり。藩決けて羸しまざるは、往くを尚べばなり」
「小人は君子が避けるような猪突猛進を好む。そのような状態では目的が正しくても危うい。あたかも牡羊が垣根に
自らの角を引っ掛けて苦しむようなザマに陥る。しかし、あくまで目的が正しいようであればそれも吉祥なことなので、
悔いの残らないような結果に至る。まるで作りの立派な走り出すように進撃する。それもよいことなので、牡羊を苦しめ
ていた垣根も取り払われる。(親鸞聖人も一時易学に傾倒していたようだが、ここから悪人正機説をも編み出したのだろう。
異生羝羊心級の蒙昧な猪突猛進さも、一向専修念仏などに転用することでの善果への結実が可能となる。一方で、
一向一揆への制裁で本願寺が江戸幕府に冷遇されたことなども、九三の『最初は苦しまされる』という記述に一致
している。大きな苦難の後に道が開けるということも実際になくはないことで、それは正当な目的と共にこそ実現される)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・大壯・九三‐九四、象伝より)
〜貞しければ吉にして悔い亡ぶ。藩決けて羸しまず。大輿の輹も壯なり。藩決けて羸しまざるは、往くを尚べばなり」
「小人は君子が避けるような猪突猛進を好む。そのような状態では目的が正しくても危うい。あたかも牡羊が垣根に
自らの角を引っ掛けて苦しむようなザマに陥る。しかし、あくまで目的が正しいようであればそれも吉祥なことなので、
悔いの残らないような結果に至る。まるで作りの立派な走り出すように進撃する。それもよいことなので、牡羊を苦しめ
ていた垣根も取り払われる。(親鸞聖人も一時易学に傾倒していたようだが、ここから悪人正機説をも編み出したのだろう。
異生羝羊心級の蒙昧な猪突猛進さも、一向専修念仏などに転用することでの善果への結実が可能となる。一方で、
一向一揆への制裁で本願寺が江戸幕府に冷遇されたことなども、九三の『最初は苦しまされる』という記述に一致
している。大きな苦難の後に道が開けるということも実際になくはないことで、それは正当な目的と共にこそ実現される)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・大壯・九三‐九四、象伝より)
この世界この宇宙というのは、不条理とも思えるような一定の非可換性に司られている。
その非可換性に即して生きとし生けるものの全てがいつかは死に、それぞれの人間も男と女、
親と子、官と民といったような身分の違いを生じさせもする。それは確かに自由度の低い部分だが、
その自由度の低さすらないのなら、そもそもこの世界や人間のような高度な構築物からして成立し得ない。
関節の曲がる方向なども限られていればこそ、人間はアメーバやタコなどよりも遥かに高度な生物でもある。
アメーバ並みに原始的な生物であれば半永久的な生存すら不可能ではないが、同時に人間のような高度な知能や
意識を持ち得ることもない。寿命も80年程度、性別は男女に分かれ、大社会を築き上げる以上は官民の身分の
差別を設ける必要があったりする、その限定度こそが「万物の霊長」たる人間を成立させてもいるのである。
人間同士が形作る世俗社会において善徳や罪悪が実在し、善徳を積み重ねるものは普遍的な安楽に与れる一方、
罪悪を積み重ねるものは普遍的な辛苦に見舞われるという罪福異熟の道理もまた、上記のような限定性の内である。
万億の人々が集い来たる都市社会において、万人を利して我が利ともする仁徳に根ざした行業に励むことが善徳と
なる一方で、多くの人々から富を収奪しての狭隘な栄華を誇ろうとすることが罪悪となり、それが善因楽果悪因苦果の
罪福異熟を不可避に招く。それはどこまでも一方的な因果応報となるばかりで、悪行に相応の苦しみに見舞われた
からといって、その後に見返りとしての楽果が期待できたりするわけもないのがその実例だといえる。
その非可換性に即して生きとし生けるものの全てがいつかは死に、それぞれの人間も男と女、
親と子、官と民といったような身分の違いを生じさせもする。それは確かに自由度の低い部分だが、
その自由度の低さすらないのなら、そもそもこの世界や人間のような高度な構築物からして成立し得ない。
関節の曲がる方向なども限られていればこそ、人間はアメーバやタコなどよりも遥かに高度な生物でもある。
アメーバ並みに原始的な生物であれば半永久的な生存すら不可能ではないが、同時に人間のような高度な知能や
意識を持ち得ることもない。寿命も80年程度、性別は男女に分かれ、大社会を築き上げる以上は官民の身分の
差別を設ける必要があったりする、その限定度こそが「万物の霊長」たる人間を成立させてもいるのである。
人間同士が形作る世俗社会において善徳や罪悪が実在し、善徳を積み重ねるものは普遍的な安楽に与れる一方、
罪悪を積み重ねるものは普遍的な辛苦に見舞われるという罪福異熟の道理もまた、上記のような限定性の内である。
万億の人々が集い来たる都市社会において、万人を利して我が利ともする仁徳に根ざした行業に励むことが善徳と
なる一方で、多くの人々から富を収奪しての狭隘な栄華を誇ろうとすることが罪悪となり、それが善因楽果悪因苦果の
罪福異熟を不可避に招く。それはどこまでも一方的な因果応報となるばかりで、悪行に相応の苦しみに見舞われた
からといって、その後に見返りとしての楽果が期待できたりするわけもないのがその実例だといえる。
「どんな質問にも指一本を立てるだけで応える倶胝という和尚がいた。
あるとき門弟の童子が問答で倶胝和尚の真似をして指を立てた。
それを視るや、和尚は童子の指を刃物で寸断してしまった。
泣き叫んで逃げようとする童子を和尚は『待て小僧』と引止めた。
童子が振り向くと和尚は一本指を立てて見せた。途端に童子は悟りを啓いた」
(「無門関」第三則・倶胝竪指より)
大した修行も積んでない未熟者の小僧が、すでに悟りを啓いている達人の真似をしたからといって同じ境地に
至れるわけではないが、もしも自分がとうてい達人にはまだまだ及ばない未熟者であることを具さに
わきまえられたなら、それが自分自身の身の程に適った悟りを啓く帰依にはなり得る。それと同じように、
悪逆非道を積み重ねて来た愚人が、断悪修善を積み重ねて来た聖賢の境地にすぐに至れたりする
わけもないが、自分がその程度の身の程でしかないということを思い知ったなら、それが自分自身の
悪逆非道を狭めていく機縁になり、もって最悪の辛苦から脱していく機縁ともなったりする。
だからといって、そこからすぐに聖賢の境地に至れるわけでもなく、凡人や善人の域にまで立ち戻るためだけでも、
長い服役や療養生活を必要としたりもする。それでももう、最悪の苦しみから脱していく機縁には与れているわけで、
それが罪福異熟のような普遍道理に司られることで初めて成立してもいる、この社会において許容できる最善の
立ち直り方ともなる。これ以上に甘ったるい許容は社会の側の破綻を招き、許しを得た者すらをも無事では済まさない。
原理的な構造上そうでしかあり得ないという事態に対して、形而上の超越神ですらもがどうにかできることはない。
あるとき門弟の童子が問答で倶胝和尚の真似をして指を立てた。
それを視るや、和尚は童子の指を刃物で寸断してしまった。
泣き叫んで逃げようとする童子を和尚は『待て小僧』と引止めた。
童子が振り向くと和尚は一本指を立てて見せた。途端に童子は悟りを啓いた」
(「無門関」第三則・倶胝竪指より)
大した修行も積んでない未熟者の小僧が、すでに悟りを啓いている達人の真似をしたからといって同じ境地に
至れるわけではないが、もしも自分がとうてい達人にはまだまだ及ばない未熟者であることを具さに
わきまえられたなら、それが自分自身の身の程に適った悟りを啓く帰依にはなり得る。それと同じように、
悪逆非道を積み重ねて来た愚人が、断悪修善を積み重ねて来た聖賢の境地にすぐに至れたりする
わけもないが、自分がその程度の身の程でしかないということを思い知ったなら、それが自分自身の
悪逆非道を狭めていく機縁になり、もって最悪の辛苦から脱していく機縁ともなったりする。
だからといって、そこからすぐに聖賢の境地に至れるわけでもなく、凡人や善人の域にまで立ち戻るためだけでも、
長い服役や療養生活を必要としたりもする。それでももう、最悪の苦しみから脱していく機縁には与れているわけで、
それが罪福異熟のような普遍道理に司られることで初めて成立してもいる、この社会において許容できる最善の
立ち直り方ともなる。これ以上に甘ったるい許容は社会の側の破綻を招き、許しを得た者すらをも無事では済まさない。
原理的な構造上そうでしかあり得ないという事態に対して、形而上の超越神ですらもがどうにかできることはない。
 >>47の引用の通り、羊にも羊なりの処世の手段というものがある。
>>47の引用の通り、羊にも羊なりの処世の手段というものがある。 ただただ発奮するばかりの牡羊であっても、根本的に正しければ最終的には吉ともなると。
それすら期待できないのは、拠り所を間違えている牡羊だけであり、
何も異生羝羊レベルの下品さすなわち破滅への片道切符だとも限らないのである。
羊牛レベルの蒙昧さであるからには、さすがに苦難が付きまとうことは避けられない。
それは正しいものを拠り所としている場合でも同じで、一向一揆が信長らによって制圧され、
天下平定後にも江戸幕府によって本願寺を東西に分割されて勢力を分散化させられたように、
活動が猪突猛進すぎること自体への警戒からなる冷遇というものが、ある程度は避けられぬものとなる。
ただ、拠り所が正しければそれだけで済む一方、拠り所すら間違っていたのなら、それですら済まない。
浄土真宗こと一向宗は上記のような処分に止め置かれた一方で、キリシタンは寺社打ち壊しや奴隷売買などの
大罪を理由として根絶の対象とされ、実際に表社会から聖書信仰が絶やされた江戸期の日本においてこそ、
当時の地球上のどこの世界にも勝るほどの文化的文明的な繁栄が実現されもしたのだった。これなど確かに、
羊牛レベルの蒙昧さと致命的な過ちの相乗が世のため人のためとなる完全破綻を呼び込んだ実例であるといえる。
これもまた、蒙昧状態にまつわる一つの非可換性であり、この世界この宇宙のあらゆる現象が非可換性
によって司られているという法則に漏れるものではない。蒙昧状態にある人間自身がそれを察せないとした所で、
やはりそういう法則が遍在していることにも変わりはなく、その結果として、同じ蒙昧さでありながら
救われ得るような人間とそうでない人間とに分かれるという結果が生じてしまうのである。
「趙州和尚がある庵主の僧に『元気かい』と声をかけた。庵主は拳を上げて返事をした。
趙州は『こんな浅いところに船を止めておくわけにはいかない』と言ってすたこら
さっさと行き去った。また別の庵主の僧に『元気かい』と声をかけた。そこの庵主もまた
拳を上げて返事をした。趙州は『従奪活殺、自由自在でございますな』と言って、
その庵主に拝礼した。〜人を殺す刀が、人を活かす剣ともなる」
(「無門関」第十一則・州勘庵主より)
上の文面だけじゃ、二人の庵主にどのような違いがあったのかは全く分からない。分からないとした上で、
そこに差別がある。蒙昧者が救われたり救われなかったりすることも、これ程にも不可思議な差別であったりする。
特に、何が正しくて何が間違っているかも分からない蒙昧者であればこそ、自分からは不条理にしか
思えないようなところで、救われるものと救われないものとが分かたれる。それはもう、
蒙昧者であればこそ完全に承諾せねばならないことである。
親鸞聖人も、自らが念仏に帰命する根拠を法然上人の学識とし、「法然さまに騙されるのなら、
それでも結構でございます」という心持ちでいたというのだから、正しきを拠り所とする蒙昧者こそは、
むしろ「正しくても間違っててもいい」という程もの心意気で拠り所となるものを信ずることが分かる。
その思い切りが足りていなかったものこそは、過ちを拠り所として致命的な破滅にも至ったのである。
「十月には場を滌め、朋と酒を斯こに饗し、曰に羔羊を殺す。彼の公堂に躋り、彼の兕觥を稱げ、万寿無疆たらしむ」
「十月には屠場を清めて、友たちと友に酒宴を挙げつつ、子羊を殺す。その肉と酒を公堂に捧げ、万寿長命を祈る。
(四書五経中にも羊牛その他の牧獣の描写は多いが、あくまで人間第一で、牧獣と人間を同一視するような真似もしない。
人と動物の命の軽重にも厳然たる差別を講じ、人間自身の福徳こそを真摯に希う、)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・豳風・七月より)
趙州は『こんな浅いところに船を止めておくわけにはいかない』と言ってすたこら
さっさと行き去った。また別の庵主の僧に『元気かい』と声をかけた。そこの庵主もまた
拳を上げて返事をした。趙州は『従奪活殺、自由自在でございますな』と言って、
その庵主に拝礼した。〜人を殺す刀が、人を活かす剣ともなる」
(「無門関」第十一則・州勘庵主より)
上の文面だけじゃ、二人の庵主にどのような違いがあったのかは全く分からない。分からないとした上で、
そこに差別がある。蒙昧者が救われたり救われなかったりすることも、これ程にも不可思議な差別であったりする。
特に、何が正しくて何が間違っているかも分からない蒙昧者であればこそ、自分からは不条理にしか
思えないようなところで、救われるものと救われないものとが分かたれる。それはもう、
蒙昧者であればこそ完全に承諾せねばならないことである。
親鸞聖人も、自らが念仏に帰命する根拠を法然上人の学識とし、「法然さまに騙されるのなら、
それでも結構でございます」という心持ちでいたというのだから、正しきを拠り所とする蒙昧者こそは、
むしろ「正しくても間違っててもいい」という程もの心意気で拠り所となるものを信ずることが分かる。
その思い切りが足りていなかったものこそは、過ちを拠り所として致命的な破滅にも至ったのである。
「十月には場を滌め、朋と酒を斯こに饗し、曰に羔羊を殺す。彼の公堂に躋り、彼の兕觥を稱げ、万寿無疆たらしむ」
「十月には屠場を清めて、友たちと友に酒宴を挙げつつ、子羊を殺す。その肉と酒を公堂に捧げ、万寿長命を祈る。
(四書五経中にも羊牛その他の牧獣の描写は多いが、あくまで人間第一で、牧獣と人間を同一視するような真似もしない。
人と動物の命の軽重にも厳然たる差別を講じ、人間自身の福徳こそを真摯に希う、)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・豳風・七月より)
長年の聖書信仰の金科玉条化によって、聖書圏では世の中のうちでも
特に悪い者、善くない者こそが権力を握る方向性が固着化してしまった。
そのせいで「権力を持つ者=悪人」というような固定観念すらもが根付いてしまっているが、
権力者が特定して悪人となるのは「内小人にして外君子」という否卦の法則にばかり
該当する現象であり、六十四卦への千変万化によってこそ健全な流動性をも保てる
この世界の普遍法則に基づけば、どこまでも不自然極まりないものなのである。
たとえば、「内君子にして外小人」という泰卦の法則に基づくなら、
むしろ権力者こそは善人でなければならず、無権力の庶民こそは悪人であってもいいことになる。
そのような状況の世の中での権力道徳者を目指すための学問が儒学であるし、
またそのような世の中での愚昧な庶民として適当であろうとするための信教が浄土教でもある。
これらの教学は、愚昧な悪人こそが権力者であることを徹底する聖書信仰の範疇からすれば
非常識極まりないものであり、善良な権力者たろうとする儒学の意図も意味不明なら、
無権力の悪人であることを開き直る浄土教も意味不明として扱う他はないものである。
しかし、そのような教学が本当に実在していて、まともな世の中を築き上げることにかけては、
聖書信仰なぞよりも遥かに絶大かつ優良な実績を挙げて来てもいるのである。
儒学や浄土教が泰卦の法則に根ざすような優良な世の中での統治に貢献しようとする一方で、
聖書信仰や洋学は否卦の法則に根ざすような劣悪な世の中での支配に加担しようとする。
統治支配に携わろうとしている環境こそが全くの別物だから、両者の言い分や教義も悉く相反している。
特に悪い者、善くない者こそが権力を握る方向性が固着化してしまった。
そのせいで「権力を持つ者=悪人」というような固定観念すらもが根付いてしまっているが、
権力者が特定して悪人となるのは「内小人にして外君子」という否卦の法則にばかり
該当する現象であり、六十四卦への千変万化によってこそ健全な流動性をも保てる
この世界の普遍法則に基づけば、どこまでも不自然極まりないものなのである。
たとえば、「内君子にして外小人」という泰卦の法則に基づくなら、
むしろ権力者こそは善人でなければならず、無権力の庶民こそは悪人であってもいいことになる。
そのような状況の世の中での権力道徳者を目指すための学問が儒学であるし、
またそのような世の中での愚昧な庶民として適当であろうとするための信教が浄土教でもある。
これらの教学は、愚昧な悪人こそが権力者であることを徹底する聖書信仰の範疇からすれば
非常識極まりないものであり、善良な権力者たろうとする儒学の意図も意味不明なら、
無権力の悪人であることを開き直る浄土教も意味不明として扱う他はないものである。
しかし、そのような教学が本当に実在していて、まともな世の中を築き上げることにかけては、
聖書信仰なぞよりも遥かに絶大かつ優良な実績を挙げて来てもいるのである。
儒学や浄土教が泰卦の法則に根ざすような優良な世の中での統治に貢献しようとする一方で、
聖書信仰や洋学は否卦の法則に根ざすような劣悪な世の中での支配に加担しようとする。
統治支配に携わろうとしている環境こそが全くの別物だから、両者の言い分や教義も悉く相反している。
儒学や浄土教が泰卦のような環境下での統治に貢献しようとしているのは、易の法則を察した上での
確信的な試みであり、真宗開祖の親鸞聖人なども易学を参考にして悪人正機説を打ち出している。
あくまで、易の法則は流動的なものであり、いつでも必ず泰卦のような良環境が遍在することを期待
できたりするわけではないが、易の法則を察するものとしては、あくまで泰卦のような優良な環境の
呼び込みを目指したり、そこでの統治に貢献したりしようとすることが最善となるために、個人的な
志しとしてはどこまでもそれを目指し、否卦のような劣悪環境の呼び込みをも避けるようにするのである。
聖書信仰や洋学が否卦のような劣悪環境下での支配に加担しようとするのは、別に聖書信仰や洋学の
関係者が易の法則を察したり諾ったりしているからではない。易の法則などを一切把握も承諾も
しない上に、この世界この宇宙の法則を超越する絶対神的なものをでっち上げての教学を構築して
来たものだから、易でいえば否卦に相当するような劣悪な環境を企図するものともなってしまった。
(イスラムの超越神アラーなどは汎神的な存在であったため、このような結果には至らなかった)
形而下の法則を完全に超越する絶対神など実在しない、存在したところでこの世界やこの宇宙とは
何の関係もないということは今しがた知れたことで、故に、易の法則こそが全世界において絶対的で
あることもまたほんのこのごろ認知が確定したことだといえる。別に易の法則を把握や承諾した上で、
なおのこと否卦のような劣悪環境の呼び込みを目指していた悪魔などが居たわけではないのだから、
「魔が差す」ということも、どこまでも過失の域内でしかなかったことまでもが確かなのである。
「夫れ人豈に勝えざるを以て患いと為さんや、為す弗きのみ」
「どうして自分に力が足らないことなどを憂う必要があるだろう。
ただ(小さな善すら)為そうとしないことを憂うばかりだ」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・告子章句下・二より)
確信的な試みであり、真宗開祖の親鸞聖人なども易学を参考にして悪人正機説を打ち出している。
あくまで、易の法則は流動的なものであり、いつでも必ず泰卦のような良環境が遍在することを期待
できたりするわけではないが、易の法則を察するものとしては、あくまで泰卦のような優良な環境の
呼び込みを目指したり、そこでの統治に貢献したりしようとすることが最善となるために、個人的な
志しとしてはどこまでもそれを目指し、否卦のような劣悪環境の呼び込みをも避けるようにするのである。
聖書信仰や洋学が否卦のような劣悪環境下での支配に加担しようとするのは、別に聖書信仰や洋学の
関係者が易の法則を察したり諾ったりしているからではない。易の法則などを一切把握も承諾も
しない上に、この世界この宇宙の法則を超越する絶対神的なものをでっち上げての教学を構築して
来たものだから、易でいえば否卦に相当するような劣悪な環境を企図するものともなってしまった。
(イスラムの超越神アラーなどは汎神的な存在であったため、このような結果には至らなかった)
形而下の法則を完全に超越する絶対神など実在しない、存在したところでこの世界やこの宇宙とは
何の関係もないということは今しがた知れたことで、故に、易の法則こそが全世界において絶対的で
あることもまたほんのこのごろ認知が確定したことだといえる。別に易の法則を把握や承諾した上で、
なおのこと否卦のような劣悪環境の呼び込みを目指していた悪魔などが居たわけではないのだから、
「魔が差す」ということも、どこまでも過失の域内でしかなかったことまでもが確かなのである。
「夫れ人豈に勝えざるを以て患いと為さんや、為す弗きのみ」
「どうして自分に力が足らないことなどを憂う必要があるだろう。
ただ(小さな善すら)為そうとしないことを憂うばかりだ」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・告子章句下・二より)
[YouTubeで再生]
 自分以外の誰かや、災害や害獣などから身を守ったりすることよりも、
自分以外の誰かや、災害や害獣などから身を守ったりすることよりも、
まず自分自身が自殺行為によって己れを損なってしまうことこそを最大級に警戒する。
そしたら自然と外的な危害に対する警戒意識も最適化されて、全く警戒を欠くということもなければ、
外的警戒ばかりを募らせ過ぎての自業自得での自滅を招くというようなこともなくなる。
どんな保護者や観察者も、自業自得で自滅するものだけは救うことができない。
そこにこそ生物としての危うさの極みがあり、保護の対象となる資格ももはやそこにはない。
忠義のためだか孝行のためだとかの已む無い理由があって我が身を危うからしめるのならともかく、
全くの酔狂によって必要もなく危難を呼び込んだりするのなら、もはや同情のしようもない。
薄情者や鬼畜とわず、人情豊かな真人間であろうとも、そんな相手に同情したりするもんじゃない。
ナザレのイエスによる邪教の触れ回りや、進んでの投降に基づく磔刑などは、一見、
同情のしようがあるようにすら思われかねないものだった。妾腹の私生児として娼婦マリアから
産まれたイエスが、その不遇からなる自暴自棄によって邪説を触れ回った挙句に冤罪で処刑された
ということが、「刑死後に蘇って昇天した」というハッピーエンドの迷信によって取り繕って
あげたくなるほどにも、当時のローマ人などにとっては同情したくなるものだったのである。
しかし、イエスよりもさらに不遇な「母子家庭の妾腹の私生児」という
境遇に生まれ育ちながら、決して自暴自棄に走ったりすることもなく、粛々と
礼学者や権力道徳者としての役儀をこなした孔子のような偉人の実例も見てみれば、
イエスの自殺行為による自滅なども、決して同情するに値するものなどではなかったことが分かる。
 自分以外の誰かや、災害や害獣などから身を守ったりすることよりも、
自分以外の誰かや、災害や害獣などから身を守ったりすることよりも、 まず自分自身が自殺行為によって己れを損なってしまうことこそを最大級に警戒する。
そしたら自然と外的な危害に対する警戒意識も最適化されて、全く警戒を欠くということもなければ、
外的警戒ばかりを募らせ過ぎての自業自得での自滅を招くというようなこともなくなる。
どんな保護者や観察者も、自業自得で自滅するものだけは救うことができない。
そこにこそ生物としての危うさの極みがあり、保護の対象となる資格ももはやそこにはない。
忠義のためだか孝行のためだとかの已む無い理由があって我が身を危うからしめるのならともかく、
全くの酔狂によって必要もなく危難を呼び込んだりするのなら、もはや同情のしようもない。
薄情者や鬼畜とわず、人情豊かな真人間であろうとも、そんな相手に同情したりするもんじゃない。
ナザレのイエスによる邪教の触れ回りや、進んでの投降に基づく磔刑などは、一見、
同情のしようがあるようにすら思われかねないものだった。妾腹の私生児として娼婦マリアから
産まれたイエスが、その不遇からなる自暴自棄によって邪説を触れ回った挙句に冤罪で処刑された
ということが、「刑死後に蘇って昇天した」というハッピーエンドの迷信によって取り繕って
あげたくなるほどにも、当時のローマ人などにとっては同情したくなるものだったのである。
しかし、イエスよりもさらに不遇な「母子家庭の妾腹の私生児」という
境遇に生まれ育ちながら、決して自暴自棄に走ったりすることもなく、粛々と
礼学者や権力道徳者としての役儀をこなした孔子のような偉人の実例も見てみれば、
イエスの自殺行為による自滅なども、決して同情するに値するものなどではなかったことが分かる。
その孔子も、たとえば濁悪にまみれ過ぎた諸侯への仕官を蹴っての青い鳥状態でいるあまり、
支援者を失っての放浪状態に追い込まれたり、魯の将軍に政敵と見間違われて殺されかけるなどの
危難に見舞われたことがあった。それはたとえば、完全なる隠遁や安静を決め込む胴か小乗仏教の見地
からすれば決して安全第一なものではなかったわけだが、それでも孔子には「衰退した我が家を盛り立てる」
や「古えの礼楽文化を今の時代に復興する」といったまともな目的が備わっていたわけだから、
決して全くの酔狂扱いとして、その苦難の旅路を鼻であしらったりしてはならないようになっている。
正当な目的があって苦難にすら臨むのと、全くの酔狂で苦難に乗ずるのとでは、決定的な
実行価値の開きを生ずる。片やそうしたほうが善い一方で、片やしないでいるほうがマシである。
それを行うことによって片や自らを英傑とならしめる一方、片やクズ同然の存在とならしめる。
危難に臨むからといって必ずしもクズ扱いにすべきでもないのだから、勇気の持ち主=人間のクズ
なんていうプラトンレベルの惰弱主義的な結論に陥ってしまってもならないといえる。
「陰陽に堪えず、蛇龍に乗る」
「陽唱陰和が破綻して、あたかも弱小な蛇が強大な龍に乗っかっているようなザマとなってしまっている。
(龍のように偉大な聖王賢臣と比べれば、権力犯罪者たちは自分たち自身がヘビのような存在と
化してしまっていることを思い知るべきである。自分たちが虚栄を謳歌している状態も、
あたかもヘビが龍に乗っかっているも同然の状態であるとわきまえるべきである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・襄公二十八年より)
支援者を失っての放浪状態に追い込まれたり、魯の将軍に政敵と見間違われて殺されかけるなどの
危難に見舞われたことがあった。それはたとえば、完全なる隠遁や安静を決め込む胴か小乗仏教の見地
からすれば決して安全第一なものではなかったわけだが、それでも孔子には「衰退した我が家を盛り立てる」
や「古えの礼楽文化を今の時代に復興する」といったまともな目的が備わっていたわけだから、
決して全くの酔狂扱いとして、その苦難の旅路を鼻であしらったりしてはならないようになっている。
正当な目的があって苦難にすら臨むのと、全くの酔狂で苦難に乗ずるのとでは、決定的な
実行価値の開きを生ずる。片やそうしたほうが善い一方で、片やしないでいるほうがマシである。
それを行うことによって片や自らを英傑とならしめる一方、片やクズ同然の存在とならしめる。
危難に臨むからといって必ずしもクズ扱いにすべきでもないのだから、勇気の持ち主=人間のクズ
なんていうプラトンレベルの惰弱主義的な結論に陥ってしまってもならないといえる。
「陰陽に堪えず、蛇龍に乗る」
「陽唱陰和が破綻して、あたかも弱小な蛇が強大な龍に乗っかっているようなザマとなってしまっている。
(龍のように偉大な聖王賢臣と比べれば、権力犯罪者たちは自分たち自身がヘビのような存在と
化してしまっていることを思い知るべきである。自分たちが虚栄を謳歌している状態も、
あたかもヘビが龍に乗っかっているも同然の状態であるとわきまえるべきである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・襄公二十八年より)
浄土経に記述されているような教義に即して「南無阿弥陀仏」と唱名すれば救われるとされ、
弘法大師の積んだ諸々の功徳に即して「南無遍照金剛」と唱えれば相応の利益に与れるともされる。
そこにはそれなりの後ろ盾があるのであって、たとえ唱名するもの自身がその後ろ盾をよく理解
できていないのであっも、潜在面からの後ろ盾の機能によってこそ利益があったりもするのである。
聖書信仰もまたそのような、潜在面からの教義的な後ろ盾の機能によって、信者を致命的な
破滅に陥れるのである。信者自身が新旧約聖書なんかまともに読んでなくたって、ただ自分が
キリストやエホバに帰依すると決断しているだけで、自動的に破滅を呼び込むものである。
他力本願系の信教というのは大体、そういったブラックボックス的要素を帯びているもので、
「教義も知らずにただ信じていただけなのにどうして破滅に陥らなければならないんだ」という
不平を抱いてしまう人間もまた多々生じてしまうのである。全ての他力信教がそうなるのではないにしろ、
そのような人間すらをも生じさせてしまう点が、他力系の信教一般の決定的な問題点だとはいえる。
ただ、教義なんかろくに知らなくても、キリスト教徒である以上は、教会に行って祈りを捧げるぐらい
のことはしたことがあるはずだ。そこで教会建築の独特の美々しさなどにも魅了されたことがあるはずで、
もしもそこで嫌悪感を抱いていたなら、率先して教会に行くことなどももう避けたはずである。
そのような、信者が魅了されたこともあるだろう教会建築の様式などからして、すでに偽善志向の
集成であり、信者もそれに魅了されたからには、偽善を好む性向が自分に潜在していたに違いないのだ。
弘法大師の積んだ諸々の功徳に即して「南無遍照金剛」と唱えれば相応の利益に与れるともされる。
そこにはそれなりの後ろ盾があるのであって、たとえ唱名するもの自身がその後ろ盾をよく理解
できていないのであっも、潜在面からの後ろ盾の機能によってこそ利益があったりもするのである。
聖書信仰もまたそのような、潜在面からの教義的な後ろ盾の機能によって、信者を致命的な
破滅に陥れるのである。信者自身が新旧約聖書なんかまともに読んでなくたって、ただ自分が
キリストやエホバに帰依すると決断しているだけで、自動的に破滅を呼び込むものである。
他力本願系の信教というのは大体、そういったブラックボックス的要素を帯びているもので、
「教義も知らずにただ信じていただけなのにどうして破滅に陥らなければならないんだ」という
不平を抱いてしまう人間もまた多々生じてしまうのである。全ての他力信教がそうなるのではないにしろ、
そのような人間すらをも生じさせてしまう点が、他力系の信教一般の決定的な問題点だとはいえる。
ただ、教義なんかろくに知らなくても、キリスト教徒である以上は、教会に行って祈りを捧げるぐらい
のことはしたことがあるはずだ。そこで教会建築の独特の美々しさなどにも魅了されたことがあるはずで、
もしもそこで嫌悪感を抱いていたなら、率先して教会に行くことなどももう避けたはずである。
そのような、信者が魅了されたこともあるだろう教会建築の様式などからして、すでに偽善志向の
集成であり、信者もそれに魅了されたからには、偽善を好む性向が自分に潜在していたに違いないのだ。
浄土真宗の寺の本堂内部の過剰な飾り立てなどは、どこにも偽善臭などない、完全なる悪の開き直り
の荘厳となっている。むしろ己れの劣悪さを開き直るぐらいの度量と共にこそ、悪人正機説に基づく
善導などもまた実現されていくのだから、あえてそのようなどぎつい飾り立てを施している。
それに魅了されたり、そこまでいかずとも受け入れられたりする人間なら、念仏信仰にも向いている
一方、そんなものにはかえって拒絶感を抱かされる、自分は教会建築などのアート的な様式のほうを
好むというのなら、そういう人間も潜在面からして念仏信仰には向いていなかったことになるのである。
浄土経を学んだこともなければ、聖書を読んだこともないというような内からでもそのような、
寺や教会の建築様式に対する感傷などの形で、人々も潜在面から信仰対象を選別していったのである。
真宗の僧侶は必ずしも剃髪しないが、それ以外の仏門では出家者は必ず剃髪するから、在家信者に
対しても、つるっぱげをあえて敬うような度量の広さが要求されている。その関門を乗り越えて
人々もまた、在家のうちからの聖道門帰依に励むわけだから、そこでもやはりすでに、
在家のうちからの信者の自己責任に基づく選別が働いているのだといえる。
あまり熱心でもないような在家の信者のうちからでも、他力系の信教を選択的に帰依した所にすら、多少の
自己責任が伴っている。教義を完全に計り知った上でなおのこと邪教に帰依していたりする場合と比べれば
その罪は軽いといえるが、適当な姿勢で邪教に帰依していたことにも全く罪がないとまでは言えないのである。
「其の名を称するや雑にして越えず。〜其の名を称するや小にして、その類を取るや大なり」
「(易の)名の称えられ方は雑多であるけれども、易の法則を表現するものとしての分を越えていない。
名の称えられ方は卑小であるけれども、それによって包含される事象の部類はとてつもなく多大である。
(『主』とか『キリスト』とかいった名称は、それ自体が単一的でひどく尊大なものだが、そのせいでかえって、
この世界この宇宙を司る易の法則などからも乖離してしまっている。重点を置くべきでない所に置いている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・繋辞下伝より)
の荘厳となっている。むしろ己れの劣悪さを開き直るぐらいの度量と共にこそ、悪人正機説に基づく
善導などもまた実現されていくのだから、あえてそのようなどぎつい飾り立てを施している。
それに魅了されたり、そこまでいかずとも受け入れられたりする人間なら、念仏信仰にも向いている
一方、そんなものにはかえって拒絶感を抱かされる、自分は教会建築などのアート的な様式のほうを
好むというのなら、そういう人間も潜在面からして念仏信仰には向いていなかったことになるのである。
浄土経を学んだこともなければ、聖書を読んだこともないというような内からでもそのような、
寺や教会の建築様式に対する感傷などの形で、人々も潜在面から信仰対象を選別していったのである。
真宗の僧侶は必ずしも剃髪しないが、それ以外の仏門では出家者は必ず剃髪するから、在家信者に
対しても、つるっぱげをあえて敬うような度量の広さが要求されている。その関門を乗り越えて
人々もまた、在家のうちからの聖道門帰依に励むわけだから、そこでもやはりすでに、
在家のうちからの信者の自己責任に基づく選別が働いているのだといえる。
あまり熱心でもないような在家の信者のうちからでも、他力系の信教を選択的に帰依した所にすら、多少の
自己責任が伴っている。教義を完全に計り知った上でなおのこと邪教に帰依していたりする場合と比べれば
その罪は軽いといえるが、適当な姿勢で邪教に帰依していたことにも全く罪がないとまでは言えないのである。
「其の名を称するや雑にして越えず。〜其の名を称するや小にして、その類を取るや大なり」
「(易の)名の称えられ方は雑多であるけれども、易の法則を表現するものとしての分を越えていない。
名の称えられ方は卑小であるけれども、それによって包含される事象の部類はとてつもなく多大である。
(『主』とか『キリスト』とかいった名称は、それ自体が単一的でひどく尊大なものだが、そのせいでかえって、
この世界この宇宙を司る易の法則などからも乖離してしまっている。重点を置くべきでない所に置いている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・繋辞下伝より)
己れの身を危うからしめることで着実な道義的成果が挙げられるというのなら、それも
アリだが、そうではあり得ない範囲での蛮行などに及ぶのでは、それこそ道義が立たない。
両者は厳密に分別して取り扱うべきものであり、これらをみそくそに扱った結果、
道義に根ざした死すらをも卑しむようになってしまうようなことがあってはならない。
日本史上や古代中国史上などに、道義のために命をも呈した英傑の事例は数多い。
道徳的、史学的にもその道義性が確かなものであるために、ひどい惨死に見舞われていたりしながらも
純粋な賞賛の対象ともなっていたりする。それを、酔狂での徒労死などともくそみそに扱って、
「野蛮な土人の凶行」か何かのように見なしたりするのも完全なる誤謬であり、道徳文化の確立を諾う
こともできないでいる自分のほうがむしろ、文化的未開状態にある土人であるのだとわきまえねばならない。
どうでもいいようなこと、むしろ避けたほうがいいようなことによって身を危うくすることと、
明白な道義に即して危難に臨むこととを厳重に差別した上で、後者のみを特筆して賞賛の対象とする、
それができるようになったならば、そのような世の中は今以上の文化的発展を実現させたのだといえる。
それを実現させるためには、むしろ酔狂によって身を危くすることに対する卑しみが強化される必要がある。
別に人命第一、保身第一だからそのような奇行を卑しむのではなく、道義に根ざした挺身を素直に賞賛
できるようになるためにこそ、なんでもかんでもの挺身一般を持て囃したりはしないようにすべきなのである。
地球上での社会情勢の自己完結化が一段落し、万人を利して我が利ともする仁義の理念もまた、
いつまでもヤクザの私物などにしていてはならないほどもの有益さをまた帯びるようになり始めている。
なればこそ、仁徳に即して道義のために身命をも賭することの価値までもが見直される必要が出て来ている。
アリだが、そうではあり得ない範囲での蛮行などに及ぶのでは、それこそ道義が立たない。
両者は厳密に分別して取り扱うべきものであり、これらをみそくそに扱った結果、
道義に根ざした死すらをも卑しむようになってしまうようなことがあってはならない。
日本史上や古代中国史上などに、道義のために命をも呈した英傑の事例は数多い。
道徳的、史学的にもその道義性が確かなものであるために、ひどい惨死に見舞われていたりしながらも
純粋な賞賛の対象ともなっていたりする。それを、酔狂での徒労死などともくそみそに扱って、
「野蛮な土人の凶行」か何かのように見なしたりするのも完全なる誤謬であり、道徳文化の確立を諾う
こともできないでいる自分のほうがむしろ、文化的未開状態にある土人であるのだとわきまえねばならない。
どうでもいいようなこと、むしろ避けたほうがいいようなことによって身を危うくすることと、
明白な道義に即して危難に臨むこととを厳重に差別した上で、後者のみを特筆して賞賛の対象とする、
それができるようになったならば、そのような世の中は今以上の文化的発展を実現させたのだといえる。
それを実現させるためには、むしろ酔狂によって身を危くすることに対する卑しみが強化される必要がある。
別に人命第一、保身第一だからそのような奇行を卑しむのではなく、道義に根ざした挺身を素直に賞賛
できるようになるためにこそ、なんでもかんでもの挺身一般を持て囃したりはしないようにすべきなのである。
地球上での社会情勢の自己完結化が一段落し、万人を利して我が利ともする仁義の理念もまた、
いつまでもヤクザの私物などにしていてはならないほどもの有益さをまた帯びるようになり始めている。
なればこそ、仁徳に即して道義のために身命をも賭することの価値までもが見直される必要が出て来ている。
道義のための挺身を評価することに有益さが生じ始めているからこそ、命知らずの暴虎馮河全般を
面白がるようなことが有害ともなり始めている。正当な勇進の評価のために、蛮勇の卑しみは
却って必要となり、定常的にはむしろ人々が穏健な自重を尽くすようになっていく必要がある。
命を軽んじ、身を危からしめることが潜在的にはむしろ羨望されているのが今という世の中である。
資本主義先進国における福祉政策の充実などからも、不用意に人が死ぬことが外的には抑制されている
ものの、そのせいでかえって個人個人が自主的な自重に努めることは萎縮してしまい、内面ではむしろ、
殺傷の狂気をヘタに面白がるような、不恰好な猟奇性が肥大化してしまったりもしているのである。
そこを転換して、むしろ個々人の内面からこそ自重が尊重されるようになっていく一方、
それに即して、道義に根ざした挺身のみを特筆して評価するようにもなっていけばいいのである。
むしろ今以上にも、自重の価値が本格的に重んじられるようになってこそ、そうなって行けるのである。
「王有廟に仮る。大人を見るに利ろし。亨る。貞しきに利ろし。大牲を用いて吉なり。往く攸有るに利ろし」
「王者は先祖の神を祀る霊廟に向かう。不世出の大人に邂逅し、何でもうまくいく。正しさを貫いた上で、
大物の犠牲を用いても吉祥となる。大きな事業を推し進めていくのにも格好の時である。(祖神や大人や
大事業のために大物の犠牲を用いるというのが、正統な供儀のあり方である。虚構の超越神や小人や
自分一人の栄華のために人間自身を犠牲にしたりするのとは、まさに対極の関係にあるといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・萃より)
面白がるようなことが有害ともなり始めている。正当な勇進の評価のために、蛮勇の卑しみは
却って必要となり、定常的にはむしろ人々が穏健な自重を尽くすようになっていく必要がある。
命を軽んじ、身を危からしめることが潜在的にはむしろ羨望されているのが今という世の中である。
資本主義先進国における福祉政策の充実などからも、不用意に人が死ぬことが外的には抑制されている
ものの、そのせいでかえって個人個人が自主的な自重に努めることは萎縮してしまい、内面ではむしろ、
殺傷の狂気をヘタに面白がるような、不恰好な猟奇性が肥大化してしまったりもしているのである。
そこを転換して、むしろ個々人の内面からこそ自重が尊重されるようになっていく一方、
それに即して、道義に根ざした挺身のみを特筆して評価するようにもなっていけばいいのである。
むしろ今以上にも、自重の価値が本格的に重んじられるようになってこそ、そうなって行けるのである。
「王有廟に仮る。大人を見るに利ろし。亨る。貞しきに利ろし。大牲を用いて吉なり。往く攸有るに利ろし」
「王者は先祖の神を祀る霊廟に向かう。不世出の大人に邂逅し、何でもうまくいく。正しさを貫いた上で、
大物の犠牲を用いても吉祥となる。大きな事業を推し進めていくのにも格好の時である。(祖神や大人や
大事業のために大物の犠牲を用いるというのが、正統な供儀のあり方である。虚構の超越神や小人や
自分一人の栄華のために人間自身を犠牲にしたりするのとは、まさに対極の関係にあるといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・萃より)
他力信仰も奨励できるものとできないものとがあるように、
一心不乱であるべき対象とそうでない対象というものもまたある。
仁徳に適った善行であるとか、正統な宗門における精進修行だとかは、
一心不乱であるに越したことのないものである一方、自分個人や隣人だけの
ための我田引水などに一心不乱であったりしていいことなどは何もない。
一心不乱であるべきことに一心不乱であったからといって、別に"淫"したりはしない
一方、そうあるべきでないものに一心不乱となると、必ず淫する。一心不乱な心境に
淫蕩さが加味されて、エサを食らう畜生ほどもの蒙昧さに陥ってしまうことになる。
一心不乱であるべきでないものに一心不乱であろうとするほど淫しやすいのは、
そこに最低限の技巧的知識すらもが伴っていないから。仁徳に根ざした善行に努める際には、
「万人を利して我が利ともする」という技巧的な知識の定常的なわきまえが必要となる一方、
我田引水なんざにはそんなわきまえは必要ない。別に「他人の利益を侵害してまで自分の利益を貪る」
なんていうわきまえすらも必要はなく、ただ専らに私益を貪り尽くすだけでそれは実現されて行くものだから、
それこそ畜生レベルの蒙昧さに陥っていたほうが、かえって罪悪感なども抱かなくて済むから都合がいいのである。
たとえば、古武術の初歩的な技巧が完全に身に付いて、わざわざ「ここはこうする」なんて考えなくても
自然と技が繰り出せるようになったとする。そしたら当該の技にまつわる技巧的知識などももはや
必要がなくなるわけだけども、そこから先にはまた、より高度な技にまつわる鍛錬の境地が開けいく。
さすれば、初歩的な技を身に付ける際に嗜んだような技巧的知識のわきまえというのは、知識そのものが
どんどん高度化していくのであっても、ずっと必要であり続けていくものなのだといえる。
一心不乱であるべき対象とそうでない対象というものもまたある。
仁徳に適った善行であるとか、正統な宗門における精進修行だとかは、
一心不乱であるに越したことのないものである一方、自分個人や隣人だけの
ための我田引水などに一心不乱であったりしていいことなどは何もない。
一心不乱であるべきことに一心不乱であったからといって、別に"淫"したりはしない
一方、そうあるべきでないものに一心不乱となると、必ず淫する。一心不乱な心境に
淫蕩さが加味されて、エサを食らう畜生ほどもの蒙昧さに陥ってしまうことになる。
一心不乱であるべきでないものに一心不乱であろうとするほど淫しやすいのは、
そこに最低限の技巧的知識すらもが伴っていないから。仁徳に根ざした善行に努める際には、
「万人を利して我が利ともする」という技巧的な知識の定常的なわきまえが必要となる一方、
我田引水なんざにはそんなわきまえは必要ない。別に「他人の利益を侵害してまで自分の利益を貪る」
なんていうわきまえすらも必要はなく、ただ専らに私益を貪り尽くすだけでそれは実現されて行くものだから、
それこそ畜生レベルの蒙昧さに陥っていたほうが、かえって罪悪感なども抱かなくて済むから都合がいいのである。
たとえば、古武術の初歩的な技巧が完全に身に付いて、わざわざ「ここはこうする」なんて考えなくても
自然と技が繰り出せるようになったとする。そしたら当該の技にまつわる技巧的知識などももはや
必要がなくなるわけだけども、そこから先にはまた、より高度な技にまつわる鍛錬の境地が開けいく。
さすれば、初歩的な技を身に付ける際に嗜んだような技巧的知識のわきまえというのは、知識そのものが
どんどん高度化していくのであっても、ずっと必要であり続けていくものなのだといえる。
それと同じように、仁徳の修練などもまた、どこまでも向上が目指していけるものであり、
仮に一定の上達が成し得たからといって、そこで停滞しきってあぐらをかいてしまうようならば、
それにより、技巧的知識のわきまえももはや必要でなくなったがための、淫蕩に耽ることはできても、
それと引き換えに今以上の向上というものが全く期待できなくもなるのである。そしてその時、
その人間はもはや仁徳の修練にかけて一心不乱であることを放棄してしまってもいる。何らの分別も
必要としない悪行こそは一心不乱な没頭によって淫することができる一方、仁徳にかなった善行のほうは、
一心不乱であることを放棄することで初めて多少の淫蕩に耽ることができる。しからば、人間というもの、
淫蕩さと無縁なところでこそ善行を推し進められる一方、淫蕩にかられた所で善の推進を滞らせたり、
悪行にふけってしまったりするわけだから、淫蕩に駆られるか否かを一つの善悪の分別のバロメーター
にしていくこともまたできるのである。何も、淫蕩に駆られることがあるという人間の性分そのものが
いけないものなのではない。それはちょうど、神経系に具わっている痛覚などと同じものなのである。
「子曰く、参よ吾が道は一を以て之れを貫けり。曾子曰く、唯。
子出ずる。門人問うて曰く、何の謂いぞや。曾子曰く、夫子の道は、忠恕のみ」
「孔先生が言われた。『参(曾子)よ、わが道はただ一つのことを貫くというばかりのことだよ』
曾先生。『確かにその通りです』 孔先生が立ち去られた後、ある門弟が曾子に『どういう意味でしょうか』
と問うた。曾先生は言われた。『大師(孔子)の道は、ただ忠恕の真心を尽くすというばかりのことなのだよ』
(孔子は存命中に多種多様な活動を為していたため、『一を以って之を貫くばかり』という孔子の言葉を
横で聞いていた門弟にはその意味が判然としなかった。何をやるかという以前に、内面からの心がけの所に
一を以って貫く忠恕がある。これこそは仁徳にまつわる技巧的智識の常日ごろからのわきまえに基づいている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・里仁第四・一五)
仮に一定の上達が成し得たからといって、そこで停滞しきってあぐらをかいてしまうようならば、
それにより、技巧的知識のわきまえももはや必要でなくなったがための、淫蕩に耽ることはできても、
それと引き換えに今以上の向上というものが全く期待できなくもなるのである。そしてその時、
その人間はもはや仁徳の修練にかけて一心不乱であることを放棄してしまってもいる。何らの分別も
必要としない悪行こそは一心不乱な没頭によって淫することができる一方、仁徳にかなった善行のほうは、
一心不乱であることを放棄することで初めて多少の淫蕩に耽ることができる。しからば、人間というもの、
淫蕩さと無縁なところでこそ善行を推し進められる一方、淫蕩にかられた所で善の推進を滞らせたり、
悪行にふけってしまったりするわけだから、淫蕩に駆られるか否かを一つの善悪の分別のバロメーター
にしていくこともまたできるのである。何も、淫蕩に駆られることがあるという人間の性分そのものが
いけないものなのではない。それはちょうど、神経系に具わっている痛覚などと同じものなのである。
「子曰く、参よ吾が道は一を以て之れを貫けり。曾子曰く、唯。
子出ずる。門人問うて曰く、何の謂いぞや。曾子曰く、夫子の道は、忠恕のみ」
「孔先生が言われた。『参(曾子)よ、わが道はただ一つのことを貫くというばかりのことだよ』
曾先生。『確かにその通りです』 孔先生が立ち去られた後、ある門弟が曾子に『どういう意味でしょうか』
と問うた。曾先生は言われた。『大師(孔子)の道は、ただ忠恕の真心を尽くすというばかりのことなのだよ』
(孔子は存命中に多種多様な活動を為していたため、『一を以って之を貫くばかり』という孔子の言葉を
横で聞いていた門弟にはその意味が判然としなかった。何をやるかという以前に、内面からの心がけの所に
一を以って貫く忠恕がある。これこそは仁徳にまつわる技巧的智識の常日ごろからのわきまえに基づいている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・里仁第四・一五)
自分が煩悩愚縛の凡夫であることをありのままに開き直るのと、
そうであることを正当化して権威化しようとするのとでは、小さいようで大きな開きがある。
前者は浄土教信者などの心境である一方、後者はキリスト信者やエホバ信者の心境であり、
両者の心境に根本的な開きがあるからこそ、信仰の対象となるものも決定的に相違するのである。
心境も違えば、帰依の対象も違うから、それぞれの人間の外面的なあり方も全く変わってくる。
念仏信者にはどこにも気負ったようなところはなく、そんなに自分自身を威厳的に見せよう
だなんていう傾向も見られない一方で、キリスト教の信者たるや、いかにも「修辞の塊」のような
見てくれで、自らを威厳的、美的に飾り立てることにかけては、どこにも隙がないように見える。
「論語」における礼節に適った孔子の立ち居振る舞いや、「礼記」に記されている様々な礼法を鑑みるに、
正統な礼法に根ざした修辞というものもありはするものの、そこに数多の辞譲が織り交ぜられていることが分かる。
周公の大廟での祭祀に出席した際、孔子はことあるごとに人に質問ばかりしていた。そのせいで無知扱い
されそうにもなったが、孔子も「大廟ではこうするのが礼儀なのだ」と弁解している。(八佾第三・一五)
これなど、かえって自分を愚かしく見せる謙譲の礼であり、かえってキリスト教徒などにとってこそは
受け入れがたい修辞ともなっているわけだけども、むしろ、本物の礼制に根ざした普遍的な威厳を
帯びるためにこそ、このような偉ぶりとも対極にあるような修辞が必要ともなってくるのである。
そうであることを正当化して権威化しようとするのとでは、小さいようで大きな開きがある。
前者は浄土教信者などの心境である一方、後者はキリスト信者やエホバ信者の心境であり、
両者の心境に根本的な開きがあるからこそ、信仰の対象となるものも決定的に相違するのである。
心境も違えば、帰依の対象も違うから、それぞれの人間の外面的なあり方も全く変わってくる。
念仏信者にはどこにも気負ったようなところはなく、そんなに自分自身を威厳的に見せよう
だなんていう傾向も見られない一方で、キリスト教の信者たるや、いかにも「修辞の塊」のような
見てくれで、自らを威厳的、美的に飾り立てることにかけては、どこにも隙がないように見える。
「論語」における礼節に適った孔子の立ち居振る舞いや、「礼記」に記されている様々な礼法を鑑みるに、
正統な礼法に根ざした修辞というものもありはするものの、そこに数多の辞譲が織り交ぜられていることが分かる。
周公の大廟での祭祀に出席した際、孔子はことあるごとに人に質問ばかりしていた。そのせいで無知扱い
されそうにもなったが、孔子も「大廟ではこうするのが礼儀なのだ」と弁解している。(八佾第三・一五)
これなど、かえって自分を愚かしく見せる謙譲の礼であり、かえってキリスト教徒などにとってこそは
受け入れがたい修辞ともなっているわけだけども、むしろ、本物の礼制に根ざした普遍的な威厳を
帯びるためにこそ、このような偉ぶりとも対極にあるような修辞が必要ともなってくるのである。
下賤をありのままに開き直ることではなく、下賤からの自分たちの美化を試みたところでこそ、
正統な礼節にすら見られることのない、ただただ美々しく大袈裟な修辞というものが生じた。今では、
どこの世界に行っても、欧米的な美化一辺倒の修辞こそが「修辞の標準」であるかのようにすら考えられて、
東洋の礼法に基づく修辞などは自己の卑下に過ぎるものとして異端扱いされるようにすらなってしまっている。
聖書圏で構築されて来たレベルの、ただただ自分を美々しく見せるばかりの修辞こそは、それを修める者に
無根拠なプライドを植え付けてしまってもいるわけだから、それもやはり、控えられて然るべきものとなる。
下賤を開き直る以上は念仏信者ほどにも完全であり、修辞を志す以上は正統な礼法に即して辞譲すらをも学ばせる
ようにする。それにより、人々が無根拠なプライドからなる思い上がりを募らせることをも控えさせるのである。
「枯楊稊を生じ、老夫其の女妻を得。利ろしからざる无し。老夫に女妻は、過ぎて以て相い与するなり。〜枯楊華を生じ、
老婦士夫を得。咎も无く誉れも无し。枯楊華を生ずるは、何ぞ久しかる可けんや。老婦に士夫も、亦た醜づ可きなり」
「枯れかかった楊柳から芽が生ずるようにして、老いた男が若い妻を娶る。これは特に問題ない。老いた男が若い妻を
娶った所で、多少異常ではあるにしたって調和は保たれるものだから。枯れかかった楊柳が花を生ずるようにして、
老いた女が若い男を得る。絶対にいけないということはないが、何の名誉にもならない。枯れかかった楊柳に花が
咲いたところで、どうしてそう持つことがあろう。老いた女に若い男は、かえって恥ずべきことですらある。
(聖書信者のように女々しく依存的な態度でいて、しかも自分が枯れ木のように老いさらばえていることを
標榜する。そこに愛の手を差し伸べたりするのは、差し伸べる側にとっても不名誉となり、恥となる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・大過・九二、九五、象伝より)
正統な礼節にすら見られることのない、ただただ美々しく大袈裟な修辞というものが生じた。今では、
どこの世界に行っても、欧米的な美化一辺倒の修辞こそが「修辞の標準」であるかのようにすら考えられて、
東洋の礼法に基づく修辞などは自己の卑下に過ぎるものとして異端扱いされるようにすらなってしまっている。
聖書圏で構築されて来たレベルの、ただただ自分を美々しく見せるばかりの修辞こそは、それを修める者に
無根拠なプライドを植え付けてしまってもいるわけだから、それもやはり、控えられて然るべきものとなる。
下賤を開き直る以上は念仏信者ほどにも完全であり、修辞を志す以上は正統な礼法に即して辞譲すらをも学ばせる
ようにする。それにより、人々が無根拠なプライドからなる思い上がりを募らせることをも控えさせるのである。
「枯楊稊を生じ、老夫其の女妻を得。利ろしからざる无し。老夫に女妻は、過ぎて以て相い与するなり。〜枯楊華を生じ、
老婦士夫を得。咎も无く誉れも无し。枯楊華を生ずるは、何ぞ久しかる可けんや。老婦に士夫も、亦た醜づ可きなり」
「枯れかかった楊柳から芽が生ずるようにして、老いた男が若い妻を娶る。これは特に問題ない。老いた男が若い妻を
娶った所で、多少異常ではあるにしたって調和は保たれるものだから。枯れかかった楊柳が花を生ずるようにして、
老いた女が若い男を得る。絶対にいけないということはないが、何の名誉にもならない。枯れかかった楊柳に花が
咲いたところで、どうしてそう持つことがあろう。老いた女に若い男は、かえって恥ずべきことですらある。
(聖書信者のように女々しく依存的な態度でいて、しかも自分が枯れ木のように老いさらばえていることを
標榜する。そこに愛の手を差し伸べたりするのは、差し伸べる側にとっても不名誉となり、恥となる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・大過・九二、九五、象伝より)
言葉や知識といった情報への対峙の仕方としては、
儒家のようにどこまでも学びて倦まざる心持ちでいるか、道家のように
情報全般の価値を否定しての「絶学無憂(老子)」の境地でいるかが適当だ。
あるいは、色声香味触法といった具体情報の価値全般の否定を体系的な
修行によって企てて行く、仏門のような姿勢でいるのでも構わない。
ある一定限度のドグマ情報に執着して、そこから抜け出すこともできなくなるという状態が、
人間にとって特に問題的となる状況で、それこそこれが世界中の社会問題の元凶ともなっている。
儒学にも四書五経を始めとする根幹的な学説があるし、仏門にも万巻の大蔵経に記録された教義学説がある。
絶学無憂を謳う道家ですら、老荘列のような最低限の意見書を後世にまで伝え遺している。(相当に素朴な著述ではあるが)
ただ、そのような教義学説があるからといって、儒仏道家が自分たちの教学ばかりで享受者をがんじがらめに
したりすることはなく、享受者がどこまでも融通無碍であり続けられるような体裁をも整えている。
(朝鮮儒教や日蓮カルトなどの異端派に、その条件を満たしていないものもいくらかはあるが)
この世界この宇宙を司る物理法則が全く線形的なものであるのなら、ある一定の情報によって全ての現象すらもが
理解しきれるようになるから、そのような情報を確保することにも意義が具わると言える。しかし実際のところ、
この世界この宇宙を司る物理法則からして非線形的なものであり、一定の情報だけで全ての現象を理解し尽くせる
などということもないから、一定の情報ばかりにこだわることがかえって不健全な事態をも招くようになっている。
儒家のようにどこまでも学びて倦まざる心持ちでいるか、道家のように
情報全般の価値を否定しての「絶学無憂(老子)」の境地でいるかが適当だ。
あるいは、色声香味触法といった具体情報の価値全般の否定を体系的な
修行によって企てて行く、仏門のような姿勢でいるのでも構わない。
ある一定限度のドグマ情報に執着して、そこから抜け出すこともできなくなるという状態が、
人間にとって特に問題的となる状況で、それこそこれが世界中の社会問題の元凶ともなっている。
儒学にも四書五経を始めとする根幹的な学説があるし、仏門にも万巻の大蔵経に記録された教義学説がある。
絶学無憂を謳う道家ですら、老荘列のような最低限の意見書を後世にまで伝え遺している。(相当に素朴な著述ではあるが)
ただ、そのような教義学説があるからといって、儒仏道家が自分たちの教学ばかりで享受者をがんじがらめに
したりすることはなく、享受者がどこまでも融通無碍であり続けられるような体裁をも整えている。
(朝鮮儒教や日蓮カルトなどの異端派に、その条件を満たしていないものもいくらかはあるが)
この世界この宇宙を司る物理法則が全く線形的なものであるのなら、ある一定の情報によって全ての現象すらもが
理解しきれるようになるから、そのような情報を確保することにも意義が具わると言える。しかし実際のところ、
この世界この宇宙を司る物理法則からして非線形的なものであり、一定の情報だけで全ての現象を理解し尽くせる
などということもないから、一定の情報ばかりにこだわることがかえって不健全な事態をも招くようになっている。
一定情報に固執しない姿勢こそが健全となるこの世界この宇宙こそは、人間ほどにも高度な生命を現出させた。
しからば、人間ほどにも高度に文化的な生物があるべき姿としては、一定のドグマ情報などに固執しない
あり方こそが自明に適切なものであるといえ、人間ほどにも高度に文化的な存在でありながら、ドグマ情報
ばかりに固執することが健全となるような理コトワリは、原理面からいってどこにもないと断定することができるのである。
限られた記憶容量の中でだけ構築されるコンピュータープログラム上のキャラクターなり世界なりは、
それこそ一定のプログラミング情報によってのみ司られているわけだから、一定の情報に固執するようなあり方で
司られているものだといえる。一方で、そのレベルで構築されている仮想空間上のキャラクターなどに「命」はなく、
どこまでもハリボテの模型止まりでしかあり得ない。もしもそれと同じように、この世界やこの宇宙もまた一定の限られた
情報によって司られていたりしたなら、人間のような生物もまた被造され得たところで、命や自我を持ちはしなかったはずである。
命が、死文に固執することを許さない。大昔から伝承されている古言なども、それが温故知新を促す活きた
言葉であるというのならいいが、そこで完結しきって何らの応用性も見られない死文となってしまっているというのなら、
それを理由としてそのような言葉は、もう考古学資料として以上の価値などを付与してやるべきではない。それが数百年〜
数千年にもわたって固執されてきたにも関わらず、何らの善果も得られなかった言葉だというのなら、なおさらのことだといえる。
「苟くも礼義忠信誠愨の心無くして以て之れに蒞めば、固く之れに結ぶと雖も、民其れ解けざらんや」
「礼儀忠信誠実の心なくして臨むというのなら、どんなに固く(束縛の縄などを)結んだとしても、いつかは解けて民たちも離反する」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓下第四より)
しからば、人間ほどにも高度に文化的な生物があるべき姿としては、一定のドグマ情報などに固執しない
あり方こそが自明に適切なものであるといえ、人間ほどにも高度に文化的な存在でありながら、ドグマ情報
ばかりに固執することが健全となるような理コトワリは、原理面からいってどこにもないと断定することができるのである。
限られた記憶容量の中でだけ構築されるコンピュータープログラム上のキャラクターなり世界なりは、
それこそ一定のプログラミング情報によってのみ司られているわけだから、一定の情報に固執するようなあり方で
司られているものだといえる。一方で、そのレベルで構築されている仮想空間上のキャラクターなどに「命」はなく、
どこまでもハリボテの模型止まりでしかあり得ない。もしもそれと同じように、この世界やこの宇宙もまた一定の限られた
情報によって司られていたりしたなら、人間のような生物もまた被造され得たところで、命や自我を持ちはしなかったはずである。
命が、死文に固執することを許さない。大昔から伝承されている古言なども、それが温故知新を促す活きた
言葉であるというのならいいが、そこで完結しきって何らの応用性も見られない死文となってしまっているというのなら、
それを理由としてそのような言葉は、もう考古学資料として以上の価値などを付与してやるべきではない。それが数百年〜
数千年にもわたって固執されてきたにも関わらず、何らの善果も得られなかった言葉だというのなら、なおさらのことだといえる。
「苟くも礼義忠信誠愨の心無くして以て之れに蒞めば、固く之れに結ぶと雖も、民其れ解けざらんや」
「礼儀忠信誠実の心なくして臨むというのなら、どんなに固く(束縛の縄などを)結んだとしても、いつかは解けて民たちも離反する」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓下第四より)
妊娠出産が女の身体そのものにとって有益だなんてことは少しもありゃしない。
「腹を痛める」という出産の歪曲表現通り、母体にとってはただだ損壊一辺倒であるばかりのもの。
ただ、それと引き換えに新たな命を宿し、家の跡取りともなる子を授かったりすることのほうが
めでたいのであって、差し引きでプラスマイナスゼロやそれ以上であることこそが名誉ともなるのだ。
母が腹を痛めて産んだ子であるにもかかわらず、その子が存在として有害無益であったりするのなら、それこそ
プラスマイナスゼロ以下の事態となるわけで、母たる女にとっては自らの出産が不名誉だったことにすらなる。
会津藩家老の子孫である田中清玄が、若き日に武装共産党の一員として乱暴を企てていたことに実母が
失望を抱き、自らの自殺によって我が子に反省を促したことなども、そのような名誉意識に基づいて
いたのであり、人の親たる女、母としての名誉というものもまた実在している確たる証拠ともなっている。
我が子が、産まないよりも産んでよかったと思えるほどにも偉大な人物となる所に、母としての名誉がある。そうで
なくたって、母には母性愛というものがあるから、出来損ないの我が子すらをも慈しむということはあるのだけれども、
そこに母としての名誉までもが具わっているわけではなく、ただただ情愛に溺れているというばかりのことであるのみ。
出来損ないの子供を母が慈しみたがる心持ちこそは、「腹を痛める」という自らの妊娠出産の不名誉と、
出来損ないな我が子の成長という不名誉の掛け合わせによって増長している。妊娠出産も不名誉であればこそ愛の源となり、
我が子の出来の悪さも不名誉であればこそ愛の源となる。社会的にいえば、母たる女がそのような濁愛の掛け合わせに
溺れきることは決して好ましいことではなく、妊娠出産の不名誉を出来の良い子の成長という名誉によって埋め合わせる
ことで、母たる女でありながら濁愛に溺れたりしないぐらいに毅然としていたほうがよい。それでこそ、田中清玄の
実母などほどにも毅然とした母であるが故に、君子士人の妻や母たるにも相応しいだけの資格が備わるのだといえる。
「腹を痛める」という出産の歪曲表現通り、母体にとってはただだ損壊一辺倒であるばかりのもの。
ただ、それと引き換えに新たな命を宿し、家の跡取りともなる子を授かったりすることのほうが
めでたいのであって、差し引きでプラスマイナスゼロやそれ以上であることこそが名誉ともなるのだ。
母が腹を痛めて産んだ子であるにもかかわらず、その子が存在として有害無益であったりするのなら、それこそ
プラスマイナスゼロ以下の事態となるわけで、母たる女にとっては自らの出産が不名誉だったことにすらなる。
会津藩家老の子孫である田中清玄が、若き日に武装共産党の一員として乱暴を企てていたことに実母が
失望を抱き、自らの自殺によって我が子に反省を促したことなども、そのような名誉意識に基づいて
いたのであり、人の親たる女、母としての名誉というものもまた実在している確たる証拠ともなっている。
我が子が、産まないよりも産んでよかったと思えるほどにも偉大な人物となる所に、母としての名誉がある。そうで
なくたって、母には母性愛というものがあるから、出来損ないの我が子すらをも慈しむということはあるのだけれども、
そこに母としての名誉までもが具わっているわけではなく、ただただ情愛に溺れているというばかりのことであるのみ。
出来損ないの子供を母が慈しみたがる心持ちこそは、「腹を痛める」という自らの妊娠出産の不名誉と、
出来損ないな我が子の成長という不名誉の掛け合わせによって増長している。妊娠出産も不名誉であればこそ愛の源となり、
我が子の出来の悪さも不名誉であればこそ愛の源となる。社会的にいえば、母たる女がそのような濁愛の掛け合わせに
溺れきることは決して好ましいことではなく、妊娠出産の不名誉を出来の良い子の成長という名誉によって埋め合わせる
ことで、母たる女でありながら濁愛に溺れたりしないぐらいに毅然としていたほうがよい。それでこそ、田中清玄の
実母などほどにも毅然とした母であるが故に、君子士人の妻や母たるにも相応しいだけの資格が備わるのだといえる。
子供にとっては、父が偉大であるかどうかよりも、母に名誉意識があるかどうかのほうが、自分自身が大成する
上での重大な材料となる。母が出来損ないの我が子への慈愛に溺れたりもせず、まず我が子が「産んでよかった」
と思えるだけの人物たり得ることのほうを重んずるようであれば、それに即して子供も着実に大成していく一方、
父があまりにも偉大過ぎたりしたなら、かえってコンプレックスを抱いて成長を滞らせたりしてしまうものだから。
母にそれなりの名誉意識があって、その意識に即して子供が成長したなら、その子供は確実に大成する。一方、
我が子への濁愛まみれの母の下で育った子供などは、それに即する以上は、ダメな子供になることが避けられない。
名誉ある母親として我が子を大成させたいのなら、妊娠出産そのものはむしろ不名誉なことだったと認識しておく
べきであり、そうともせず、妊娠出産そのものを「聖なること」などとして正当化してしまい、その心持ちに
即して我が子を育て上げたりしたなら、その影響下にあった分だけ、子供もろくでもない育ち方をすることになる。
(もちろん子ども自身の自助努力に基づく不遇の克服のような例外もあり得る)
良家の跡取りを産んだりしたなら、それだけでめでたいこととされたりすることもまたあるけれども、
別に妊娠一般、出産一般が女にとって必ずしも名誉になったりするわけでは決してない。ろくでもない男との
間に子を作ることが名誉にならなかったりするだけでなく、本人自身が我が子への濁愛に溺れてろくでもない子供を
育て上げ、自業自得の不名誉を招くようなことすらある。それこそ、自刃ものの不名誉だったりもするのである。
「晋如たり、愁如たり、貞しければ吉なり。玆の介いなる福いを、
其の王母に受く。玆の介いなる福を受けるは、中正を以ってなり」
「中正を以って進もうとしても、憂いを感じさせられるほどにうまくいかない。それでも正しきを貫けば吉祥であり、
大いなる慶福を自らの祖母や母から受けるようになる。(中正な行いは母系にまで着実な福を賜うのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・晋・六二‐象伝)
上での重大な材料となる。母が出来損ないの我が子への慈愛に溺れたりもせず、まず我が子が「産んでよかった」
と思えるだけの人物たり得ることのほうを重んずるようであれば、それに即して子供も着実に大成していく一方、
父があまりにも偉大過ぎたりしたなら、かえってコンプレックスを抱いて成長を滞らせたりしてしまうものだから。
母にそれなりの名誉意識があって、その意識に即して子供が成長したなら、その子供は確実に大成する。一方、
我が子への濁愛まみれの母の下で育った子供などは、それに即する以上は、ダメな子供になることが避けられない。
名誉ある母親として我が子を大成させたいのなら、妊娠出産そのものはむしろ不名誉なことだったと認識しておく
べきであり、そうともせず、妊娠出産そのものを「聖なること」などとして正当化してしまい、その心持ちに
即して我が子を育て上げたりしたなら、その影響下にあった分だけ、子供もろくでもない育ち方をすることになる。
(もちろん子ども自身の自助努力に基づく不遇の克服のような例外もあり得る)
良家の跡取りを産んだりしたなら、それだけでめでたいこととされたりすることもまたあるけれども、
別に妊娠一般、出産一般が女にとって必ずしも名誉になったりするわけでは決してない。ろくでもない男との
間に子を作ることが名誉にならなかったりするだけでなく、本人自身が我が子への濁愛に溺れてろくでもない子供を
育て上げ、自業自得の不名誉を招くようなことすらある。それこそ、自刃ものの不名誉だったりもするのである。
「晋如たり、愁如たり、貞しければ吉なり。玆の介いなる福いを、
其の王母に受く。玆の介いなる福を受けるは、中正を以ってなり」
「中正を以って進もうとしても、憂いを感じさせられるほどにうまくいかない。それでも正しきを貫けば吉祥であり、
大いなる慶福を自らの祖母や母から受けるようになる。(中正な行いは母系にまで着実な福を賜うのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・晋・六二‐象伝)
 この世界この宇宙が根本法則から「何でも出来るわけではない」ようにできていて、
この世界この宇宙が根本法則から「何でも出来るわけではない」ようにできていて、 その自由度の限定性があればこそ、人間ほどにも高度な生命体が成立してもいる。(>>48>>65なども参照)
本当に何でもできるというのなら、摩擦現象すら消滅させられもするだろうが、
人体や社会規模の物理構造も摩擦によってこそ成り立っている部分が多いから、
それでは人間や社会といった構造からして崩落して灰燼に帰してしまうことにもなる。
摩擦や空気抵抗を消滅させられてこそ永久機関が成立し、永遠の命などを得る原理的な手立てと
なることも期待できるわけだが、それでは摩擦をも介することでこそ成り立っている人間や社会が
成り立たなくもなってしまう。かくなる二律背反のジレンマを克服できる術こそは、どこにもありはしない。
相反性だとか因果応報の理コトワリだとか、万能性によってですら原理的にどうしようもない部分はさっさと諦観して、
一定限度の自由の範囲内での最善を尽くしたなら、それが本当に出来る限りのことをやったことにもなる。
日本の伝統文化など、上記の摩擦現象を巧みに利用したものが非常に多いという点で特筆に価する。
和服や注連縄や日本刀の拵など、縄紐を巧みに編み結ぶことで仕立てる物品というものが数多く、
その編み結び方にも巧みな工夫が凝らされていて、その技能を身に付けるためには一定の熟練を
必要とする場合もある。実際、それらの技巧を数学上の結び目理論などに置き換えてみると、
それはそれは複雑怪奇な位相幾何学と化すわけで、それほどにも理論的に難解となってしまう技巧を
直観で練り抜いてきたからこそ、日本人も世界で他に類を見ない程もの器用さを見につけたのでもある。
何でも出来ることではなく、一定限度の自由度の理コトワリの範囲内で最善を尽くす所にこそ、
人が感じられる最高級の面白みもまたある。単純に、結び目理論並みの高度な位相幾何学構造を練り込むことが
折り紙や綾取りのような遊戯でも行われるし、それぐらいに高度な思索からの練り込みこそが色々な「見事」さを
創出しもする。ただ新規なもの、奇抜なものを創作するだけなら見事だとも限らないが、高度な思索からの
練り込みに即するなら、そんなに新規でもないような工芸細工などの中にすら見事さを組み込むことが出来る。
そういった見事さを味わうことが人間にとっての最高級の楽しみともなるわけで、そうでない、ただただ
奇を衒うばかりの創作などには飽きてしまったような人間ですら、それを楽しむことができたりするのである。
その、人間にとっての最高級の楽しみを知らないから、万年欲求不満状態でいて、とにかく何でもやることで
快楽を得ようとするようにもなる。これは精神的未開というよりは、知能的未開に基づく悪循環であり、
いくら全能を実現する試みにかけての開発が進んでいるのであっても、根本的な部分で知能自体の
最高級の練り込みが足りていないままであり続けていたには違いないのである。そういった人間は
もはや、西洋文明にドップリ浸かりきってしまっている日本人などの内にも多いようではあるが。
「宰我、子貢は善く説辞を為し、冉牛、閔子、顔淵は善く徳行を言う。
孔子は之れを兼ねるも、曰うに、我れ辞命に於いては則ち能わざるなりと」
「(孔子の門弟の内でも)宰我や子貢は言辞能力が極めて優れ、冉牛や閔子や顔淵は徳行の実践が優れていた。
孔子は師匠なだけあって、言辞と徳行いずれにかけても優れていたが、自分では『ものを言うのが苦手だ』とも
言っていた。(巧言令色を卑劣なものと見なすなどの理由で、あえて万能をひけらかすことなどは避けた)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句上・二より)
人が感じられる最高級の面白みもまたある。単純に、結び目理論並みの高度な位相幾何学構造を練り込むことが
折り紙や綾取りのような遊戯でも行われるし、それぐらいに高度な思索からの練り込みこそが色々な「見事」さを
創出しもする。ただ新規なもの、奇抜なものを創作するだけなら見事だとも限らないが、高度な思索からの
練り込みに即するなら、そんなに新規でもないような工芸細工などの中にすら見事さを組み込むことが出来る。
そういった見事さを味わうことが人間にとっての最高級の楽しみともなるわけで、そうでない、ただただ
奇を衒うばかりの創作などには飽きてしまったような人間ですら、それを楽しむことができたりするのである。
その、人間にとっての最高級の楽しみを知らないから、万年欲求不満状態でいて、とにかく何でもやることで
快楽を得ようとするようにもなる。これは精神的未開というよりは、知能的未開に基づく悪循環であり、
いくら全能を実現する試みにかけての開発が進んでいるのであっても、根本的な部分で知能自体の
最高級の練り込みが足りていないままであり続けていたには違いないのである。そういった人間は
もはや、西洋文明にドップリ浸かりきってしまっている日本人などの内にも多いようではあるが。
「宰我、子貢は善く説辞を為し、冉牛、閔子、顔淵は善く徳行を言う。
孔子は之れを兼ねるも、曰うに、我れ辞命に於いては則ち能わざるなりと」
「(孔子の門弟の内でも)宰我や子貢は言辞能力が極めて優れ、冉牛や閔子や顔淵は徳行の実践が優れていた。
孔子は師匠なだけあって、言辞と徳行いずれにかけても優れていたが、自分では『ものを言うのが苦手だ』とも
言っていた。(巧言令色を卑劣なものと見なすなどの理由で、あえて万能をひけらかすことなどは避けた)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句上・二より)
 たとえば、日本史の時代時代を代表する人物といえば、
たとえば、日本史の時代時代を代表する人物といえば、 聖徳太子だとか藤原道長だとか源頼朝だとか足利尊氏だとか徳川家康だとかいった風に、
日本国の最高位たる天皇本人であるようなことがほとんどない。みな天皇の臣下であり、
また親戚だったりもするものの、ほとんどあえて天子の座からは距離を置こうとしてもいる。
それは、天子の座にある者が俗世で実力を行使することの汚らわしさを忌んでいるからで、
それが汚らわしいものとなってしまうのは、天皇こそがまさに「天人」そのものでもあるからだ。
天人そのものであるが故に、天皇こそは太陽そのものであるとすらいえる。
太陽そのもののように光り輝く存在であり、臣下はその光を受けて受動的に輝くもの。
俗世で活躍するに相応しいのはむしろ臣下のほうであり、自分自身が「光源」ではないが故に、
濁世のしがらみに苛まれることをさして問題にしたりする必要もなくて済む。
これこそは、身の程のわきまえによって、かえって最大級の実力を発揮できる実例であり、
そうともせず、誰も彼もが天人のように光源そのものでいて、しかも実力すら持とうなどとしたなら、
そのせいでの陰陽不全が深刻化し、誰しもが能力を発揮できないようなことにすらなってしまう。
このあたりの繊細な陰陽法則のわきまえは、秦帝国によって古代の中国文化の多くが損失させられた
以降の中国においてすら、疎かにされて来た所がある。だから、皇帝が皇帝として突出した世俗での
業績を挙げたり、重臣や将軍が帝位を簒奪することによる帝国の崩壊などの問題をも来たしてきた。
日本の神道文化に基づく体制構造は、秦帝国による文化破壊以前の中国の古代文化をも受け継いでいる
ものであり、日本が中国と比べれば小国であることからも、その価値を十分に発揮させることができた。
元々が「点と線」の統治止まりだった夏殷周時代の中国の文化であったものだから、国土全面規模での強権
支配を企てる大諸侯がのさばり始めた春秋戦国時代に、中国では伝統文化が衰亡せざるを得なかったわけだが、
細く長くて亡国級の争いも起こりにくい日本だと、国土全体を古代の秀逸文化によって覆い尽くすことができた。
いまたとえば、日本の伝統文化が古代の中国文化をも継承していることを標榜しつつ、それを中国大陸
などに移植することを考えてみたとしても、濁りきった新造文化に慣れきってしまっている今の中国人らの
好評を得られるとも限らない。特に魚食文化などは、内陸国である中国にそのまま適用するわけにも
いかないようなものだから、日本の風土に適用させた部分を中版用に改定し直すなどの必要が出てくる。
そも「覆水盆に返らず」であって、いくら昔の文化が秀逸であっても、色々と世相の転変してしまっている
現代にそのまま適用するわけにはいかないということがいくらでもある。それも重々踏まえた上で、
復古する価値のあるものは復古して、その手法にも現代に適った工夫を凝らすようにすればいい。
それこそ、道理に反する完全誤謬の集成であることが確証された、新旧約聖書の教義を完全な
反面教師としての参考にしていくことすら、時宜に適った工夫となるに違いないのである。
「剛健篤実にして輝光あり、日び其の徳を新たにす」
「剛健篤実で、日々徳を新たにして行くが故に、まるで自分自身が光り輝いているようである。
(『自らが光り輝いている』という表現は、自力作善の徳行が豊かである相手にこそ用いるべきもの。
日本史上でそれなりに功績を挙げたような人間ですら徳輝で天子には及ばないとしているのだから、
全くの他力本願である人間が自らを光輝に満ちているなどと考えるのは、もっての外だといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・大畜・彖伝より)
支配を企てる大諸侯がのさばり始めた春秋戦国時代に、中国では伝統文化が衰亡せざるを得なかったわけだが、
細く長くて亡国級の争いも起こりにくい日本だと、国土全体を古代の秀逸文化によって覆い尽くすことができた。
いまたとえば、日本の伝統文化が古代の中国文化をも継承していることを標榜しつつ、それを中国大陸
などに移植することを考えてみたとしても、濁りきった新造文化に慣れきってしまっている今の中国人らの
好評を得られるとも限らない。特に魚食文化などは、内陸国である中国にそのまま適用するわけにも
いかないようなものだから、日本の風土に適用させた部分を中版用に改定し直すなどの必要が出てくる。
そも「覆水盆に返らず」であって、いくら昔の文化が秀逸であっても、色々と世相の転変してしまっている
現代にそのまま適用するわけにはいかないということがいくらでもある。それも重々踏まえた上で、
復古する価値のあるものは復古して、その手法にも現代に適った工夫を凝らすようにすればいい。
それこそ、道理に反する完全誤謬の集成であることが確証された、新旧約聖書の教義を完全な
反面教師としての参考にしていくことすら、時宜に適った工夫となるに違いないのである。
「剛健篤実にして輝光あり、日び其の徳を新たにす」
「剛健篤実で、日々徳を新たにして行くが故に、まるで自分自身が光り輝いているようである。
(『自らが光り輝いている』という表現は、自力作善の徳行が豊かである相手にこそ用いるべきもの。
日本史上でそれなりに功績を挙げたような人間ですら徳輝で天子には及ばないとしているのだから、
全くの他力本願である人間が自らを光輝に満ちているなどと考えるのは、もっての外だといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・大畜・彖伝より)
自分個人としては、内面からの善意修身によって善行や善言をも派生させていくのが基本だが、
社会的存在としての人間にとっての罪の重さは、悪行>悪言>悪意の順番である。
いくら内心で悪いことを考えていたりした所で、行いにそれが反映されていないのなら、
善意を心がけながらも行いは罪悪にまみれている人間などと比べれば、その罪も皆無に等しい。
ただ、本当に最善の善意や善思を心がけているのなら、そこから積極的な悪行などが派生するはずもない。
善意を心がけながらも行いが罪悪にまみれているというのなら、それは自分自身の意思配慮のどこかに
片手落ちな部分が残存しているからで、そのような片手落ちな善意による行いこそは偽善の行いともなる。
内心にいくらかもの悪意が残存しているというのなら、そこから積極的な行いが為された場合、
必ず悪行となる。ただ、必ずしも行いに移されるとも限らないから、悪意が必ずしも悪行になるともいえない。
実践にかけての配慮が足りない場合などがあるから、善意も必ずしも善行に結び付くとは限らないし、
そもそも実践に移さない場合があるから、悪意も必ずしも悪行に結び付くとは限らない。その上で、
世俗上での罪の重さは悪行>悪言>悪意だから、善意の持ち主や悪意の持ち主の罪の重さも
悪行を為す悪意の持ち主>悪行を為す善意の持ち主>悪行を為さない悪意の持ち主>悪行を為さない善意の持ち主
の順位となる。世俗上での罪の重さで言えば、悪行を為す善意の持ち主よりも、悪行を為さない善意の持ち主の
ほうがまだマシであり、これに即して、前者こそは後者以上もの重罪人として相応の処罰をも受けなければならない。
社会的存在としての人間にとっての罪の重さは、悪行>悪言>悪意の順番である。
いくら内心で悪いことを考えていたりした所で、行いにそれが反映されていないのなら、
善意を心がけながらも行いは罪悪にまみれている人間などと比べれば、その罪も皆無に等しい。
ただ、本当に最善の善意や善思を心がけているのなら、そこから積極的な悪行などが派生するはずもない。
善意を心がけながらも行いが罪悪にまみれているというのなら、それは自分自身の意思配慮のどこかに
片手落ちな部分が残存しているからで、そのような片手落ちな善意による行いこそは偽善の行いともなる。
内心にいくらかもの悪意が残存しているというのなら、そこから積極的な行いが為された場合、
必ず悪行となる。ただ、必ずしも行いに移されるとも限らないから、悪意が必ずしも悪行になるともいえない。
実践にかけての配慮が足りない場合などがあるから、善意も必ずしも善行に結び付くとは限らないし、
そもそも実践に移さない場合があるから、悪意も必ずしも悪行に結び付くとは限らない。その上で、
世俗上での罪の重さは悪行>悪言>悪意だから、善意の持ち主や悪意の持ち主の罪の重さも
悪行を為す悪意の持ち主>悪行を為す善意の持ち主>悪行を為さない悪意の持ち主>悪行を為さない善意の持ち主
の順位となる。世俗上での罪の重さで言えば、悪行を為す善意の持ち主よりも、悪行を為さない善意の持ち主の
ほうがまだマシであり、これに即して、前者こそは後者以上もの重罪人として相応の処罰をも受けなければならない。
ただ善意や悪意を持つというのなら、もちろん悪意を持たずに善意を持つことのほうがいいに決まっている。ただ、
いくら純然たる善意を抱いているのであっても、それを行動に移すのならば、そこに必ず最大級の配慮が尽くされて
いなければならない。配慮を欠いているが故に片手落ちである善行を為したりしたならば、たとえば一億円の寄付を
するために十億円の不正利得をせしめたりするようにして、結果としては善行以上の悪行となってしまったりする。
そうなればもはや、内心は悪意の塊だが何もしないでいる匹夫にすら及ばないザマと化してしまうのである。
内面からの断悪修善もするに越したことはないが、同時に、行動の有無や積極消極の選別をも尽くしていくべきである。
「善意と配慮が尽くされているので積極的に行動する」「善意はあっても配慮が足りないので行動は控える」
「悪意の塊なのでできる限りなにもしないでいる」「善意がなくてむしろ悪意があるが、機械的に善行を為す術は
熟知しているので、その知恵に即して善行に限って積極的に行動する」これらの行動規範なら全く問題がない一方、
「善意はあっても配慮はないままに積極的に行動する」「善意もなくて善行を為す知恵もないのに積極的に行動する」
というのでは問題大アリであり、そのような行動規範に凝り固まってしまっている人間にはただひたすらの謹慎を促す次第である。
「我れも亦た人心を正し、邪説を息め、詖行を距ぎ、淫辞を放ち、以て三聖者を承がんと欲す」
「私(孟子)もまた人々の内心を正し、間違った教義学説を排し、偏った行いを防ぎ止め、淫らな言論を追放して、
三人の大聖人(禹、周公、孔子)の業を受け継ぎたいと欲しているのだ。(『格物致知誠意正心修身斉家治国平天下』
という順番の通り、やはり内心からの乱れが邪説暴行を蔓延させる原因ともなってしまうのである。悪意悪言悪行の
開き直りを促したイエスの邪説暴行からして、当時のパリサイ人らの偽善志向がもたらしたものなのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・滕文公章句下・九より)
いくら純然たる善意を抱いているのであっても、それを行動に移すのならば、そこに必ず最大級の配慮が尽くされて
いなければならない。配慮を欠いているが故に片手落ちである善行を為したりしたならば、たとえば一億円の寄付を
するために十億円の不正利得をせしめたりするようにして、結果としては善行以上の悪行となってしまったりする。
そうなればもはや、内心は悪意の塊だが何もしないでいる匹夫にすら及ばないザマと化してしまうのである。
内面からの断悪修善もするに越したことはないが、同時に、行動の有無や積極消極の選別をも尽くしていくべきである。
「善意と配慮が尽くされているので積極的に行動する」「善意はあっても配慮が足りないので行動は控える」
「悪意の塊なのでできる限りなにもしないでいる」「善意がなくてむしろ悪意があるが、機械的に善行を為す術は
熟知しているので、その知恵に即して善行に限って積極的に行動する」これらの行動規範なら全く問題がない一方、
「善意はあっても配慮はないままに積極的に行動する」「善意もなくて善行を為す知恵もないのに積極的に行動する」
というのでは問題大アリであり、そのような行動規範に凝り固まってしまっている人間にはただひたすらの謹慎を促す次第である。
「我れも亦た人心を正し、邪説を息め、詖行を距ぎ、淫辞を放ち、以て三聖者を承がんと欲す」
「私(孟子)もまた人々の内心を正し、間違った教義学説を排し、偏った行いを防ぎ止め、淫らな言論を追放して、
三人の大聖人(禹、周公、孔子)の業を受け継ぎたいと欲しているのだ。(『格物致知誠意正心修身斉家治国平天下』
という順番の通り、やはり内心からの乱れが邪説暴行を蔓延させる原因ともなってしまうのである。悪意悪言悪行の
開き直りを促したイエスの邪説暴行からして、当時のパリサイ人らの偽善志向がもたらしたものなのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・滕文公章句下・九より)
善も偽善も、善である部分自体に大差はない。
まともな勤労で得た収益の内から一億円を寄付しようが、強盗殺人で得た金の内から一億円を寄付しようが、
一億円の寄付は一億円の寄付であり、それだけを見て善行のように思えたとしても別におかしいことではない。
それでも前者が善となり、後者が悪となるのは、本人たちの総合的な素行がプラスマイナスゼロ以上の
善行となっていたり、プラマイゼロ以下の悪行となっていたりするからだ。
内心の善意悪意如何によって行いの善悪までもが決するのではなく、総合的な素行の如何によってこそ
行いの善悪が決する。>>75の「善意がなくてむしろ悪意があるが、機械的に善行を為す術は熟知しているので、
その知恵に即して善行に限って積極的に行動する」という行動規範に即して行われる善行も、決して偽善とはならない。
この場合でも悪を為さずに善を為すから、総合的な素行もまた善行となって、偽善のそしりを免れることができる。
上では「一億円の寄付」という例を挙げたけれども、私人による大金の寄付などが偽善でなくて済むようなことは
ほとんどない。「富めば仁ならず、仁なれば富まず(孟子)」で、寄付をできるほどもの大金をせしめているからには
何か後ろめたい裏があると考えるほうが、世の常のあり方にも即している。だから世界でも突出して堅実志向である
日本人などは、個人での寄付などをあまり自他共に推奨しないし、海外でもチップの慣習をうざったく感じたりする。
着実に偽善でない善を実行できる手段こそは、為政者としての仁徳にかなった善政でこそある。
民間人としての副業なども行わない公人であるならば、自分やその家族は民の納める年貢や税金によって食い扶持を繋ぐ
ことともなるから、善政によって人々を豊かにすれば、それによって自分たちもまた連動的に豊かになれる一方で、苛政に
よって人々を苦しめたなら、それによって世の中全体の荒廃をもたらして、挙句には自分たちごとの破滅を招くことになる。
そのような自明な法則に即していればこそ、善政によって人々を安楽ならしめることこそは、純然たる善行でしかあり得ない。
まともな勤労で得た収益の内から一億円を寄付しようが、強盗殺人で得た金の内から一億円を寄付しようが、
一億円の寄付は一億円の寄付であり、それだけを見て善行のように思えたとしても別におかしいことではない。
それでも前者が善となり、後者が悪となるのは、本人たちの総合的な素行がプラスマイナスゼロ以上の
善行となっていたり、プラマイゼロ以下の悪行となっていたりするからだ。
内心の善意悪意如何によって行いの善悪までもが決するのではなく、総合的な素行の如何によってこそ
行いの善悪が決する。>>75の「善意がなくてむしろ悪意があるが、機械的に善行を為す術は熟知しているので、
その知恵に即して善行に限って積極的に行動する」という行動規範に即して行われる善行も、決して偽善とはならない。
この場合でも悪を為さずに善を為すから、総合的な素行もまた善行となって、偽善のそしりを免れることができる。
上では「一億円の寄付」という例を挙げたけれども、私人による大金の寄付などが偽善でなくて済むようなことは
ほとんどない。「富めば仁ならず、仁なれば富まず(孟子)」で、寄付をできるほどもの大金をせしめているからには
何か後ろめたい裏があると考えるほうが、世の常のあり方にも即している。だから世界でも突出して堅実志向である
日本人などは、個人での寄付などをあまり自他共に推奨しないし、海外でもチップの慣習をうざったく感じたりする。
着実に偽善でない善を実行できる手段こそは、為政者としての仁徳にかなった善政でこそある。
民間人としての副業なども行わない公人であるならば、自分やその家族は民の納める年貢や税金によって食い扶持を繋ぐ
ことともなるから、善政によって人々を豊かにすれば、それによって自分たちもまた連動的に豊かになれる一方で、苛政に
よって人々を苦しめたなら、それによって世の中全体の荒廃をもたらして、挙句には自分たちごとの破滅を招くことになる。
そのような自明な法則に即していればこそ、善政によって人々を安楽ならしめることこそは、純然たる善行でしかあり得ない。
こうして見てみると、道理に適った善と偽善の分別というのは、いま人々が考えているような善偽善の区別とは
大幅に食い違っていることが分かる。裏事情なんか無視して、寄付こそは善行の最たるものであるかのように扱われ、
それでも内面に下心や悪意があったりするようなら、それだけで偽善だなどと決め付けられもする。端的に言って、
大衆の善と偽善の区別が極度に稚拙化してしまっており、そのせいで、道理に即して偽善や悪と断じられる素行を
「偽善でない善行」のように見せかける情報工作などにも、まんまと乗せられるようになってしまっている。
そのような、洗脳工作の餌食ともなってしまう稚拙な善偽善の区別基準を広く世に流布した代表者もまた
イエスキリストであり、これは全く「郷原(田舎者の偽善者)」としてのイエス本人の愚かさに基づくものだった。
自分たちではまともに国政を担うこともできないでいた商業民族古代ユダヤ人の内で、さらに妾腹の私生児として生まれ
育った、あまりにも「井の中の蛙」然としたその境遇によって、稚拙極まりない善偽善の区別基準をも捏造したのだった。
あまりにも稚拙で的外れな善偽善の区別基準が広く認知されてしまっているからこそ、まずは善悪も偽善も全く
判別できていないということを今の人々には深くわきまえさせなければならない。その上で本物の道理に即した
善悪や善偽善の分別を学ばせていくのでなければ、思考回路がこんがらがって全く修正も覚束なくなってしまう。
最低限の倫理的分別ぐらいできていると思っていた連中が、一旦は畜生も同然の蒙昧さを重々自覚させられなければ
ならなくなるわけだから、相当の赤っ恥になるに違いなく、その辱めを乗り越えていくことが大きな障壁ともなっていく。
「怨むのならイエスを怨め」という他はないが、イエスをその罪状に即して怨むことができるように
なった頃には、もうすでに最低限の善悪や善偽善の分別ぐらいは付くようにもなっているだろうから、
まずは「イエスを怨めるようになれ」という所から目標にもしていかなければならないのだろう。
大幅に食い違っていることが分かる。裏事情なんか無視して、寄付こそは善行の最たるものであるかのように扱われ、
それでも内面に下心や悪意があったりするようなら、それだけで偽善だなどと決め付けられもする。端的に言って、
大衆の善と偽善の区別が極度に稚拙化してしまっており、そのせいで、道理に即して偽善や悪と断じられる素行を
「偽善でない善行」のように見せかける情報工作などにも、まんまと乗せられるようになってしまっている。
そのような、洗脳工作の餌食ともなってしまう稚拙な善偽善の区別基準を広く世に流布した代表者もまた
イエスキリストであり、これは全く「郷原(田舎者の偽善者)」としてのイエス本人の愚かさに基づくものだった。
自分たちではまともに国政を担うこともできないでいた商業民族古代ユダヤ人の内で、さらに妾腹の私生児として生まれ
育った、あまりにも「井の中の蛙」然としたその境遇によって、稚拙極まりない善偽善の区別基準をも捏造したのだった。
あまりにも稚拙で的外れな善偽善の区別基準が広く認知されてしまっているからこそ、まずは善悪も偽善も全く
判別できていないということを今の人々には深くわきまえさせなければならない。その上で本物の道理に即した
善悪や善偽善の分別を学ばせていくのでなければ、思考回路がこんがらがって全く修正も覚束なくなってしまう。
最低限の倫理的分別ぐらいできていると思っていた連中が、一旦は畜生も同然の蒙昧さを重々自覚させられなければ
ならなくなるわけだから、相当の赤っ恥になるに違いなく、その辱めを乗り越えていくことが大きな障壁ともなっていく。
「怨むのならイエスを怨め」という他はないが、イエスをその罪状に即して怨むことができるように
なった頃には、もうすでに最低限の善悪や善偽善の分別ぐらいは付くようにもなっているだろうから、
まずは「イエスを怨めるようになれ」という所から目標にもしていかなければならないのだろう。
「許子の道に従わば、則ち市は賈いに弐なく、国中に偽り無く、五尺の童をして市に適かしむと雖も、之れを欺く或無し。
布帛の長短同じければ、則ち賈相い若しく、麻縷絲絮の軽重同じければ、則ち賈相い若しく、五穀の多寡同じければ、
則ち賈相い若しく、屨の大小同じければ、則ち賈相い若し。曰く、夫れ物の斉しからざるは、物の情なり。或いは相い倍蓰し、
或いは相い什伯し、或いは相い千万す。子比べて之れを同じうせんとするは、是れ天下を乱すなり。巨屨と小屨の賈
同じうせば、人豈に之れを為らんや。許子の道に従うは、相い率いて偽りを為す者なり。悪んぞ能く国家を治めんか」
布帛の長短同じければ、則ち賈相い若しく、麻縷絲絮の軽重同じければ、則ち賈相い若しく、五穀の多寡同じければ、
則ち賈相い若しく、屨の大小同じければ、則ち賈相い若し。曰く、夫れ物の斉しからざるは、物の情なり。或いは相い倍蓰し、
或いは相い什伯し、或いは相い千万す。子比べて之れを同じうせんとするは、是れ天下を乱すなり。巨屨と小屨の賈
同じうせば、人豈に之れを為らんや。許子の道に従うは、相い率いて偽りを為す者なり。悪んぞ能く国家を治めんか」
「陳相『(農業版の墨家とでも言うべき農家思想の実践者である)許子のやり方に従うのであれば、あらゆる物品の値段に
掛け値が付けられることがなくなり、国中で偽りを働くものがなくなり、小さな子供を市に買い物に行かせても誰も
値段をごまかして高く売ったりすることがなくなります。布や錦も長さが同じなら同じ値段、麻糸生糸真綿も分量が同じなら
同じ値段、五穀も目方が同じなら同じ値段、靴も同じ大きさなら同じ値段となるのです』 孟子『諸々の物品に品質の
ばらつきがあって、決してその価値が一定的でないのが物の理コトワリというもの。時には倍程もの値段の開きが、また時には
十倍百倍、千倍万倍の開きすらもが生じてしまうもの。もしもそれを全く一定にしてしまうとすれば、これは天下を乱す
原因となってしまう。上等な靴と粗末な靴の値段も同じにしてしまうのであれば、もはや誰も上等な靴などを拵えようと
したりはしなくなる。許子のやり方に従えば偽りがなくなるのではなく、誰しもに偽りをけしかけることにすらなってしまう。
それでどうして国家を治めたりすることができるだろうか』(驚異の、2300年前の共産主義批判。孟子は性善論者である
にもかかわらず、玩物喪志が生業となる商売人が偽善詐悪に及ぶことは全くの折込済みとしている。別にそれを悲嘆したりは
せずに、自分たちが君子士人として農工商三民の営みを適正に制御していくことのほうにこそ前向きでいる。商売人なんて
いつの時代も世界の少数派でしかいられないのだから、そんな連中の偽善さ加減に憤ったりしてるほうが井中の蛙だといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・滕文公章句上・四より)
掛け値が付けられることがなくなり、国中で偽りを働くものがなくなり、小さな子供を市に買い物に行かせても誰も
値段をごまかして高く売ったりすることがなくなります。布や錦も長さが同じなら同じ値段、麻糸生糸真綿も分量が同じなら
同じ値段、五穀も目方が同じなら同じ値段、靴も同じ大きさなら同じ値段となるのです』 孟子『諸々の物品に品質の
ばらつきがあって、決してその価値が一定的でないのが物の理コトワリというもの。時には倍程もの値段の開きが、また時には
十倍百倍、千倍万倍の開きすらもが生じてしまうもの。もしもそれを全く一定にしてしまうとすれば、これは天下を乱す
原因となってしまう。上等な靴と粗末な靴の値段も同じにしてしまうのであれば、もはや誰も上等な靴などを拵えようと
したりはしなくなる。許子のやり方に従えば偽りがなくなるのではなく、誰しもに偽りをけしかけることにすらなってしまう。
それでどうして国家を治めたりすることができるだろうか』(驚異の、2300年前の共産主義批判。孟子は性善論者である
にもかかわらず、玩物喪志が生業となる商売人が偽善詐悪に及ぶことは全くの折込済みとしている。別にそれを悲嘆したりは
せずに、自分たちが君子士人として農工商三民の営みを適正に制御していくことのほうにこそ前向きでいる。商売人なんて
いつの時代も世界の少数派でしかいられないのだから、そんな連中の偽善さ加減に憤ったりしてるほうが井中の蛙だといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・滕文公章句上・四より)
許されないことは許されないというのが常道であり、それすら時に為すというのが非常である。
非常は非常で一応あることであり、「六韜」「三略」にあるような兵法もまたその内に入る。
賄賂で敵を籠絡したり、近隣同士で利権を守り合って遠方を蔑ろにしたり※といったことも、
戦闘状態のような非常時であれば必ずしも許されないとも限らないが、それが常道化してしまえば
もはや倫理的制御が振り切れて、自業自得の自滅を招く原因ともなる。だから六韜三略なども、
前置きで正義に根ざした英雄としての心構えやその実践を促しているわけだが、新約の登場人物の
イエスなんざは、三略が非常時の手段としてのみ提示している「釈遠謀近(※に相当)」を「隣人愛」
として常道化してしまうことすらをも促しているわけで、これは「非常時に限って許されることを
常道化してしまう」という禁忌を犯している所こそが決定的な落ち度となっているのだといえる。
非常時に限って許されることを含めれば、この世に許されないことなんて無いとすら言っていい。
儒学で絶対の禁忌とされている父殺しですら、源義朝が勅命によってさせられている。その父の恥辱を晴らす
形で源頼朝も怨敵平氏を討伐して武家政権を立ち上げるという功績を挙げたわけで、これも非常を常道に
戻すという落とし前が済まされているからこそ、倫理的な問題として扱われたりする必要がなくなっている。
非常時に限って許されることを常道化しようとすることが、倫理的にも決定的な禁忌となる。
平時にわけもなく親を殺したりすれば、それこそ本人を処刑して家の跡地を堀池にしてしまうぐらいの
厳罰が妥当ともなる(「礼記」参照)。それを許してしまったりすることことそは決定的な禁忌であり、
その禁忌すら犯してしまったりした所でこそ、人は悪逆非道の自業自得に基づく自滅が免れられなくもなる。
非常は非常で一応あることであり、「六韜」「三略」にあるような兵法もまたその内に入る。
賄賂で敵を籠絡したり、近隣同士で利権を守り合って遠方を蔑ろにしたり※といったことも、
戦闘状態のような非常時であれば必ずしも許されないとも限らないが、それが常道化してしまえば
もはや倫理的制御が振り切れて、自業自得の自滅を招く原因ともなる。だから六韜三略なども、
前置きで正義に根ざした英雄としての心構えやその実践を促しているわけだが、新約の登場人物の
イエスなんざは、三略が非常時の手段としてのみ提示している「釈遠謀近(※に相当)」を「隣人愛」
として常道化してしまうことすらをも促しているわけで、これは「非常時に限って許されることを
常道化してしまう」という禁忌を犯している所こそが決定的な落ち度となっているのだといえる。
非常時に限って許されることを含めれば、この世に許されないことなんて無いとすら言っていい。
儒学で絶対の禁忌とされている父殺しですら、源義朝が勅命によってさせられている。その父の恥辱を晴らす
形で源頼朝も怨敵平氏を討伐して武家政権を立ち上げるという功績を挙げたわけで、これも非常を常道に
戻すという落とし前が済まされているからこそ、倫理的な問題として扱われたりする必要がなくなっている。
非常時に限って許されることを常道化しようとすることが、倫理的にも決定的な禁忌となる。
平時にわけもなく親を殺したりすれば、それこそ本人を処刑して家の跡地を堀池にしてしまうぐらいの
厳罰が妥当ともなる(「礼記」参照)。それを許してしまったりすることことそは決定的な禁忌であり、
その禁忌すら犯してしまったりした所でこそ、人は悪逆非道の自業自得に基づく自滅が免れられなくもなる。
六韜三略を始めとする優良な兵法書に書かれてあることの多くが「非常時に限って許される手段」
である一方、四書五経に書かれてるあることは「平時に守るべき常道」である。両者を合わせれば、
結局何も許されないことなどないわけで、ただ平時と非常時の分別が必要とされているというだけの
ことであることが分かる。「義とは時宜に即することである(中庸)」という通り、平時には平時の、
非常時には非常時のあり方に即することが結局は、仁義道徳の実践のためにも至上となるのである。
絶対的な禁忌は、純粋な位相上の領域にある。平時と非常時の分別すら付けたなら、人間に許されない
ことなど何もないが、その分別を欠いて、非常時にのみ許されることを平時に為そうものなら、それが
致命的な落ち度となって、不可避な破綻を招くことともなる。具体的に何が許されて何が許されない
などということとはまた別に、そこにこそ人類の存亡をも左右する禁忌があったのだから、いま人類が
滅亡の危機に瀕している原因となっているのも、物事の位相を把握する能力の欠如でこそあるのだといえる。
非常時に限って許される手法を常道化しようとした邪義の集成が新旧約聖書であり、そうであること
こそが人類滅亡の危機の元凶ともなった。記述が悪逆非道であることにかけては、兵法書の戦略部分など
も勝るとも劣らないが、兵法書にはそれを非常手段とする分別がある一方、新旧約聖書にはそれがない。
違うのは位相の把握の有無というばかりのことで、六三のごとき兵法書の記録が時宜の分別を欠けば、
それだけで新旧約聖書のような奇天烈なカルト文書と化してしまう。炊きたてのご飯は真っ白でも、
何日も置いとけばご飯も腐ってカビだらけの七色変化を始めるようなもので、この場合のご飯に
相当する記録材料自体は、四書五経や兵法書と新旧約聖書とで、何も代わるところはないのである。
(むしろ、四書五経や七書よりも新旧約聖書のほうが記録材料としているものは些少だといえる。)
である一方、四書五経に書かれてるあることは「平時に守るべき常道」である。両者を合わせれば、
結局何も許されないことなどないわけで、ただ平時と非常時の分別が必要とされているというだけの
ことであることが分かる。「義とは時宜に即することである(中庸)」という通り、平時には平時の、
非常時には非常時のあり方に即することが結局は、仁義道徳の実践のためにも至上となるのである。
絶対的な禁忌は、純粋な位相上の領域にある。平時と非常時の分別すら付けたなら、人間に許されない
ことなど何もないが、その分別を欠いて、非常時にのみ許されることを平時に為そうものなら、それが
致命的な落ち度となって、不可避な破綻を招くことともなる。具体的に何が許されて何が許されない
などということとはまた別に、そこにこそ人類の存亡をも左右する禁忌があったのだから、いま人類が
滅亡の危機に瀕している原因となっているのも、物事の位相を把握する能力の欠如でこそあるのだといえる。
非常時に限って許される手法を常道化しようとした邪義の集成が新旧約聖書であり、そうであること
こそが人類滅亡の危機の元凶ともなった。記述が悪逆非道であることにかけては、兵法書の戦略部分など
も勝るとも劣らないが、兵法書にはそれを非常手段とする分別がある一方、新旧約聖書にはそれがない。
違うのは位相の把握の有無というばかりのことで、六三のごとき兵法書の記録が時宜の分別を欠けば、
それだけで新旧約聖書のような奇天烈なカルト文書と化してしまう。炊きたてのご飯は真っ白でも、
何日も置いとけばご飯も腐ってカビだらけの七色変化を始めるようなもので、この場合のご飯に
相当する記録材料自体は、四書五経や兵法書と新旧約聖書とで、何も代わるところはないのである。
(むしろ、四書五経や七書よりも新旧約聖書のほうが記録材料としているものは些少だといえる。)
「時に先んずる者は殺して赦さず。時に及ばざる者も殺して赦さず」
「時宜に反して先んじようとする者は許さず死刑に、遅れてくるものも許さず死刑に。
(時宜をわきまえぬ位相感覚の欠如の致命的な問題性を鋭く見抜いた格言。
これこそが、自他の不可避なる破滅を招く決定的な要因となるのであり、
そこに厳格な刑罰を加えるのは、支配というよりは運命への準拠だといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・夏書・胤征より)
「時宜に反して先んじようとする者は許さず死刑に、遅れてくるものも許さず死刑に。
(時宜をわきまえぬ位相感覚の欠如の致命的な問題性を鋭く見抜いた格言。
これこそが、自他の不可避なる破滅を招く決定的な要因となるのであり、
そこに厳格な刑罰を加えるのは、支配というよりは運命への準拠だといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・夏書・胤征より)
君子はまず徳を懐うにしても、やはりいつの時代も小人のほうは土を懐うもので(里仁第四・一一)、
民間の匹夫による身勝手な縄張り争いを防止する目的でも、士大夫を統べる徳治社会の王侯大名は
封土を頂き、領土単位での責任ある統治を執り行う。それは決して地権への執着などによって
行われるべきものではないために、諸国を統べる帝王だとか大将軍だとかがトップダウンに
それぞれの国を治める王侯大名を指名するのが基本ともなっている。江戸幕府では参勤交代に
よって諸大名の封土への根付ききりを人工的に抑制することまでもが実施され、徹底して
土地利権そのものと諸大名が癒着しきることを牽制する施策が敷かれてもいた。
(土佐藩や薩摩藩など、検地の不備からこれが行き届かなかった例もあった)
民間人が私的に恵まれた土地を囲い込んで有効利用することによる収益たるや半端なものではなく、
山形の酒田一帯を私有していた本間氏のように、徳治社会ですら大名諸侯も顔負けの富裕を手に入れる
場合すらある。徳治社会でない、西洋型の封建社会などでの地権に基づく富裕はさらにそれ以上で、
ちゃんと封土を区切っての責任ある統治を心がけたりすることもなかいから、徳治社会では被支配階級と
される地主身分の人間がそのまま王侯としての権限を掌握したりする。その最大例がハプスブルグ家や
ロマノフ家だったりもするが、封土の責任ある統治ではなく、地主兼陣取り合戦の覇者であることこそを
生業としていたことから、家としての富裕は徳治社会の王侯家のそれをも上回るほどのものとなっていた。
民間の匹夫による身勝手な縄張り争いを防止する目的でも、士大夫を統べる徳治社会の王侯大名は
封土を頂き、領土単位での責任ある統治を執り行う。それは決して地権への執着などによって
行われるべきものではないために、諸国を統べる帝王だとか大将軍だとかがトップダウンに
それぞれの国を治める王侯大名を指名するのが基本ともなっている。江戸幕府では参勤交代に
よって諸大名の封土への根付ききりを人工的に抑制することまでもが実施され、徹底して
土地利権そのものと諸大名が癒着しきることを牽制する施策が敷かれてもいた。
(土佐藩や薩摩藩など、検地の不備からこれが行き届かなかった例もあった)
民間人が私的に恵まれた土地を囲い込んで有効利用することによる収益たるや半端なものではなく、
山形の酒田一帯を私有していた本間氏のように、徳治社会ですら大名諸侯も顔負けの富裕を手に入れる
場合すらある。徳治社会でない、西洋型の封建社会などでの地権に基づく富裕はさらにそれ以上で、
ちゃんと封土を区切っての責任ある統治を心がけたりすることもなかいから、徳治社会では被支配階級と
される地主身分の人間がそのまま王侯としての権限を掌握したりする。その最大例がハプスブルグ家や
ロマノフ家だったりもするが、封土の責任ある統治ではなく、地主兼陣取り合戦の覇者であることこそを
生業としていたことから、家としての富裕は徳治社会の王侯家のそれをも上回るほどのものとなっていた。
春秋戦国時代の中国の大諸侯だとか、日本の戦国大名だとかも、陣取り合戦に勝利するようなことが
あればこそ、泰平社会の大名諸侯などにはありえない程もの巨万の富に与れることが多々あった。
権力者が責任ある封土の統治をも無視して、ただひたすら土地利権の収奪を目指したところでこそ
人として最大級の富裕が手に入れられるとすら言え、20世紀におけるアメリカの富豪の栄華なぞも、
「北米大陸中部」という土地の利を寡占することによってこそ成し得たものだといえるわけだが、
それは同時に、土地を収益対象ではなく堅実な生活の場としている庶民たちに極度の疲弊を強いるという
弊害をも招いてしまうことなわけで、それを常なることとするのではやはり致命的な破滅を招くことになる。
王侯大名も当然領土を所有するが、それは完全に領土の保全を目的としたものであるべきで、
地の利を自分たち自身が私有しての富裕に与るためなどであってはならない。地の利は純粋に民間人の
消費物としてやるべきで、その代わりに民間人のトップダウンな統制を徹底するようにもする。
それが実現されるのが泰平統治の常道というもので、公権力者までもが地の利への野望などを抱いたり
するのは非常である。これもまた一つの位相のわきまえであり、乱世に武王や劉邦や信長や秀吉や家康の
ごとき天下取りが、国土の一掃的な征服を期したことまでもが、このような位相のわきまえによって
全否定されたりすることはない。これも「位相すらよくわきまえたなら、許されないこと、できないこと
など何もない」という法則に根ざしており、やはり最大の問題は位相感覚の欠如に集約されるのだといえる。
「普天の下、王土に非ざるは莫く、率土の浜、王臣に非ざるは莫し」
「天下全土全てに至るまで、王の土地でない土地はなく、偏狭の土地の民に至るまで、
王の臣下でないものはない。(王道の基本理念。覇道や選民志向はこれに反することで地の利を慕う)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・北山之什・北山より)
あればこそ、泰平社会の大名諸侯などにはありえない程もの巨万の富に与れることが多々あった。
権力者が責任ある封土の統治をも無視して、ただひたすら土地利権の収奪を目指したところでこそ
人として最大級の富裕が手に入れられるとすら言え、20世紀におけるアメリカの富豪の栄華なぞも、
「北米大陸中部」という土地の利を寡占することによってこそ成し得たものだといえるわけだが、
それは同時に、土地を収益対象ではなく堅実な生活の場としている庶民たちに極度の疲弊を強いるという
弊害をも招いてしまうことなわけで、それを常なることとするのではやはり致命的な破滅を招くことになる。
王侯大名も当然領土を所有するが、それは完全に領土の保全を目的としたものであるべきで、
地の利を自分たち自身が私有しての富裕に与るためなどであってはならない。地の利は純粋に民間人の
消費物としてやるべきで、その代わりに民間人のトップダウンな統制を徹底するようにもする。
それが実現されるのが泰平統治の常道というもので、公権力者までもが地の利への野望などを抱いたり
するのは非常である。これもまた一つの位相のわきまえであり、乱世に武王や劉邦や信長や秀吉や家康の
ごとき天下取りが、国土の一掃的な征服を期したことまでもが、このような位相のわきまえによって
全否定されたりすることはない。これも「位相すらよくわきまえたなら、許されないこと、できないこと
など何もない」という法則に根ざしており、やはり最大の問題は位相感覚の欠如に集約されるのだといえる。
「普天の下、王土に非ざるは莫く、率土の浜、王臣に非ざるは莫し」
「天下全土全てに至るまで、王の土地でない土地はなく、偏狭の土地の民に至るまで、
王の臣下でないものはない。(王道の基本理念。覇道や選民志向はこれに反することで地の利を慕う)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・北山之什・北山より)
「三十年の通を以ってすれば、凶旱水溢有ると雖も、民に菜色無し。
然る後に天子の食するときは、日に挙ぐるに楽を以ってする(既出)」
「三十年分の国の収支を通算して毎年の予算をも決めるのであれば、たとえ旱魃や洪水が起ころうとも
民が飢え渇くことはない。それほどにも治世が成功して後には、天子も日々の宴食に舞楽を呼びもする」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・王制第五より)
国家や帝国が全国全土の公益を期して長期計画的な仁政を執り行う場合と、
個人や私企業などが長期的な私益の管理に務めて行く場合とでも、位相の食い違いが生ずる。
前者は真に人々にとっての最大級の福利厚生を実現する試みとなる一方、
後者はむしろ天下の回り物であるべき富を滞留させることによる困窮を招くこととなる。
利益を貯め込んでいる個人や企業以外の人間が平常以上の困窮に見舞われるのはもちろんのこと、
富を退蔵している私人たち自身の、世の中全体の破滅に巻き込まれての困窮までもが避けられなくなる。
神祇祭祀を奉っての加護を請うたところでこの法則が逆転するようなことは決してなく、
天下国家の公益のための仁政に神護を乞うたなら、その経験さによって福利厚生のより一層の増進にも
与れたりする一方、私人による富の退蔵への神護などを乞うた所で、破綻に至る道程をさらに惨劇化
させてしまうようなことにしかならない。何よりもわきまえるべきなのは、この公益の普遍性と私益の
脆弱性でこそあり、神の加護を乞いすらすればどんな利益でも守られる一方、神の加護に与れなければ
微塵の利益も守られないなどといったようなカルトの教条であったりすることは当然ないのである。
ということはつまり、天下国家の公益の普遍性をも上回る普遍性を具えた神などは、いないということである。
言い方を変えれば、天下国家級の公益を司る日月星辰のごとき大局的な宇宙法則をありのままに模した
神こそは、最も普遍的な存在性を持つ神であるともいえ、中でも、人間社会を含む地球界に対して最大級の
物理的影響をもたらしているのが太陽だから、太陽神こそは人間にとって最も普遍的な神であるともいえる。
然る後に天子の食するときは、日に挙ぐるに楽を以ってする(既出)」
「三十年分の国の収支を通算して毎年の予算をも決めるのであれば、たとえ旱魃や洪水が起ころうとも
民が飢え渇くことはない。それほどにも治世が成功して後には、天子も日々の宴食に舞楽を呼びもする」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・王制第五より)
国家や帝国が全国全土の公益を期して長期計画的な仁政を執り行う場合と、
個人や私企業などが長期的な私益の管理に務めて行く場合とでも、位相の食い違いが生ずる。
前者は真に人々にとっての最大級の福利厚生を実現する試みとなる一方、
後者はむしろ天下の回り物であるべき富を滞留させることによる困窮を招くこととなる。
利益を貯め込んでいる個人や企業以外の人間が平常以上の困窮に見舞われるのはもちろんのこと、
富を退蔵している私人たち自身の、世の中全体の破滅に巻き込まれての困窮までもが避けられなくなる。
神祇祭祀を奉っての加護を請うたところでこの法則が逆転するようなことは決してなく、
天下国家の公益のための仁政に神護を乞うたなら、その経験さによって福利厚生のより一層の増進にも
与れたりする一方、私人による富の退蔵への神護などを乞うた所で、破綻に至る道程をさらに惨劇化
させてしまうようなことにしかならない。何よりもわきまえるべきなのは、この公益の普遍性と私益の
脆弱性でこそあり、神の加護を乞いすらすればどんな利益でも守られる一方、神の加護に与れなければ
微塵の利益も守られないなどといったようなカルトの教条であったりすることは当然ないのである。
ということはつまり、天下国家の公益の普遍性をも上回る普遍性を具えた神などは、いないということである。
言い方を変えれば、天下国家級の公益を司る日月星辰のごとき大局的な宇宙法則をありのままに模した
神こそは、最も普遍的な存在性を持つ神であるともいえ、中でも、人間社会を含む地球界に対して最大級の
物理的影響をもたらしているのが太陽だから、太陽神こそは人間にとって最も普遍的な神であるともいえる。
太陽神以上に超越的な神というものを想定してみたところで、それが人間にとって最大級の普遍性を持つ
ということもない。太陽よりも大きな恒星なども太陽系外にはいくらでもあるが、それらの恒星を神に
見立てて崇め立たりしてみたところで、太陽系第三惑星であるこの地球に与えている物理的な影響などは
微々たるものだから、それを崇め立てることによって外的な利益などがもたらされることなどを期待
できないのはもちろんのこと、神を崇める自らの真摯さが養われて、諸々の事業を真剣に務めて行く
ようになることすら期待は出来ない。だから、敬神からなる修己大成ということもまた期待出来はしない。
それと同じように、この世界この宇宙を全く超越する形而上神などを想定して崇めたりしてみた所で、
そのような神がこの世界に与えている影響などは皆無だから、実際的な神からの加護なども期待できないし、
神を敬うことによる修身やそれに基づく健全な成功などを期待することも出来ない。このあたりに、
神を信じて敬うということを大概にすべき領域というものがあり、そのような無益な領域での信仰に
溺れるぐらいなら、信教などとは無縁な所での自助努力に努めていたほうがまだよい。せいぜい、太陽神
程度には実相に根ざしている神への崇敬によって事業の成功などを願い、自らも真摯であるように努める
ところまでが、神格信仰というものがプラスマイナスゼロ以上の好影響をもたらせる限度になっている。
「盛徳大業至れるかな。富有之れを大業と謂い、日新之れを盛徳と謂う。(略)法象は天地より大なるは莫く、
変通は四時よりも大なるは莫く、縣象の著明なるは日月より大なるは莫く、崇高は富貴よりも大なるは莫し」
「道理こそは、徳の盛んにして業の大いなる最たるものである。道理に根ざせば自然と大いなる富に与れる、
これこそは最も大いなる業である。そして日々何もかもが新たに成長して行く、これが得の盛んなる姿である。
人間の与る法則で天地よりも大いなるものはなく、現象の転変について四季よりも大いなるものはなく、甚だ
明らかなものとして日月に優るものはなく、崇高であるものとして天子が富貴であることに優るものはない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・繋辞上伝より)
ということもない。太陽よりも大きな恒星なども太陽系外にはいくらでもあるが、それらの恒星を神に
見立てて崇め立たりしてみたところで、太陽系第三惑星であるこの地球に与えている物理的な影響などは
微々たるものだから、それを崇め立てることによって外的な利益などがもたらされることなどを期待
できないのはもちろんのこと、神を崇める自らの真摯さが養われて、諸々の事業を真剣に務めて行く
ようになることすら期待は出来ない。だから、敬神からなる修己大成ということもまた期待出来はしない。
それと同じように、この世界この宇宙を全く超越する形而上神などを想定して崇めたりしてみた所で、
そのような神がこの世界に与えている影響などは皆無だから、実際的な神からの加護なども期待できないし、
神を敬うことによる修身やそれに基づく健全な成功などを期待することも出来ない。このあたりに、
神を信じて敬うということを大概にすべき領域というものがあり、そのような無益な領域での信仰に
溺れるぐらいなら、信教などとは無縁な所での自助努力に努めていたほうがまだよい。せいぜい、太陽神
程度には実相に根ざしている神への崇敬によって事業の成功などを願い、自らも真摯であるように努める
ところまでが、神格信仰というものがプラスマイナスゼロ以上の好影響をもたらせる限度になっている。
「盛徳大業至れるかな。富有之れを大業と謂い、日新之れを盛徳と謂う。(略)法象は天地より大なるは莫く、
変通は四時よりも大なるは莫く、縣象の著明なるは日月より大なるは莫く、崇高は富貴よりも大なるは莫し」
「道理こそは、徳の盛んにして業の大いなる最たるものである。道理に根ざせば自然と大いなる富に与れる、
これこそは最も大いなる業である。そして日々何もかもが新たに成長して行く、これが得の盛んなる姿である。
人間の与る法則で天地よりも大いなるものはなく、現象の転変について四季よりも大いなるものはなく、甚だ
明らかなものとして日月に優るものはなく、崇高であるものとして天子が富貴であることに優るものはない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・繋辞上伝より)
天下において、人々が際限のない富の奪い合いに興じているような状態であるのなら、
人間関係において「利害反するあり(韓非子)」という状態が常套化してしまうことともなる。
他人の富をくすねて自分が裕福になるということがあるのだから、これは当然のことである。
そしてそのような事態が深刻化すれば、富めるものと富まざるものとの格差もまた激化してしまい、
最悪の場合には富まざるものの側に餓死するようなものすらもが頻発するようになる。
そのような状態での勝ちや負けにこだわり続けるのならば、一時は富裕を謳歌していたものが
一転してジリ貧に見舞われたり、その逆となったりといった逆転現象もまた生じたりするものだ。
だからといって貧困者の側に回されていたものが、逆転勝利によって膨大な富をせしめることでの
名誉挽回を目指したりするのでは、結局の所、品性の部分ではかつての怨敵とも同じ穴の狢となってしまう。
だから、奪い合いが常套化してしまっているような世相での勝利などではなく、そもそも奪い合い
などが常套化していない世相の呼び込みこそを企図したとする。したらば、富めるものがそんなに
極端に富むようなこともなくなる代わりに、極端に困窮したり飢餓に見舞われたりする人間もいなくなる。
奪い合いによって不正に取り回されていたことからなる富の目減りが抑制されることともなるために、
天下万人が所有する富の平均値は、奪い合いが常套化している状態の平均値よりも相当に増加することともなる。
だからたとえば、今の地球社会における極端な富の偏在を是正したからといって、天下万人の資産の
平均値が、いま世界平均とほぼ同等の状態にあるインドネシアやフィリピンの平均値並みになるなんて
こともなく、それよりはずっと多くの富を天下全土の誰しもが所有できるようにもなるはずなのである。
これは季氏第十六・一にも「(富の)寡なきを患えずして均しからざるを患う。〜均しければ貧しきこと無し」
という風に確言されていることであり、別に共産主義者などが言いだしっぺの幻想だったりするわけでもない。
人間関係において「利害反するあり(韓非子)」という状態が常套化してしまうことともなる。
他人の富をくすねて自分が裕福になるということがあるのだから、これは当然のことである。
そしてそのような事態が深刻化すれば、富めるものと富まざるものとの格差もまた激化してしまい、
最悪の場合には富まざるものの側に餓死するようなものすらもが頻発するようになる。
そのような状態での勝ちや負けにこだわり続けるのならば、一時は富裕を謳歌していたものが
一転してジリ貧に見舞われたり、その逆となったりといった逆転現象もまた生じたりするものだ。
だからといって貧困者の側に回されていたものが、逆転勝利によって膨大な富をせしめることでの
名誉挽回を目指したりするのでは、結局の所、品性の部分ではかつての怨敵とも同じ穴の狢となってしまう。
だから、奪い合いが常套化してしまっているような世相での勝利などではなく、そもそも奪い合い
などが常套化していない世相の呼び込みこそを企図したとする。したらば、富めるものがそんなに
極端に富むようなこともなくなる代わりに、極端に困窮したり飢餓に見舞われたりする人間もいなくなる。
奪い合いによって不正に取り回されていたことからなる富の目減りが抑制されることともなるために、
天下万人が所有する富の平均値は、奪い合いが常套化している状態の平均値よりも相当に増加することともなる。
だからたとえば、今の地球社会における極端な富の偏在を是正したからといって、天下万人の資産の
平均値が、いま世界平均とほぼ同等の状態にあるインドネシアやフィリピンの平均値並みになるなんて
こともなく、それよりはずっと多くの富を天下全土の誰しもが所有できるようにもなるはずなのである。
これは季氏第十六・一にも「(富の)寡なきを患えずして均しからざるを患う。〜均しければ貧しきこと無し」
という風に確言されていることであり、別に共産主義者などが言いだしっぺの幻想だったりするわけでもない。
徳治によって富の遍在を是正することと、共産化によって富の偏在を是正することとでは、その手法が
決定的に異なる。徳治では士農工商その他の生業の格付けを正すことで、商人階級による富の貪りを
厳重な差別下に置く一方、共産化では逆に産業階級が国を乗っ取って直接政治を執り行うことが企図される。
物価の変動なども完全に固定化して、世に出回る物品全てを半公有物ともしてしまう、
実際にそれを実施した共産圏はといえば、>>78-79で孟子が予言した通りの産業の停滞を招き、
製品の品質はがた落ちして、人々も勤労意欲を損なわせ、自他の所有物にろくな
区別も付けられなくなる、著しい公共マナーの欠如という問題をも来たした。
一方で、武士によるトップダウンな民衆の統制によって、富の偏在にも適度な抑制をかけていた
江戸時代の日本はといえば、だからといって人々の勤労意欲が損なわれるようなこともなく、
武士の勤勉さを見習っての人々の民度の向上までもが実現され、商人階級や地主階級も服装や生活規範などの
制限を受けながらも、それなりの商業活動によって、庶民を痛め付けない程度の富裕に与ることができていた。
道徳統治と共産化とで、目指すところ(富の偏在の是正)は似ているけれども、それぞれを実施しようとする
人間の世の中の捉え方や倫理観からして位相がひっくり返っており、故にこそ目的のための手段もまた相違している。
徳治主義には修己治人のわきまえがある一方で、共産主義には全くそれがない。徳治主義は士人階級と資本家階級を
別物として捉えている一方、共産主義は両者を同一不可分のものとして捉えている。総合的に、徳治主義のほうが
共産主義よりも世の中の捉え方や倫理観が秀逸であり、故にこそ、それによって実現される世の中もまた、共産主義が
実現する世の中において来たしてしまうような諸々の問題を来たさない。徳治主義のほうが共産主義よりも遥かにその
発祥が古いから、旧態依然としたものとして捉えてしまいがちにもなるが、ここは、若造のほうが青すぎた事案だといえる
決定的に異なる。徳治では士農工商その他の生業の格付けを正すことで、商人階級による富の貪りを
厳重な差別下に置く一方、共産化では逆に産業階級が国を乗っ取って直接政治を執り行うことが企図される。
物価の変動なども完全に固定化して、世に出回る物品全てを半公有物ともしてしまう、
実際にそれを実施した共産圏はといえば、>>78-79で孟子が予言した通りの産業の停滞を招き、
製品の品質はがた落ちして、人々も勤労意欲を損なわせ、自他の所有物にろくな
区別も付けられなくなる、著しい公共マナーの欠如という問題をも来たした。
一方で、武士によるトップダウンな民衆の統制によって、富の偏在にも適度な抑制をかけていた
江戸時代の日本はといえば、だからといって人々の勤労意欲が損なわれるようなこともなく、
武士の勤勉さを見習っての人々の民度の向上までもが実現され、商人階級や地主階級も服装や生活規範などの
制限を受けながらも、それなりの商業活動によって、庶民を痛め付けない程度の富裕に与ることができていた。
道徳統治と共産化とで、目指すところ(富の偏在の是正)は似ているけれども、それぞれを実施しようとする
人間の世の中の捉え方や倫理観からして位相がひっくり返っており、故にこそ目的のための手段もまた相違している。
徳治主義には修己治人のわきまえがある一方で、共産主義には全くそれがない。徳治主義は士人階級と資本家階級を
別物として捉えている一方、共産主義は両者を同一不可分のものとして捉えている。総合的に、徳治主義のほうが
共産主義よりも世の中の捉え方や倫理観が秀逸であり、故にこそ、それによって実現される世の中もまた、共産主義が
実現する世の中において来たしてしまうような諸々の問題を来たさない。徳治主義のほうが共産主義よりも遥かにその
発祥が古いから、旧態依然としたものとして捉えてしまいがちにもなるが、ここは、若造のほうが青すぎた事案だといえる
「孚有りて攣如たり、富其の隣りと以にす。孚有りて攣如たりとは、独り富まんとせざるなり」
「誠意と共に協力的であり、富も誰しもと分け合おうという心持ちでいる。誠意があって協力的だから、
自分独りで富もうなどという気持ちもない。(誠意があるのなら、始めから富を独占しようなどという気は
起こらない。してみれば、私利の追求が生業である商売人は必ず、内面に不誠実を抱えているのでもある)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・小畜・九五‐象伝)
「誠意と共に協力的であり、富も誰しもと分け合おうという心持ちでいる。誠意があって協力的だから、
自分独りで富もうなどという気持ちもない。(誠意があるのなら、始めから富を独占しようなどという気は
起こらない。してみれば、私利の追求が生業である商売人は必ず、内面に不誠実を抱えているのでもある)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・小畜・九五‐象伝)
何かを信じきって全く疑わないというのは、それ自体は愚かなことである。
愚かであると諾いつつ阿弥陀仏に帰依する念仏信仰などは、それはそれで相が狂ってはいない。
何ものかを信じて疑わないということそれ自体が「神聖なこと」のように見なされて、
信じて疑わないものがあるが故に、そのような拠り所を持たない相手よりも自分のほうが
偉いなどと考えるようになるのでは、それ自体が凶相となり、何も信じないでいることは愚か、
愚かなことと知りつつ信仰に没頭する場合以上にも劣悪なザマとなる。
何か信じてやまぬ拠り所があればこそ、そんなものを持たない人間よりも偉いというような
間違った思い込みが方々で通用してしまっているからこそ、「宗教」という枠組みがそれなりの
権威性を以って取り扱われてしまってもいる。公けに「カルト」と指定されている新興宗教などの
扱いはそれなりに眉唾物扱いだったりもするが、「なによりもまず、信教は信教であるだけで貴い」
というような通念が未だに一般的であるために、日本国憲法にも明記されている「信教の自由」
などといった理念が、イヤイヤながらであっても黙認されてしまっていたりするのだ。
今でこそ仏門も「仏教」としての扱いが定着しているけれども、天台真言律禅のごとき自力作善の聖道門は
本来「学門」としての立場を持ち合わせていたわけで、昔の日本などでも、仏門での学門修養が行き届いて
いればこそ、中国などのように科挙試験の合格を目指してのガリ勉競争を激化させたりする必要もなかった。
その日本が廃仏毀釈によって仏門での学門修養を絶ち、大学での勉強が主要教育ともされるようになって後は、
中国などと同じ拙いガリ勉競争の様相を呈し始めることともなった。座禅や托鉢行脚などの実践的な修養が伴わない
から、勉強にかけてばかりガリガリでいるしかない。そのせいで学問自体が「過ぎたるはなお及ばざるが如し」
の様相を呈してしまい、複雑怪奇で晦渋であるばかりでろくな実用性もないという事態に陥ってもしまった。
愚かであると諾いつつ阿弥陀仏に帰依する念仏信仰などは、それはそれで相が狂ってはいない。
何ものかを信じて疑わないということそれ自体が「神聖なこと」のように見なされて、
信じて疑わないものがあるが故に、そのような拠り所を持たない相手よりも自分のほうが
偉いなどと考えるようになるのでは、それ自体が凶相となり、何も信じないでいることは愚か、
愚かなことと知りつつ信仰に没頭する場合以上にも劣悪なザマとなる。
何か信じてやまぬ拠り所があればこそ、そんなものを持たない人間よりも偉いというような
間違った思い込みが方々で通用してしまっているからこそ、「宗教」という枠組みがそれなりの
権威性を以って取り扱われてしまってもいる。公けに「カルト」と指定されている新興宗教などの
扱いはそれなりに眉唾物扱いだったりもするが、「なによりもまず、信教は信教であるだけで貴い」
というような通念が未だに一般的であるために、日本国憲法にも明記されている「信教の自由」
などといった理念が、イヤイヤながらであっても黙認されてしまっていたりするのだ。
今でこそ仏門も「仏教」としての扱いが定着しているけれども、天台真言律禅のごとき自力作善の聖道門は
本来「学門」としての立場を持ち合わせていたわけで、昔の日本などでも、仏門での学門修養が行き届いて
いればこそ、中国などのように科挙試験の合格を目指してのガリ勉競争を激化させたりする必要もなかった。
その日本が廃仏毀釈によって仏門での学門修養を絶ち、大学での勉強が主要教育ともされるようになって後は、
中国などと同じ拙いガリ勉競争の様相を呈し始めることともなった。座禅や托鉢行脚などの実践的な修養が伴わない
から、勉強にかけてばかりガリガリでいるしかない。そのせいで学問自体が「過ぎたるはなお及ばざるが如し」
の様相を呈してしまい、複雑怪奇で晦渋であるばかりでろくな実用性もないという事態に陥ってもしまった。
それなりの実践修行が伴う仏門における学問こそは、そのような問題をも呈さなかったわけで、むしろ
仏門における学問こそは、今の大学などでの学問以上にも「最適」でいられるところがあったのだった。
(ちょうど実践修行が、情報処理を行うコンピュータにとってのデフラグのような役割を果たしていた)
宗教的には、日本も「仏教圏」とされるけれども、実情をいえば、日本の仏門は今の大学並みかそれ以上にも
「権威ある学門」としての立場を担っていた。宗教としての信仰に専らでいたのは浄土門などの一部の宗派
のみであり、むしろ寺といえば学門道場としての役割のほうが大きかった。仏門が信仰の場以上にも学門の場
として重要な役割を担っていた以上、日本は昔から信仰以上にも学問を重んずる国でもあったと言え、信仰一辺倒の
激化などは、僧兵や一向一揆や日蓮カルトなどへの制圧が試みられていたことからも、忌避されていたことがわかる。
そういった、日本の伝統的な教学のあり方こそは見習うべきものでもある。信教を信教だからといって
保護するようなことはしない一方で、学問振興のための絶妙なエッセンスとして信教を用いもする。
これが信教一辺倒なアブラハム教圏のあり方などよりはもちろんのこと、信教に対する冷遇や弾圧の過ぎる
中国などよりも優れている。今の日本ではなく、昔からの日本の教学に対する姿勢こそが模範的なのであり、
それは今の日本人自身もまた復興を心がけていくことによってのみ、また取り戻せることがあるものである。
「疑を稽する。択んで卜筮の人を建立する」
「疑わしきことにまでよく配慮を利かして精査する。そのためには卜筮者を厳選して擁立しもする。
(オッカムの剃刀的な配慮の怠惰を非としていたから、占筮にまで頼る所があったのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・洪範より)
仏門における学問こそは、今の大学などでの学問以上にも「最適」でいられるところがあったのだった。
(ちょうど実践修行が、情報処理を行うコンピュータにとってのデフラグのような役割を果たしていた)
宗教的には、日本も「仏教圏」とされるけれども、実情をいえば、日本の仏門は今の大学並みかそれ以上にも
「権威ある学門」としての立場を担っていた。宗教としての信仰に専らでいたのは浄土門などの一部の宗派
のみであり、むしろ寺といえば学門道場としての役割のほうが大きかった。仏門が信仰の場以上にも学門の場
として重要な役割を担っていた以上、日本は昔から信仰以上にも学問を重んずる国でもあったと言え、信仰一辺倒の
激化などは、僧兵や一向一揆や日蓮カルトなどへの制圧が試みられていたことからも、忌避されていたことがわかる。
そういった、日本の伝統的な教学のあり方こそは見習うべきものでもある。信教を信教だからといって
保護するようなことはしない一方で、学問振興のための絶妙なエッセンスとして信教を用いもする。
これが信教一辺倒なアブラハム教圏のあり方などよりはもちろんのこと、信教に対する冷遇や弾圧の過ぎる
中国などよりも優れている。今の日本ではなく、昔からの日本の教学に対する姿勢こそが模範的なのであり、
それは今の日本人自身もまた復興を心がけていくことによってのみ、また取り戻せることがあるものである。
「疑を稽する。択んで卜筮の人を建立する」
「疑わしきことにまでよく配慮を利かして精査する。そのためには卜筮者を厳選して擁立しもする。
(オッカムの剃刀的な配慮の怠惰を非としていたから、占筮にまで頼る所があったのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・洪範より)
「室を労とする靡く、夙に興きて夜に寐ぬるに、朝有る靡し」
「家庭での仕事の苦労を苦労ともせず、朝から晩まで家事仕事を欠かしたこともない。
(人の苦労を全否定するようなら、家族関係一つうまく行くこともありはしない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・衛風・氓より)
「家庭での仕事の苦労を苦労ともせず、朝から晩まで家事仕事を欠かしたこともない。
(人の苦労を全否定するようなら、家族関係一つうまく行くこともありはしない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・衛風・氓より)
 人は、自らが努力したぶんだけ、僥倖抜きの福徳に与れる。
人は、自らが努力したぶんだけ、僥倖抜きの福徳に与れる。 そしてその僥倖抜きの福徳こそは、真に普遍的な福徳である。
「棚からぼた餅」的な僥倖に基づく慶福こそは脆弱なものであり、
そんなものを期待し過ぎずに、着実な自助努力に基づく慶福を
得ようとすることこそが、人として最善を尽くすあり方ともなる。
ただ、人々を惑わせやすいのが、「僥倖を得るための努力」というものだ。
西洋文化文明に基づく発明だとか学術的発見だとかいったものが概ねその部類で、
古くはピタゴラスによる三平方の定理の発見から、エジソンによる電球の発明や
ライト兄弟による飛行機の発明、そして複数の計算機学者によるコンピュータの発明など、
それなりに研究開発の努力を積んだ結果として、発明や発見に至ったものとなっている。
僥倖を得るための努力もまた、決して絶対に報われないわけでもない。
報われたときには、着実な福徳を企図している場合以上もの「一発当ててウハウハ」
すらもが実現できたりもするわけだが、残念ながら、僥倖を得るための努力が報われる
確率はきわめて低く、その低率な成功を得るためにも莫大な資本投入を必要とする。
19世紀後半から20世紀中盤にかけて、アメリカ人たちが膨大な数の文明の利器を発明することが
できたのも、当時のアメリカが資本主義国として未曾有の規模にまで発展していたからで、
その代償は資本主義後進国の極度の貧窮や二度の世界大戦、そして現代に至っての
リバウンド状態の経済破綻などの形で確実に業報されて来ているのである。
「小道といえども必ず観るべきものあり。遠きを致すには恐らくは泥まん(子張第十九・四)」
「君子の道は闇然として日に章らかに、小人の道は的然として日に亡ぶ(中庸・三十三)」
小道といえども見るべきところが全くないわけではない、僥倖を求めての尽力も多少は報われる
ことがあるが、やっぱり総合的に授かれる福徳の度合いで、着実な常道の邁進に優ることはない。
着実な常道の邁進によって得られる福徳こそは禍い以上の福ともなる一方で、僥倖に与ろうと
した結果としての福にはむしろ、それ以上に甚大な禍いが付き物となるようにもなっている。
僥倖を得るに際して、福以上の禍いをもたらしてしまったからこそ、小道での尽力者が深く
感謝されたりすることもない。漢帝国も、秦帝国が築き上げた文明インフラを引き継ぐ形で
尊敬に値する長期の泰平統治を実現したわけだが、秦帝国の権力者たちはといえば、自分
たちが放辟邪侈によって人々を痛め付ける過程で文明インフラを新造して行ったわけだから、
全く感謝や尊敬の対象にされることもなく、後々に迫害や差別の対象となるばかりとなった。
これも一つの文明社会の宿命であるといえ、漢帝国成立後にも項羽の親戚家は生きながらえた
ものの始皇帝の家は中国で滅ぼされたり(日本に残党が逃げ込んだりはしていた)、徳川幕府
成立後に織田信長の子孫は生きながらえたものの、豊臣秀吉の子孫は滅ぼされたりといった風に、
文明社会の黎明期の立役者となった連中同士でもまた、多少の運命の枝分かれが生ずることとなる。
全てが全て滅ぼしつくされたりまではしないのは、小道ながらに見るべきところも多少はあったからだ。
「君子の道は闇然として日に章らかに、小人の道は的然として日に亡ぶ(中庸・三十三)」
小道といえども見るべきところが全くないわけではない、僥倖を求めての尽力も多少は報われる
ことがあるが、やっぱり総合的に授かれる福徳の度合いで、着実な常道の邁進に優ることはない。
着実な常道の邁進によって得られる福徳こそは禍い以上の福ともなる一方で、僥倖に与ろうと
した結果としての福にはむしろ、それ以上に甚大な禍いが付き物となるようにもなっている。
僥倖を得るに際して、福以上の禍いをもたらしてしまったからこそ、小道での尽力者が深く
感謝されたりすることもない。漢帝国も、秦帝国が築き上げた文明インフラを引き継ぐ形で
尊敬に値する長期の泰平統治を実現したわけだが、秦帝国の権力者たちはといえば、自分
たちが放辟邪侈によって人々を痛め付ける過程で文明インフラを新造して行ったわけだから、
全く感謝や尊敬の対象にされることもなく、後々に迫害や差別の対象となるばかりとなった。
これも一つの文明社会の宿命であるといえ、漢帝国成立後にも項羽の親戚家は生きながらえた
ものの始皇帝の家は中国で滅ぼされたり(日本に残党が逃げ込んだりはしていた)、徳川幕府
成立後に織田信長の子孫は生きながらえたものの、豊臣秀吉の子孫は滅ぼされたりといった風に、
文明社会の黎明期の立役者となった連中同士でもまた、多少の運命の枝分かれが生ずることとなる。
全てが全て滅ぼしつくされたりまではしないのは、小道ながらに見るべきところも多少はあったからだ。
 若いうちには御飯茶碗何倍分もの飯を平気で平らげていたような人間でも、年取ると
若いうちには御飯茶碗何倍分もの飯を平気で平らげていたような人間でも、年取ると 胃腸が弱り、唾液の量も減って、そんなに穀類を大量に食べたりもできないようになる。
代わりに甘いものや高級魚や肉などの、高カロリーなものを少量採って栄養を補給するなど
すればよく、そのために食費がかさむぐらいのことは大目に見てやるべきだともいえる。
しかし特に、肉や魚はその生産量が限られており、万人が好きなだけ食したりしているようではあっという間に
枯渇してしまうことにもなる。(それを無理に克服しようとしてもBSEや鳥獣インフルエンザなどの問題が生ずる)
そのため、穀類で十分な栄養が採れる若者の内はなるべく穀類で栄養を採るようにし、年を取ってなかなか穀類が
食べにくくなってからは肉や魚を旺盛に食べるようにするなどの、世代による食の住み分けを講ずるべきだといえる。
しかれば、老若男女にかかわらず誰しもが食べたいものを食べて食べさせるだなんていう、
「共食」の論理などを決して通用させるべきではないわけで、世の中における食習慣一つとっても、
立場や身分の違いに基づく差別を講じることのほうがより適切であることが分かるのである。
食い物に限らず、「自分もやりたいことばかりやって、人にもやりたいことばかりさせる」という、やりたい放題の
論理が通用しないことはいくらでもある。そりゃあ、それでも通用するなら、それが一番嬉しいにも違いないが、
世の中の大局構造というのは、誰しもの欲望を無制限に叶え続けていられるようには決してできていないから、
どこかで譲り合いを講ずるようにもしていかなければ、必ず世の中のほうが立ち行かなくなってしまうのである。
世の中の大局構造というものを実感的に把握することができないから、女子供や小人男はできる限りやりたい放題で
いようとする。大局を実感的に把握できる君子の大丈夫であろうとも、出家者でもない限りはあらゆる欲望を抑制し
尽くすなんていうことまではしないが、「欲はほしいままにすべからず」ということを常日ごろからのわきまえとし、
何もかもを欲望のあるがままにさせようなどとするような最悪の放逸心にだけは決して溺れないでいようとはする。
そのために、君子の大丈夫は「世の中を平穏に取り仕切る」という大欲こそを、他の如何なる欲望よりも優先させる。
それは別に欲しやすいものではないが、欲そうと思えば欲することもできないといった程度のものであり、
それを欲することこそを他のあらゆる欲望よりも優先させていくこと自体が、一種の精進ともなるものである。
そして、その「世の中を平穏に取り仕切る」という欲望対象もまた、女子供や小人男にまで欲することを強制
できるもんじゃない。世の中の大局構造を実感的に把握することもできない身の程である以上は、そんなことを
心の底から欲することも決して期待できたもんじゃないから、天下の泰平統治への邁進も、あくまで自分たち
大丈夫にとっての領分であるとして、女子供や小人男にまでそれに対する共感などを強制したりすべきでもない。
それで結局、上記のような諸々の社会規範上の住み分けを講ずるためには、君臣父子夫婦官民長幼といった
立場の違いに基づく序列を徹底していくべきだということにもなる。元より、古来からの儒学道徳に基づく
封建制での秩序序列というのは、上記のような住み分けこそを企図して講じられていたものなのであり、その
内実にまで立ち入って見るなら、封建制も極めて切実で罪のない正当性に即していたことが分かるのである。
(士産階級の分離も疎かだった西洋の封建制などにまでこの分析が当てはまるわけでは決してないが)
「嗚呼、惟れ天、民を生じて欲有り。主無ければ乃ち乱る」
「ああ、天は民たちを欲望の塊として生み出された。そのせいで、
主君を立てないことには必ず乱れるようになってしまってもいる」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・仲虺之誥より)
それは別に欲しやすいものではないが、欲そうと思えば欲することもできないといった程度のものであり、
それを欲することこそを他のあらゆる欲望よりも優先させていくこと自体が、一種の精進ともなるものである。
そして、その「世の中を平穏に取り仕切る」という欲望対象もまた、女子供や小人男にまで欲することを強制
できるもんじゃない。世の中の大局構造を実感的に把握することもできない身の程である以上は、そんなことを
心の底から欲することも決して期待できたもんじゃないから、天下の泰平統治への邁進も、あくまで自分たち
大丈夫にとっての領分であるとして、女子供や小人男にまでそれに対する共感などを強制したりすべきでもない。
それで結局、上記のような諸々の社会規範上の住み分けを講ずるためには、君臣父子夫婦官民長幼といった
立場の違いに基づく序列を徹底していくべきだということにもなる。元より、古来からの儒学道徳に基づく
封建制での秩序序列というのは、上記のような住み分けこそを企図して講じられていたものなのであり、その
内実にまで立ち入って見るなら、封建制も極めて切実で罪のない正当性に即していたことが分かるのである。
(士産階級の分離も疎かだった西洋の封建制などにまでこの分析が当てはまるわけでは決してないが)
「嗚呼、惟れ天、民を生じて欲有り。主無ければ乃ち乱る」
「ああ、天は民たちを欲望の塊として生み出された。そのせいで、
主君を立てないことには必ず乱れるようになってしまってもいる」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・仲虺之誥より)
儒説というものにも、ある程度は密教的な部分がある。
現代に至るまでの内で最も整備された儒学である朱子学などにおいて、
孔孟や荀子の教えを体系化したものとしての三綱五常の教えが尊ばれている。
君臣父子夫婦の序列を尊ぶという三綱の教えにも実は裏があり、「易経」の序卦伝などには
「天地ありて然る後に万物あり、万物ありて然る後に男女あり、
男女ありて然る後に夫婦あり、夫婦ありて然る後に父子あり、父子ありて然る後に君臣あり、
君臣ありて然る後に上下あり、上下ありて然る後に礼儀おくところあり」
などとある。時系列においてはむしろ男女や夫婦のほうが先に生じているわけだから、
君臣や父子の関係よりも男女や夫婦の関係のほうを尊重すべきであるかのように考えられなくもない。
実際、冒頭の創世記にアダムとイヴというツガイの原人類の物語を置いている旧約などはその考え方に
即しているわけだが、易においては、そもそも天地万物が生じた最原初の頃には上下関係など存在しない、
都市社会において君臣父子の関係などが重んじられるようになってから初めて上下関係が生じ、
その上下関係に即して礼儀礼節をわきまえる必要性もまた生じたわけだから、礼節をわきまえる
上下関係も「君臣父子夫婦」の序列であることこそが正しいとされているのである。
——以上のような論説は、表向きの儒学においてはわざわざ深く立ち入られもしないことであり、
むしろ出来上がった教説としての三綱五常のわきまえや、その実践こそがより重んじられていくものである。
上のような密教的な部分も、儒学をより深く理解する上では有用であっても、そればかりに囚われて
積極的な実践を蔑ろにしたりするのでは、世俗の学問としての儒学のあり方にも悖ることとなるから、
「高きに上らず、深きに臨まず(礼記)」で、基本は出来上がった教説の受容のほうを優先させるのである。
現代に至るまでの内で最も整備された儒学である朱子学などにおいて、
孔孟や荀子の教えを体系化したものとしての三綱五常の教えが尊ばれている。
君臣父子夫婦の序列を尊ぶという三綱の教えにも実は裏があり、「易経」の序卦伝などには
「天地ありて然る後に万物あり、万物ありて然る後に男女あり、
男女ありて然る後に夫婦あり、夫婦ありて然る後に父子あり、父子ありて然る後に君臣あり、
君臣ありて然る後に上下あり、上下ありて然る後に礼儀おくところあり」
などとある。時系列においてはむしろ男女や夫婦のほうが先に生じているわけだから、
君臣や父子の関係よりも男女や夫婦の関係のほうを尊重すべきであるかのように考えられなくもない。
実際、冒頭の創世記にアダムとイヴというツガイの原人類の物語を置いている旧約などはその考え方に
即しているわけだが、易においては、そもそも天地万物が生じた最原初の頃には上下関係など存在しない、
都市社会において君臣父子の関係などが重んじられるようになってから初めて上下関係が生じ、
その上下関係に即して礼儀礼節をわきまえる必要性もまた生じたわけだから、礼節をわきまえる
上下関係も「君臣父子夫婦」の序列であることこそが正しいとされているのである。
——以上のような論説は、表向きの儒学においてはわざわざ深く立ち入られもしないことであり、
むしろ出来上がった教説としての三綱五常のわきまえや、その実践こそがより重んじられていくものである。
上のような密教的な部分も、儒学をより深く理解する上では有用であっても、そればかりに囚われて
積極的な実践を蔑ろにしたりするのでは、世俗の学問としての儒学のあり方にも悖ることとなるから、
「高きに上らず、深きに臨まず(礼記)」で、基本は出来上がった教説の受容のほうを優先させるのである。
という風に、儒学の学理教説の内にすら、優先すべきものとそうでないものとがある。
必要なのは何もかもを知り尽くすこと以上にも、優先すべき学知とそうでない学知とをよく分別して、
優先すべき学知の積極的な受容に取り組んでいったり、そうでない学知の適切な扱いを守ったりすることである。
それを怠るのであれば、知識なんてものは享受する以上にもしないほうがマシなほどにも無益極まりないものに
すらなりかねない。異端の小知ばかりを貪り続けた挙句に、自業自得の破滅に陥るようなことにもなりかねない。
ここではかなり、実践に移す上では深入りに過ぎるような、密教的な儒説も取り扱っている。それも、
儒学の実践が全く不能と化してしまっている今という時代の現状に合わせたものであり、もしもこれから
儒学の実践ぐらいは可能になって行くというのであれば、深く分析するまでもない、四書五経の文面ありのままの
教説の実践などに取り組んでいくようにすべきなのである。分析主義的な西洋文化の国内への大量流入などによって、
表向きの儒説だけではその正当性の根拠が脆弱だという文句が多々付けられてもいるものだから、密教的な儒説と、
洋学の学説や聖書教義なども照らし合わせつつ、表向きの儒学の正当性までをも厳密に実証し続けて来たのである。
そればかりであっていいわけでもないが、時宜に即して、そういうことがたまたま必要ともされたのである。
「聖謨洋洋として、嘉言孔だ彰かなり。」
「聖人の定められた則はまことに輝かしいものであり、その優れた言葉も甚だ明らかなものである。
(むしろ明らかに正善であればこそ、邪神邪人はそれを隠蔽したり無視したりしようともする)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・伊訓より)
必要なのは何もかもを知り尽くすこと以上にも、優先すべき学知とそうでない学知とをよく分別して、
優先すべき学知の積極的な受容に取り組んでいったり、そうでない学知の適切な扱いを守ったりすることである。
それを怠るのであれば、知識なんてものは享受する以上にもしないほうがマシなほどにも無益極まりないものに
すらなりかねない。異端の小知ばかりを貪り続けた挙句に、自業自得の破滅に陥るようなことにもなりかねない。
ここではかなり、実践に移す上では深入りに過ぎるような、密教的な儒説も取り扱っている。それも、
儒学の実践が全く不能と化してしまっている今という時代の現状に合わせたものであり、もしもこれから
儒学の実践ぐらいは可能になって行くというのであれば、深く分析するまでもない、四書五経の文面ありのままの
教説の実践などに取り組んでいくようにすべきなのである。分析主義的な西洋文化の国内への大量流入などによって、
表向きの儒説だけではその正当性の根拠が脆弱だという文句が多々付けられてもいるものだから、密教的な儒説と、
洋学の学説や聖書教義なども照らし合わせつつ、表向きの儒学の正当性までをも厳密に実証し続けて来たのである。
そればかりであっていいわけでもないが、時宜に即して、そういうことがたまたま必要ともされたのである。
「聖謨洋洋として、嘉言孔だ彰かなり。」
「聖人の定められた則はまことに輝かしいものであり、その優れた言葉も甚だ明らかなものである。
(むしろ明らかに正善であればこそ、邪神邪人はそれを隠蔽したり無視したりしようともする)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・伊訓より)
自力作善が本旨である密教や禅などでも、不動明王なり遍照金剛(弘法大師)なり
釈迦牟尼仏なりの尊格を補助的な信仰の対象とし、それによって精進修行の大成を図ることがある。
そもそも信教を本職としない為政者なども、祖神への崇敬などによって自らが善政を心がけることができる。
そういった信仰や崇敬の用い方のほうが優良であり、信仰一辺倒の他力本願となるのは劣悪である。
浄土門などはそれを知った上での他力本願でいるから、信者たちが思い上がりを募らせたりすることはないが、
日蓮宗とか聖書教とかは、信仰一辺倒であることこそが優良であるとすら考えているところがあるから、
信者たちが思い上がりを募らせての悪逆非道に走ったりもする、これこそは「信仰の暗黒面」だといえる。
江戸時代までの日本には、「信仰することそれ自体が尊いことである」などという認識が、
一部の日蓮教徒間などを除いて一切通用していなかったから、宗教という概念もまた意味を持たないために
始めから整備して定義されることもなかった。浄土信者なども、死への恐怖を緩和するための気休め程度に
念仏を嗜んでいたわけで、そこには悪人正機説などに基づく着実な心理的効果もあったから、
わざわざ捨て去るまでもないものとしての信仰が続けられてきたのだった。
念仏信仰が信者に付与する心理的効果は優良なものであり、純粋に死への恐怖からの解脱を促してくれる。
一方で、聖書信仰が信者に与える心理個的効果は劣悪なものであり、むしろ死への恐怖を最大級に
増幅させた挙句に、心神喪失状態に陥らせることをその正体としている。そのために、一旦聖書信仰に
耽溺してしまったような人間が信仰を取り止めると、並みの人間以上もの極度な死への恐怖に見舞われる
ことともなる。そして長年、世の中総出を挙げての聖書信仰を続けてきた西洋のような社会においては、
「信仰を取り止めれば極度の死への恐怖に見舞われる」ということがデフォルト扱いすらされることになって
しまうために、それと比べて信仰に基づく心神喪失状態がより良いもののように思えてしまったりもする。
釈迦牟尼仏なりの尊格を補助的な信仰の対象とし、それによって精進修行の大成を図ることがある。
そもそも信教を本職としない為政者なども、祖神への崇敬などによって自らが善政を心がけることができる。
そういった信仰や崇敬の用い方のほうが優良であり、信仰一辺倒の他力本願となるのは劣悪である。
浄土門などはそれを知った上での他力本願でいるから、信者たちが思い上がりを募らせたりすることはないが、
日蓮宗とか聖書教とかは、信仰一辺倒であることこそが優良であるとすら考えているところがあるから、
信者たちが思い上がりを募らせての悪逆非道に走ったりもする、これこそは「信仰の暗黒面」だといえる。
江戸時代までの日本には、「信仰することそれ自体が尊いことである」などという認識が、
一部の日蓮教徒間などを除いて一切通用していなかったから、宗教という概念もまた意味を持たないために
始めから整備して定義されることもなかった。浄土信者なども、死への恐怖を緩和するための気休め程度に
念仏を嗜んでいたわけで、そこには悪人正機説などに基づく着実な心理的効果もあったから、
わざわざ捨て去るまでもないものとしての信仰が続けられてきたのだった。
念仏信仰が信者に付与する心理的効果は優良なものであり、純粋に死への恐怖からの解脱を促してくれる。
一方で、聖書信仰が信者に与える心理個的効果は劣悪なものであり、むしろ死への恐怖を最大級に
増幅させた挙句に、心神喪失状態に陥らせることをその正体としている。そのために、一旦聖書信仰に
耽溺してしまったような人間が信仰を取り止めると、並みの人間以上もの極度な死への恐怖に見舞われる
ことともなる。そして長年、世の中総出を挙げての聖書信仰を続けてきた西洋のような社会においては、
「信仰を取り止めれば極度の死への恐怖に見舞われる」ということがデフォルト扱いすらされることになって
しまうために、それと比べて信仰に基づく心神喪失状態がより良いもののように思えてしまったりもする。
というような事情もあるために、聖書信仰のような信者に心理的な悪影響を及ぼす信仰を長年享受してきた
世の中においては、「信仰を持つことは尊い」「信仰を持たないことは卑しい」などという風にすら
思い込まれてしまうようにもなる。死への恐怖を自力作善によって克服することも、他力本願によって健全に
克服することもできなくはないのに、そもそも劣悪な信仰によって人々の死への恐怖を最大級に増幅させる
ことを定常状態としてしまっているから、世の風潮からして信仰ありきでしかあり得なくなってしまっている。
自学作善>善い信仰>無学無信>悪い信仰①というのが真如の実相だが、悪い信仰には無信仰状態を苦痛とさせる
「誘引効果」があるために、その信仰に陥ってしまったような人間に対して信仰一般>無信仰②であるような
思い違いを抱かせもする。真実である①と、思い違いである②とでは決定的に相容れないところがあるから、
悪い信仰に陥ったせいで②が真実だと思い込んでしまった人間は、致命的に真実が見えなくなってもしまう。
信仰内容の劣悪さ以前に、悪い信仰にはそういった問題点が付き物でもあるわけだから、そのような信仰の
代表格である聖書信仰の特殊な教義に立ち入るまでもなく、悪い信仰一般を控えるべきだということが言える。
とはいえやはり、聖書信仰の教条こそは、「信者を極度の恐怖に見舞わせた挙句に心神喪失状態に陥れる」という
悪い信仰の黄金比を如実に体現していることも間違いがない。聖書の教義に根ざさなくとも、同様の心理的効果を
他の邪教が信者にもたらすことはいくらでもあり得るが、結局のところは五十歩百歩であり、その効果が甚大で
あるような邪教ほど、聖書信仰の教義に近似していくことにもなるだろう。いかにも「宗教らしい宗教」ほどそうで
あるらしい場合が多いから、宗教という枠組み自体、邪教こそを保護してやるためのものだったのだとも考えられる。
邪教ではないような宗教ほど、実は「宗教」という枠組み自体を必要としていたりするようなことがないのである。
世の中においては、「信仰を持つことは尊い」「信仰を持たないことは卑しい」などという風にすら
思い込まれてしまうようにもなる。死への恐怖を自力作善によって克服することも、他力本願によって健全に
克服することもできなくはないのに、そもそも劣悪な信仰によって人々の死への恐怖を最大級に増幅させる
ことを定常状態としてしまっているから、世の風潮からして信仰ありきでしかあり得なくなってしまっている。
自学作善>善い信仰>無学無信>悪い信仰①というのが真如の実相だが、悪い信仰には無信仰状態を苦痛とさせる
「誘引効果」があるために、その信仰に陥ってしまったような人間に対して信仰一般>無信仰②であるような
思い違いを抱かせもする。真実である①と、思い違いである②とでは決定的に相容れないところがあるから、
悪い信仰に陥ったせいで②が真実だと思い込んでしまった人間は、致命的に真実が見えなくなってもしまう。
信仰内容の劣悪さ以前に、悪い信仰にはそういった問題点が付き物でもあるわけだから、そのような信仰の
代表格である聖書信仰の特殊な教義に立ち入るまでもなく、悪い信仰一般を控えるべきだということが言える。
とはいえやはり、聖書信仰の教条こそは、「信者を極度の恐怖に見舞わせた挙句に心神喪失状態に陥れる」という
悪い信仰の黄金比を如実に体現していることも間違いがない。聖書の教義に根ざさなくとも、同様の心理的効果を
他の邪教が信者にもたらすことはいくらでもあり得るが、結局のところは五十歩百歩であり、その効果が甚大で
あるような邪教ほど、聖書信仰の教義に近似していくことにもなるだろう。いかにも「宗教らしい宗教」ほどそうで
あるらしい場合が多いから、宗教という枠組み自体、邪教こそを保護してやるためのものだったのだとも考えられる。
邪教ではないような宗教ほど、実は「宗教」という枠組み自体を必要としていたりするようなことがないのである。
「功臣を枚卜し、惟れ吉なれば之れ従わん」
「功績のあった臣下を一人一人占ってみて、吉と出ればそれに従ってその者を跡継ぎの王としよう。
(重大な決断に易占を用いた実例。占いのような不確定的な手法に従えばこそ角も立たない。
何ものかに服従しきることを全てとしたりするのでは、このような方法による和楽も期待できない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・虞書・大禹謨より)
「功績のあった臣下を一人一人占ってみて、吉と出ればそれに従ってその者を跡継ぎの王としよう。
(重大な決断に易占を用いた実例。占いのような不確定的な手法に従えばこそ角も立たない。
何ものかに服従しきることを全てとしたりするのでは、このような方法による和楽も期待できない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・虞書・大禹謨より)
日本神話上の最高神であり、皇祖神であり、家内安全を司る神でもある
天照大神が、記紀神話上で高度な知見や技能を働かせたような逸話こそはない。
荒神のスサノオが高天原にやって来るに際して、過剰な程もの軍備を敷いたなどの
話はあるが、それも結局は用いられず、スサノオに高天原を荒らし回られて天岩戸に
引きこもり、世界を暗闇に陥れて穀物の実りなども滞らせる。高天原の諸神の企図によって
何とか天岩戸から連れ出されて後、スサノオが平定した出雲国を継いだオオクニヌシに
国譲りを促すため自らの子孫を天下りさせて遣わすが、その子孫をアマテラスが
どのように育て上げたかなどといったことが記紀神話上に記されているわけでもない。
一国統治の有能さにかけては、むしろスサノオやオオクニヌシの有能さのほうが
際立っていて、天下りした天孫自身がそんなに有能であるような描写があるわけでもない。
それでいて、天照大神を祖神とする天皇家こそは、125代に渡る系譜を繋いで来てもいる。
有能さで突出していたスサノオやオオクニヌシではなく、特に有能であるという
逸話もないアマテラスの子孫こそが、日本国の首長たる天子の座を守り続けている。
——中国の道家では、男性女性に関わらず「無能の能」というものが尊ばれ、
帝王たる男自身が無為自然の道術を嗜むことまでもが試みられていた。日本は
それとは違って、妻であり母たる女こそが「無能の能」を最大級に発揮していくことが、
日本神話におけるアマテラス崇拝などにも即して、特筆して推進されて来てもいる。
昔ながらの日本女性が、世界的に見て特に有能であるというわけでもない。
紫式部のような才女もいることはいるが、やはり女文字であるかな文字を用いての
宮中文学という、女性ならではの文化的功績を挙げたわけで、別に社会的人間たるべき
男の領分を侵してまでの、純粋に社会的な有能さなどを発揮したわけではない。
天照大神が、記紀神話上で高度な知見や技能を働かせたような逸話こそはない。
荒神のスサノオが高天原にやって来るに際して、過剰な程もの軍備を敷いたなどの
話はあるが、それも結局は用いられず、スサノオに高天原を荒らし回られて天岩戸に
引きこもり、世界を暗闇に陥れて穀物の実りなども滞らせる。高天原の諸神の企図によって
何とか天岩戸から連れ出されて後、スサノオが平定した出雲国を継いだオオクニヌシに
国譲りを促すため自らの子孫を天下りさせて遣わすが、その子孫をアマテラスが
どのように育て上げたかなどといったことが記紀神話上に記されているわけでもない。
一国統治の有能さにかけては、むしろスサノオやオオクニヌシの有能さのほうが
際立っていて、天下りした天孫自身がそんなに有能であるような描写があるわけでもない。
それでいて、天照大神を祖神とする天皇家こそは、125代に渡る系譜を繋いで来てもいる。
有能さで突出していたスサノオやオオクニヌシではなく、特に有能であるという
逸話もないアマテラスの子孫こそが、日本国の首長たる天子の座を守り続けている。
——中国の道家では、男性女性に関わらず「無能の能」というものが尊ばれ、
帝王たる男自身が無為自然の道術を嗜むことまでもが試みられていた。日本は
それとは違って、妻であり母たる女こそが「無能の能」を最大級に発揮していくことが、
日本神話におけるアマテラス崇拝などにも即して、特筆して推進されて来てもいる。
昔ながらの日本女性が、世界的に見て特に有能であるというわけでもない。
紫式部のような才女もいることはいるが、やはり女文字であるかな文字を用いての
宮中文学という、女性ならではの文化的功績を挙げたわけで、別に社会的人間たるべき
男の領分を侵してまでの、純粋に社会的な有能さなどを発揮したわけではない。
「たらちね(母親)の 庭の教えは 狭けれど 広き世に立つ基とはなれ」
(明治天皇御製)
言葉も分からず、二足歩行すらままならない赤ん坊の内から母たる女が我が子に教えて
やっていくことこそは、特に突出したところがあるわけでもないにもかかわらず、最重要である。
言葉ぐらい分かるようになってからの教育はもう他人に任せたっていいわけで、それこそ、
言葉では表しようもないような最原初の、幼き我が子に母が注ぐ愛情こそが、子の成長を
最大級かつ決定的に左右もする。それが決定するのが大体三歳ごろだから、「三つ子の魂百まで」
とも言えるわけで、言葉だ知識だ技能だでは太刀打ちも出来ない密教がそこにこそあるのである。
それは、女がただ女であることによってのみ先天的に授かっている密教であり、
後天的な能力などによってはどうすることもできないものである。男はもちろんのこと、
女自身にも、それを好き勝手に捨てたり拾ったり増進したりすることはできない。
月経などもその先天性に派生しているものであり、むしろ女を悩ませ、男並みの社会的な勇躍を
決定的に阻んでいるものですらある。我が子を最原初のうちから立派に育て上げていくための
女の天分こそは、真の社会的な有能さなどとはむしろ相容れないものであり、故にこそ、
天上において祀られるのが適切ともなるのである。悪い意味だけでなく善い意味でも、
女が女としての身の程をわきまえるべき要素が、そこにあるのだといえる。
「牝雞は晨すること無し、牝雞の晨するは、惟れ家の索くるなり」
「雌鳥は時を告げて鳴いたりせぬもの。雌鳥が鳴いたりするようであれば、その家はもうおしまいだ。
(女が小ざかしく知恵を持ったり出しゃばってものを言ったりすることこそは、家や国を傾ける元凶である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・牧誓より)
(明治天皇御製)
言葉も分からず、二足歩行すらままならない赤ん坊の内から母たる女が我が子に教えて
やっていくことこそは、特に突出したところがあるわけでもないにもかかわらず、最重要である。
言葉ぐらい分かるようになってからの教育はもう他人に任せたっていいわけで、それこそ、
言葉では表しようもないような最原初の、幼き我が子に母が注ぐ愛情こそが、子の成長を
最大級かつ決定的に左右もする。それが決定するのが大体三歳ごろだから、「三つ子の魂百まで」
とも言えるわけで、言葉だ知識だ技能だでは太刀打ちも出来ない密教がそこにこそあるのである。
それは、女がただ女であることによってのみ先天的に授かっている密教であり、
後天的な能力などによってはどうすることもできないものである。男はもちろんのこと、
女自身にも、それを好き勝手に捨てたり拾ったり増進したりすることはできない。
月経などもその先天性に派生しているものであり、むしろ女を悩ませ、男並みの社会的な勇躍を
決定的に阻んでいるものですらある。我が子を最原初のうちから立派に育て上げていくための
女の天分こそは、真の社会的な有能さなどとはむしろ相容れないものであり、故にこそ、
天上において祀られるのが適切ともなるのである。悪い意味だけでなく善い意味でも、
女が女としての身の程をわきまえるべき要素が、そこにあるのだといえる。
「牝雞は晨すること無し、牝雞の晨するは、惟れ家の索くるなり」
「雌鳥は時を告げて鳴いたりせぬもの。雌鳥が鳴いたりするようであれば、その家はもうおしまいだ。
(女が小ざかしく知恵を持ったり出しゃばってものを言ったりすることこそは、家や国を傾ける元凶である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・牧誓より)
信仰自体は、多動か不動かでいえば、むしろ不動のためにあるべきもので、
行いそのものはむしろ「稽疑>>91」をも尽くした自力作善でこそあるべきである。
他力本願の浄土門において、行不退以上に信不退を優先すると断言し、法然上人からの同意も
取り付けた親鸞和尚はといえば、衆生の安堵のために浄土門の根本聖典である「無量寿経」の
何百回にもわたる読経を志したものの、途中で投げ出したともいう。専門の宗教家の宗教行為すら、
それが他力本願の信仰第一な系統であるというのなら、むしろ消極的であるべきで、信仰について
積極的であるのと引き換えに行いが消極的である姿こそを、在家の信者にも見習わせるべきなのである。
信仰によって行いを積極化すると、否応なく「オッカムの剃刀(考究から不可思議要素をできる限り排す)」
的な論理の発動に基づく不注意が生ずる。そのような不注意と共に大きな事業を為せば為すほど大きな過ちに
結び付きかねないために、「国家規模の大事業は徹底して危険要素を排してから行う(中庸)」という道徳倫理に
それだけでも悖ることになる。だから儒学道徳が広く通用していた江戸時代までの日本において、信仰による
妄動の推進を促すキリシタンは絶やされて、日蓮宗も差別下に置かれた商工階級などが主に信ずるものとなった。
酒も動き回りながら飲んだほうが酔いがよく回るが、信仰も積極的な行いと共にあってこそ酔えるものだ。
行いに信仰を伴わせず、不動の中に信仰を嗜むのであればシラフでいられる一方、むしろ無信仰状態の不動に
焦燥感を抱き、行いこそを信仰によって積極化させようなどとしたならば、そのせいで信仰中毒ともなってしまう。
これも純粋な位相の問題であり、絶対に信仰しろするな、行動するなしろなどという一辺倒な極論ではない。
行動する以上は信仰も捨てろ、信仰したければ行動を積極化するなという「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」
レベルの場合分け論であり、よい信仰、よい行動を心がけるためには「分別」が必要であるというまでのことである。
行いそのものはむしろ「稽疑>>91」をも尽くした自力作善でこそあるべきである。
他力本願の浄土門において、行不退以上に信不退を優先すると断言し、法然上人からの同意も
取り付けた親鸞和尚はといえば、衆生の安堵のために浄土門の根本聖典である「無量寿経」の
何百回にもわたる読経を志したものの、途中で投げ出したともいう。専門の宗教家の宗教行為すら、
それが他力本願の信仰第一な系統であるというのなら、むしろ消極的であるべきで、信仰について
積極的であるのと引き換えに行いが消極的である姿こそを、在家の信者にも見習わせるべきなのである。
信仰によって行いを積極化すると、否応なく「オッカムの剃刀(考究から不可思議要素をできる限り排す)」
的な論理の発動に基づく不注意が生ずる。そのような不注意と共に大きな事業を為せば為すほど大きな過ちに
結び付きかねないために、「国家規模の大事業は徹底して危険要素を排してから行う(中庸)」という道徳倫理に
それだけでも悖ることになる。だから儒学道徳が広く通用していた江戸時代までの日本において、信仰による
妄動の推進を促すキリシタンは絶やされて、日蓮宗も差別下に置かれた商工階級などが主に信ずるものとなった。
酒も動き回りながら飲んだほうが酔いがよく回るが、信仰も積極的な行いと共にあってこそ酔えるものだ。
行いに信仰を伴わせず、不動の中に信仰を嗜むのであればシラフでいられる一方、むしろ無信仰状態の不動に
焦燥感を抱き、行いこそを信仰によって積極化させようなどとしたならば、そのせいで信仰中毒ともなってしまう。
これも純粋な位相の問題であり、絶対に信仰しろするな、行動するなしろなどという一辺倒な極論ではない。
行動する以上は信仰も捨てろ、信仰したければ行動を積極化するなという「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」
レベルの場合分け論であり、よい信仰、よい行動を心がけるためには「分別」が必要であるというまでのことである。
むろん、信仰によって行動を積極化することを促す邪教というものがあるわけで、そのような教義を持つ信教を
行動の消極化のために転用するのもほぼ不可能である。ルターの信仰義認説に即して信行一致を放棄した
プロテスタントの信者も、信仰に基づくわけでもないのに、行動は悪逆非道でしかいられなかった。結局、
キリスト信仰というものが信行一致如何に関わらず、信者に悪逆非道をけしかける代物であることには
変わりなかったわけで、それはキリスト信仰が絶対的に「行動のための信仰」でしかあり得なかったからだ。
不動のための信仰として代表的なのはやはり仏教信仰だし、神道も>>102-103のような文化的意義に即して、
妻母となる女に自重を尽くした良妻賢母となることを促すものである。近ごろでは中国でも下火なようだが、
道家思想を宗教化した道教も、信仰としては不動のための信仰の部類である。歴史的にも人口的にも、信仰を
不動のために善用してきた人間のほうが遥かに多く、故に、信仰によって悪逆非道を犯して来た人間も少数派でいる。
儒学は、純粋な学問として用いられた場合には良好な大業績ばかりを挙げてきたものの、信教である「儒教」として
用いられた場合には、明代の中国や李氏朝鮮のように権力腐敗を来たす温床ともなってしまった。それは、儒学が
どちらかといえば積極的な善行を促すことを本旨とした教学であるからで、これも「行動のための信仰は危険である」
という上記の諸々の論説に漏れないものとなっている。儒学すらそうなのだから、産業学術である洋学も同様である。
洋学の場合、自分がそれを信仰してしまっていることに気づいてすらいない人間が未だ多いのが厄介なことだが。
「王其れ徳を之れ用い、天の永命を祈れ」
「王たるもの、己れの仁徳をよく振るい用いて、永遠の天命に授かることを祈らねばならない。
(『人事を尽くして天命を待つ』で、むしろ自力作善に基づく活動生活の結果としての慶福こそを祈らねばならない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・召誥より)
行動の消極化のために転用するのもほぼ不可能である。ルターの信仰義認説に即して信行一致を放棄した
プロテスタントの信者も、信仰に基づくわけでもないのに、行動は悪逆非道でしかいられなかった。結局、
キリスト信仰というものが信行一致如何に関わらず、信者に悪逆非道をけしかける代物であることには
変わりなかったわけで、それはキリスト信仰が絶対的に「行動のための信仰」でしかあり得なかったからだ。
不動のための信仰として代表的なのはやはり仏教信仰だし、神道も>>102-103のような文化的意義に即して、
妻母となる女に自重を尽くした良妻賢母となることを促すものである。近ごろでは中国でも下火なようだが、
道家思想を宗教化した道教も、信仰としては不動のための信仰の部類である。歴史的にも人口的にも、信仰を
不動のために善用してきた人間のほうが遥かに多く、故に、信仰によって悪逆非道を犯して来た人間も少数派でいる。
儒学は、純粋な学問として用いられた場合には良好な大業績ばかりを挙げてきたものの、信教である「儒教」として
用いられた場合には、明代の中国や李氏朝鮮のように権力腐敗を来たす温床ともなってしまった。それは、儒学が
どちらかといえば積極的な善行を促すことを本旨とした教学であるからで、これも「行動のための信仰は危険である」
という上記の諸々の論説に漏れないものとなっている。儒学すらそうなのだから、産業学術である洋学も同様である。
洋学の場合、自分がそれを信仰してしまっていることに気づいてすらいない人間が未だ多いのが厄介なことだが。
「王其れ徳を之れ用い、天の永命を祈れ」
「王たるもの、己れの仁徳をよく振るい用いて、永遠の天命に授かることを祈らねばならない。
(『人事を尽くして天命を待つ』で、むしろ自力作善に基づく活動生活の結果としての慶福こそを祈らねばならない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・召誥より)
ただの実情と、ただの概念と、実情を何らかの方向へと導く実質的な理念というものがある。
実情を教導する理念の内にも優良なものと劣悪なものがあり、優良な理念は世の中を
泰平や繁栄へと導く一方、劣悪な理念は世の中を困窮や破滅へと導く効能を伴っている。
ただの実情の尊重を促したのが老荘列に代表される道家思想である一方、
概念一般の偏重を促したのがソクラテス=プラトンのイデア思想である。
実情を吉方へと導く優良な理念を打ち出したのが儒学や仏教である一方、
実情を破滅へと陥れる劣悪な理念を打ち出したのが聖書信仰や洋学である。
儒学が実質的な世の中を吉方へと導く最たる理念としているのが四書五経の、中でも易学であり、
易学上の陰陽五行思想は数理科学的にもこの世界、この宇宙の普遍法則こそをよく抽出して純化させている。
また、古代の黎明期から宋儒の活躍した中興期やその後に至るまで、儒者は道家思想をも兼学することが
奨励されて来ている。この世界の法則こそを抽出した理念である易学と、実情一般の尊重を促す道家思想とを
儒家は是としているわけで、儒学は概念一般以上にも実情一般のほうをより重んずる教学であるのだと位置づけられる。
死海文書におけるグノーシズムにまつわる記録などからも、聖書信仰の、特に新約信仰が
プラトンのイデア思想の影響を深く受けていたことが明らかとなっている。ただでさえ新旧約聖書には
自然などにまつわる具体的な描写が乏しく、得体の知れない超越神との対話だ関係だばかりが延々と
書き連ねられているわけで、新旧約聖書やそれに対する信仰が概念一般を偏重するものでこそあれ、
実情を尊ぶようなものでは決してないことが、見るに明らかともなっている。
実情を教導する理念の内にも優良なものと劣悪なものがあり、優良な理念は世の中を
泰平や繁栄へと導く一方、劣悪な理念は世の中を困窮や破滅へと導く効能を伴っている。
ただの実情の尊重を促したのが老荘列に代表される道家思想である一方、
概念一般の偏重を促したのがソクラテス=プラトンのイデア思想である。
実情を吉方へと導く優良な理念を打ち出したのが儒学や仏教である一方、
実情を破滅へと陥れる劣悪な理念を打ち出したのが聖書信仰や洋学である。
儒学が実質的な世の中を吉方へと導く最たる理念としているのが四書五経の、中でも易学であり、
易学上の陰陽五行思想は数理科学的にもこの世界、この宇宙の普遍法則こそをよく抽出して純化させている。
また、古代の黎明期から宋儒の活躍した中興期やその後に至るまで、儒者は道家思想をも兼学することが
奨励されて来ている。この世界の法則こそを抽出した理念である易学と、実情一般の尊重を促す道家思想とを
儒家は是としているわけで、儒学は概念一般以上にも実情一般のほうをより重んずる教学であるのだと位置づけられる。
死海文書におけるグノーシズムにまつわる記録などからも、聖書信仰の、特に新約信仰が
プラトンのイデア思想の影響を深く受けていたことが明らかとなっている。ただでさえ新旧約聖書には
自然などにまつわる具体的な描写が乏しく、得体の知れない超越神との対話だ関係だばかりが延々と
書き連ねられているわけで、新旧約聖書やそれに対する信仰が概念一般を偏重するものでこそあれ、
実情を尊ぶようなものでは決してないことが、見るに明らかともなっている。
 プラトンがイデア論などを打ち出すまでもなく、人間はある程度は概念的な思考を嗜むものである。
プラトンがイデア論などを打ち出すまでもなく、人間はある程度は概念的な思考を嗜むものである。 それをイデア論に基づいて濫用したりせずに、実情を適格に捉えるための道具として用いたなら、
易の陰陽五行思想やインドの五大思想のようなものが見極められたのである。一方で、プラトンの
イデア論なども参考に、概念夢想を最大級に働かせ尽くした結果として編み出されたのが新約の教義
だったりするわけで、その教義内容はといえば、易の法則などに即すれば「最悪の凶相」を帯びているという
他はないものとなっている。概念を偏重しまくりながら、実情を何らかの方向へと導こうとした結果として、
聖書信仰は易の評価に基づけば最低最悪である、世の中を破滅や滅亡へと陥れる教相を帯びることとなった。
ということはつまり、世の中を吉方へと導くためには、概念以上にも実情こそを尊びつつ
理念をも編み出していくべきである一方で、世の中を破滅へと陥れたいというのなら、
実情以上にも概念を偏重しつつ諸々の理念を編み出していけばいいということである。
イデア論なんかなくたって、概念は概念で有る。だからといって概念思考の喪失を恐れたりする必要は全くなく、
ただ実情と概念とであれば、より実情のほうが尊ばれて行くべきだということである。複雑怪奇な数式などを
多用する洋学と比べて、儒学上の説話も実情に根ざしたありきたりな言葉だったりすることが多いが、それも
そうあるべきだからこそそうしているまでのことで、別に東洋人に概念思考の素養が欠けていたからなわけでも
ないのは、昨今の東洋人の数理科学やコンピュータ開発などにかけての突出的な活躍からも窺えることである。
やればできるが、むしろ本当はそうでないほうがよい。四書五経の言葉ほどにも自明であったほうがいいのである。
「静女の其れ姝き、我れを城隅に俟つ。愛して見せず、首を掻きて踟躕す」
「しとやかで器量よしなあの娘が、自分を城郭の片隅で待っている。
わざと自分を隠して見せようとせず、うなじをかきながらぐずぐずしている。
(婦女子のもったいぶりあたりとしては、隠して見せないのも可愛いもんだ)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・邶風・静女より)
川に譬えるなら、無為自然が源流を司り、道徳が中流を司り、法律が下流を司るというのが
社会統治の実相であるといえる。源流ではわずかな流れだった川が下に行くに連れて
段々と大きくなる。大きくなると共に濁り始めるのを、中流からの道徳統治で
十分に抑制できたなら、下流における汚濁の程度も低くなり、わざわざ法律によってまで
大々的な浄化を講じていく必要などはなくなる。一方、中流からの汚濁防止を怠って
下流を汚濁まみれにしたなら、法律による熾烈な浄化措置が必要となり、最悪の場合
浄化が追いつかなくなって、そのような国からの傾国や亡国などの末路を辿ることともなる。
中流からの道徳統治を完全に怠って、下流での汚濁まみれを法律によって浄化することばかりに
頼りきりでいる世の中というのは、100年と持たない。権力道徳が皆無である西洋社会もそうだし、
東洋でもそのような法治支配を講じた秦始皇帝などが、数十年と治世を保つことができなかった。
一方で、権力道徳による中流からの汚濁防止に努める世の中というのは、数百年程度は治世を
保つことができる。その実例も今までに挙げたとおり枚挙に暇がなく、徳治による汚濁の防止が
実施された世の中こそは、人類史上でも花形中の花形の時代ともなっている。
宗教は、権力道徳による世相の汚濁防止を助成したり、阻んだりする。
仏教や神道や道教やヒンズー教には、道徳統治を補助する効能があるし、
拝火教やイスラム教も、修羅道に没頭し過ぎる面もあるにしろ、そういった効果が多少はある。
キリスト教やユダヤ教はかえって道徳統治による汚濁防止を阻む効果があるため、乱世か、
さもなくば法律による雁字搦めの締め付けのいずれかしか許されないようにもさせてしまう。
社会統治の実相であるといえる。源流ではわずかな流れだった川が下に行くに連れて
段々と大きくなる。大きくなると共に濁り始めるのを、中流からの道徳統治で
十分に抑制できたなら、下流における汚濁の程度も低くなり、わざわざ法律によってまで
大々的な浄化を講じていく必要などはなくなる。一方、中流からの汚濁防止を怠って
下流を汚濁まみれにしたなら、法律による熾烈な浄化措置が必要となり、最悪の場合
浄化が追いつかなくなって、そのような国からの傾国や亡国などの末路を辿ることともなる。
中流からの道徳統治を完全に怠って、下流での汚濁まみれを法律によって浄化することばかりに
頼りきりでいる世の中というのは、100年と持たない。権力道徳が皆無である西洋社会もそうだし、
東洋でもそのような法治支配を講じた秦始皇帝などが、数十年と治世を保つことができなかった。
一方で、権力道徳による中流からの汚濁防止に努める世の中というのは、数百年程度は治世を
保つことができる。その実例も今までに挙げたとおり枚挙に暇がなく、徳治による汚濁の防止が
実施された世の中こそは、人類史上でも花形中の花形の時代ともなっている。
宗教は、権力道徳による世相の汚濁防止を助成したり、阻んだりする。
仏教や神道や道教やヒンズー教には、道徳統治を補助する効能があるし、
拝火教やイスラム教も、修羅道に没頭し過ぎる面もあるにしろ、そういった効果が多少はある。
キリスト教やユダヤ教はかえって道徳統治による汚濁防止を阻む効果があるため、乱世か、
さもなくば法律による雁字搦めの締め付けのいずれかしか許されないようにもさせてしまう。
道徳皆無の西洋諸国に限らず、日本や中国も今は法治主義であり、かつての道徳統治の面影すら
ほとんど見られなくなっている。そうなってしまってからの日本の支配層や中国社会の腐敗
も凄まじいもので、西洋社会などと違って、徳治による汚濁防止が敷かれたこともかつては
あったからこそ、法治主義に基づく世相のド腐れ加減が如実なものともなっている。
今では西洋社会すらもが宗教信仰は下火気味となっているが、法律や科学などによって
世相の乱脈を無理やり押さえつて行かなければいられないままでいるのは、やはり、
キリスト信仰やユダヤ信仰の禍根であると言える。そのとばっちりは伝統的に、聖書圏でない
日本や中国やその他の地球社会にまで及んでしまっており、まるで法律や科学がないことには
人間社会は原始的な土人社会でしかあり得ないかのような思い込みまでもが通用してしまってもいる。
まず、今の人類社会は、聖書信仰からの深刻な悪影響で、道徳統治による汚濁防止が不能と化して
しまったままでいる「特殊な社会」であるということをわきまえ直す必要がある。その上で、
意識的に聖書信仰を改めて排除して行くことで、わざわざ法律による締め付けや科学による
取り繕いばかりを講じなくても済むぐらいに、世相が清浄でいられるように道徳統治を実施して行く。
そのためには、道徳統治を助成してくれるような良好な信教の手を借りることもありだといえる。
もちろん、だからといって「信教の自由」などというものを無制限に認めたのでは、また聖書教
みたいな邪教の流布すらもが企てられかねないから、信教を精査して行く必要は当然あるといえる。
「徳を度らず、力を量らず、親に親しまず、辞を徴わさず、罪有るを察せず」
「他人の徳を推し量らず、その力を見くびり、肉親に親しもうともせず、語弊を正さず、己れに罪が
あるのを察しもしない。(息侯の五犯。イエスやその隣人もこのような道徳違反の罪を犯してはいた)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・隠公十一年より)
ほとんど見られなくなっている。そうなってしまってからの日本の支配層や中国社会の腐敗
も凄まじいもので、西洋社会などと違って、徳治による汚濁防止が敷かれたこともかつては
あったからこそ、法治主義に基づく世相のド腐れ加減が如実なものともなっている。
今では西洋社会すらもが宗教信仰は下火気味となっているが、法律や科学などによって
世相の乱脈を無理やり押さえつて行かなければいられないままでいるのは、やはり、
キリスト信仰やユダヤ信仰の禍根であると言える。そのとばっちりは伝統的に、聖書圏でない
日本や中国やその他の地球社会にまで及んでしまっており、まるで法律や科学がないことには
人間社会は原始的な土人社会でしかあり得ないかのような思い込みまでもが通用してしまってもいる。
まず、今の人類社会は、聖書信仰からの深刻な悪影響で、道徳統治による汚濁防止が不能と化して
しまったままでいる「特殊な社会」であるということをわきまえ直す必要がある。その上で、
意識的に聖書信仰を改めて排除して行くことで、わざわざ法律による締め付けや科学による
取り繕いばかりを講じなくても済むぐらいに、世相が清浄でいられるように道徳統治を実施して行く。
そのためには、道徳統治を助成してくれるような良好な信教の手を借りることもありだといえる。
もちろん、だからといって「信教の自由」などというものを無制限に認めたのでは、また聖書教
みたいな邪教の流布すらもが企てられかねないから、信教を精査して行く必要は当然あるといえる。
「徳を度らず、力を量らず、親に親しまず、辞を徴わさず、罪有るを察せず」
「他人の徳を推し量らず、その力を見くびり、肉親に親しもうともせず、語弊を正さず、己れに罪が
あるのを察しもしない。(息侯の五犯。イエスやその隣人もこのような道徳違反の罪を犯してはいた)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・隠公十一年より)
[YouTubeで再生]
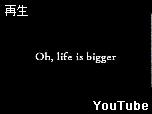 >「地蔵氏ね」とか適当な短文レスしてくれててもいいよ。←>>73
>「地蔵氏ね」とか適当な短文レスしてくれててもいいよ。←>>73
そのレスの相手>>70ではありませんが。
『Losing My Religion』(直訳すると“私の宗教を失う”だが……)
歌いだし)〜人生はずっと、大きいもんなんだ キミなんかより ずっと大きいんだ
和訳参考サイト:http://i-love-xtc.seesaa.net/article/216282359.htm...
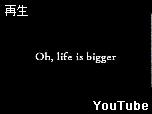 >「地蔵氏ね」とか適当な短文レスしてくれててもいいよ。←>>73
>「地蔵氏ね」とか適当な短文レスしてくれててもいいよ。←>>73 そのレスの相手>>70ではありませんが。
『Losing My Religion』(直訳すると“私の宗教を失う”だが……)
歌いだし)〜人生はずっと、大きいもんなんだ キミなんかより ずっと大きいんだ
和訳参考サイト:http://i-love-xtc.seesaa.net/article/216282359.htm...
「言葉でこういったからこうだ」などという所に全ての信用を
還元してしまうことからして、精神的な怠惰にまみれている。
家康公のように、信用ある行いを何十年にも渡って積み重ねておきながら、
老耄した秀吉との口約束などは反故にしてしまった場合など、だからといって信用を失うなどということはない。
むしろ、人の発言などよりも行いのほうに信用性の重点を置く真摯さに即してこそ、信用を置き続けることができる。
始めからそういった真摯な態度で自分自身が居たならば、舌先三寸の確約ばかりに全ての信用を
還元しようとする聖書信仰などにも溺れたりするはずがない。そんなものに溺れてしまっている時点で、
本人自身が人並み以上の精神的な怠惰に陥ってしまっているのだから、明らかに自らにも落ち度があるのである。
真摯な行いから派生する言葉こそはむしろ素朴であり、行いの伴わない虚飾の言葉こそはむしろ美麗である。
言行一致の聖王賢臣や儒者の言葉をありのままに記録した四書五経の言葉(「詩経」の庶民の唄などは除く)が
特筆して美麗だなどということもなく、その背景に真摯な行いへの心がけが具わっていることを見越すことで
初めてその意義を味わえるような言葉ばかりとなっている。一方、口先ばかりで一切実質の伴わない犯罪聖書
の言葉はといえば、一つ一つの物言いからしていかにも思わせぶりで、匹夫小人の想像力をかき立てたがる
ような誘惑性に満ちている。そいうものを愛でたい人間には愛でやすいものであっても、言葉の背景にある
行いにまで配慮を利かせる人間からすれば、上ずってばかりで信実さにかける言葉のようにしか思われないのである。
これも一つの位相上の問題であり、行動が全て、言葉などに大した価値はないなどという極論なわけでも決してない。
「実質主義ばかりで文飾が一切伴わないようなら野蛮だし、文飾ばかりで実質が一切伴わないようなら文書係止まりである。
質と文両方が相まってこそ君子である(雍也第六・一八)」であり、立派な行いにそれ相応の言葉を付帯させるのは、
特に世俗での善行を心がける君子士人にはあって然るべきことともなっている。その上で、言葉か行いかでいえば
還元してしまうことからして、精神的な怠惰にまみれている。
家康公のように、信用ある行いを何十年にも渡って積み重ねておきながら、
老耄した秀吉との口約束などは反故にしてしまった場合など、だからといって信用を失うなどということはない。
むしろ、人の発言などよりも行いのほうに信用性の重点を置く真摯さに即してこそ、信用を置き続けることができる。
始めからそういった真摯な態度で自分自身が居たならば、舌先三寸の確約ばかりに全ての信用を
還元しようとする聖書信仰などにも溺れたりするはずがない。そんなものに溺れてしまっている時点で、
本人自身が人並み以上の精神的な怠惰に陥ってしまっているのだから、明らかに自らにも落ち度があるのである。
真摯な行いから派生する言葉こそはむしろ素朴であり、行いの伴わない虚飾の言葉こそはむしろ美麗である。
言行一致の聖王賢臣や儒者の言葉をありのままに記録した四書五経の言葉(「詩経」の庶民の唄などは除く)が
特筆して美麗だなどということもなく、その背景に真摯な行いへの心がけが具わっていることを見越すことで
初めてその意義を味わえるような言葉ばかりとなっている。一方、口先ばかりで一切実質の伴わない犯罪聖書
の言葉はといえば、一つ一つの物言いからしていかにも思わせぶりで、匹夫小人の想像力をかき立てたがる
ような誘惑性に満ちている。そいうものを愛でたい人間には愛でやすいものであっても、言葉の背景にある
行いにまで配慮を利かせる人間からすれば、上ずってばかりで信実さにかける言葉のようにしか思われないのである。
これも一つの位相上の問題であり、行動が全て、言葉などに大した価値はないなどという極論なわけでも決してない。
「実質主義ばかりで文飾が一切伴わないようなら野蛮だし、文飾ばかりで実質が一切伴わないようなら文書係止まりである。
質と文両方が相まってこそ君子である(雍也第六・一八)」であり、立派な行いにそれ相応の言葉を付帯させるのは、
特に世俗での善行を心がける君子士人にはあって然るべきことともなっている。その上で、言葉か行いかでいえば
より行いの如何のほうが重要なことであるとするのが可である一方、行いよりも言葉の如何ばかりを重視するのが
不可であるということである。前者のような姿勢に基づいて著されているのが四書五経などである一方、後者のような
姿勢に基づいて著されているのが犯罪聖書だから、前者を読み倣って後者を倣わないようにもすべきなのである。
>>110
「信仰第一」という姿勢自体、「言葉第一行動第二」という精神的怠惰に即している。
日本における代表的な他力本願系の信教である浄土教の信者も、大半が百姓であり、信仰などよりも
まず毎日の田畑の耕作のほうが第一義であるような人々によってこそ、副次的に信仰もまた嗜まれていた。
他力本願でない他の仏教宗派なども当然より自己本位であり、出家者も在俗信者もまず己れがいかにあるかということを
第一として、副次的に信教という体裁をも採っている。禅や密教の坊主は命の保証もないような修行に取り組み、
それに在俗から帰依する武家や公家なども、儒学や武士道の理念に即した道徳統治を第一義としていた。
故に、日本に「信仰第一」などという人間がいたことなどもほとんどないのであり、信仰を保つか失うか
などということが、自らの全ての命運を左右する程もの一大事としてまで取り扱われたりすることもないのである。
一人一人の人間の人生が、その全てを信教に拘束されなければならないほど矮小であるなどということはない。少なくとも、
必ずしもそこまで卑小でなければならないことわりなどはどこにもない。あるとすればそんなものからして偽証である。
そのような偽証を信じ込む所から是正していくべきであり、結局は己れの奴隷根性を払拭していくことこそが要となる。
「翩翩として富もうとせず、其の隣りと以にす。戒めずして以て孚あり。〜戒めずして以て孚あるは、中心より願えばなり」
「多くの鳥が羽を揃えて飛ぶように、自分ばかりが富もうとはせず、富をみんなで分け合おうとする。わざわざ戒めずとも
誠実さに満ちている。誠実さに道いてるのは、人としての本願に即しているからだ。(我田引水や富の寡占は本願ではない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・泰・六四‐象伝より)
不可であるということである。前者のような姿勢に基づいて著されているのが四書五経などである一方、後者のような
姿勢に基づいて著されているのが犯罪聖書だから、前者を読み倣って後者を倣わないようにもすべきなのである。
>>110
「信仰第一」という姿勢自体、「言葉第一行動第二」という精神的怠惰に即している。
日本における代表的な他力本願系の信教である浄土教の信者も、大半が百姓であり、信仰などよりも
まず毎日の田畑の耕作のほうが第一義であるような人々によってこそ、副次的に信仰もまた嗜まれていた。
他力本願でない他の仏教宗派なども当然より自己本位であり、出家者も在俗信者もまず己れがいかにあるかということを
第一として、副次的に信教という体裁をも採っている。禅や密教の坊主は命の保証もないような修行に取り組み、
それに在俗から帰依する武家や公家なども、儒学や武士道の理念に即した道徳統治を第一義としていた。
故に、日本に「信仰第一」などという人間がいたことなどもほとんどないのであり、信仰を保つか失うか
などということが、自らの全ての命運を左右する程もの一大事としてまで取り扱われたりすることもないのである。
一人一人の人間の人生が、その全てを信教に拘束されなければならないほど矮小であるなどということはない。少なくとも、
必ずしもそこまで卑小でなければならないことわりなどはどこにもない。あるとすればそんなものからして偽証である。
そのような偽証を信じ込む所から是正していくべきであり、結局は己れの奴隷根性を払拭していくことこそが要となる。
「翩翩として富もうとせず、其の隣りと以にす。戒めずして以て孚あり。〜戒めずして以て孚あるは、中心より願えばなり」
「多くの鳥が羽を揃えて飛ぶように、自分ばかりが富もうとはせず、富をみんなで分け合おうとする。わざわざ戒めずとも
誠実さに満ちている。誠実さに道いてるのは、人としての本願に即しているからだ。(我田引水や富の寡占は本願ではない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・泰・六四‐象伝より)
たとえば、易の六十四卦中でも「環境最悪」の卦である否卦のような状況において、
在野に放逐された孔孟のような君子が、仁徳を湛える気高さを糧に朗らかでいたりするのは、
これは良好なことだといえる。一方、「環境最良」の卦である泰卦のような状況において、
逆に小人が世の中の中枢から追いやられて辛酸をなめさせられるようになった時に、
新旧約の教義のような邪義を慰み物にしたとすれば、これは良くないことだといえる。
易の法則上、泰卦のような状況も否卦のような状況も、春夏秋冬の移り巡りのように
いつかはやって来ることを予期しておくべきものである。ただそれにしたって、泰卦のような
良好な状況を追い求め、そこに至るやその堅持にも務めて行くのが、人間の側にとっての
最善の姿勢となる一方、否卦のような陰惨な状況をあえて追い求め、そこに世相を凝り固まらせ
ようとしたりしたなら、それは人間の側にとってのそうあるべきでない劣悪な姿勢となる。
孔孟のごとき聖人君子が、否卦のような劣悪な環境下(春秋戦国時代の中国)において、
本望である徳治が実現できない代替として編纂したのが権力道徳聖書——通称四書五経である一方、
政商として放辟邪侈の限りを尽くしていた古代ユダヤ人が、バビロニアで拘留された際に、
自分たちの鬱憤を晴らす目的で書き始めたのが権力犯罪聖書——通称聖書である。いずれも、
ある種の人間が、自分たちにとっての不遇に置かれて、本望が達せないがための代替として
執筆編纂されたものであることでは共通している。ただ、片や権力道徳者であり、片や
権力犯罪者であったから、その産物も権力道徳聖書や権力犯罪聖書となったのである。
在野に放逐された孔孟のような君子が、仁徳を湛える気高さを糧に朗らかでいたりするのは、
これは良好なことだといえる。一方、「環境最良」の卦である泰卦のような状況において、
逆に小人が世の中の中枢から追いやられて辛酸をなめさせられるようになった時に、
新旧約の教義のような邪義を慰み物にしたとすれば、これは良くないことだといえる。
易の法則上、泰卦のような状況も否卦のような状況も、春夏秋冬の移り巡りのように
いつかはやって来ることを予期しておくべきものである。ただそれにしたって、泰卦のような
良好な状況を追い求め、そこに至るやその堅持にも務めて行くのが、人間の側にとっての
最善の姿勢となる一方、否卦のような陰惨な状況をあえて追い求め、そこに世相を凝り固まらせ
ようとしたりしたなら、それは人間の側にとってのそうあるべきでない劣悪な姿勢となる。
孔孟のごとき聖人君子が、否卦のような劣悪な環境下(春秋戦国時代の中国)において、
本望である徳治が実現できない代替として編纂したのが権力道徳聖書——通称四書五経である一方、
政商として放辟邪侈の限りを尽くしていた古代ユダヤ人が、バビロニアで拘留された際に、
自分たちの鬱憤を晴らす目的で書き始めたのが権力犯罪聖書——通称聖書である。いずれも、
ある種の人間が、自分たちにとっての不遇に置かれて、本望が達せないがための代替として
執筆編纂されたものであることでは共通している。ただ、片や権力道徳者であり、片や
権力犯罪者であったから、その産物も権力道徳聖書や権力犯罪聖書となったのである。
確かに「大道廃れて仁義あり(老子)」であり、仁義道徳を謳う四書五経のような権力道徳聖書もまた、
聖人君子がその実力を発揮できない不遇な時代にこそ生み出されたのである。一方、極東社会のように、
士人階級と産業階級の癒着が倫理的に問題視されることもなかったからこそ、古代の中東や西洋では、
政商集団がユダヤ人のような民族宗教団体までをも形成するに至ったわけだから、それ自体がより
劣悪なことだといえる。そのユダヤ人が、悪逆非道の積み重ねによって肥大化させた自意識過剰の
思い上がりを文書として書きなぐったのが犯罪聖書だったりするわけだから、これも当然濁世の
産物であることには変わりない。良いことが記録されるか、悪いことが記録されるかに関わらず、
駄目な環境こそは、一大事を文書としてしたためる機会をもたらすものなのである。
それでいてやはり、優良なことを書いている聖書と、劣悪なことばかりを書き連ねている聖書とでは、
前者を採って後者を棄てるようにしたほうがよい。それが書物を享受する人間の側にとっての最善の
姿勢となるわけだから、両者が並存しているにもかかわらず、あえて劣悪な聖書のほうを採ったり
するようなら、そうした本人自身の責任問題が問われることになっても全く仕方がないといえる。
環境が良かったり悪かったりするのは世の常である。ただそんな中にも最善を尽くしていく術という
のは必ずあるものだから、それ以外の選択肢に溺れていてそれでよしなんてことはないのである。
聖人君子がその実力を発揮できない不遇な時代にこそ生み出されたのである。一方、極東社会のように、
士人階級と産業階級の癒着が倫理的に問題視されることもなかったからこそ、古代の中東や西洋では、
政商集団がユダヤ人のような民族宗教団体までをも形成するに至ったわけだから、それ自体がより
劣悪なことだといえる。そのユダヤ人が、悪逆非道の積み重ねによって肥大化させた自意識過剰の
思い上がりを文書として書きなぐったのが犯罪聖書だったりするわけだから、これも当然濁世の
産物であることには変わりない。良いことが記録されるか、悪いことが記録されるかに関わらず、
駄目な環境こそは、一大事を文書としてしたためる機会をもたらすものなのである。
それでいてやはり、優良なことを書いている聖書と、劣悪なことばかりを書き連ねている聖書とでは、
前者を採って後者を棄てるようにしたほうがよい。それが書物を享受する人間の側にとっての最善の
姿勢となるわけだから、両者が並存しているにもかかわらず、あえて劣悪な聖書のほうを採ったり
するようなら、そうした本人自身の責任問題が問われることになっても全く仕方がないといえる。
環境が良かったり悪かったりするのは世の常である。ただそんな中にも最善を尽くしていく術という
のは必ずあるものだから、それ以外の選択肢に溺れていてそれでよしなんてことはないのである。
「宋の皇国父、大宰と為る。平公の為に臺を築き、農収を妨ぐ。子罕、農功の畢わるを俟たんと請う。
公、許さず。築く者謳いて曰く、沢門の皙、実に我が役を興し、邑中の黔、実に我が心を慰めり、と。
子罕之を聞き、親ら扑を執りて、以て築く者に行きて、其の勉めざる者を抶ちて曰く、吾が儕小人も、
皆闔廬有りて、以て燥濕寒暑を辟く。今君一臺を為して速やかに成さずんば、何を以て役と為さん、と。
謳う者乃ち止む。或ひと其の故を問う。子罕曰く、宋国は区区たり。而るに詛有り祝有るは、禍の本なり」
「宋の皇国父は大宰相となり、平公のために高台の御殿を築くことを計画した。ちょうどその頃農繁期に
当たり、農夫を徴集すれば収穫を妨げることになるため、まだ小役人だった子罕が皇国父に農繁期が
過ぎるまで待つように諫言した。しかしその言葉は聞き入れられず、御殿築造の工事は速やかに始められた。
徴集され工事に従事させられている農夫たちは『東城の門の所に居る色白の男(皇国父)がこんな仕事を
させ始めやがった。村の中に居る色黒の男(子罕)が俺たちを慰めてくれる』と歌い始めた。これを聞くと
子罕は杖を持って農夫たちの所に行き、工事をサボっている者を厳しく打ち据えた。『俺たち身分の低い者
でもそれ相応の家を構えて乾燥や雨露や寒暑を防げているのだ。主君一人のために御殿を建てることぐらい
一体どうだというのだ』と、多少こじつけ気味な言葉によって農夫たちを叱責もした。すると農夫たちも
以前のような歌を唄うことをしなくなった。ある人が子罕にどうしてそんなことをしたのかを問うた。
子罕は答えた。『宋のような小国である役人をが呪われたり、別の役人が誉められたりしていたのでは
国が持たないから』(公益のために、自らの慰めを農夫たちが褒め上げることすらをも蹴った例)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・襄公十七年より)
公、許さず。築く者謳いて曰く、沢門の皙、実に我が役を興し、邑中の黔、実に我が心を慰めり、と。
子罕之を聞き、親ら扑を執りて、以て築く者に行きて、其の勉めざる者を抶ちて曰く、吾が儕小人も、
皆闔廬有りて、以て燥濕寒暑を辟く。今君一臺を為して速やかに成さずんば、何を以て役と為さん、と。
謳う者乃ち止む。或ひと其の故を問う。子罕曰く、宋国は区区たり。而るに詛有り祝有るは、禍の本なり」
「宋の皇国父は大宰相となり、平公のために高台の御殿を築くことを計画した。ちょうどその頃農繁期に
当たり、農夫を徴集すれば収穫を妨げることになるため、まだ小役人だった子罕が皇国父に農繁期が
過ぎるまで待つように諫言した。しかしその言葉は聞き入れられず、御殿築造の工事は速やかに始められた。
徴集され工事に従事させられている農夫たちは『東城の門の所に居る色白の男(皇国父)がこんな仕事を
させ始めやがった。村の中に居る色黒の男(子罕)が俺たちを慰めてくれる』と歌い始めた。これを聞くと
子罕は杖を持って農夫たちの所に行き、工事をサボっている者を厳しく打ち据えた。『俺たち身分の低い者
でもそれ相応の家を構えて乾燥や雨露や寒暑を防げているのだ。主君一人のために御殿を建てることぐらい
一体どうだというのだ』と、多少こじつけ気味な言葉によって農夫たちを叱責もした。すると農夫たちも
以前のような歌を唄うことをしなくなった。ある人が子罕にどうしてそんなことをしたのかを問うた。
子罕は答えた。『宋のような小国である役人をが呪われたり、別の役人が誉められたりしていたのでは
国が持たないから』(公益のために、自らの慰めを農夫たちが褒め上げることすらをも蹴った例)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・襄公十七年より)
罪悪不法を開き直るような邪教邪学というのは、善の楽しみを知りもしない
ような世の中でしか生じ得ないし、また通用することもないものである。
人々の食い扶持のために作物を育てたり、悪人の乱暴を取り締まるための警備を行ったり
といった善行が、大規模な世の中にはどうしたって必要となる。ただ、必要だから仕方なく
やっている場合と、それこそが楽しみだからやっている場合とがあり、古代オリエント社会や
西洋社会は前者だった一方、古代の中国社会や日本社会は後者だった。だから前二つの社会では
不法を開き直ってよしとする聖書信仰みたいな邪教が生じてしまった一方、後二つの社会では
それに相当する程もの邪教は生じず、代わりに勧善懲悪の楽しみを促す儒学のような正学こそが生じた。
儒学が体系化された春秋戦国時代の中国にも、決して勧善懲悪志向などではない異学異見が
多数生じてもいたが、対抗馬としての儒学のような学問もまたあって、人々と共に善行を楽しんでいた
舜帝の伝説なども引き合いに出しつつ人々を教化していたから、「悪行こそは楽しい」なんていう
物言いまでもがまかり通りはしなかった。法家だ名家だ縦横家だとか、異端の儒学である荀子学派
だとかも、残念ながら陥ってしまっているものとしての罪悪まみれを擁護したりしていたわけで、
悪逆非道こそを完全に開き直って権威化までしてしまうような所までは行けなかったのである。
ような世の中でしか生じ得ないし、また通用することもないものである。
人々の食い扶持のために作物を育てたり、悪人の乱暴を取り締まるための警備を行ったり
といった善行が、大規模な世の中にはどうしたって必要となる。ただ、必要だから仕方なく
やっている場合と、それこそが楽しみだからやっている場合とがあり、古代オリエント社会や
西洋社会は前者だった一方、古代の中国社会や日本社会は後者だった。だから前二つの社会では
不法を開き直ってよしとする聖書信仰みたいな邪教が生じてしまった一方、後二つの社会では
それに相当する程もの邪教は生じず、代わりに勧善懲悪の楽しみを促す儒学のような正学こそが生じた。
儒学が体系化された春秋戦国時代の中国にも、決して勧善懲悪志向などではない異学異見が
多数生じてもいたが、対抗馬としての儒学のような学問もまたあって、人々と共に善行を楽しんでいた
舜帝の伝説なども引き合いに出しつつ人々を教化していたから、「悪行こそは楽しい」なんていう
物言いまでもがまかり通りはしなかった。法家だ名家だ縦横家だとか、異端の儒学である荀子学派
だとかも、残念ながら陥ってしまっているものとしての罪悪まみれを擁護したりしていたわけで、
悪逆非道こそを完全に開き直って権威化までしてしまうような所までは行けなかったのである。
古代オリエント社会や西洋社会では、勧善懲悪の楽しみを味わうものも、その楽しみこそを
体系的に推進して行こうとするものもいなかったから、悪の楽しみこそを開き直って、
それこそを権威化してしまうようなことまでもが聖書信仰として生じてしまいもした。
いわゆる「鳥なき里のコウモリ」というやつで、もしも儒学のような勧善懲悪の楽しみを
推進する教学があったなら、決してでかい顔もできないでいたものである。実際に、
アブラハム教にしては勧善懲悪的な傾向のあるイスラムがムハンマドによって創始された
後には、古代オリエントに相当する中東社会からは聖書信仰もその地位を追われたのである。
勧善懲悪の楽しみの権威化と、悪逆非道の楽しみの権威化とは排他的な関係にあり、
なおかつ勧善懲悪の楽しみの権威化のほうが「優性」であり、悪逆非道の楽しみの権威化のほうが
「劣性」である。両者が並存している以上は、必ず勧善懲悪の楽しみの権威化のほうが勝ち、
悪逆非道の楽しみの権威化のほうが負ける。それは、勧善懲悪の楽しみの体系化である
四書五経の言葉が、悪逆非道の楽しみの体系化である犯罪聖書の言葉と比べて見るからに正しい
ということからも言えるし、善因楽果悪因苦果の罪福異熟の真理に即して、勧善懲悪の楽しみの
ほうが悪逆非道の楽しみよりも絶対的かつ普遍的により楽しいという事実からも言えるのである。
両者の優劣を理屈で計り知りたいものは、四書五経と犯罪聖書を比較査読すればいいし、
理屈ではなく感覚で悟りたいというのなら、ただより楽しいものが何なのかを見極めればよい。
それらの努力を尽くしたならば、誰しもが勧善懲悪の楽しみを採り、悪逆非道の楽しみを
棄てるであろう。楽しみを尽くそうともしないような所でこそ、そうでないこともあるだろう。
体系的に推進して行こうとするものもいなかったから、悪の楽しみこそを開き直って、
それこそを権威化してしまうようなことまでもが聖書信仰として生じてしまいもした。
いわゆる「鳥なき里のコウモリ」というやつで、もしも儒学のような勧善懲悪の楽しみを
推進する教学があったなら、決してでかい顔もできないでいたものである。実際に、
アブラハム教にしては勧善懲悪的な傾向のあるイスラムがムハンマドによって創始された
後には、古代オリエントに相当する中東社会からは聖書信仰もその地位を追われたのである。
勧善懲悪の楽しみの権威化と、悪逆非道の楽しみの権威化とは排他的な関係にあり、
なおかつ勧善懲悪の楽しみの権威化のほうが「優性」であり、悪逆非道の楽しみの権威化のほうが
「劣性」である。両者が並存している以上は、必ず勧善懲悪の楽しみの権威化のほうが勝ち、
悪逆非道の楽しみの権威化のほうが負ける。それは、勧善懲悪の楽しみの体系化である
四書五経の言葉が、悪逆非道の楽しみの体系化である犯罪聖書の言葉と比べて見るからに正しい
ということからも言えるし、善因楽果悪因苦果の罪福異熟の真理に即して、勧善懲悪の楽しみの
ほうが悪逆非道の楽しみよりも絶対的かつ普遍的により楽しいという事実からも言えるのである。
両者の優劣を理屈で計り知りたいものは、四書五経と犯罪聖書を比較査読すればいいし、
理屈ではなく感覚で悟りたいというのなら、ただより楽しいものが何なのかを見極めればよい。
それらの努力を尽くしたならば、誰しもが勧善懲悪の楽しみを採り、悪逆非道の楽しみを
棄てるであろう。楽しみを尽くそうともしないような所でこそ、そうでないこともあるだろう。
「先君周公の周礼を制して曰うに、則を以て徳を観、徳を以て事を処し、事を以て功を度り、
功を以て民を食せしむと。誓命を作りてく、則を毀つを賊と為し、族を掩うを蔵と為し、賄を竊むを盗と為し、
器を盗むを姦と為す、蔵を主として之れに名し、姦を頼みて之れを用いるを大凶徳と為す、常有りて赦す無しと」
「先君の周公は周礼を制定し、法をよく守るかどうかによって徳の厚薄をも見極められた。徳の厚薄によって
人事も処理し、その功績如何によって臣下を大小の国へと振り分けて封じもした。誓命を作り、『不法を為すのを
賊罪とし、賊を匿うのを蔵罪とし、金品を盗むことを盗罪とし、国宝を盗むことを姦罪とする。賊をかくまってこれに
悪名を付与し、国宝を盗んで私財とすることを最悪の大凶徳とする。常法に照らして処刑し、赦すこともない』ともした。
(不法を赦さぬだけでなく、模範的な遵法者に褒賞を与えてもいた。法治支配にも徳政を付与する
程にも旺盛な積善志向があればこそ、不法を赦さぬことにかけても毅然としていられたのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・文公十八年より)
功を以て民を食せしむと。誓命を作りてく、則を毀つを賊と為し、族を掩うを蔵と為し、賄を竊むを盗と為し、
器を盗むを姦と為す、蔵を主として之れに名し、姦を頼みて之れを用いるを大凶徳と為す、常有りて赦す無しと」
「先君の周公は周礼を制定し、法をよく守るかどうかによって徳の厚薄をも見極められた。徳の厚薄によって
人事も処理し、その功績如何によって臣下を大小の国へと振り分けて封じもした。誓命を作り、『不法を為すのを
賊罪とし、賊を匿うのを蔵罪とし、金品を盗むことを盗罪とし、国宝を盗むことを姦罪とする。賊をかくまってこれに
悪名を付与し、国宝を盗んで私財とすることを最悪の大凶徳とする。常法に照らして処刑し、赦すこともない』ともした。
(不法を赦さぬだけでなく、模範的な遵法者に褒賞を与えてもいた。法治支配にも徳政を付与する
程にも旺盛な積善志向があればこそ、不法を赦さぬことにかけても毅然としていられたのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・文公十八年より)
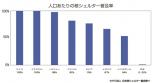 欧米の聖書信仰者ほど、「この世での身勝手な安寧」を追い求めてきた人種民族も他にない。
欧米の聖書信仰者ほど、「この世での身勝手な安寧」を追い求めてきた人種民族も他にない。 ある程度以上に成熟した社会的な人間であるなら、安寧を求めることの大切さも知っている。
世界でも最も好戦的な部類に当たるイスラム教徒ですら、「アッサラーム・アレイクム(神の下での平和を)」
を一つの合言葉としている。ただ、その安寧の求め方が民族や宗教圏などによって様々であり、
イスラム圏は「神の下での平和」というとおり、イスラム教圏内に限っての平和の確立を第一とする。
ヒンズー教や小乗仏教が安寧を企図するのも自分たちの教義に帰依する宗教圏であり、それは
超国家規模となることもあれば、国家の一部に限られることもある。必ずしも国家という体裁に
はまることなく人々を安寧に導こうとするのがこれらの信教である一方、「国家鎮護」を一大教義に
据える大乗仏教などは、一国家全体の安寧を企図しようとする側面がある。密教僧も国家の安寧のために
護摩を焚き、禅僧も「皇帝(天皇)陛下万歳」と謳って重大な為政の外的な顧問となったりする。
そのため、儒学を正式な政治学に据える昔の中国や日本などでも大乗仏教は重宝された。そして
儒学が国家の徳治を専門とする教学であることは、君臣の義を重んずるその学理体系からも明らかなことである。
国家規模の安寧を企図するのであれ、宗教帰依者の安寧を企図するのであれ、大抵の教学には
社会的な安寧を実現していく上での体系性というものが備わっている。それがほとんどないか、
あってもかりそめで稚拙なもの止まりでしかなかったのがユダヤ=キリスト両聖書信仰であり、
純粋な聖書教義のみに基づくのであれば、「私は剣をもたらしに来た」というイエスの暴言などに従って
延々と戦乱状態に没入しているしかない。しかし、そもそも聖書の教義(特に新約の教義)には
実践不能な部分が多々あり、イエスの行いに倣って自殺行為で死んでみたところで、聖書の記述どおりに
復活して天国に召されるなどということも決してないわけだから、最原初の頃からアウグスチヌスが
聖書の教義とは無縁な自殺の禁止をキリスト教徒に強いるなど、実践面での乖離を来たし始めていたのである。
その結果、信者たちはそれぞれに我流での安寧を勝手に追い求めるようになり、
儒学のような権力道徳はおろか、他の宗教教義に基づいて体系的な安寧を得る場合以上にも、
稚拙な安寧ばかりを追い求めては失敗を繰り返すザマと化してしまったのである。
その伝統的な稚拙さが今でも色濃く残っているのがイギリスであり、世界中に侵略の魔の手を広げての
覇権を追い求めながら、当のイギリス自体がイングランドやスコットランドやアイルランドに分裂したままでいる。
国内での階級格差も絶対的であるのみならず、格差が富の占有率に完全に比例してしまっており、
他国人と比べても貴族階級が非常識な規模の不労所得に与れている一方、労働者階級はこれまた
一般的な資本主義国の人間並み以上の貧しさに置かれ続けている。それもこれも、イギリス人が狂った
世相を追い求めていたがためではなく、イギリス人が個々人で身勝手な安寧ばかりを追い求め続けて
来たがための所産であり、イギリス人といえどもそれぞに安寧を欲していたことには変わりない。
イギリスからの移民が主な支配層を占めている今のアメリカも、やはり国家として奇形的な体裁を多々持っており、
対外的には連邦政府の長たる大統領がいかにも「アメリカの顔」的な立場を見せ付けているが、国内で多くの
実権を保持しているのは州政府であり、日本などでは国そのものが付与する弁護士や税理士などの資格も
各州政府が付与している。オバマ大統領がいくら「American people(アメリカ国民)」という言葉を多様しようとも、
アメリカ人たち自身は自分たちを「citizen(市民)」と呼び、国そのものに対する帰服からは一歩も二歩も
距離を置いている。国民としての自覚意識が希薄であるのは米英人ともに共通しており、故にこそ米大統領や
英女王といった個人のみを熱狂的な支持対象ともする。それは国に対しても、信教に対しても安寧の求め所を
人々が定めきれなかったがための苦肉の姿なのであり、国家や信教の下で磐石の安寧に与れた人々と比べれば、
英米人を始めとする欧米キリスト教徒は、安寧を求めることにかけて根本から不遇であり続けてきたのである。
儒学のような権力道徳はおろか、他の宗教教義に基づいて体系的な安寧を得る場合以上にも、
稚拙な安寧ばかりを追い求めては失敗を繰り返すザマと化してしまったのである。
その伝統的な稚拙さが今でも色濃く残っているのがイギリスであり、世界中に侵略の魔の手を広げての
覇権を追い求めながら、当のイギリス自体がイングランドやスコットランドやアイルランドに分裂したままでいる。
国内での階級格差も絶対的であるのみならず、格差が富の占有率に完全に比例してしまっており、
他国人と比べても貴族階級が非常識な規模の不労所得に与れている一方、労働者階級はこれまた
一般的な資本主義国の人間並み以上の貧しさに置かれ続けている。それもこれも、イギリス人が狂った
世相を追い求めていたがためではなく、イギリス人が個々人で身勝手な安寧ばかりを追い求め続けて
来たがための所産であり、イギリス人といえどもそれぞに安寧を欲していたことには変わりない。
イギリスからの移民が主な支配層を占めている今のアメリカも、やはり国家として奇形的な体裁を多々持っており、
対外的には連邦政府の長たる大統領がいかにも「アメリカの顔」的な立場を見せ付けているが、国内で多くの
実権を保持しているのは州政府であり、日本などでは国そのものが付与する弁護士や税理士などの資格も
各州政府が付与している。オバマ大統領がいくら「American people(アメリカ国民)」という言葉を多様しようとも、
アメリカ人たち自身は自分たちを「citizen(市民)」と呼び、国そのものに対する帰服からは一歩も二歩も
距離を置いている。国民としての自覚意識が希薄であるのは米英人ともに共通しており、故にこそ米大統領や
英女王といった個人のみを熱狂的な支持対象ともする。それは国に対しても、信教に対しても安寧の求め所を
人々が定めきれなかったがための苦肉の姿なのであり、国家や信教の下で磐石の安寧に与れた人々と比べれば、
英米人を始めとする欧米キリスト教徒は、安寧を求めることにかけて根本から不遇であり続けてきたのである。
安寧の拠り所を国家に求めるべきか、信教に求めるべきかは、それぞれの地域社会によって適性が異なる。
日本などはちょうどいい大きさの島国であるため、学問と信教と祭祀との全てが国家を基調として規律されている。
東南アジアなどはまちまちであり、仏教国だったりイスラム国だったり、多宗教の混在する国だったりする。
ただ、人間にとっての安寧の拠り所として最適なのは国家か信教かのいずれかであり、個々人の身勝手でそれぞれに
安寧を求めたりするのでは、結果として社会規模での安寧が余計に損なわれたりするのだとも知らねばならない。
そして聖書信仰はそもそも、人々に安寧を付与する信教ではなかったのだとも了承するのである。
「君子は其の位に素して行い、其の外を願わず。〜患難に素しては患難に行う」
「君子はそれぞれの状況において相応の行いを心がけ、不相応な願いなどにはかられない。
患難に際しては、患難に対するに相応の行いを心がける。(患難に対するに相応の行いとは、たとえば
慎重さに万全を期することなどであろう。来世昇天などの不相応な願いがあれば、蛮勇を帯びたりもする)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・一四より)
日本などはちょうどいい大きさの島国であるため、学問と信教と祭祀との全てが国家を基調として規律されている。
東南アジアなどはまちまちであり、仏教国だったりイスラム国だったり、多宗教の混在する国だったりする。
ただ、人間にとっての安寧の拠り所として最適なのは国家か信教かのいずれかであり、個々人の身勝手でそれぞれに
安寧を求めたりするのでは、結果として社会規模での安寧が余計に損なわれたりするのだとも知らねばならない。
そして聖書信仰はそもそも、人々に安寧を付与する信教ではなかったのだとも了承するのである。
「君子は其の位に素して行い、其の外を願わず。〜患難に素しては患難に行う」
「君子はそれぞれの状況において相応の行いを心がけ、不相応な願いなどにはかられない。
患難に際しては、患難に対するに相応の行いを心がける。(患難に対するに相応の行いとは、たとえば
慎重さに万全を期することなどであろう。来世昇天などの不相応な願いがあれば、蛮勇を帯びたりもする)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・一四より)
夢を見る就寝状態はレム睡眠で眠りが浅く、夢を見ない就寝状態はノンレム睡眠で眠りが深い。
熟睡状態のほうが十分に脳までもが休みを取れて、次の日などに疲れを持ち越すこともない。
実際には一夜の就寝中に人間はレム睡眠とノンレム睡眠を繰り返している場合がほとんどだから、
熟睡状態であるノンレム睡眠をいかに効率的に行うかが、人間の健康にとっての鍵ともなる。
おもいっきり運動や仕事をしまくって寝付いたりしたなら、簡単に熟睡状態に入れる。
それは難しいことじゃないが、むやみやたらに自分の身体を疲れさせた反動でしかないわけだから、
それで健康が増進されるというわけでもない。そもそも運動や仕事をしまくったから熟睡できる、
そういうわけでもないから熟睡できないというのなら、人間は活動が消極的である中に、
健全な睡眠を阻害する悪質な要素ばかりを湛えているということにもなってしまう。
実際には、そうであることもあれば、そうでないこともある。
日々、洋学知識や聖書教義などにも即した粗悪で卑俗な思考や一般生活ばかりを営んでいたなら、
特に大きな活動を為すわけでもない消極的なあり方というものが、それだけでも精神的不衛生に
まみれたものとなるわけで、そのせいでなかなか寝付けなかったり、寝付いても眠りが浅かったり
といった問題に悩まされることともなる。一方で、禅僧あたりが営んでいるようなごくごく健全な
無念無想の清貧生活を続けたなら、それこそ「座睡」でも十分な睡眠が取れるようになるという。
「人間は睡眠中に生気を養い、覚醒中にそれを用いる、ただその用い方が粗暴であるようなら、
だんだん生気が覆われて本来の善性を見失ってしまう」というのが孟子の睡眠論(告子章句上・八)
であるが、これはむしろ基本的な「境界例」の話であり、覚醒中の粗暴さを極度化させてしまった
人間はもはや睡眠中に生気を養うことすら疎かになってしまうし、逆に覚醒中の安静にも務めたなら、
今度は睡眠すら座睡で済ませられるぐらいに、就寝中の生気の養いが十二分なものとなる。
熟睡状態のほうが十分に脳までもが休みを取れて、次の日などに疲れを持ち越すこともない。
実際には一夜の就寝中に人間はレム睡眠とノンレム睡眠を繰り返している場合がほとんどだから、
熟睡状態であるノンレム睡眠をいかに効率的に行うかが、人間の健康にとっての鍵ともなる。
おもいっきり運動や仕事をしまくって寝付いたりしたなら、簡単に熟睡状態に入れる。
それは難しいことじゃないが、むやみやたらに自分の身体を疲れさせた反動でしかないわけだから、
それで健康が増進されるというわけでもない。そもそも運動や仕事をしまくったから熟睡できる、
そういうわけでもないから熟睡できないというのなら、人間は活動が消極的である中に、
健全な睡眠を阻害する悪質な要素ばかりを湛えているということにもなってしまう。
実際には、そうであることもあれば、そうでないこともある。
日々、洋学知識や聖書教義などにも即した粗悪で卑俗な思考や一般生活ばかりを営んでいたなら、
特に大きな活動を為すわけでもない消極的なあり方というものが、それだけでも精神的不衛生に
まみれたものとなるわけで、そのせいでなかなか寝付けなかったり、寝付いても眠りが浅かったり
といった問題に悩まされることともなる。一方で、禅僧あたりが営んでいるようなごくごく健全な
無念無想の清貧生活を続けたなら、それこそ「座睡」でも十分な睡眠が取れるようになるという。
「人間は睡眠中に生気を養い、覚醒中にそれを用いる、ただその用い方が粗暴であるようなら、
だんだん生気が覆われて本来の善性を見失ってしまう」というのが孟子の睡眠論(告子章句上・八)
であるが、これはむしろ基本的な「境界例」の話であり、覚醒中の粗暴さを極度化させてしまった
人間はもはや睡眠中に生気を養うことすら疎かになってしまうし、逆に覚醒中の安静にも務めたなら、
今度は睡眠すら座睡で済ませられるぐらいに、就寝中の生気の養いが十二分なものとなる。
一般的な社会人としては、睡眠で養った生気を健全な社会活動のために消費するのが最善である。
就寝中の生気の養いすら阻害するほどにも粗悪な社会活動に及ぶぐらいなら何もしないでいる、
何もしないでいる中にも禅寺での生活のような清廉さを保つことで、精神的不衛生を省いていく。
睡眠中の生気の養いを阻害する程にも、粗暴な活動に及ぶものこそは、やったらめったらな活動に
よってひどく肉体を酷使し、極度の身体の疲労からなる強制的な熟睡を追い求めるようにもなる。
これこそは「活動的な馬鹿」の悪循環であり、その行いもまた「極度に旺盛な悪逆非道」という
目も当てられないような代物となる。ここに、人間が旺盛な悪行を持続的に為してしまう原理も
また存在するのであり、このような問題を生じさせないためには、粗暴な活動を控えさせることと、
粗暴な活動や生活を控えた所にこそ、極度の肉体的疲労からなる熟睡などを追い求めるまでも
ないような、充実した睡眠生活が実在していることを認知させていくこととの両方が必要となる。
そのために最も有効となるのは、禅仏教の興隆だったりもする。禅門自体は社会的な勧善懲悪を
推進していく主体とはならないが、生気を養うことよりは、勧善懲悪のために消費していく
ことを旨とする儒学の社会的な実践者などが、生気を養うことにかけての模範となるとも限らない。
弟子の楽世子が魯国の宰相となったことが嬉しいあまり寝付けなくなったという孟子の逸話なども、
微笑ましい話ではあるが、生気を養う模範としてはやはり孟子が「亜聖」止まりであった証拠と
なる逸話ともなっている。権力への直接介入を断つ禅僧ぐらいの境地から初めて、安静な生活と
適切な睡眠によって生気を養う純粋な模範とするに相応しい存在となっていくのである。
「寝ぬるに言わず」
「就寝中は話をしない。(貝原益軒『養生訓』にも『就寝時はなるべく目を閉じておく』とある。
就寝中にまで活動を差し挟むのは、礼節や陰陽法則に即しても吉祥であるとはいえない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・郷党第十・八より)
就寝中の生気の養いすら阻害するほどにも粗悪な社会活動に及ぶぐらいなら何もしないでいる、
何もしないでいる中にも禅寺での生活のような清廉さを保つことで、精神的不衛生を省いていく。
睡眠中の生気の養いを阻害する程にも、粗暴な活動に及ぶものこそは、やったらめったらな活動に
よってひどく肉体を酷使し、極度の身体の疲労からなる強制的な熟睡を追い求めるようにもなる。
これこそは「活動的な馬鹿」の悪循環であり、その行いもまた「極度に旺盛な悪逆非道」という
目も当てられないような代物となる。ここに、人間が旺盛な悪行を持続的に為してしまう原理も
また存在するのであり、このような問題を生じさせないためには、粗暴な活動を控えさせることと、
粗暴な活動や生活を控えた所にこそ、極度の肉体的疲労からなる熟睡などを追い求めるまでも
ないような、充実した睡眠生活が実在していることを認知させていくこととの両方が必要となる。
そのために最も有効となるのは、禅仏教の興隆だったりもする。禅門自体は社会的な勧善懲悪を
推進していく主体とはならないが、生気を養うことよりは、勧善懲悪のために消費していく
ことを旨とする儒学の社会的な実践者などが、生気を養うことにかけての模範となるとも限らない。
弟子の楽世子が魯国の宰相となったことが嬉しいあまり寝付けなくなったという孟子の逸話なども、
微笑ましい話ではあるが、生気を養う模範としてはやはり孟子が「亜聖」止まりであった証拠と
なる逸話ともなっている。権力への直接介入を断つ禅僧ぐらいの境地から初めて、安静な生活と
適切な睡眠によって生気を養う純粋な模範とするに相応しい存在となっていくのである。
「寝ぬるに言わず」
「就寝中は話をしない。(貝原益軒『養生訓』にも『就寝時はなるべく目を閉じておく』とある。
就寝中にまで活動を差し挟むのは、礼節や陰陽法則に即しても吉祥であるとはいえない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・郷党第十・八より)
人間は、道具をうまく取り扱って行くことを通じて、サルからヒトへと進化した。
人間の男のヒゲはほっとけばどこまでも伸び続けるが、サルのオスの顔の毛がどこまでも
伸び続けることはない。これは、人間の先祖である猿人のオスが、研ぎあげた石や貝殻などの
刃物で口元の毛を整えることを志し始めたことの名残りであり、そのように刃物などの
高度な扱いを研鑽していくことを通じて、人間も今に至るまでの進化を遂げてきたのである。
ヒゲか伸びるのは人間では基本男だけで、女はヒゲが生えもしない。
これは、人間のうちでは女ではなく男こそが道具の扱いを研鑽していく主体であり続けて来た
証拠となっている。個人差はあるものの、男と女では男のほうが道具にこだわりを持つ一方、
女はさほど道具などにこだわらない場合が多い。女が高度な行員作業に携わることも
なくはないが、最大級に道具を有用に扱うことにかけてはやはり男のほうが優れている。
易学に即しても、道具を持つということが陽剛であり、道具を持たないということが陰柔であるとされる。
だから刀剣を持って闘う剣術が「陽の武術」とされる一方、徒手空拳が基本である柔術は「陰の武術」ともされる。
陰陽でいえば陽にあたる男のほうが道具にこだわりたがる一方、陰にあたる女はあまり道具にこだわろうともしない。
武家社会でも、陽剛な君子階級の男こそは大小二本の刀を持つ一方、陰柔な女子供と平民の男は基本丸腰でもいた。
敗戦後の武装解除の後、GHQらの画策によって空手やプロレスなどの非武道の格闘技が日本で
大いに持て囃されてブームともなったりしたため、まるで「丸腰こそは男らしさの証し」のように
思い込まれるようにもなってしまったが、本来、丸腰は陰陽でいえば陰、男か女かでいえば女の領分である。
実際に、どんな格闘技で鍛えぬいた猛者といえども、重火器で武装した軍人などに力で敵うわけじゃない。
本当に現実から最強であることによって女子供を守りもするのが男の使命なのだから、そのための手段を丸腰
ばかりに頼るのは片手落ちとしかならない。最強であるために道具をも用いてこその「真の男」なのだといえる。
人間の男のヒゲはほっとけばどこまでも伸び続けるが、サルのオスの顔の毛がどこまでも
伸び続けることはない。これは、人間の先祖である猿人のオスが、研ぎあげた石や貝殻などの
刃物で口元の毛を整えることを志し始めたことの名残りであり、そのように刃物などの
高度な扱いを研鑽していくことを通じて、人間も今に至るまでの進化を遂げてきたのである。
ヒゲか伸びるのは人間では基本男だけで、女はヒゲが生えもしない。
これは、人間のうちでは女ではなく男こそが道具の扱いを研鑽していく主体であり続けて来た
証拠となっている。個人差はあるものの、男と女では男のほうが道具にこだわりを持つ一方、
女はさほど道具などにこだわらない場合が多い。女が高度な行員作業に携わることも
なくはないが、最大級に道具を有用に扱うことにかけてはやはり男のほうが優れている。
易学に即しても、道具を持つということが陽剛であり、道具を持たないということが陰柔であるとされる。
だから刀剣を持って闘う剣術が「陽の武術」とされる一方、徒手空拳が基本である柔術は「陰の武術」ともされる。
陰陽でいえば陽にあたる男のほうが道具にこだわりたがる一方、陰にあたる女はあまり道具にこだわろうともしない。
武家社会でも、陽剛な君子階級の男こそは大小二本の刀を持つ一方、陰柔な女子供と平民の男は基本丸腰でもいた。
敗戦後の武装解除の後、GHQらの画策によって空手やプロレスなどの非武道の格闘技が日本で
大いに持て囃されてブームともなったりしたため、まるで「丸腰こそは男らしさの証し」のように
思い込まれるようにもなってしまったが、本来、丸腰は陰陽でいえば陰、男か女かでいえば女の領分である。
実際に、どんな格闘技で鍛えぬいた猛者といえども、重火器で武装した軍人などに力で敵うわけじゃない。
本当に現実から最強であることによって女子供を守りもするのが男の使命なのだから、そのための手段を丸腰
ばかりに頼るのは片手落ちとしかならない。最強であるために道具をも用いてこその「真の男」なのだといえる。
道具というのは、富よりもさらに以前にあるものである。
食物を貯蔵するための壷などの容器が作製されたことで、初めて富というものもまたその具体性を持ち始めた。
道具の扱いが十分に手堅ければ、自然と富の扱いも真っ当なものとなる一方、道具の扱いが疎かであるようなら、
富の扱いも粗雑になる。縄文時代の頃から注連縄信仰などを通じて「縄」の扱いを貴んできた日本では、
世界でもぶっちぎりに早くの内から奴隷拘束などの悪習が絶やされてきた一方、そんな慣習のない海外では、
ほんの前世紀まで奴隷の手足を縄で縛って売り買いするようなことが平気で横行してもいた。
物品から人材に至るまで、あらゆる富の扱いを正しからしめるためにも、道具の扱いから人はよく
貴んでいく必要があり、それが十分であれば富を無闇に貪ることも、富を完全に捨て去ったりすることも、
どちらの必要もなくなるのである。それは持ち物、具足全般を透徹して大事に扱うということにもなるのであり、
人々が最大級に充実した文明生活を営むために最適となる姿勢でもある。富も名誉も捨て去るなんていう以前に、
そこにこそ文明人としてのごく健全なあり方が存在しているのである。
「孔子は先ず簿して祭器を正し、四方の食を以って簿正に供せしめざらしむ」
「孔先生は古えの礼法に則って神前の祭器を正し、乱獲した方々の供物などを祭祀に用いられないようにした。
(祭祀への供物を廃止するのではなく、祭器を正すことでその限度を厳しく規定し、乱獲などの悪習を止めた。
トーラーの祭壇描写なども無闇に豪勢だが、このような中庸に適った神に対する振る舞いは、
当時のパリサイ人にもイエスにも、両方共に全く欠けていたのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・万章章句下・四)
食物を貯蔵するための壷などの容器が作製されたことで、初めて富というものもまたその具体性を持ち始めた。
道具の扱いが十分に手堅ければ、自然と富の扱いも真っ当なものとなる一方、道具の扱いが疎かであるようなら、
富の扱いも粗雑になる。縄文時代の頃から注連縄信仰などを通じて「縄」の扱いを貴んできた日本では、
世界でもぶっちぎりに早くの内から奴隷拘束などの悪習が絶やされてきた一方、そんな慣習のない海外では、
ほんの前世紀まで奴隷の手足を縄で縛って売り買いするようなことが平気で横行してもいた。
物品から人材に至るまで、あらゆる富の扱いを正しからしめるためにも、道具の扱いから人はよく
貴んでいく必要があり、それが十分であれば富を無闇に貪ることも、富を完全に捨て去ったりすることも、
どちらの必要もなくなるのである。それは持ち物、具足全般を透徹して大事に扱うということにもなるのであり、
人々が最大級に充実した文明生活を営むために最適となる姿勢でもある。富も名誉も捨て去るなんていう以前に、
そこにこそ文明人としてのごく健全なあり方が存在しているのである。
「孔子は先ず簿して祭器を正し、四方の食を以って簿正に供せしめざらしむ」
「孔先生は古えの礼法に則って神前の祭器を正し、乱獲した方々の供物などを祭祀に用いられないようにした。
(祭祀への供物を廃止するのではなく、祭器を正すことでその限度を厳しく規定し、乱獲などの悪習を止めた。
トーラーの祭壇描写なども無闇に豪勢だが、このような中庸に適った神に対する振る舞いは、
当時のパリサイ人にもイエスにも、両方共に全く欠けていたのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・万章章句下・四)
神が契約を反故にしたのではなく、そもそも聖書の神などは実在しなかった。
新旧約聖書なんてものからして、拘束下に置かれた政商や、自暴自棄と化した妾腹の私生児の
怨みつらみの吐露の寄せ集めでしかなかった。そうであることが判明したのは昨今のことだが、
実際そうであればこそ、聖書圏の人間は昔からひどくルサンチマンを帯びてもいた。
自分たちの信仰対象が新旧約であるものだから、本当のところ怨みつらみの塊でしかない
新旧約の記述に即して、自分たちまでもが旺盛な嫉妬心を湛えることになってしまったのだった。
コーランやハディースの教えを啓示したとされるムハンマドは、「文盲」だったという。
だから文化的な有機性というものをあまり解さなかった一方、「文弱」でもあり得なかった。
そういった傾向はイスラム教徒たちにも落とし込まれていて、ムスリムも正直、粗暴である
ように見受けられることはあるが、同時に聖書信者が帯びているようなルサンチマンなどはほとんど
見られない場合が多い。嫉妬心などというものは文弱なものこそが抱くものだから、文盲としての
ムハンマドの良い面が落とし込まれた結果として、ムスリムも嫉妬的ではなくなったのだといえる。
アブラハム教徒の内だけを見ても、キリスト教徒やユダヤ教徒はひどく嫉妬的である一方、
イスラム教徒はそんなに嫉妬的だったりすることもない。この点について、世界標準に近いと
いえるのはイスラム教徒のほうであるといえ、インド人や東南アジア人や中国人や日本人なども、
それぞれに性格の違いはあるにしても、聖書信者ほどにも嫉妬心まみれでいたりすることは少ない。
結局、聖書こそが今の世界中の主な嫉妬心の源流ともなっている。韓国人などもキリスト信仰に
即して自分たちの嫉妬心を倍化させ、朝鮮戦争で米露人に国土を荒廃化させられた怨みを戦前の
日本人に転嫁して、あてはずれな謝罪や賠償を日本に要求し続けている。そんな厚顔無恥な振る舞いを
今の韓国人がしていられるのも、自分たちが聖書信者であればこそであり、聖書信仰が人間の嫉妬心を
異常なほどにまで増幅させて、冤罪すらよしとさせてしまうことを実証する材料ともなっているのである。
新旧約聖書なんてものからして、拘束下に置かれた政商や、自暴自棄と化した妾腹の私生児の
怨みつらみの吐露の寄せ集めでしかなかった。そうであることが判明したのは昨今のことだが、
実際そうであればこそ、聖書圏の人間は昔からひどくルサンチマンを帯びてもいた。
自分たちの信仰対象が新旧約であるものだから、本当のところ怨みつらみの塊でしかない
新旧約の記述に即して、自分たちまでもが旺盛な嫉妬心を湛えることになってしまったのだった。
コーランやハディースの教えを啓示したとされるムハンマドは、「文盲」だったという。
だから文化的な有機性というものをあまり解さなかった一方、「文弱」でもあり得なかった。
そういった傾向はイスラム教徒たちにも落とし込まれていて、ムスリムも正直、粗暴である
ように見受けられることはあるが、同時に聖書信者が帯びているようなルサンチマンなどはほとんど
見られない場合が多い。嫉妬心などというものは文弱なものこそが抱くものだから、文盲としての
ムハンマドの良い面が落とし込まれた結果として、ムスリムも嫉妬的ではなくなったのだといえる。
アブラハム教徒の内だけを見ても、キリスト教徒やユダヤ教徒はひどく嫉妬的である一方、
イスラム教徒はそんなに嫉妬的だったりすることもない。この点について、世界標準に近いと
いえるのはイスラム教徒のほうであるといえ、インド人や東南アジア人や中国人や日本人なども、
それぞれに性格の違いはあるにしても、聖書信者ほどにも嫉妬心まみれでいたりすることは少ない。
結局、聖書こそが今の世界中の主な嫉妬心の源流ともなっている。韓国人などもキリスト信仰に
即して自分たちの嫉妬心を倍化させ、朝鮮戦争で米露人に国土を荒廃化させられた怨みを戦前の
日本人に転嫁して、あてはずれな謝罪や賠償を日本に要求し続けている。そんな厚顔無恥な振る舞いを
今の韓国人がしていられるのも、自分たちが聖書信者であればこそであり、聖書信仰が人間の嫉妬心を
異常なほどにまで増幅させて、冤罪すらよしとさせてしまうことを実証する材料ともなっているのである。
一般人が聖書信者と対面させられた時に違和感を抱かされるのが、何もかもにかけて、
旺盛な嫉妬心ばかりを大前提として、ものを考えたり、言ったりやったりしようとする所である。
そんな嫉妬心が自分たちにはないものだから、「どうしてそこまで下衆な態度でしかいられないのだろう」
という疑問を抱かされるほかはないわけだが、それもやはり、聖書の記述に即して自然と帯びてしまった
態度なのである。健全な精神の持ち主からすれば、そのような態度は不快なものだし、本人たち自身
からして自業自得の不快さにまみれているだろうと考えるほかはないわけだが、ちょうどマゾヒスト
のような性向に根ざして、聖書信者も自らの態度の不快さを快楽だと倒錯してしまっているのである。
とはいえ、そんな倒錯は普遍的に通用するものではなく、実際のところ聖書信者たち自身もやはり、
自分たちの下衆な態度からなる自業自得の不快さを相当に苦しんでもいる、苦しんでいるからこそ、
その苦しみを紛らわすはけ口を外界侵略や異教徒迫害などの悪逆非道に求めざるを得なかったのである。
新旧約の神などが実在しない、聖書など古代ユダヤ人の怨みつらみの殴り書きでしかないということが
判明したのは、一般人だけでなく、聖書信者たちにとってもめでたいことである。今までは神を信じる
ために聖書を信じていた、その結果として否応なくルサンチマンをも抱いてしまったという言い訳が
立てられたわけだが、これからはそんな言い訳も通用しない。だからこそ、信者に深刻なルサンチマンを
植え付けるだけの代物でしかない聖書への信仰なぞを、惜しみなく捨て去れるようにもなったのだから。
これで現聖書信者たちも、嫉妬心からなる自業自得の不快さから解放されて、万々歳というものである。
「明らかならずして晦し、初め天に登り、後に地に入る。
初め天に登るは、四国を照らすなり。後地に入るは、則を失えばなり」
「徳に明らかでない暗愚の支配者が世界中を罪悪まみれの支配下に置く。
始めは天にも昇るようであるが、後には規則性を失って地獄に堕ちることになる」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・明夷・上六‐彖伝より )
旺盛な嫉妬心ばかりを大前提として、ものを考えたり、言ったりやったりしようとする所である。
そんな嫉妬心が自分たちにはないものだから、「どうしてそこまで下衆な態度でしかいられないのだろう」
という疑問を抱かされるほかはないわけだが、それもやはり、聖書の記述に即して自然と帯びてしまった
態度なのである。健全な精神の持ち主からすれば、そのような態度は不快なものだし、本人たち自身
からして自業自得の不快さにまみれているだろうと考えるほかはないわけだが、ちょうどマゾヒスト
のような性向に根ざして、聖書信者も自らの態度の不快さを快楽だと倒錯してしまっているのである。
とはいえ、そんな倒錯は普遍的に通用するものではなく、実際のところ聖書信者たち自身もやはり、
自分たちの下衆な態度からなる自業自得の不快さを相当に苦しんでもいる、苦しんでいるからこそ、
その苦しみを紛らわすはけ口を外界侵略や異教徒迫害などの悪逆非道に求めざるを得なかったのである。
新旧約の神などが実在しない、聖書など古代ユダヤ人の怨みつらみの殴り書きでしかないということが
判明したのは、一般人だけでなく、聖書信者たちにとってもめでたいことである。今までは神を信じる
ために聖書を信じていた、その結果として否応なくルサンチマンをも抱いてしまったという言い訳が
立てられたわけだが、これからはそんな言い訳も通用しない。だからこそ、信者に深刻なルサンチマンを
植え付けるだけの代物でしかない聖書への信仰なぞを、惜しみなく捨て去れるようにもなったのだから。
これで現聖書信者たちも、嫉妬心からなる自業自得の不快さから解放されて、万々歳というものである。
「明らかならずして晦し、初め天に登り、後に地に入る。
初め天に登るは、四国を照らすなり。後地に入るは、則を失えばなり」
「徳に明らかでない暗愚の支配者が世界中を罪悪まみれの支配下に置く。
始めは天にも昇るようであるが、後には規則性を失って地獄に堕ちることになる」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・明夷・上六‐彖伝より )
ある社会における人々に対する課税の種類や税率を制定するのは、国や自治体などの為政者の仕事である。
徴税人はその税制に即した税を徴収するだけの役割を持ち、自分で税制をどうにかできるわけではない。
もしも為政者が社会の情勢に合致した適正な税制の執行を徴税人に請け負わせたなら、徴税人もまた
徳治の一翼を担う立派な役割になるといえる。一方、為政者が時世に添わないおかしな税制の執行を
徴税人に請け負わせたりしたなら、今度は徴税人までもが権力犯罪の従犯ということになってしまう。
税が重すぎても権力犯罪になるし、軽すぎても権力犯罪になる。重税で民を痛め付けることが、
民の側から見ていかにも犯罪的なものとして取り扱われることが多いのは世の常であるが、
逆に政府などが民(特に素封家など)に対して最低限課して行くべき税すらをもおろそかにした結果、
貧富の格差を極度に広げてしまい、その挙句の国家社会の経済破綻を招いてしまったりすることもある。
これも権力者にとっての道義的な犯罪であるといえ、税制はただ優しいばかりでもいけない理由になっている。
民から徴集した税を糧として、士人階級の人間がトップダウンに世の中を取り仕切っていくのでなければ、
実際問題世の中も持たない、だから税制も必要だし、税制を執行する徴税人も世の中にとって必須な存在である。
上記のようなやむない理由で、徴税人が「権力犯罪者の従犯」という罪を帯びてしまうことも無くは
ないにしろ、徴税という仕事自体はむしろ世のため人のために存在するものなのだから、決して「賤業」
などとして取り扱うべきではないし、ましてや、罪人と同等に扱ったりするのはもってのほかだと言える。
仮に百人の人間がいたとして、救われる価値のある者から順々に救われていくとした場合、
徴税人は五十番目前後ぐらいに当てはまるだろうことが予想される。適正な税制を執行していれば
五十番目以内に入るだろうし、不正な税制を執行していれば五十番目以下となるだろう。いずれにしろ、
徴税人自身が税制を取り決められているわけではないのだから、そんなに順位が高下することもない。
百人いれば一番最後の百番目に救われるか、もしくは救われないかといったところである
本物の犯罪者などと比べれば、徴税人も随分と高いほうの順位にあるといえる。
徴税人はその税制に即した税を徴収するだけの役割を持ち、自分で税制をどうにかできるわけではない。
もしも為政者が社会の情勢に合致した適正な税制の執行を徴税人に請け負わせたなら、徴税人もまた
徳治の一翼を担う立派な役割になるといえる。一方、為政者が時世に添わないおかしな税制の執行を
徴税人に請け負わせたりしたなら、今度は徴税人までもが権力犯罪の従犯ということになってしまう。
税が重すぎても権力犯罪になるし、軽すぎても権力犯罪になる。重税で民を痛め付けることが、
民の側から見ていかにも犯罪的なものとして取り扱われることが多いのは世の常であるが、
逆に政府などが民(特に素封家など)に対して最低限課して行くべき税すらをもおろそかにした結果、
貧富の格差を極度に広げてしまい、その挙句の国家社会の経済破綻を招いてしまったりすることもある。
これも権力者にとっての道義的な犯罪であるといえ、税制はただ優しいばかりでもいけない理由になっている。
民から徴集した税を糧として、士人階級の人間がトップダウンに世の中を取り仕切っていくのでなければ、
実際問題世の中も持たない、だから税制も必要だし、税制を執行する徴税人も世の中にとって必須な存在である。
上記のようなやむない理由で、徴税人が「権力犯罪者の従犯」という罪を帯びてしまうことも無くは
ないにしろ、徴税という仕事自体はむしろ世のため人のために存在するものなのだから、決して「賤業」
などとして取り扱うべきではないし、ましてや、罪人と同等に扱ったりするのはもってのほかだと言える。
仮に百人の人間がいたとして、救われる価値のある者から順々に救われていくとした場合、
徴税人は五十番目前後ぐらいに当てはまるだろうことが予想される。適正な税制を執行していれば
五十番目以内に入るだろうし、不正な税制を執行していれば五十番目以下となるだろう。いずれにしろ、
徴税人自身が税制を取り決められているわけではないのだから、そんなに順位が高下することもない。
百人いれば一番最後の百番目に救われるか、もしくは救われないかといったところである
本物の犯罪者などと比べれば、徴税人も随分と高いほうの順位にあるといえる。
徴税人が権力犯罪の従犯でしかあり得ないほどにも、世の中が総出を挙げて乱れきっていたとする。
そしたらもうそんな世の中には、上記の「百人の人間」のうちの五十番目から百番目あたりまでの
「下半分」の人間しか存在していないことにもなる。公人としては最低位の部類である徴税人すらをも
従犯と化すような権力機構は丸ごと徴税人ほどにも救われない人間の集まりである。そんな連中に
支配されている国や自治体の民たちもやはり救われようがない。特に、不正な重税が課されている場合以上にも、
富豪などに対する不正な税制緩和が敷かれている場合のほうがより救いようがなく、この場合、
もはや「労働者すなわち道義的犯罪者」ということにすらなってしまう。自由主義や資本主義が
目指して来たのもまさにこのような状況であり、暴君が民に重税を課しまくる場合並みか
それ以上にも、致命的な罪悪を国中や世界中に撒き散らしたことともなっているのである。
税制が適正であるが故に徴税人に罪を負わせたりしなくて済む世の中であれば、まずあらゆる
公人は「士農工商」の位階などに即して、民の上に立つ貴人として振る舞うことすら許されることになる。
それほどにも尊貴な公人の下で社会生活を営む民もまた、働いたからと言って罪になるようなこともない。
世の営みに無駄な罪障を帯びさせないためのバロメーターともなるのが税制の適正如何であり、
当然適正であるに越したことはないし、災害などで一時的に重税が敷かれるようなことがあったとしても、
決して「徴税人=罪人」などという思い込みまでもがまかり通るようなことはないようにしなければならない。
徴税人を立派な公人として尊重できるぐらいのあたりから、徳治の素地も固まっていくのだから。
そしたらもうそんな世の中には、上記の「百人の人間」のうちの五十番目から百番目あたりまでの
「下半分」の人間しか存在していないことにもなる。公人としては最低位の部類である徴税人すらをも
従犯と化すような権力機構は丸ごと徴税人ほどにも救われない人間の集まりである。そんな連中に
支配されている国や自治体の民たちもやはり救われようがない。特に、不正な重税が課されている場合以上にも、
富豪などに対する不正な税制緩和が敷かれている場合のほうがより救いようがなく、この場合、
もはや「労働者すなわち道義的犯罪者」ということにすらなってしまう。自由主義や資本主義が
目指して来たのもまさにこのような状況であり、暴君が民に重税を課しまくる場合並みか
それ以上にも、致命的な罪悪を国中や世界中に撒き散らしたことともなっているのである。
税制が適正であるが故に徴税人に罪を負わせたりしなくて済む世の中であれば、まずあらゆる
公人は「士農工商」の位階などに即して、民の上に立つ貴人として振る舞うことすら許されることになる。
それほどにも尊貴な公人の下で社会生活を営む民もまた、働いたからと言って罪になるようなこともない。
世の営みに無駄な罪障を帯びさせないためのバロメーターともなるのが税制の適正如何であり、
当然適正であるに越したことはないし、災害などで一時的に重税が敷かれるようなことがあったとしても、
決して「徴税人=罪人」などという思い込みまでもがまかり通るようなことはないようにしなければならない。
徴税人を立派な公人として尊重できるぐらいのあたりから、徳治の素地も固まっていくのだから。
「諸侯を合わせ百県を制し、来歳の為めの朔日と、諸侯の民に税する所の軽重の法と、貢職の数とを
受けしむ。土地の遠近の宜しき所を以って度を為す。郊廟の事を以って給し、私する所有る無し」
「諸侯を呼び寄せて、全国を統制するために、来年の暦と、税制のための軽重の法と、貢物の必要数とを受理させる。
都から諸国までの遠近なども推し量って負担を加減する。全ては公益のためとし、利益を私するようなことは許さない。
(これ程にも清廉で巧みな為政のための徴税は、困窮に駆られた貧国での犯罪の横行などをも防止するであろう。
万人のうちでも特に救われないような罪人の発生などを、税制の適正化にもよって未然に防いで行くことこそは重要である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・月令第六より)
受けしむ。土地の遠近の宜しき所を以って度を為す。郊廟の事を以って給し、私する所有る無し」
「諸侯を呼び寄せて、全国を統制するために、来年の暦と、税制のための軽重の法と、貢物の必要数とを受理させる。
都から諸国までの遠近なども推し量って負担を加減する。全ては公益のためとし、利益を私するようなことは許さない。
(これ程にも清廉で巧みな為政のための徴税は、困窮に駆られた貧国での犯罪の横行などをも防止するであろう。
万人のうちでも特に救われないような罪人の発生などを、税制の適正化にもよって未然に防いで行くことこそは重要である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・月令第六より)
たとえば、キリスト教圏でも特に他力本願的な教義を持つプロテスタント圏こそは、特にメシがまずい。
メシの美味さではフランス・イタリア(カトリック)≧ドイツ(カトリックとプロテスタント半々)≫アメリカ・イギリス(プロテスタント)
あたりが典型的な評価で、聖書教義に仏教教義を織り交ぜてまで何とか自力作善的な傾向を持たせていたカトリック圏に
おいてこそ、それなりに料理を心がける者も生じた一方、プロテスタント圏には始めからそんな人間が生じもしなかった。
いくら脳内の超越神なんかに祈ったって、うまい料理がどこからかわいて出てくるようなことがあるはずもないわけで、
当地の料理文化が盛んか否かで、その地における根本的な自力作善の頻度までをも計り知ることができるのだといえる。
日本でも、他力本願を謳う浄土門こそは肉食を伝統的に可としている。肉料理ほど、手っ取り早くそれなりの味を出せる
料理も他にないわけで、いかにも易行道の仏門のあり方らしい。難行道である禅門などは今でも寺中での肉食などは基本禁止で、
(托鉢時の布施に肉料理が含まれることは許されている)代わりに菜食などが主体の精進料理に非常な精魂を込めている。
今でこそベジタリアンの風習なども盛んだが、ただサラダなどの菜食で食事を済ますというばかりのことで、そこでこそ
精進料理のような料理文化を発達させようという所まで行っているわけではない。菜食を本当に料理として味わえるものに
仕立て上げるということこそは本当に難儀なことであり、聖道門の僧侶か本格の主婦でもなければやりきれないことなのである。
メシの美味さではフランス・イタリア(カトリック)≧ドイツ(カトリックとプロテスタント半々)≫アメリカ・イギリス(プロテスタント)
あたりが典型的な評価で、聖書教義に仏教教義を織り交ぜてまで何とか自力作善的な傾向を持たせていたカトリック圏に
おいてこそ、それなりに料理を心がける者も生じた一方、プロテスタント圏には始めからそんな人間が生じもしなかった。
いくら脳内の超越神なんかに祈ったって、うまい料理がどこからかわいて出てくるようなことがあるはずもないわけで、
当地の料理文化が盛んか否かで、その地における根本的な自力作善の頻度までをも計り知ることができるのだといえる。
日本でも、他力本願を謳う浄土門こそは肉食を伝統的に可としている。肉料理ほど、手っ取り早くそれなりの味を出せる
料理も他にないわけで、いかにも易行道の仏門のあり方らしい。難行道である禅門などは今でも寺中での肉食などは基本禁止で、
(托鉢時の布施に肉料理が含まれることは許されている)代わりに菜食などが主体の精進料理に非常な精魂を込めている。
今でこそベジタリアンの風習なども盛んだが、ただサラダなどの菜食で食事を済ますというばかりのことで、そこでこそ
精進料理のような料理文化を発達させようという所まで行っているわけではない。菜食を本当に料理として味わえるものに
仕立て上げるということこそは本当に難儀なことであり、聖道門の僧侶か本格の主婦でもなければやりきれないことなのである。
実際問題、自力作善に積極的であったほうが、他力本願ばかりに専らであるよりも、うまいのである。うまいし、痛くない。
全くいい姿勢なども心がけずに、フカフカのソファの上でふんぞり返ってばかりいれば、そのせいで腰痛やリューマチにもなる。
ヨガや古武術の身体躁法にも根ざしたいい姿勢でのキビキビとした生活を心がけていれば、そんな問題にも悩まされずに、
常日ごろからすがすがしい気持ちでもいられる。何事にかけても自力作善然とした積極的なあり方であったほうが、自分自身に
とっても良い結果を招く一方、他力本願然とした消極的なあり方でいたなら、そのせいでの自業自得で、自分にとっても
悪い結果を招くこととなる。それが普遍的な真理に根ざした法則であり、超越神と雖も決して覆せるものではないからだ。
本当に自力作善を心がけるのなら、行いに相応の対価すら必ずしも期待しないほどに旺盛な積極性主義あるべきである。
いくら積極的であっても、そこに執拗な打算が付きまとっていたりするようなら、そのせいで自力作善とまではいかなくなる。
仮に、行いに相応以上の対価ばかりを追い求めて積極的でいるようなら、この場合には「自力作悪」とすらなってしまい、
諸々の行いにかけて消極的であるような場合以上にも問題的な結果を招くことにすらなりかねない。エントロピー増大則
とも相まって、行いに相応の対価のみを企図する場合でも、相応以上の対価を期待する場合のような問題を多少は生じさせ
かねないので、行いに相応の対価すら期待しないぐらいの心がけに基づく場合にのみ、そのような問題をも退けることができる。
全くいい姿勢なども心がけずに、フカフカのソファの上でふんぞり返ってばかりいれば、そのせいで腰痛やリューマチにもなる。
ヨガや古武術の身体躁法にも根ざしたいい姿勢でのキビキビとした生活を心がけていれば、そんな問題にも悩まされずに、
常日ごろからすがすがしい気持ちでもいられる。何事にかけても自力作善然とした積極的なあり方であったほうが、自分自身に
とっても良い結果を招く一方、他力本願然とした消極的なあり方でいたなら、そのせいでの自業自得で、自分にとっても
悪い結果を招くこととなる。それが普遍的な真理に根ざした法則であり、超越神と雖も決して覆せるものではないからだ。
本当に自力作善を心がけるのなら、行いに相応の対価すら必ずしも期待しないほどに旺盛な積極性主義あるべきである。
いくら積極的であっても、そこに執拗な打算が付きまとっていたりするようなら、そのせいで自力作善とまではいかなくなる。
仮に、行いに相応以上の対価ばかりを追い求めて積極的でいるようなら、この場合には「自力作悪」とすらなってしまい、
諸々の行いにかけて消極的であるような場合以上にも問題的な結果を招くことにすらなりかねない。エントロピー増大則
とも相まって、行いに相応の対価のみを企図する場合でも、相応以上の対価を期待する場合のような問題を多少は生じさせ
かねないので、行いに相応の対価すら期待しないぐらいの心がけに基づく場合にのみ、そのような問題をも退けることができる。
資本主義は行いに相応以上の対価を追い求める活動を是とし、共産主義は行いに相応の対価のみを追い求める活動を是とした。
いずれも経済破綻や労役怠惰などの致命的な問題を来たすことには変わりなかったわけで、君子士人を模範とする天下万民の
誰しもが、行いに相応の対価すら期待しない程もの心がけによって自力作善を推し進めていくことを是とした徳治主義こそは、
乱世を反正した世の中を相当な治世や繁栄へと持ち込むことをも可能としている。そのような中で一部分、肉食によって
手っ取り早く美味に与ろうとするような他力本願者が生じてしまったところで、それでもそれなりにうまく行くぐらいに、
徳治社会こそは人々の十二分な努力によって、世の中に遍在する公益をも十二分なものとして行くことができるのである。
「民其の力を三として、二を公に入れ、其の一を衣食とす。公聚は朽蠹して、三老は凍餒す。国の諸市、屨は賤しく踊は貴し」
「(今斉で)民は自分たちの労役によって得た収益の三分の二を公室に納め、残りの三分の一で自分たちの衣食を賄っている。
公室の貯蔵庫の穀物は消費されることもなく腐れ果てているというのに、民間では高名な長老までもが飢えて凍え死んでいる。
(困窮にかられて罪を働き足きりの刑になるものが多いから)国の諸市で一般の履物は売れず、片足用の靴ばかりが売れる始末。
(徴税人を罪人扱いするイエスの暴言然り、古代ユダヤ人は『権力者こそは民から富を徴集する側の立場である』という基本的な
社会構造すらをもわきまえてはいない。だから支配者たる神こそが衣食や富を恵んでくれるような稚拙な倒錯をもしたのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・昭公三年より)
いずれも経済破綻や労役怠惰などの致命的な問題を来たすことには変わりなかったわけで、君子士人を模範とする天下万民の
誰しもが、行いに相応の対価すら期待しない程もの心がけによって自力作善を推し進めていくことを是とした徳治主義こそは、
乱世を反正した世の中を相当な治世や繁栄へと持ち込むことをも可能としている。そのような中で一部分、肉食によって
手っ取り早く美味に与ろうとするような他力本願者が生じてしまったところで、それでもそれなりにうまく行くぐらいに、
徳治社会こそは人々の十二分な努力によって、世の中に遍在する公益をも十二分なものとして行くことができるのである。
「民其の力を三として、二を公に入れ、其の一を衣食とす。公聚は朽蠹して、三老は凍餒す。国の諸市、屨は賤しく踊は貴し」
「(今斉で)民は自分たちの労役によって得た収益の三分の二を公室に納め、残りの三分の一で自分たちの衣食を賄っている。
公室の貯蔵庫の穀物は消費されることもなく腐れ果てているというのに、民間では高名な長老までもが飢えて凍え死んでいる。
(困窮にかられて罪を働き足きりの刑になるものが多いから)国の諸市で一般の履物は売れず、片足用の靴ばかりが売れる始末。
(徴税人を罪人扱いするイエスの暴言然り、古代ユダヤ人は『権力者こそは民から富を徴集する側の立場である』という基本的な
社会構造すらをもわきまえてはいない。だから支配者たる神こそが衣食や富を恵んでくれるような稚拙な倒錯をもしたのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・昭公三年より)
温故知新が、全く創造をもたらさないなんてことはない。
古代の儒学と比べれば、朱子学や日本の律令制や武家制度も温故知新の一種だといえる。
特に律令制や武家制は、その概ねの統治規範を儒家教学に採りながらも、
神道文化や武道精神といった別個の文化的理念を大いに取り入れているものだから、
その根本的な様相が「儒家統治」であることを忘れ去られがちなほどのものとなっている。
全くの我流な創造と比べれば、温故知新に基づく創造は、遥かにその頻度が低い。
朱子学や武家制度級の大規模な創造は、それこそ1000年に一度あるかないか程度のもので、
しかも一度創造されるや、何百年もかけての同じ道の研鑽が繰り返されて行く。
武士道も、最初期の平安末期から鎌倉期頃には「朝廷の警護者」に過ぎなかった武家としての
身分に即して、ただ命知らずの血みどろであるばかりだったのが、室町期には禅宗を始めとする
仏教文化との融合が顕著なものとなり、戦国期には方々の大名が王侯並みの政治的な
実力を付けて割拠し、江戸期には公家も同然な程の厳正な礼節統治が敷かれるようになった。
平安末期から江戸期に至るまで、一度創造された武士道という理念が800年に以上にも
わたってその練り込みを続けてきたわけで、なればこそ、温故知新に基づく創造というのは、
短期的に乱造されまくったりしてる"余裕"もないものであることが分かるのである。
最大の価値を、悠久の歴史の流れではなく個々人に置く個人主義者からすれば、
温故知新に基づく創造はあまりにも悠長すぎるように思われるに違いない。たとえ自分が
武士道を好むのであっても、たまたま自分が鎌倉期の武士に生まれたなら、嫡子でもない限りは
全員が捨て身の乱戦に没入して行かなければならなくなる一方、仮に自分が江戸期の武士に
生まれたとしたなら、今度は小笠原流礼法などの「今どき」な礼法に即する規律ばかりを徹底して
いかなければならなかったことになる。しかもそのような時代が100年200年と続いていた
わけで、個人の趣向が時代時代によって極度に束縛されていたと考えざるを得ないわけである。
古代の儒学と比べれば、朱子学や日本の律令制や武家制度も温故知新の一種だといえる。
特に律令制や武家制は、その概ねの統治規範を儒家教学に採りながらも、
神道文化や武道精神といった別個の文化的理念を大いに取り入れているものだから、
その根本的な様相が「儒家統治」であることを忘れ去られがちなほどのものとなっている。
全くの我流な創造と比べれば、温故知新に基づく創造は、遥かにその頻度が低い。
朱子学や武家制度級の大規模な創造は、それこそ1000年に一度あるかないか程度のもので、
しかも一度創造されるや、何百年もかけての同じ道の研鑽が繰り返されて行く。
武士道も、最初期の平安末期から鎌倉期頃には「朝廷の警護者」に過ぎなかった武家としての
身分に即して、ただ命知らずの血みどろであるばかりだったのが、室町期には禅宗を始めとする
仏教文化との融合が顕著なものとなり、戦国期には方々の大名が王侯並みの政治的な
実力を付けて割拠し、江戸期には公家も同然な程の厳正な礼節統治が敷かれるようになった。
平安末期から江戸期に至るまで、一度創造された武士道という理念が800年に以上にも
わたってその練り込みを続けてきたわけで、なればこそ、温故知新に基づく創造というのは、
短期的に乱造されまくったりしてる"余裕"もないものであることが分かるのである。
最大の価値を、悠久の歴史の流れではなく個々人に置く個人主義者からすれば、
温故知新に基づく創造はあまりにも悠長すぎるように思われるに違いない。たとえ自分が
武士道を好むのであっても、たまたま自分が鎌倉期の武士に生まれたなら、嫡子でもない限りは
全員が捨て身の乱戦に没入して行かなければならなくなる一方、仮に自分が江戸期の武士に
生まれたとしたなら、今度は小笠原流礼法などの「今どき」な礼法に即する規律ばかりを徹底して
いかなければならなかったことになる。しかもそのような時代が100年200年と続いていた
わけで、個人の趣向が時代時代によって極度に束縛されていたと考えざるを得ないわけである。
ただ、中世から近世にかけての欧米文化なども、今から見ればノッペリとした単調なものに
見えるし、近代もやはりそこそこの単一性があるように思われる。現代こそは、何でもアリな
創造しまくりの世の中のように思えたりもするが、それも自分が今という時代に生きているから
なだけであって、その服装もスーツから作業着からカジュアルまで、それなりに定型的なもの
となっている。昔なら奴隷こそが着用するものだった半そでのTシャツやタンクトップなどの
形状の服装が公に認められていたりもするあたり、「極度に服装にだらしなかった時代」として、
後世の人々にまで白眼視され続けたりするようになる可能性があるぐらいのものである。
実は、我流によるやたらめったらな創造というのは、温故知新に基づく創造と比べれば、
さほど決定的な創造でもないのである。水面に一石を投ずる程度の、さほど決定的でもない
変化を世の中にもたらすばかりで、水面の波が収まればそれっきりなのである。それと比べれば、
温故知新に基づく創造などは、水面を形作っている池や湖の形状から変えてしまうような
決定的な変化を世の中にもたらすわけで、それがまた新たに別の変化を被ったりすることは
あるにしても、変化の影響は恒久的なものである。故にこそ、真に決定的な創造的変化を
もたらそうと思うものこそは、温故知新をも志すべきなのであり、温故知新すなわち旧態依然
だなんていう固定観念にも、決して囚われたままでいたりしてはいけないのだといえる。
「干禄百福、子孫千億。穆穆皇皇として、君に宜しく王に宜しき。愆たず忘れず、旧章に率いて由る」
「福禄も百千、その子孫の数も千億。明らかに雄大にして、主君も満足、王侯たちも満足。
決して誤らぬよう忘れぬよう、古えの則に慎重に準拠して来たからである。(万民と帝王の福寿を
第一に願えばこそ、述べて作らず信じて古えを好むのである。最も、旧約のトーラーなどは
『古えの良き則』としての条件すら満たせていない、政商集団の悪知恵集だったりするわけだが)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・生民之什・仮楽より)
見えるし、近代もやはりそこそこの単一性があるように思われる。現代こそは、何でもアリな
創造しまくりの世の中のように思えたりもするが、それも自分が今という時代に生きているから
なだけであって、その服装もスーツから作業着からカジュアルまで、それなりに定型的なもの
となっている。昔なら奴隷こそが着用するものだった半そでのTシャツやタンクトップなどの
形状の服装が公に認められていたりもするあたり、「極度に服装にだらしなかった時代」として、
後世の人々にまで白眼視され続けたりするようになる可能性があるぐらいのものである。
実は、我流によるやたらめったらな創造というのは、温故知新に基づく創造と比べれば、
さほど決定的な創造でもないのである。水面に一石を投ずる程度の、さほど決定的でもない
変化を世の中にもたらすばかりで、水面の波が収まればそれっきりなのである。それと比べれば、
温故知新に基づく創造などは、水面を形作っている池や湖の形状から変えてしまうような
決定的な変化を世の中にもたらすわけで、それがまた新たに別の変化を被ったりすることは
あるにしても、変化の影響は恒久的なものである。故にこそ、真に決定的な創造的変化を
もたらそうと思うものこそは、温故知新をも志すべきなのであり、温故知新すなわち旧態依然
だなんていう固定観念にも、決して囚われたままでいたりしてはいけないのだといえる。
「干禄百福、子孫千億。穆穆皇皇として、君に宜しく王に宜しき。愆たず忘れず、旧章に率いて由る」
「福禄も百千、その子孫の数も千億。明らかに雄大にして、主君も満足、王侯たちも満足。
決して誤らぬよう忘れぬよう、古えの則に慎重に準拠して来たからである。(万民と帝王の福寿を
第一に願えばこそ、述べて作らず信じて古えを好むのである。最も、旧約のトーラーなどは
『古えの良き則』としての条件すら満たせていない、政商集団の悪知恵集だったりするわけだが)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・生民之什・仮楽より)
この世界の全様相を鑑みるに、世界を滅亡級の危機に陥れる程もの
壮絶な劣悪さを帯びた統治理念というのも、そんなに多くは見られない。
儒学や仏教が社会統治の理念として申し分ないのはもちろんのこと、
玄学(老荘の学)やヒンズー教もまた、民度の低下や酷烈な階級差別などの問題的要素が
ありはするものの、世の中を最悪の戦乱から引き上げさせる程度の効能は伴っている。
イスラムも傍から見れば奇異な戒律の厳守や原理主義者の好戦志向などの異常点があるにしても、
自分たちから世界を滅亡に陥れるほどもの破滅志向までを帯びているわけではない。
教理の異同や、傍から見た場合の好みの差などもありはするにしても、全世界を破滅に陥れる程にも
極限級に粗悪な要素を持つ学問宗教などは稀有だし、あったとしても、その受容者が世の中の多数派となって、
一国や一世界を統治支配しきるほどもの勢力を手に入れたようなことともなれば、東洋などでは皆無に等しい。
(強いて言えば、始皇帝が法家支配を敷いた秦帝国などがそれに当たるが、わずか15年しか持たなかった)
異端の中国諸子百家だとかインドの外道教派だとかが、そんなに大きな勢力を持てなかったり、
持てても短命に終わったりしていたのは、儒学や仏教の如き優良な教学が「王道」として君臨していたがための
冷遇に依るのはすでに述べたことである。儒学が正学としての地位を獲得して後の、道家や兵家以外の諸子百家の
扱いはといえば、その正典(墨子、公孫龍子)からしてその一部が欠落したり、あるいは全文が遺失したり
といった程にも冷ややかなもので、そこに中国人の冷酷なほどもの合理主義すらうかがうことができる。
インドの外道教派はもう少しマシな扱いで、マハーヴィーラの興したジャイナ教なども一応は今に至るまで
存続している。教義的には聖書信仰並みの粗悪さを持つといえる害為正法外道ですら、「泥棒階級のカースト」
などに形を変えて一応は存在しているという。(ただし泥棒が公認されているわけではなく、捕まれば罰を受ける)
壮絶な劣悪さを帯びた統治理念というのも、そんなに多くは見られない。
儒学や仏教が社会統治の理念として申し分ないのはもちろんのこと、
玄学(老荘の学)やヒンズー教もまた、民度の低下や酷烈な階級差別などの問題的要素が
ありはするものの、世の中を最悪の戦乱から引き上げさせる程度の効能は伴っている。
イスラムも傍から見れば奇異な戒律の厳守や原理主義者の好戦志向などの異常点があるにしても、
自分たちから世界を滅亡に陥れるほどもの破滅志向までを帯びているわけではない。
教理の異同や、傍から見た場合の好みの差などもありはするにしても、全世界を破滅に陥れる程にも
極限級に粗悪な要素を持つ学問宗教などは稀有だし、あったとしても、その受容者が世の中の多数派となって、
一国や一世界を統治支配しきるほどもの勢力を手に入れたようなことともなれば、東洋などでは皆無に等しい。
(強いて言えば、始皇帝が法家支配を敷いた秦帝国などがそれに当たるが、わずか15年しか持たなかった)
異端の中国諸子百家だとかインドの外道教派だとかが、そんなに大きな勢力を持てなかったり、
持てても短命に終わったりしていたのは、儒学や仏教の如き優良な教学が「王道」として君臨していたがための
冷遇に依るのはすでに述べたことである。儒学が正学としての地位を獲得して後の、道家や兵家以外の諸子百家の
扱いはといえば、その正典(墨子、公孫龍子)からしてその一部が欠落したり、あるいは全文が遺失したり
といった程にも冷ややかなもので、そこに中国人の冷酷なほどもの合理主義すらうかがうことができる。
インドの外道教派はもう少しマシな扱いで、マハーヴィーラの興したジャイナ教なども一応は今に至るまで
存続している。教義的には聖書信仰並みの粗悪さを持つといえる害為正法外道ですら、「泥棒階級のカースト」
などに形を変えて一応は存在しているという。(ただし泥棒が公認されているわけではなく、捕まれば罰を受ける)
中国のように辛うじてその正典の一部が現存したりする場合にしろ、インドのように厳密な冷遇下に置かれた
うえで教派が存続している場合にしろ、異端外道の統治理念というものが破滅級の危害までは帯びることなく
残存していった例であるといえ、その点、異教を完全に絶やし尽くしたイスラムなどよりはまだ参考になる。
もちろん参考になるにしても、やはり今のキリスト教やユダヤ教並みの厚遇などが許されるわけもなく、
そんなものを好むものが人並みの扱いすら受けられないようになることには違いないのである。
今は天にも昇らんとする程もの勢力を手に入れているのだとしても、そのような教派が人類滅亡級の
危害を帯びていたりするからには、中国やインドの異端外道並みの扱いにまで引き戻されなければならない。
人並み以上どころか、人並みの扱いすら保証されないような扱いにこそ甘んじていくのでなければ、
ただでは済まない。つまり、「これ程にも悪逆非道を尽くしていたにもかかわらず、許される」
という程度の「不幸中の幸い」すらをも、決して期待してはならないのである。
少なくとも、自らがそのような邪教信仰を興じていた本人である以上は、不幸中の幸いすら期待してはならない。
そんなものを期待するようなら、まだ自分たちが邪信に溺れたままでいるのだと思われたとしても仕方がない。
邪教への信奉を払拭したシラフの境地でいたなら、邪信に溺れていたものなど人並み以下の冷遇に見舞われるのが
当然だと考えるものなのであり、それはちょうど、罪を犯した者が罰を受けることとも全く様相を同じくする。
犯罪者が相応の処罰を受けるのと全く同じように、邪教信者なども邪信に相応の処分を受けなければならないと
心からわきまえて、その通りの服罪に臨んで行こうとする場合にのみ、その神妙さが買われて、断罪にかけての
手心が加えられるようなこともあるだろう。それもあくまで、邪信の範疇を脱し切れていればこそのことである。
うえで教派が存続している場合にしろ、異端外道の統治理念というものが破滅級の危害までは帯びることなく
残存していった例であるといえ、その点、異教を完全に絶やし尽くしたイスラムなどよりはまだ参考になる。
もちろん参考になるにしても、やはり今のキリスト教やユダヤ教並みの厚遇などが許されるわけもなく、
そんなものを好むものが人並みの扱いすら受けられないようになることには違いないのである。
今は天にも昇らんとする程もの勢力を手に入れているのだとしても、そのような教派が人類滅亡級の
危害を帯びていたりするからには、中国やインドの異端外道並みの扱いにまで引き戻されなければならない。
人並み以上どころか、人並みの扱いすら保証されないような扱いにこそ甘んじていくのでなければ、
ただでは済まない。つまり、「これ程にも悪逆非道を尽くしていたにもかかわらず、許される」
という程度の「不幸中の幸い」すらをも、決して期待してはならないのである。
少なくとも、自らがそのような邪教信仰を興じていた本人である以上は、不幸中の幸いすら期待してはならない。
そんなものを期待するようなら、まだ自分たちが邪信に溺れたままでいるのだと思われたとしても仕方がない。
邪教への信奉を払拭したシラフの境地でいたなら、邪信に溺れていたものなど人並み以下の冷遇に見舞われるのが
当然だと考えるものなのであり、それはちょうど、罪を犯した者が罰を受けることとも全く様相を同じくする。
犯罪者が相応の処罰を受けるのと全く同じように、邪教信者なども邪信に相応の処分を受けなければならないと
心からわきまえて、その通りの服罪に臨んで行こうとする場合にのみ、その神妙さが買われて、断罪にかけての
手心が加えられるようなこともあるだろう。それもあくまで、邪信の範疇を脱し切れていればこそのことである。
インドの被差別カーストの現況など、確かに目も当てられないほどに悲惨なものがある。
ただしそれは、今のインドがカースト社会であるからのみならず、イギリスなどからの
激烈な侵略や植民地支配によって全社会規模での貧困に見舞われ続けているからで、
最底辺のカーストが極度の被虐下にあるのも、所詮は聖書信仰のせいでしかないといえる。
インド全体がそれなりに富裕であった約2000年前ごろに仏教も隆盛し、
カーストによっては下位に置かれているような人々までもの出家者による救済などが
旺盛に講じられていた。そのような時代には、下位のカーストだからといって今ほどにも
激烈な被虐下に置かれていたようなこともなかったわけで、今のハリジャン(不可触賤民)や
シュードラ(奴隷階級)ほどもの差別下に置かれることを恐れるようなことがあるとすれば、
それは今のインド全体を極度の困窮に陥れている者たち自身にとっての自業自得だといえる。
全世界が仏教のような優良な教学によって統治されたなら、そこで底辺のカースト並みの
地位に置かれた者の扱いもさほどひどくはならない一方、今のように全世界が最悪の邪教に
支配されたままでいるなら、底辺のカーストなども、それはそれは陰惨な扱いを受けることになる。
なればこそ、底辺のカーストのような扱いに甘んじていかなければならない者たちにとっても、
世界の王権をそれなりにできた統治理念の持ち主へと明け渡して行くことが求められるのである。
ただしそれは、今のインドがカースト社会であるからのみならず、イギリスなどからの
激烈な侵略や植民地支配によって全社会規模での貧困に見舞われ続けているからで、
最底辺のカーストが極度の被虐下にあるのも、所詮は聖書信仰のせいでしかないといえる。
インド全体がそれなりに富裕であった約2000年前ごろに仏教も隆盛し、
カーストによっては下位に置かれているような人々までもの出家者による救済などが
旺盛に講じられていた。そのような時代には、下位のカーストだからといって今ほどにも
激烈な被虐下に置かれていたようなこともなかったわけで、今のハリジャン(不可触賤民)や
シュードラ(奴隷階級)ほどもの差別下に置かれることを恐れるようなことがあるとすれば、
それは今のインド全体を極度の困窮に陥れている者たち自身にとっての自業自得だといえる。
全世界が仏教のような優良な教学によって統治されたなら、そこで底辺のカースト並みの
地位に置かれた者の扱いもさほどひどくはならない一方、今のように全世界が最悪の邪教に
支配されたままでいるなら、底辺のカーストなども、それはそれは陰惨な扱いを受けることになる。
なればこそ、底辺のカーストのような扱いに甘んじていかなければならない者たちにとっても、
世界の王権をそれなりにできた統治理念の持ち主へと明け渡して行くことが求められるのである。
「秋、宋に大水あり。公弔を使わしめて曰く、天淫雨を作し、粢盛を害す、若し之れを何ぞ弔せざらん。
対えて曰く、孤実に不敬なりて、天之れに災いを降せり。又た以て君の憂いを為せり。拝命して之れを辱む。
臧文仲曰く、宋は其れ興らんか。禹湯も己れを罪し、其の興るや悖焉たり。桀紂は人を罪し、其の亡ぶや
忽焉たり。且つ列国に凶有りて、孤と呼するは礼なり。言懼れて名礼たり、其れ庶からんかな。既に而て
之れを聞きて曰く、公子御説の辞なりと。臧孫達曰く、是れ宜しき君と為せり、民の心を恤える有り」
「秋、宋国で大洪水の被害があった。荘公が見舞いの使者を遣わして言った。『天は長雨を降らして、
貴国の祭祀用の穀物にまで被害をもたらしたといいます。どうしてこれを見舞わずにいられましょうか』
宋公は答えていった。『真に弧人の不敬の至りでありまして、天もそこに災いを下されたのであります。
そして今また君にもご心配をおかけしました。そのお言葉を拝しつつ、我が辱めとさせていただきます』
臧文仲がこの返答を聞いて言った。『宋国はきっと興隆するに違いない。禹王や湯王もあえて自らに罪あり
という姿勢でいたが、それによりみるみると国を勃興させていった。桀王や紂王のごときは全ての罪を
他者に押し付けて自分たちの栄華ばかりを追い求めていたが、その滅び去るさまも速やかなものであった。
しかも宋公は列国に心配をかけたことを恥じて自らを〈弧(当時の王侯の謙譲的一人称である《寡人》
よりもさらに自らを卑しめている)〉と自称している。これも礼に適ったものである。文章も恐れ慎み、
言葉も礼儀に適っている、きっと国を安定させられることだろう』 宋公はこの評判を聞いて言った。
『あの文章は自分ではなく公子の御説が作ったものです』 臧文仲はまたこれを評して言った。
『実に賢明な主君なことだ。真に民を憂える真心があればこそ、このようでいられるのだ。』」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・荘公十一年より)
対えて曰く、孤実に不敬なりて、天之れに災いを降せり。又た以て君の憂いを為せり。拝命して之れを辱む。
臧文仲曰く、宋は其れ興らんか。禹湯も己れを罪し、其の興るや悖焉たり。桀紂は人を罪し、其の亡ぶや
忽焉たり。且つ列国に凶有りて、孤と呼するは礼なり。言懼れて名礼たり、其れ庶からんかな。既に而て
之れを聞きて曰く、公子御説の辞なりと。臧孫達曰く、是れ宜しき君と為せり、民の心を恤える有り」
「秋、宋国で大洪水の被害があった。荘公が見舞いの使者を遣わして言った。『天は長雨を降らして、
貴国の祭祀用の穀物にまで被害をもたらしたといいます。どうしてこれを見舞わずにいられましょうか』
宋公は答えていった。『真に弧人の不敬の至りでありまして、天もそこに災いを下されたのであります。
そして今また君にもご心配をおかけしました。そのお言葉を拝しつつ、我が辱めとさせていただきます』
臧文仲がこの返答を聞いて言った。『宋国はきっと興隆するに違いない。禹王や湯王もあえて自らに罪あり
という姿勢でいたが、それによりみるみると国を勃興させていった。桀王や紂王のごときは全ての罪を
他者に押し付けて自分たちの栄華ばかりを追い求めていたが、その滅び去るさまも速やかなものであった。
しかも宋公は列国に心配をかけたことを恥じて自らを〈弧(当時の王侯の謙譲的一人称である《寡人》
よりもさらに自らを卑しめている)〉と自称している。これも礼に適ったものである。文章も恐れ慎み、
言葉も礼儀に適っている、きっと国を安定させられることだろう』 宋公はこの評判を聞いて言った。
『あの文章は自分ではなく公子の御説が作ったものです』 臧文仲はまたこれを評して言った。
『実に賢明な主君なことだ。真に民を憂える真心があればこそ、このようでいられるのだ。』」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・荘公十一年より)
人類社会において、一人前の社会人としてやっていける程度の十分な精神力があるならば、
「一般的社会人は安楽に思うものを『善』、苦痛に思うものを『悪』と定義付けている」という
言語構造上の根本原理に即して、善であるものに対する安楽と、悪であるものに対する苦痛とを感じる。
「十分な精神力がある」ということは、自分が社会一般の大局構造に即してものを考えられる程度の
精神力があるということであり、この条件に満たない程度の精神力しか持たない人間の場合は、
社会一般が善と楽、悪と苦を等価なものとして扱っていることにまでは察知が及びもしないから、
己の精神性の矮小さからなる倒錯によって、善であるものを苦、悪であるものを楽であるかのように
思い込んでしまうようになったりもする。とはいえ、「善」とか「悪」とかいった倫理判断自体が
「人間社会」における是非の判断でしかないわけだから、世の中にとって最も普遍的な善悪である
「善≡楽」「悪≡苦」といった善悪が絶対的に普遍的な善悪ともなる一方、精神薄弱な個人などが
勝手に定義した「善≡苦」「悪≡楽」といった善悪は、絶対的な誤謬性を帯びた善悪ともなる。
一般的な人間が善と楽、悪と苦を等価なものとして扱おうとしたのは、それによって致命的な災いを
精神的苦痛として未然に察知し、なるべく災禍を避けて福徳に与っていこうとしたからである。
人間の身体に痛覚があるのも、それによって身の危険を察知することを目的としているからで、
四肢切断級やそれ以上の致命傷を負った場合などには、もはや感覚が麻痺して痛みを感じないように
もなっている。それと全く同じように、人間の心もまた本来は禍いとなるものを苦痛だと感じていて、
故にそれを「悪いもの」と言語的に定義付けたりしていたわけだけれども、たとえば「磔での死刑」
級の禍いというのは、人間にとって、自業自得という点でも決定的に致命的なものだから、これを
観想することによって精神が致命傷を負い、ろくに禍いを精神的な苦痛であると感じられないように
なったりもする。身体の致命傷がまさに致命的であるのと同じように、精神の致命傷もまた致命的な
ものであり、そのような深手を負った人間の自存能力もまた、著しく損なわれていることが間違いない。
「一般的社会人は安楽に思うものを『善』、苦痛に思うものを『悪』と定義付けている」という
言語構造上の根本原理に即して、善であるものに対する安楽と、悪であるものに対する苦痛とを感じる。
「十分な精神力がある」ということは、自分が社会一般の大局構造に即してものを考えられる程度の
精神力があるということであり、この条件に満たない程度の精神力しか持たない人間の場合は、
社会一般が善と楽、悪と苦を等価なものとして扱っていることにまでは察知が及びもしないから、
己の精神性の矮小さからなる倒錯によって、善であるものを苦、悪であるものを楽であるかのように
思い込んでしまうようになったりもする。とはいえ、「善」とか「悪」とかいった倫理判断自体が
「人間社会」における是非の判断でしかないわけだから、世の中にとって最も普遍的な善悪である
「善≡楽」「悪≡苦」といった善悪が絶対的に普遍的な善悪ともなる一方、精神薄弱な個人などが
勝手に定義した「善≡苦」「悪≡楽」といった善悪は、絶対的な誤謬性を帯びた善悪ともなる。
一般的な人間が善と楽、悪と苦を等価なものとして扱おうとしたのは、それによって致命的な災いを
精神的苦痛として未然に察知し、なるべく災禍を避けて福徳に与っていこうとしたからである。
人間の身体に痛覚があるのも、それによって身の危険を察知することを目的としているからで、
四肢切断級やそれ以上の致命傷を負った場合などには、もはや感覚が麻痺して痛みを感じないように
もなっている。それと全く同じように、人間の心もまた本来は禍いとなるものを苦痛だと感じていて、
故にそれを「悪いもの」と言語的に定義付けたりしていたわけだけれども、たとえば「磔での死刑」
級の禍いというのは、人間にとって、自業自得という点でも決定的に致命的なものだから、これを
観想することによって精神が致命傷を負い、ろくに禍いを精神的な苦痛であると感じられないように
なったりもする。身体の致命傷がまさに致命的であるのと同じように、精神の致命傷もまた致命的な
ものであり、そのような深手を負った人間の自存能力もまた、著しく損なわれていることが間違いない。
人間級に高等な生物が痛覚を持つのは健常なことで、痛覚を持たないほうが異常ないし障害である。
健常であってこそ人も最大級に生活を営める一方、異常者や障害者は生活に支障を来たさざるを得ない。
どちらのほうが生に近いかといえばそれは健常者であり、死に近いのは異常者や障害者のほうである。
人間は万物の霊長であるほどにも高等な生物であればこそ、自然淘汰などをそのまま引き継ぐ必要もなく、
仁政によって健常者が異常者や障害者を労わって行くことだってできるわけだけども、それにしたって、
最大級の生命力を持つのは健常者である一方、比較的生命力に欠けるのが異常者や障害者だといえる。
故に、精神面にかけても、善と楽、悪と苦が等価なものであることを実感的にわきまえられて、罪悪
であるものに対する苦痛を健全に感じられる者こそは、より大きな生命力の持ち主であるといえる一方、
磔刑の観想などによって精神が致命傷を負ってしまったせいで、罪悪を苦痛であるとも感じられなく
なってしまっているような人間こそは比較的、生命力にも劣るといえる。極言すれば「すでに死んでいる
も同然の人間」であるといえ、罪悪に対する苦痛などを実感できるような所にまで立ち戻った時にこそ、
またそれなりの生命力を取り戻せるのだといえる。このあたりの生死を取り違えてしまっている人間も
邪信耽溺者などには非常に多いから、それもまた全くの誤解であることをここに実証的に断言しておく。
「之れ子の于に征き、野に劬労したまう。爰に矜人と、此の鰥寡を哀れむ」
「我が君は(治水などの)土木作業に従事する人夫の所に行かれて、野の果てで共に苦労をされている。
ああして困窮している人たちと、病人や孤独のものたちをも憐れんでくださっているのだ」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・彤弓之什・鴻雁より)
「哀れなるは我が填寡のもの、宜いは岸に宜いは獄に。粟を握みて出でて卜くれども、自て何ぞ能く穀せん」
「それにしても憐れなのはわが国の窮苦孤独の者たちよ。その行き場はといえば仮屋か獄舎かといったざま。
一掴み程度の粟を授けてやったりしたところで、どうしてそれだけで食い繋いでいくこともできようか」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・小旻之什・小宛より)
健常であってこそ人も最大級に生活を営める一方、異常者や障害者は生活に支障を来たさざるを得ない。
どちらのほうが生に近いかといえばそれは健常者であり、死に近いのは異常者や障害者のほうである。
人間は万物の霊長であるほどにも高等な生物であればこそ、自然淘汰などをそのまま引き継ぐ必要もなく、
仁政によって健常者が異常者や障害者を労わって行くことだってできるわけだけども、それにしたって、
最大級の生命力を持つのは健常者である一方、比較的生命力に欠けるのが異常者や障害者だといえる。
故に、精神面にかけても、善と楽、悪と苦が等価なものであることを実感的にわきまえられて、罪悪
であるものに対する苦痛を健全に感じられる者こそは、より大きな生命力の持ち主であるといえる一方、
磔刑の観想などによって精神が致命傷を負ってしまったせいで、罪悪を苦痛であるとも感じられなく
なってしまっているような人間こそは比較的、生命力にも劣るといえる。極言すれば「すでに死んでいる
も同然の人間」であるといえ、罪悪に対する苦痛などを実感できるような所にまで立ち戻った時にこそ、
またそれなりの生命力を取り戻せるのだといえる。このあたりの生死を取り違えてしまっている人間も
邪信耽溺者などには非常に多いから、それもまた全くの誤解であることをここに実証的に断言しておく。
「之れ子の于に征き、野に劬労したまう。爰に矜人と、此の鰥寡を哀れむ」
「我が君は(治水などの)土木作業に従事する人夫の所に行かれて、野の果てで共に苦労をされている。
ああして困窮している人たちと、病人や孤独のものたちをも憐れんでくださっているのだ」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・彤弓之什・鴻雁より)
「哀れなるは我が填寡のもの、宜いは岸に宜いは獄に。粟を握みて出でて卜くれども、自て何ぞ能く穀せん」
「それにしても憐れなのはわが国の窮苦孤独の者たちよ。その行き場はといえば仮屋か獄舎かといったざま。
一掴み程度の粟を授けてやったりしたところで、どうしてそれだけで食い繋いでいくこともできようか」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・小旻之什・小宛より)
正統な仏者が「善悪も本質的には空である」と言うのと、ニヒリストやニューエイジ信奉者
などが「善悪など虚妄だ」と言うのとでは、結論は似ていても、その内実が決定的に異なる。
仏者は、善悪の分別もまた罪福異熟のような絶対真理に合致している場合がある。しかし、
そうであっても>>140-141で述べたような真相に基づく、言語構造上の単なる真理であるわけだから、
善悪もまた「神による定義」みたいな神秘的要素もない、完全なる「空の真理」であるというのである。
ニヒリストやニューエイジ信奉者が「善悪など虚妄だ」と断ずるのは、
人間には普遍的な善悪の分別など不可能であり、個々人が思い思いのままに勝手な
善悪を定義付けているだけだから、善悪なんてものは虚妄だと断定しているのである。
ニヒリズムもニューエイジも西洋社会の産物であり、西洋社会の文化的基幹は相も変わらず
聖書信仰である。聖書教義に基づく善悪の分別なんてものは確かに虚妄であり、仏者の言う「空の真理」
に即した善悪ですらない。そんな聖書教義を文化的な取っ掛かりとする以上は、あらゆる善悪もまた
虚妄でしかあり得ないわけだから、確かにそんな社会において、あらゆる善悪の分別が
個々人の身勝手な虚妄にしか基づいていないと結論付けるのは正しいといえる。
しかし、全世界的に見れば実際の所、仏法上の空の真理や、>>140-141で述べたような自然科学的根拠
に基づく「普遍的な善悪の分別」というものをわきまえている人間のほうが多数派に上っていて、
知識面と潜在意識面の両面から、普遍的な善悪と虚妄の善悪を分けて考えるようにもなっている。
などが「善悪など虚妄だ」と言うのとでは、結論は似ていても、その内実が決定的に異なる。
仏者は、善悪の分別もまた罪福異熟のような絶対真理に合致している場合がある。しかし、
そうであっても>>140-141で述べたような真相に基づく、言語構造上の単なる真理であるわけだから、
善悪もまた「神による定義」みたいな神秘的要素もない、完全なる「空の真理」であるというのである。
ニヒリストやニューエイジ信奉者が「善悪など虚妄だ」と断ずるのは、
人間には普遍的な善悪の分別など不可能であり、個々人が思い思いのままに勝手な
善悪を定義付けているだけだから、善悪なんてものは虚妄だと断定しているのである。
ニヒリズムもニューエイジも西洋社会の産物であり、西洋社会の文化的基幹は相も変わらず
聖書信仰である。聖書教義に基づく善悪の分別なんてものは確かに虚妄であり、仏者の言う「空の真理」
に即した善悪ですらない。そんな聖書教義を文化的な取っ掛かりとする以上は、あらゆる善悪もまた
虚妄でしかあり得ないわけだから、確かにそんな社会において、あらゆる善悪の分別が
個々人の身勝手な虚妄にしか基づいていないと結論付けるのは正しいといえる。
しかし、全世界的に見れば実際の所、仏法上の空の真理や、>>140-141で述べたような自然科学的根拠
に基づく「普遍的な善悪の分別」というものをわきまえている人間のほうが多数派に上っていて、
知識面と潜在意識面の両面から、普遍的な善悪と虚妄の善悪を分けて考えるようにもなっている。
「金が全て」などの洗脳操作に基づく情報汚染が蔓延してしまっている今の日本においてですら、
投機によって大金を稼ぎ上げようなどとする人間は稀であり、せいぜい当選者が限られていることが
予め分かっている宝くじだとか、必ず店の側のほうがより勝つようになっているパチンコだとかに
手を出す人間がそこそこいる程度である。それは、江戸時代までの長年の道徳統治や道徳教育、
さらには仏法の流布にまで基づく、普遍的な善悪の分別の徹底が今でも深く根ざしているからで、
そんな分別のない西洋社会などと比べれば、今でも「金を稼ぐばかりではない、実のある労働」
を心がけようとする潜在意識が少なからず日本人にも具わり続けているのである。
資本主義経済に参加しながら、ある程度そのようなわきまえを保っているのが日本人なわけだが、
そもそも資本主義経済に参画することから忌んでいるような人間こそが未だ世界の多数派にも
上っている。全世界が完全に資本主義化したりすれば、それこそ誰もろくに実のある労働を
心がけなくなって、あっという間に世界が破綻することになるわけで(今も半分そうだが)、
資本主義者が世界の少数派に止め置かれるのも不可避なることであるとはいえるが、実際、
世界人類は全体規模で資本主義に没頭することを拒絶している。これこそは、金満主義に
よる自滅のような悪因苦果を地球人類が本能的に避けた実例であるといえ、人類全体には、
本能的に普遍的な善悪を分別する能力が備わっていた証拠ともなっているといえる。
投機によって大金を稼ぎ上げようなどとする人間は稀であり、せいぜい当選者が限られていることが
予め分かっている宝くじだとか、必ず店の側のほうがより勝つようになっているパチンコだとかに
手を出す人間がそこそこいる程度である。それは、江戸時代までの長年の道徳統治や道徳教育、
さらには仏法の流布にまで基づく、普遍的な善悪の分別の徹底が今でも深く根ざしているからで、
そんな分別のない西洋社会などと比べれば、今でも「金を稼ぐばかりではない、実のある労働」
を心がけようとする潜在意識が少なからず日本人にも具わり続けているのである。
資本主義経済に参加しながら、ある程度そのようなわきまえを保っているのが日本人なわけだが、
そもそも資本主義経済に参画することから忌んでいるような人間こそが未だ世界の多数派にも
上っている。全世界が完全に資本主義化したりすれば、それこそ誰もろくに実のある労働を
心がけなくなって、あっという間に世界が破綻することになるわけで(今も半分そうだが)、
資本主義者が世界の少数派に止め置かれるのも不可避なることであるとはいえるが、実際、
世界人類は全体規模で資本主義に没頭することを拒絶している。これこそは、金満主義に
よる自滅のような悪因苦果を地球人類が本能的に避けた実例であるといえ、人類全体には、
本能的に普遍的な善悪を分別する能力が備わっていた証拠ともなっているといえる。
世界の資本主義者の大多数は聖書信仰者であり、逆に非聖書圏においてこそ資本主義への参画が
滞っている場合が多い。欧米聖書圏で資本主義が提唱されたのだから当たり前といえば当たり前だが、
世の中を挙げて金満主義の悪逆非道を推し進めていったのは主に聖書圏であった一方、非聖書圏は
比較的それを避けようとした。ここからも、聖書教義こそは虚妄に即した間違った善悪の分別を
人々にけしかけるか許容する代物である一方、非聖書教義はそのようなことがないということが
推断される。普遍的な善悪は普遍的な善悪である一方、虚妄の善悪もまた虚妄の善悪で別にあり、
それは主に聖書圏における善悪や、聖書教義に基づく善悪であるといえる。普遍的な善悪の側の
信頼性の確保のためにも、このような虚妄の善悪の特筆的な誤謬性こそをよく認知すべきであり、
それにより「世界中の全ての善悪は虚妄である」などという思い込みを駆逐して行くべきだといえる。
「善を挙げて不能を教うれば則ち勧む」
「まず善人を引き立てて、(善業にかけて)不能なものを教導するようにさせれば、それなりに捗る。
(罪業まみれの善業不能者などが目指すべきなのは、まずは善人からの教導に服することだといえる。
善業不能者自身が王座に就いたりするような『第一の存在』などで決してあるべきではないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・為政第二・二〇より)
滞っている場合が多い。欧米聖書圏で資本主義が提唱されたのだから当たり前といえば当たり前だが、
世の中を挙げて金満主義の悪逆非道を推し進めていったのは主に聖書圏であった一方、非聖書圏は
比較的それを避けようとした。ここからも、聖書教義こそは虚妄に即した間違った善悪の分別を
人々にけしかけるか許容する代物である一方、非聖書教義はそのようなことがないということが
推断される。普遍的な善悪は普遍的な善悪である一方、虚妄の善悪もまた虚妄の善悪で別にあり、
それは主に聖書圏における善悪や、聖書教義に基づく善悪であるといえる。普遍的な善悪の側の
信頼性の確保のためにも、このような虚妄の善悪の特筆的な誤謬性こそをよく認知すべきであり、
それにより「世界中の全ての善悪は虚妄である」などという思い込みを駆逐して行くべきだといえる。
「善を挙げて不能を教うれば則ち勧む」
「まず善人を引き立てて、(善業にかけて)不能なものを教導するようにさせれば、それなりに捗る。
(罪業まみれの善業不能者などが目指すべきなのは、まずは善人からの教導に服することだといえる。
善業不能者自身が王座に就いたりするような『第一の存在』などで決してあるべきではないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・為政第二・二〇より)
「悔い改める」とは、本来的には「悔いて行いを改める」という意味で用いられるが、
キリスト教徒なぞは「心の中だけで悔い改める」という意味で用い、行いを改めることには用いない。
多くの非キリスト教徒は、前者のような意味に即してキリスト教徒が散々悔い改めていると
思い込んでいるものだから「クリスチャンとはなんと真摯な人々なのだろう」などとすら
勘違いしてしまっているわけだが、実際には改めるフリをしてるだけで、過ちを行いから改めたり
することは一切しないわけだから、不誠実極まりないものである。「悔い改める」という言葉を
不正に用いることで人々からの偽りの好感を得たりしているのも、これまた不誠実の上塗りだといえる。
これこそは、孔子が「自分が政治を任されたなら、まずは名辞の乱れから正していこう(子路第十三・三)」
と述べたところの「名辞の乱れ」であるといえる。「悔い改める」という言葉に、「悔いて行いを改める」
の他に「心の中だけで悔い改める」という意味までもが付帯してしまっていたりすること、これこそは
名辞の乱れの典型例であるといえ、この場合に名辞を正していくならば、「悔い改める」という言葉には
「悔いて行いを改める」という意味だけが存在することを公認し、「心の中だけで悔い改める」という
意味が他にあったりすることは公認しないといった措置を講じていく必要がある。
「悔いて行いを改める」だけが「悔い改める」という言葉の意味であるにも関わらず、性懲りもなく
「心の中だけで悔い改める」という意味で「悔い改める」という言葉を濫用する人間がいたりしたなら、
これはもう言語障害者に認定して、それ相応の社会的制限などを課していくようにしなければならない。
特に、そのような言語の不正利用を目論む人間が重職に就いたり、権威として扱われたりすることは
もってのほかで、そのせいで過ちを改めもしない性向が下位の人間にまで落とし込まれるようなことに
すらかねないから、世の中の最底辺にのみ、その居場所を追い込んでいくようにしなければならない。
キリスト教徒なぞは「心の中だけで悔い改める」という意味で用い、行いを改めることには用いない。
多くの非キリスト教徒は、前者のような意味に即してキリスト教徒が散々悔い改めていると
思い込んでいるものだから「クリスチャンとはなんと真摯な人々なのだろう」などとすら
勘違いしてしまっているわけだが、実際には改めるフリをしてるだけで、過ちを行いから改めたり
することは一切しないわけだから、不誠実極まりないものである。「悔い改める」という言葉を
不正に用いることで人々からの偽りの好感を得たりしているのも、これまた不誠実の上塗りだといえる。
これこそは、孔子が「自分が政治を任されたなら、まずは名辞の乱れから正していこう(子路第十三・三)」
と述べたところの「名辞の乱れ」であるといえる。「悔い改める」という言葉に、「悔いて行いを改める」
の他に「心の中だけで悔い改める」という意味までもが付帯してしまっていたりすること、これこそは
名辞の乱れの典型例であるといえ、この場合に名辞を正していくならば、「悔い改める」という言葉には
「悔いて行いを改める」という意味だけが存在することを公認し、「心の中だけで悔い改める」という
意味が他にあったりすることは公認しないといった措置を講じていく必要がある。
「悔いて行いを改める」だけが「悔い改める」という言葉の意味であるにも関わらず、性懲りもなく
「心の中だけで悔い改める」という意味で「悔い改める」という言葉を濫用する人間がいたりしたなら、
これはもう言語障害者に認定して、それ相応の社会的制限などを課していくようにしなければならない。
特に、そのような言語の不正利用を目論む人間が重職に就いたり、権威として扱われたりすることは
もってのほかで、そのせいで過ちを改めもしない性向が下位の人間にまで落とし込まれるようなことに
すらかねないから、世の中の最底辺にのみ、その居場所を追い込んでいくようにしなければならない。
名辞の乱れた言葉を濫用することは、確かに多くの精神障害の発端ともなっている。
古くは秦帝国の宦官趙高が、臣下たちに無理やり鹿を馬と言い張らせた「馬鹿」の逸話などがあるが、
それこそ、名辞の乱れはバカの発端でもあり、バカが酷すぎて自己修正も不能な状態ともなれば、
そこで人は分裂病などの精神疾患を患う。ある時は鹿を鹿と言い、ある時は鹿を馬と言う、
またある時は「悔い改める」を「悔いて行いを改める」という意味で用い、ある時は「心の中だけで
悔い改める」という意味で用いたりする。そういった、同一の言葉の全く食い違った意味での
多用が知識構造の深刻な分裂を生じ、矛盾する諸々の知識を統制する精神の薄弱化をも促すのである。
逆に言えば、そういった知識構造の深刻な分裂こそは「典型的な精神疾患」として取り扱うべきなのであり、
それ以外の別に害もないような風狂なぞを、矯正治療や社会的制限までをも必要とするような障害
などとしてまで取り扱ったりする必要はないのである。臣下たちに鹿を馬と言い張らせた趙高こそは
秦帝国崩壊の元凶ともなったように、名辞の乱れを濫用するものこそは傾国や亡国の元凶とすら
なるわけだから、本人たち自身に病識がなくとも、そのような人間こそは「社会的要求」に即して
矯正治療や社会的制限の対象とされねばならない。孔子が「政治を任されたならまずは名辞の乱れから
正していく」というほどにも、名辞の乱れを問題視していたのにも、それなりの理由があったのだから。
「口は費して煩し、出だし易くして悔い難し、以て人を溺らし易し」
「口先というのは、そこに労力を費やせば費やすほど当人を煩わせるものである。言葉を発するのは
簡単だがそれによって心から悔いたりすることは難しい。そのため人を濁念にも溺れさせやすいのである。
(口先だけでの『悔い改めた』などという発言によって、かえって罪過への心からの悔いも損なうのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・緇衣第三十三より)
古くは秦帝国の宦官趙高が、臣下たちに無理やり鹿を馬と言い張らせた「馬鹿」の逸話などがあるが、
それこそ、名辞の乱れはバカの発端でもあり、バカが酷すぎて自己修正も不能な状態ともなれば、
そこで人は分裂病などの精神疾患を患う。ある時は鹿を鹿と言い、ある時は鹿を馬と言う、
またある時は「悔い改める」を「悔いて行いを改める」という意味で用い、ある時は「心の中だけで
悔い改める」という意味で用いたりする。そういった、同一の言葉の全く食い違った意味での
多用が知識構造の深刻な分裂を生じ、矛盾する諸々の知識を統制する精神の薄弱化をも促すのである。
逆に言えば、そういった知識構造の深刻な分裂こそは「典型的な精神疾患」として取り扱うべきなのであり、
それ以外の別に害もないような風狂なぞを、矯正治療や社会的制限までをも必要とするような障害
などとしてまで取り扱ったりする必要はないのである。臣下たちに鹿を馬と言い張らせた趙高こそは
秦帝国崩壊の元凶ともなったように、名辞の乱れを濫用するものこそは傾国や亡国の元凶とすら
なるわけだから、本人たち自身に病識がなくとも、そのような人間こそは「社会的要求」に即して
矯正治療や社会的制限の対象とされねばならない。孔子が「政治を任されたならまずは名辞の乱れから
正していく」というほどにも、名辞の乱れを問題視していたのにも、それなりの理由があったのだから。
「口は費して煩し、出だし易くして悔い難し、以て人を溺らし易し」
「口先というのは、そこに労力を費やせば費やすほど当人を煩わせるものである。言葉を発するのは
簡単だがそれによって心から悔いたりすることは難しい。そのため人を濁念にも溺れさせやすいのである。
(口先だけでの『悔い改めた』などという発言によって、かえって罪過への心からの悔いも損なうのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・緇衣第三十三より)
「鬼神を敬して之れを遠ざく」「怪力乱神を語らず」(論語)
儒家における妖神敬遠志向は、四書五経を始めとする儒書中における
ごくありきたりな言葉での教理の説明としても現れている。別にそれが、
儒者の頭が悪いからなわけでもないのは、「易経」繋辞伝における孔子の
精密極まりない哲学的論及などからも知れるわけだが、そのような論及はあくまで
例外的なものであり、基本は誰にでも分かるような簡単な言葉での教示が心がけられている。
(そのため、そのような熟語を達筆で清書する文化などが興隆もしたのだった)
妖艶な神異などを、仮に言葉でありのままに表そうとしたなら、それこそ真言や呪文のような
不可解なものとなる。もちろんそこには確かな意味が込められているともされるわけだが、
一般人に理解不能であるからにはインチキの材料などにもされやすく、真言密教なども
異端派がインチキも同然な所業に及ぶなどの問題が歴史的に頻発してもいる。
西洋の哲学や科学にまつわる難解な論及なども、元はといえば呪術信仰などを発祥源と
するものである。そこに錬金術などの打算的な志向が加味された結果、実物の物理現象や
行為能力に訴えかける形而上的論及の体系としての近代科学や西洋哲学が生じたのである。
原始的な呪術の領域か、科学的、哲学的な領域かに関わらず、儒者であれば極端に晦渋な
論及などはなるべく避ける。それは、そこにのめりこむのでもない限りは理解できないような
難解な論及体系というものが一切合切「死文」と見なす他ないものであるからで、そんなものを
世の中での実践に適用したりした場合には、諸々の文化的停滞が避けられなくもなるからだ。
死文に基づく文化的停滞とは、たとえば「それにのめり込むものの怠慢化」「それの理解に
参加しなかったものの愚民化」などで、理解するにしろしないにしろ、難解すぎて躍動に欠ける
言葉などを、世の中で活動する人々などが自力で享受して良い効能があるようなことはない。
儒家における妖神敬遠志向は、四書五経を始めとする儒書中における
ごくありきたりな言葉での教理の説明としても現れている。別にそれが、
儒者の頭が悪いからなわけでもないのは、「易経」繋辞伝における孔子の
精密極まりない哲学的論及などからも知れるわけだが、そのような論及はあくまで
例外的なものであり、基本は誰にでも分かるような簡単な言葉での教示が心がけられている。
(そのため、そのような熟語を達筆で清書する文化などが興隆もしたのだった)
妖艶な神異などを、仮に言葉でありのままに表そうとしたなら、それこそ真言や呪文のような
不可解なものとなる。もちろんそこには確かな意味が込められているともされるわけだが、
一般人に理解不能であるからにはインチキの材料などにもされやすく、真言密教なども
異端派がインチキも同然な所業に及ぶなどの問題が歴史的に頻発してもいる。
西洋の哲学や科学にまつわる難解な論及なども、元はといえば呪術信仰などを発祥源と
するものである。そこに錬金術などの打算的な志向が加味された結果、実物の物理現象や
行為能力に訴えかける形而上的論及の体系としての近代科学や西洋哲学が生じたのである。
原始的な呪術の領域か、科学的、哲学的な領域かに関わらず、儒者であれば極端に晦渋な
論及などはなるべく避ける。それは、そこにのめりこむのでもない限りは理解できないような
難解な論及体系というものが一切合切「死文」と見なす他ないものであるからで、そんなものを
世の中での実践に適用したりした場合には、諸々の文化的停滞が避けられなくもなるからだ。
死文に基づく文化的停滞とは、たとえば「それにのめり込むものの怠慢化」「それの理解に
参加しなかったものの愚民化」などで、理解するにしろしないにしろ、難解すぎて躍動に欠ける
言葉などを、世の中で活動する人々などが自力で享受して良い効能があるようなことはない。
もちろん難解すぎるような哲学的論及の中にも、人々の悟りを促すようなよき説話もあるわけで、
そのような教説は、出家して世の中での旺盛な活動から身を引いている人間などがその勉強や
布教に務めることで、人々に良い影響を与えるようなことがあり得る。もちろんそのような人間は、
世俗での善行に専らである儒者などとは全く別物の領分の持ち主なわけで、そこまで身の程を
割り切るのなら、別に儒家の神仏に対する敬遠志向までをも倣ったりする必要はないのである。
世俗での旺盛な活動は簡単な言葉と共にあるぐらいで。難しい言葉は出家や隠遁と共に。
世俗での活動こそは「人間の生きた姿」であるというのなら、そのような活動を健全に
司れるのは簡単な言葉のほうであり、不健全な司り方しかできないのが難解な言葉なわけだから、
簡単な言葉こそは生きた言葉であり得る一方、難解な言葉こそは死んだ言葉であるといえる。
神仏を敬遠する素っ気ない言葉こそは生きた言葉である一方、怪力乱神をもてあそぶような
妖しげで不可解な言葉こそは死んだ言葉である。別にそれが人間の唯一のあり方などであるわけ
ではないが、最大級に人としての生を謳歌しようと思うなら、死文も避けるようにすべきなのである。
「君子は其の子を遠ざく」
「君子は我が子をなるべく遠ざける。(甘やかさないため、劣等感を抱かせないためなど、
理由は色々ある。犯罪聖書における『父なる神』などはあくまで架空の父であって本物の父では
ないわけだが、架空の親であるにしても、自由に子を近づけるというのは道義に悖っている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・季氏第十六・一三より)
そのような教説は、出家して世の中での旺盛な活動から身を引いている人間などがその勉強や
布教に務めることで、人々に良い影響を与えるようなことがあり得る。もちろんそのような人間は、
世俗での善行に専らである儒者などとは全く別物の領分の持ち主なわけで、そこまで身の程を
割り切るのなら、別に儒家の神仏に対する敬遠志向までをも倣ったりする必要はないのである。
世俗での旺盛な活動は簡単な言葉と共にあるぐらいで。難しい言葉は出家や隠遁と共に。
世俗での活動こそは「人間の生きた姿」であるというのなら、そのような活動を健全に
司れるのは簡単な言葉のほうであり、不健全な司り方しかできないのが難解な言葉なわけだから、
簡単な言葉こそは生きた言葉であり得る一方、難解な言葉こそは死んだ言葉であるといえる。
神仏を敬遠する素っ気ない言葉こそは生きた言葉である一方、怪力乱神をもてあそぶような
妖しげで不可解な言葉こそは死んだ言葉である。別にそれが人間の唯一のあり方などであるわけ
ではないが、最大級に人としての生を謳歌しようと思うなら、死文も避けるようにすべきなのである。
「君子は其の子を遠ざく」
「君子は我が子をなるべく遠ざける。(甘やかさないため、劣等感を抱かせないためなど、
理由は色々ある。犯罪聖書における『父なる神』などはあくまで架空の父であって本物の父では
ないわけだが、架空の親であるにしても、自由に子を近づけるというのは道義に悖っている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・季氏第十六・一三より)
他者の利益を害してでも自らが富み栄えようとする我田引水の横行の防止、
世の中における「利害反するあり(韓非子)」という事態のできる限りの抑制こそは
仁政の要である。特に、我田引水が激化し過ぎたあまり餓死者までもが多発して
しまうような状態だけは徹底して避けねばならず、全くの天災外の人災としてそのような
事態が生じてしまったとしたなら、もはや仁政など完全に失敗してしまったともいえる。
餓死者が発生してしまうほどにも極度の我田引水が横行してしまっているような世の中では、
十中八九、もはや仁政などというものは試みられてもいない。人間が自力の仁政によって
この世から餓死者を絶やすなどということは、もはや夢物語か何かのように扱われて、
全く「仕方のない現実」としての、人災による餓死まみれな世の中を許容しようとすらする。
そういった人間に対してこそ、これまた「仕方のない現実」としての、自分たちのこの世からの
強制退場という否応のない運命がやって来る。不良経済からなる人災としての戦乱や餓死が
横行し過ぎた余り、もはや国家規模や社会規模、世界規模での完全破綻が免れられなくなる、
その時に、相も変わらず「仕方のない現実」としての濁世を営み続けようとしているような
連中こそは、仕方なくないものを仕方ないものとして片付けてきた罪業のはね返りを被って、
本当に仕方のないこととして、濁世の全ての責任を負わされての自滅に見舞われることとなる。
こんなことは、この世界、この宇宙の外側に実在する超越神を想定でもしない限りは、
全く自明なことである。「限られた領域内において一部の人間が多人数の利益を収奪して、
そのほとんどを退蔵下に置いたりしたなら、そのせいで当該領域全体が破綻に見舞われる、
領域内の破綻の元凶となったのは紛れもなく一部の利益の独占者だから、破綻の責任も
独占者こそが第一に追わねばならない」、こんなことは、自己完結した思考実験の範囲内で
自明に導き出せることであり、その実験結果を別物に挿げ替えるためには、「領域外からの
超越者による救い」なんていう都合の良すぎるような条件でも付加するしかないのである。
世の中における「利害反するあり(韓非子)」という事態のできる限りの抑制こそは
仁政の要である。特に、我田引水が激化し過ぎたあまり餓死者までもが多発して
しまうような状態だけは徹底して避けねばならず、全くの天災外の人災としてそのような
事態が生じてしまったとしたなら、もはや仁政など完全に失敗してしまったともいえる。
餓死者が発生してしまうほどにも極度の我田引水が横行してしまっているような世の中では、
十中八九、もはや仁政などというものは試みられてもいない。人間が自力の仁政によって
この世から餓死者を絶やすなどということは、もはや夢物語か何かのように扱われて、
全く「仕方のない現実」としての、人災による餓死まみれな世の中を許容しようとすらする。
そういった人間に対してこそ、これまた「仕方のない現実」としての、自分たちのこの世からの
強制退場という否応のない運命がやって来る。不良経済からなる人災としての戦乱や餓死が
横行し過ぎた余り、もはや国家規模や社会規模、世界規模での完全破綻が免れられなくなる、
その時に、相も変わらず「仕方のない現実」としての濁世を営み続けようとしているような
連中こそは、仕方なくないものを仕方ないものとして片付けてきた罪業のはね返りを被って、
本当に仕方のないこととして、濁世の全ての責任を負わされての自滅に見舞われることとなる。
こんなことは、この世界、この宇宙の外側に実在する超越神を想定でもしない限りは、
全く自明なことである。「限られた領域内において一部の人間が多人数の利益を収奪して、
そのほとんどを退蔵下に置いたりしたなら、そのせいで当該領域全体が破綻に見舞われる、
領域内の破綻の元凶となったのは紛れもなく一部の利益の独占者だから、破綻の責任も
独占者こそが第一に追わねばならない」、こんなことは、自己完結した思考実験の範囲内で
自明に導き出せることであり、その実験結果を別物に挿げ替えるためには、「領域外からの
超越者による救い」なんていう都合の良すぎるような条件でも付加するしかないのである。
仮に、上記のような思考実験に「領域外からの超越者による救い」などという条件を加味
してみたところで、そんなものにばかり頼って、一定領域内での我田引水ばかりを激化させ
ようとしたりすること自体が不誠実の至りであり、人間としての不幸の積み重ねでしかない。
「利害反するあり」という状態をできる限り排して、人災による餓死者なども根絶できた
ような世の中における人々のほうが、我田引水餓死まみれの世の中における最大級の利益的
成功者などよりもさらに恒常的に幸せであるのだから、濁世の権力犯罪者にすら救いの余地を
与えようとするような超越者の存在からして、人々の不幸を助長するものでしかないといえる。
そしてそのような、人々にとっての甚大なる不幸の元凶となる超越者の存在などを絶対に想定
できなくなったのが、今というこの時代この瞬間である。かつてのヨーロッパの小国ぐらいで
あれば、まだ自国の破綻のツケを外界に回すことなども容易だった。欧英から数多の侵略者が外界
へと進出し始めた大航海時代にも、まだキリスト教圏の破綻のツケを外界に押し付けることができた。
世界中のほぼ全ての国土を可能な限りの征服下に置き、これ以上自分たちキリスト教徒の放辟邪侈
のツケを押し付けるような「外界」がどこにもなくなってしまった今、ついに、欧米キリスト教徒
たち自身こそは、自分たちの全ての過ちの責任を自分たちで負わなければならなくなった。
「外界侵略による利益の収奪」を「領域外からの超越者による救い」に摩り替えて、自分たちの
救いを邪教信仰に追い求め続けて来たツケが今、否応なく全てはね返ってくることとなった。
それは、この世界、この宇宙の大局構造に即して原理的に免れられないことであるのと同時に、
倫理的にはむしろ好ましいことである。国家規模、社会規模の破綻を頻繁に繰り返さねばならない
ほどにも我田引水が蔓延してしまっているような世の中こそは、恒常的に不幸まみれの世の中であり、
そのような世の中の存続を無理やりにでも助長して来たような理念上の超越神からして、人間にとって
は不幸の元凶となる邪神でしかなかったわけだから、そのような邪神が全く以って実在しないことが
証明され、そのような邪神に仮託した外界侵略を企てる余地が絶やされたのも、好ましいことである。
してみたところで、そんなものにばかり頼って、一定領域内での我田引水ばかりを激化させ
ようとしたりすること自体が不誠実の至りであり、人間としての不幸の積み重ねでしかない。
「利害反するあり」という状態をできる限り排して、人災による餓死者なども根絶できた
ような世の中における人々のほうが、我田引水餓死まみれの世の中における最大級の利益的
成功者などよりもさらに恒常的に幸せであるのだから、濁世の権力犯罪者にすら救いの余地を
与えようとするような超越者の存在からして、人々の不幸を助長するものでしかないといえる。
そしてそのような、人々にとっての甚大なる不幸の元凶となる超越者の存在などを絶対に想定
できなくなったのが、今というこの時代この瞬間である。かつてのヨーロッパの小国ぐらいで
あれば、まだ自国の破綻のツケを外界に回すことなども容易だった。欧英から数多の侵略者が外界
へと進出し始めた大航海時代にも、まだキリスト教圏の破綻のツケを外界に押し付けることができた。
世界中のほぼ全ての国土を可能な限りの征服下に置き、これ以上自分たちキリスト教徒の放辟邪侈
のツケを押し付けるような「外界」がどこにもなくなってしまった今、ついに、欧米キリスト教徒
たち自身こそは、自分たちの全ての過ちの責任を自分たちで負わなければならなくなった。
「外界侵略による利益の収奪」を「領域外からの超越者による救い」に摩り替えて、自分たちの
救いを邪教信仰に追い求め続けて来たツケが今、否応なく全てはね返ってくることとなった。
それは、この世界、この宇宙の大局構造に即して原理的に免れられないことであるのと同時に、
倫理的にはむしろ好ましいことである。国家規模、社会規模の破綻を頻繁に繰り返さねばならない
ほどにも我田引水が蔓延してしまっているような世の中こそは、恒常的に不幸まみれの世の中であり、
そのような世の中の存続を無理やりにでも助長して来たような理念上の超越神からして、人間にとって
は不幸の元凶となる邪神でしかなかったわけだから、そのような邪神が全く以って実在しないことが
証明され、そのような邪神に仮託した外界侵略を企てる余地が絶やされたのも、好ましいことである。
人類にとって、「一度は不幸を極める」ということも、もしかしたら必要なことだったのかもしれない。
宋代以降や明治以降、中国や日本が甚大な文化的文明的な侵略を被って来たことも、それ以前に
栄光の歴史ばかりを歩み続けていたことに対するカウンターバランスの補完として役立ったとは
いえるぐらいに、この世界に人々の不幸ばかりを助長する邪教が振興して、一時は全世界をも
不幸の渦に巻き込んだことも、地球人類にとってのショック療法的なクスリになったのかもしれない。
今ここで、かの邪教集団が完全なる棄教を決断して、「信仰存続による人類滅亡か、棄教による人類存続か」
という危機を乗り越えて人類の存続に寄与し、実際に今後も人類が存続や繁栄を遂げていくことができたと
したなら、いつかは上のような評価を受けるようなことがあるかもしれない。スポーツ選手などにとっては
怪我や病気が損失になるばかりだが、武道修練者などにとっては、技の修練に際して負った腰痛や筋違い
などの支障が、かえって技を修正するいい機縁になったりする。人類がこれからスポーツ選手ではなく
武道修練者のような心がけで世の中を営んでいくのなら、邪教の蔓延に基づく今の世の中の腐敗すら、
何らかの向上のための材料として、転用していけるようなことがあるかもしれないのである。
「三代の天下を得るや仁を以ってし、其の天下を失うや不仁を以ってせり。国の以って廃興存亡する所の者も
亦た然り。天子不仁なれば四海は保んぜず、諸侯不仁なれば社稷は保んぜず、卿大夫不仁なれば宗廟は保んぜず、
士庶人不仁なれば四体も保んぜず。今死亡を悪みて不仁を楽しむは、是れ猶お醉いを悪みて酒を強うるが如し」
「夏殷周三代の大国が興ったのは仁に依り、その天下を失ったのは不仁に依る。その他の国々が存亡興廃したりする
のも全くこれと同じ理由に依る。天子が不仁であれば諸国が保たれず、諸国の王侯が不仁であれば社稷が保たれず、
卿大夫が不仁であれば宋廟が保たれず、下士庶民が不仁であればその四体もろくに保たれない。自分個人の死を憎み
嫌いながら不仁を楽しんだりするのは、まるで酔うのを嫌いながら酒を強いるようなもので、全く理に適っていない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句上・三より)
宋代以降や明治以降、中国や日本が甚大な文化的文明的な侵略を被って来たことも、それ以前に
栄光の歴史ばかりを歩み続けていたことに対するカウンターバランスの補完として役立ったとは
いえるぐらいに、この世界に人々の不幸ばかりを助長する邪教が振興して、一時は全世界をも
不幸の渦に巻き込んだことも、地球人類にとってのショック療法的なクスリになったのかもしれない。
今ここで、かの邪教集団が完全なる棄教を決断して、「信仰存続による人類滅亡か、棄教による人類存続か」
という危機を乗り越えて人類の存続に寄与し、実際に今後も人類が存続や繁栄を遂げていくことができたと
したなら、いつかは上のような評価を受けるようなことがあるかもしれない。スポーツ選手などにとっては
怪我や病気が損失になるばかりだが、武道修練者などにとっては、技の修練に際して負った腰痛や筋違い
などの支障が、かえって技を修正するいい機縁になったりする。人類がこれからスポーツ選手ではなく
武道修練者のような心がけで世の中を営んでいくのなら、邪教の蔓延に基づく今の世の中の腐敗すら、
何らかの向上のための材料として、転用していけるようなことがあるかもしれないのである。
「三代の天下を得るや仁を以ってし、其の天下を失うや不仁を以ってせり。国の以って廃興存亡する所の者も
亦た然り。天子不仁なれば四海は保んぜず、諸侯不仁なれば社稷は保んぜず、卿大夫不仁なれば宗廟は保んぜず、
士庶人不仁なれば四体も保んぜず。今死亡を悪みて不仁を楽しむは、是れ猶お醉いを悪みて酒を強うるが如し」
「夏殷周三代の大国が興ったのは仁に依り、その天下を失ったのは不仁に依る。その他の国々が存亡興廃したりする
のも全くこれと同じ理由に依る。天子が不仁であれば諸国が保たれず、諸国の王侯が不仁であれば社稷が保たれず、
卿大夫が不仁であれば宋廟が保たれず、下士庶民が不仁であればその四体もろくに保たれない。自分個人の死を憎み
嫌いながら不仁を楽しんだりするのは、まるで酔うのを嫌いながら酒を強いるようなもので、全く理に適っていない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句上・三より)
犯罪聖書スレの常駐員に聞け。
「浸潤の譖り、膚受の愬え、行われざるは、明と謂う可きなるのみ。
浸潤の譖り、膚受の愬え、行われざるは、遠きと謂う可きなるのみ」
「心にじわじわと染み込んで来るような陰湿な悪口や、肌身に突き刺さってくるような痛烈な訴えといえども
通用させないようであれば、聡明であるといえるだろう。心にじわじわと染み込んで来るような陰湿な悪口や、
肌身に突き刺さってくるような痛烈な訴えといえども通用させないようであれば、遠慮が効いているといえる」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・顔淵第十二・六より)
四書五経中にも、「孔子が妾腹の私生児だった」ということが明記されているわけではない。
孔子自身、「若い頃自分は卑しかった(子罕第九・六)」と言っているし、孟子も「孤立した臣下や妾腹の子は
注意力を高めて上達する場合がある(尽心章句上・一八)」と言っているなど、暗に孔子が妾腹の私生児で
あったことを示唆するような記述はいくらかある。そうであったことが明記されているのは「史記」孔子世家などであり、
何でもかんでも根掘り葉掘り書き立てている「史記」の記録姿勢も、必ずしも儒者に手放しに評価されているわけではない。
特に孔子自身の「若い頃自分は卑しかった」という独白は、自分が妾腹の私生児の如き境遇に生まれ育ったことを
卑下した言葉として特筆に価する。本人自身がこう言うからには、周囲の人間も不遇な生まれつきに対する同情などを
抱く必要もない。もしも妾腹の私生児という生まれ付きを「神の子」だなどと自称したなら、それによってある者からは
同情を買い、またある者からは顰蹙を買うといったような、不埒な扇情を催したに違いないわけだが、孔子はそのような
選択肢をキッパリと斬り捨てて、無闇に人からの同情を買ったりすることの不適切さを上記のような言葉で戒めもしたのである。
浸潤の譖り、膚受の愬え、行われざるは、遠きと謂う可きなるのみ」
「心にじわじわと染み込んで来るような陰湿な悪口や、肌身に突き刺さってくるような痛烈な訴えといえども
通用させないようであれば、聡明であるといえるだろう。心にじわじわと染み込んで来るような陰湿な悪口や、
肌身に突き刺さってくるような痛烈な訴えといえども通用させないようであれば、遠慮が効いているといえる」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・顔淵第十二・六より)
四書五経中にも、「孔子が妾腹の私生児だった」ということが明記されているわけではない。
孔子自身、「若い頃自分は卑しかった(子罕第九・六)」と言っているし、孟子も「孤立した臣下や妾腹の子は
注意力を高めて上達する場合がある(尽心章句上・一八)」と言っているなど、暗に孔子が妾腹の私生児で
あったことを示唆するような記述はいくらかある。そうであったことが明記されているのは「史記」孔子世家などであり、
何でもかんでも根掘り葉掘り書き立てている「史記」の記録姿勢も、必ずしも儒者に手放しに評価されているわけではない。
特に孔子自身の「若い頃自分は卑しかった」という独白は、自分が妾腹の私生児の如き境遇に生まれ育ったことを
卑下した言葉として特筆に価する。本人自身がこう言うからには、周囲の人間も不遇な生まれつきに対する同情などを
抱く必要もない。もしも妾腹の私生児という生まれ付きを「神の子」だなどと自称したなら、それによってある者からは
同情を買い、またある者からは顰蹙を買うといったような、不埒な扇情を催したに違いないわけだが、孔子はそのような
選択肢をキッパリと斬り捨てて、無闇に人からの同情を買ったりすることの不適切さを上記のような言葉で戒めもしたのである。
実際、妾腹の子だとか私生児だとか、寡婦だとか鰥夫だとかいった境遇は、無いに越したことのないものであるには違いない。
孟子の言うとおり、孔子が妾腹の私生児としての不遇をバネにして礼学者として大成したのも確かなことである。しかし、
妾腹の私生児が不遇をバネにしてまで、仁義礼楽を体系化しなければならなかったのは、春秋時代末期という当時の世相が、
今にも正統な礼楽刑政の風習が途絶えようとしていた濁世であったからで、実際、春秋時代と共に周朝は滅亡し、
中国史上でも最悪級の乱世である戦国時代へと、中国全土が突入していくことともなったのである。
そこからまた時代が移り変わって、漢代に撥乱反正の治世が中原に広められた頃、今度は、別に生まれ育ちが特段不遇だったり
するわけでもないような数多の儒者たちが治世の確立に貢献もしたのだった。それは当時の中国が、妾腹の私生児までもが
超人的な能力を発揮して礼楽の保護に努めなければならないほど、荒んだ時代でもなかったからだ、孔子が興した儒学と
いえども、その本領が発揮されたのはそのような、むしろ孔子級の働きまでは必要とされなかった時代だったのである。
なればこそ、いつの時代といえども、己れの不遇を嵩にかかっての同情売りなどは、控えて然るべきものなのだといえる。
不遇をバネにした大成こそがものを言うような乱世においても、むしろそのような能力に基づく実物の業績を挙げることに
専らであるべきだし、そんな能力の発揮がものを言うわけでもない治世においては、もはや不遇にある人間こそがその
存在価値を買われるべきなどということもないわけだから、これまたそんな人間が出しゃばる余地は無いのだといえる。
故に、「痛烈な同情売りなど通用させないでこそ聡明である」という孔子の発言もまた普遍的であることが分かるのである。
孟子の言うとおり、孔子が妾腹の私生児としての不遇をバネにして礼学者として大成したのも確かなことである。しかし、
妾腹の私生児が不遇をバネにしてまで、仁義礼楽を体系化しなければならなかったのは、春秋時代末期という当時の世相が、
今にも正統な礼楽刑政の風習が途絶えようとしていた濁世であったからで、実際、春秋時代と共に周朝は滅亡し、
中国史上でも最悪級の乱世である戦国時代へと、中国全土が突入していくことともなったのである。
そこからまた時代が移り変わって、漢代に撥乱反正の治世が中原に広められた頃、今度は、別に生まれ育ちが特段不遇だったり
するわけでもないような数多の儒者たちが治世の確立に貢献もしたのだった。それは当時の中国が、妾腹の私生児までもが
超人的な能力を発揮して礼楽の保護に努めなければならないほど、荒んだ時代でもなかったからだ、孔子が興した儒学と
いえども、その本領が発揮されたのはそのような、むしろ孔子級の働きまでは必要とされなかった時代だったのである。
なればこそ、いつの時代といえども、己れの不遇を嵩にかかっての同情売りなどは、控えて然るべきものなのだといえる。
不遇をバネにした大成こそがものを言うような乱世においても、むしろそのような能力に基づく実物の業績を挙げることに
専らであるべきだし、そんな能力の発揮がものを言うわけでもない治世においては、もはや不遇にある人間こそがその
存在価値を買われるべきなどということもないわけだから、これまたそんな人間が出しゃばる余地は無いのだといえる。
故に、「痛烈な同情売りなど通用させないでこそ聡明である」という孔子の発言もまた普遍的であることが分かるのである。
人間は救われるためではなく、救われなければならないような破滅的事態に
自らが遭遇したりしないためにこそ、断悪修善や勧善懲悪をこころがけるものである。
それにより悪因苦果を避けて善因楽果にも与り、人として最大級の福利厚生をも得るのである。
たとえ救われるとしたって、救われなければならないような事態に陥ってしまっていること
自体がすでに比較的不幸なことであり、救われない場合と比べてもさして変わらないほどに、
本人たち自身の心性が悪因苦果にまみれてしまっていることに変わりはない。
全世界が破滅的な事態に見舞われて、誰一人として「救われるか救われないか」という二者択一
から逃れられないような状態になってしまっているとすれば、これはもう、どこにも断悪修善や
勧善懲悪を実行できる余地がなくなってしまっているに違いなく、多少善行を為しているらしい
ような人間がいたところで、所詮は悪行以内の偽善行しか為せていないに違いないのである。
誰も本当の善悪の分別が付かなくなってしまっているような状況では、誰も本当の善行が
できなくなる。善行というのは、遠方の的に矢を命中させるようなもので、メクラ滅法に
矢を放ったからといって命中したりはしないのと同じように、善悪の分別もないままに
一概な善行を為せたりすることもありはしない。だから、いっさい善悪の分別が付けられなく
なってしまっているような世の中において、善行を為して行ける人間もまたあり得はしない。
しかし、実際問題、絶対真理にも即した普遍的な善悪の分別というものは実在していて、
誰か一人でもそれに気づいた途端に、全世界が「救われるまでもなくて済む世の中」となる。
救われるか救われないかなんていう所に全てを還元すること自体がひどく低レベルなこととなり、
そんな所に話を集約させようとする連中全員が大恥をかかせられるようなことにもなる。
自らが遭遇したりしないためにこそ、断悪修善や勧善懲悪をこころがけるものである。
それにより悪因苦果を避けて善因楽果にも与り、人として最大級の福利厚生をも得るのである。
たとえ救われるとしたって、救われなければならないような事態に陥ってしまっていること
自体がすでに比較的不幸なことであり、救われない場合と比べてもさして変わらないほどに、
本人たち自身の心性が悪因苦果にまみれてしまっていることに変わりはない。
全世界が破滅的な事態に見舞われて、誰一人として「救われるか救われないか」という二者択一
から逃れられないような状態になってしまっているとすれば、これはもう、どこにも断悪修善や
勧善懲悪を実行できる余地がなくなってしまっているに違いなく、多少善行を為しているらしい
ような人間がいたところで、所詮は悪行以内の偽善行しか為せていないに違いないのである。
誰も本当の善悪の分別が付かなくなってしまっているような状況では、誰も本当の善行が
できなくなる。善行というのは、遠方の的に矢を命中させるようなもので、メクラ滅法に
矢を放ったからといって命中したりはしないのと同じように、善悪の分別もないままに
一概な善行を為せたりすることもありはしない。だから、いっさい善悪の分別が付けられなく
なってしまっているような世の中において、善行を為して行ける人間もまたあり得はしない。
しかし、実際問題、絶対真理にも即した普遍的な善悪の分別というものは実在していて、
誰か一人でもそれに気づいた途端に、全世界が「救われるまでもなくて済む世の中」となる。
救われるか救われないかなんていう所に全てを還元すること自体がひどく低レベルなこととなり、
そんな所に話を集約させようとする連中全員が大恥をかかせられるようなことにもなる。
全世界が「救われるまでもなくて済む世の中」であるからには、
救われるか救われないかで言えば、みんな救われるのである。
阿弥陀如来が普遍的な善悪の分別に即した自力作善によって
救済を尽くしたなら、全世界の誰しもが救われる。自ら救済を拒むほどもの
愚人でもない限りは誰でも救われ得るから、万人救済を当たり前の大前提として、
親鸞聖人も「善人なおもて往生を遂ぐ、いわんや悪人をや」と述べられたのである。
「救われるか救われないか」ばかりに全てを集約させてものを考えているうちは、
そんなことは思いもよらない。そういう風にしかものを考えられないのは、
自分自身がまともに善悪の分別も付けられないままでいるからだ。正しい倫理的判断に
即するなら、立派な公職であると見なさねばならない徴税者を「罪人」扱いしたりする
ほどにも、自分自身が善悪の分別など思いもよらない愚人となってしまっているからだ。
卒業すべきは、その蒙昧である。
「救われるか救われないか」の範囲でしか何も考えることができない、
末期状態のギャンブラー並みに危うい心理状態からこそ、もう脱却して行かなければならない。
その危うさこそが、本来はあり得もしないような危難すらをもわざわざ呼び込んでいるのだから、
そのような自業自得の危難から人々を救ってやろうとするような神もまた、邪神であることが
確かである。人々を救済する神というのは表向きだけで、実際には、人々の自業自得の苦難を
増長させる禍いの神でこそあるのだから、もうそんな神を意識すらすべきでないのである。
「天、有徳を命ず、五服五章なる哉。天、有罪を討つ、五刑五用なる哉。政事懋まん哉、懋まん哉」
「天は有徳者を高位に命じることを望んでおられるようですので、五段階の等級を分けて命じましょう。
天は有罪者を討伐することを望んでおられるようですので、これも五段階の等級を分けて罰しましょう。
さあ、政事に励みましょうや、励みましょうや。(罪と別のものとして徳を見定め、そこに罪状並みの
等級分けすら行っている。漢字で『徳』と表記する東洋的、積極的徳の原形であるといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・虞書・皋陶謨より)
救われるか救われないかで言えば、みんな救われるのである。
阿弥陀如来が普遍的な善悪の分別に即した自力作善によって
救済を尽くしたなら、全世界の誰しもが救われる。自ら救済を拒むほどもの
愚人でもない限りは誰でも救われ得るから、万人救済を当たり前の大前提として、
親鸞聖人も「善人なおもて往生を遂ぐ、いわんや悪人をや」と述べられたのである。
「救われるか救われないか」ばかりに全てを集約させてものを考えているうちは、
そんなことは思いもよらない。そういう風にしかものを考えられないのは、
自分自身がまともに善悪の分別も付けられないままでいるからだ。正しい倫理的判断に
即するなら、立派な公職であると見なさねばならない徴税者を「罪人」扱いしたりする
ほどにも、自分自身が善悪の分別など思いもよらない愚人となってしまっているからだ。
卒業すべきは、その蒙昧である。
「救われるか救われないか」の範囲でしか何も考えることができない、
末期状態のギャンブラー並みに危うい心理状態からこそ、もう脱却して行かなければならない。
その危うさこそが、本来はあり得もしないような危難すらをもわざわざ呼び込んでいるのだから、
そのような自業自得の危難から人々を救ってやろうとするような神もまた、邪神であることが
確かである。人々を救済する神というのは表向きだけで、実際には、人々の自業自得の苦難を
増長させる禍いの神でこそあるのだから、もうそんな神を意識すらすべきでないのである。
「天、有徳を命ず、五服五章なる哉。天、有罪を討つ、五刑五用なる哉。政事懋まん哉、懋まん哉」
「天は有徳者を高位に命じることを望んでおられるようですので、五段階の等級を分けて命じましょう。
天は有罪者を討伐することを望んでおられるようですので、これも五段階の等級を分けて罰しましょう。
さあ、政事に励みましょうや、励みましょうや。(罪と別のものとして徳を見定め、そこに罪状並みの
等級分けすら行っている。漢字で『徳』と表記する東洋的、積極的徳の原形であるといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・虞書・皋陶謨より)
 人間の身体に、発光する部分はない。特に、生存中に身体が発光することこそがない。
人間の身体に、発光する部分はない。特に、生存中に身体が発光することこそがない。 細胞が燃えて焼け死ねば、その時に炎が光を発するし、腐乱した遺体から抜け出た
リンが化学反応を起こして光ることもある。(これが人魂伝説の正体ともされる)
むしろ死してこそ人は光を発する一方、存命中に自らが光り輝くようなことはないのだから、
実相に即して考えてみるならば、「永遠の命」などを光に見立てるのは倒錯だといえる一方、
「不生不滅」の悟りの境地を光に見立てたりするのは、別に間違ったことでもないといえる。
夜光生物なら命を光に見立てていいのかといえば、それもそんなに適切なことではない。
ホタルやホタルイカなどの発光部位も、心臓などの命を司る部位であるわけではないわけで、
命というものそれ自体が光と等価である実例にまでなっているわけではない。
命は、光でもなければ闇でもない、この世界で最も有機的な物体である。物体だから完全に
唯物的に扱っていいというわけでもなく、物体でありながら光や闇に強く感化される所がある。
人体が植物の葉緑体のように光合成を行うわけではないが、目に光を見て何かを感じ、
肌に光を浴びて温もりを感じるようなことがある。そういった光の享受の仕方や、逆に
光を避けることでの闇の享受の仕方が、人々の生き方にまで多大なる影響を及ぼしている。
達磨大師が、若い頃に見事な宝玉を見て「確かに美しいですが、この宝玉そのものが輝いて
いるわけではありません。もっと大切なものが他にあるはずです」と述べたという伝説など、
光に対する実相的な把握が秀逸だった好例となっている。上に述べたとおり、命というものもまた、
基本は光り輝くものではない。むしろドロドロジメジメとした陰湿な血肉の塊であり、それが
美女などの形で美しく見えることがあったとしても、あくまで外部から光を受けてこそのことである。
食物を摂ることで熱エネルギーが命に換わるが、その食物が実り育つ上での最大級の熱源となっている
のも太陽であり、人は光り輝く太陽に依存しきることで、辛うじて陰湿な命を繋いでいるのだといえる。
光というものを根源的なもの、本質的なものと捉えるのは、間違ったことではない。ただ、その光が
実際上どこを根源としているのかを見極めるか、見損なうかで、人の品性も極端に遠ざかってしまう。
太陽のような本物の光源を見極められている者こそは、達磨のように品性を磨き上げられもする一方、
本物の光源というものが見極められず、こじ付けで自分自身の命などを光源として扱ってしまったり
したなら、そのせいで不健全な自意識過剰を募らせて、かえって品性を下落させてしまったりもする。
命は光そのものではなく、外部から光を受けて生かされているものであるということをわきまえられてこそ、
命というものを本当に適切に扱えるようにもなる。無闇に偏重も軽んじもせず、時宜に即して至極適正に
扱えるようになる。そしたら、一方では巨万の富を退蔵しての放辟邪侈、一方ではなけなしの食糧にすら
与れなくての大量餓死なんていうような、狂いきった世相を根本から是正していけるようにもなったりする。
命が光そのものなのではなく、外部からの光を反射して輝くようなことがあるのみであるという
事実関係を諾うことができればこそ、人は本物の光をも知るのである。崇めるに値する本物の
光源を知り、そこに崇敬の念を注ぐことで、偽りのない誇りや、心からの安楽をも得るのである。
諸々の動物ですら、日向ぼっこをするぐらいのことはある。本物の光源を取り違えたりしない度合いでは、
人間よりも動物のほうが上ですらある。動物よりも知能で優れているはずの人間のほうが、知能面で事実誤認の
過ちを犯すことがあるわけで、それぐらいは克服できてこそ、人間も万物の霊長と見なすに値するといえる。
のも太陽であり、人は光り輝く太陽に依存しきることで、辛うじて陰湿な命を繋いでいるのだといえる。
光というものを根源的なもの、本質的なものと捉えるのは、間違ったことではない。ただ、その光が
実際上どこを根源としているのかを見極めるか、見損なうかで、人の品性も極端に遠ざかってしまう。
太陽のような本物の光源を見極められている者こそは、達磨のように品性を磨き上げられもする一方、
本物の光源というものが見極められず、こじ付けで自分自身の命などを光源として扱ってしまったり
したなら、そのせいで不健全な自意識過剰を募らせて、かえって品性を下落させてしまったりもする。
命は光そのものではなく、外部から光を受けて生かされているものであるということをわきまえられてこそ、
命というものを本当に適切に扱えるようにもなる。無闇に偏重も軽んじもせず、時宜に即して至極適正に
扱えるようになる。そしたら、一方では巨万の富を退蔵しての放辟邪侈、一方ではなけなしの食糧にすら
与れなくての大量餓死なんていうような、狂いきった世相を根本から是正していけるようにもなったりする。
命が光そのものなのではなく、外部からの光を反射して輝くようなことがあるのみであるという
事実関係を諾うことができればこそ、人は本物の光をも知るのである。崇めるに値する本物の
光源を知り、そこに崇敬の念を注ぐことで、偽りのない誇りや、心からの安楽をも得るのである。
諸々の動物ですら、日向ぼっこをするぐらいのことはある。本物の光源を取り違えたりしない度合いでは、
人間よりも動物のほうが上ですらある。動物よりも知能で優れているはずの人間のほうが、知能面で事実誤認の
過ちを犯すことがあるわけで、それぐらいは克服できてこそ、人間も万物の霊長と見なすに値するといえる。
「先君の令徳を光昭けくせんこと、務めざる可けんや。吾が子、其れ先君の功を廃つること無かれ」
「先君から引き継いだこの令徳を、光の如く明らかにすることにどうして務めないでおれようか。
我が子たちよ、おまえたちも決して先君の功業を打ち捨てて勝手を働いたりすることがないように。
(先祖の威徳を『光』に譬えているが、やはり自分一身の命などは超えた所にあるとされる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・隠公三年より)
「先君から引き継いだこの令徳を、光の如く明らかにすることにどうして務めないでおれようか。
我が子たちよ、おまえたちも決して先君の功業を打ち捨てて勝手を働いたりすることがないように。
(先祖の威徳を『光』に譬えているが、やはり自分一身の命などは超えた所にあるとされる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・隠公三年より)
「目には目を、歯には歯を(ハムラビ法典)」が復讐なら、
「直きを以って怨みに報う(憲問第十四・三六)」もまた一種の復讐である。
違うのは、前者が完全なる同態復讐である一方で、後者はそうとも限らない復讐であるという点である。
「直きを以って怨みに報う」といえども、ほぼ同態復讐となる場合があり得る。
親を殺された場合の仇討ちが果たされて、犯人が殺された上に、その犯人に子供がいたならば、その
子供にとっては「親殺しの復讐で自分の親が殺された」ということになる。「父母の仇とは天下を共にせず」
と「礼記」檀弓上第三にもあるとおり、純正な人間道徳に基づいても、親殺しに対する復讐は相手の殺害
ですらあるべきもので、これこそは「直きを以って怨みに報う」が同態復讐に近似する特例ともなっている。
一方で、「直きを以って怨みに報う」は、同態復讐よりは道義的である場合がほとんどである。
強盗をされたからといって自分が強盗をやり返したりするのではなく、犯人を裁きにかけて、
強奪物を返品させたり、相応の処罰を科したりする。犯罪に対する復讐に道義性を帯びさせたのが
正式な刑罰であり、それが「目には目を、歯には歯を」そのものであるとも限らない。
江戸時代の日本のように、五十両(約三百万円)の金を盗めば死罪となることもあった。
これは同態復讐以上にも過酷な刑罰だったように思われるかもしれないが、当時、
食い扶持に困った女子が身売りをする場合の相場が約五十両だったとされ、人の生き死にを
左右する最低限の金額が五十両だったわけである。故に、五十両を盗むものは殺人同然の
罪を犯したものとされ、同態復讐と同等の裁量に即して死罪に処されたのである。
親殺しを以って親殺しに報う程の場合か、それよりはより法的な手続きを踏む場合かに関わらず、
「直きを以って怨みに報う」に基づく報復も、同態復讐並みに厳酷である場合がほとんどである。
ただ、同態復讐と決定的に違うのは、過剰報復を一貫して避けるという点である。
「直きを以って怨みに報う(憲問第十四・三六)」もまた一種の復讐である。
違うのは、前者が完全なる同態復讐である一方で、後者はそうとも限らない復讐であるという点である。
「直きを以って怨みに報う」といえども、ほぼ同態復讐となる場合があり得る。
親を殺された場合の仇討ちが果たされて、犯人が殺された上に、その犯人に子供がいたならば、その
子供にとっては「親殺しの復讐で自分の親が殺された」ということになる。「父母の仇とは天下を共にせず」
と「礼記」檀弓上第三にもあるとおり、純正な人間道徳に基づいても、親殺しに対する復讐は相手の殺害
ですらあるべきもので、これこそは「直きを以って怨みに報う」が同態復讐に近似する特例ともなっている。
一方で、「直きを以って怨みに報う」は、同態復讐よりは道義的である場合がほとんどである。
強盗をされたからといって自分が強盗をやり返したりするのではなく、犯人を裁きにかけて、
強奪物を返品させたり、相応の処罰を科したりする。犯罪に対する復讐に道義性を帯びさせたのが
正式な刑罰であり、それが「目には目を、歯には歯を」そのものであるとも限らない。
江戸時代の日本のように、五十両(約三百万円)の金を盗めば死罪となることもあった。
これは同態復讐以上にも過酷な刑罰だったように思われるかもしれないが、当時、
食い扶持に困った女子が身売りをする場合の相場が約五十両だったとされ、人の生き死にを
左右する最低限の金額が五十両だったわけである。故に、五十両を盗むものは殺人同然の
罪を犯したものとされ、同態復讐と同等の裁量に即して死罪に処されたのである。
親殺しを以って親殺しに報う程の場合か、それよりはより法的な手続きを踏む場合かに関わらず、
「直きを以って怨みに報う」に基づく報復も、同態復讐並みに厳酷である場合がほとんどである。
ただ、同態復讐と決定的に違うのは、過剰報復を一貫して避けるという点である。
たとえばの話、自分が強盗に全財産を奪われたとする。だからといって自分も相手の全財産を
奪い返したとしたなら、かえって自分の財産が増える場合もある。奪われた財産と、強盗自身の財産とを
合わせてより財産が増したりすることになるわけだが、これは「全財産収奪には全財産収奪を」という
同態復讐にはなっている。「直きを以って怨みに報う」んなら、決してこんなことはあってはならない。
「他者の犯罪行為をさらなる利殖の手がかりとする」などということは絶対にないようにしなければならない。
イラクが外国を侵略したからといって、なぜかアメリカがイラクの石油利権を奪取し、
エジプトやリビアで体制革命があったからといって、なぜかEU主体のNATO軍が軍産利権をせしめる。
「直きを以って怨みに報う」のなら、決してそんなことはあり得ないことのはずで、
所詮、「目には目を、歯には歯を」や「右の頬を打たれれば左の頬も差し出せ」レベルの
低劣な倫理観しか持ち合わせていないままでいるような未開領域での恥辱沙汰だったのだといえる。
「直きを以って怨みに報う」という倫理観こそが、「目には目を、歯に歯を」という倫理観の欠陥性を
白日の下にさらけ出している。後者の同態復讐も、それだけを聞けば最もな教条のように思われたりもするが、
所詮は上記のような問題を来たしてしまうことがあるわけだから、同態復讐ばかりを凶事処理の原則などに
していてはならないことが分かる。当然、だからといって「右の頬を打たれれば左の頬も差し出せ」でいい
わけもない。「直きを以って怨みに報う」か、さもなくば「徳を以って怨みに報う」か。己れの徳によって
怨み沙汰を立ち消えにさせられるほどでもないのなら、正直を第一として凶事を処するに越したことはないのである。
奪い返したとしたなら、かえって自分の財産が増える場合もある。奪われた財産と、強盗自身の財産とを
合わせてより財産が増したりすることになるわけだが、これは「全財産収奪には全財産収奪を」という
同態復讐にはなっている。「直きを以って怨みに報う」んなら、決してこんなことはあってはならない。
「他者の犯罪行為をさらなる利殖の手がかりとする」などということは絶対にないようにしなければならない。
イラクが外国を侵略したからといって、なぜかアメリカがイラクの石油利権を奪取し、
エジプトやリビアで体制革命があったからといって、なぜかEU主体のNATO軍が軍産利権をせしめる。
「直きを以って怨みに報う」のなら、決してそんなことはあり得ないことのはずで、
所詮、「目には目を、歯には歯を」や「右の頬を打たれれば左の頬も差し出せ」レベルの
低劣な倫理観しか持ち合わせていないままでいるような未開領域での恥辱沙汰だったのだといえる。
「直きを以って怨みに報う」という倫理観こそが、「目には目を、歯に歯を」という倫理観の欠陥性を
白日の下にさらけ出している。後者の同態復讐も、それだけを聞けば最もな教条のように思われたりもするが、
所詮は上記のような問題を来たしてしまうことがあるわけだから、同態復讐ばかりを凶事処理の原則などに
していてはならないことが分かる。当然、だからといって「右の頬を打たれれば左の頬も差し出せ」でいい
わけもない。「直きを以って怨みに報う」か、さもなくば「徳を以って怨みに報う」か。己れの徳によって
怨み沙汰を立ち消えにさせられるほどでもないのなら、正直を第一として凶事を処するに越したことはないのである。
「独夫受、洪いに惟れ威を作す、乃ち汝じの世仇なり。徳を樹つるには滋を務め、
悪を除くには本を務む。肆に予れ小子、誕いに爾じら衆士を以って、乃じの仇を殄殲せん」
「あの、天から見放された哀れな男(紂王)は、無益に粗暴な威を振るい、諸君たちにとっての先祖代々の
仇となって来た。徳を育てるにはじっくりと根気よく努めねばならず、悪を除くにはその根本から根こそぎで
なければならぬ。故に私は、諸君らのごとき壮士を引き連れて、諸君らの仇を討ち果たすのである。
(あらゆる復讐の内でも、権力犯罪者の如き巨悪に対する復習こそは『根こそぎ』でなければならない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・泰誓下より)
悪を除くには本を務む。肆に予れ小子、誕いに爾じら衆士を以って、乃じの仇を殄殲せん」
「あの、天から見放された哀れな男(紂王)は、無益に粗暴な威を振るい、諸君たちにとっての先祖代々の
仇となって来た。徳を育てるにはじっくりと根気よく努めねばならず、悪を除くにはその根本から根こそぎで
なければならぬ。故に私は、諸君らのごとき壮士を引き連れて、諸君らの仇を討ち果たすのである。
(あらゆる復讐の内でも、権力犯罪者の如き巨悪に対する復習こそは『根こそぎ』でなければならない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・泰誓下より)
自分が加害者となるのであれ被害者となるのであれ、「害為」を是として
それを信仰対象とすらするのであれば、それは「害為正法外道」である。
この名で呼べば、大抵の人間は「そんなものが許されていいはずがない」と
考えるに違いないわけだが、「自分が他者に迫害されることを是とする」と聞けば、
それも害為正法外道であるにもかかわらず、あまり悪く思えなかったりするのである。
兵事だ武事だも、害為正法外道的な理念に即して執り行われる場合もあれば、
あくまで平和主義に即して執り行われる場合もある。前者は覇道となる一方、
後者は王道となり、人倫に即するなら覇道よりも王道のほうが優位なものとされる。
ただ、人倫に即して王道のほうが優位だからといって、必ずしも王道のほうが
覇道よりも強いとは限らない。徹底した平和主義でいた周文王を殷の紂王は
幽閉などの迫害下に置き、>>163にあるような暴威をふるってもいた。それでも
文王自身は紂王との反目などを徹底して避け、幽閉された中での易占によって
「明夷は艱貞に利あり(不当な迫害下においては正しきを貫くものに天が利する)」
という結果をも得た。そのまま文王は紂王への臣従を貫いたままで死するも、
文王の徳を慕って天下全土の諸国が周の味方に付き、文王の息子の武王を立てて
殷を放伐し、中国史上最長の王朝である周朝を創建させもしたのだった。このような
事実から考えるに、確かに王道は覇道よりも弱小である場合もあり得るが、だからと
いって覇道が王道を迫害下に置いたりするようなら、それにより王道のほうが力を付けて、
最終的に王道のほうが強大さでも覇道を上回り、覇道に勝つことになるのだといえる。
一時的に覇道の強大さが王道を上回ることがあっても、最終的には王道が勝つということは、
害為正法外道的な理念に基づく武威の振りかざしもまた、一時的に害為否定者のそれを
上回るようなことがあったとした所で、いつかは敗れ去ってしまうということである。
それを信仰対象とすらするのであれば、それは「害為正法外道」である。
この名で呼べば、大抵の人間は「そんなものが許されていいはずがない」と
考えるに違いないわけだが、「自分が他者に迫害されることを是とする」と聞けば、
それも害為正法外道であるにもかかわらず、あまり悪く思えなかったりするのである。
兵事だ武事だも、害為正法外道的な理念に即して執り行われる場合もあれば、
あくまで平和主義に即して執り行われる場合もある。前者は覇道となる一方、
後者は王道となり、人倫に即するなら覇道よりも王道のほうが優位なものとされる。
ただ、人倫に即して王道のほうが優位だからといって、必ずしも王道のほうが
覇道よりも強いとは限らない。徹底した平和主義でいた周文王を殷の紂王は
幽閉などの迫害下に置き、>>163にあるような暴威をふるってもいた。それでも
文王自身は紂王との反目などを徹底して避け、幽閉された中での易占によって
「明夷は艱貞に利あり(不当な迫害下においては正しきを貫くものに天が利する)」
という結果をも得た。そのまま文王は紂王への臣従を貫いたままで死するも、
文王の徳を慕って天下全土の諸国が周の味方に付き、文王の息子の武王を立てて
殷を放伐し、中国史上最長の王朝である周朝を創建させもしたのだった。このような
事実から考えるに、確かに王道は覇道よりも弱小である場合もあり得るが、だからと
いって覇道が王道を迫害下に置いたりするようなら、それにより王道のほうが力を付けて、
最終的に王道のほうが強大さでも覇道を上回り、覇道に勝つことになるのだといえる。
一時的に覇道の強大さが王道を上回ることがあっても、最終的には王道が勝つということは、
害為正法外道的な理念に基づく武威の振りかざしもまた、一時的に害為否定者のそれを
上回るようなことがあったとした所で、いつかは敗れ去ってしまうということである。
他者を迫害するものが、自らへの危害を可とするものに敗れるのではなく、害為全般を
本是とするものが、そんなものを是としないものに敗れるのである。武威自体は害為
でもあるわけだが、だからといって害為を大肯定するようならば、害為を劣後する
ものに力でも敗れることとなる。微妙ではあるが、これが普遍的な位相上の法則である。
王道を貴ぶものは、覇道を好むものから「女々しい」ものとして揶揄されるような場合がままある。
孔子も諸侯から「優柔不断」との謗りを受けていたと「左伝」にあるし、比較的平和主義的な剣術
である柳生流なども、一刀流や示現流などの好戦的な剣術の嗜好者から冷やかされることがある。
しかし、王道こそは必ず最終的に覇道に勝つのであり、勝って家族や人々を守ることこそは
益荒男としての務めなのだから、本質的には王道のほうがより男らしいといえる一方、
欲望に取り込まれての好戦主義となる覇道のほうがより女々しいものなのだといえる。
覇道が伏せられて王道が復権する世の中こそは、より男らしい世の中である。
欲望まみれ故の迫害まみれや掠奪まみれも駆逐されて、「武士はくわねど高楊枝」がいっぱしの
美徳として通用するようにもなる。そこでこそ活躍するような男こそは真に男らしい男である一方、
そうなった途端に卑しい小人身分と化してしまうような男こそは、まさに女の腐ったようなもん
だといえる。乱世に暴威をふるっていたような覇者こそは、かえってそのような女々しい境遇に
置かれざるを得なくなるわけで、乱世とは、女々しい男を立てる女々しい世の中でこそあったのである。
「百姓睦を以って相い守るは、天下の肥えたるなり。是れを大順と謂う。
〜連らなりて相い及ばず、動きて相い害わざるは、此れ順の至りなり」
「天下万人が親睦によってお互いを守りあおうとするところでこそ、天下もよく肥沃となっている。
これを大順という。一緒にいても利益を侵害し合ったりせず、共に行っても迫害し合ったりしない
ようであってこそ、貞順も完全であるといえる。(天下万人がこのように完全とならなければならぬ)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼運第九より)
本是とするものが、そんなものを是としないものに敗れるのである。武威自体は害為
でもあるわけだが、だからといって害為を大肯定するようならば、害為を劣後する
ものに力でも敗れることとなる。微妙ではあるが、これが普遍的な位相上の法則である。
王道を貴ぶものは、覇道を好むものから「女々しい」ものとして揶揄されるような場合がままある。
孔子も諸侯から「優柔不断」との謗りを受けていたと「左伝」にあるし、比較的平和主義的な剣術
である柳生流なども、一刀流や示現流などの好戦的な剣術の嗜好者から冷やかされることがある。
しかし、王道こそは必ず最終的に覇道に勝つのであり、勝って家族や人々を守ることこそは
益荒男としての務めなのだから、本質的には王道のほうがより男らしいといえる一方、
欲望に取り込まれての好戦主義となる覇道のほうがより女々しいものなのだといえる。
覇道が伏せられて王道が復権する世の中こそは、より男らしい世の中である。
欲望まみれ故の迫害まみれや掠奪まみれも駆逐されて、「武士はくわねど高楊枝」がいっぱしの
美徳として通用するようにもなる。そこでこそ活躍するような男こそは真に男らしい男である一方、
そうなった途端に卑しい小人身分と化してしまうような男こそは、まさに女の腐ったようなもん
だといえる。乱世に暴威をふるっていたような覇者こそは、かえってそのような女々しい境遇に
置かれざるを得なくなるわけで、乱世とは、女々しい男を立てる女々しい世の中でこそあったのである。
「百姓睦を以って相い守るは、天下の肥えたるなり。是れを大順と謂う。
〜連らなりて相い及ばず、動きて相い害わざるは、此れ順の至りなり」
「天下万人が親睦によってお互いを守りあおうとするところでこそ、天下もよく肥沃となっている。
これを大順という。一緒にいても利益を侵害し合ったりせず、共に行っても迫害し合ったりしない
ようであってこそ、貞順も完全であるといえる。(天下万人がこのように完全とならなければならぬ)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼運第九より)
面白いですね。王道を治国までの考え、治国における宗教の象徴
そんな感じに想像しますが覇道よりはるかに上、かもしれないなーなんて感慨深いです。
そんな感じに想像しますが覇道よりはるかに上、かもしれないなーなんて感慨深いです。
近ごろは家事手伝いやらが忙しくて、四書五経以外はろくに読んでないよ。
最低限の情報収集のための蔵書集め(骨董趣味とは違う)やその通読も
大体済んだから、いい加減知識を実践に移すべき時のようにも思う。
しかし、それでも己れの知見に不安を抱き続けるべきなのが儒者である。
「学は及ばざるが如くし、なおこれを失わんことを恐る(泰伯第八・一七)」
という通り、学問にかけての精神的死亡を許してはならないのである。
最低限の情報収集のための蔵書集め(骨董趣味とは違う)やその通読も
大体済んだから、いい加減知識を実践に移すべき時のようにも思う。
しかし、それでも己れの知見に不安を抱き続けるべきなのが儒者である。
「学は及ばざるが如くし、なおこれを失わんことを恐る(泰伯第八・一七)」
という通り、学問にかけての精神的死亡を許してはならないのである。
あらゆる学知の上に「信じる」ということを置く、「信>智」の序列を強制するのが「信仰」である。
単なる信条や信義程度なら「智>信」でもあり得るが、信仰者である以上は必ず「信>智」である。
信じる対象が必ずあらゆる知識の上にあり、どのような知識に即しても、信じる対象のみは無謬とされる。
のみならず、信じる対象の都合によっていくらでも他の知識が捻じ曲げられ、最悪の場合、「1+1=3」
や「鹿は馬である」といったレベルの無理な判断までもが、信仰対象の下で押し通されることになる。
儒学(×儒教)は、それこそを禁止する学問なのである。
「仁義礼智信」の序列の下で、あらゆる頑なな信義信条を学知の目下に置き、「健全な学知の永久的な成長」を
促すのが本来の儒学である。明代以降の中国や朝鮮などにおいては、本来のこのような儒学のあり方が損なわれて
「儒教」と化してしまったものだから、儒者たちの学問的な成長なども滞ってしまったわけだが、日本においては、
江戸期に至るまで純正な儒学のみが嗜まれていたから、それによって養われた学問に対する意欲を洋学にも
転用して、良くも悪しくも西洋文化ペースでの文明発展を早急に推し進めていくことができたのである。
(国民総出の学識水準では、一部のエリートだけが突出している欧米などをも即座に上回ったのだった)
儒学は「智>信」を徹底する学問である一方、洋学は「信教の自由」の名の下に「信>智」を容認する学である。
仏教も聖道門では「智>信」だし、他力本願の浄土門もまた「信>智でしかあり得ない我ら信者は愚か者」という
姿勢を健気に守っているものだから、儒学と仏教は並存することができた。しかし、聖書信仰は「信>智である
ことこそは偉い」とする信教であるし、洋学もまたそのレベルの信教を自由の名の下に容認する学術であるから、
聖書信仰や洋学と儒学が並存することはできず、それらが解禁された明治以降には儒学も実質途絶えたのである。
単なる信条や信義程度なら「智>信」でもあり得るが、信仰者である以上は必ず「信>智」である。
信じる対象が必ずあらゆる知識の上にあり、どのような知識に即しても、信じる対象のみは無謬とされる。
のみならず、信じる対象の都合によっていくらでも他の知識が捻じ曲げられ、最悪の場合、「1+1=3」
や「鹿は馬である」といったレベルの無理な判断までもが、信仰対象の下で押し通されることになる。
儒学(×儒教)は、それこそを禁止する学問なのである。
「仁義礼智信」の序列の下で、あらゆる頑なな信義信条を学知の目下に置き、「健全な学知の永久的な成長」を
促すのが本来の儒学である。明代以降の中国や朝鮮などにおいては、本来のこのような儒学のあり方が損なわれて
「儒教」と化してしまったものだから、儒者たちの学問的な成長なども滞ってしまったわけだが、日本においては、
江戸期に至るまで純正な儒学のみが嗜まれていたから、それによって養われた学問に対する意欲を洋学にも
転用して、良くも悪しくも西洋文化ペースでの文明発展を早急に推し進めていくことができたのである。
(国民総出の学識水準では、一部のエリートだけが突出している欧米などをも即座に上回ったのだった)
儒学は「智>信」を徹底する学問である一方、洋学は「信教の自由」の名の下に「信>智」を容認する学である。
仏教も聖道門では「智>信」だし、他力本願の浄土門もまた「信>智でしかあり得ない我ら信者は愚か者」という
姿勢を健気に守っているものだから、儒学と仏教は並存することができた。しかし、聖書信仰は「信>智である
ことこそは偉い」とする信教であるし、洋学もまたそのレベルの信教を自由の名の下に容認する学術であるから、
聖書信仰や洋学と儒学が並存することはできず、それらが解禁された明治以降には儒学も実質途絶えたのである。
宗教圏としては、仏教圏と儒教圏は被っている場合が多い。しかも日本などでは一貫して非信仰的な儒学で
あり続けて来たわけだから、宗教第一の固定観念に即して「儒教(儒学)などマイナーなものでしかない」などと
決め付けられることがある。そう決め付けてしまうような人間は、まず宗教第一なものの考え方から脱却するので
なければ、決して儒学の真髄を計り知ることはできない。そもそも宗教第一、「信>智こそは偉い」なんていう
ものの考え方から禁止していくのが儒学の本分なのだから、宗教が云々、宗教圏云々といったものの考え方から
卒業していくのでなければ、本物の儒学が眼中に入るところにまで近寄って来てくれることすらないのである。
洋学以上にも、「智>信」の序列を徹底するのが儒学なのだから、「信教的である度合い」でも
諸宗教>洋学>儒学である。儒学こそは、洋学以上にも信仰性を排した純度100%の学問なのであり、
「洋学よりも儒学のほうが信教的だ」などと思い込んだ時点で、すでに儒学は分からなくなるのである。
信仰第一学知第二なものの考え方で、あらゆる知識を身勝手な捻じ曲げの対象とするようなことこそを
儒学は厳禁している一方、洋学は別に全面禁止にしてはいない。科学系統における信仰の否定は顕著だし、
精密に分析的である度合いでも洋学>儒学だったりするが、人文的な思索を講ずる場合に、「信>智」
という程もの無謬強制的な論及を行うことが洋学では相当に許されている。故にこそ、洋学こそは数多の
事実誤認を持ち越したままでいてしまってもいるのであり、科学的、分析的であること以上にも、「智>信」
であることこそは学問にとって最も重要なことであったのだということを裏付ける事例ともなっているのである。
あり続けて来たわけだから、宗教第一の固定観念に即して「儒教(儒学)などマイナーなものでしかない」などと
決め付けられることがある。そう決め付けてしまうような人間は、まず宗教第一なものの考え方から脱却するので
なければ、決して儒学の真髄を計り知ることはできない。そもそも宗教第一、「信>智こそは偉い」なんていう
ものの考え方から禁止していくのが儒学の本分なのだから、宗教が云々、宗教圏云々といったものの考え方から
卒業していくのでなければ、本物の儒学が眼中に入るところにまで近寄って来てくれることすらないのである。
洋学以上にも、「智>信」の序列を徹底するのが儒学なのだから、「信教的である度合い」でも
諸宗教>洋学>儒学である。儒学こそは、洋学以上にも信仰性を排した純度100%の学問なのであり、
「洋学よりも儒学のほうが信教的だ」などと思い込んだ時点で、すでに儒学は分からなくなるのである。
信仰第一学知第二なものの考え方で、あらゆる知識を身勝手な捻じ曲げの対象とするようなことこそを
儒学は厳禁している一方、洋学は別に全面禁止にしてはいない。科学系統における信仰の否定は顕著だし、
精密に分析的である度合いでも洋学>儒学だったりするが、人文的な思索を講ずる場合に、「信>智」
という程もの無謬強制的な論及を行うことが洋学では相当に許されている。故にこそ、洋学こそは数多の
事実誤認を持ち越したままでいてしまってもいるのであり、科学的、分析的であること以上にも、「智>信」
であることこそは学問にとって最も重要なことであったのだということを裏付ける事例ともなっているのである。
「信>智であることこそは偉い」という程にも、信仰絶対主義であるような宗教すらをも容認する「信教の自由」
を世の中から撤廃するのでなければ、儒学の復興も決して覚束ない。仮に信仰主義の根絶が悲痛に思われた所で、
そうである以上は儒学のほうの復興が不能と化してしまうことにも違いはないわけで、むしろそのせいで儒学の
ような健全な学問が途絶させられてしまっていることこそを遺憾に思うべきである。信仰ばかりを保護して、
純正な学知を全くの反故にする、そんな現状に安住してしまっている恥こそを知るべきである。
「学ぶ者に四失有り、教うる者は必ず之れを知れ。人の学ぶや、或いは則ち多きに失い、或いは則ち
寡なきに失い、或いは則ち易きに失い、或いは則ち止どむるに失う。此の四者は、心の莫きに同じなり」
「人がものを学ぶときには凡そ四つの過失に陥りやすい。人にものを教える時にも必ずそうならぬよう注意
せねばならない。人がものを学ぶとき、あるいはただ多くを学んで要点を欠くことになり、あるいは少しの
ことばかりを学んで融通が利かなくなったり、あるいは簡単でありながら重要なことを軽んじてしまったり、
あるいは学ぶことを途絶して成長が止まってしまったりする。これら四つの過失を犯してしまうようならば、
人は何も学ばないのと全く同等の心の成長しか得られない。(信仰もこのような学問にかけての過失を誘発する)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・学記第十八より)
を世の中から撤廃するのでなければ、儒学の復興も決して覚束ない。仮に信仰主義の根絶が悲痛に思われた所で、
そうである以上は儒学のほうの復興が不能と化してしまうことにも違いはないわけで、むしろそのせいで儒学の
ような健全な学問が途絶させられてしまっていることこそを遺憾に思うべきである。信仰ばかりを保護して、
純正な学知を全くの反故にする、そんな現状に安住してしまっている恥こそを知るべきである。
「学ぶ者に四失有り、教うる者は必ず之れを知れ。人の学ぶや、或いは則ち多きに失い、或いは則ち
寡なきに失い、或いは則ち易きに失い、或いは則ち止どむるに失う。此の四者は、心の莫きに同じなり」
「人がものを学ぶときには凡そ四つの過失に陥りやすい。人にものを教える時にも必ずそうならぬよう注意
せねばならない。人がものを学ぶとき、あるいはただ多くを学んで要点を欠くことになり、あるいは少しの
ことばかりを学んで融通が利かなくなったり、あるいは簡単でありながら重要なことを軽んじてしまったり、
あるいは学ぶことを途絶して成長が止まってしまったりする。これら四つの過失を犯してしまうようならば、
人は何も学ばないのと全く同等の心の成長しか得られない。(信仰もこのような学問にかけての過失を誘発する)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・学記第十八より)
 在野の民間人が第一の拠り所とすべきなのは、自領の統治者である。
在野の民間人が第一の拠り所とすべきなのは、自領の統治者である。 統治者もまた自らよりも上位の官職者に臣従し、臣従先としての頂点は天子に極まる。
それが封建制のあり方だけれども、結局のところ、それが健全に実現されてこそ、
人間社会が最高級の治世に与れもする。一方で、君臣官民の主従関係が疎かと化して
しまっているような世の中こそは、程度の差こそあれど乱世となる。それは、世の中が
カルト宗教に乗っ取られた場合であれ、民主主義のような無宗教のイデオロギーによって
「民こそは王」のような思い込みが確信的に流布された場合であれ、同じことである。
人々が自らよりも高位の人間以外の何ものかを副次的な拠り所とすることは、別に禁止さるべきことでもない。
世界史上でも屈指の治世が敷かれた平安時代の日本などにおいても、当時絶大な権限を持ち合わせていた
藤原氏が、平等院や中尊寺の如き他力本願の浄土系の寺院を建立して、敬虔な帰依の対象ともしていた。
もちろん最大の従属対象は天子だったわけだれども、自らの恭敬意識を育むための対象として仏神が
副次的な機能を果たしてくれることもあるわけで、これこそは神仏帰依の純正なあり方だともいえる。
神だ教祖だが、正式な王侯以上の立場に立とうとしたなら、それにより王侯やその他の為政者が
無責任でいる余地を与えることとなってしまう。王権神授説を正統性の根拠としていた西洋の主君こそは、
政商や地主とつるんでの我田引水による富裕三昧でもいた。暴政に対する怨み極まる庶民をごまかす
気休めとして「ノブレス・オブリージュ(高貴なものの義務)」などを掲げたりもしていたものの、
そこで果たされる義務はといえば、戦地での敵兵殺しに直接参加するとかいった程度のもので、
それによりかえって西洋の庶民たちは、王侯や貴族に対する恐怖感を募らせてすらいたのである。
王侯をも上回る程もの信奉対象に神仏がなるべきではない一方で、あらゆる神仏を排して実在の王侯にのみ
服従すべきだというのでもない。共産主義時代のソ連や文化大革命後の中国など、あらゆる神仏帰依を
否定して共産党に対する絶対服従を万民に強いたりしていたわけだけれども、それによる人々の
精神的堕落や公共意識の欠損は甚だしく、赤化が終焉したり形骸化したりしている現代においても、
未だ共産制時代の悪癖(労働者の怠惰や物品の粗末な扱いなど)を克服しきれないままでいる。
世の中における神仏帰依のあり方も「中正」であるべきなのであり、それを実現するためにもやはり、
「鬼神を敬して之れを遠ざく(雍也第六・二二)」などの中庸を保った神仏との接し方を推奨する儒学こそを
一般社会に通用させる必要がある。あくまで儒学であって、「儒教」ではない。儒教が完全な国教とされて
しまっていた時代の中国や朝鮮などにおいては、ライバルとしての仏教や道教を迫害下に置いたりすることが
しばしばあったわけだから、あくまで儒学自体は純粋な学問として、諸宗教との間に一線を引くべきである。
とはいえやはり、儒学を通用させるためにこそ、廃絶されなければならない宗教というものがある。
それこそは他でもない、神仏を実物の権力機構の上にすら置こうとするような信教である。創価のような
異端のカルトでもない限りは、仏教がそんな条件を満たすことはない。道教も隠退主義を是とする
老荘思想を拠り所としているため、基本は権力機構の権威を侵害しない。神道やヒンズー教やイスラム教は
権力機構のためにこそ拵えられた政教一致専門の信教であるため、権力の権威を侵害したりすることは当然ない。
これらの宗教は純粋な学問としての儒学の一般への通用を侵害しない一方、残念ながら、純学としての
儒学の流布すらをも上記のような理由によって妨げる類いの宗教というものもまた、実在している。
服従すべきだというのでもない。共産主義時代のソ連や文化大革命後の中国など、あらゆる神仏帰依を
否定して共産党に対する絶対服従を万民に強いたりしていたわけだけれども、それによる人々の
精神的堕落や公共意識の欠損は甚だしく、赤化が終焉したり形骸化したりしている現代においても、
未だ共産制時代の悪癖(労働者の怠惰や物品の粗末な扱いなど)を克服しきれないままでいる。
世の中における神仏帰依のあり方も「中正」であるべきなのであり、それを実現するためにもやはり、
「鬼神を敬して之れを遠ざく(雍也第六・二二)」などの中庸を保った神仏との接し方を推奨する儒学こそを
一般社会に通用させる必要がある。あくまで儒学であって、「儒教」ではない。儒教が完全な国教とされて
しまっていた時代の中国や朝鮮などにおいては、ライバルとしての仏教や道教を迫害下に置いたりすることが
しばしばあったわけだから、あくまで儒学自体は純粋な学問として、諸宗教との間に一線を引くべきである。
とはいえやはり、儒学を通用させるためにこそ、廃絶されなければならない宗教というものがある。
それこそは他でもない、神仏を実物の権力機構の上にすら置こうとするような信教である。創価のような
異端のカルトでもない限りは、仏教がそんな条件を満たすことはない。道教も隠退主義を是とする
老荘思想を拠り所としているため、基本は権力機構の権威を侵害しない。神道やヒンズー教やイスラム教は
権力機構のためにこそ拵えられた政教一致専門の信教であるため、権力の権威を侵害したりすることは当然ない。
これらの宗教は純粋な学問としての儒学の一般への通用を侵害しない一方、残念ながら、純学としての
儒学の流布すらをも上記のような理由によって妨げる類いの宗教というものもまた、実在している。
「神は権力の上に置かれるか、さもなくば完全に撤廃されるか」といった極論から、まず脱却せねばならない。
それは、どちらもよろしくない選択肢であり、どちらを採ったところでマシな世の中すら実現され得ない代物なのだから。
そのような極論にばかり思考回路が追い詰められてしまっている人間にとっては、
そこからの脱却が死ぬほど恐ろしいことのように思われるかもしれないが、別にそれによって死ぬわけでもない。
むしろ、万民が神仏や王侯への帰依を「最適化」して、より快適な生活を送れるようになるきっかけとなるわけだから、
人としてのより活気ある将来こそを期待して、それに臨むべきなのだといえる。
「君に事うるには、貴かる可く、賤かる可く、富む可く、貧しかる可く、生く可く、殺さる可く、而して乱を為さしむ可からず」
「君侯に仕える以上は、自らが高貴となることも卑賤となることも、富裕となることも貧乏となることも、
生かされることも殺されることも全て受け入れる覚悟であった上で、自分はただ乱を招かないように務めるのみである。
(自分自身が君侯から利益を得たいばかりであるような人間には、始めから君侯に仕える資格すらないのである。)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・表記第三十二より)
それは、どちらもよろしくない選択肢であり、どちらを採ったところでマシな世の中すら実現され得ない代物なのだから。
そのような極論にばかり思考回路が追い詰められてしまっている人間にとっては、
そこからの脱却が死ぬほど恐ろしいことのように思われるかもしれないが、別にそれによって死ぬわけでもない。
むしろ、万民が神仏や王侯への帰依を「最適化」して、より快適な生活を送れるようになるきっかけとなるわけだから、
人としてのより活気ある将来こそを期待して、それに臨むべきなのだといえる。
「君に事うるには、貴かる可く、賤かる可く、富む可く、貧しかる可く、生く可く、殺さる可く、而して乱を為さしむ可からず」
「君侯に仕える以上は、自らが高貴となることも卑賤となることも、富裕となることも貧乏となることも、
生かされることも殺されることも全て受け入れる覚悟であった上で、自分はただ乱を招かないように務めるのみである。
(自分自身が君侯から利益を得たいばかりであるような人間には、始めから君侯に仕える資格すらないのである。)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・表記第三十二より)
思慮深く慎重であることと、ただハラハラドキドキしてるのとでは、当然全くの別物である。
何もかもにひどく一喜一憂させられる、嬉しがり悲しがりなどはかえって慎んで、
それでも恐るべきものを恐れ、楽しむべきものを楽しむものこそは、
薄氷を踏むように何事にも慎重で注意深くあろうとする人間だといえる。
ただのハラハラドキドキでもなければ、全くの無感情なのでもない。
厳重な思慮深さの中にこそ得られる歓喜や悲哀などというものもあるのであり、
厳しい修行の果てに啓いた悟りの歓喜だとか、必死の介護の果てに親が死んだことへの悲しみだとかが
それに当たる。それは、常日ごろからウレシがりカナシがりでばかりいるような人間などには決して
抱けないような、充実した歓喜や悲哀なのであり、(悲哀が充実しているというのは多少語弊があるが)
それ程にも実の伴った悲喜に与ればこそ、人は人としての人生を最大級に全うもするのである。
叙事詩「オデュッセイア」で主人公のオデュッセウスが、慎重な計画の末に一矢を報いたキュプロクスに対し、
逃走しながら感情を爆発させての罵倒の限りを尽くす場面だとか、長旅の末に妻ペネロペのいる自宅へと
戻ってきたら、しょうもない男どもが蝿のようにペネロペにたかっていたことに憤激して男どもを殺し回り、
中には男の性器を切り落とす場面までもがあったりとかいった所から鑑みるに、西洋流の思慮深さや慎重さ
というのは、ただただ感情を押し殺して機械のようにことを企てることばかりを指しているのが窺える。
東洋流の思慮深さ慎重深さというのはそれとは違い、上記のように、慎重で思慮深い中にこそそれなりの
情感を保つことを是とする。それにより、常日ごろから無理なく慎重さや思慮深さを保っていようとし、
オデュッセウスのように作戦や仕事が終わったからといって緊張の糸が切れるようなことも防ぎ続けるのである。
何もかもにひどく一喜一憂させられる、嬉しがり悲しがりなどはかえって慎んで、
それでも恐るべきものを恐れ、楽しむべきものを楽しむものこそは、
薄氷を踏むように何事にも慎重で注意深くあろうとする人間だといえる。
ただのハラハラドキドキでもなければ、全くの無感情なのでもない。
厳重な思慮深さの中にこそ得られる歓喜や悲哀などというものもあるのであり、
厳しい修行の果てに啓いた悟りの歓喜だとか、必死の介護の果てに親が死んだことへの悲しみだとかが
それに当たる。それは、常日ごろからウレシがりカナシがりでばかりいるような人間などには決して
抱けないような、充実した歓喜や悲哀なのであり、(悲哀が充実しているというのは多少語弊があるが)
それ程にも実の伴った悲喜に与ればこそ、人は人としての人生を最大級に全うもするのである。
叙事詩「オデュッセイア」で主人公のオデュッセウスが、慎重な計画の末に一矢を報いたキュプロクスに対し、
逃走しながら感情を爆発させての罵倒の限りを尽くす場面だとか、長旅の末に妻ペネロペのいる自宅へと
戻ってきたら、しょうもない男どもが蝿のようにペネロペにたかっていたことに憤激して男どもを殺し回り、
中には男の性器を切り落とす場面までもがあったりとかいった所から鑑みるに、西洋流の思慮深さや慎重さ
というのは、ただただ感情を押し殺して機械のようにことを企てることばかりを指しているのが窺える。
東洋流の思慮深さ慎重深さというのはそれとは違い、上記のように、慎重で思慮深い中にこそそれなりの
情感を保つことを是とする。それにより、常日ごろから無理なく慎重さや思慮深さを保っていようとし、
オデュッセウスのように作戦や仕事が終わったからといって緊張の糸が切れるようなことも防ぎ続けるのである。
 一時だけまったくの無信仰状態で厳密に分析的な学説を論及したりすることよりも、常日ごろから「智>信」
一時だけまったくの無信仰状態で厳密に分析的な学説を論及したりすることよりも、常日ごろから「智>信」 という序列を保ち続けることのほうがより重要である。それを五常としてわきまえるのが儒学でもあるから、
そんなわきまえのない洋学よりも儒学のほうがより純学問的だとは>>168-170でもすでに述べたことである。
それと全く同じで、一時だけ完全な無感情で徹底的に思慮深く慎重であったりするよりも、多少は感情を
差し挟む余地があってもいいから、常日ごろから一定以上の思慮深さ慎重さを保つようにしたほうがよい。
それでこそ、人は最大級の「総合的な思慮深さや慎重さ」を獲得することができるものでもあるからだ。
総合的に思慮深さ慎重さが多大であるということは、人が一生の内に嗜む思慮深さや慎重さが、
質でも量でもより多大であるということである。多少の感情も差し挟みながら、常日ごろからの
慎重さを保つことこそは、一時だけ完全な無感情状態での慎重さを極めたりすることよりも、
総合的な思慮深さや慎重さで上回る。上回るからこそ、安全保障の錬度や確度でも前者が後者を
上回るのであり、女子供や庶民までもが恒常的な拠り所とするに足るものともなるのである。
女子供や庶民のような弱者が、自分たちから最大級の思慮深さや慎重さの持ち主を頼りにしたがるとも限らない。
そんな人間は畏れ多くて近づくこともできず、むしろオデュッセウスみたいな危なっかしい側面の持ち主
にこそ親しみを抱いて近づきたがるかも知れない。だとすれば、女子供や小人たちもまた、自分たちより
優等な相手を嫉むルサンチマンに駆られたりしているに違いないわけで、それを払拭して、真に頼りとするに
値するからこそ、自分たちよりも優等であるような相手に対する崇敬を育んでいく所から始めなければならない。
ハラハラドキドキは女子供や小人の常である。
全くの無感情も、女子供や小人が嫉みまでをも抱くような対象ではない。
最大級の思慮深さと共に大人びた情緒までをも湛えていられることこそは、
それが確かに優れていると察せる一方で、自分たちには決して到達できない
境地でもあるものだから、女子供や小人にとっての嫉妬の対象ともなる。
嫉妬は羨望の裏返しでこそあるのだから、素直に羨望させればいいのである。
「所謂身を修むるは其の心を正すに在りとは、身に忿懥する所有れば、則ち其の正を得ず、恐懼する所有れば、
則ち其の正を得ず、好楽する所有れば、則ち其の正を得ず、憂患する所有れば、則ち其の正を得ざればなり」
「身を修めるためにはまず心から正さねばならない。もしやたらと怒りに駆られたり、恐れおののいたり、
好み楽しんだり、憂患したりするようであれば、それは心が正されていないからだ。(中庸・一には
『君子は見えぬ所にまで戒め慎み、聞こえぬ所にまで恐懼する』とあるが、これは上記のような、
無闇やたらなハラハラドキドキを払拭した上での慎重さを期すことこそを促しているのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——大学・七より)
全くの無感情も、女子供や小人が嫉みまでをも抱くような対象ではない。
最大級の思慮深さと共に大人びた情緒までをも湛えていられることこそは、
それが確かに優れていると察せる一方で、自分たちには決して到達できない
境地でもあるものだから、女子供や小人にとっての嫉妬の対象ともなる。
嫉妬は羨望の裏返しでこそあるのだから、素直に羨望させればいいのである。
「所謂身を修むるは其の心を正すに在りとは、身に忿懥する所有れば、則ち其の正を得ず、恐懼する所有れば、
則ち其の正を得ず、好楽する所有れば、則ち其の正を得ず、憂患する所有れば、則ち其の正を得ざればなり」
「身を修めるためにはまず心から正さねばならない。もしやたらと怒りに駆られたり、恐れおののいたり、
好み楽しんだり、憂患したりするようであれば、それは心が正されていないからだ。(中庸・一には
『君子は見えぬ所にまで戒め慎み、聞こえぬ所にまで恐懼する』とあるが、これは上記のような、
無闇やたらなハラハラドキドキを払拭した上での慎重さを期すことこそを促しているのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——大学・七より)
政財の癒着を徹底して分断するなどの清廉を尽くした道徳統治の持続などは、
完全な踏襲主義、世襲主義であるのが好ましく、仮に目付のような能力主義の陪臣家を
助役として別に置くとしても、あくまで下位のものとしての領分を守らせるべきである。
そうであるべきなのは、「新しいことをやりたがるような欲求」を為政に差し挟んだり
することがかえって害にばかりなるからで、無為自然の心持ちによって世の中を平穏に
司っていくためにも、むしろ世襲で仕方なく士業を引き継いで行くぐらいのほうがいいのである。
(>>160の左伝からの引用なども参照)
「天下国家を治めるが如き大業は、予め万端の準備を整えてから成せ」とは「中庸」二〇にも
大略としてある。世襲や良き前例の踏襲といった温故はもちろんのこと、事業を為すにかけての、
よく踏み止まっての準備なども、大業に欠かせられはしない。ほとんどそれらばかりを主として、
事業を推進していくことなどは完全な成り行きに任せるぐらいのつもりでいたほうがよい。
天下国家を司るような大業であればあるほど、過去に遡ることや、
じっと踏み止まって万端の準備を敷くことが必須となる。大業でないのならそんな
必要もなかったりするのは、あたかも小児の戯れが何もかも行き当たりばったりで
あるのと同時に、規模的には大したことでもないようなものだといえる。
過去の踏襲も、現在の注意も全く疎かにしての、ただ先へ先への行き当たりばったりで
全社会規模の大事業などを企てたりした場合にこそ、人も致命的な破滅から免れられなくなる。
小児や動物にそんな能力はないが、大人の男などには大事業を成す能力がある。にもかかわらず、
そうであるなりの温故や注意を欠いた場合にこそ、自業自得の破滅を呼び込んでしまうのである。
完全な踏襲主義、世襲主義であるのが好ましく、仮に目付のような能力主義の陪臣家を
助役として別に置くとしても、あくまで下位のものとしての領分を守らせるべきである。
そうであるべきなのは、「新しいことをやりたがるような欲求」を為政に差し挟んだり
することがかえって害にばかりなるからで、無為自然の心持ちによって世の中を平穏に
司っていくためにも、むしろ世襲で仕方なく士業を引き継いで行くぐらいのほうがいいのである。
(>>160の左伝からの引用なども参照)
「天下国家を治めるが如き大業は、予め万端の準備を整えてから成せ」とは「中庸」二〇にも
大略としてある。世襲や良き前例の踏襲といった温故はもちろんのこと、事業を為すにかけての、
よく踏み止まっての準備なども、大業に欠かせられはしない。ほとんどそれらばかりを主として、
事業を推進していくことなどは完全な成り行きに任せるぐらいのつもりでいたほうがよい。
天下国家を司るような大業であればあるほど、過去に遡ることや、
じっと踏み止まって万端の準備を敷くことが必須となる。大業でないのならそんな
必要もなかったりするのは、あたかも小児の戯れが何もかも行き当たりばったりで
あるのと同時に、規模的には大したことでもないようなものだといえる。
過去の踏襲も、現在の注意も全く疎かにしての、ただ先へ先への行き当たりばったりで
全社会規模の大事業などを企てたりした場合にこそ、人も致命的な破滅から免れられなくなる。
小児や動物にそんな能力はないが、大人の男などには大事業を成す能力がある。にもかかわらず、
そうであるなりの温故や注意を欠いた場合にこそ、自業自得の破滅を呼び込んでしまうのである。
小児や動物はもちろんのこと、大人の女にだって、自力で大事業を成す能力などはない。
だからこそというべきか、歴史を体系的に学びたがる女というのも少ない。歴史上の大人物の
ほとんどは男であり、女は出てきても悪女だったりするから、それがつまらなくもあるのだろうが、
だからといって、歴史的な大事業を成す能力のある大人の男にまで歴史忌避を強要するのもおかしい。
歴史感覚の豊かな男こそは、歴史的大事業をも磐石に成すことができる。故にこそ、本当に
女子供を養っていくにも値する。一方で、歴史感覚も注意力もない行き当たりばったりの男こそは、
ヘタに大事業に手を付けて自業自得の大破滅を招いたりするのだから、これこそは女子供を
守るにも値しない匹夫であると見なす他はない。してみればこそ、自分自身が歴史などに全く
興味のない女といえども、男に対しては、歴史に対する豊富な見解や、ことにあたっての慎重さ
などを期待すべきなのであり、そうでないような軽薄な男こそを「自分ともさして変わらない
品性の下劣さの持ち主」として親しんだりするようなことがないようにしなければならない。
それでこそ、女なりの婦徳を持った賢婦であるということまでもが言えるだろう。
そんな女は、今みたいな仁徳皆無の世の中には、共に皆無でもいるわけだが。
「君子は徳性を尊んで問学を道とし、広大を致して精微を尽くし、
高明を極めて中庸を道とし、故きを温めて新しきを知り、厚きを敦くして以って礼を崇ぶ」
「君子は徳性を尊びつつあらゆる事物に問い学ぶことを常道とし、その知見は広大さと精微さを尽くし、
高明さを極めてなおのこと中庸を常とし、古えを尋ねて新しきを知り、より重んずるべきものを
重んずることを通じて礼への崇敬を育む。(去来今にかけて広大精微な問学を志せばこそ、
儒者はその当然なる一環として、温故知新をも嗜むのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・二七より)
だからこそというべきか、歴史を体系的に学びたがる女というのも少ない。歴史上の大人物の
ほとんどは男であり、女は出てきても悪女だったりするから、それがつまらなくもあるのだろうが、
だからといって、歴史的な大事業を成す能力のある大人の男にまで歴史忌避を強要するのもおかしい。
歴史感覚の豊かな男こそは、歴史的大事業をも磐石に成すことができる。故にこそ、本当に
女子供を養っていくにも値する。一方で、歴史感覚も注意力もない行き当たりばったりの男こそは、
ヘタに大事業に手を付けて自業自得の大破滅を招いたりするのだから、これこそは女子供を
守るにも値しない匹夫であると見なす他はない。してみればこそ、自分自身が歴史などに全く
興味のない女といえども、男に対しては、歴史に対する豊富な見解や、ことにあたっての慎重さ
などを期待すべきなのであり、そうでないような軽薄な男こそを「自分ともさして変わらない
品性の下劣さの持ち主」として親しんだりするようなことがないようにしなければならない。
それでこそ、女なりの婦徳を持った賢婦であるということまでもが言えるだろう。
そんな女は、今みたいな仁徳皆無の世の中には、共に皆無でもいるわけだが。
「君子は徳性を尊んで問学を道とし、広大を致して精微を尽くし、
高明を極めて中庸を道とし、故きを温めて新しきを知り、厚きを敦くして以って礼を崇ぶ」
「君子は徳性を尊びつつあらゆる事物に問い学ぶことを常道とし、その知見は広大さと精微さを尽くし、
高明さを極めてなおのこと中庸を常とし、古えを尋ねて新しきを知り、より重んずるべきものを
重んずることを通じて礼への崇敬を育む。(去来今にかけて広大精微な問学を志せばこそ、
儒者はその当然なる一環として、温故知新をも嗜むのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・二七より)
磔刑への極度の恐怖による心神喪失状態だとか、
あるいは麻薬の服用や性交による朦朧状態だとかが真理に通ずるというのなら、
「真理は知能を極度に低下させたところにこそある」ということになる。
1+1が3にも4にもなり、馬も鹿になるようなところにこそ真理があることになる。
確かに「そうでもあり得る」というほうが、誤謬数理や矛盾許容論理までをも包含することになるから、
「真理は全て」という観点からいえば、真理を肯定し尽くすことに真摯であるということにすらなる。
それは万物斉同を唱える荘子なども是としていることであり、だからこそ荘子本人の著作であることが
ほぼ確かな「荘子」内篇の斉物論第二において、荘子も「動物の毛ほど大きいものはなく、泰山ほど小さいものはなく、
幼くして死んだ子供ほど長生きしたものはなく、八百歳生きたという彭祖ほど短命だったものもない」というような、
全く人間らしい正常な尺度を度外視した物言いにもあえて及んだのだった。
そういったバカアホ級の何でもありと、儒家で解くような善悪の分別との両方を理解できてこその、真理把捉者である。
老荘列などの道家は、儒家に対する否定的な見解も述べてはいたけれども、それでも、儒家の言わんとすることに対する
理解ぐらいはあったようである。特に、列子の物言いにその傾向が顕著だし、老荘も儒家の教条を理解した上であえてそこに
天邪鬼を唱えているからこそ、儒家への理解をほぼ完全に喪失している現代人にとってその論及が難解だったりするのである。
儒家が重んずる善悪の分別と、老荘が重んずる、誤謬や矛盾を含む万物の肯定の両者を止揚しているのが、大乗仏教である。
「あるもない、ないもない」といった般若の空の論理によって、厳密に論理的に万事万物を全否定することで等価なものとする。
そこから万事万物に対する無意識からの肯定意識を養っていく離れ業をやってのけているものだから、わざわざ意識的に肯定
するまでもないほどの好感(可愛楽)を常に湛えながら、善悪の分別に即した現実の俗世での処断すらもが自在となる。
あるいは麻薬の服用や性交による朦朧状態だとかが真理に通ずるというのなら、
「真理は知能を極度に低下させたところにこそある」ということになる。
1+1が3にも4にもなり、馬も鹿になるようなところにこそ真理があることになる。
確かに「そうでもあり得る」というほうが、誤謬数理や矛盾許容論理までをも包含することになるから、
「真理は全て」という観点からいえば、真理を肯定し尽くすことに真摯であるということにすらなる。
それは万物斉同を唱える荘子なども是としていることであり、だからこそ荘子本人の著作であることが
ほぼ確かな「荘子」内篇の斉物論第二において、荘子も「動物の毛ほど大きいものはなく、泰山ほど小さいものはなく、
幼くして死んだ子供ほど長生きしたものはなく、八百歳生きたという彭祖ほど短命だったものもない」というような、
全く人間らしい正常な尺度を度外視した物言いにもあえて及んだのだった。
そういったバカアホ級の何でもありと、儒家で解くような善悪の分別との両方を理解できてこその、真理把捉者である。
老荘列などの道家は、儒家に対する否定的な見解も述べてはいたけれども、それでも、儒家の言わんとすることに対する
理解ぐらいはあったようである。特に、列子の物言いにその傾向が顕著だし、老荘も儒家の教条を理解した上であえてそこに
天邪鬼を唱えているからこそ、儒家への理解をほぼ完全に喪失している現代人にとってその論及が難解だったりするのである。
儒家が重んずる善悪の分別と、老荘が重んずる、誤謬や矛盾を含む万物の肯定の両者を止揚しているのが、大乗仏教である。
「あるもない、ないもない」といった般若の空の論理によって、厳密に論理的に万事万物を全否定することで等価なものとする。
そこから万事万物に対する無意識からの肯定意識を養っていく離れ業をやってのけているものだから、わざわざ意識的に肯定
するまでもないほどの好感(可愛楽)を常に湛えながら、善悪の分別に即した現実の俗世での処断すらもが自在となる。
善悪の分別を万物の肯定とまた別に理解する必要があることは、これまた大乗仏教の唯識思想で確証されている。
人間にとっての善悪の分別にもそれなりの真理性があって、全くの蔑ろにするのでは最悪の苦痛や完全なる破滅までもが
免れられなくなるから、人間にとっての厄除けの処方としての普遍的な善悪の分別ぐらいは嗜むべきだとするのである。
1+1=3も鹿の馬呼ばわりも、何でもありの万事万物の肯定だけがあって、善悪の分別のほうは
全く疎かにしているというのなら、むしろ万物の肯定などしないでいる場合以上にも下劣なこととなる。
1+1=2、馬は馬、鹿は鹿、この程度の分別は小学生でもできることである。にもかかわらず、それに違う誤謬や
矛盾ばかりを是とするようなら、もはや小学生以下、多少頭のいい幼稚園児以下の品性にまで自らが下落したことともなる。
そうならないためには、まともな分別はまともな分別でよく貴んでいく必要があるわけで、1+1を2だけでなく3や4にも
してしまってそれでよしとするような人間にこそ、それは必須なことである。にもかかわらず、ただただ誤謬や矛盾を許容
しまくって、分別など全くの疎かにしたりするものだから、小学生以下の下品下生さしか残らないこととなるのである。
真理を知った人間こそは愚か者だろうか、そんなはずはない。真理こそは本来、人を人並み以上に成長させるものである。
それは、万事万物への理解とそれに対する分別という、全ての手管を尽くせばこそ達成されることであり、それこそは
本人自身が真理に適った姿ともなっている(だからこそ真理学である仏教にも断悪修善の教義が伴っているのである)。
誤謬や矛盾を含む万事万物を愛でようとしながら、分別だけは疎かにする、それは自分自身が全ての手管を尽くして
いないが故に真理にも悖っているのであり、故に上記のような原理で以って、人並み以下や小学生以下の品性にまで
没落させてしまうことともなる。真理への近づき方が真理に適っていないからこそ、真理などに近づかないでいる
場合以上にも下劣な自分自身と化してしまう。それは真理が悪いからではなく、自分が悪いからである。
人間にとっての善悪の分別にもそれなりの真理性があって、全くの蔑ろにするのでは最悪の苦痛や完全なる破滅までもが
免れられなくなるから、人間にとっての厄除けの処方としての普遍的な善悪の分別ぐらいは嗜むべきだとするのである。
1+1=3も鹿の馬呼ばわりも、何でもありの万事万物の肯定だけがあって、善悪の分別のほうは
全く疎かにしているというのなら、むしろ万物の肯定などしないでいる場合以上にも下劣なこととなる。
1+1=2、馬は馬、鹿は鹿、この程度の分別は小学生でもできることである。にもかかわらず、それに違う誤謬や
矛盾ばかりを是とするようなら、もはや小学生以下、多少頭のいい幼稚園児以下の品性にまで自らが下落したことともなる。
そうならないためには、まともな分別はまともな分別でよく貴んでいく必要があるわけで、1+1を2だけでなく3や4にも
してしまってそれでよしとするような人間にこそ、それは必須なことである。にもかかわらず、ただただ誤謬や矛盾を許容
しまくって、分別など全くの疎かにしたりするものだから、小学生以下の下品下生さしか残らないこととなるのである。
真理を知った人間こそは愚か者だろうか、そんなはずはない。真理こそは本来、人を人並み以上に成長させるものである。
それは、万事万物への理解とそれに対する分別という、全ての手管を尽くせばこそ達成されることであり、それこそは
本人自身が真理に適った姿ともなっている(だからこそ真理学である仏教にも断悪修善の教義が伴っているのである)。
誤謬や矛盾を含む万事万物を愛でようとしながら、分別だけは疎かにする、それは自分自身が全ての手管を尽くして
いないが故に真理にも悖っているのであり、故に上記のような原理で以って、人並み以下や小学生以下の品性にまで
没落させてしまうことともなる。真理への近づき方が真理に適っていないからこそ、真理などに近づかないでいる
場合以上にも下劣な自分自身と化してしまう。それは真理が悪いからではなく、自分が悪いからである。
「人亦た言える有り、柔ければ則ち之れを茹い、剛ければ則ち之れを吐くと。
維れ仲山甫のみは、柔きをも亦ち茹わず、剛きをも亦た吐かず、矜寡を侮らず、疆禦をも畏れず。
人亦た言える有り、徳の輶きこと毛の如くなるも、民に克く之れを挙ぐるものは鮮なしと。
我れ之れを儀図するに、維れ仲山甫のみ之れを挙ぐ、しむらくは之れを助くるもの莫し」
「ある人がこう言った。『柔らかい食い物は好んで食らい、硬い食い物は吐き捨てる。(意志薄弱なものの譬え)』
近ごろでは(周の卿士の)仲山甫ばかりがこれに違い、柔らかいからといって食わず、硬いからといって吐き捨てず、
鰥寡孤独の者をだからといって侮ったりもせず、荒くれ者をもだからといって畏怖したりもしないでいる。
またある人がこう言った。『徳を実践する軽さは毛ほどのものであるのに、民のうちでこれを挙げられるものもいない』
自分の推し量るに、やはり仲山甫のみがこれを挙げられているという他はなく、彼を助けられる者すら見当たりはしない。
(毛を挙げるほどにも簡単な徳の実践を人々が率先して為すことはおろか、人が為すのを助けようとすらしないのも、
柔らかいものだけを食べて硬いものは吐き捨てようとするような薄弱さによる。そのような薄弱さの持ち主こそは、
自らの多重人格の別人格を『神』に見立てるような、常人には到底受け入れがたい内面的所業にも及ぶのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・蕩之什・烝民より)
維れ仲山甫のみは、柔きをも亦ち茹わず、剛きをも亦た吐かず、矜寡を侮らず、疆禦をも畏れず。
人亦た言える有り、徳の輶きこと毛の如くなるも、民に克く之れを挙ぐるものは鮮なしと。
我れ之れを儀図するに、維れ仲山甫のみ之れを挙ぐ、しむらくは之れを助くるもの莫し」
「ある人がこう言った。『柔らかい食い物は好んで食らい、硬い食い物は吐き捨てる。(意志薄弱なものの譬え)』
近ごろでは(周の卿士の)仲山甫ばかりがこれに違い、柔らかいからといって食わず、硬いからといって吐き捨てず、
鰥寡孤独の者をだからといって侮ったりもせず、荒くれ者をもだからといって畏怖したりもしないでいる。
またある人がこう言った。『徳を実践する軽さは毛ほどのものであるのに、民のうちでこれを挙げられるものもいない』
自分の推し量るに、やはり仲山甫のみがこれを挙げられているという他はなく、彼を助けられる者すら見当たりはしない。
(毛を挙げるほどにも簡単な徳の実践を人々が率先して為すことはおろか、人が為すのを助けようとすらしないのも、
柔らかいものだけを食べて硬いものは吐き捨てようとするような薄弱さによる。そのような薄弱さの持ち主こそは、
自らの多重人格の別人格を『神』に見立てるような、常人には到底受け入れがたい内面的所業にも及ぶのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・蕩之什・烝民より)
元日早々から犯罪聖書の駄文を読まされるのも目障りなんで、まずは真正聖書の
「論語」の頁を無作為に開いてみた。そのとき真っ先に目に飛び込んできたのが以下の言葉。
「戦戦兢兢として、深淵に臨むが如く、薄氷を履むが如し」
(泰伯第八・三)
曾子が「詩経」小旻から引用した言葉で、このとき曾子は重篤だったため遺言も兼ねていた。今までは
戦々恐々として、薄氷を踏むように慎重な人生を送ってきたけれども、いま死の床について、やっと自分も
その緊張から解放されると、曾子は自らの五体満足な身体の手先などを見せながら弟子に言ったのだった。
深淵に臨むが如く、薄氷を踏むが如しとはいっても、実際に儒者が深山に立ち入ったり、薄氷を踏んだり
することを好き好んで行うわけではない。むしろそのような危うい行いに及ぶことから避けていく、
その回避にかけての慎重さからして、深淵に望むが如く、薄氷を踏むが如しでいようとするのである。
だから結局、儒者の行いはどこまでも常道の踏襲でいるわけで、平和の上にも平和を尽くす保守系なわけだけども、
それでいて心内はやはりいつも「戦戦兢兢」としている。平和だからといって平和に安んじきるのではなく、
いつ問題を来たさぬか、争いを招かぬかと、内憂外患の警戒を尽くし続けるのである。
儒者が必ず君子階級であるとは限らないが、これはまさに君子階級こそがそうあるべき姿勢だといえる。
匹夫小人なら世の中の情勢如何にかかわらず、ただ自分自身が安穏としていたいばかりでいたりするわけだが、
世の中の平穏の責任をも司る君子士人であるならば、逆に世の情勢の如何に関わらず、
常日ごろから戦戦兢兢とした警戒を続けていかなければならない。
「論語」の頁を無作為に開いてみた。そのとき真っ先に目に飛び込んできたのが以下の言葉。
「戦戦兢兢として、深淵に臨むが如く、薄氷を履むが如し」
(泰伯第八・三)
曾子が「詩経」小旻から引用した言葉で、このとき曾子は重篤だったため遺言も兼ねていた。今までは
戦々恐々として、薄氷を踏むように慎重な人生を送ってきたけれども、いま死の床について、やっと自分も
その緊張から解放されると、曾子は自らの五体満足な身体の手先などを見せながら弟子に言ったのだった。
深淵に臨むが如く、薄氷を踏むが如しとはいっても、実際に儒者が深山に立ち入ったり、薄氷を踏んだり
することを好き好んで行うわけではない。むしろそのような危うい行いに及ぶことから避けていく、
その回避にかけての慎重さからして、深淵に望むが如く、薄氷を踏むが如しでいようとするのである。
だから結局、儒者の行いはどこまでも常道の踏襲でいるわけで、平和の上にも平和を尽くす保守系なわけだけども、
それでいて心内はやはりいつも「戦戦兢兢」としている。平和だからといって平和に安んじきるのではなく、
いつ問題を来たさぬか、争いを招かぬかと、内憂外患の警戒を尽くし続けるのである。
儒者が必ず君子階級であるとは限らないが、これはまさに君子階級こそがそうあるべき姿勢だといえる。
匹夫小人なら世の中の情勢如何にかかわらず、ただ自分自身が安穏としていたいばかりでいたりするわけだが、
世の中の平穏の責任をも司る君子士人であるならば、逆に世の情勢の如何に関わらず、
常日ごろから戦戦兢兢とした警戒を続けていかなければならない。
基本そうであらねばならないのは君子だが、江戸初期の日本のように、巷で兵法書の購読が流行るほどにも、
人々がみな憂患を尽くすようになったなら、それもまた好ましいことである。戦国時代のような乱世だから
誰しもが孫呉に飛びついたりするのではなく、平和の獲得された治世においても、誰しもがよく警戒的でいる。
それがいわゆる、江戸っ子のいう「粋」の原形ともなったわけで、ただただ平民を家畜のようにのんべんだらり
とさせていたがために、人々の怠慢さを助長してしまった中国や今の欧米などとは一線を画す点なのである。
むろん、中国や欧米のような大規模な大陸社会では、世相の乱脈を防いで人々を安穏ならしめるだけでも精一杯
というところがありもするわけで、小人にまで君子並みの機敏さを持たせようなんてことからして夢のまた夢
のような話であるのかもしれない。日本人の機敏さは、魚食忠心の食生活などからもきているわけで、大陸の人間
誰しもが日本人みたいな食生活を目指したなら、海洋の食資源があっという間に枯渇するなどの限界点もまたある。
少なくとも、平和が獲得されたからといって誰しもがのんべんだらりとしててよくなるなん考え方だけは、
島国といわず大陸国といわず排さねばならない。どんな世の中でも君子は最大級の警戒を欠かさず、小人もまた
怠慢でいるよりは警戒的であったほうがよい。世の中全般、天下万民がなるべくそうあるべき指針としては、
「戦戦兢兢として、深淵に臨むが如く、薄氷を履むが如し」が理想であり、そうであることを忌むようなことが
ないようにせねばならない。あくまで指針上の話であって、どこまで達成されるかということには個体差がある。
人々がみな憂患を尽くすようになったなら、それもまた好ましいことである。戦国時代のような乱世だから
誰しもが孫呉に飛びついたりするのではなく、平和の獲得された治世においても、誰しもがよく警戒的でいる。
それがいわゆる、江戸っ子のいう「粋」の原形ともなったわけで、ただただ平民を家畜のようにのんべんだらり
とさせていたがために、人々の怠慢さを助長してしまった中国や今の欧米などとは一線を画す点なのである。
むろん、中国や欧米のような大規模な大陸社会では、世相の乱脈を防いで人々を安穏ならしめるだけでも精一杯
というところがありもするわけで、小人にまで君子並みの機敏さを持たせようなんてことからして夢のまた夢
のような話であるのかもしれない。日本人の機敏さは、魚食忠心の食生活などからもきているわけで、大陸の人間
誰しもが日本人みたいな食生活を目指したなら、海洋の食資源があっという間に枯渇するなどの限界点もまたある。
少なくとも、平和が獲得されたからといって誰しもがのんべんだらりとしててよくなるなん考え方だけは、
島国といわず大陸国といわず排さねばならない。どんな世の中でも君子は最大級の警戒を欠かさず、小人もまた
怠慢でいるよりは警戒的であったほうがよい。世の中全般、天下万民がなるべくそうあるべき指針としては、
「戦戦兢兢として、深淵に臨むが如く、薄氷を履むが如し」が理想であり、そうであることを忌むようなことが
ないようにせねばならない。あくまで指針上の話であって、どこまで達成されるかということには個体差がある。
削除(by投稿者)
「惰農自らを安んじ、作労を昏めず、田畝に服さず、越に其れ黍稷有ること罔し。
汝じ吉言にて百姓を和せざるは、惟れ汝じ自ら毒を生すなり。乃ち敗禍姦宄、
以て自ら厥の身に災す。乃ち既に悪を民に先んじ、乃ち其の恫みを奉ず。汝じ悔いるも
身に何ぞ及ばん。時の憸民を相るに、猶お箴言を胥い顧み、其れ逸口を発して有らん」
「怠惰な農夫が自らの安楽ばかりを求めて農作に努めず、田畝に赴こうともしないために、
作物も実らない。(そうなってしまうほどにも、民を化育する立場にあるおまえたちが)よい言葉によって
百姓を平和に導いてやりもしないでいるのは、おまえたち自身が害毒を為しているも同然のことだ。
(百姓が平和となるためには、せっせと田畑を耕して穀物を実らせる必要があるのである。
『礼記』楽記第十九や『左伝』昭公元年など、『平和』という言葉は、五穀豊穣を神に感謝する
ための雅楽が人々を相い和ませることこそを指して、最原初の頃には用いられてもいたのである)
その腐敗的な所業こそは、おまえたちに免れようのない禍いをもたらすだろう。民に先んじて悪を行い、
それにより禍いを被ってしまってから悔いたところで、それで助かるようなこともありはしない。
(化育者としての怠惰はありのままに、民に先んずる悪行と見なして差し支えないのである)
今の民たちですら、自分たちで自主的に警戒を促す言葉(それを昔は箴言といった)を
重んじて、失言を為さないように努めてすらいるのに。(犯罪聖書の箴言は失言の間違いだろう)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・盤庚上より)
汝じ吉言にて百姓を和せざるは、惟れ汝じ自ら毒を生すなり。乃ち敗禍姦宄、
以て自ら厥の身に災す。乃ち既に悪を民に先んじ、乃ち其の恫みを奉ず。汝じ悔いるも
身に何ぞ及ばん。時の憸民を相るに、猶お箴言を胥い顧み、其れ逸口を発して有らん」
「怠惰な農夫が自らの安楽ばかりを求めて農作に努めず、田畝に赴こうともしないために、
作物も実らない。(そうなってしまうほどにも、民を化育する立場にあるおまえたちが)よい言葉によって
百姓を平和に導いてやりもしないでいるのは、おまえたち自身が害毒を為しているも同然のことだ。
(百姓が平和となるためには、せっせと田畑を耕して穀物を実らせる必要があるのである。
『礼記』楽記第十九や『左伝』昭公元年など、『平和』という言葉は、五穀豊穣を神に感謝する
ための雅楽が人々を相い和ませることこそを指して、最原初の頃には用いられてもいたのである)
その腐敗的な所業こそは、おまえたちに免れようのない禍いをもたらすだろう。民に先んじて悪を行い、
それにより禍いを被ってしまってから悔いたところで、それで助かるようなこともありはしない。
(化育者としての怠惰はありのままに、民に先んずる悪行と見なして差し支えないのである)
今の民たちですら、自分たちで自主的に警戒を促す言葉(それを昔は箴言といった)を
重んじて、失言を為さないように努めてすらいるのに。(犯罪聖書の箴言は失言の間違いだろう)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・盤庚上より)
実際、この世界には、「神の意思」かと見紛われるほどにも作為的な極大現象というものがある。
とはいえ、それは別に特定の超越神の作為によるものだったりするのではなく、人間という
生物種族が本能的な集団意思を集約させることによって自然と捻出するものなのである。
およそ世界史上において、貧農から天下取りにまでのし上がるほどもの成功を果たした人物としては、
漢の高祖劉邦、明の太祖朱元璋、そして日本の豊臣秀吉などが挙げられる。ただ、このうちで
世襲の王朝継続までは実現できなかったのが豊臣秀吉であり、王朝を持続させられはしたものの
官僚腐敗などの致命的な問題を来たしたのが朱元璋であり、そのような問題を来たすことなく、
中国史上でも屈指の良王朝を築き上げられたのが劉邦だったという程度の違いがある。
豊臣秀吉が世襲の家門相続すら覚束なかったのは、何もかもを自分一人の意思ばかりに頼りすぎて、
王朝や幕府を形成して行けるだけのまとまった勢力確保を存続することができなかったからである。
朱元璋の興した明が深刻な腐敗を来たしたのも、やはり太祖たる本人からして孟子嫌い
だったりしながら、無理やり朱子学を国学に据えるなどのイビツな歴史的経緯があったからで、
形骸化した儒学の需要が政財界の癒着からなる経済的腐敗をも黙認してしまったからだった。
漢の高祖劉邦が興した漢王朝こそが、模範的な長期の治世をも実現することができたのは、
前二人と違い、劉邦が自らの意思ではなく寛容さこそを主体として天下取りにまで躍り出たからだった。
秀吉のように自らが戦略を練り込むのでもなく、主要な戦略はほとんど張良や韓信に任せきり、
項羽追討によって天下取りとしての立場が固まる瞬間まで、劉邦は虚心を第一として続けたのだった。
漢帝国の皇帝に即位して後も、為政にかけて我を張り通すようなことは極力避け、当初は儒者嫌いだった
にもかかわらず、陸賈の説得や、叔孫通の気の利いた礼楽の再興などを受けて全面的に儒学統治を取り入れもした。
とはいえ、それは別に特定の超越神の作為によるものだったりするのではなく、人間という
生物種族が本能的な集団意思を集約させることによって自然と捻出するものなのである。
およそ世界史上において、貧農から天下取りにまでのし上がるほどもの成功を果たした人物としては、
漢の高祖劉邦、明の太祖朱元璋、そして日本の豊臣秀吉などが挙げられる。ただ、このうちで
世襲の王朝継続までは実現できなかったのが豊臣秀吉であり、王朝を持続させられはしたものの
官僚腐敗などの致命的な問題を来たしたのが朱元璋であり、そのような問題を来たすことなく、
中国史上でも屈指の良王朝を築き上げられたのが劉邦だったという程度の違いがある。
豊臣秀吉が世襲の家門相続すら覚束なかったのは、何もかもを自分一人の意思ばかりに頼りすぎて、
王朝や幕府を形成して行けるだけのまとまった勢力確保を存続することができなかったからである。
朱元璋の興した明が深刻な腐敗を来たしたのも、やはり太祖たる本人からして孟子嫌い
だったりしながら、無理やり朱子学を国学に据えるなどのイビツな歴史的経緯があったからで、
形骸化した儒学の需要が政財界の癒着からなる経済的腐敗をも黙認してしまったからだった。
漢の高祖劉邦が興した漢王朝こそが、模範的な長期の治世をも実現することができたのは、
前二人と違い、劉邦が自らの意思ではなく寛容さこそを主体として天下取りにまで躍り出たからだった。
秀吉のように自らが戦略を練り込むのでもなく、主要な戦略はほとんど張良や韓信に任せきり、
項羽追討によって天下取りとしての立場が固まる瞬間まで、劉邦は虚心を第一として続けたのだった。
漢帝国の皇帝に即位して後も、為政にかけて我を張り通すようなことは極力避け、当初は儒者嫌いだった
にもかかわらず、陸賈の説得や、叔孫通の気の利いた礼楽の再興などを受けて全面的に儒学統治を取り入れもした。
劉邦の没後には、本人の遺言に即して、陳平や周勃が、正室家にして半ば政商でもあった呂氏を殲滅し、
漢室における政財癒着の問題の根をも断ち切った。劉邦の曾孫の武帝の代には大々的な贋金造りの摘発も行われ、
公務に失敗しようものなら引責自殺も辞さないような忠臣ばかりで君子階級が固められることともなった。
かような手続きを通じて、漢帝国は明や豊臣政権が来たしたような問題を予防や克服しつつの治世を築き上げた。
ほとんど裸一貫からのし上がった点では共通している三例であればこそ如実なのが、そうであって
なおかつ無我虚心を貫いたのが漢の劉家だった一方、ヘタクソな意思を差し挟んだのが明の朱家であり、
ほとんど自分自身の意思ばかりで全てを塗り固めようとしたのが豊臣秀吉だったという点である。
貧農ほどにも最底辺の身分であればこそ、世の中の大局をも俯瞰して、世界レベルの集団意思の大波に
乗ることすらもが可能となる場合がある。ただそれは、あくまで本人が劉邦のような虚心さを保ち続けられる
限りにおけるのであり、多少の恣意を差し挟んだりした時点ですでに、それなりの身分の持ち主などともさして
俯瞰力が変わらなくなる。俯瞰力も位持ち並みで、しかも自分は位なしというのだから、もはや何の価値も無くなる。
最底辺級の身分の持ち主こそは、それなりの身分の持ち主以上もの俯瞰力によって天命すらをも味方に付けられる
場合があるのは、天命も本質的には虚空の真理に即するものだからだ。天命を左右する主体などというものは
この世界にもその外側にもありはしないが、無為自然の中に自然と形成される天命らしきものがある。
それが決して誰かの恣意によって左右されるようなものではないからこそ、常日ごろから恣意を控えている
必要がある底辺身分の人間こそが、運気に乗っかって天命に与れるようなことがあるのである。
ただし、底辺身分こそはそのような運気に乗っかれるようであるとするなら、それは、世の中の有位者たちが
揃いも揃って天命に真っ向から反する凶事ばかりを働いている時代だったりもするに違いないわけだが。
漢室における政財癒着の問題の根をも断ち切った。劉邦の曾孫の武帝の代には大々的な贋金造りの摘発も行われ、
公務に失敗しようものなら引責自殺も辞さないような忠臣ばかりで君子階級が固められることともなった。
かような手続きを通じて、漢帝国は明や豊臣政権が来たしたような問題を予防や克服しつつの治世を築き上げた。
ほとんど裸一貫からのし上がった点では共通している三例であればこそ如実なのが、そうであって
なおかつ無我虚心を貫いたのが漢の劉家だった一方、ヘタクソな意思を差し挟んだのが明の朱家であり、
ほとんど自分自身の意思ばかりで全てを塗り固めようとしたのが豊臣秀吉だったという点である。
貧農ほどにも最底辺の身分であればこそ、世の中の大局をも俯瞰して、世界レベルの集団意思の大波に
乗ることすらもが可能となる場合がある。ただそれは、あくまで本人が劉邦のような虚心さを保ち続けられる
限りにおけるのであり、多少の恣意を差し挟んだりした時点ですでに、それなりの身分の持ち主などともさして
俯瞰力が変わらなくなる。俯瞰力も位持ち並みで、しかも自分は位なしというのだから、もはや何の価値も無くなる。
最底辺級の身分の持ち主こそは、それなりの身分の持ち主以上もの俯瞰力によって天命すらをも味方に付けられる
場合があるのは、天命も本質的には虚空の真理に即するものだからだ。天命を左右する主体などというものは
この世界にもその外側にもありはしないが、無為自然の中に自然と形成される天命らしきものがある。
それが決して誰かの恣意によって左右されるようなものではないからこそ、常日ごろから恣意を控えている
必要がある底辺身分の人間こそが、運気に乗っかって天命に与れるようなことがあるのである。
ただし、底辺身分こそはそのような運気に乗っかれるようであるとするなら、それは、世の中の有位者たちが
揃いも揃って天命に真っ向から反する凶事ばかりを働いている時代だったりもするに違いないわけだが。
「長者に於いて謀るには必ず几杖を操りて以て之れに従う。長者問うに、辞讓せずして対えるは非礼なり」
「年長者と共に物事を計画する場合には、必ず杖を携えてこれに従う。年長者が質問してきた場合にも、
『私の考えなど聞くに耐える程のものでもありません』などと謙りもせずに、即座に答えるようならば非礼である。
(真正聖書四書五経のほうが、犯罪聖書通称聖書よも、その成立時期からして数百年以上年長である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・曲礼上第一より)
「年長者と共に物事を計画する場合には、必ず杖を携えてこれに従う。年長者が質問してきた場合にも、
『私の考えなど聞くに耐える程のものでもありません』などと謙りもせずに、即座に答えるようならば非礼である。
(真正聖書四書五経のほうが、犯罪聖書通称聖書よも、その成立時期からして数百年以上年長である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・曲礼上第一より)
>>178の「中庸」からの引用を見ても分かるように、
儒者は去来今の広大無辺に渡る積極性の一環として、温故知新などの故旧をも貴んでいく。
これは大乗仏教の華厳思想などにも通ずる「時空の超越」であり、
ただの一方向ばかりに積極性を限らぬが故にこそ、積極性の極致でもあるといえる。
将来ばかりに積極的であるというのは、前向きのようでいて、実は「逃避」にかけてこそ積極的なのである。
過去からも、現在からも逃げて、ただ未来を追い求めて行くことにばかり積極的でいる、それは、
あらゆる積極性の中でもむしろ消極的な部類の積極性なのであり、そんなものを追い求めたりしなくても
自然と「時間ありて有あり、有ありて時間あり(正法眼蔵)」という不変法則に即して時間は流れて行く。
わざわざ希求しなくたって自然とやってくるものばかりを積極的に希求するというのだから、
易行か難行かでいえば易行であり、易行にしか積極的でいられないからには自分が愚か者なのである。
自分もまだ生まれていなかった頃の歴史にまで思いを馳せ、自らの行いとも照合して、何ら恥じるところが無く、
むしろ誇らしげにすら思えたりするのなら、それは時空を超越した愉悦であるといえ、世襲であれ否であれ、
己れの業を引き継がせて行くことを通じて、後継者にその愉悦をも受け継がせて行くことができる。
それが礼楽刑政の「楽」の要ともなり、代々の泰平統治の礎とすらなって行く。
そのような、去来今の三世を超越した時の流れの征服者であることこそは、人間としての最大の栄誉で
あると共に、自らが超人的な領域、神仏の域にすら近似する福寿ともなる。自分一身の命や意思をも超越した
絶対的なものとの合致によって、自分自身こそは最大級の福徳にも与ることができる。もしも人が永遠の命を
手に入れられたりするのならそうとも限らないだろうが、実際のところ諸行無常が真理でもあるから、永久不変の
絶対法則として、時空を超越した「歴史的人間」としての大成こそは、個人としても無常の栄華となるのである。
儒者は去来今の広大無辺に渡る積極性の一環として、温故知新などの故旧をも貴んでいく。
これは大乗仏教の華厳思想などにも通ずる「時空の超越」であり、
ただの一方向ばかりに積極性を限らぬが故にこそ、積極性の極致でもあるといえる。
将来ばかりに積極的であるというのは、前向きのようでいて、実は「逃避」にかけてこそ積極的なのである。
過去からも、現在からも逃げて、ただ未来を追い求めて行くことにばかり積極的でいる、それは、
あらゆる積極性の中でもむしろ消極的な部類の積極性なのであり、そんなものを追い求めたりしなくても
自然と「時間ありて有あり、有ありて時間あり(正法眼蔵)」という不変法則に即して時間は流れて行く。
わざわざ希求しなくたって自然とやってくるものばかりを積極的に希求するというのだから、
易行か難行かでいえば易行であり、易行にしか積極的でいられないからには自分が愚か者なのである。
自分もまだ生まれていなかった頃の歴史にまで思いを馳せ、自らの行いとも照合して、何ら恥じるところが無く、
むしろ誇らしげにすら思えたりするのなら、それは時空を超越した愉悦であるといえ、世襲であれ否であれ、
己れの業を引き継がせて行くことを通じて、後継者にその愉悦をも受け継がせて行くことができる。
それが礼楽刑政の「楽」の要ともなり、代々の泰平統治の礎とすらなって行く。
そのような、去来今の三世を超越した時の流れの征服者であることこそは、人間としての最大の栄誉で
あると共に、自らが超人的な領域、神仏の域にすら近似する福寿ともなる。自分一身の命や意思をも超越した
絶対的なものとの合致によって、自分自身こそは最大級の福徳にも与ることができる。もしも人が永遠の命を
手に入れられたりするのならそうとも限らないだろうが、実際のところ諸行無常が真理でもあるから、永久不変の
絶対法則として、時空を超越した「歴史的人間」としての大成こそは、個人としても無常の栄華となるのである。
自分個人の刹那的な栄華ばかりを追いかけて、後を振り返ってみれば醜悪な放辟邪侈の残骸ばかり、
だからこれからも将来の栄華ばかりを追い求めて行く、そのような悪循環に陥ってしまっている人間がいざ
自らの死に直面させられる時ほど、絶望的なことも他にない。人間である以上はいつかは死ぬ、にもかかわらず
誰にも褒められようのないような、邪まな無道ばかりをひた走り続けてきたままに命を終える、だからこそ、
大業ではなくともそれなりに堅実な人生を送ってきたような人間以上もの絶望にすら見舞われることとなる。
永遠の命などあり得ない、諸行無常こそは真理であるというわきまえが磐石であるなら、人は最大級の栄華を
追い求めるためにこそ、いち個人としての栄華以上にも、歴史的人物としての栄華こそを追い求めるはずである。
いつかは誰しもが死して灰燼に帰する、にもかかわらず自分一身の栄華ばかりを追い求めたりするよりは、
先人たちの偉業を引き継いで、自分もまた最善を尽くした大業を後継者へと受け継がせて行くようにする中での
栄華を追い求めていくほうが、明らかにより壮大かつ普遍的な栄華を追い求めていくことともなるのだから。
栄華など追い求めずに隠遁や出家に甘んじるというのなら、それも一つの生き方だといえる。ただ、
仮に自分が社会的な栄華を追い求めようと思うのならば、個人的な栄華以上にも、個人性を超えた
歴史的な大業を通じての栄華こそを追い求めて行くべきである。それでこそ、人と人とがお互いに
助け合うことでこそ成り立っている世の中における、純正な栄華の追い求め方ともなるのだから。
「日に省み月に試み、既廩事に称うは、百工を勧むる所以なり」
「工業従事者の生産労働などは特にその巧拙の落差が甚だしいため、日々その仕事を
省みて月々に技巧試験なども科し、仕事の手堅さに相応の報酬を与えて行くようにする必要がある。
(共産化による産業従事の平坦化が深刻な職務怠惰を招いた元凶の指摘。そのような問題を未然に防いでいる
というのなら、そのような人間こそは、共産主義と聖書信仰両方ともを非としているのだから、結構なことだ)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・二〇より)
だからこれからも将来の栄華ばかりを追い求めて行く、そのような悪循環に陥ってしまっている人間がいざ
自らの死に直面させられる時ほど、絶望的なことも他にない。人間である以上はいつかは死ぬ、にもかかわらず
誰にも褒められようのないような、邪まな無道ばかりをひた走り続けてきたままに命を終える、だからこそ、
大業ではなくともそれなりに堅実な人生を送ってきたような人間以上もの絶望にすら見舞われることとなる。
永遠の命などあり得ない、諸行無常こそは真理であるというわきまえが磐石であるなら、人は最大級の栄華を
追い求めるためにこそ、いち個人としての栄華以上にも、歴史的人物としての栄華こそを追い求めるはずである。
いつかは誰しもが死して灰燼に帰する、にもかかわらず自分一身の栄華ばかりを追い求めたりするよりは、
先人たちの偉業を引き継いで、自分もまた最善を尽くした大業を後継者へと受け継がせて行くようにする中での
栄華を追い求めていくほうが、明らかにより壮大かつ普遍的な栄華を追い求めていくことともなるのだから。
栄華など追い求めずに隠遁や出家に甘んじるというのなら、それも一つの生き方だといえる。ただ、
仮に自分が社会的な栄華を追い求めようと思うのならば、個人的な栄華以上にも、個人性を超えた
歴史的な大業を通じての栄華こそを追い求めて行くべきである。それでこそ、人と人とがお互いに
助け合うことでこそ成り立っている世の中における、純正な栄華の追い求め方ともなるのだから。
「日に省み月に試み、既廩事に称うは、百工を勧むる所以なり」
「工業従事者の生産労働などは特にその巧拙の落差が甚だしいため、日々その仕事を
省みて月々に技巧試験なども科し、仕事の手堅さに相応の報酬を与えて行くようにする必要がある。
(共産化による産業従事の平坦化が深刻な職務怠惰を招いた元凶の指摘。そのような問題を未然に防いでいる
というのなら、そのような人間こそは、共産主義と聖書信仰両方ともを非としているのだから、結構なことだ)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・二〇より)
人並みの罪識能力を保てることを「死」などと呼んで貶め、
罪識能力が保てないことを「生」などと呼んで誉めそやすことがあるとすれば、
これはありのままに人々の精神病質を助長する邪教であることが自明であり、
宗派教派の如何に関わらず、そんな教条を持つ信教などを倫理的な非難や
取締りの対象としていかなければならないことが明らかである。
実際に罪があるということ、罪を罪だと認識できることが生に近いか死に近いかということは、
解釈の仕方によってどうとでも言えることである。自分が罪を犯して、罪識があるために
良心の呵責に苛まれて苦しむ、そのことを以ってして「死に近い」などと小人なら
考えてしまいがちなものである。しかし君子としての見識から、良心の呵責を抱けるような
機敏な性情の持ち主こそは精神的な生者であり、罪に対する良心の呵責も抱けなくなって
しまっているような精神病質者こそは精神的な死者であると見なすこともできるのである。
ここは、真理ではなく道理の問題である。
解釈の仕方によってどうとでも言えるところを、あえて「一人前の罪識能力の持ち主こそは
生者であり、そうでない人間こそは死者である」と形容することのほうが道理に適っている一方、
「良心の呵責に苛まれているような人間こそは死者であり、良心の呵責などを抱かないで
いられる人間こそは生者である」などと形容することのほうが道理に反している。
孔子が「性相い近し、習えば相い遠し(陽貨第十七・二)」と言っていたのを引き継いで、
孟子は「人は本来性善だが、後天的に濁悪にまみれる場合がある」と言ったのに対し、
荀子は「人の生は本来悪であり、礼節の修得によって改善されて行く」といったのも、
孟子には人々をより根本から徳化していこうとする積極性があった一方、荀子には
そんな積極性はなく、濁悪まみれだった当時のような世の中でも受け入れられやすい
ような「同調圧力に屈した論及」をこしらえることしかできなかったからである。
罪識能力が保てないことを「生」などと呼んで誉めそやすことがあるとすれば、
これはありのままに人々の精神病質を助長する邪教であることが自明であり、
宗派教派の如何に関わらず、そんな教条を持つ信教などを倫理的な非難や
取締りの対象としていかなければならないことが明らかである。
実際に罪があるということ、罪を罪だと認識できることが生に近いか死に近いかということは、
解釈の仕方によってどうとでも言えることである。自分が罪を犯して、罪識があるために
良心の呵責に苛まれて苦しむ、そのことを以ってして「死に近い」などと小人なら
考えてしまいがちなものである。しかし君子としての見識から、良心の呵責を抱けるような
機敏な性情の持ち主こそは精神的な生者であり、罪に対する良心の呵責も抱けなくなって
しまっているような精神病質者こそは精神的な死者であると見なすこともできるのである。
ここは、真理ではなく道理の問題である。
解釈の仕方によってどうとでも言えるところを、あえて「一人前の罪識能力の持ち主こそは
生者であり、そうでない人間こそは死者である」と形容することのほうが道理に適っている一方、
「良心の呵責に苛まれているような人間こそは死者であり、良心の呵責などを抱かないで
いられる人間こそは生者である」などと形容することのほうが道理に反している。
孔子が「性相い近し、習えば相い遠し(陽貨第十七・二)」と言っていたのを引き継いで、
孟子は「人は本来性善だが、後天的に濁悪にまみれる場合がある」と言ったのに対し、
荀子は「人の生は本来悪であり、礼節の修得によって改善されて行く」といったのも、
孟子には人々をより根本から徳化していこうとする積極性があった一方、荀子には
そんな積極性はなく、濁悪まみれだった当時のような世の中でも受け入れられやすい
ような「同調圧力に屈した論及」をこしらえることしかできなかったからである。
結局、その論及姿勢としては、朱子などの主要な後代の儒者がみな、荀子ではなく孟子の
物言いにこそ軍配を挙げ、性即理説のような自前の論説による支援すらをも試みている。
(王陽明の心即理説も、孟子の性善説を過剰なほどに補強しようとするものでこそあった)
そのような諸々の儒者のあり方こそはありのままに、道理の啓発をより積極的に推進して
いくものであった。超俗の真理ではなく世俗の道理を専門的に司って行くのが儒者の本分で
あればこそ、道理をただ静観するだけでなく、積極的に啓発して行くことをも試みたのである。
無理だけでなく、道理もまた積極的に推進して行けるものである。
「無理が通れば道理が引っ込む」の逆として、「道理を通して無理を引っ込める」という
こともまたできることであり、撥乱反正が実現された長期の泰平社会などにおいては、ほぼ必ず
作為的な道理の啓発までもが推進されている。それ以前に乱世の辛酸を嘗め尽くしていればこそ、
「もうあんな時代はこりごり」という思いも込めて、より積極的に道理が肯んじられることとなる。
そういうことがあり得るからこそ、無理ばかりが通ることを恐れたりする必要もないのである。
精神病質の蔓延を推進するような邪教に急進的な傾向があるのと同じように、無理を排して
道理を通していく正学もまた健全な急進性を伴い得る。1+1=3であることなどを許さず、
馬は馬、鹿は鹿であることこそをより積極的に承認して行く道理の急進的な推進によってこそ、
無理を玩ぶ大火すらもが消し止められて、厳重な防火の用意すらもが整えられることとなる。
そこにこそ、人としての最高の楽しみまでもがある。人が最大級に精神的に活きられもする。
もちろん邪悪の楽しみなどというものもあるにしろ、それとはまた別に、それほどもの楽しみだとか
活気だとかがある。少なくともそういう解釈の仕方もできて、自分はそうであることこそを標榜し
もする。そのような姿勢こそが積極的な道理の推進ともなっていて、なおかつ本当に楽しいからだ。
物言いにこそ軍配を挙げ、性即理説のような自前の論説による支援すらをも試みている。
(王陽明の心即理説も、孟子の性善説を過剰なほどに補強しようとするものでこそあった)
そのような諸々の儒者のあり方こそはありのままに、道理の啓発をより積極的に推進して
いくものであった。超俗の真理ではなく世俗の道理を専門的に司って行くのが儒者の本分で
あればこそ、道理をただ静観するだけでなく、積極的に啓発して行くことをも試みたのである。
無理だけでなく、道理もまた積極的に推進して行けるものである。
「無理が通れば道理が引っ込む」の逆として、「道理を通して無理を引っ込める」という
こともまたできることであり、撥乱反正が実現された長期の泰平社会などにおいては、ほぼ必ず
作為的な道理の啓発までもが推進されている。それ以前に乱世の辛酸を嘗め尽くしていればこそ、
「もうあんな時代はこりごり」という思いも込めて、より積極的に道理が肯んじられることとなる。
そういうことがあり得るからこそ、無理ばかりが通ることを恐れたりする必要もないのである。
精神病質の蔓延を推進するような邪教に急進的な傾向があるのと同じように、無理を排して
道理を通していく正学もまた健全な急進性を伴い得る。1+1=3であることなどを許さず、
馬は馬、鹿は鹿であることこそをより積極的に承認して行く道理の急進的な推進によってこそ、
無理を玩ぶ大火すらもが消し止められて、厳重な防火の用意すらもが整えられることとなる。
そこにこそ、人としての最高の楽しみまでもがある。人が最大級に精神的に活きられもする。
もちろん邪悪の楽しみなどというものもあるにしろ、それとはまた別に、それほどもの楽しみだとか
活気だとかがある。少なくともそういう解釈の仕方もできて、自分はそうであることこそを標榜し
もする。そのような姿勢こそが積極的な道理の推進ともなっていて、なおかつ本当に楽しいからだ。
「書に曰く、安きに居りて危うきを思えと。
思えば則ち備え有り。備え有れば患え無し、と。敢えて此を以て規とす」
「書経(説命中、一部遺失)に『未だ安全である内にも危難を思って警戒せよ。予め危難を思って警戒することにより
備えができる。備えあれば憂いなし』とある。これこそを通用的な規則として、自分たちを正していくべきだといえる。
(規則とは本来、危難を避けるための備えなのだから、規則を取り払えばただ危難に見舞われるのみである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・襄公十一年より)
思えば則ち備え有り。備え有れば患え無し、と。敢えて此を以て規とす」
「書経(説命中、一部遺失)に『未だ安全である内にも危難を思って警戒せよ。予め危難を思って警戒することにより
備えができる。備えあれば憂いなし』とある。これこそを通用的な規則として、自分たちを正していくべきだといえる。
(規則とは本来、危難を避けるための備えなのだから、規則を取り払えばただ危難に見舞われるのみである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・襄公十一年より)
今年始め>>182-183の書き込みでも論じたように、心内はむしろ常日ごろからの警戒を尽くし、
現実における安全や平和こそを真摯に追い求めて行くのが、正しい人間のあり方である。
その逆のあり方、安からざる所に安らぎ、楽しむべからざる所に楽しむ体たらくを
荀子が「狂生(君道第十二)」と呼んだのに順ずるなら、上記のような内面の警戒と
外面の平安を尽くそうとするあり方こそは「正気の生」だといえる。
正気の生を保つためにこそ、人は決して一人だけでは生きられない、複数の人々が
家庭や世の中を共に形作ることを通じて初めて個人もまた生きられているのだということを
わきまえねばならない。それをわきまえることができて初めて、自分一身の安楽ばかりを
追い求めることなく、まずは他人を含む世の中の側の平安こそを優先して企図するようにもなれる。
理想としては、そのような正気の生に与れる人間だけで世の中が形成されるに越したことはない。
それでこそ、世の中もそこに住まう人間も総てが「健康体」でいられているともいえるわけだが、
なかなかそこにまで到達するのも難しいことで、多少は世の中の平安よりも
自分個人の安楽のほうを追い求めるような人間が生じもするものである。
それもまた、十分な抑制下に置かれてすらいれば、別に問題はないことである。
昔の日本などでも、豪商や地主身分の人間が相当に個人的な富裕を誇ることがあったわけだが、
それとて、武家による威力的な牽制が利いてもいたものだから、傾国級の問題にまでは発展しなかった。
(部落階級が人身御供的な差別対象となることで、素封の富裕が観念面から戒められてもいた)
治世を企図する立場から許されるのは、ここまでである。
現実における安全や平和こそを真摯に追い求めて行くのが、正しい人間のあり方である。
その逆のあり方、安からざる所に安らぎ、楽しむべからざる所に楽しむ体たらくを
荀子が「狂生(君道第十二)」と呼んだのに順ずるなら、上記のような内面の警戒と
外面の平安を尽くそうとするあり方こそは「正気の生」だといえる。
正気の生を保つためにこそ、人は決して一人だけでは生きられない、複数の人々が
家庭や世の中を共に形作ることを通じて初めて個人もまた生きられているのだということを
わきまえねばならない。それをわきまえることができて初めて、自分一身の安楽ばかりを
追い求めることなく、まずは他人を含む世の中の側の平安こそを優先して企図するようにもなれる。
理想としては、そのような正気の生に与れる人間だけで世の中が形成されるに越したことはない。
それでこそ、世の中もそこに住まう人間も総てが「健康体」でいられているともいえるわけだが、
なかなかそこにまで到達するのも難しいことで、多少は世の中の平安よりも
自分個人の安楽のほうを追い求めるような人間が生じもするものである。
それもまた、十分な抑制下に置かれてすらいれば、別に問題はないことである。
昔の日本などでも、豪商や地主身分の人間が相当に個人的な富裕を誇ることがあったわけだが、
それとて、武家による威力的な牽制が利いてもいたものだから、傾国級の問題にまでは発展しなかった。
(部落階級が人身御供的な差別対象となることで、素封の富裕が観念面から戒められてもいた)
治世を企図する立場から許されるのは、ここまでである。
世の中の平安よりも自分一身の安楽ばかりを追い求めることが抑制の対象にすらされず、挙句には
積極的な推進の対象にすらされるとなれば、これはもう乱世や亡国すらもが免れられるものではない。
今はもはや、自分個人の安楽ばかりを追い求めることが常識とすら化してしまっている時代である。
「自分第一世の中第二」や「自分が全て世の中無視」であるような人間こそは一般的な常識人としてすら
扱われている時代であり、しかもそれが「いつの時代にも共通する世の常」だとすら考えられている。
そんな常識は恒久的に通用するものではないから、いま人類社会も滅亡の危機に瀕している。そんな
常識が通用しないにもかかわらず、これまで人類はどうにかやって来ているわけだから、上記のような
現代にこそ特有の常識が、人類社会において持続的に通用していた試しもまたないことが確かである。
ジョンレノンは「今の世界は狂人が支配している」と言ったが、そもそも今の世の一般人からして
狂っている。別に精神病診断を受けたりしているわけでもない、健康体とされているような人間
からして、人類の滅亡にすら加担してやまぬほどもの深刻な病理を内に抱えてしまっている。
その狂気が正されるとき、人はかえってそれこそを狂気との遭遇だなどと勘違いしかねない。
本当は狂気から脱していく時なのに、狂気に駆られている現状こそを正気だなどと倒錯しているもの
だから、その倒錯に即して、狂気からの脱却こそを狂気への没入だなどと思い込んでしまうのである。
「江戸時代の人間は精神主義すぎて狂ってた」みたいなことが言われるのも、そのためである。
むしろ、何百年もの治世を保つためにこそ、江戸時代の日本人並みの精神力が必須なのであり、
今の人間並みに精神がへたり過ぎていることこそは、我と人とを破滅へと追いやる狂態なのである。
積極的な推進の対象にすらされるとなれば、これはもう乱世や亡国すらもが免れられるものではない。
今はもはや、自分個人の安楽ばかりを追い求めることが常識とすら化してしまっている時代である。
「自分第一世の中第二」や「自分が全て世の中無視」であるような人間こそは一般的な常識人としてすら
扱われている時代であり、しかもそれが「いつの時代にも共通する世の常」だとすら考えられている。
そんな常識は恒久的に通用するものではないから、いま人類社会も滅亡の危機に瀕している。そんな
常識が通用しないにもかかわらず、これまで人類はどうにかやって来ているわけだから、上記のような
現代にこそ特有の常識が、人類社会において持続的に通用していた試しもまたないことが確かである。
ジョンレノンは「今の世界は狂人が支配している」と言ったが、そもそも今の世の一般人からして
狂っている。別に精神病診断を受けたりしているわけでもない、健康体とされているような人間
からして、人類の滅亡にすら加担してやまぬほどもの深刻な病理を内に抱えてしまっている。
その狂気が正されるとき、人はかえってそれこそを狂気との遭遇だなどと勘違いしかねない。
本当は狂気から脱していく時なのに、狂気に駆られている現状こそを正気だなどと倒錯しているもの
だから、その倒錯に即して、狂気からの脱却こそを狂気への没入だなどと思い込んでしまうのである。
「江戸時代の人間は精神主義すぎて狂ってた」みたいなことが言われるのも、そのためである。
むしろ、何百年もの治世を保つためにこそ、江戸時代の日本人並みの精神力が必須なのであり、
今の人間並みに精神がへたり過ぎていることこそは、我と人とを破滅へと追いやる狂態なのである。
どんなに現時点で明白に訴えてみたところで、現状こそは普通であり、
現状から脱却させられることこそは狂気の沙汰だなどと考えてしまう人間を
今すぐに絶やし尽くすことまではできもしないとも知れている。「変化はどんなに善いことでもイヤだ」
と考えてしまうのは老人の常であり、今の資本主義先進国の大半も少子高齢化が深刻化してしまっているのだから、
(名目上の少子高齢化が抑えられている国なども、若い移民によって平均年齢を下げたりしているだけである)
現状の特殊性だけでなく、いつの世でもの常に即してすら、意識改革などなかなか覚束かないことだといえる。
過ちにこそ安住し、正されることこそを苦痛に思う、それは自分が人としての過ちを尽くし過ぎたからであり、
ちょうどゴミ屋敷を作ってしまった人間がそこに安住してしまうようなものだといえる。誰の目から見ても
ゴミを片付けたほうがいいように思えるが、ゴミ屋敷の住人自身は、それこそが普通のあり方だとする。
そういう観点から現状を捉えられる人間が、できる限り早くの内から多く現れてくれることを願うまでである。
「貞に安んずれば吉なり。〜貞に安んずるの吉なるは、地の疆り无きに應ずればなり」
「正しきに安んじれば吉である。正しきに安んじれば吉であるのは、地の果てに至るまでの正直に適うからである。
(正しからざるに安んずるのが狂生であり、狂生は不吉であるである一方、その逆はむしろ吉祥である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・坤・卦辞‐彖伝より)
現状から脱却させられることこそは狂気の沙汰だなどと考えてしまう人間を
今すぐに絶やし尽くすことまではできもしないとも知れている。「変化はどんなに善いことでもイヤだ」
と考えてしまうのは老人の常であり、今の資本主義先進国の大半も少子高齢化が深刻化してしまっているのだから、
(名目上の少子高齢化が抑えられている国なども、若い移民によって平均年齢を下げたりしているだけである)
現状の特殊性だけでなく、いつの世でもの常に即してすら、意識改革などなかなか覚束かないことだといえる。
過ちにこそ安住し、正されることこそを苦痛に思う、それは自分が人としての過ちを尽くし過ぎたからであり、
ちょうどゴミ屋敷を作ってしまった人間がそこに安住してしまうようなものだといえる。誰の目から見ても
ゴミを片付けたほうがいいように思えるが、ゴミ屋敷の住人自身は、それこそが普通のあり方だとする。
そういう観点から現状を捉えられる人間が、できる限り早くの内から多く現れてくれることを願うまでである。
「貞に安んずれば吉なり。〜貞に安んずるの吉なるは、地の疆り无きに應ずればなり」
「正しきに安んじれば吉である。正しきに安んじれば吉であるのは、地の果てに至るまでの正直に適うからである。
(正しからざるに安んずるのが狂生であり、狂生は不吉であるである一方、その逆はむしろ吉祥である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・坤・卦辞‐彖伝より)
以前にも、摩擦抵抗や関節の可動領域などの自由度の制限があるからこそ、
人間という生き物もまた成立しているということは述べた。そのような
制限による束縛をほとんど受けないアメーバやクラゲなどの生物もいるものの、
あまりにも原始的で、人間のような精密な有機性を持ち得てもいないわけで、
もしも人間が「完全なる自由」だの「永遠の命」だのを追い求めたところで、
そのような原始化の付帯が避けられない、ということも凡そ述べたことである。
無制限の自由を追い求めた先にあるのは、いつも原始化である。
人間にとっては稚拙化となり、それこそは「下劣」と見なされるに値するものである。
自由は稚拙であり、下劣である、そうであることを知った上でなお自由を求めるということも
完全に禁止されるべきことでもない。出家者でもない俗人が多少ハメを外して酒を飲んだり
することがあったって別に構いやしないが、それも度を越せば戒められるべきこととなる。
節度を保った自由ならいくらでもありだが、完全に無制限な自由ともなれば問題となる。
そのような自由こそを神聖化しようなどとする試みもまた、決してよしとすべきものではない。
必要悪としての自由ではなく、善いものとしての自由などを希求したりすることだけがいけない。
以上の論及で用いた「自由」は、福沢諭吉が英語のlibertyやfreedomを和訳した所の「自由」である。
「自由」という言葉自体は本来「臨済録」などに出てくる禅語であり、禅語としての「自由」は
むしろ追い求められて然るべきものである。というのは、英語のlibertyやfreedomが意味する所は
「行為能力の自由」であるのに対し、禅語の「自由」は「精神の自由」こそを指しているからだ。
人間という生き物もまた成立しているということは述べた。そのような
制限による束縛をほとんど受けないアメーバやクラゲなどの生物もいるものの、
あまりにも原始的で、人間のような精密な有機性を持ち得てもいないわけで、
もしも人間が「完全なる自由」だの「永遠の命」だのを追い求めたところで、
そのような原始化の付帯が避けられない、ということも凡そ述べたことである。
無制限の自由を追い求めた先にあるのは、いつも原始化である。
人間にとっては稚拙化となり、それこそは「下劣」と見なされるに値するものである。
自由は稚拙であり、下劣である、そうであることを知った上でなお自由を求めるということも
完全に禁止されるべきことでもない。出家者でもない俗人が多少ハメを外して酒を飲んだり
することがあったって別に構いやしないが、それも度を越せば戒められるべきこととなる。
節度を保った自由ならいくらでもありだが、完全に無制限な自由ともなれば問題となる。
そのような自由こそを神聖化しようなどとする試みもまた、決してよしとすべきものではない。
必要悪としての自由ではなく、善いものとしての自由などを希求したりすることだけがいけない。
以上の論及で用いた「自由」は、福沢諭吉が英語のlibertyやfreedomを和訳した所の「自由」である。
「自由」という言葉自体は本来「臨済録」などに出てくる禅語であり、禅語としての「自由」は
むしろ追い求められて然るべきものである。というのは、英語のlibertyやfreedomが意味する所は
「行為能力の自由」であるのに対し、禅語の「自由」は「精神の自由」こそを指しているからだ。
精神の自由を得るためには、むしろ行為能力利用の適切な自制や制限こそが必要である。
他人から無理やり制限を被るよりは、自分から進んで自制を心がけるほうがより有効であり、
その真摯さこそが精神の自由にも寄与しやすい。禅僧なども、親などに強制されて出家した場合よりは、
自分から進んで出家した場合のほうが大成しやすいとは、後者の理由に即して自主的に出家し、厳しい
修行をこなして日本臨済宗最大教派である妙心寺派の管長となった玄峰老師も言われていたことである。
精神の自由は、人としての稚拙化などを徹底して防ぎ止めた所にこそある。精神的な成熟を
極めたところにこそ、最大級の精神の自由もまたあるのだから、行為能力の濫用などによって
己れの品性を下落させてしまったのでは、かえって精神の自由は損なわれることになるのである。
「精神の自由と行為能力の自由は反比例関係にある」といっても、過言ではない。ただ、
行為能力を適正に活用することで精神の自由を保ったり助成したりすることは可能である。
それは、日本刀の刃筋ほどにも細く長い一本道を歩き続けるようなもので、決して行為能力の
自由などと共にあり得るものではない。仁政専門の為政者となったりすることがそれに当たるが、
仁政家になったからといってそれで自分が得するようなこともないわけで、行為能力の自由など
もむしろ制限される。それよりは、民間の素封家ででもいたほうがよっぽど金銭面などで自由で
いられるのは、昔の武家や公家などよりも、豪商や地主のほうがよっぽど潤っていたことからも窺える。
他人から無理やり制限を被るよりは、自分から進んで自制を心がけるほうがより有効であり、
その真摯さこそが精神の自由にも寄与しやすい。禅僧なども、親などに強制されて出家した場合よりは、
自分から進んで出家した場合のほうが大成しやすいとは、後者の理由に即して自主的に出家し、厳しい
修行をこなして日本臨済宗最大教派である妙心寺派の管長となった玄峰老師も言われていたことである。
精神の自由は、人としての稚拙化などを徹底して防ぎ止めた所にこそある。精神的な成熟を
極めたところにこそ、最大級の精神の自由もまたあるのだから、行為能力の濫用などによって
己れの品性を下落させてしまったのでは、かえって精神の自由は損なわれることになるのである。
「精神の自由と行為能力の自由は反比例関係にある」といっても、過言ではない。ただ、
行為能力を適正に活用することで精神の自由を保ったり助成したりすることは可能である。
それは、日本刀の刃筋ほどにも細く長い一本道を歩き続けるようなもので、決して行為能力の
自由などと共にあり得るものではない。仁政専門の為政者となったりすることがそれに当たるが、
仁政家になったからといってそれで自分が得するようなこともないわけで、行為能力の自由など
もむしろ制限される。それよりは、民間の素封家ででもいたほうがよっぽど金銭面などで自由で
いられるのは、昔の武家や公家などよりも、豪商や地主のほうがよっぽど潤っていたことからも窺える。
世の中の公益に寄与することだけを目的として行為能力を自制するのでは、堅苦しい。むしろ
精神の自由を得るためにこそ、そのための障りになる行為能力の自由を制限するぐらいであるべきだ。
金持ちや権力犯罪者こそは「精神の不能者」であることを戒めとして、行為能力の自制という精進に励む。
元より「精進」という言葉もそのような意味合いこそを伴っていたのであり、宗教法人法に守られる
ことで私腹を肥やしている今の日本の僧団などが本当に精進できているようなことも、極めて稀である。
精神の自由と行為能力の自由が別物であることすら、今はほとんど認知されてもいない。
両者が反比例関係にあることはおろか、比例的に連動しないことすら察知されてはいないものだから、
精神の自由こそを追い求めて行為能力の濫用に及んでしまっているような人間すらもが多々いる。
アルファベット圏の人間の多くはそうであり、禅語の「自由」をlibertyやfreedomの訳語として
用いてしまっている今の日本人にもそのような人間は多い。本来、「自由」という言葉はそんな
低劣な意味ばかりを持ち合わせいてたわけではないことを、今一度啓発し直していかねばならない。
精神の自由を得るためにこそ、そのための障りになる行為能力の自由を制限するぐらいであるべきだ。
金持ちや権力犯罪者こそは「精神の不能者」であることを戒めとして、行為能力の自制という精進に励む。
元より「精進」という言葉もそのような意味合いこそを伴っていたのであり、宗教法人法に守られる
ことで私腹を肥やしている今の日本の僧団などが本当に精進できているようなことも、極めて稀である。
精神の自由と行為能力の自由が別物であることすら、今はほとんど認知されてもいない。
両者が反比例関係にあることはおろか、比例的に連動しないことすら察知されてはいないものだから、
精神の自由こそを追い求めて行為能力の濫用に及んでしまっているような人間すらもが多々いる。
アルファベット圏の人間の多くはそうであり、禅語の「自由」をlibertyやfreedomの訳語として
用いてしまっている今の日本人にもそのような人間は多い。本来、「自由」という言葉はそんな
低劣な意味ばかりを持ち合わせいてたわけではないことを、今一度啓発し直していかねばならない。
「天下の士之れに悦するは人の欲する所なるも、以て憂いを解くに足らず。妃色は人の欲する所なるも、
帝の二女を妻とするといえども、以て憂いを解くに足らず。富は人の欲する所なるも、天下を富として有すれども、
以て憂いを解くに足らず。貴きは人の欲する所なるも、天子と為れども、以て憂いを解くに足らず。人之れに悦すと、
色を好むと、富貴なると、以て憂いを解くに足らず。惟だ父母に順るることのみ、以て憂いを解くに足る可し」
「天下の権力者たちがみな自分に従うこともまた欲せはするが、それによって憂いを解くには足らない。
妻女を得ることもまた欲せはするが、たとえ帝王の娘二人をめあわされた所で、それで憂いを解くには足らない。
富もまた欲せるものではあるが、たとえ天下全てを富として私有できたところで、それで憂いを解くには足らない。
尊貴であることも欲せるものではあるが、たとえ天下を統べる皇帝になれたとしても、それで憂いを解くには足らない。
権力者が服従すること、妻女を得ること、富貴に与れることのどれも憂いを解くには足らず、
ただ自らの親に喜ばれることのみが、真に自らの憂いを解くに値することである」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・万章章句上・一より)
帝の二女を妻とするといえども、以て憂いを解くに足らず。富は人の欲する所なるも、天下を富として有すれども、
以て憂いを解くに足らず。貴きは人の欲する所なるも、天子と為れども、以て憂いを解くに足らず。人之れに悦すと、
色を好むと、富貴なると、以て憂いを解くに足らず。惟だ父母に順るることのみ、以て憂いを解くに足る可し」
「天下の権力者たちがみな自分に従うこともまた欲せはするが、それによって憂いを解くには足らない。
妻女を得ることもまた欲せはするが、たとえ帝王の娘二人をめあわされた所で、それで憂いを解くには足らない。
富もまた欲せるものではあるが、たとえ天下全てを富として私有できたところで、それで憂いを解くには足らない。
尊貴であることも欲せるものではあるが、たとえ天下を統べる皇帝になれたとしても、それで憂いを解くには足らない。
権力者が服従すること、妻女を得ること、富貴に与れることのどれも憂いを解くには足らず、
ただ自らの親に喜ばれることのみが、真に自らの憂いを解くに値することである」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・万章章句上・一より)
神道で主に忌まれている血肉の穢れなども一種の汚れには違いないが、その他
にも色々な汚れというものはある。結局、最も致命的なのは「心の汚れ」であって、
その他のあらゆる汚れもまた心の汚れに結び付くことこそが最たる問題となるのである。
心の汚れは精神面における汚れであり、視聴覚や嗅覚によって外的に精神が
汚されることもあるし、自他の行業の粗悪さによって精神が汚されることもある。
精神が汚される原因となる現象はいくらでもあるが、それらの現象は根本的に
何なのであるかといえば、「命の不正な操作にまつわる現象」であるのだといえる。
簡単に言えば「罪のある現象」だが、法律や宗教の戒律に基づいて
定義される「罪」が「命の不正な操作」であるとは限らない。旧約の割礼や
飲酒運転などのように、それ自体がなんら命の操作に関わりのないものである
場合もあるわけだから、罪一般を帯びた現象が必ず汚れをもたらすとも限らない。
殺人は人の命を奪うことだから、命の不正な操作である場合がほとんどである。
(重罪人に対する相応の刑罰としての死刑などを除く)傷害も緩慢な命の不正操作となるし、
窃盗も他人の財物を奪うことで相手を貧窮に追いやったりすることが、間接的な命の
不正操作となる。このあたりの通用的な罪は、まさに汚れの元凶となるものである。
動物を殺してまでその肉を食らおうとすることなども、度を越せばBSEや
鳥獣インフルエンザのような人間にまで危害を及ぼす災禍をもたらすわけだから、
多少は人間たち自身の命の不正操作にも結び付き得ることである。大気汚染や
森林伐採などの環境破壊も、人間自身がそれによって諸々の悪影響を被るのだから、
人命の不正操作にまつわるものであり得るが故に、汚れをも帯びるものだといえる。
にも色々な汚れというものはある。結局、最も致命的なのは「心の汚れ」であって、
その他のあらゆる汚れもまた心の汚れに結び付くことこそが最たる問題となるのである。
心の汚れは精神面における汚れであり、視聴覚や嗅覚によって外的に精神が
汚されることもあるし、自他の行業の粗悪さによって精神が汚されることもある。
精神が汚される原因となる現象はいくらでもあるが、それらの現象は根本的に
何なのであるかといえば、「命の不正な操作にまつわる現象」であるのだといえる。
簡単に言えば「罪のある現象」だが、法律や宗教の戒律に基づいて
定義される「罪」が「命の不正な操作」であるとは限らない。旧約の割礼や
飲酒運転などのように、それ自体がなんら命の操作に関わりのないものである
場合もあるわけだから、罪一般を帯びた現象が必ず汚れをもたらすとも限らない。
殺人は人の命を奪うことだから、命の不正な操作である場合がほとんどである。
(重罪人に対する相応の刑罰としての死刑などを除く)傷害も緩慢な命の不正操作となるし、
窃盗も他人の財物を奪うことで相手を貧窮に追いやったりすることが、間接的な命の
不正操作となる。このあたりの通用的な罪は、まさに汚れの元凶となるものである。
動物を殺してまでその肉を食らおうとすることなども、度を越せばBSEや
鳥獣インフルエンザのような人間にまで危害を及ぼす災禍をもたらすわけだから、
多少は人間たち自身の命の不正操作にも結び付き得ることである。大気汚染や
森林伐採などの環境破壊も、人間自身がそれによって諸々の悪影響を被るのだから、
人命の不正操作にまつわるものであり得るが故に、汚れをも帯びるものだといえる。
家の部屋を汚いままにして掃除もしないでいれば、そのせいで自分が鼻炎などの
アレルギー反応を催したりするのも、ごく軽微ではあるが、命の不正操作にまつわる
現象であるといえる。そういったわかりやすい汚れから、地球規模の環境破壊による
人間自身の破滅の危機に至るまで、実害を伴うものこそは不可避に汚れてもいる。
偽物の血や死体を用いたホラー映画などで汚れを演出してみたところで、
実害を伴う現象の汚れには遠く及ばないものとなっている。
ただ、汚い部屋でも平気でいられるような人間もまたいるようにして、
実害の伴う現象の汚れにこそ鈍感な人間もまたいる。そのような人間に限って、架空の
ホラー映画あたりには心底恐怖したりもするわけで、それは正常な危機意識を欠いている
がための問題点であり、そのような人間こそは汚れに染まりきった人間であるともいえる。
まともに汚れを汚れだと把握できるうちは、自分自身が汚れてはいない。
もはや汚れを汚れだと認識することもできなくなってしまっているような人間こそは、
自分自身が汚れに染まりきってしまってもいる。そのような人間こそはかえって、
「自分は汚れから遠ざかっている」などとすら勘違いもする。俗世には汚れなど掃いて
捨てるほどあるにもかかわらず、自分の周りに汚れなんて見当たらないなんて思える人間が
いたとしたなら、そんな人間はほぼ間違いなく自分自身が汚れてしまっているのだといえる。
アレルギー反応を催したりするのも、ごく軽微ではあるが、命の不正操作にまつわる
現象であるといえる。そういったわかりやすい汚れから、地球規模の環境破壊による
人間自身の破滅の危機に至るまで、実害を伴うものこそは不可避に汚れてもいる。
偽物の血や死体を用いたホラー映画などで汚れを演出してみたところで、
実害を伴う現象の汚れには遠く及ばないものとなっている。
ただ、汚い部屋でも平気でいられるような人間もまたいるようにして、
実害の伴う現象の汚れにこそ鈍感な人間もまたいる。そのような人間に限って、架空の
ホラー映画あたりには心底恐怖したりもするわけで、それは正常な危機意識を欠いている
がための問題点であり、そのような人間こそは汚れに染まりきった人間であるともいえる。
まともに汚れを汚れだと把握できるうちは、自分自身が汚れてはいない。
もはや汚れを汚れだと認識することもできなくなってしまっているような人間こそは、
自分自身が汚れに染まりきってしまってもいる。そのような人間こそはかえって、
「自分は汚れから遠ざかっている」などとすら勘違いもする。俗世には汚れなど掃いて
捨てるほどあるにもかかわらず、自分の周りに汚れなんて見当たらないなんて思える人間が
いたとしたなら、そんな人間はほぼ間違いなく自分自身が汚れてしまっているのだといえる。
邪教信仰で自分自身が汚れに染まり、汚れを汚れだと認識できなくなるようなこともあるが、
むしろより根本的なのは、カネの濫用で汚れを汚れだと認識できなくなることのほうである。
古代のユダヤ人なども、政商として巨万の富を思うがままに操れることに精神をやられて、
ユダヤ教やキリスト教などの元祖「汚穢認識喪失型邪教」をでっち上げもしたわけで、
市場での投機資金や国家規模の税収のような大金の濫用こそは、自分自身がそうとも
気づかないうちから、人名の不正操作に加担する元凶の最たるものともなっている。
殺傷や窃盗のようなあからさまな犯罪は警戒もしやすいから、その規模もさほどには
ならない。肉食依存や地球規模の環境破壊もまた、未だ不十分とはいえ、それなりに
問題意識が高められつつある。大金の不正な取り回しによる窮乏者の死傷こそは、
未だまともな問題意識が抱かれることもなく野放しのままにされていると同時に、
今の世界における未曾有の規模の大害悪ともなっている。
そのようなことが現代に限った問題でないのは、金融犯罪(主に贋金造り)が
野放しにされていた武帝即位時の前漢帝国で数多の餓死者が発生していたという
「漢書」の記録などからも察せられることである。いくら血肉の汚れを忌んで見たところで、
自分がカネを不正に取り回した挙句に人々を窮死に追いやるという問題に対する忌避感は生じない。
故に、日本列島のような商売が一定以上の規模とはなり得ない狭隘地でもない限りは、
士農工商の位階すらをも徹底することで、悪徳商売の横行を防いで行くようにするのでも
なければ、金融犯罪の蔓延からなる大破綻すらもが免れ得なくなるのである。
むしろより根本的なのは、カネの濫用で汚れを汚れだと認識できなくなることのほうである。
古代のユダヤ人なども、政商として巨万の富を思うがままに操れることに精神をやられて、
ユダヤ教やキリスト教などの元祖「汚穢認識喪失型邪教」をでっち上げもしたわけで、
市場での投機資金や国家規模の税収のような大金の濫用こそは、自分自身がそうとも
気づかないうちから、人名の不正操作に加担する元凶の最たるものともなっている。
殺傷や窃盗のようなあからさまな犯罪は警戒もしやすいから、その規模もさほどには
ならない。肉食依存や地球規模の環境破壊もまた、未だ不十分とはいえ、それなりに
問題意識が高められつつある。大金の不正な取り回しによる窮乏者の死傷こそは、
未だまともな問題意識が抱かれることもなく野放しのままにされていると同時に、
今の世界における未曾有の規模の大害悪ともなっている。
そのようなことが現代に限った問題でないのは、金融犯罪(主に贋金造り)が
野放しにされていた武帝即位時の前漢帝国で数多の餓死者が発生していたという
「漢書」の記録などからも察せられることである。いくら血肉の汚れを忌んで見たところで、
自分がカネを不正に取り回した挙句に人々を窮死に追いやるという問題に対する忌避感は生じない。
故に、日本列島のような商売が一定以上の規模とはなり得ない狭隘地でもない限りは、
士農工商の位階すらをも徹底することで、悪徳商売の横行を防いで行くようにするのでも
なければ、金融犯罪の蔓延からなる大破綻すらもが免れ得なくなるのである。
別に、世界中を見回してみても、現状でそのような教条が一般的に
広められたことがあるわけでもないが、これからは「カネは汚れている」
という風に考えて行くぐらいがちょうどいいのではないかと思う。
別にカネが必ずしも汚れているわけではない。正常に扱えば物流の便利な道具となるのみだが、
多少儲かる商売などが横行しただけでもはや、利益の我田引水を通じての人命の不正操作に
直結してしまうわけだから、カネが極めて汚れやすいものであることだけは間違いがない。
商売人が多少儲けたりすることがあるのならば、もはや天下のゼニもみな少なからず汚れて
しまっているのだといえる。だから、カネは汚れていると考えてもほとんどおかしくはない。
そういった通念が十分に行き渡ったなら、別に身分制度によって商工階級を徹底的な
差別下に置いたりする必要もなくなるだろうが、それもまた難しいことだろうか。
「川沢も汚を納れ、山藪も疾を蔵し、瑾瑜も瑕を匿す。国君も垢を含むは、天の道なり」
「川や沢にも汚水が流れ込むことがあり、山や藪も毒のある生き物を宿し、美しい宝玉もその内に
疵を隠し持っている。国君といえども恥汚れを呑まなければならないことがあるのが天道である。
(仏道帰依で天人五衰を予防することもできはするものの、それは天道とは別物である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・宣公十五年より)
「春秋の稱は微にして顕われ、志にして晦く、婉にして章を成し、 尽にして汚ならず、悪を懲らして善を勧む」
「『春秋経』の筆法は、字数は少ないがその意味は明らかであり、 明確に言うときにも露骨になることを避け、
遠回しに言うときにも筋道を通し、実際のところを直言して事実を曲げず、 勧善懲悪を基調として書かれている。
(この引用は既出。『汚』とは『事実を曲げる』という意味でもあり、事実歪曲甚だしい犯罪聖書も
『汚書』と呼ぶに値するものとなっている。また、事実を曲げることは勧善懲悪にも反している」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・成公十四年より)
広められたことがあるわけでもないが、これからは「カネは汚れている」
という風に考えて行くぐらいがちょうどいいのではないかと思う。
別にカネが必ずしも汚れているわけではない。正常に扱えば物流の便利な道具となるのみだが、
多少儲かる商売などが横行しただけでもはや、利益の我田引水を通じての人命の不正操作に
直結してしまうわけだから、カネが極めて汚れやすいものであることだけは間違いがない。
商売人が多少儲けたりすることがあるのならば、もはや天下のゼニもみな少なからず汚れて
しまっているのだといえる。だから、カネは汚れていると考えてもほとんどおかしくはない。
そういった通念が十分に行き渡ったなら、別に身分制度によって商工階級を徹底的な
差別下に置いたりする必要もなくなるだろうが、それもまた難しいことだろうか。
「川沢も汚を納れ、山藪も疾を蔵し、瑾瑜も瑕を匿す。国君も垢を含むは、天の道なり」
「川や沢にも汚水が流れ込むことがあり、山や藪も毒のある生き物を宿し、美しい宝玉もその内に
疵を隠し持っている。国君といえども恥汚れを呑まなければならないことがあるのが天道である。
(仏道帰依で天人五衰を予防することもできはするものの、それは天道とは別物である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・宣公十五年より)
「春秋の稱は微にして顕われ、志にして晦く、婉にして章を成し、 尽にして汚ならず、悪を懲らして善を勧む」
「『春秋経』の筆法は、字数は少ないがその意味は明らかであり、 明確に言うときにも露骨になることを避け、
遠回しに言うときにも筋道を通し、実際のところを直言して事実を曲げず、 勧善懲悪を基調として書かれている。
(この引用は既出。『汚』とは『事実を曲げる』という意味でもあり、事実歪曲甚だしい犯罪聖書も
『汚書』と呼ぶに値するものとなっている。また、事実を曲げることは勧善懲悪にも反している」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・成公十四年より)
人間は一人では生きられない生き物であり、
なおかつ誰かと共にい続けることもできない生き物である。
親も自然と自分よりも早く死ぬものだし、妻や夫も自分とは別個に死ぬのが普通である。
軍人なら戦死で友と別れるなんてのはありきたりなことだし、他の社会人でも
友や兄弟と死に別れたり生き別れたりすることは決して少ないことではない。それでいて、
人間という生き物はある程度以上そういった相手がいないと成り立たない生き物なのでもある。
仏教で、人間が免れることができないとされる八つの苦しみの中にも「愛別離苦」がある。
愛するものと離別することを苦しまなければならないのは、愛するものと一時は共にあることでこそ
人間や人間社会といったものが成り立つからでもある。夫婦陰陽相和するのでなければ万物の化育も
あり得ない。いつかはまた分かれなければならない夫婦親子が共に家を形作るのでもなければ、人間社会
の最小単位すら成立することがない。故に、人間と愛別離苦の苦しみとは不可分なものなのである。
その苦しみを真理の悟りによって克服して行くのなら、人間として特に問題のあることではない。
昔の正統な仏門で、出家するものが自家から出たなら、それによって家の側が長きの繁栄に与れるともされた。
それは、愛別離苦などの苦しみにかられて家を損なうようなことが、家から出家者を出すことでこそ予防する
ことができたからで、現代人が出家に対して抱いている暗いイメージなどとはかけ離れている側面だといえる。
よくないのは、愛別離苦の苦しみを不実な気休めで紛らわしたりすることである。
実在しない超越神をでっち上げて「永遠にそばにいてくださる」などとし、それで別れの苦しみを紛らわし
たりしたとしたなら、それで家の繁栄を助成するどころか、かえって家を損なうことにすらなってしまう。
なおかつ誰かと共にい続けることもできない生き物である。
親も自然と自分よりも早く死ぬものだし、妻や夫も自分とは別個に死ぬのが普通である。
軍人なら戦死で友と別れるなんてのはありきたりなことだし、他の社会人でも
友や兄弟と死に別れたり生き別れたりすることは決して少ないことではない。それでいて、
人間という生き物はある程度以上そういった相手がいないと成り立たない生き物なのでもある。
仏教で、人間が免れることができないとされる八つの苦しみの中にも「愛別離苦」がある。
愛するものと離別することを苦しまなければならないのは、愛するものと一時は共にあることでこそ
人間や人間社会といったものが成り立つからでもある。夫婦陰陽相和するのでなければ万物の化育も
あり得ない。いつかはまた分かれなければならない夫婦親子が共に家を形作るのでもなければ、人間社会
の最小単位すら成立することがない。故に、人間と愛別離苦の苦しみとは不可分なものなのである。
その苦しみを真理の悟りによって克服して行くのなら、人間として特に問題のあることではない。
昔の正統な仏門で、出家するものが自家から出たなら、それによって家の側が長きの繁栄に与れるともされた。
それは、愛別離苦などの苦しみにかられて家を損なうようなことが、家から出家者を出すことでこそ予防する
ことができたからで、現代人が出家に対して抱いている暗いイメージなどとはかけ離れている側面だといえる。
よくないのは、愛別離苦の苦しみを不実な気休めで紛らわしたりすることである。
実在しない超越神をでっち上げて「永遠にそばにいてくださる」などとし、それで別れの苦しみを紛らわし
たりしたとしたなら、それで家の繁栄を助成するどころか、かえって家を損なうことにすらなってしまう。
実際、そのような気休めで別れの苦しみを紛らわしてきた欧米社会たるや、まともに家系が保たれた試しもない。
せいぜい遺産が莫大である場合などに名を継ぐものが多少続いたりするだけで、家を守るということそれ自体が
貴ばれるということがない。それは、愛する家族が死に別れる苦しみを虚構の超越神への帰依などによって
紛らわし続けること自体に無理があるからで、そのペースで家を守っていく志しなど生じようもないからだ。
いま、社会の最小単位としての家をよく守っていくということが、地球人類社会にとっての急務ともなっている。
個々人ではなく個々の家から尊重して、その厳重な継続に務めていくのでなければ、やりたい放題からなる
人口爆発にも歯止めがかからないから、禁治産措置によって子孫を絶やしたりするのでもない限りは、
家を守っていく心がけを保てる生き方をしていくことが必須となる。そのためには、家の繁栄を約束する
仏教や神道に帰依することは許される一方で、愛別離苦の苦しみを紛らわしながらかえって増幅させてしまう
虚構の超越神への心理的帰依などは排して行かなければならない。「聖書信仰を排すべし」ということは
すでに幾度も述べてきているが、そうせざるを得ない具体的証拠の一つが、以上のような論及ともなっている。
「日昃くの離なり。缶を鼓みて歌わざれば、則ち大耋の嗟きあらん。凶なり」
「太陽も日没には天上から離別するようにして、人の命もまたいつかは寿命でなくなるものである。
その時に酒杯を叩いて唄うぐらいの朗らかさでなければ、八十を過ぎても老衰を嘆くことになる。凶である。
(諸行無常のわきまえがあればこそ、その思い切りも付く。それを妨げたりはすべきでない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・離・九三)
せいぜい遺産が莫大である場合などに名を継ぐものが多少続いたりするだけで、家を守るということそれ自体が
貴ばれるということがない。それは、愛する家族が死に別れる苦しみを虚構の超越神への帰依などによって
紛らわし続けること自体に無理があるからで、そのペースで家を守っていく志しなど生じようもないからだ。
いま、社会の最小単位としての家をよく守っていくということが、地球人類社会にとっての急務ともなっている。
個々人ではなく個々の家から尊重して、その厳重な継続に務めていくのでなければ、やりたい放題からなる
人口爆発にも歯止めがかからないから、禁治産措置によって子孫を絶やしたりするのでもない限りは、
家を守っていく心がけを保てる生き方をしていくことが必須となる。そのためには、家の繁栄を約束する
仏教や神道に帰依することは許される一方で、愛別離苦の苦しみを紛らわしながらかえって増幅させてしまう
虚構の超越神への心理的帰依などは排して行かなければならない。「聖書信仰を排すべし」ということは
すでに幾度も述べてきているが、そうせざるを得ない具体的証拠の一つが、以上のような論及ともなっている。
「日昃くの離なり。缶を鼓みて歌わざれば、則ち大耋の嗟きあらん。凶なり」
「太陽も日没には天上から離別するようにして、人の命もまたいつかは寿命でなくなるものである。
その時に酒杯を叩いて唄うぐらいの朗らかさでなければ、八十を過ぎても老衰を嘆くことになる。凶である。
(諸行無常のわきまえがあればこそ、その思い切りも付く。それを妨げたりはすべきでない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・離・九三)
家から出家者を出すことによる家の繁栄を図るためには、
当然二男三男や分家の人間などを優先的ゆ出家させるようにしなければならない。
本家の長男あたりまで出家させようものなら、本末転倒となる。
そういった便宜を図って行くのであれば、家族主義の神道と
出家主義の仏教もまた共存が可能となって、いい具合となる。
当然二男三男や分家の人間などを優先的ゆ出家させるようにしなければならない。
本家の長男あたりまで出家させようものなら、本末転倒となる。
そういった便宜を図って行くのであれば、家族主義の神道と
出家主義の仏教もまた共存が可能となって、いい具合となる。
人間が本当に苦しみから解放されるのは、それこそ死ぬ時である。
生きるということは基本苦しみの塊であり、その中に多少苦しみの軽減や
楽しみがあるだけのことであるというのが仏教の「一切皆苦」の教えでもある。
悲観ではなく、単なる現実としての一切皆苦という法則を把握して、断悪修善や勧善懲悪による
苦しみの軽減や楽しみを追い求めていくことでこそ、人は最高級の楽しみや苦しまずに与ることができる。
そもそも「生きる」ということ自体が楽しみの塊であるなどと思い込んで、ただ過剰な生を謳歌しようとして放辟邪侈
などに走った場合に、人は楽しみを追い求めているつもりでいながら、より大きな苦しみに苛まれることともなる。
生きるということは基本、死ぬ以上もの苦しみなのだから、ただただ粗大な生を貪ったりしたなら、
自然とより大きな苦しみに苛まれることとなるのである。それよりは、細々としながらも罪のない人生を
送っていくほうがはるかに苦しみの少ない人生を送れるものである。だからといってそんな仙人か坊主みたいな
人生を送るばかりが全てでもなく、勧善懲悪や断悪修善を推進していくことにかけてこそ盛大であるような
生き方をすることでこそ、人として最大級に楽しくて苦しゅうない人生を送ることができるのでもある。
何度もいうが、それを可能とするのが「権力道徳者」としての活動である。
権力道徳者としての活動を活発化すらさせたなら、それによってほぼ必ず純粋な勧善懲悪を推進して行ける。
他の立場、たとえば商売人としての活動を活発化させたからといってそれが勧善懲悪の推進などになることは
ほぼ全くないが、聖王賢臣としての仁政などを推進すらしていったなら、それは自動的に勧善懲悪の推進ともなる。
権力道徳者としての活動以外の活動というものを活発化させていくことも当然、人間には可能であり、
現代人など、その手の活動しかやっていなかったりする。仁政不能の乱世に特有の活動ばかりを好き好んでやっていて、
それらの活動こそは、たとえば江戸時代に賢い殿様が敷いていた善政などよりも遥かに「如実に粗大」であったりする。
生きるということは基本苦しみの塊であり、その中に多少苦しみの軽減や
楽しみがあるだけのことであるというのが仏教の「一切皆苦」の教えでもある。
悲観ではなく、単なる現実としての一切皆苦という法則を把握して、断悪修善や勧善懲悪による
苦しみの軽減や楽しみを追い求めていくことでこそ、人は最高級の楽しみや苦しまずに与ることができる。
そもそも「生きる」ということ自体が楽しみの塊であるなどと思い込んで、ただ過剰な生を謳歌しようとして放辟邪侈
などに走った場合に、人は楽しみを追い求めているつもりでいながら、より大きな苦しみに苛まれることともなる。
生きるということは基本、死ぬ以上もの苦しみなのだから、ただただ粗大な生を貪ったりしたなら、
自然とより大きな苦しみに苛まれることとなるのである。それよりは、細々としながらも罪のない人生を
送っていくほうがはるかに苦しみの少ない人生を送れるものである。だからといってそんな仙人か坊主みたいな
人生を送るばかりが全てでもなく、勧善懲悪や断悪修善を推進していくことにかけてこそ盛大であるような
生き方をすることでこそ、人として最大級に楽しくて苦しゅうない人生を送ることができるのでもある。
何度もいうが、それを可能とするのが「権力道徳者」としての活動である。
権力道徳者としての活動を活発化すらさせたなら、それによってほぼ必ず純粋な勧善懲悪を推進して行ける。
他の立場、たとえば商売人としての活動を活発化させたからといってそれが勧善懲悪の推進などになることは
ほぼ全くないが、聖王賢臣としての仁政などを推進すらしていったなら、それは自動的に勧善懲悪の推進ともなる。
権力道徳者としての活動以外の活動というものを活発化させていくことも当然、人間には可能であり、
現代人など、その手の活動しかやっていなかったりする。仁政不能の乱世に特有の活動ばかりを好き好んでやっていて、
それらの活動こそは、たとえば江戸時代に賢い殿様が敷いていた善政などよりも遥かに「如実に粗大」であったりする。
為政者のやっていることというのは、それこそ「雲上の仕事」であり、庶民にはどうしたって分かりにくい所がある。
それは民主制を敷いている今の諸国でも同じことで、結局のところ政治なんかより、民間企業がやっていること
などのほうが庶民からすれば親しみやすい。親しみやすくて分かりやすいから、その仕事が大きければ、
その大きさも実感しやすい。故に、民間の商売人としての活動などが極大化している今の社会での活動こそは、
権力道徳者が行う盛大な活動などよりも遥かに「如実に粗大」なものともなっている。
「仏の救いは微妙不可思議なものである」とは、他力本願の浄土門ですら肯んじられていることである。
権力道徳者の活動も、庶民にはなかなか図り知りがたい雲上の仕事であればこそ、世の中を丸ごと吉方へと導くような、
純粋な勧善懲悪の事業たりうるのである。逆に民間の商売人としての仕事などは、私利私益を求めることばかりに
専らであるからこそ庶民にも分かりやすいのであり、分かりやすいからといってそれが善美だったりするわけではない。
邪学邪教の流布によってルサンチマンを極大化させられてしまっている現代人の多くは、為政者即悪人というほどもの
固定観念すら持ち合わせてしまっている。特に、封建社会の為政者などは「お山の大将」「過去の遺物」などとしてその
存在価値を顧みようともしない。確かに、封建社会の為政者が権力犯罪をやらかす場合ほど如実に醜悪なことも他に
ないが、それと同時に、封建制に基づく権力道徳の実践こそが、人として最大級の勧善懲悪たり得るのでもある。
民間の商売人としての事業などは、よさげな部分はいかにもよさげに見せびらかせる一方で、悪い部分はいくらでも
隠し通せる。そもそも同じ民間人である大衆などにわざわざお伺いを立てなければならないような身分ではないと、
特に民主主義社会の素封家こそは認められるわけで、為政者による抑圧を解かれた民間の素封家たちは、
それこそ人として最大級の放辟邪侈にまみれた所業をもやってのけ始めたのである。
それは民主制を敷いている今の諸国でも同じことで、結局のところ政治なんかより、民間企業がやっていること
などのほうが庶民からすれば親しみやすい。親しみやすくて分かりやすいから、その仕事が大きければ、
その大きさも実感しやすい。故に、民間の商売人としての活動などが極大化している今の社会での活動こそは、
権力道徳者が行う盛大な活動などよりも遥かに「如実に粗大」なものともなっている。
「仏の救いは微妙不可思議なものである」とは、他力本願の浄土門ですら肯んじられていることである。
権力道徳者の活動も、庶民にはなかなか図り知りがたい雲上の仕事であればこそ、世の中を丸ごと吉方へと導くような、
純粋な勧善懲悪の事業たりうるのである。逆に民間の商売人としての仕事などは、私利私益を求めることばかりに
専らであるからこそ庶民にも分かりやすいのであり、分かりやすいからといってそれが善美だったりするわけではない。
邪学邪教の流布によってルサンチマンを極大化させられてしまっている現代人の多くは、為政者即悪人というほどもの
固定観念すら持ち合わせてしまっている。特に、封建社会の為政者などは「お山の大将」「過去の遺物」などとしてその
存在価値を顧みようともしない。確かに、封建社会の為政者が権力犯罪をやらかす場合ほど如実に醜悪なことも他に
ないが、それと同時に、封建制に基づく権力道徳の実践こそが、人として最大級の勧善懲悪たり得るのでもある。
民間の商売人としての事業などは、よさげな部分はいかにもよさげに見せびらかせる一方で、悪い部分はいくらでも
隠し通せる。そもそも同じ民間人である大衆などにわざわざお伺いを立てなければならないような身分ではないと、
特に民主主義社会の素封家こそは認められるわけで、為政者による抑圧を解かれた民間の素封家たちは、
それこそ人として最大級の放辟邪侈にまみれた所業をもやってのけ始めたのである。
民間の商売人などによる放辟邪侈まみれの事業が、権力道徳者の活動を規模面で上回ることもある。
呂不韋のような政商の活動を大々的に容認していた秦国こそは、それよりはまだ清浄な為政を
執り行っている場合もあった春秋戦国時代の諸国を征服して統一帝国を立ち上げられもした。
政治家の活動は旺盛でも民間人の活動は貧弱である場合よりは、政治家も民間人も
共に活動が旺盛である場合のほうが一時的な国力などを極大化させられもする。しかし、
そのような形での国力の増強はそう長く持つものではなく、秦帝国も短期で瓦解したし、
政財両面の活動が活発である今の資本主義諸国も、少子高齢化などによるどん詰まり化が著しい。
政治家を自分たちにとって都合のいいノミの夫婦の夫状態とさせてまでのやりたい放題に及んでいた
民間の素封家などが、権力道徳者とそのまま共存できたりするわけもない。増税ぐらいで済むなら
まだしも、服装や乗車の制限みたいな封建的差別すらをも講じなければならなくなりもする。
結局、封建制というものを敷かなければならない最大の理由もそういったところにあるのであり、
放辟邪侈まみれの粗大な活動を適正に取り締まっていくことこそは、勧善懲悪の実践ともなるのである。
してみれば、勧善懲悪と放辟邪侈はコインの裏表であり、一方の活動が旺盛であるならば、
もう一方の活動もそれと同じぐらいに活発であり得るということである。春秋諸国や秦帝国が
もたらした国土の荒廃の治癒に取り組んだ漢帝国の事業こそは、秦帝国のそれ並みに盛大たり得もした。
始皇帝が失敗した泰山での封禅も武帝が成功させ、当時までの中国史上では最大級の繁栄をも実現した。
だからこそ、放辟邪侈主体だった時代が勧善懲悪主体の時代に転換するからといって、その活動が
矮小化することなどを危惧したりする必要はない。むしろそれから後の世界においてこそ、健全かつ
最大級の繁栄すらもが約束されているのだから、民間の商売人などが自分たちの都合に合わせて「世界が
暗黒の時代に突入する」みたいな触れ回りをしていたりしたとしても、決してそれに耳を貸すべきではない。
呂不韋のような政商の活動を大々的に容認していた秦国こそは、それよりはまだ清浄な為政を
執り行っている場合もあった春秋戦国時代の諸国を征服して統一帝国を立ち上げられもした。
政治家の活動は旺盛でも民間人の活動は貧弱である場合よりは、政治家も民間人も
共に活動が旺盛である場合のほうが一時的な国力などを極大化させられもする。しかし、
そのような形での国力の増強はそう長く持つものではなく、秦帝国も短期で瓦解したし、
政財両面の活動が活発である今の資本主義諸国も、少子高齢化などによるどん詰まり化が著しい。
政治家を自分たちにとって都合のいいノミの夫婦の夫状態とさせてまでのやりたい放題に及んでいた
民間の素封家などが、権力道徳者とそのまま共存できたりするわけもない。増税ぐらいで済むなら
まだしも、服装や乗車の制限みたいな封建的差別すらをも講じなければならなくなりもする。
結局、封建制というものを敷かなければならない最大の理由もそういったところにあるのであり、
放辟邪侈まみれの粗大な活動を適正に取り締まっていくことこそは、勧善懲悪の実践ともなるのである。
してみれば、勧善懲悪と放辟邪侈はコインの裏表であり、一方の活動が旺盛であるならば、
もう一方の活動もそれと同じぐらいに活発であり得るということである。春秋諸国や秦帝国が
もたらした国土の荒廃の治癒に取り組んだ漢帝国の事業こそは、秦帝国のそれ並みに盛大たり得もした。
始皇帝が失敗した泰山での封禅も武帝が成功させ、当時までの中国史上では最大級の繁栄をも実現した。
だからこそ、放辟邪侈主体だった時代が勧善懲悪主体の時代に転換するからといって、その活動が
矮小化することなどを危惧したりする必要はない。むしろそれから後の世界においてこそ、健全かつ
最大級の繁栄すらもが約束されているのだから、民間の商売人などが自分たちの都合に合わせて「世界が
暗黒の時代に突入する」みたいな触れ回りをしていたりしたとしても、決してそれに耳を貸すべきではない。
「不仁、不智、無礼、無義は、人に役せらるものなり。人に役せらるものにして役を為すを恥ずるは、由お
弓人にして弓を為るを恥じ、矢人にして矢を為るを恥ずるが如し。之れを恥ずるなら、仁と為るに如くは莫し」
「不仁や無知や無礼や不義でいるものは、人に夫役を課せられる身分であるのが当たり前である。召使の身分
でありながら召使であることを恥じるのは、弓職人が弓を作るのを恥じ、矢職人が矢を作るのを恥じるのと全く
同じことだ。それが恥であるというのなら、仁者となる他はない。(不仁者は永遠に召使であり続ける他はない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句上・七より)
弓人にして弓を為るを恥じ、矢人にして矢を為るを恥ずるが如し。之れを恥ずるなら、仁と為るに如くは莫し」
「不仁や無知や無礼や不義でいるものは、人に夫役を課せられる身分であるのが当たり前である。召使の身分
でありながら召使であることを恥じるのは、弓職人が弓を作るのを恥じ、矢職人が矢を作るのを恥じるのと全く
同じことだ。それが恥であるというのなら、仁者となる他はない。(不仁者は永遠に召使であり続ける他はない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句上・七より)
大道が廃れ、さらには仁義までもが廃れてから、すでに久しい。
つまり、真理に適うことも、道理を守ることも、共に廃れきってしまっているが現代という時代である。
その証拠に、儒者として飯を食っていくことも、自力作善の仏者として食っていくことも覚束ない。
大学の中国哲学科や仏教哲学科なども単なる知識を学び教えるというばかりのこと止まりで、
最高級の学者といえどもその知識内容を忠実に実践したりすることはない。せいぜい
自分の知識を我流の筆法で披露した書籍を販促して儲けたりすることがあるぐらいである。
個人的に儒学や仏教の教えを好むようなことがあっても、それに忠実に従うなどということはできない。
渋沢栄一なぞも、本来は権力道徳のための倫理である儒学上の倫理体系を、商売哲学として相当に
曲解することで初めて、近代における実践対象としていた。それは当然、儒学の忠実な実践などには
なっていないわけで、かえって人々に儒学への偏見を抱かせる原因ばかりになったのである。
ただ、それらも現状、大いに肯んじる他はない現実である。
「そんなことはない、これほどもの乱世であっても、それなりに儒学や仏教を実践して行ける余地はある」
などという綺麗ごとを言うことはできても、実際そんなことはない。他力本願の念仏や曲解儒学の実践なら
ともかく、自力作善の本格仏教や、道徳統治を本分とする本物の儒学の実践までもが覚束くものではない。
だからこそ、今のような破滅寸前の乱世の責任を、儒学や仏教に押し付けたりすることもまた全くの不可能である。
儒学が中国発祥の学問であるからといって、今の中国を敵対視してみたりしたところで、とっくの昔に
儒学も中国本土からその姿を消してしまっている。文化大革命などを通じて古来の伝統文化の継承が徹底的に
絶やされて、かろうじて歴史的価値のある寺院建築の保全などが存続している程度でしかなくなって
しまっているわけだから、今の中国と戦争をして侵略対象などにしてみたところで、それで
儒学や仏教文化がより損なわれるなどということもほとんど皆無に等しい。
つまり、真理に適うことも、道理を守ることも、共に廃れきってしまっているが現代という時代である。
その証拠に、儒者として飯を食っていくことも、自力作善の仏者として食っていくことも覚束ない。
大学の中国哲学科や仏教哲学科なども単なる知識を学び教えるというばかりのこと止まりで、
最高級の学者といえどもその知識内容を忠実に実践したりすることはない。せいぜい
自分の知識を我流の筆法で披露した書籍を販促して儲けたりすることがあるぐらいである。
個人的に儒学や仏教の教えを好むようなことがあっても、それに忠実に従うなどということはできない。
渋沢栄一なぞも、本来は権力道徳のための倫理である儒学上の倫理体系を、商売哲学として相当に
曲解することで初めて、近代における実践対象としていた。それは当然、儒学の忠実な実践などには
なっていないわけで、かえって人々に儒学への偏見を抱かせる原因ばかりになったのである。
ただ、それらも現状、大いに肯んじる他はない現実である。
「そんなことはない、これほどもの乱世であっても、それなりに儒学や仏教を実践して行ける余地はある」
などという綺麗ごとを言うことはできても、実際そんなことはない。他力本願の念仏や曲解儒学の実践なら
ともかく、自力作善の本格仏教や、道徳統治を本分とする本物の儒学の実践までもが覚束くものではない。
だからこそ、今のような破滅寸前の乱世の責任を、儒学や仏教に押し付けたりすることもまた全くの不可能である。
儒学が中国発祥の学問であるからといって、今の中国を敵対視してみたりしたところで、とっくの昔に
儒学も中国本土からその姿を消してしまっている。文化大革命などを通じて古来の伝統文化の継承が徹底的に
絶やされて、かろうじて歴史的価値のある寺院建築の保全などが存続している程度でしかなくなって
しまっているわけだから、今の中国と戦争をして侵略対象などにしてみたところで、それで
儒学や仏教文化がより損なわれるなどということもほとんど皆無に等しい。
俺もまた、別に現状で儒学を実践できているわけでもない。ただ文面の知識を学んでいるだけの匹夫の
身分であり、そんな相手を迫害対象にしてみたりしたところで、儒学や仏教のほうは痛くもかゆくもない。
真理を把捉した教学の代表としては仏教を、道理を把捉した学問の代表としては儒学をここでは主に挙げて
いるけども、真理や道理を忠実に把捉しているような教学はいずれも、その実践が覚束なくなってしまっている。
真理や道理にたがう邪教邪学が最大級に幅を利かせることで、善良な教学はその立場を追われてしまっているのが現状
であるからこそ、今の世界を破滅に陥れている邪教邪学が、他の教学などにその責任を押し付けることもできないのである。
自分たちの教えにたがう者であるからこそ、自分たち以上の破滅に陥れられる相手などというのを、
この地球上のどこにも見つけることができない。自分たちこそがそのような人間を現世から絶やして
しまったのだから、そうである責任を自分たち以外の誰かに押し付けたりすることもまた、全くの不能である。
「他人がもたらした禍いは、たとえ天からの禍いであっても多少の逃れようがあるが、
自らがもたらした禍いは、それほどの逃れようすらない」とは「書経」にもあるとおり。
そうである如実なるケースの一つが、現代における邪教邪学の自業自得の破滅ともなっている。
身分であり、そんな相手を迫害対象にしてみたりしたところで、儒学や仏教のほうは痛くもかゆくもない。
真理を把捉した教学の代表としては仏教を、道理を把捉した学問の代表としては儒学をここでは主に挙げて
いるけども、真理や道理を忠実に把捉しているような教学はいずれも、その実践が覚束なくなってしまっている。
真理や道理にたがう邪教邪学が最大級に幅を利かせることで、善良な教学はその立場を追われてしまっているのが現状
であるからこそ、今の世界を破滅に陥れている邪教邪学が、他の教学などにその責任を押し付けることもできないのである。
自分たちの教えにたがう者であるからこそ、自分たち以上の破滅に陥れられる相手などというのを、
この地球上のどこにも見つけることができない。自分たちこそがそのような人間を現世から絶やして
しまったのだから、そうである責任を自分たち以外の誰かに押し付けたりすることもまた、全くの不能である。
「他人がもたらした禍いは、たとえ天からの禍いであっても多少の逃れようがあるが、
自らがもたらした禍いは、それほどの逃れようすらない」とは「書経」にもあるとおり。
そうである如実なるケースの一つが、現代における邪教邪学の自業自得の破滅ともなっている。
「君仁なれば不仁なるもの莫く、君義なれば不義なるもの莫し」
「主君に仁があれば不仁なものもなく、主君に義があれば不義を働くものもない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句下・五)
「仲子は不義にして之れに斉国を与うるも受けること弗からん、人皆な之れを信ずるも、
是れ箪食豆羹を舎つるの義なり。人の親戚、君臣、上下を亡するより大なるは莫し」
「斉の陳仲子はたとえ斉一国をくれるとしてもそこに不義があればもらわないほど潔癖だという。
みなそれを信じて仲子を称えているが、私に言わせれば、そんなのはちょっとした食い物の贈り物を
不義だからといって断る程度のものでしかない。親戚君臣上下の序列を乱すことの不義には遠く及ばない。
(上の引用と合わせて。主君に不義を働かせて国中不義まみれにしたり、君臣上下の序列を乱して民に勝手に
不義を働かせたりすること両方ともが大罪である。犯罪聖書の神は必ずいずれかの罪を犯している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・三四より)
「主君に仁があれば不仁なものもなく、主君に義があれば不義を働くものもない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句下・五)
「仲子は不義にして之れに斉国を与うるも受けること弗からん、人皆な之れを信ずるも、
是れ箪食豆羹を舎つるの義なり。人の親戚、君臣、上下を亡するより大なるは莫し」
「斉の陳仲子はたとえ斉一国をくれるとしてもそこに不義があればもらわないほど潔癖だという。
みなそれを信じて仲子を称えているが、私に言わせれば、そんなのはちょっとした食い物の贈り物を
不義だからといって断る程度のものでしかない。親戚君臣上下の序列を乱すことの不義には遠く及ばない。
(上の引用と合わせて。主君に不義を働かせて国中不義まみれにしたり、君臣上下の序列を乱して民に勝手に
不義を働かせたりすること両方ともが大罪である。犯罪聖書の神は必ずいずれかの罪を犯している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・三四より)
どんな形であれ、この世で役に立つ言葉は、この世の内側の言葉である。
この世との密接な関係性によってのみその存在意義を帯びる言葉である。
そのような限定的な有用性を超越しているのが他でもない仏説であり、この世での有用性などに
飽き足りていないからこそ、その意味も俗人にはなかなか計り知りがたいものとなっている。
そういった分かりにくさは儒説にはないし、犯罪聖書の言葉にもない。
犯罪聖書の場合、極度の精神薄弱者やサイコパス患者が落書きした言葉であるために、
構文などが稚拙なせいで分かりにくいということはあるが、書いてある内容が難解だから
分かりにくいなどということはない。あくまでもこの世の内側の範疇に止まる意味の言葉であり、
そのセット数も厳密に四書五経以内の四書五経以下なものに止まっている。
それでいて、ただの俗人が適当に述べる言葉などとは決定的に違う点が、四書五経の言葉にも
犯罪聖書の言葉にもある。四書五経の言葉が俗人の戯言などと決定的に違うのは、易の法則に
即した陽唱陰和を念頭にした言葉こそを集成している点である。しかもそれを俗世の言葉で簡潔に
述べているものだから、それが「勧善懲悪」の理念に適った言葉であるとも考えられるのである。
犯罪聖書の言葉はその逆で、易の法則でいえば陽唱陰和の逆を行く言葉の集成となっている。
それは別に犯罪聖書の編纂者がそれを狙ったからではなく、政商犯などとしての自分たちの
素行の悪さに即してものを書こうとした結果、自然とそうなってしまったのであり、
自分たちでも知らず知らずのうちから、悪逆非道の黄金比こそを体系化てしまったのである。
四書五経の言葉と犯罪聖書の言葉のうちで、どちらのほうがより形而上的かといえば、
それもむしろ四書五経のほうである。別に儒説が形而上的な物言いなどを心がけているわけでは
ないが、精一杯この世界のすべてを捉えきろうとしていることは間違いがない。そのために、
易の法則の如きこの世界のすべてを包括する法則の把握にまで及んでいる。犯罪聖書の著者には
そんな心がけはなく、この世界の内側のごく一部の法則の把握までにしか心がけが及んでいない。
この世との密接な関係性によってのみその存在意義を帯びる言葉である。
そのような限定的な有用性を超越しているのが他でもない仏説であり、この世での有用性などに
飽き足りていないからこそ、その意味も俗人にはなかなか計り知りがたいものとなっている。
そういった分かりにくさは儒説にはないし、犯罪聖書の言葉にもない。
犯罪聖書の場合、極度の精神薄弱者やサイコパス患者が落書きした言葉であるために、
構文などが稚拙なせいで分かりにくいということはあるが、書いてある内容が難解だから
分かりにくいなどということはない。あくまでもこの世の内側の範疇に止まる意味の言葉であり、
そのセット数も厳密に四書五経以内の四書五経以下なものに止まっている。
それでいて、ただの俗人が適当に述べる言葉などとは決定的に違う点が、四書五経の言葉にも
犯罪聖書の言葉にもある。四書五経の言葉が俗人の戯言などと決定的に違うのは、易の法則に
即した陽唱陰和を念頭にした言葉こそを集成している点である。しかもそれを俗世の言葉で簡潔に
述べているものだから、それが「勧善懲悪」の理念に適った言葉であるとも考えられるのである。
犯罪聖書の言葉はその逆で、易の法則でいえば陽唱陰和の逆を行く言葉の集成となっている。
それは別に犯罪聖書の編纂者がそれを狙ったからではなく、政商犯などとしての自分たちの
素行の悪さに即してものを書こうとした結果、自然とそうなってしまったのであり、
自分たちでも知らず知らずのうちから、悪逆非道の黄金比こそを体系化てしまったのである。
四書五経の言葉と犯罪聖書の言葉のうちで、どちらのほうがより形而上的かといえば、
それもむしろ四書五経のほうである。別に儒説が形而上的な物言いなどを心がけているわけでは
ないが、精一杯この世界のすべてを捉えきろうとしていることは間違いがない。そのために、
易の法則の如きこの世界のすべてを包括する法則の把握にまで及んでいる。犯罪聖書の著者には
そんな心がけはなく、この世界の内側のごく一部の法則の把握までにしか心がけが及んでいない。
故にこそ、いくら卑俗な言葉の集成であるにしても、
四書五経の言葉のほうが比較的形而上に近い一方、どんなに思わせぶりでも、
犯罪聖書の言葉のほうが比較的形而上から遠いものだといえる。
四書五経のような模範的な儒説を会得できたものこそは、この世界の内側にいながら、
この世界の全てを知る。世界の全てを知るがゆえに、自分自身が形而上的な存在とすらなれる。
犯罪聖書の言葉はその逆で、この世界の内側の、さらにごく一部の矮小な領域に
のみ信者たちを閉じ込めてしまうものである。そのせいで信者たちは、自分たちが
形而上的な存在であることを禁止される一方、自分たちがごく矮小な領域に閉じ込め
られたことを以ってして、「形而上への昇天」だなどと倒錯してしまいもするのである。
儒術の体得は結局、この世界の法則を超越する真理の法(仏法)に合致しようとする仏教の修養
にも漸近する。儒学が専門とするのはあくまでこの世界の内側の問題であるが、この世界の全てを
捉えきるほどにも儒学を修め尽くせたなら、もはやその人間自身の境地は形而上にあるも同然である、
故にこそ、始めからそれを狙っている仏門の境地にも、図らずとも合致することとなるのである。
(実際には、仏教の修得が儒学の修養を助成するようなことのほうが多いようである)
この世界の内側の、さらにごく一部の矮小な領域の法則ばかりに拘泥して、それを
形而上への昇天だなどと倒錯する件の邪教への耽溺は、儒学の修養と仏教の修養
いずれとも相容れないものである。形而下の全てを知って形而上の境地に赴くことも、
始めから形而上の境地を目指すことも、いずれをも不能と化してしまうものである。
そんな所ばかりに自分たちが陥ってしまうことほど、もったいないことも他にないのである。
「天地の害を除去す、之れを義と謂う」
「天地に跋扈する害、天地を害するものを除去して行くことこそを『義』という。
(所詮天地が滅んだりすることはないわけだが、天地が害されて懸隔状態となり、万物が利を損なう
ようなことはいくらでもある。そのようになるのを黙認したり、助長したりすることこそは不義である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・経解第二十六より)
四書五経の言葉のほうが比較的形而上に近い一方、どんなに思わせぶりでも、
犯罪聖書の言葉のほうが比較的形而上から遠いものだといえる。
四書五経のような模範的な儒説を会得できたものこそは、この世界の内側にいながら、
この世界の全てを知る。世界の全てを知るがゆえに、自分自身が形而上的な存在とすらなれる。
犯罪聖書の言葉はその逆で、この世界の内側の、さらにごく一部の矮小な領域に
のみ信者たちを閉じ込めてしまうものである。そのせいで信者たちは、自分たちが
形而上的な存在であることを禁止される一方、自分たちがごく矮小な領域に閉じ込め
られたことを以ってして、「形而上への昇天」だなどと倒錯してしまいもするのである。
儒術の体得は結局、この世界の法則を超越する真理の法(仏法)に合致しようとする仏教の修養
にも漸近する。儒学が専門とするのはあくまでこの世界の内側の問題であるが、この世界の全てを
捉えきるほどにも儒学を修め尽くせたなら、もはやその人間自身の境地は形而上にあるも同然である、
故にこそ、始めからそれを狙っている仏門の境地にも、図らずとも合致することとなるのである。
(実際には、仏教の修得が儒学の修養を助成するようなことのほうが多いようである)
この世界の内側の、さらにごく一部の矮小な領域の法則ばかりに拘泥して、それを
形而上への昇天だなどと倒錯する件の邪教への耽溺は、儒学の修養と仏教の修養
いずれとも相容れないものである。形而下の全てを知って形而上の境地に赴くことも、
始めから形而上の境地を目指すことも、いずれをも不能と化してしまうものである。
そんな所ばかりに自分たちが陥ってしまうことほど、もったいないことも他にないのである。
「天地の害を除去す、之れを義と謂う」
「天地に跋扈する害、天地を害するものを除去して行くことこそを『義』という。
(所詮天地が滅んだりすることはないわけだが、天地が害されて懸隔状態となり、万物が利を損なう
ようなことはいくらでもある。そのようになるのを黙認したり、助長したりすることこそは不義である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・経解第二十六より)
己れの利得が道義に適っているか否かを、仁者はあくまで自分自身が判断する。
その判断基準は「公益を害していないか否か」であり、害しているような
場合には不正利得とみなして、自らが受けたりすることも拒む。
公益を害しているか否かということが、普遍的な判断材料によって判別することが難しいから、
「仁」という理念も漠然としている所がある。なぜ普遍的な判断材料に乏しいかといって、
それは、商売人なり何なりが、私利私益の追求をあたかも公益寄与であるかのように
見せかける手段にも枚挙に暇がないからである。本当はただ私腹を肥やしたいだけであり、
実際に、世の中に利益以上の損害をもたらすことで不当な利得をかすめたりもするわけだが、
そうであることがあからさまだと凶賊もいいとこだから、そうであることを開き直っている
わけでもないような商売人などの場合、手を変え品を変えしての我田引水の隠蔽にも務めるのである。
その手段は、日に日に進化して行く。かつては黙認されたりすることがあった贋金作りも、
今は公然では厳禁とされている。だからといって悪徳商人などによるあぶく銭の膨らましが
完全に禁じられていたりするのではなく、株式市場での実態に沿わない景況の釣り上げだとか、
一部の富豪が各国中央銀行を私物化しての紙幣増刷の身勝手な操作だとかまでもが企てられている。
要は、贋金作りの手段が巧妙化したというばかりのことであり、事態はむしろ深刻化すらしてしまっている。
そういった現状において仁政を尽くすというのであれば、ただ贋金作りを禁止するだけで済んでいた
かつてのままの取り締まり手段などではとうてい済むはずもない。悪徳金融の犯行が巧妙化して
しまったぶんだけ、取り締まりの手法にも手管を尽くさねばならない。なればこそ、それを試みて
いくための「仁」という理念もまた、漠然とした範疇にとどめられておく必要があるのである。
その判断基準は「公益を害していないか否か」であり、害しているような
場合には不正利得とみなして、自らが受けたりすることも拒む。
公益を害しているか否かということが、普遍的な判断材料によって判別することが難しいから、
「仁」という理念も漠然としている所がある。なぜ普遍的な判断材料に乏しいかといって、
それは、商売人なり何なりが、私利私益の追求をあたかも公益寄与であるかのように
見せかける手段にも枚挙に暇がないからである。本当はただ私腹を肥やしたいだけであり、
実際に、世の中に利益以上の損害をもたらすことで不当な利得をかすめたりもするわけだが、
そうであることがあからさまだと凶賊もいいとこだから、そうであることを開き直っている
わけでもないような商売人などの場合、手を変え品を変えしての我田引水の隠蔽にも務めるのである。
その手段は、日に日に進化して行く。かつては黙認されたりすることがあった贋金作りも、
今は公然では厳禁とされている。だからといって悪徳商人などによるあぶく銭の膨らましが
完全に禁じられていたりするのではなく、株式市場での実態に沿わない景況の釣り上げだとか、
一部の富豪が各国中央銀行を私物化しての紙幣増刷の身勝手な操作だとかまでもが企てられている。
要は、贋金作りの手段が巧妙化したというばかりのことであり、事態はむしろ深刻化すらしてしまっている。
そういった現状において仁政を尽くすというのであれば、ただ贋金作りを禁止するだけで済んでいた
かつてのままの取り締まり手段などではとうてい済むはずもない。悪徳金融の犯行が巧妙化して
しまったぶんだけ、取り締まりの手法にも手管を尽くさねばならない。なればこそ、それを試みて
いくための「仁」という理念もまた、漠然とした範疇にとどめられておく必要があるのである。
とはいえ、仁という理念を実践して行くために適切となる手段として、現代でも普遍的に
通用する古来からの儒説というものもまたやはりある。それが、それぞれの国家の体制をよく
整えて、国益をよく尊重して行くということである。そのために必要なのは、一国や二国ばかりの
国益が偏重されることではなく、天下全土の国家の権益が相応に守られて行く必要がある。
今も、公私織り交ぜた悪徳外交家(縦横家)が多数暗躍している時代であり、それらの人間によって、
一国や同盟国の利益すら守られればそれでいいというような偏見の流布までもが企てられている時代である。
それはむしろあらゆる国家の長期的な国益を損なうと共に、仁義道徳に反する狭隘に過ぎた見識でもある
のだから、そんな讒言に囚われることなく、天下国家の公益というものを第一に考えて行かなければならない。
これもまた、実際に企図していくとなると、画一的な手法ばかりに囚われていてはならない所がある。
それもやはり、悪徳外交家による国益横領の手段が昔以上に巧妙化したりしているからで、戦時中は
嘘八百を並べ立てる説客などとしても活躍していた儒者の叔孫通ぐらいの機転を利かせるのでなければ、
縦横家の権謀術数にもとうてい対抗しきれるものではない。もちろん縦横家や悪徳商人の暗躍が絶やされて
治世が確立されて後には、これまた叔孫通のような礼楽統治の復興にも務めて行けばいいわけで、仁政の
ための手段というものは乱世においてこそ不定なものとなり、治世においては定まるものであるのだといえる。
「仁を里とするを美と為す。択んで仁に処らずんば、焉んぞ知なることを得ん」
「仁を自らの居場所とすることこそは善美なことである。自分から選んで仁に居ようとするのでなければ、
どうして知者であるなどということが言えようか。(仁なることを強要する他者など居ないし、また
居てはならない。強制されて仁となるようでは、仁義礼智>信という五条の徳の序列にももとるから)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——里仁第四・一より)
通用する古来からの儒説というものもまたやはりある。それが、それぞれの国家の体制をよく
整えて、国益をよく尊重して行くということである。そのために必要なのは、一国や二国ばかりの
国益が偏重されることではなく、天下全土の国家の権益が相応に守られて行く必要がある。
今も、公私織り交ぜた悪徳外交家(縦横家)が多数暗躍している時代であり、それらの人間によって、
一国や同盟国の利益すら守られればそれでいいというような偏見の流布までもが企てられている時代である。
それはむしろあらゆる国家の長期的な国益を損なうと共に、仁義道徳に反する狭隘に過ぎた見識でもある
のだから、そんな讒言に囚われることなく、天下国家の公益というものを第一に考えて行かなければならない。
これもまた、実際に企図していくとなると、画一的な手法ばかりに囚われていてはならない所がある。
それもやはり、悪徳外交家による国益横領の手段が昔以上に巧妙化したりしているからで、戦時中は
嘘八百を並べ立てる説客などとしても活躍していた儒者の叔孫通ぐらいの機転を利かせるのでなければ、
縦横家の権謀術数にもとうてい対抗しきれるものではない。もちろん縦横家や悪徳商人の暗躍が絶やされて
治世が確立されて後には、これまた叔孫通のような礼楽統治の復興にも務めて行けばいいわけで、仁政の
ための手段というものは乱世においてこそ不定なものとなり、治世においては定まるものであるのだといえる。
「仁を里とするを美と為す。択んで仁に処らずんば、焉んぞ知なることを得ん」
「仁を自らの居場所とすることこそは善美なことである。自分から選んで仁に居ようとするのでなければ、
どうして知者であるなどということが言えようか。(仁なることを強要する他者など居ないし、また
居てはならない。強制されて仁となるようでは、仁義礼智>信という五条の徳の序列にももとるから)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——里仁第四・一より)
信仰は情念のほとばしりである。
何を信じるのであれそれは共通していて、その情念こそを正信によって善用することもできれば、
邪信によって悪用することもできる。全く知性を欠いた情念が正信に踏み止まれるか邪信に
陥るかは不定なことだから、まずは十分な分別知によって正信と邪信を区別できるものが
社会的に後者を排して前者を推奨するなどして、たとえ妄信にしか耽っていられないような
人間であっても自然と正信を選択できるような風潮を盛り立てて行ってやる必要がある。
キリシタンや日蓮カルトが排されて、最低でも念仏信仰ぐらいに踏み止まっていられる体制が
敷かれていた頃の日本などはまさにそのようだった。みんながやってる当たり前なものとしての
念仏唱名が無知な百姓あたりにまで行き渡り、さして善行は為せずとも、最悪の悪行にまでは
走らないでいられる程度の正信による「結界」が日本中に張り巡らされていた。
キリシタンが解禁された明治以降、さらにはマッカーサー憲法で「信教の自由」が謳われて、
カルト教団でも宗教法人法による税制優遇が受けられるようになった敗戦後などには、誰かが
正信と邪信をより分けて、邪信を排して正信を奨めておいてやるなんていうことは不可能となった。
正信を促す正統な信教こそは泰然として、無闇な布教などにも及ばないでいる一方、邪信を促すカルト
こそは、信者獲得による儲けのために必死で布教を試みているものだから、特に目に付く宗教といえば
カルトばかりとなって、そのせいで宗教全般への嫌悪感が日本人に植え付けられることともなったのだった。
誰しもが信仰なんか抜きにして、己れの知恵によってまともな生活や社会活動を営めるというのなら、
全くそれでいいのである。しかし残念ながら、そこまで誰しもが賢良方正であるほど世の中という
ものもできていないものだから、己れの知恵だけでは生きていくこともままならないような愚人を
精神面から統御してやるための手段として、信教が有効となる場合がある。科学至上主義の時代に
未だ宗教なんてものが残存していることが不可解に思われたりもするが、そう思えてしまう
ような人間は、世の中のダメな部分に対する配慮が未だ足りていないのである。
何を信じるのであれそれは共通していて、その情念こそを正信によって善用することもできれば、
邪信によって悪用することもできる。全く知性を欠いた情念が正信に踏み止まれるか邪信に
陥るかは不定なことだから、まずは十分な分別知によって正信と邪信を区別できるものが
社会的に後者を排して前者を推奨するなどして、たとえ妄信にしか耽っていられないような
人間であっても自然と正信を選択できるような風潮を盛り立てて行ってやる必要がある。
キリシタンや日蓮カルトが排されて、最低でも念仏信仰ぐらいに踏み止まっていられる体制が
敷かれていた頃の日本などはまさにそのようだった。みんながやってる当たり前なものとしての
念仏唱名が無知な百姓あたりにまで行き渡り、さして善行は為せずとも、最悪の悪行にまでは
走らないでいられる程度の正信による「結界」が日本中に張り巡らされていた。
キリシタンが解禁された明治以降、さらにはマッカーサー憲法で「信教の自由」が謳われて、
カルト教団でも宗教法人法による税制優遇が受けられるようになった敗戦後などには、誰かが
正信と邪信をより分けて、邪信を排して正信を奨めておいてやるなんていうことは不可能となった。
正信を促す正統な信教こそは泰然として、無闇な布教などにも及ばないでいる一方、邪信を促すカルト
こそは、信者獲得による儲けのために必死で布教を試みているものだから、特に目に付く宗教といえば
カルトばかりとなって、そのせいで宗教全般への嫌悪感が日本人に植え付けられることともなったのだった。
誰しもが信仰なんか抜きにして、己れの知恵によってまともな生活や社会活動を営めるというのなら、
全くそれでいいのである。しかし残念ながら、そこまで誰しもが賢良方正であるほど世の中という
ものもできていないものだから、己れの知恵だけでは生きていくこともままならないような愚人を
精神面から統御してやるための手段として、信教が有効となる場合がある。科学至上主義の時代に
未だ宗教なんてものが残存していることが不可解に思われたりもするが、そう思えてしまう
ような人間は、世の中のダメな部分に対する配慮が未だ足りていないのである。
宗教なんて、なくて済むならそれに越したことはない。ただ、どうしても必要というのなら、
正信を促すまともな信教に限るべきだ。どんな宗教でも信じることは自由、むしろ邪な宗教こそを
信じてしまえなんていうのなら、本当に宗教保護なんか一切取り去ってしまったほうがマシである。
信仰にそれなりの統制が効かされていた頃の日本でも、朝廷や幕府からの手厚い庇護を受けていた
仏門宗派(天台真言禅など)と、ほとんど民間からの支援だけで成り立っていた宗派(一向宗や日蓮宗)
との両方があった。信仰を禁じる・禁じないなんてのは極端な話で、禁教まで施される必要があるような
信教はごくごく限られている。禁教まではされない信教のうちでも、権力者からの手厚い庇護を受ける
宗門と、庇護を受けられない宗門とを分けたりすべきなのだから、禁教すべき邪教はさっさと禁教して、
さらにその先、保護すべき秀教と保護まではすべきでない凡教との選別へと早急に向かうべきである。
宗教なんて世の中の必要悪でしかないからこそ、そうするのである。まずは、宗教というジャンル
に対する無駄な憧憬を軒並み排すべきである。そうしたなら、信仰なんてそれなりの統制を受けて当然、
信教の自由なんて非常識極まりないことだとも自然と思えるはずである。そういう風に考えられる人間が
世の中の大多数となり、権力機構には必ずその程度の達観の持ち主が従事するようになることを心がける
べきである。宗教というものを排することまではできなくとも、それぐらいのことは目指すべきである。
「信を惇くし義を明らかにし、徳を崇び功に報ずれば、垂拱して天下治まる」
「信心を篤くして道義を明らかにし、仁徳を貴んで功業にも相応の報償を施せば、
指一つ動かさずとも天下はよく治まる。(正信は戦いを収めるものである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・武成より)
正信を促すまともな信教に限るべきだ。どんな宗教でも信じることは自由、むしろ邪な宗教こそを
信じてしまえなんていうのなら、本当に宗教保護なんか一切取り去ってしまったほうがマシである。
信仰にそれなりの統制が効かされていた頃の日本でも、朝廷や幕府からの手厚い庇護を受けていた
仏門宗派(天台真言禅など)と、ほとんど民間からの支援だけで成り立っていた宗派(一向宗や日蓮宗)
との両方があった。信仰を禁じる・禁じないなんてのは極端な話で、禁教まで施される必要があるような
信教はごくごく限られている。禁教まではされない信教のうちでも、権力者からの手厚い庇護を受ける
宗門と、庇護を受けられない宗門とを分けたりすべきなのだから、禁教すべき邪教はさっさと禁教して、
さらにその先、保護すべき秀教と保護まではすべきでない凡教との選別へと早急に向かうべきである。
宗教なんて世の中の必要悪でしかないからこそ、そうするのである。まずは、宗教というジャンル
に対する無駄な憧憬を軒並み排すべきである。そうしたなら、信仰なんてそれなりの統制を受けて当然、
信教の自由なんて非常識極まりないことだとも自然と思えるはずである。そういう風に考えられる人間が
世の中の大多数となり、権力機構には必ずその程度の達観の持ち主が従事するようになることを心がける
べきである。宗教というものを排することまではできなくとも、それぐらいのことは目指すべきである。
「信を惇くし義を明らかにし、徳を崇び功に報ずれば、垂拱して天下治まる」
「信心を篤くして道義を明らかにし、仁徳を貴んで功業にも相応の報償を施せば、
指一つ動かさずとも天下はよく治まる。(正信は戦いを収めるものである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・武成より)
麻雀は哲学だ、とか
商売は哲学だ、とか
哲学のての字も知らないような俗物がよく嘯いてるでしょ。しかし頭は悪いにしてもされはそれである意味正しいんですね。どういうことかと言うと、
そら何ごとであれ一生懸命やれば古典哲学的あるいは形示上学的な世界を垣間見ることはあるでしょう。
儒教をやれば真理に近づくなんて論法も全く同じですよ。
真理を求めるのであれば儒教から攻める必要性はないし、それなら正面切ってそれを求める宗教の方が好感がもてるし、そのやり方を俗人が聖人のふりをしてとやかく言う資格もないでしょう。
商売は哲学だ、とか
哲学のての字も知らないような俗物がよく嘯いてるでしょ。しかし頭は悪いにしてもされはそれである意味正しいんですね。どういうことかと言うと、
そら何ごとであれ一生懸命やれば古典哲学的あるいは形示上学的な世界を垣間見ることはあるでしょう。
儒教をやれば真理に近づくなんて論法も全く同じですよ。
真理を求めるのであれば儒教から攻める必要性はないし、それなら正面切ってそれを求める宗教の方が好感がもてるし、そのやり方を俗人が聖人のふりをしてとやかく言う資格もないでしょう。
「小道と雖ども、必ず観るべき者有り。遠きを致すには
泥まぬことを恐る。是を以て君子は為さざるなり(既出)」
「小道にも全く見所がないわけではない。 しかし、遠く進んで行けば
必ず泥沼にはまることになる。だから君子はその道を歩まないのだ」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子張第十九・四より)
「君子の道は闇然として而も日に章らかに、小人の道は的然として日に亡ぶ(既出)」
「君子の道は(謙譲を尽くすので)始めは暗がりのようだが、日々の積み重ねで次第に明らかになり、
小人の道は(巧言令色を尽くすので)始めは明るげでも、風化によって次第に衰亡していく。」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・三三より)
「非可換なものの実在」を、これから改めて人々に啓蒙して行く必要がある。
それは、昔は直観的に認識されていたものだが、今は無理に無きものとされている。
しかし、残念ながらやっぱり実在していたわけだから、それはわきまえて行くほかない。
泥まぬことを恐る。是を以て君子は為さざるなり(既出)」
「小道にも全く見所がないわけではない。 しかし、遠く進んで行けば
必ず泥沼にはまることになる。だから君子はその道を歩まないのだ」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子張第十九・四より)
「君子の道は闇然として而も日に章らかに、小人の道は的然として日に亡ぶ(既出)」
「君子の道は(謙譲を尽くすので)始めは暗がりのようだが、日々の積み重ねで次第に明らかになり、
小人の道は(巧言令色を尽くすので)始めは明るげでも、風化によって次第に衰亡していく。」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・三三より)
「非可換なものの実在」を、これから改めて人々に啓蒙して行く必要がある。
それは、昔は直観的に認識されていたものだが、今は無理に無きものとされている。
しかし、残念ながらやっぱり実在していたわけだから、それはわきまえて行くほかない。
安らぐべからざる所に安んじ、楽しむべからざる所を楽しむような状態を
荀子は「狂生」と呼んだ。ただ、この言葉は唱えられ始めた頃からすでに誤用されていたようで、
戦国時代末期から荀子学派の儒者であった酈食其なども、自らが始皇帝の焚書坑儒から逃れるために
アル中の狂人を装っていたために、人々から「狂生」と呼ばれていたという。(「漢書」酈生列伝参照)
おそらく本人自身が、秦帝国の権力者などを「狂生者」などと呼んでいたのだろうが、その時にはむしろ
自分のほうが狂人を装っていたわけだから、自らの言葉を跳ね返されて、自分自身まこそが人から「狂生」と
呼ばれてしまったのである。(この『狂生』には『狂った先生』という皮肉めいた意味までもが込められている)
ただ、結果はやはり本物の狂生者にこそ最大級の禍いを報い、そうでない者にはそれなりの厚遇を処した。
秦帝国は民衆レベルの反乱によって完全崩壊し、その王統に至るまで中国では完全に絶やされた。
酈食其もまた楚漢戦争中に韓信(正確にはその参謀の蒯通)の策略の犠牲となって斉国で客死するも、
一度は斉国を説得で帰服させたその功績が認められて、子孫が万戸侯として封ぜられるなどしている。
酈食其も結局は戦死したわけだから、必ずしも救われたとまではいえないが、中国本土でも逃亡先の
日本などでも、天下の笑い者としての恥辱に見舞われ続けることとなった秦帝国の徒輩などと比べれば、
ずいぶんとマシな運命を辿ることとなったものだといえる。荀子が定義した「狂生」という言葉の意味も、
本来からしてそういった長期的な普遍性に即したものだったはずで、本物の狂生者は不謹慎な安静を
追い求めて最悪の破滅に見舞われる一方、あてつけや言いがかりで狂生者扱いされたような人間は、
いつかは誤解が解かれて名誉を取り戻し、子孫代々にいたるまでのマシ以上な処遇に与れるものである。
荀子は「狂生」と呼んだ。ただ、この言葉は唱えられ始めた頃からすでに誤用されていたようで、
戦国時代末期から荀子学派の儒者であった酈食其なども、自らが始皇帝の焚書坑儒から逃れるために
アル中の狂人を装っていたために、人々から「狂生」と呼ばれていたという。(「漢書」酈生列伝参照)
おそらく本人自身が、秦帝国の権力者などを「狂生者」などと呼んでいたのだろうが、その時にはむしろ
自分のほうが狂人を装っていたわけだから、自らの言葉を跳ね返されて、自分自身まこそが人から「狂生」と
呼ばれてしまったのである。(この『狂生』には『狂った先生』という皮肉めいた意味までもが込められている)
ただ、結果はやはり本物の狂生者にこそ最大級の禍いを報い、そうでない者にはそれなりの厚遇を処した。
秦帝国は民衆レベルの反乱によって完全崩壊し、その王統に至るまで中国では完全に絶やされた。
酈食其もまた楚漢戦争中に韓信(正確にはその参謀の蒯通)の策略の犠牲となって斉国で客死するも、
一度は斉国を説得で帰服させたその功績が認められて、子孫が万戸侯として封ぜられるなどしている。
酈食其も結局は戦死したわけだから、必ずしも救われたとまではいえないが、中国本土でも逃亡先の
日本などでも、天下の笑い者としての恥辱に見舞われ続けることとなった秦帝国の徒輩などと比べれば、
ずいぶんとマシな運命を辿ることとなったものだといえる。荀子が定義した「狂生」という言葉の意味も、
本来からしてそういった長期的な普遍性に即したものだったはずで、本物の狂生者は不謹慎な安静を
追い求めて最悪の破滅に見舞われる一方、あてつけや言いがかりで狂生者扱いされたような人間は、
いつかは誤解が解かれて名誉を取り戻し、子孫代々にいたるまでのマシ以上な処遇に与れるものである。
子孫代々の将来にまで至るような、長期的な視点に即した安寧の希求こそは正善である一方、
その場しのぎの事なかれ主義は狂生だし、間違った方法での長期的安定の企図もまた狂生である。
後二つの方針に即した平和の追い求めは、より大きな破滅を後々にもたらす原因ともなる。
故にこそ狂生である。破滅をもたらすような偽りの平和を追い求めているからこそ、狂生である。
平和なんかわざと追い求めなくたって、自然と平和ということがある。人々の濁念が根本から清められて、
争いの火種になるような不埒な言行なども始めから試みられないような状態、それこそを理想とするのが
正しい平和の追い求め方である一方、人々の濁念は肥大化させっぱなし、争いや奪い合いの火種はそこら中に
撒き散らしておいた上で、腕力によって無理やり停戦状態を持続させようなどとするのが、狂生然とした平和の
追い求め方である。狂生者は、自分自身が不埒な濁念にまみれきっているからこそ、人々の濁念を根本から清めて
いくことこそは無理があることのように自分では思ったりするわけだが、それ以上にも、戦乱の火種で溢れ返って
いる世の中を、極大級の暴力で無理やり抑え付け続けたりすることのほうが、よっぽと無理のあることである。
人々の本然からの清浄さの養生に基づく平和状態は数百年と持たせられる一方、暴力による抑え付けでの平和は
百年と持たない。百年持てば自分の人生だけは平和裡に済ませられるからそれでいいなどとも、極度の狂生者
であれば考えるわけで、実際、前ロスチャイルド家当主なども、英米帝国の完全崩壊が決定的となった2008年
には早々とこの世を去った。哀れなのはその子孫や残党であり、これから人類史上でも最悪級の破滅や恥辱
に見舞われる運命ばかりが待っている。自分たちをそんな非業の運命に見舞わせたのも自分たちの先代でこそある。
にもかかわらず逆恨みを外部の人間に当て付けたりするようならば、それこそ一族郎党皆殺し級の処遇すらもが
免れられるものではない。自分たちは、自分たちや自分たちの先祖の狂生によって不可避なる破滅に見舞われた
のだということへの切なる反省がある場合にのみ、狂生の報いとしての破滅や恥辱が軽減されることもあり得る。
その場しのぎの事なかれ主義は狂生だし、間違った方法での長期的安定の企図もまた狂生である。
後二つの方針に即した平和の追い求めは、より大きな破滅を後々にもたらす原因ともなる。
故にこそ狂生である。破滅をもたらすような偽りの平和を追い求めているからこそ、狂生である。
平和なんかわざと追い求めなくたって、自然と平和ということがある。人々の濁念が根本から清められて、
争いの火種になるような不埒な言行なども始めから試みられないような状態、それこそを理想とするのが
正しい平和の追い求め方である一方、人々の濁念は肥大化させっぱなし、争いや奪い合いの火種はそこら中に
撒き散らしておいた上で、腕力によって無理やり停戦状態を持続させようなどとするのが、狂生然とした平和の
追い求め方である。狂生者は、自分自身が不埒な濁念にまみれきっているからこそ、人々の濁念を根本から清めて
いくことこそは無理があることのように自分では思ったりするわけだが、それ以上にも、戦乱の火種で溢れ返って
いる世の中を、極大級の暴力で無理やり抑え付け続けたりすることのほうが、よっぽと無理のあることである。
人々の本然からの清浄さの養生に基づく平和状態は数百年と持たせられる一方、暴力による抑え付けでの平和は
百年と持たない。百年持てば自分の人生だけは平和裡に済ませられるからそれでいいなどとも、極度の狂生者
であれば考えるわけで、実際、前ロスチャイルド家当主なども、英米帝国の完全崩壊が決定的となった2008年
には早々とこの世を去った。哀れなのはその子孫や残党であり、これから人類史上でも最悪級の破滅や恥辱
に見舞われる運命ばかりが待っている。自分たちをそんな非業の運命に見舞わせたのも自分たちの先代でこそある。
にもかかわらず逆恨みを外部の人間に当て付けたりするようならば、それこそ一族郎党皆殺し級の処遇すらもが
免れられるものではない。自分たちは、自分たちや自分たちの先祖の狂生によって不可避なる破滅に見舞われた
のだということへの切なる反省がある場合にのみ、狂生の報いとしての破滅や恥辱が軽減されることもあり得る。
狂生者の悲哀は、
自分たちの過ちを認めて贖罪と反省の限りを尽くす所にしか、
自分たち自身の救いまでもが見込めなくなるところにこそある。
自分たちを救うためにこそ、世のため人のためにも尽くさねばならない、
すでに罪悪の限りを尽くしているわけだから、その手段も当分は贖罪や反省で
しかあり得ないわけだが、そうであるにしたって、自分たち自身が仁徳に適った
相応の振る舞いを為すのでなければ、自分たちの救いもないというわけであって、
世界でも最も仁徳を忌み嫌って来た部類の者たちこそが、完全に強制的に、仁徳に
適った振る舞いを実行していかなければならないというのだから、悲惨の限りである。
仁徳こそは、それを慕う者にとっての福果ともなる一方、それを忌み嫌う者にとっての
地獄の仕打ちともなるのである。故に、始めから慕っておくに越したこともないのである。
「是の月や、日短至れり。陰陽争い、諸生蕩ず。君子斎戒し、処るには必ず身を掩い、身寧からんことを欲す。
声色を去り、耆欲を禁ず。形性を安んじ、事は静かならんことを欲し、以て陰陽の定むる所を待つ」
「日照時間が一番短くなる冬至のころ、陰陽の和気は乱れて互いに相い争い、諸々の生き物も蕩心を
帯びやすくなる。君子は斎戒沐浴して安居中には必ず身を覆い、己れの身が安からんことを企図する。
大声をあげたりすることを慎み、欲にまみれることも戒める。それにより万物の形性をも安んじ、
物事が静穏であるように企図し、陰陽の和気が定まることを待つのである。(自分一身の安静ではなく、
天下万物万人諸生の安静を修己治人にもよって企図している。狂生とは程遠いあり方だといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・月令第六より)
自分たちの過ちを認めて贖罪と反省の限りを尽くす所にしか、
自分たち自身の救いまでもが見込めなくなるところにこそある。
自分たちを救うためにこそ、世のため人のためにも尽くさねばならない、
すでに罪悪の限りを尽くしているわけだから、その手段も当分は贖罪や反省で
しかあり得ないわけだが、そうであるにしたって、自分たち自身が仁徳に適った
相応の振る舞いを為すのでなければ、自分たちの救いもないというわけであって、
世界でも最も仁徳を忌み嫌って来た部類の者たちこそが、完全に強制的に、仁徳に
適った振る舞いを実行していかなければならないというのだから、悲惨の限りである。
仁徳こそは、それを慕う者にとっての福果ともなる一方、それを忌み嫌う者にとっての
地獄の仕打ちともなるのである。故に、始めから慕っておくに越したこともないのである。
「是の月や、日短至れり。陰陽争い、諸生蕩ず。君子斎戒し、処るには必ず身を掩い、身寧からんことを欲す。
声色を去り、耆欲を禁ず。形性を安んじ、事は静かならんことを欲し、以て陰陽の定むる所を待つ」
「日照時間が一番短くなる冬至のころ、陰陽の和気は乱れて互いに相い争い、諸々の生き物も蕩心を
帯びやすくなる。君子は斎戒沐浴して安居中には必ず身を覆い、己れの身が安からんことを企図する。
大声をあげたりすることを慎み、欲にまみれることも戒める。それにより万物の形性をも安んじ、
物事が静穏であるように企図し、陰陽の和気が定まることを待つのである。(自分一身の安静ではなく、
天下万物万人諸生の安静を修己治人にもよって企図している。狂生とは程遠いあり方だといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・月令第六より)
 日本の戦国時代、あらん限りの手管を尽くしての総力戦にいそしんでいた武将や武士たちこそは、
日本の戦国時代、あらん限りの手管を尽くしての総力戦にいそしんでいた武将や武士たちこそは、 防護のための甲冑にも趣向を凝らし、立てこもりにも向いた城普請などにも多額の費用をかけていた。
信長のように頑丈な木柵をこしらえて、その隙間からの連射戦法を企てることで武田の騎馬軍を
打ち破るものもあった。(これは近代戦におけるトーチカや戦車や機関銃の原型ともなっている)
総力戦だからこそ、そのような防護にかけての手管が尽くされるということがあった。
泰平が確立された江戸時代には銃砲も取り締まられ、城の造営も厳しく制限され、戦国時代に
用いられていた甲冑なども破棄されるなり、お蔵入りするなりして実用の場を追われて行った。
武家社会の中枢たる江戸城ですら、明暦の大火で焼失して後には天守閣の再建が断念された。
それ程にも、世の中総出を挙げての武装解除ならぬ防護解除が推進されて後になお、
正規の武士たちは大小二本の刀を差して街を歩き、浪人も一本差しで武家としての面子を守っていた。
刀にも刃長制限などのそれなりの取締りが講じられたものの、武士の魂としての刀の温存は
それなりに認められ、場合によってはそれを実用しての仇討ちや無礼討ちすらもが実行に移された。
この時にこそ、人々は戦国時代以上もの勇気が場合によっては必要とされるようにもなったのだった。
上記の事例は、特に分かりやすいものとして挙げたわけだが、実際、戦時だからといって
危険というわけでもなければ、平時だからといって安全というわけでもないようなことはいくら
でもある。利権がらみでの謀殺なんてのは、今の日本でですら陰に陽に横行していることであり、
その実情を大っぴらにしなかったりするぶんだけ、戦死以上にも陰惨なものですらある。
だから結局、戦地に赴く勇気などではなく、常日頃から死への覚悟を欠かさずにいる
勇気こそは、実質的にも必要だったりするものであるが故にこそ、本物の大勇でもあるといえる。
平時にもただ凶事がひた隠されているだけであって、実際にはどこかでくすぶっている刃傷沙汰が
あったりする。そのような影の側面も宿している所、少なくとも宿しうる所である世の中という
ものに対して、常に泰然自若としながら対峙できる者こそは、真の大勇の持ち主だといえる。
蛮勇や匹夫の勇には隙があるが、大勇には隙がない。常日頃からの死への覚悟、
勇気の善用にかけて最善を尽くす配慮などがあればこそ、隙がない。
そんな勇気が実在し得ること自体、西洋などでは認知されて来たことですらない。
ギリシャ神話における勇士アキレウスと策士オデュッセウスの対比以来、
勇気のあるものには知謀がなく、知謀のあるものには勇気がないというのが
西洋社会における固定観念と化したままであり続けてきてしまったものだから、
配慮にかけても最善を尽くす所にこそ大勇があるなどとは考えられもしなかったのである。
東洋においても、大勇こそは知謀にも長け、匹夫の勇こそは知謀を欠くということをちゃんと
理解している人間はそんなに多くない。真の大勇の持ち主だった劉邦や源頼朝や徳川家康よりも、
匹夫の勇止まりだった項羽や源義経や織田信長のほうが人気があったりするのもそのためである。
前者三人を軽んじて後者三人を無責任に持て囃すような人間は、東洋人といえどもろくに政治責任を
負う覚悟もないような人間である可能性が高い。自分自身が責任を担って為政を働いていくことを
本格的に想定してみたならば、ただ劉邦や頼朝や家康を慕いやすくなるだけでなく、彼らこそは
項羽や義経や信長以上もの大勇の持ち主であったことすらもが計り知れるはずなのだから。
討ち死にを果たした項羽や義経や信長の死に様と比べても、劉邦や頼朝や家康の死に様が別段
華々しいなどということもない。矢傷や落馬や食あたりを原因として、床の上で亡くなっている。
それは、乱世の最終勝利者であるが故にこその、比較的平穏な死だったのであり、生存中に
命の危機に見舞われた頻度では、項羽や義経や信長に勝るとも劣らないものとなっている。
そうであることを計り知るためには、ちゃんと数十年以上にわたる偉人たちの事跡を調べ通す必要が
あるわけだから、勉強嫌いな人間こそは大勇の何たるかを計り知ることもできないままに終わるのである。
勇気の善用にかけて最善を尽くす配慮などがあればこそ、隙がない。
そんな勇気が実在し得ること自体、西洋などでは認知されて来たことですらない。
ギリシャ神話における勇士アキレウスと策士オデュッセウスの対比以来、
勇気のあるものには知謀がなく、知謀のあるものには勇気がないというのが
西洋社会における固定観念と化したままであり続けてきてしまったものだから、
配慮にかけても最善を尽くす所にこそ大勇があるなどとは考えられもしなかったのである。
東洋においても、大勇こそは知謀にも長け、匹夫の勇こそは知謀を欠くということをちゃんと
理解している人間はそんなに多くない。真の大勇の持ち主だった劉邦や源頼朝や徳川家康よりも、
匹夫の勇止まりだった項羽や源義経や織田信長のほうが人気があったりするのもそのためである。
前者三人を軽んじて後者三人を無責任に持て囃すような人間は、東洋人といえどもろくに政治責任を
負う覚悟もないような人間である可能性が高い。自分自身が責任を担って為政を働いていくことを
本格的に想定してみたならば、ただ劉邦や頼朝や家康を慕いやすくなるだけでなく、彼らこそは
項羽や義経や信長以上もの大勇の持ち主であったことすらもが計り知れるはずなのだから。
討ち死にを果たした項羽や義経や信長の死に様と比べても、劉邦や頼朝や家康の死に様が別段
華々しいなどということもない。矢傷や落馬や食あたりを原因として、床の上で亡くなっている。
それは、乱世の最終勝利者であるが故にこその、比較的平穏な死だったのであり、生存中に
命の危機に見舞われた頻度では、項羽や義経や信長に勝るとも劣らないものとなっている。
そうであることを計り知るためには、ちゃんと数十年以上にわたる偉人たちの事跡を調べ通す必要が
あるわけだから、勉強嫌いな人間こそは大勇の何たるかを計り知ることもできないままに終わるのである。
天性によって、知らず知らずの内から大勇を持てるような人間も居はするが、大勇の何たるかを
自主的に計り知った上でそれにあやかろうとするのであれば、惜しみのない勉強が必須ともなる。
その心がけもないのに、短絡的な勇猛さを追い求めたりすれば、それが匹夫の勇に転んだりするのである。
「雄雉于こに飛ぶ、泄泄たる其の羽。我れ之れを懐いて、自ら伊の阻いを詒す。
雄雉于こに飛ぶ、下上する其の音。展なる君子、実に我が心を労せしむ。
彼の日月を瞻れば、悠悠として我れ思う。道の云こに遠き、曷か云こに能く来たらん。
百そ爾じ君子、徳行を知らざらんや。忮わず求めざれば、何ぞ用て臧からざらんや」
「雄キジがその羽を打ち立てて飛び立つように、わが夫も出征して行く。私はそれを思うと憂いばかりが募る。
雄キジが天空を羽音を立てて上下するように、わが夫も出征して行く。かの君子は、私の心を労させるばかり。
空に日月を見上げれば、憂患を募らせながらまた思う。遠い道を往きて、またここに帰ってくださることを。
あなたは君子だから、徳行にかけては私などよりもずっと知っていることでしょう。ただ、害悪を好んだり
無闇に利益を追い求めたりしないことで、不善に手を染めないことばかりを私は願うのみです。(雄雄しく
出征して行く夫を思い慕う妻の歌。『忮わず求めざれば、何ぞ用て臧からざらんや』は、孔子の弟子の子路が
好んで謳っていた一節で、孔子は『そんなことばかりでいいはずがない』と子路に苦言を呈していたわけだが、
上記のような文脈で歌われた言葉なわけだから、この言葉にもそれなりの含蓄があることがわかる。雄雄しく
ある夫こそは、最悪の不善にまでは手を染めないで居てくれというのが、妻たるものの切なる願いなのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・邶風・雄雉)
自主的に計り知った上でそれにあやかろうとするのであれば、惜しみのない勉強が必須ともなる。
その心がけもないのに、短絡的な勇猛さを追い求めたりすれば、それが匹夫の勇に転んだりするのである。
「雄雉于こに飛ぶ、泄泄たる其の羽。我れ之れを懐いて、自ら伊の阻いを詒す。
雄雉于こに飛ぶ、下上する其の音。展なる君子、実に我が心を労せしむ。
彼の日月を瞻れば、悠悠として我れ思う。道の云こに遠き、曷か云こに能く来たらん。
百そ爾じ君子、徳行を知らざらんや。忮わず求めざれば、何ぞ用て臧からざらんや」
「雄キジがその羽を打ち立てて飛び立つように、わが夫も出征して行く。私はそれを思うと憂いばかりが募る。
雄キジが天空を羽音を立てて上下するように、わが夫も出征して行く。かの君子は、私の心を労させるばかり。
空に日月を見上げれば、憂患を募らせながらまた思う。遠い道を往きて、またここに帰ってくださることを。
あなたは君子だから、徳行にかけては私などよりもずっと知っていることでしょう。ただ、害悪を好んだり
無闇に利益を追い求めたりしないことで、不善に手を染めないことばかりを私は願うのみです。(雄雄しく
出征して行く夫を思い慕う妻の歌。『忮わず求めざれば、何ぞ用て臧からざらんや』は、孔子の弟子の子路が
好んで謳っていた一節で、孔子は『そんなことばかりでいいはずがない』と子路に苦言を呈していたわけだが、
上記のような文脈で歌われた言葉なわけだから、この言葉にもそれなりの含蓄があることがわかる。雄雄しく
ある夫こそは、最悪の不善にまでは手を染めないで居てくれというのが、妻たるものの切なる願いなのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・邶風・雄雉)
損なわず求めないが故に不善ではない——
そんなことは、多少できた婦女子でも分かることだってんだ。
女だから害悪を求めるわけじゃない。
老若男女に関わりない人でなしだからこそ、害悪を可とするんだ。
そんなことは、多少できた婦女子でも分かることだってんだ。
女だから害悪を求めるわけじゃない。
老若男女に関わりない人でなしだからこそ、害悪を可とするんだ。
この世界、天地万物全宇宙は生々流転の易の法則に即しているから、それなりの柔軟性や流動性を
持ち合わせている事物こそは、ただただ堅固であるような事物以上にも普遍的である場合が多々ある。
故に老子も「柔よく剛を制す」と言ったのであり、決してただの草の根志向だったりしたのではない。
生々流転の易の法則に即した上で、なおかつこの世界この宇宙は自己完結的なものであり、
形而上との連絡などが可能となったりすることもない。故に、形而上における絶対に普遍的な事物への
寄りすがりなどが実質性を帯びたりすることもなく、そのような試みは必ず不毛に終わることともなる。
ただただ堅固なだけでは柔軟でもあるものに敵わない。かといってただただ柔軟なのでは張り合いがない。
だから剛柔織り交ぜての為政を心がけるのが儒家の推奨する礼楽統治だったりもする。ただただ世の中を
制度で雁字搦めにする法家支配よりも柔軟でいて、何もかもをやらせたい放題なままにおく道家的統治
などと比べれば、メリハリがある。礼楽統治といえども数百年も経てば腐敗を来たして瓦解してしまう
のが常ではあるけれども、人間が実現する治世としては最上級のものであることにも間違いがない。
礼楽統治が法家支配や道家的統治よりも長寿で上質となるからには、剛柔織り交ぜた中正なあり方こそが
至上ともなるということである。ただただ硬いばかりでは脆くもなるが、ただただ柔らかいのでも
腐敗を来たす。硬いばかりじゃダメだからヤワヤワに振れ切るというのも極端なことであり、それが
休暇程度に許容されるのは可であるにしたって、振り切れてそのまんまというのでは賢いもんじゃない。
ただただ強固なものを追い求めるものにとって、ただただ柔弱なものが絶対に相容れないものなのではない。
法家の韓非も老子に傾倒していたし、キリスト教圏のままである近現代の欧米社会においても、自分たちで
示し合わせた範囲でのアンチキリストだとかアナーキズムだとかはそれなりに許容されている。あくまでその
勢力を矮小化させたりした範囲での活動ではあるものの、共存が絶対に不可能だったりまではしないのである。
持ち合わせている事物こそは、ただただ堅固であるような事物以上にも普遍的である場合が多々ある。
故に老子も「柔よく剛を制す」と言ったのであり、決してただの草の根志向だったりしたのではない。
生々流転の易の法則に即した上で、なおかつこの世界この宇宙は自己完結的なものであり、
形而上との連絡などが可能となったりすることもない。故に、形而上における絶対に普遍的な事物への
寄りすがりなどが実質性を帯びたりすることもなく、そのような試みは必ず不毛に終わることともなる。
ただただ堅固なだけでは柔軟でもあるものに敵わない。かといってただただ柔軟なのでは張り合いがない。
だから剛柔織り交ぜての為政を心がけるのが儒家の推奨する礼楽統治だったりもする。ただただ世の中を
制度で雁字搦めにする法家支配よりも柔軟でいて、何もかもをやらせたい放題なままにおく道家的統治
などと比べれば、メリハリがある。礼楽統治といえども数百年も経てば腐敗を来たして瓦解してしまう
のが常ではあるけれども、人間が実現する治世としては最上級のものであることにも間違いがない。
礼楽統治が法家支配や道家的統治よりも長寿で上質となるからには、剛柔織り交ぜた中正なあり方こそが
至上ともなるということである。ただただ硬いばかりでは脆くもなるが、ただただ柔らかいのでも
腐敗を来たす。硬いばかりじゃダメだからヤワヤワに振れ切るというのも極端なことであり、それが
休暇程度に許容されるのは可であるにしたって、振り切れてそのまんまというのでは賢いもんじゃない。
ただただ強固なものを追い求めるものにとって、ただただ柔弱なものが絶対に相容れないものなのではない。
法家の韓非も老子に傾倒していたし、キリスト教圏のままである近現代の欧米社会においても、自分たちで
示し合わせた範囲でのアンチキリストだとかアナーキズムだとかはそれなりに許容されている。あくまでその
勢力を矮小化させたりした範囲での活動ではあるものの、共存が絶対に不可能だったりまではしないのである。
ただただ強固であろうとするような姿勢と、剛柔織り交ぜた中正の尊重こそは、決して相容れることがない。
礼楽統治もまた礼法などにかけて格式ばるところがある、そしてその取り決めこそは、実定法の規律などとも
全く次元の違うものであり、礼節の範囲で人々の品性を根本から正していくものだから、そのぶんだけ
実定法によって人々の活動を取り締まったりする必要がなくなる。お互いに権益を脅かし合うもの同士で
あればこそ、ただただ頑なな法家支配と、剛柔織り交ぜる礼楽統治もまた相容れることがないのである。
ただただ強固であることにばかり慣れきってしまった人間こそは、中正の実践にも参画のしようがない。
ただの一般人以上にも、中正を守ることへの素養を欠いてしまっていて、もはや中正の何たるかも分からない。
そんな人間ばかりが支配層を占めてしまっていたりするようなら、革命すらもが避けられるものではなく、
革命によって地位を追われた旧支配層こそは、治産行為を強く制限される被差別階級にすらならねばならない。
キリスト教がそのような強固一辺倒の姿勢を信者に深く植え付けたのなら、キリスト教こそは、信者たる
欧米人などから、自分たちが世界の支配者たる資格を奪い去ったのだといえる。強固一辺倒を基調とした
世界支配などが、どんな形であれ長続きするものではなく、最悪の場合は滅亡級の破綻すらもが免れるもの
ではない、だから中正に適った礼楽統治を実現できるものにこの世を明け渡して、自分たちは飼い犬か飼い猫
も同然の立場に甘んじるしかない、そのような自分たちの運命を、キリスト教こそは決定付けたのである。
「有の扁りし石は、之れを履むにも卑き兮む」
「形のゆがんだ踏み石は、それを踏むときに自分の姿勢をもゆがめる必要がある。
(堅固な岩石であればこそ、それ自体が歪んでいれば、それを踏襲するものも態度姿勢が歪む)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・都人士之什・白華より)
礼楽統治もまた礼法などにかけて格式ばるところがある、そしてその取り決めこそは、実定法の規律などとも
全く次元の違うものであり、礼節の範囲で人々の品性を根本から正していくものだから、そのぶんだけ
実定法によって人々の活動を取り締まったりする必要がなくなる。お互いに権益を脅かし合うもの同士で
あればこそ、ただただ頑なな法家支配と、剛柔織り交ぜる礼楽統治もまた相容れることがないのである。
ただただ強固であることにばかり慣れきってしまった人間こそは、中正の実践にも参画のしようがない。
ただの一般人以上にも、中正を守ることへの素養を欠いてしまっていて、もはや中正の何たるかも分からない。
そんな人間ばかりが支配層を占めてしまっていたりするようなら、革命すらもが避けられるものではなく、
革命によって地位を追われた旧支配層こそは、治産行為を強く制限される被差別階級にすらならねばならない。
キリスト教がそのような強固一辺倒の姿勢を信者に深く植え付けたのなら、キリスト教こそは、信者たる
欧米人などから、自分たちが世界の支配者たる資格を奪い去ったのだといえる。強固一辺倒を基調とした
世界支配などが、どんな形であれ長続きするものではなく、最悪の場合は滅亡級の破綻すらもが免れるもの
ではない、だから中正に適った礼楽統治を実現できるものにこの世を明け渡して、自分たちは飼い犬か飼い猫
も同然の立場に甘んじるしかない、そのような自分たちの運命を、キリスト教こそは決定付けたのである。
「有の扁りし石は、之れを履むにも卑き兮む」
「形のゆがんだ踏み石は、それを踏むときに自分の姿勢をもゆがめる必要がある。
(堅固な岩石であればこそ、それ自体が歪んでいれば、それを踏襲するものも態度姿勢が歪む)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・都人士之什・白華より)
今の法人法の改正によっても、医療法人はそのほとんどが公益法人としての認可を
受けることが出来ず、おおむね社団法人として扱われるようにもなっている。
この実情一つとっても、怪我や病気を押してでも人間が無理に
生き続けようとすること自体、私欲の充足でしかないことが分かる。
公共機関で重要な職務に就いている人間が、己れの職務を果たすために健康や長寿を企図するとする。
その場合においても、まず病気や怪我に見舞われるような不摂生や不注意から排除して行くべきだし、
それでも老齢による心身の衰弱は免れられないから、潔く後代に職務を譲るなどする必要が出てくる。
人間、個人個人が独立的な生に執着することが公益に適う場合があるとは、この場合にも言えはしない。
家康公のように、天下の情勢が定まるまで死にきろうにも死にきれないでいた挙句に、
当時としては非常に高齢な75歳まで生きたような事例もあるが、やはり征夷大将軍としての
座は早急に息子の秀忠に譲り、駿府城からの半隠居状態での時局の見守りに徹したのだった。
生きる限りにおいても、やはり消極的に生きるということが仁者の事跡にこそ顕著であり、
やたらめったら自分自身が生きて個人的な繁栄を謳歌するようなことは控えている。
少なくとも、そうだったりすることを恥じて、見せびらかしたりはしないようにしている。
(一汁三菜を基本としていたという家康公の食生活も、本人の恰幅のよさなどからいえば疑わしい
ことだが、それでも大食いだったりしたことは恥じて隠している。その姿勢からして仁者である)
最大級に世のため人のためにあろうとする仁者であってなお、なるべく自分自身の健康を保つ程度までが、
自らが生きることに積極的であることが道義に適う限度だといえる。それ以上にも、利得をむさぼって
遊興に耽ったりするのなら、その時点で道義からは外れるのである。清廉すぎる物言いのように
思われるかもしれないが、それはそれで事実であり、それをわきまえた上で、適度に清濁
併せ呑んだ生き方をして行くことが、現実上から仁を為していく手立てともなるのである。
受けることが出来ず、おおむね社団法人として扱われるようにもなっている。
この実情一つとっても、怪我や病気を押してでも人間が無理に
生き続けようとすること自体、私欲の充足でしかないことが分かる。
公共機関で重要な職務に就いている人間が、己れの職務を果たすために健康や長寿を企図するとする。
その場合においても、まず病気や怪我に見舞われるような不摂生や不注意から排除して行くべきだし、
それでも老齢による心身の衰弱は免れられないから、潔く後代に職務を譲るなどする必要が出てくる。
人間、個人個人が独立的な生に執着することが公益に適う場合があるとは、この場合にも言えはしない。
家康公のように、天下の情勢が定まるまで死にきろうにも死にきれないでいた挙句に、
当時としては非常に高齢な75歳まで生きたような事例もあるが、やはり征夷大将軍としての
座は早急に息子の秀忠に譲り、駿府城からの半隠居状態での時局の見守りに徹したのだった。
生きる限りにおいても、やはり消極的に生きるということが仁者の事跡にこそ顕著であり、
やたらめったら自分自身が生きて個人的な繁栄を謳歌するようなことは控えている。
少なくとも、そうだったりすることを恥じて、見せびらかしたりはしないようにしている。
(一汁三菜を基本としていたという家康公の食生活も、本人の恰幅のよさなどからいえば疑わしい
ことだが、それでも大食いだったりしたことは恥じて隠している。その姿勢からして仁者である)
最大級に世のため人のためにあろうとする仁者であってなお、なるべく自分自身の健康を保つ程度までが、
自らが生きることに積極的であることが道義に適う限度だといえる。それ以上にも、利得をむさぼって
遊興に耽ったりするのなら、その時点で道義からは外れるのである。清廉すぎる物言いのように
思われるかもしれないが、それはそれで事実であり、それをわきまえた上で、適度に清濁
併せ呑んだ生き方をして行くことが、現実上から仁を為していく手立てともなるのである。
生きるということに積極的であり過ぎることをほとんどの東洋教学が戒めている一方、
「さっさと死んじまえ」などという虚無主義を前面に押し出しているものもまた、まれである。
「荘子」の雑篇などに、国王になることを薦められたが、権力嫌悪のあまり逃亡して自殺してしまう
隠者の逸話などもあるが、これも権力者としての奢り高ぶりなどに対するアンチテーゼとして提示された
方便的な極論なのであり、とにかく死をよしとするような所にまで暴論が及んでいるわけではないのである。
生きるか死ぬか、そんな極論に振り切れないような人生やその死に与れることこそは理想である。
偉大な人間は誰しもがその生を羨望し、死ねば誰しもがその死を悲しむ、外的にそのようであることはいい
としても、自分自身は生きることにも死ぬことにも積極的であり過ぎない、楚々とした態度でこそあるべきだ。
肉体や頭脳は所詮は単なる物質であり、それが死して廃壊するのも単なる物質の損壊であるまでだ。
そこに命をもたらしていた精神そのものは、肉体の生死などに関わらず不滅である。さほど大事で
ないものこそは生死の乱脈に翻弄される一方、本当に大事なものは始めから生じることも滅ぶことも
ありはしない。故にこそ、生死というものをさほど偏重して取り扱ったりする必要もないのである。
「我れ生の初め、尚お為すこと無し。
我れ生れて後、此の百罹に逢う。尚くは寐ねて吪くこと無からん」
「私は生まれたばかりの頃には無為の清浄に与れていたのに、長らく生きて後の今には
もはや百千万の難儀に見舞われるばかりである。もう寝たままで一切動かずにでもいたいものだ。
(仏法の一切皆苦ほど極端ではないが、生きるということの濁悪さをよく捉えた一節である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・王風・兔爰より)
「さっさと死んじまえ」などという虚無主義を前面に押し出しているものもまた、まれである。
「荘子」の雑篇などに、国王になることを薦められたが、権力嫌悪のあまり逃亡して自殺してしまう
隠者の逸話などもあるが、これも権力者としての奢り高ぶりなどに対するアンチテーゼとして提示された
方便的な極論なのであり、とにかく死をよしとするような所にまで暴論が及んでいるわけではないのである。
生きるか死ぬか、そんな極論に振り切れないような人生やその死に与れることこそは理想である。
偉大な人間は誰しもがその生を羨望し、死ねば誰しもがその死を悲しむ、外的にそのようであることはいい
としても、自分自身は生きることにも死ぬことにも積極的であり過ぎない、楚々とした態度でこそあるべきだ。
肉体や頭脳は所詮は単なる物質であり、それが死して廃壊するのも単なる物質の損壊であるまでだ。
そこに命をもたらしていた精神そのものは、肉体の生死などに関わらず不滅である。さほど大事で
ないものこそは生死の乱脈に翻弄される一方、本当に大事なものは始めから生じることも滅ぶことも
ありはしない。故にこそ、生死というものをさほど偏重して取り扱ったりする必要もないのである。
「我れ生の初め、尚お為すこと無し。
我れ生れて後、此の百罹に逢う。尚くは寐ねて吪くこと無からん」
「私は生まれたばかりの頃には無為の清浄に与れていたのに、長らく生きて後の今には
もはや百千万の難儀に見舞われるばかりである。もう寝たままで一切動かずにでもいたいものだ。
(仏法の一切皆苦ほど極端ではないが、生きるということの濁悪さをよく捉えた一節である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・王風・兔爰より)
「困った時の神頼み」という言葉は、ご都合主義の神仏帰依として
批判目的で用いられる場合が多いことわざだが、これはこれで一つの真実の提示である。
困ってない時は神仏なんかにすがらない。自分から積極的に善行すら為していくというのなら、
神仏も我が子の自立を遠くから見守る親ぐらいのものでしかあり得ないというのが実際である。
本当に善を為して行く時には、もはや自問自答すらすべきでない。
一切の雑念を排した無念夢想の境地と共にこそ、真の善行もまた為し得るものである。
だからこそ幼少期の頃から儒学や武芸を学び込んでいた武家なども、
さらに禅寺での座禅によって雑念を排する修養を積んだりしていたのである。
「信仰によってこそ善が為せる、信仰がなければ善は為せない」というところにまで固定観念が
定着しきってしまっているようなら、そのせいでこそ、誰も善は為せなくなる。善を為そうとして
無為以上の悪しか為せなくなる。せいぜい信仰によって不善を最小限に控えるぐらいのことしかできはせず、
そのような信仰を辛うじて保っているのが浄土信仰や正統のイスラム信仰だったりするのみである。
不善を為さなかったり、最小限に止めたりすることは、それだけでは善と呼ぶにも値しないとは孔子も
子罕第九・二八に言い遺していることである。ただ、不善を為さないという程度のことも、女子供や
小人にとってはそれなりに重大なことであるのが、>>228の詩経からの引用を読んでも分かることである。
自分たちではさして大きな善行を為すこともできない、やもすれば大悪すらをも働きかねない
小人や女子供にとって、ただ不善や悪を為さないことだけでも一大命題となるのであり、
ただそれを守り通せただけでも、十分に賞賛に値するものだといえなくもないのである。
批判目的で用いられる場合が多いことわざだが、これはこれで一つの真実の提示である。
困ってない時は神仏なんかにすがらない。自分から積極的に善行すら為していくというのなら、
神仏も我が子の自立を遠くから見守る親ぐらいのものでしかあり得ないというのが実際である。
本当に善を為して行く時には、もはや自問自答すらすべきでない。
一切の雑念を排した無念夢想の境地と共にこそ、真の善行もまた為し得るものである。
だからこそ幼少期の頃から儒学や武芸を学び込んでいた武家なども、
さらに禅寺での座禅によって雑念を排する修養を積んだりしていたのである。
「信仰によってこそ善が為せる、信仰がなければ善は為せない」というところにまで固定観念が
定着しきってしまっているようなら、そのせいでこそ、誰も善は為せなくなる。善を為そうとして
無為以上の悪しか為せなくなる。せいぜい信仰によって不善を最小限に控えるぐらいのことしかできはせず、
そのような信仰を辛うじて保っているのが浄土信仰や正統のイスラム信仰だったりするのみである。
不善を為さなかったり、最小限に止めたりすることは、それだけでは善と呼ぶにも値しないとは孔子も
子罕第九・二八に言い遺していることである。ただ、不善を為さないという程度のことも、女子供や
小人にとってはそれなりに重大なことであるのが、>>228の詩経からの引用を読んでも分かることである。
自分たちではさして大きな善行を為すこともできない、やもすれば大悪すらをも働きかねない
小人や女子供にとって、ただ不善や悪を為さないことだけでも一大命題となるのであり、
ただそれを守り通せただけでも、十分に賞賛に値するものだといえなくもないのである。
「信仰によって善を為すことなんかできない、せいぜい不善を止める効果があったりするのみであり、
積極的な善行ともなれば、もはや無念無想によって為すぐらいでなければ勤まらない」といった認識こそを
誰しもに広めて行ったとき、せいぜい不善を為さない程度の所にしか自分たちの目的を定められなくなる
人間が多々生じ得る。自分たちでも善を為せるつもりでいたのが、せいぜい不善を控える程度のことしか
自分たちにはできないのだと思い知らされた時の小人男や女子供の落胆たるや、生半可なものではあるまい。
それこそ、身の程を思い知らされたがための落胆であるわけで、時には鬱病の発症すらもが免れ得ないだろう。
しかし、実際に世の中で為して行ける大規模な善行というのも、実物からして地味なものでもある。
権力道徳者としての活動こそは純粋かつ極大級の善行ともなるわけだが、そこで心がけられるのも万人の
食糧確保だとか、贋金作りや盗賊活動の取り締まりだとかで、とうてい女子供や小人男などがそれをこなして
行くことを欲しすらできないものである。しかもそれらの善行を為したからといって、貧民に寄付を恵んで
やった時の笑顔のような、己れの良心をくすぐるあからさまな見返りが得られたりするとも限らない。
仁政がよく行き届いている世の中においてこそ、恵みをありがたがる貧民なども始めから生じないのだから、
はじめからそのような世の中を保全していく権力道徳者の活動たるや、どこまでも「縁の下の力持ち」
であることこそを主体として行かねばならない。ゆえに、あからさまな見返りばかりを求めたがる
小人や女子供が率先して実行して行くことなどは、到底できないようにもなっているのである。
積極的な善行ともなれば、もはや無念無想によって為すぐらいでなければ勤まらない」といった認識こそを
誰しもに広めて行ったとき、せいぜい不善を為さない程度の所にしか自分たちの目的を定められなくなる
人間が多々生じ得る。自分たちでも善を為せるつもりでいたのが、せいぜい不善を控える程度のことしか
自分たちにはできないのだと思い知らされた時の小人男や女子供の落胆たるや、生半可なものではあるまい。
それこそ、身の程を思い知らされたがための落胆であるわけで、時には鬱病の発症すらもが免れ得ないだろう。
しかし、実際に世の中で為して行ける大規模な善行というのも、実物からして地味なものでもある。
権力道徳者としての活動こそは純粋かつ極大級の善行ともなるわけだが、そこで心がけられるのも万人の
食糧確保だとか、贋金作りや盗賊活動の取り締まりだとかで、とうてい女子供や小人男などがそれをこなして
行くことを欲しすらできないものである。しかもそれらの善行を為したからといって、貧民に寄付を恵んで
やった時の笑顔のような、己れの良心をくすぐるあからさまな見返りが得られたりするとも限らない。
仁政がよく行き届いている世の中においてこそ、恵みをありがたがる貧民なども始めから生じないのだから、
はじめからそのような世の中を保全していく権力道徳者の活動たるや、どこまでも「縁の下の力持ち」
であることこそを主体として行かねばならない。ゆえに、あからさまな見返りばかりを求めたがる
小人や女子供が率先して実行して行くことなどは、到底できないようにもなっているのである。
偽りでない本物の善というものもそれはそれである、ただ、それは意外と微妙不可思議なものであり、
あからさまに分かりやすいものとして現出するほうがまれである。中国の三国時代の群雄割拠だとか、
寛政期の火盗改長官である長谷川平蔵の活躍をフィクション混じりに描いた時代劇だとかが、一般にも
分かりやすい善の姿ともなっているが、それはむしろ当時の中国や日本の世相が乱れていたからこそ、
それを対症的に取り締まる英雄たちの姿が分かりやいというばかりのことなのであって、それで
善たるもののあり方をわかり切ったつもりになったりするのも、危険なことだといえる。
第一に微妙不可思議なものであり、第二に辛うじて分かりやすかったりすることがある、
そういう風に善というものを捉えて行くべきなのであり、何よりも分かりやすさばかりを善に要求
したりするようなことがあってはならない。善は分かりにくいが故にこそ旺盛でもあったりする一方、
脆弱化してしまったればこそ分かりやすくなってしまったりもするのだから、分かりにくいぐらいのほうがいいのだ。
「徳に常師無し、善を主とするを師と為す。善に常主無し、克く一なるに協うのみ」
「徳に恒常的な師というものはない、ただ善を主とするものを師とするのみ。
善にも恒常的な主というものはない、よく一を以って貫くことに適っているものが主たるのみ。
(死ぬことで生きるみたいな一貫しない態度姿勢からしてすでに善の主たるものではない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・咸有一徳より)
あからさまに分かりやすいものとして現出するほうがまれである。中国の三国時代の群雄割拠だとか、
寛政期の火盗改長官である長谷川平蔵の活躍をフィクション混じりに描いた時代劇だとかが、一般にも
分かりやすい善の姿ともなっているが、それはむしろ当時の中国や日本の世相が乱れていたからこそ、
それを対症的に取り締まる英雄たちの姿が分かりやいというばかりのことなのであって、それで
善たるもののあり方をわかり切ったつもりになったりするのも、危険なことだといえる。
第一に微妙不可思議なものであり、第二に辛うじて分かりやすかったりすることがある、
そういう風に善というものを捉えて行くべきなのであり、何よりも分かりやすさばかりを善に要求
したりするようなことがあってはならない。善は分かりにくいが故にこそ旺盛でもあったりする一方、
脆弱化してしまったればこそ分かりやすくなってしまったりもするのだから、分かりにくいぐらいのほうがいいのだ。
「徳に常師無し、善を主とするを師と為す。善に常主無し、克く一なるに協うのみ」
「徳に恒常的な師というものはない、ただ善を主とするものを師とするのみ。
善にも恒常的な主というものはない、よく一を以って貫くことに適っているものが主たるのみ。
(死ぬことで生きるみたいな一貫しない態度姿勢からしてすでに善の主たるものではない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・咸有一徳より)
危難を外界にしわ寄せすることで、領域内の人間の安全を確保してやっていた邪教があったとして、
もはや危難をしわ寄せする余地が外界になくなって、自分たち領域内の人間たち自身で危難を甘受して
行かなければならなくなった場合に、「(邪教の)神の保護から離れざるを得なくなった」などと嘆いたりする
のはおかしい。あくまで、自分たちで危難を甘受しなければならなくなったことまで含めて邪教やその神の責任
なのであり、責任はそれらや、そんなものを信じてしまった自分たちにこそあるのだとわきまえねばならない。
今まで他者に危難を押し付けてきたぶんだけ、人並み以上もの危難を自分たちが受け入れて行かなければならない。
それもまた邪教やその神の責任なのであり、怨むのならそれらこそを対象としなければならない。
(実在しない架空神であるのなら、そんなものを捏造した人間こそを怨むべきだ)
「完全なる平和」「完全なる秩序」、そんなものを本当に望めるような人間からして稀である。
まずは心から安寧を欲することのできる衆生こそを育て上げて行くのでなければ、みんな戦乱を望んでいるにも
関わらず、極大級の軍力で強制的に世情を鎮圧するなんていう状態にすらなってしまう。それこそ、名目上は平和で
あるにもかかわらず、その平和を謳歌する人間自身がろくにいないという、本末転倒の事態となってしまうのである。
心から安寧を求めるというのなら、当然マッチポンプの結果としての安全や平和などを欲したりもしない。
それは、より大きな危難をもたらしつつのなけなしの安全や平和でしかないのだから、本当に心から平安を求める
人間こそは、そんな風であってはならないと考えるのである。仮にマッチポンプ込みの安全や平和を欲することが
あるとすれば、そんな人間は本当は安全も平和も求めてはいない、暴虎馮河の危難こそを本質的に求めているのである。
もはや危難をしわ寄せする余地が外界になくなって、自分たち領域内の人間たち自身で危難を甘受して
行かなければならなくなった場合に、「(邪教の)神の保護から離れざるを得なくなった」などと嘆いたりする
のはおかしい。あくまで、自分たちで危難を甘受しなければならなくなったことまで含めて邪教やその神の責任
なのであり、責任はそれらや、そんなものを信じてしまった自分たちにこそあるのだとわきまえねばならない。
今まで他者に危難を押し付けてきたぶんだけ、人並み以上もの危難を自分たちが受け入れて行かなければならない。
それもまた邪教やその神の責任なのであり、怨むのならそれらこそを対象としなければならない。
(実在しない架空神であるのなら、そんなものを捏造した人間こそを怨むべきだ)
「完全なる平和」「完全なる秩序」、そんなものを本当に望めるような人間からして稀である。
まずは心から安寧を欲することのできる衆生こそを育て上げて行くのでなければ、みんな戦乱を望んでいるにも
関わらず、極大級の軍力で強制的に世情を鎮圧するなんていう状態にすらなってしまう。それこそ、名目上は平和で
あるにもかかわらず、その平和を謳歌する人間自身がろくにいないという、本末転倒の事態となってしまうのである。
心から安寧を求めるというのなら、当然マッチポンプの結果としての安全や平和などを欲したりもしない。
それは、より大きな危難をもたらしつつのなけなしの安全や平和でしかないのだから、本当に心から平安を求める
人間こそは、そんな風であってはならないと考えるのである。仮にマッチポンプ込みの安全や平和を欲することが
あるとすれば、そんな人間は本当は安全も平和も求めてはいない、暴虎馮河の危難こそを本質的に求めているのである。
引っ切り無しの動乱こそを欲しているような輩に対して平和をあてがってやったりするのは、
猫に小判もいいとこである。むしろ武力支配の到来などによって、己れの剣呑さをよく自覚させて、
それでも乱世を欲するか否かを問うてみればいい。それでも相変わらず欲するようであれば武力支配を継続、
それに懲りて心から平和を求めるようになるようなら、より柔弱な統治方法に切り替えるようにしてやればいい。
(京都に朝廷を置き、東京に幕府を置くような両輪統治もまた不可能ではない)
マッチポンプの一環としてのなけなしの平和などを欲したりする人間にも、自分たちが本当は平和以上にも
乱世こそを欲しているのだということを思い知らせた上で、それでも乱世を欲し続けるか、本物の平和を求める
ようになるかを問うべきである。そしてその答えようによって、武力統治か文治かのいずれかをあてがったりする。
それでこそ、本当に平和を企図することにもなる。乱世以上の平和を現実に呼び込む施策となる。
それと比べれば、ただ引っ切り無しの乱世を呼び込むのはもちろんのこと、マッチポンプの平和を希求したり
することですら、むしろ乱世を呼び込むことのうちに入るものである。日本の武家統治など、今の欧米聖書圏の
統治などと比べてもあからさまにこわもてではあるが、心から平和を追い求めたりすることのできない愚かな
人間を統治対象とするうえでは、むしろ武家統治のほうが真の平和を企図する手段ともなっていたのである。
「彼の譖人を取らえて、豺虎に投げ畀えよ。
豺虎も食わずんば、有北に投げ畀えよ。有北も受けずんば、有昊に投げ畀えよ」
「讒言を放つあの凶人をひっ捕らえて、豹や虎に投げ与えよ。豹や虎も嫌がって口にしないようなら、
北の果ての鬼に食わせよ。北の果ての鬼すら嫌がって受けぬようなら、後は天の裁きにかけるばかり。
(猛獣の害を免れられたからといって、さらにその先により大きな危難が待ち受けるのみである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・小旻之什・巷伯より)
猫に小判もいいとこである。むしろ武力支配の到来などによって、己れの剣呑さをよく自覚させて、
それでも乱世を欲するか否かを問うてみればいい。それでも相変わらず欲するようであれば武力支配を継続、
それに懲りて心から平和を求めるようになるようなら、より柔弱な統治方法に切り替えるようにしてやればいい。
(京都に朝廷を置き、東京に幕府を置くような両輪統治もまた不可能ではない)
マッチポンプの一環としてのなけなしの平和などを欲したりする人間にも、自分たちが本当は平和以上にも
乱世こそを欲しているのだということを思い知らせた上で、それでも乱世を欲し続けるか、本物の平和を求める
ようになるかを問うべきである。そしてその答えようによって、武力統治か文治かのいずれかをあてがったりする。
それでこそ、本当に平和を企図することにもなる。乱世以上の平和を現実に呼び込む施策となる。
それと比べれば、ただ引っ切り無しの乱世を呼び込むのはもちろんのこと、マッチポンプの平和を希求したり
することですら、むしろ乱世を呼び込むことのうちに入るものである。日本の武家統治など、今の欧米聖書圏の
統治などと比べてもあからさまにこわもてではあるが、心から平和を追い求めたりすることのできない愚かな
人間を統治対象とするうえでは、むしろ武家統治のほうが真の平和を企図する手段ともなっていたのである。
「彼の譖人を取らえて、豺虎に投げ畀えよ。
豺虎も食わずんば、有北に投げ畀えよ。有北も受けずんば、有昊に投げ畀えよ」
「讒言を放つあの凶人をひっ捕らえて、豹や虎に投げ与えよ。豹や虎も嫌がって口にしないようなら、
北の果ての鬼に食わせよ。北の果ての鬼すら嫌がって受けぬようなら、後は天の裁きにかけるばかり。
(猛獣の害を免れられたからといって、さらにその先により大きな危難が待ち受けるのみである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・小旻之什・巷伯より)
善徳や罪悪と利害とは、必ずしも関連付けて論じられるとも限らないものである。
しかし、結局のところこれらは不可分な関係にあるのであり、
全くの別物として捉えてまでいいものではないのである。
善徳は結局のところ公益寄与であり、罪悪は結局のところ公的害悪である。
ただ、人間必ずしも善行ばかりをやっていられるものでもなければ、悪行ばかりに専らでいるものでも
ないから、純粋な公益寄与か公的害悪ばかりを善や悪として捉えていると実情からかけ離れることになる。
金融詐欺で世界中に多大なる損害を及ぼしておきながら、それによって得た金の一部で貧窮者を救済したり
する場合もあり、その救済という部分だけをみれば善行のように思えたりすることもあるわけだから、
上記のような結局論ばかりを念頭に置くこともあまり奨められたものではないのである。
己れが天下に及ぼしている公益が公害を上回れば善、公害が公益を上回れば悪である。
これならより厳密な善悪の定義になるが、これまた実社会における分析的な把握は困難である。
商売なんていう職業は大元のところ、商売人本人が世の中に及ぼす利益よりも、本人が世の中から奪い取る
利益のほうがより大きくなるものである。そうであっても、商売人たちはあたかも自分たちの労働が
公益に寄与しているかのように手を変え品を変え見せかけてくる。それらの偽りを全て見抜いて、
害悪を分析的に糾弾するのも難しいことであり(商売人もあえてそうしているのだから)、
結局は上の定義を実社会で厳密に援用して行くのもなかなか難しいこととなるのである。
実社会における勧善懲悪の実践のためには、どうしたって直観的、本能的な判断にも頼る必要が出てくる。
上二つのような理論的な定義を、偽善詐悪の限りを尽くす悪徳商人なども入り混じる世の中で
いちいち通用させ尽くすことにこそ無理があるから、善悪の分別を漠然とした理念に止めて、
己れの直観に基づく勧善懲悪こそを実践して行く必要がある。
しかし、結局のところこれらは不可分な関係にあるのであり、
全くの別物として捉えてまでいいものではないのである。
善徳は結局のところ公益寄与であり、罪悪は結局のところ公的害悪である。
ただ、人間必ずしも善行ばかりをやっていられるものでもなければ、悪行ばかりに専らでいるものでも
ないから、純粋な公益寄与か公的害悪ばかりを善や悪として捉えていると実情からかけ離れることになる。
金融詐欺で世界中に多大なる損害を及ぼしておきながら、それによって得た金の一部で貧窮者を救済したり
する場合もあり、その救済という部分だけをみれば善行のように思えたりすることもあるわけだから、
上記のような結局論ばかりを念頭に置くこともあまり奨められたものではないのである。
己れが天下に及ぼしている公益が公害を上回れば善、公害が公益を上回れば悪である。
これならより厳密な善悪の定義になるが、これまた実社会における分析的な把握は困難である。
商売なんていう職業は大元のところ、商売人本人が世の中に及ぼす利益よりも、本人が世の中から奪い取る
利益のほうがより大きくなるものである。そうであっても、商売人たちはあたかも自分たちの労働が
公益に寄与しているかのように手を変え品を変え見せかけてくる。それらの偽りを全て見抜いて、
害悪を分析的に糾弾するのも難しいことであり(商売人もあえてそうしているのだから)、
結局は上の定義を実社会で厳密に援用して行くのもなかなか難しいこととなるのである。
実社会における勧善懲悪の実践のためには、どうしたって直観的、本能的な判断にも頼る必要が出てくる。
上二つのような理論的な定義を、偽善詐悪の限りを尽くす悪徳商人なども入り混じる世の中で
いちいち通用させ尽くすことにこそ無理があるから、善悪の分別を漠然とした理念に止めて、
己れの直観に基づく勧善懲悪こそを実践して行く必要がある。
すると、衆生に対する厳密な説明というのが追い付かなくなる。悪徳商人なんざを摘発するにしたって、
どんな悪いことをやって来たのかということをいちいち厳密に説明し尽くすのでは埒が明かない。
そうなるように悪徳商人の側こそはあの手この手の権謀術数の限りを尽くして来たのだから、
摘発に際して十分な説明が追い付かないこともまた、悪徳商人の側の自業自得というものである。
そしてそのような、直観的な方法に基づく勧善懲悪の指針を示したのが、他でもない儒学である。
孔子も全く利害と善悪を別物として扱っていたわけではないが、そもそも利害について語ること
自体が稀であったという(子罕第九・一)。実際的な勘定なども抜きにした純粋なな善悪論こそを
述べ立てていたのも、実は勧善懲悪の現実的な実践こそを目的としていたからなのであり、
だからといって現実への適用に無理があるなどと考えるのでは誤解となってしまうのである。
直観に基づく活動を尊重するためには、密教的なものに対する尊重もまた必要となる。
何もかもを明らかに説明されなければ気が済まないなどというのは、密教的なものへの尊重が足りない
からであり、それ自体、是正されて行かねばならない不埒さの一種なのである。そのための手段は、
仏門の密教への尊崇でもいいし、神道の神への誠意ある崇敬でもかまわない、信教などを抜きにして、
「密談中らしき部屋があるようなら立ち入るな(礼記・曲礼上第一)」という礼法に即するのでもいい。
何もかもをあからさまにしてしまおうとする意地汚さすら正されたなら、それでいいのである。
「事典を制し、法罪を正す」
「諸事の典礼を制して、法の定める所の罪や罰を正す。
(そもそも悪法を正して善法に替え、それを守らせることこそが自他の善行となるのだから、
法規に触れることを不善と見なしもしないようなことからしておかしい)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左子伝・文公六年より)
どんな悪いことをやって来たのかということをいちいち厳密に説明し尽くすのでは埒が明かない。
そうなるように悪徳商人の側こそはあの手この手の権謀術数の限りを尽くして来たのだから、
摘発に際して十分な説明が追い付かないこともまた、悪徳商人の側の自業自得というものである。
そしてそのような、直観的な方法に基づく勧善懲悪の指針を示したのが、他でもない儒学である。
孔子も全く利害と善悪を別物として扱っていたわけではないが、そもそも利害について語ること
自体が稀であったという(子罕第九・一)。実際的な勘定なども抜きにした純粋なな善悪論こそを
述べ立てていたのも、実は勧善懲悪の現実的な実践こそを目的としていたからなのであり、
だからといって現実への適用に無理があるなどと考えるのでは誤解となってしまうのである。
直観に基づく活動を尊重するためには、密教的なものに対する尊重もまた必要となる。
何もかもを明らかに説明されなければ気が済まないなどというのは、密教的なものへの尊重が足りない
からであり、それ自体、是正されて行かねばならない不埒さの一種なのである。そのための手段は、
仏門の密教への尊崇でもいいし、神道の神への誠意ある崇敬でもかまわない、信教などを抜きにして、
「密談中らしき部屋があるようなら立ち入るな(礼記・曲礼上第一)」という礼法に即するのでもいい。
何もかもをあからさまにしてしまおうとする意地汚さすら正されたなら、それでいいのである。
「事典を制し、法罪を正す」
「諸事の典礼を制して、法の定める所の罪や罰を正す。
(そもそも悪法を正して善法に替え、それを守らせることこそが自他の善行となるのだから、
法規に触れることを不善と見なしもしないようなことからしておかしい)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左子伝・文公六年より)
「力(特に剛力)」こそは、人間を世俗の汚濁や深刻な情欲と
切っても切れない関係に追いやってしまうものである。
力を競うのは修羅道であり、修羅道こそは人間を六道輪廻の業から引き止めて離すことがない。
特に100%純粋な修羅道は、ただただ腕力の強大さばかりを競い合い、技巧や謀略での勝利なども邪道とする。
歴史上に多々出没する「猪武者」こそはまさに純粋な修羅道を体現していて(項羽や呂布や不破数右衛門など)、
動乱にかけての名物的な存在ともなり得るものの、決して「最高の武人」たり得ているわけでもない点が共通する。
力を駆使する中にも、まだ剛柔織り交ぜる要素を織り込むようであれば、神仏の域にも達することがある。
合気柔術など小手先の腕力は全くといっていいほど用いず、姿勢制御や深層筋の潜在力だけで屈強な相手を
投げ飛ばしもする。和風プロレス化した今の柔道などにはほとんど見られなくなった「柔よく剛を制す(老子)」
という理念もまた天道に適うものであり、天道に適うからには、多少は世俗の汚濁を脱却しかけてもいるのだといえる。
ただ、修羅道から天道や仏道に向かうにかけて、単なる剛力の出しゃばる余地は次第になくなって行く。
修羅道然とした剣術である一刀流や次元流のほうが力にものをいわせる一方で、神道や仏道の理念も取り入れた
新当流や新陰流こそは腕力を超えたところにある崇高な理念に基づく武芸を旨としている。幕末に腕力で幕府から
政権を乗っ取ろうとした反幕勢力が主要な修得対象としていたのも一刀流や次元流であり、(ただし実際に倒幕を
決定付ける原因となったのは、連中が大阪堺の豪商から借金して外国の武器商人から購入した重火器であった)
力で何かを達成しようとするものにとっては、神仏の域に達するような武芸などもまた邪道扱いになるのである。
力の競い合いにかけて専らであろうとすることこそは、世俗の汚濁にまみれきる原因となる一方、
そんなことに専らでなけれはこそ、多少なりとも世俗の汚濁から離縁していくことができるようになる。
切っても切れない関係に追いやってしまうものである。
力を競うのは修羅道であり、修羅道こそは人間を六道輪廻の業から引き止めて離すことがない。
特に100%純粋な修羅道は、ただただ腕力の強大さばかりを競い合い、技巧や謀略での勝利なども邪道とする。
歴史上に多々出没する「猪武者」こそはまさに純粋な修羅道を体現していて(項羽や呂布や不破数右衛門など)、
動乱にかけての名物的な存在ともなり得るものの、決して「最高の武人」たり得ているわけでもない点が共通する。
力を駆使する中にも、まだ剛柔織り交ぜる要素を織り込むようであれば、神仏の域にも達することがある。
合気柔術など小手先の腕力は全くといっていいほど用いず、姿勢制御や深層筋の潜在力だけで屈強な相手を
投げ飛ばしもする。和風プロレス化した今の柔道などにはほとんど見られなくなった「柔よく剛を制す(老子)」
という理念もまた天道に適うものであり、天道に適うからには、多少は世俗の汚濁を脱却しかけてもいるのだといえる。
ただ、修羅道から天道や仏道に向かうにかけて、単なる剛力の出しゃばる余地は次第になくなって行く。
修羅道然とした剣術である一刀流や次元流のほうが力にものをいわせる一方で、神道や仏道の理念も取り入れた
新当流や新陰流こそは腕力を超えたところにある崇高な理念に基づく武芸を旨としている。幕末に腕力で幕府から
政権を乗っ取ろうとした反幕勢力が主要な修得対象としていたのも一刀流や次元流であり、(ただし実際に倒幕を
決定付ける原因となったのは、連中が大阪堺の豪商から借金して外国の武器商人から購入した重火器であった)
力で何かを達成しようとするものにとっては、神仏の域に達するような武芸などもまた邪道扱いになるのである。
力の競い合いにかけて専らであろうとすることこそは、世俗の汚濁にまみれきる原因となる一方、
そんなことに専らでなけれはこそ、多少なりとも世俗の汚濁から離縁していくことができるようになる。
相撲のように、むしろ力の競い合いを定型化して興行化してしまうことで、観衆たち自身が腕力を蓄えようとする
気概を萎えさせてしまう神事などもあるわけだが、その目的はやはり「力の適切な扱い」にこそ集約されていて、
適切に扱おうとするからには、腕力中毒による濁世へのしがらみなどを脱却する目的もまたあるのだといえる。
戦史上に名のある猪武者といえども、まだ力の扱いが適切なほうだったといえる。古今東西史上でも最大級の
猪武者だった西楚の覇王項羽も、自らが俗世の汚濁にまみれていることを否定したりまでしているのではなかった。
むしろ、そのやり過ぎな戦いぶりが、対抗馬であり漢帝国の祖となった劉邦に「あれほどにも強大な相手を
屈服させて天下を取った」という箔を付ける助けにもなったのだった。
「腕力こそは神の域にすら達する」という倒錯、これこそは力の不適切な扱いの最たるものである。
そこまで倒錯が深刻化しきったままの状態では、もはや本物の神仏の域に触れることはおろか、目に見える範囲に
近づくことすらも叶いはしない。失神状態仏滅状態でただただ俗世の汚濁にまみれきることしかできなくなってしまう。
出家でもしない限りは世俗に生きる常人として、「腕力こそは神の域にすら達する」という倒錯にまでは及ばない
でいること、これだけは必須条件である。ただただそれなりの力比べに乗ずることは、許容範囲内だったり、
ちょっと問題的だったりする。力の適切な扱いを旨として、柔よく剛を制することの合理性にまで配慮が
及ぶのならそれに越したことはなく、それでこそ自分自身が神仏の域にすら触れることができるようにもなる。
鬼畜の領域、修羅の領域、神仏の領域。人間が進取することまでもが可とされ得るのは、後二つのみである。
気概を萎えさせてしまう神事などもあるわけだが、その目的はやはり「力の適切な扱い」にこそ集約されていて、
適切に扱おうとするからには、腕力中毒による濁世へのしがらみなどを脱却する目的もまたあるのだといえる。
戦史上に名のある猪武者といえども、まだ力の扱いが適切なほうだったといえる。古今東西史上でも最大級の
猪武者だった西楚の覇王項羽も、自らが俗世の汚濁にまみれていることを否定したりまでしているのではなかった。
むしろ、そのやり過ぎな戦いぶりが、対抗馬であり漢帝国の祖となった劉邦に「あれほどにも強大な相手を
屈服させて天下を取った」という箔を付ける助けにもなったのだった。
「腕力こそは神の域にすら達する」という倒錯、これこそは力の不適切な扱いの最たるものである。
そこまで倒錯が深刻化しきったままの状態では、もはや本物の神仏の域に触れることはおろか、目に見える範囲に
近づくことすらも叶いはしない。失神状態仏滅状態でただただ俗世の汚濁にまみれきることしかできなくなってしまう。
出家でもしない限りは世俗に生きる常人として、「腕力こそは神の域にすら達する」という倒錯にまでは及ばない
でいること、これだけは必須条件である。ただただそれなりの力比べに乗ずることは、許容範囲内だったり、
ちょっと問題的だったりする。力の適切な扱いを旨として、柔よく剛を制することの合理性にまで配慮が
及ぶのならそれに越したことはなく、それでこそ自分自身が神仏の域にすら触れることができるようにもなる。
鬼畜の領域、修羅の領域、神仏の領域。人間が進取することまでもが可とされ得るのは、後二つのみである。
「此こに人有りて、力は一匹の雛に勝うることも能わずといわば、則ち力無き人と為すも、
今百鈞を挙ぐると曰わば、則ち力有る人と為さんや。然れば則ち烏獲の任を挙ぐれば、是れ亦た烏獲と為すのみ。
夫れ人豈に勝えざるを以って患いと為さんや。為さざるのみ。徐行して長者に後る、之れを弟と謂い、
疾行して長者に先んずる、之れを不弟と謂う。夫れ徐行は、豈に人の能わざる所たらんや。為さぬ所なり」
「ここに一人の人間がいて、アヒルの雛一羽も持ち上げることができないというなら、みな彼を力のない人間だ
と見なすだろうが、もし百鈞(約1.8トン)のものすら持ち上げられるというなら、誰しもが力ある人間だと
見なすだろう。(伝説上の力士である)烏獲が持ち上げられたものを自分も持ち上げられるというのなら、
その人間もまた烏獲並みだと見なされるだろう。ただそれだけのことなのであり、どうして力がないことなどを
憂いとする必要があるだろうか。自分がゆっくり歩いて年長者の後ろを行くのは悌順なことだが、さっさと
走り去って年長者の先を行くようならこれは不悌である。どうして力がないからといって、徐行して年長者の
後を行くことができなかったりするだろう。ただそうあろうとする心がけがないだけのことだろう。
(儒家の司る人道もまた、力の有無ではなく、真心の有無こそを第一の問題としている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・告子章句下・二より)
今百鈞を挙ぐると曰わば、則ち力有る人と為さんや。然れば則ち烏獲の任を挙ぐれば、是れ亦た烏獲と為すのみ。
夫れ人豈に勝えざるを以って患いと為さんや。為さざるのみ。徐行して長者に後る、之れを弟と謂い、
疾行して長者に先んずる、之れを不弟と謂う。夫れ徐行は、豈に人の能わざる所たらんや。為さぬ所なり」
「ここに一人の人間がいて、アヒルの雛一羽も持ち上げることができないというなら、みな彼を力のない人間だ
と見なすだろうが、もし百鈞(約1.8トン)のものすら持ち上げられるというなら、誰しもが力ある人間だと
見なすだろう。(伝説上の力士である)烏獲が持ち上げられたものを自分も持ち上げられるというのなら、
その人間もまた烏獲並みだと見なされるだろう。ただそれだけのことなのであり、どうして力がないことなどを
憂いとする必要があるだろうか。自分がゆっくり歩いて年長者の後ろを行くのは悌順なことだが、さっさと
走り去って年長者の先を行くようならこれは不悌である。どうして力がないからといって、徐行して年長者の
後を行くことができなかったりするだろう。ただそうあろうとする心がけがないだけのことだろう。
(儒家の司る人道もまた、力の有無ではなく、真心の有無こそを第一の問題としている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・告子章句下・二より)
とりあえず板だとたたかれるのでこちらに書きます。
ほぼ毎日読ませてもらってるぜ。ではもう寝ますお休み。
ほぼ毎日読ませてもらってるぜ。ではもう寝ますお休み。
人間はその本性が善だから、外物に囚われることなく己れの本性に立ち返ることでこそ、
善思善言善行を為すことができる。その逆に、外物に囚われて己れの本性を見失うことでこそ、
悪思悪言悪行に走ってしまう。故に、自力作善を基本として行くことこそは真に善徳の推進とも
なる一方、他力本願でいることはそれだけでも罪悪の積み重ねになってしまいがちなのである。
一時的に人に頼るとか頼らないとかいった段階の話ではなく、己れの心持ちが常日頃から
自律的であるか他律的であるかということこそが問題である。人に頼るか頼らないかでいえば、
人間は誰しもがお互いに頼り合うことでしかやっていけない生き物なのだから、頼るしかない。
そうであってなお、自らの心持ちが本質的に独立的であることが善徳の推進につながって行く一方、
本当に心持ちから完全に頼りきり、依存第一な状態でしかいられないことが罪悪に繋がるのである。
依存第一の状態を極大化させたところにこそあるのが、自分の見失いである。
自らの心を完全に失って、単なる情報処理機械も同然な脳内状態でしかいられなくなる状態、
そこでこそ、人は絶対に善行を為すことも、善徳の実在を計り知ることすらも適わなくなる。
確信犯の罪人や悪人はおおむねそういった精神状態であり、サイコパスともなれば確実にそうである。
そこに至る過程は人さまざまであり、あからさまな罪悪に手を染めることでそうなるとも限らない。
人の真心を蔑ろにするような世知辛い世の中の荒波にもまれることでそうなってしまうこともある。
ただ、そうなってしまうほどにも世の中が世知辛いのは、やっぱり世の中のどこかで致命的な
罪悪が積み重ねられてもいるからであり、自分が知らず知らずのうちからその従犯と化せられて
しまう過程として、殺伐とした世の中に嫌らしく順応させられてしまうようなことがあるのである。
一時的な頼り合いではなく、恒久的な心持ちからの依存状態を促すもの——そんなものが
あるとすれば、これこそは人々に罪悪の積み重ねをけしかける元凶の最たるものだといえる。
少なくとも、人々から善思善言善行といった選択肢を完全に奪い去るものであり、どんなに無害な
教条に止め置かれた所で、所詮は不善を最小限に抑える程度の効果しか期待できないものである。
善思善言善行を為すことができる。その逆に、外物に囚われて己れの本性を見失うことでこそ、
悪思悪言悪行に走ってしまう。故に、自力作善を基本として行くことこそは真に善徳の推進とも
なる一方、他力本願でいることはそれだけでも罪悪の積み重ねになってしまいがちなのである。
一時的に人に頼るとか頼らないとかいった段階の話ではなく、己れの心持ちが常日頃から
自律的であるか他律的であるかということこそが問題である。人に頼るか頼らないかでいえば、
人間は誰しもがお互いに頼り合うことでしかやっていけない生き物なのだから、頼るしかない。
そうであってなお、自らの心持ちが本質的に独立的であることが善徳の推進につながって行く一方、
本当に心持ちから完全に頼りきり、依存第一な状態でしかいられないことが罪悪に繋がるのである。
依存第一の状態を極大化させたところにこそあるのが、自分の見失いである。
自らの心を完全に失って、単なる情報処理機械も同然な脳内状態でしかいられなくなる状態、
そこでこそ、人は絶対に善行を為すことも、善徳の実在を計り知ることすらも適わなくなる。
確信犯の罪人や悪人はおおむねそういった精神状態であり、サイコパスともなれば確実にそうである。
そこに至る過程は人さまざまであり、あからさまな罪悪に手を染めることでそうなるとも限らない。
人の真心を蔑ろにするような世知辛い世の中の荒波にもまれることでそうなってしまうこともある。
ただ、そうなってしまうほどにも世の中が世知辛いのは、やっぱり世の中のどこかで致命的な
罪悪が積み重ねられてもいるからであり、自分が知らず知らずのうちからその従犯と化せられて
しまう過程として、殺伐とした世の中に嫌らしく順応させられてしまうようなことがあるのである。
一時的な頼り合いではなく、恒久的な心持ちからの依存状態を促すもの——そんなものが
あるとすれば、これこそは人々に罪悪の積み重ねをけしかける元凶の最たるものだといえる。
少なくとも、人々から善思善言善行といった選択肢を完全に奪い去るものであり、どんなに無害な
教条に止め置かれた所で、所詮は不善を最小限に抑える程度の効果しか期待できないものである。
そんなものの享受が横行してしまっているせいで、人々がみな善性を湛えた己れの心を
見失ってしまっているような状況において、人々をその心から正して行ってやるなどというのも、
順序の取り違えになるといえる。自らの本然からの善性を完全に見失わせてしまうような諸々の
外物の除去だとか、善性を見失った状態での人々の妄動の制限だとかの、外的な措置をそれなりに
講じてから、その後に己れの本性たる善性に気づかせて行くほうが、順序としても正しいといえる。
最悪の濁世における、実力行使による矯正の優先、それぐらいは確かに許容せざるを得ないことでも
あるらしい。だからといって「誠意正心修身斉家治国平天下(大学)」といった、人々の心からの
成長やそれに基づく治世などが全く蔑ろにされたりしてもならない。実力での矯正は、せいぜい
最悪の乱世の収拾のめどが立つあたりまで。そこから先は、人々の善性を養生することでの
低コスト高パフォーマンスかつ堅実な統治こそを主体として行くべきである。
どこまでも実力支配一辺倒でい続けるというのなら、せいぜい独裁主義支配や共産主義支配の
レベルに止まるばかり。平安時代の日本のような理想的な文治はおろか、それなりに人々の善性をも
重んじていた武家時代の実力支配にすら、為政の健全度で及ぶことはない。未だ実力支配が旺盛で
ある時期からでも、人々の本性からの善性への尊重ぐらいはあるべきであり、それに基づいて、
己れの心を見失ってしまっている愚人たちへの相応な扱いにも及んで行くべきなのである。
心ないものたちの非道が横行する世の中と、それをただ実力で押さえつけるだけ世の中と、
どちらのほうがよりマシかすら判別のしようもない。どちらも最悪にろくでもないという他はなく、
そのような両極端への振り切れから脱却して行くことこそをマシ以上の指針とすべきである。
人間の本性からの善性を蔑ろにしたままでいるような状態全般からの脱却のあらんことを。
見失ってしまっているような状況において、人々をその心から正して行ってやるなどというのも、
順序の取り違えになるといえる。自らの本然からの善性を完全に見失わせてしまうような諸々の
外物の除去だとか、善性を見失った状態での人々の妄動の制限だとかの、外的な措置をそれなりに
講じてから、その後に己れの本性たる善性に気づかせて行くほうが、順序としても正しいといえる。
最悪の濁世における、実力行使による矯正の優先、それぐらいは確かに許容せざるを得ないことでも
あるらしい。だからといって「誠意正心修身斉家治国平天下(大学)」といった、人々の心からの
成長やそれに基づく治世などが全く蔑ろにされたりしてもならない。実力での矯正は、せいぜい
最悪の乱世の収拾のめどが立つあたりまで。そこから先は、人々の善性を養生することでの
低コスト高パフォーマンスかつ堅実な統治こそを主体として行くべきである。
どこまでも実力支配一辺倒でい続けるというのなら、せいぜい独裁主義支配や共産主義支配の
レベルに止まるばかり。平安時代の日本のような理想的な文治はおろか、それなりに人々の善性をも
重んじていた武家時代の実力支配にすら、為政の健全度で及ぶことはない。未だ実力支配が旺盛で
ある時期からでも、人々の本性からの善性への尊重ぐらいはあるべきであり、それに基づいて、
己れの心を見失ってしまっている愚人たちへの相応な扱いにも及んで行くべきなのである。
心ないものたちの非道が横行する世の中と、それをただ実力で押さえつけるだけ世の中と、
どちらのほうがよりマシかすら判別のしようもない。どちらも最悪にろくでもないという他はなく、
そのような両極端への振り切れから脱却して行くことこそをマシ以上の指針とすべきである。
人間の本性からの善性を蔑ろにしたままでいるような状態全般からの脱却のあらんことを。
「昊天を瞻卬するも、嘒たる其の星の有るのみ。大夫君子よ、昭め仮みて贏る無かれ。
大命も止みて近くも、爾じが成イサオを棄つる無かれ。何をか求めて我が為めにせん、
以て庶正を戻せんとて。昊天を瞻卬するにも、曷しか恵みて其れ寧からん」
「天上を見上げてもまたたく星があるばかりで、天の助けなどを期待すべくもない。
君子大夫たちよ、だからといって怠るようなこともせず、よく謹んで勤めに励むがよい。
大いなる天命に与ることもできなくなって久しいが、だからといって己れの功業を軽んじてもならない。
どうして自分のためなどであろうか、ただ正しき民たちに利するため。天上を見上げれば、
いつかは天もまた恵みを施してこの世を安んじてくれるかもしれぬ。(天からの恵みなど全く
当てにせず修善に励み、恵みがあるとてそれは衆生のためにとする。徹底した自力作善志向)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・蕩之什・雲漢より)
大命も止みて近くも、爾じが成イサオを棄つる無かれ。何をか求めて我が為めにせん、
以て庶正を戻せんとて。昊天を瞻卬するにも、曷しか恵みて其れ寧からん」
「天上を見上げてもまたたく星があるばかりで、天の助けなどを期待すべくもない。
君子大夫たちよ、だからといって怠るようなこともせず、よく謹んで勤めに励むがよい。
大いなる天命に与ることもできなくなって久しいが、だからといって己れの功業を軽んじてもならない。
どうして自分のためなどであろうか、ただ正しき民たちに利するため。天上を見上げれば、
いつかは天もまた恵みを施してこの世を安んじてくれるかもしれぬ。(天からの恵みなど全く
当てにせず修善に励み、恵みがあるとてそれは衆生のためにとする。徹底した自力作善志向)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・蕩之什・雲漢より)
悪党をその心から正してやるなんてことも、もう望むべきでもない。
それこそ、心から正されることが最も困難な類いの人種であるのだから。
悪党を常人並みの心境にまで持って行ってやるぐらいまでは、
武力制圧だとか刑罰だとか禁治産だとかの実力行使にも頼らねばならない。
ただ、頼るのはそこまでであって、治世のための統治手段はあくまで、
「誠意正心修身斉家治国平天下」といった順序に則って行かねばならない。
心田の耕しを十八番としているのは何といっても仏門だから、
武力以上にも仏教に頼るぐらいのつもりでなければならない。
それこそ、心から正されることが最も困難な類いの人種であるのだから。
悪党を常人並みの心境にまで持って行ってやるぐらいまでは、
武力制圧だとか刑罰だとか禁治産だとかの実力行使にも頼らねばならない。
ただ、頼るのはそこまでであって、治世のための統治手段はあくまで、
「誠意正心修身斉家治国平天下」といった順序に則って行かねばならない。
心田の耕しを十八番としているのは何といっても仏門だから、
武力以上にも仏教に頼るぐらいのつもりでなければならない。
http://bbs0.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/toriaezu/13594671...
「人間は本性が善だから、悪党を心から正せはしない。」
大したことないようでいて、実は重大な発見になっている。
ここんとこすらちゃんとわきまえとけば、独裁制の到来も防げる。
実力行使による悪党の摘発があまって、いつまでも世の中を
腕力によって支配し続けるようなことも防げるから。
「人間は本性が善だから、悪党を心から正せはしない。」
大したことないようでいて、実は重大な発見になっている。
ここんとこすらちゃんとわきまえとけば、独裁制の到来も防げる。
実力行使による悪党の摘発があまって、いつまでも世の中を
腕力によって支配し続けるようなことも防げるから。
つまり、逆に言えば、
そこんとこすらわきまえとけば、やり過ぎなども気にせずに、
心置きなく悪党どもを取り締まって行けるということでもある。
悪党を裁きにかけることと、無辜の市民を支配下に置くこととは、
全く別の性格を帯びたものとして捉えねばならなくなるから。
そこんとこすらわきまえとけば、やり過ぎなども気にせずに、
心置きなく悪党どもを取り締まって行けるということでもある。
悪党を裁きにかけることと、無辜の市民を支配下に置くこととは、
全く別の性格を帯びたものとして捉えねばならなくなるから。
邪教信仰はえてして、信者に自己を偽る迫真の演技を促すものである。
旧約信仰の肝要は、信者たるユダヤ人が政商犯としての横暴を深刻化させていくことを促すものであるし、
新約信仰の肝要も、信者に政商犯の横行を許容させたり、犯行の被害者となることを容認させたりする所にある。
真実のところを正しく指摘すれば上のようだけれども、自分が新旧約の信者となるためには、
むしろそんなことに気づいてはならないのである。ただ「神の物語」を享受するだけの盲目な子羊で
いられればこそ、内実がそれほどにも悪辣な犯罪寓意の教条を信仰対象にすらして行けるのである。
邪教にとって、真実を悟ることは信仰に結び付かず、真実から目を背けることこそは信仰に結び付く。
他人に信仰を促す邪教信者なども、「真実こそは直視しがたいもの」であるかのようにあえて触れ回ったりも
するけれども、(たとえば、ドストエフスキーが「カラマーゾフの兄弟」でイワンに語らせている現実描写など)
そのような直視しがたい現実を到来させているものこそは、邪教信仰に基づく政商の横行だったりするのであり、
現実が直視しがたいからといって盲目な信仰を促すこと自体、1セットのマッチポンプ戦略になっているのである。
新旧約信仰の内実という真実から目を背けさせて、ただただ神に帰依する、神の愛に服するなどという怠慢に
陥れるものこそは真性の信仰にも溺れてしまう。それこそ、邪教の側にとっての絶好のカモともなるわけだが、
そうならないためには、現実をよく直視して、決して見失ったりすることのない強靭な精神力こそが必要である。
すでに政商犯の暴慢が肥大化してしまっているようならば、邪教信仰を排した所にある現実社会の実情なども、
それはそれは見るに耐えない惨状と化してしまっていたりするわけだが、それでもなお現実を直視することを
やめないでいられるだけの胆力と、そこから着実に回復して行こうと志せるだけの大勇こそが必要となるのである。
邪教信仰自体は、精神の薄弱な女子供や小人男こそが享受しやすいものである。しかし、
邪教信仰がこの世にもたらす惨暴たるや、大の大人の男でも直視しがたい程のものであったりする。
旧約信仰の肝要は、信者たるユダヤ人が政商犯としての横暴を深刻化させていくことを促すものであるし、
新約信仰の肝要も、信者に政商犯の横行を許容させたり、犯行の被害者となることを容認させたりする所にある。
真実のところを正しく指摘すれば上のようだけれども、自分が新旧約の信者となるためには、
むしろそんなことに気づいてはならないのである。ただ「神の物語」を享受するだけの盲目な子羊で
いられればこそ、内実がそれほどにも悪辣な犯罪寓意の教条を信仰対象にすらして行けるのである。
邪教にとって、真実を悟ることは信仰に結び付かず、真実から目を背けることこそは信仰に結び付く。
他人に信仰を促す邪教信者なども、「真実こそは直視しがたいもの」であるかのようにあえて触れ回ったりも
するけれども、(たとえば、ドストエフスキーが「カラマーゾフの兄弟」でイワンに語らせている現実描写など)
そのような直視しがたい現実を到来させているものこそは、邪教信仰に基づく政商の横行だったりするのであり、
現実が直視しがたいからといって盲目な信仰を促すこと自体、1セットのマッチポンプ戦略になっているのである。
新旧約信仰の内実という真実から目を背けさせて、ただただ神に帰依する、神の愛に服するなどという怠慢に
陥れるものこそは真性の信仰にも溺れてしまう。それこそ、邪教の側にとっての絶好のカモともなるわけだが、
そうならないためには、現実をよく直視して、決して見失ったりすることのない強靭な精神力こそが必要である。
すでに政商犯の暴慢が肥大化してしまっているようならば、邪教信仰を排した所にある現実社会の実情なども、
それはそれは見るに耐えない惨状と化してしまっていたりするわけだが、それでもなお現実を直視することを
やめないでいられるだけの胆力と、そこから着実に回復して行こうと志せるだけの大勇こそが必要となるのである。
邪教信仰自体は、精神の薄弱な女子供や小人男こそが享受しやすいものである。しかし、
邪教信仰がこの世にもたらす惨暴たるや、大の大人の男でも直視しがたい程のものであったりする。
メディア戦略などの洗脳支配で、人々の精神力の平均値から大幅に引き下げられているような世の中で、
まともに政商犯の暴慢込みの世の中の実情と向き合って行けるような人間なども、そんなに多くいる
などとは期待できない。仮にいたとした所で、その人間が惨憺たる世の中の実情を着実に改善して
いけるだけの事務的な能力を持ち合わせているとも限らない。人々の文科系と体育会系への大別によって、
無知な蛮勇の持ち主と文弱の徒とにばかり、ほとんどの人間が枝分かれしてしまっていたりもするから、
智勇兼ね備えた真の壮士というものを期待すること自体、ほとんど望みのないことともなってしまっている。
——というような、現実との対峙者の側の不遇自体、すでに惨憺たる実情の一環ともなっている。
智勇兼備の英雄たち自身がほとんどこの世から絶やされてしまっているような最悪の状況において、
なおのこと着実な起死回生を目指して行ける指針があるとすれば、それはもはや真理の悟りでしかあるまい。
真理真実を悟った先にこそ、盲目な狂信に溺れている状態以上もの爽快さすらもがあるのだという
確信のみが、最悪の事態すらをも正善へと反して行けるだけの気概のよりどころともなるであろう。
真理に即してしか物事を改善して行く目処も立たないことを、今一度、真理の大切さを見直す機会と
することによって、このこの最悪の事態をも、一つのめでたい機縁に変えてしまえばいいのである。
「鳲鳩桑に在り、其の子は七つ。淑人君子、其の儀一なり。其の儀一なりて、心も結ばるるが如し」
「カッコウの親鳥が桑の木に止まり、その子供も七羽にまで至っている。仁徳ある君子もまた、
(多くの民を養って行くための)儀を一にする。ただ一つの儀にのみ、その心も結ばれている。
(むしろ、民を統治下に置く君子こそは民の化育に心を結ぶ。君子の志しとサービス精神の相違)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・曹風・鳲鳩より)
まともに政商犯の暴慢込みの世の中の実情と向き合って行けるような人間なども、そんなに多くいる
などとは期待できない。仮にいたとした所で、その人間が惨憺たる世の中の実情を着実に改善して
いけるだけの事務的な能力を持ち合わせているとも限らない。人々の文科系と体育会系への大別によって、
無知な蛮勇の持ち主と文弱の徒とにばかり、ほとんどの人間が枝分かれしてしまっていたりもするから、
智勇兼ね備えた真の壮士というものを期待すること自体、ほとんど望みのないことともなってしまっている。
——というような、現実との対峙者の側の不遇自体、すでに惨憺たる実情の一環ともなっている。
智勇兼備の英雄たち自身がほとんどこの世から絶やされてしまっているような最悪の状況において、
なおのこと着実な起死回生を目指して行ける指針があるとすれば、それはもはや真理の悟りでしかあるまい。
真理真実を悟った先にこそ、盲目な狂信に溺れている状態以上もの爽快さすらもがあるのだという
確信のみが、最悪の事態すらをも正善へと反して行けるだけの気概のよりどころともなるであろう。
真理に即してしか物事を改善して行く目処も立たないことを、今一度、真理の大切さを見直す機会と
することによって、このこの最悪の事態をも、一つのめでたい機縁に変えてしまえばいいのである。
「鳲鳩桑に在り、其の子は七つ。淑人君子、其の儀一なり。其の儀一なりて、心も結ばるるが如し」
「カッコウの親鳥が桑の木に止まり、その子供も七羽にまで至っている。仁徳ある君子もまた、
(多くの民を養って行くための)儀を一にする。ただ一つの儀にのみ、その心も結ばれている。
(むしろ、民を統治下に置く君子こそは民の化育に心を結ぶ。君子の志しとサービス精神の相違)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・曹風・鳲鳩より)
精子 Part9wwww
自らが社会的な弱者であることを認めるというのなら、
なぜ正規の王侯将相に統治されることを認められないのだろうか。
王侯のごとき封建社会の統治者こそは、弱者としての民たちの保護に務めることを本分としている。
民主主義社会の為政者のように民の強壮化を促したりするのでもなく、純粋な弱者としての民を保護下
に置き、その安全や福利厚生を保証するのと引き換えに、自分たちが「人の上に立つ人」たろうともする。
封建社会において為政者が上位の存在として扱われるのも、それによって相対的な弱者としての
扱いが確立される民たちを保護下に置くためでこそある。にもかかわらず、王侯や士大夫に見下される
ことに反感を抱いて体制の転覆を企てたり、士民全人の平等を謳うような信教を好んだりするのは、
「自分たち民こそは強者である」というような思い込みと共にであればまだ話が通るが、
「自分たちこそは弱者である」という自認と共にであるのなら、完全に矛盾している。
実際のところ、為政者こそは極大級の軍事力すらをも保持することが公的に認められる存在だから、
公人と民間人とでどちらのほうが普遍的に強者であるのかといえば、それは公人のほうだといえる。
「軍事力も民を守るためにこそ存在する」、理念としてはそうであるが、民同士が大規模な詐欺行為
などによって利権の共食い争いを繰り広げていたりするようならば、一時的に民間社会こそを
軍事的な制圧下に置いて事態の沈静化を図ったりすることも一種の民の保護になるといえる。
一方で、民間人が民間人であるままに国家規模の軍事力を私有したりすることはできない。軍需産業
を牛耳って陰ながらの軍部支配を試みたりすることはできても、「これこそは俺を守るための私兵だ」
などと公言しつつ民間人が私有できる軍事力なんてのは、せいぜいテロ組織レベルに止まり続ける。
故に、コソコソと陰ながらに済ますこともできないような極大級、大局規模の領域において、
民間人が正規の公人に実力行使の能力面で勝るようなことも決してありはしないのである。
なぜ正規の王侯将相に統治されることを認められないのだろうか。
王侯のごとき封建社会の統治者こそは、弱者としての民たちの保護に務めることを本分としている。
民主主義社会の為政者のように民の強壮化を促したりするのでもなく、純粋な弱者としての民を保護下
に置き、その安全や福利厚生を保証するのと引き換えに、自分たちが「人の上に立つ人」たろうともする。
封建社会において為政者が上位の存在として扱われるのも、それによって相対的な弱者としての
扱いが確立される民たちを保護下に置くためでこそある。にもかかわらず、王侯や士大夫に見下される
ことに反感を抱いて体制の転覆を企てたり、士民全人の平等を謳うような信教を好んだりするのは、
「自分たち民こそは強者である」というような思い込みと共にであればまだ話が通るが、
「自分たちこそは弱者である」という自認と共にであるのなら、完全に矛盾している。
実際のところ、為政者こそは極大級の軍事力すらをも保持することが公的に認められる存在だから、
公人と民間人とでどちらのほうが普遍的に強者であるのかといえば、それは公人のほうだといえる。
「軍事力も民を守るためにこそ存在する」、理念としてはそうであるが、民同士が大規模な詐欺行為
などによって利権の共食い争いを繰り広げていたりするようならば、一時的に民間社会こそを
軍事的な制圧下に置いて事態の沈静化を図ったりすることも一種の民の保護になるといえる。
一方で、民間人が民間人であるままに国家規模の軍事力を私有したりすることはできない。軍需産業
を牛耳って陰ながらの軍部支配を試みたりすることはできても、「これこそは俺を守るための私兵だ」
などと公言しつつ民間人が私有できる軍事力なんてのは、せいぜいテロ組織レベルに止まり続ける。
故に、コソコソと陰ながらに済ますこともできないような極大級、大局規模の領域において、
民間人が正規の公人に実力行使の能力面で勝るようなことも決してありはしないのである。
実際のところ、民間人は公人以上の強者たり得ないし、民間人も「自分たちこそは強者である」
などとまで開き直るようなこともほとんどない。いくら女が男に対してえらそうな顔をしようとも、
実際のところの能力面でまで男に敵わないのは、女もまた認めざるを得ないでいるのと同じように、
民間人もまた自分たちが本質的な弱者であることを大前提としながら、それなりに従順でいたり、
逆にルサンチマンを抱いて官民上下の序列の転覆をも図ったりする。とはいえ、後者によって
実現されるのもあくまで「カカア天下」止まりであり、そのせいで公人の側が天下国家の
総裁としての責任を放棄しての、世相の乱脈ばかりを招いたりすることともなるのである。
公人こそは強者であり、民間人こそは弱者である。その普遍的な前提に即して公人が民を保護
するというのなら、ある程度は官民上下の序列もまたわきまえられてしかるべきである。もちろん
強い者が弱い者を虐げるためではなく、強い者が弱い者を守ってやることを磐石化するためでこそある。
それを健全に実現して行くためには、官民上下の序列を否定したり蔑ろにしたりするような
思想信条をよしとしたりもしないことである。虚構の超越神への浮気によって実際の君子階級への
崇敬が疎かになったりするようならば、そのような神格信仰も害あるものとしていかねばならない。
あくまで、実際の君子士人への崇敬を助成するような神仏への信仰に限って正統とする。
ただ、それは世界中のほとんどの神仏が満たしている条件であり、それに即して邪神と見なされて
排されるような神のほうがむしろ少ない。実際の為政者への崇敬を損なわせるような邪神こそは、
八百万の神なり毛穴の数ほどの仏なりとの並存を禁止してまで、自らへの絶対的帰依を信者に強制
したりするものでもあるから、世界中の数多の神仏信仰系の信教にとっても、上のような正統異端の
条件付けが興隆の助けになることこそあれど、妨げになるようなことは決してないのである。
などとまで開き直るようなこともほとんどない。いくら女が男に対してえらそうな顔をしようとも、
実際のところの能力面でまで男に敵わないのは、女もまた認めざるを得ないでいるのと同じように、
民間人もまた自分たちが本質的な弱者であることを大前提としながら、それなりに従順でいたり、
逆にルサンチマンを抱いて官民上下の序列の転覆をも図ったりする。とはいえ、後者によって
実現されるのもあくまで「カカア天下」止まりであり、そのせいで公人の側が天下国家の
総裁としての責任を放棄しての、世相の乱脈ばかりを招いたりすることともなるのである。
公人こそは強者であり、民間人こそは弱者である。その普遍的な前提に即して公人が民を保護
するというのなら、ある程度は官民上下の序列もまたわきまえられてしかるべきである。もちろん
強い者が弱い者を虐げるためではなく、強い者が弱い者を守ってやることを磐石化するためでこそある。
それを健全に実現して行くためには、官民上下の序列を否定したり蔑ろにしたりするような
思想信条をよしとしたりもしないことである。虚構の超越神への浮気によって実際の君子階級への
崇敬が疎かになったりするようならば、そのような神格信仰も害あるものとしていかねばならない。
あくまで、実際の君子士人への崇敬を助成するような神仏への信仰に限って正統とする。
ただ、それは世界中のほとんどの神仏が満たしている条件であり、それに即して邪神と見なされて
排されるような神のほうがむしろ少ない。実際の為政者への崇敬を損なわせるような邪神こそは、
八百万の神なり毛穴の数ほどの仏なりとの並存を禁止してまで、自らへの絶対的帰依を信者に強制
したりするものでもあるから、世界中の数多の神仏信仰系の信教にとっても、上のような正統異端の
条件付けが興隆の助けになることこそあれど、妨げになるようなことは決してないのである。
「三老五更を大学に食うときは、天子も袒ぎて牲を割き、醤を執りて饋り、
爵を執りて酳い、冕して干を總る。諸侯の弟を教える所以なり。是の故に、
郷里に齒有りて、老窮を遺さず、強は弱を犯さず、衆は寡を暴かず、此れ大学由り来たる者なり」
「旧公卿で孤独の引退者たちを大学に招いた時は、天子も肩脱ぎして生贄を割き、
ひしおの料理でもてなし、名誉の爵位を送り、冕服に干という尊者に対する装束で舞いを踊る。
この大学での天子の振る舞いによる教化によって、方々の地域でも年長者を困窮させたままで
いるようなことがなくなり、強者が弱者を犯すことも、多数派が少数派を脅かすこともなくなる。
(天子が弱者を憐れみ尊ぶことでこそ、誰しもが自分以上の弱者を哀れむようになれるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭義第二十四より)
爵を執りて酳い、冕して干を總る。諸侯の弟を教える所以なり。是の故に、
郷里に齒有りて、老窮を遺さず、強は弱を犯さず、衆は寡を暴かず、此れ大学由り来たる者なり」
「旧公卿で孤独の引退者たちを大学に招いた時は、天子も肩脱ぎして生贄を割き、
ひしおの料理でもてなし、名誉の爵位を送り、冕服に干という尊者に対する装束で舞いを踊る。
この大学での天子の振る舞いによる教化によって、方々の地域でも年長者を困窮させたままで
いるようなことがなくなり、強者が弱者を犯すことも、多数派が少数派を脅かすこともなくなる。
(天子が弱者を憐れみ尊ぶことでこそ、誰しもが自分以上の弱者を哀れむようになれるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭義第二十四より)
人間にとってのあらゆる救いのなさは、全て生への執着を元凶としている。
生々流転、諸行無常の実世界において、個人の生存ばかりに専らであろうとすることが、
人間にとってのあらゆる苦しみの源となる。他人の命を重んずることではなく、
自分の命を偏重しようとすることこそは致命的な救いのなさの原因となり、
そのような傾向を人々に植え付けようとするような教条こそは、
人々に救いようのないほどもの苦しみをもたらすことともなる。
他人の命はむしろ重んずるべきであり、そのために自分の命をなげうつぐらいであるべきである。
しかも、そのような心情を一般化して世間に広く通用すらさせれば、個人個人はむしろ
自らの命を惜しみもしないにもかかわらず、お互いがお互いの命を尊重し合うことで
奪い合い殺し合いなども横行しない福利厚生の万全な世の中が形成されて行くこととなる。
しかもそれでこそ、人々が個人的な生への執着からなる苦悩を脱却して、わさわざ救いを
求めねばならなくなるような濁悪な思考や言行を帯びなくても済むようになるのである。
そのような世の中の実現を直接的に企図しているのが仏教であり、生への執着を
捨て去らせようとするその教条が個人の救いになるばかりでなく、上記のような
実利面からの福利厚生に満ち足りた世の中の到来をも実現して行けるのである。
儒学や神道やヒンズー教などはそこまでは行かず、生への執着を家の尊重などに善用することで
適正化して行こうとする。自分自身の生存もそれなりに重要なものとするが、それはあくまで
世のため人のため自分の家のための生であるとし、私的な生存欲などはやはり捨て去るのである。
長らく仏教振興に与ってきた日本人の感覚などからすれば、もはや生への執着など完全に
捨て去ってもいいぐらいの心持ちでいられもする。その上で、自分が大切な家の嫡子で
あったりする場合に限って、相応の世俗的な人生を営んで行くぐらいでちょうどだと思える。
これは、仏教も儒学も神道もという風に、世界中の教学のいいとこばかりを選別して
凝縮的に享受して来た、この日本ならではの恵まれた境遇に基づく心持ちだともいえる。
生々流転、諸行無常の実世界において、個人の生存ばかりに専らであろうとすることが、
人間にとってのあらゆる苦しみの源となる。他人の命を重んずることではなく、
自分の命を偏重しようとすることこそは致命的な救いのなさの原因となり、
そのような傾向を人々に植え付けようとするような教条こそは、
人々に救いようのないほどもの苦しみをもたらすことともなる。
他人の命はむしろ重んずるべきであり、そのために自分の命をなげうつぐらいであるべきである。
しかも、そのような心情を一般化して世間に広く通用すらさせれば、個人個人はむしろ
自らの命を惜しみもしないにもかかわらず、お互いがお互いの命を尊重し合うことで
奪い合い殺し合いなども横行しない福利厚生の万全な世の中が形成されて行くこととなる。
しかもそれでこそ、人々が個人的な生への執着からなる苦悩を脱却して、わさわざ救いを
求めねばならなくなるような濁悪な思考や言行を帯びなくても済むようになるのである。
そのような世の中の実現を直接的に企図しているのが仏教であり、生への執着を
捨て去らせようとするその教条が個人の救いになるばかりでなく、上記のような
実利面からの福利厚生に満ち足りた世の中の到来をも実現して行けるのである。
儒学や神道やヒンズー教などはそこまでは行かず、生への執着を家の尊重などに善用することで
適正化して行こうとする。自分自身の生存もそれなりに重要なものとするが、それはあくまで
世のため人のため自分の家のための生であるとし、私的な生存欲などはやはり捨て去るのである。
長らく仏教振興に与ってきた日本人の感覚などからすれば、もはや生への執着など完全に
捨て去ってもいいぐらいの心持ちでいられもする。その上で、自分が大切な家の嫡子で
あったりする場合に限って、相応の世俗的な人生を営んで行くぐらいでちょうどだと思える。
これは、仏教も儒学も神道もという風に、世界中の教学のいいとこばかりを選別して
凝縮的に享受して来た、この日本ならではの恵まれた境遇に基づく心持ちだともいえる。
そのような恵まれた環境下に与れなかったような人々が、まずどうすべきかを考えてみるに、
それは、「どういう風に恵まれていなかったか」によって対処法が変わるものだといえる。
欧米のように生への執着ばかりに専らでい過ぎた地域では、生への執着こそを捨てさせる
仏教のような教学の受容が推奨できるし、アフリカのようにむしろ個人個人の生命を蔑ろに
し過ぎているような地域では、古来からの民俗文化に神道や儒学の文化的手法を兼ね合わさせる
などして、家族単位での人々の生活をより尊重させて行くなどすればいいのではないかと思う。
今の人類社会は、総体的に生への執着が過剰化してしまっている状態である。
だからといって人々が不老不死の命を手に入れたりできるわけでもないから、
苦悩のはけ口を性向に追い求めて、世界人口を爆発的に増大させるまでに至っている。
人々に過剰な生への執着を捨てさせることこそは、人類にとっての急務である。
そのために第一に必要となるのは、人々の生への執着を極大化させる例の邪教の根絶である
けれども、ただ根絶するだけでその後に何らの精神的ケアも行わないままでいるのであれば、
邪教によって植えつけられた執着を持ち越して問題を引き起こし続けることにもなりかねない。
だからこそ、邪教を根絶した後の穴の埋め合わせにもまた勤しんで行かねばならないのである。
「我れ生の初め、庸き無きを尚いしに、我れ生の後、此の百凶に逢えり。尚くば寐ねて聡むる無からん」
「まだ生まれ付いて間もない頃から、私はただ無事な人生を送れたならばと思っていたのに、
しばらく生きてみれば、ただただ百千万の凶事に見舞われるばかり。願わくばずっと寝たままで
人の言うことも聞きたくはない。(人生の就寝以上ものつまらなさ。乱世を嘆く君子の歌でもある)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・王風・兔爰より)
それは、「どういう風に恵まれていなかったか」によって対処法が変わるものだといえる。
欧米のように生への執着ばかりに専らでい過ぎた地域では、生への執着こそを捨てさせる
仏教のような教学の受容が推奨できるし、アフリカのようにむしろ個人個人の生命を蔑ろに
し過ぎているような地域では、古来からの民俗文化に神道や儒学の文化的手法を兼ね合わさせる
などして、家族単位での人々の生活をより尊重させて行くなどすればいいのではないかと思う。
今の人類社会は、総体的に生への執着が過剰化してしまっている状態である。
だからといって人々が不老不死の命を手に入れたりできるわけでもないから、
苦悩のはけ口を性向に追い求めて、世界人口を爆発的に増大させるまでに至っている。
人々に過剰な生への執着を捨てさせることこそは、人類にとっての急務である。
そのために第一に必要となるのは、人々の生への執着を極大化させる例の邪教の根絶である
けれども、ただ根絶するだけでその後に何らの精神的ケアも行わないままでいるのであれば、
邪教によって植えつけられた執着を持ち越して問題を引き起こし続けることにもなりかねない。
だからこそ、邪教を根絶した後の穴の埋め合わせにもまた勤しんで行かねばならないのである。
「我れ生の初め、庸き無きを尚いしに、我れ生の後、此の百凶に逢えり。尚くば寐ねて聡むる無からん」
「まだ生まれ付いて間もない頃から、私はただ無事な人生を送れたならばと思っていたのに、
しばらく生きてみれば、ただただ百千万の凶事に見舞われるばかり。願わくばずっと寝たままで
人の言うことも聞きたくはない。(人生の就寝以上ものつまらなさ。乱世を嘆く君子の歌でもある)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・王風・兔爰より)
Out of Base.^^;;
この世には、陰陽法則に即して日向者(ひたなもの)として扱うべきものと、日陰者
として扱うべきものとの両方がある。男か女かでいえば、男を日向者、女を日陰者として
扱うべきだし、官か民かでいえば、官職者を日向者、民間人を日陰者として扱うべきである。
民間人同士のうちでも、農業や必需産業に従事するものを日向者として扱い、ガラクタ産業や
商業に従事するものを日陰者として扱うべきである。以上のような扱いを講じることでこそ、
陰陽法則に司られているこの世の中もまた、最善級にうまくいくようになるのである。
日陰者だからといって完全な排斥対象になるのではなく、日向者に順ずるものとしてこそ
模範的であるべきである。女が夫や子に尽くす良妻賢母たれば、それが女としての誉れ
ともなる。本家の嫡子の長男などと比べれば日陰者であるべき分家の庶子や次男三男、
さらには妾腹の私生児なども、学者や僧侶や、養子先での孝子などとしての精進に励めば、
孔子や一休和尚や鬼平のような高名を後世にまで轟かすことだってできなくはないのである。
一概な日向者でいることと、多少は日陰者に甘んずることと、どちらのほうがより
個人的な幸福に与れる可能性があるかといって、それはむしろ日陰者のほうである。
偉大な王侯将相の跡取りなどのほうが、もはや個人的な栄達などを追い求めて行ける
余地もほとんどないのに対し、劉邦や羽柴秀吉のような卑賤の身分の出身者であればこそ、
そこからどこまでも上を目指して行ける余地があるために、それに基づく僥倖をも
期待して行けるのである。(ただしこの場合にも高転びなどへの注意が必要である)
ただ日陰者であるべきような立場の人間が、そこからの栄達を目指して行くためには、
相当な苦労が必要ともなる。妾腹の私生児から大学者へと大成した孔子の血のにじむような
その努力具合も、本人が体系化した五経の記録内容の精緻さなどからも伺えることである。
として扱うべきものとの両方がある。男か女かでいえば、男を日向者、女を日陰者として
扱うべきだし、官か民かでいえば、官職者を日向者、民間人を日陰者として扱うべきである。
民間人同士のうちでも、農業や必需産業に従事するものを日向者として扱い、ガラクタ産業や
商業に従事するものを日陰者として扱うべきである。以上のような扱いを講じることでこそ、
陰陽法則に司られているこの世の中もまた、最善級にうまくいくようになるのである。
日陰者だからといって完全な排斥対象になるのではなく、日向者に順ずるものとしてこそ
模範的であるべきである。女が夫や子に尽くす良妻賢母たれば、それが女としての誉れ
ともなる。本家の嫡子の長男などと比べれば日陰者であるべき分家の庶子や次男三男、
さらには妾腹の私生児なども、学者や僧侶や、養子先での孝子などとしての精進に励めば、
孔子や一休和尚や鬼平のような高名を後世にまで轟かすことだってできなくはないのである。
一概な日向者でいることと、多少は日陰者に甘んずることと、どちらのほうがより
個人的な幸福に与れる可能性があるかといって、それはむしろ日陰者のほうである。
偉大な王侯将相の跡取りなどのほうが、もはや個人的な栄達などを追い求めて行ける
余地もほとんどないのに対し、劉邦や羽柴秀吉のような卑賤の身分の出身者であればこそ、
そこからどこまでも上を目指して行ける余地があるために、それに基づく僥倖をも
期待して行けるのである。(ただしこの場合にも高転びなどへの注意が必要である)
ただ日陰者であるべきような立場の人間が、そこからの栄達を目指して行くためには、
相当な苦労が必要ともなる。妾腹の私生児から大学者へと大成した孔子の血のにじむような
その努力具合も、本人が体系化した五経の記録内容の精緻さなどからも伺えることである。
ただ勉強に励んでいただけでなく、卑賤の身分からなる劣等感との葛藤に孔子も苛まれていた
はずである。その劣等感に取り込まれて非道な邪義を触れ回ったのがイエスだったりするわけで、
妾腹の私生児級の不遇者の大半はそのような暴発に陥るか、もしくは日陰者としての苦しみの中に
一生を尽くすかのいずれかに終わるものである。そのようなあり方では「やっぱり日陰者止まり」
という謗りを免れ得ないのはもちろんのこと、日陰者としての不遇を克服した先にこそある幸福に
与るような醍醐味をも得られはしない。日陰者が日陰者なりに大成して行くという選択肢は確かに
拓けているが、その道は大変細く険しく、生半な努力などでは到底踏破できないようになっている。
以上のような論及は、もちろん先天的な不遇を克服して行く場合にこそ言えることである。
自分から好き好んで悪徳商売のような賤業に従事したりするようなら、もはや自力で不遇を克服
して行く選択肢すらをもかなぐり捨てているといえる。先天的な日陰者扱いの不遇を克服して
行くために必須となるのは、何といっても自助努力であり、自助努力こそは人並み以上でなければ
何も務まらない。自分から不遇の限りを尽くした挙句に誰かからの救いを期待するなんていう
選択肢こそはなく、それこそ誰からの同情も受けるに値しない道化としての自滅を招くのみである。
「王憂いに宅り、陰に亮すこと三祀。既に喪を免るるも、其れ惟れ言うこと弗し。(中略)曰く、
台れ四方に正たるを以って、惟れ徳の類からざるを恐る、茲の故に言わず。恭みて黙して道を思う」
「殷の王(武丁)は先代の死後、常に憂いの中にあり、三年もの間影ながらの生活に順じていた。
すでに服喪期間を過ぎてからも、ほとんどものを言わなかった。(これでは仕事にならないと憂えた
臣下が催促すると)王は言われた。『私は自分が四方の国々に対して正大な存在たるに相応しい
だけの徳を具えていないことを恐れている。そのためほとんどものも言わず、慎み黙って道を
懐い続けているのである』(影ながらの生活の中に慎み黙する中にこそ、徳を得るための道を
思うこともまたある。『伝道の書』の著者はそんなことは思いもよらなかったのだろう)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・説命上より)
はずである。その劣等感に取り込まれて非道な邪義を触れ回ったのがイエスだったりするわけで、
妾腹の私生児級の不遇者の大半はそのような暴発に陥るか、もしくは日陰者としての苦しみの中に
一生を尽くすかのいずれかに終わるものである。そのようなあり方では「やっぱり日陰者止まり」
という謗りを免れ得ないのはもちろんのこと、日陰者としての不遇を克服した先にこそある幸福に
与るような醍醐味をも得られはしない。日陰者が日陰者なりに大成して行くという選択肢は確かに
拓けているが、その道は大変細く険しく、生半な努力などでは到底踏破できないようになっている。
以上のような論及は、もちろん先天的な不遇を克服して行く場合にこそ言えることである。
自分から好き好んで悪徳商売のような賤業に従事したりするようなら、もはや自力で不遇を克服
して行く選択肢すらをもかなぐり捨てているといえる。先天的な日陰者扱いの不遇を克服して
行くために必須となるのは、何といっても自助努力であり、自助努力こそは人並み以上でなければ
何も務まらない。自分から不遇の限りを尽くした挙句に誰かからの救いを期待するなんていう
選択肢こそはなく、それこそ誰からの同情も受けるに値しない道化としての自滅を招くのみである。
「王憂いに宅り、陰に亮すこと三祀。既に喪を免るるも、其れ惟れ言うこと弗し。(中略)曰く、
台れ四方に正たるを以って、惟れ徳の類からざるを恐る、茲の故に言わず。恭みて黙して道を思う」
「殷の王(武丁)は先代の死後、常に憂いの中にあり、三年もの間影ながらの生活に順じていた。
すでに服喪期間を過ぎてからも、ほとんどものを言わなかった。(これでは仕事にならないと憂えた
臣下が催促すると)王は言われた。『私は自分が四方の国々に対して正大な存在たるに相応しい
だけの徳を具えていないことを恐れている。そのためほとんどものも言わず、慎み黙って道を
懐い続けているのである』(影ながらの生活の中に慎み黙する中にこそ、徳を得るための道を
思うこともまたある。『伝道の書』の著者はそんなことは思いもよらなかったのだろう)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・説命上より)
「泰山其れ頽れんか、梁木其れ壊れんか、哲人其れ萎まんか」
「泰山ですらもが崩れ落ちるのか、巨木すらもが折れ去るのか、哲人も衰え死ぬのか」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓上第三より)
孔子が晩年に死期を悟ったときに詠ったとされる歌。半ば尊大なようにも受け止められかねないが、
孔子自身の生まれの不遇さだとか、それをバネにしての努力研鑽による大成だとかをよく
慮ってみたならば、この歌も決して誇張表現などではなかったことが計り知れるのである。
母子家庭育ちの妾腹の私生児から、世界で最も子孫の多い偉人へと上り詰めたその由緒も、
決してまがい物だったりするのではなく、宇宙の真理にすら半ば合致しているものであった。
それでいて孔子は出家者や隠遁者などとは違って、旺盛な活動意欲や生存欲の持ち主でもあった。
ただそうであるというだけなら、生きる価値の無さにすらさいなまれることになりかねないような
「妾腹の私生児」という極度の逆境をはねのけて大成すればこそ、人一倍自尊心も強かったのである。
それも、根拠のない自尊心などではなく、磐石な根拠にこそ根ざした、きわめて安定的な自尊心。
妾腹の私生児にもかかわらずではなくだからこそ、それが得られた。純粋な自力作善のみによって
勝ち得た、磐石な根拠と共なる自尊心であればこそ、泰山ほどにも揺らぐことがなかったのだった。
確かにそれはきわめて困難なことであり、妾腹の私生児に生まれついたからといって誰しもが
それほどもの大成を実現できるなどとは決して言えないことである。ただ、上に書いたような
孔子の事績などもあればこそ、「妾腹の私生児=決して救われることのない不遇」などと開き直って、
不遇を極めることに陶酔したり、そのような状態の人間に同情したりすることも許されないのである。
自分が妾腹の私生児だからといって、孔子ほどもの大成はとうてい見込めない。
だとすれば隠遁者なり出家者なりとして日陰者の人生に徹すればいいのであり、
不遇に呑み込まれた自己こそをひけらかして同情を買うなんてことだけは自制すべきである。
「泰山ですらもが崩れ落ちるのか、巨木すらもが折れ去るのか、哲人も衰え死ぬのか」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓上第三より)
孔子が晩年に死期を悟ったときに詠ったとされる歌。半ば尊大なようにも受け止められかねないが、
孔子自身の生まれの不遇さだとか、それをバネにしての努力研鑽による大成だとかをよく
慮ってみたならば、この歌も決して誇張表現などではなかったことが計り知れるのである。
母子家庭育ちの妾腹の私生児から、世界で最も子孫の多い偉人へと上り詰めたその由緒も、
決してまがい物だったりするのではなく、宇宙の真理にすら半ば合致しているものであった。
それでいて孔子は出家者や隠遁者などとは違って、旺盛な活動意欲や生存欲の持ち主でもあった。
ただそうであるというだけなら、生きる価値の無さにすらさいなまれることになりかねないような
「妾腹の私生児」という極度の逆境をはねのけて大成すればこそ、人一倍自尊心も強かったのである。
それも、根拠のない自尊心などではなく、磐石な根拠にこそ根ざした、きわめて安定的な自尊心。
妾腹の私生児にもかかわらずではなくだからこそ、それが得られた。純粋な自力作善のみによって
勝ち得た、磐石な根拠と共なる自尊心であればこそ、泰山ほどにも揺らぐことがなかったのだった。
確かにそれはきわめて困難なことであり、妾腹の私生児に生まれついたからといって誰しもが
それほどもの大成を実現できるなどとは決して言えないことである。ただ、上に書いたような
孔子の事績などもあればこそ、「妾腹の私生児=決して救われることのない不遇」などと開き直って、
不遇を極めることに陶酔したり、そのような状態の人間に同情したりすることも許されないのである。
自分が妾腹の私生児だからといって、孔子ほどもの大成はとうてい見込めない。
だとすれば隠遁者なり出家者なりとして日陰者の人生に徹すればいいのであり、
不遇に呑み込まれた自己こそをひけらかして同情を買うなんてことだけは自制すべきである。
実際、孔子のような極度の不遇からの大成者が実在していればこそ、東洋社会においては不遇を
ひけらかしての人気取りなどは非とされて来た。特に、妾腹の私生児のような克服のしようの
ある不遇で同情を買おうなどとする人間には「甘ったれんな」という冷たい視線が注がれた。
それは別に間違ったことでもない、世界的に通用させても何ら問題のない常識的措置なのであり、
それにすら耐えられないなんていう薄弱者こそは社会的立場を追われたとしても仕方がないのである。
それが「ガサツ」だったりするのでもない。どちらかといえば、己れの精神の薄弱さのあまり
私利私益ばかりをむさぼって、遠方の他人を困窮や餓死にまで追い込んでおきながら、一向に意に
介さないでいたりすることのほうがよっぽどガサツである。そんなガサツさよりは、社会人として
最低限必要な厳しさとしての、克服可能な不遇に対する同情の抑制のほうを講じて行くべきである。
接ぎ木ではなく、種から生えた芽としてこれから育って行かねばならないものがあったとして、
「まだまだこれからだ」というような叱咤激励をかけてやるのが水遣りに相当するとすれば、
「大変だねえ」などと同情ばかりをかけるのは芽を無理に伸ばしたりすることに相当するといえる。
前者は成長を促す一方、後者はかえって芽を立ち枯れにさせる原因にすらなってしまう。これから
育って行こうとする芽に対する適切な助成のためにも、不埒な同情などは禁物なのである。
「災いを救いて鄰りを恤れむは道なり。道を行えば福有り」
「災いからの救いを企図し、隣りの被害者を憐れむのは道である。道を行えば福徳にも与れる。
(災いへの救助支援や憐憫は確かに人道に適っている。人道に適わなければこそ福もない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・僖公十三年より)
ひけらかしての人気取りなどは非とされて来た。特に、妾腹の私生児のような克服のしようの
ある不遇で同情を買おうなどとする人間には「甘ったれんな」という冷たい視線が注がれた。
それは別に間違ったことでもない、世界的に通用させても何ら問題のない常識的措置なのであり、
それにすら耐えられないなんていう薄弱者こそは社会的立場を追われたとしても仕方がないのである。
それが「ガサツ」だったりするのでもない。どちらかといえば、己れの精神の薄弱さのあまり
私利私益ばかりをむさぼって、遠方の他人を困窮や餓死にまで追い込んでおきながら、一向に意に
介さないでいたりすることのほうがよっぽどガサツである。そんなガサツさよりは、社会人として
最低限必要な厳しさとしての、克服可能な不遇に対する同情の抑制のほうを講じて行くべきである。
接ぎ木ではなく、種から生えた芽としてこれから育って行かねばならないものがあったとして、
「まだまだこれからだ」というような叱咤激励をかけてやるのが水遣りに相当するとすれば、
「大変だねえ」などと同情ばかりをかけるのは芽を無理に伸ばしたりすることに相当するといえる。
前者は成長を促す一方、後者はかえって芽を立ち枯れにさせる原因にすらなってしまう。これから
育って行こうとする芽に対する適切な助成のためにも、不埒な同情などは禁物なのである。
「災いを救いて鄰りを恤れむは道なり。道を行えば福有り」
「災いからの救いを企図し、隣りの被害者を憐れむのは道である。道を行えば福徳にも与れる。
(災いへの救助支援や憐憫は確かに人道に適っている。人道に適わなければこそ福もない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・僖公十三年より)
妾腹の私生児程度の不遇は、実際に孔子のように克服ができるものでもあるわけだから、
その不遇からなる悲哀にかられての暴発に及んで、非業の最期を辿ったことなどに
「聖性」を見出せたりするようなことも、決してないわけである。
そんなものに聖性を見出すような界隈があったとすれば、そんな界隈全体が一人前の
社会人としてやっていくにも値しない重度の精神薄弱者の集いであることが確かである。
実際、そのような持て囃すべきでないものを持て囃す慣習を持つ薄弱者の界隈である
キリスト教圏こそは、世界中にガン細胞並みの有害無益な悪影響ばかりを撒き散らし続けてもいる。
他者の不運や危難を憐れむ心、いわゆる「惻隠の情」それ自体は道理に適ったものである。(>>264の引用参照)
ただ、同情をかけるべき相手とそうでない相手とを分別するのもまた、一つの道理である。
人間の心に内在する本性としての善性を完全に見失っての悪逆非道に及んだ挙句、自業自得の
自滅に見舞われてしまったような人間にまで同情をかけたりはしないのも、一つの道義的措置である。
そんな人間に同情をかけて救ってやったりした所で、何も懲りることなしにまた同じ過ちを
繰り返すことになるだけなのだから、あえて同情もかけず、救いも講じないでいるべきなのである。
己れの善性ごと心を見失っているような人間を心から矯正して行くのも不可能なことであり、
常人並みの品性に立ち戻るまでは実力での矯正が必要となることもまた、すでに述べた通りである。
(>>245-251あたりの論議を参照)
故に、「地獄」と表現されるような状況もまた、必要悪たり得ることがあるわけである。
仏教などでは、地獄をあくまで心象の一つとして捉えているけれども、実際に社会上で酷烈な処罰だとか
社会的制限だとかを講じることがあるとすれば、そのような実力行使が処理対象となる人間にとっての
「地獄」となったりもするわけである。そのような地獄こそは、やはりどうしても必要となる場合がある。
その不遇からなる悲哀にかられての暴発に及んで、非業の最期を辿ったことなどに
「聖性」を見出せたりするようなことも、決してないわけである。
そんなものに聖性を見出すような界隈があったとすれば、そんな界隈全体が一人前の
社会人としてやっていくにも値しない重度の精神薄弱者の集いであることが確かである。
実際、そのような持て囃すべきでないものを持て囃す慣習を持つ薄弱者の界隈である
キリスト教圏こそは、世界中にガン細胞並みの有害無益な悪影響ばかりを撒き散らし続けてもいる。
他者の不運や危難を憐れむ心、いわゆる「惻隠の情」それ自体は道理に適ったものである。(>>264の引用参照)
ただ、同情をかけるべき相手とそうでない相手とを分別するのもまた、一つの道理である。
人間の心に内在する本性としての善性を完全に見失っての悪逆非道に及んだ挙句、自業自得の
自滅に見舞われてしまったような人間にまで同情をかけたりはしないのも、一つの道義的措置である。
そんな人間に同情をかけて救ってやったりした所で、何も懲りることなしにまた同じ過ちを
繰り返すことになるだけなのだから、あえて同情もかけず、救いも講じないでいるべきなのである。
己れの善性ごと心を見失っているような人間を心から矯正して行くのも不可能なことであり、
常人並みの品性に立ち戻るまでは実力での矯正が必要となることもまた、すでに述べた通りである。
(>>245-251あたりの論議を参照)
故に、「地獄」と表現されるような状況もまた、必要悪たり得ることがあるわけである。
仏教などでは、地獄をあくまで心象の一つとして捉えているけれども、実際に社会上で酷烈な処罰だとか
社会的制限だとかを講じることがあるとすれば、そのような実力行使が処理対象となる人間にとっての
「地獄」となったりもするわけである。そのような地獄こそは、やはりどうしても必要となる場合がある。
己れの心を見失ってまでの悪逆非道に走っているような人間がいれば、そのような人間に対して
特定的に施すべきものとしての酷烈な刑罰などが必要となるし、妾腹の私生児の暴発死ごときに同情を
抱いてしまうような精神縛弱者がいたとすれば、これまたそのような人間に特定的に施すべきものとしての
行為能力制限だとかが必要ともなる。これらこそは、実社会に到来する必要悪としての地獄だといえる。
地獄自体は必要悪であり、地獄を招かざるを得なくなるようなならず者の悪逆非道こそは不必要悪である。
そのようなならず者の活動を活発化させる教条などがあったとすれば、これこそは地獄の到来以上にも
不必要で有害無益な邪教であったことが確実であり、地獄の仕打ちを怨むとしても、地獄そのものではなく
そのような邪教こそを怨まねばならない。むしろそのような邪教こそは、言葉巧みに信者をたぶらかして
一時的にいい思いをさせてやったりもしたわけだが、それでも、そこにこそ地獄を招く元凶があったのだ
ということをわきまえて、全ての罪責はそこにばかりあったのだということを承っていかねばならない。
そんなものに依存してしまった自分こそは、救いようのない馬鹿だったことを認めねばならない。
「一隅を挙げるに三隅を以って反さざれば、則ち復せざるなり」
「一つの物事を挙げれば、それに三つの答えを返してくるぐらいの者でなければ、繰り返し物事を
教えてやるには値しない。(一度きりで満足という慢心の非。新井白石もキリシタンの形而上学が
一世代上止まりで、二世代や三世代上の形而上への想定を全く欠いていることを非難した)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・述而第七・八より)
特定的に施すべきものとしての酷烈な刑罰などが必要となるし、妾腹の私生児の暴発死ごときに同情を
抱いてしまうような精神縛弱者がいたとすれば、これまたそのような人間に特定的に施すべきものとしての
行為能力制限だとかが必要ともなる。これらこそは、実社会に到来する必要悪としての地獄だといえる。
地獄自体は必要悪であり、地獄を招かざるを得なくなるようなならず者の悪逆非道こそは不必要悪である。
そのようなならず者の活動を活発化させる教条などがあったとすれば、これこそは地獄の到来以上にも
不必要で有害無益な邪教であったことが確実であり、地獄の仕打ちを怨むとしても、地獄そのものではなく
そのような邪教こそを怨まねばならない。むしろそのような邪教こそは、言葉巧みに信者をたぶらかして
一時的にいい思いをさせてやったりもしたわけだが、それでも、そこにこそ地獄を招く元凶があったのだ
ということをわきまえて、全ての罪責はそこにばかりあったのだということを承っていかねばならない。
そんなものに依存してしまった自分こそは、救いようのない馬鹿だったことを認めねばならない。
「一隅を挙げるに三隅を以って反さざれば、則ち復せざるなり」
「一つの物事を挙げれば、それに三つの答えを返してくるぐらいの者でなければ、繰り返し物事を
教えてやるには値しない。(一度きりで満足という慢心の非。新井白石もキリシタンの形而上学が
一世代上止まりで、二世代や三世代上の形而上への想定を全く欠いていることを非難した)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・述而第七・八より)
イエスも甘ったれだし、そこに付いて行こうとした信者も甘ったれでしかない。
一人前の社会人としてやって行く上での、最低限の厳しさも受け付けられなかった甘ったれ。
地球規模での大罪を犯したのも、あくまでその結果に過ぎないであって、本質的な問題は、
社会人としてやって行くにも値しない甘ったれにすら権能を与えようとした所にこそある。
一人前の社会人としてやって行く上での、最低限の厳しさも受け付けられなかった甘ったれ。
地球規模での大罪を犯したのも、あくまでその結果に過ぎないであって、本質的な問題は、
社会人としてやって行くにも値しない甘ったれにすら権能を与えようとした所にこそある。
「願わくは善を伐ることなく、労を施すこと無けん(既出)」
「願わくは自らの善行を誇ることなく、他人に労役を課すようなこともないようにしたい」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・公冶長第五・二六より)
「勲労有るを挾みて問うは、〜皆な答えざる所なり」
「自分の仕事の功労を鼻にかけるような無礼者は、その質問に答えてやるにも値しない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・四三より)
俺も皮肉で自分の無為自然を誇ったりしてるがな。
いずれも今の世の中では全くわきまえられていない道徳的教条だといえる。
働いてなんぼ、働かせてなんぼなんてのは、道家思想だけでなく、
人間道徳上の勧善懲悪志向にも完全にもとっているのだ。
「願わくは自らの善行を誇ることなく、他人に労役を課すようなこともないようにしたい」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・公冶長第五・二六より)
「勲労有るを挾みて問うは、〜皆な答えざる所なり」
「自分の仕事の功労を鼻にかけるような無礼者は、その質問に答えてやるにも値しない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・四三より)
俺も皮肉で自分の無為自然を誇ったりしてるがな。
いずれも今の世の中では全くわきまえられていない道徳的教条だといえる。
働いてなんぼ、働かせてなんぼなんてのは、道家思想だけでなく、
人間道徳上の勧善懲悪志向にも完全にもとっているのだ。
聖書圏には、仁義道徳と、あと無為自然の徳に対する察知や理解が全く存在しない。
どちらかといえば、無為自然の徳に対する了解こそが全く欠けている。だからこそ、
人々が絶え間ない焦燥やルサンチマンにまみれた状態とも化してしまっている。
妾腹の私生児といえども、孔子のように社会的な大成を果たすことができる。
そこまでいかずとも、卑賤の身の上を恥じて安静を決め込んですらいたならば、暴発して
邪教を触れ回ったりするよりは、よっぽどマシな存在でいられるとはすでに述べたことである。
(道家の見地からすれば、そのほうが社会的大成以上にも上等なこととすらされる)
無為自然の徳を解さないことが、無根拠な劣等意識や嫉妬の原因ともなる。
「悪いことをするぐらいなら何もしないでいたほうがマシ」という事実関係をわきまえられて
すらいたなら、悪逆非道な犯罪稼業によって暴利を巻き上げてやりたい放題でいるような
畜生野郎などに対しては、当たり前なこととしての侮蔑意識を抱いたりするものである。
しかし、上記のような事実関係へのわきまえを欠いていたならば、なりふり構わぬ稼ぎで
富裕となっているような者に対する劣等感や羨望すらをも抱いてしまいかねないのである。
世界中の億万長者を「世界の偉人ランキング」の上位に並べ立ている欧米の経済誌なども、
無為自然の徳を全く解さない聖書信仰的な価値観に即して発行されているものである。
そんな連中はむしろ「世界の賤人ランキング」の上位にこそはべらせなければならないと、
無為自然の徳を解するものであれば考える。ただそう考えるだけでなく、それによって
賤人ランキングの上位者を心からの笑いものの対象として行きもする。
小百姓の末子や下級役人だった頃の高祖劉邦なども、そのような「いるよりも
いないほうがマシな権力者に対する心からの侮蔑意識」を抱いていたのである。
だからこそ、当時すでに相当な富豪でもあった呂氏のVIP御用達の宴会などにも
無一文で乗り込んで、好き勝手に飲食するなどの豪快な振る舞いにも及んでいたのだった。
そして、その豪放さをそのまま押し通した挙句に中華皇帝にまでのし上がった。
画像削除(by投稿者)
どちらかといえば、無為自然の徳に対する了解こそが全く欠けている。だからこそ、
人々が絶え間ない焦燥やルサンチマンにまみれた状態とも化してしまっている。
妾腹の私生児といえども、孔子のように社会的な大成を果たすことができる。
そこまでいかずとも、卑賤の身の上を恥じて安静を決め込んですらいたならば、暴発して
邪教を触れ回ったりするよりは、よっぽどマシな存在でいられるとはすでに述べたことである。
(道家の見地からすれば、そのほうが社会的大成以上にも上等なこととすらされる)
無為自然の徳を解さないことが、無根拠な劣等意識や嫉妬の原因ともなる。
「悪いことをするぐらいなら何もしないでいたほうがマシ」という事実関係をわきまえられて
すらいたなら、悪逆非道な犯罪稼業によって暴利を巻き上げてやりたい放題でいるような
畜生野郎などに対しては、当たり前なこととしての侮蔑意識を抱いたりするものである。
しかし、上記のような事実関係へのわきまえを欠いていたならば、なりふり構わぬ稼ぎで
富裕となっているような者に対する劣等感や羨望すらをも抱いてしまいかねないのである。
世界中の億万長者を「世界の偉人ランキング」の上位に並べ立ている欧米の経済誌なども、
無為自然の徳を全く解さない聖書信仰的な価値観に即して発行されているものである。
そんな連中はむしろ「世界の賤人ランキング」の上位にこそはべらせなければならないと、
無為自然の徳を解するものであれば考える。ただそう考えるだけでなく、それによって
賤人ランキングの上位者を心からの笑いものの対象として行きもする。
小百姓の末子や下級役人だった頃の高祖劉邦なども、そのような「いるよりも
いないほうがマシな権力者に対する心からの侮蔑意識」を抱いていたのである。
だからこそ、当時すでに相当な富豪でもあった呂氏のVIP御用達の宴会などにも
無一文で乗り込んで、好き勝手に飲食するなどの豪快な振る舞いにも及んでいたのだった。
そして、その豪放さをそのまま押し通した挙句に中華皇帝にまでのし上がった。
画像削除(by投稿者)
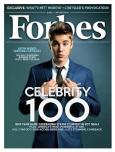 これも、無為自然の徳を十分に計り知っていればこその事績であり、権力者が揃いも揃って
これも、無為自然の徳を十分に計り知っていればこその事績であり、権力者が揃いも揃って いるよりもいないほうがマシな世の中のガンと化してしまっている時に、「悪いことをする
ぐらいなら何もしないでいたほうがマシ」という事実関係への了解を守り通せてすらいたなら、
小百姓すらもが皇帝にのし上がることだってできなくはないという史実的証拠になっている。
だからこそ、権力者に対する「ルサンチマン」などというものが不正であるともいえるのである。
権力者が、磐石な治世に貢献する徳治者であるのならば、民もまたそれを素直に尊崇すべきである。
また、権力者が「いないほうがマシ」なほどもの暴政を働く権力犯罪者であるというのなら、
その場合には「世の中のガン」としての権力者たちを透徹した見下しの対象とすればいいのであり、
権力者が優良である場合と劣悪である場合いずれにおいても、無為自然の徳をわきまえている
民が権力者を嫉妬の的にしたりする道理はないわけである。
庶民が権力者に対するルサンチマンを抱いたりするのも、無為自然の徳への了解が足りていないか、
もしくは皆無だからである。権力者が悪辣だからといって、庶民の身分からそれを羨望や嫉妬の
対象にするのも「事実誤認」の結果なのであり、その限りにおいて民の側もまた間抜けなのである。
その間抜けさからの脱却が可能であるのも、高祖劉邦の匹夫時代の振る舞いなどから察せる
ことであり、権力者へのルサンチマンを抱かないではいられないような間抜けな民であることを
開き直ったりすることも決して認められはしないのである。自らが妾腹の私生児だったりする
ことと同じように、間抜けな小市民だったりすることも克服しようとすればできることなのだから、
その惨めさを開き直ることを認めてもらおうとするような甘ったれであってもいけないのである。
植草! 乳首! ^^
「刑死しても生き返る」ということ自体、実際問題不可能な上に、
倫理的にも許されがたいことであるから、そんなものを自らの努力の指針にしてもならない。
たとえしてみたところで、決してそれが健全な尽力たり得たりすることもなく、
必ず人と世と自分とに有害無益な悪影響ばかりを及ぼす結果となることが間違いない。
実際問題不可能であるという以上に、生き返ることなど不可能なように刑死させてこその処罰である。
何らかの蘇生が可能となる手段が許容されていたりする時点で、当該の刑事のほうが不正となるだけである。
故に、刑死しても生き返ることを可とするのは、刑事処理の不正を可とするのと全く同義であり、
そんなことを奨励する神がいたとすれば、社会的不正を助長する邪神であることが自明である。
そこにこそ、「始めに毛筋ほどもの過ちを犯していれば、後々に千里の過ちともなる(礼記・経解第二十六)」
というところの「始めの毛筋ほどの過ち」がありもする。後付けでどんなに取り繕ったりしてみたところで
決して正しきれはしない、限りなき不正推進の種子が邪教の信者たちの心中に植え付けられることとなる。
ほとんどそれは、本人たち自身が自覚してもいないような所からその振る舞いを束縛して行くものである。
「今まさに私は神の教えを信じている」などと意識しているわけでもない時に、何気なく考えたことや口に
したこと、行ったことまでもが全て「不正の推進」に加担する代物となってしまう。仁義道徳に基づくような
公正な思考や言行と真逆の振る舞いを、ごくごく当たり前なこととして為してしまうようになるのである。
仮に、不滅の命を手に入れられたりするとしても、そのような罪人に対する処罰をまた別に工夫して
行かなければならなくなるのみである。永遠の命の持ち主であるからして、死刑が不能であるというのなら、
永遠に地獄の責め苦にあえがせ続けたり、無間地獄に延々と幽閉し続けたりするのみである。限りある命の持ち主
に対する処罰こそは死刑であるのだから、やはり刑死後に生き返ったりしないでこそ自明に公正なことだといえる。
倫理的にも許されがたいことであるから、そんなものを自らの努力の指針にしてもならない。
たとえしてみたところで、決してそれが健全な尽力たり得たりすることもなく、
必ず人と世と自分とに有害無益な悪影響ばかりを及ぼす結果となることが間違いない。
実際問題不可能であるという以上に、生き返ることなど不可能なように刑死させてこその処罰である。
何らかの蘇生が可能となる手段が許容されていたりする時点で、当該の刑事のほうが不正となるだけである。
故に、刑死しても生き返ることを可とするのは、刑事処理の不正を可とするのと全く同義であり、
そんなことを奨励する神がいたとすれば、社会的不正を助長する邪神であることが自明である。
そこにこそ、「始めに毛筋ほどもの過ちを犯していれば、後々に千里の過ちともなる(礼記・経解第二十六)」
というところの「始めの毛筋ほどの過ち」がありもする。後付けでどんなに取り繕ったりしてみたところで
決して正しきれはしない、限りなき不正推進の種子が邪教の信者たちの心中に植え付けられることとなる。
ほとんどそれは、本人たち自身が自覚してもいないような所からその振る舞いを束縛して行くものである。
「今まさに私は神の教えを信じている」などと意識しているわけでもない時に、何気なく考えたことや口に
したこと、行ったことまでもが全て「不正の推進」に加担する代物となってしまう。仁義道徳に基づくような
公正な思考や言行と真逆の振る舞いを、ごくごく当たり前なこととして為してしまうようになるのである。
仮に、不滅の命を手に入れられたりするとしても、そのような罪人に対する処罰をまた別に工夫して
行かなければならなくなるのみである。永遠の命の持ち主であるからして、死刑が不能であるというのなら、
永遠に地獄の責め苦にあえがせ続けたり、無間地獄に延々と幽閉し続けたりするのみである。限りある命の持ち主
に対する処罰こそは死刑であるのだから、やはり刑死後に生き返ったりしないでこそ自明に公正なことだといえる。
物理的に不可能であるという以上にも、原理的に不正であるのが「刑死しても生き返る」という事態であればこそ、
そんなものを思想信条の根本に据えてしまったならば、否応なく何もかもを不正に為してしまうようになるのである。
永遠の命を手に入れられるか入れられないかでいえばやはり手に入れられないが、仮に手に入れられるとしたところで、
不滅の命の持ち主が「刑死しても生き返る」などということを自由の証拠にしたりするのはやはりおかしなことである。
故に、そのような事態の信奉者が「原理的に不正な作為規範」を植えつけられることだけは間違いないのである。
それこそ、1+1を3にしたり、鹿を馬と言ったりする類いの、名辞(言葉の定義)の乱れからの過ちであり、
だからこそ現実問題を扱うか空想問題を扱うかに関わらず、間違いきった思考や言行に及んでしまうようになる。
しかも、「刑死しても生き返る」という事態は強度に現実問題にも根ざした不正であり、不正を為してしまいがちな
精神薄弱者には特に信奉しやすい代物でもある。それでいてなおかつ名辞の乱れに即した原理的な不正でもある
わけだから、ただ1+1=3だと言ったり、鹿を馬だと言ったりする以上にも悪質な意味合いを備えているのだといえる。
あらゆる名辞の乱れの中でも、特に現実問題に即して悪質なのが「刑死しても生き返る」という教条であればこそ、
それが不可能であることを科学的に実証しようなどとする試みが多々為されてきているけれども、本質的には、
当該の教条もまた1+1=3のような原理的な誤謬性を帯びた代物なのであり、だからこそ、それを信奉するものに
致命的な悪為を植え付けてしまうことこそが一番の問題なのである。そこの所をうやむやにしてしまうようなら、
刑死後の復活の不能性の科学的実証なども、かえって邪教の延命に加担してしまうことにすらなりかねないのである。
とにかく論争を続けていられればまだ生き延びられる、それがまた邪宗門にとっての助けとなってしまうのだから。
そんなものを思想信条の根本に据えてしまったならば、否応なく何もかもを不正に為してしまうようになるのである。
永遠の命を手に入れられるか入れられないかでいえばやはり手に入れられないが、仮に手に入れられるとしたところで、
不滅の命の持ち主が「刑死しても生き返る」などということを自由の証拠にしたりするのはやはりおかしなことである。
故に、そのような事態の信奉者が「原理的に不正な作為規範」を植えつけられることだけは間違いないのである。
それこそ、1+1を3にしたり、鹿を馬と言ったりする類いの、名辞(言葉の定義)の乱れからの過ちであり、
だからこそ現実問題を扱うか空想問題を扱うかに関わらず、間違いきった思考や言行に及んでしまうようになる。
しかも、「刑死しても生き返る」という事態は強度に現実問題にも根ざした不正であり、不正を為してしまいがちな
精神薄弱者には特に信奉しやすい代物でもある。それでいてなおかつ名辞の乱れに即した原理的な不正でもある
わけだから、ただ1+1=3だと言ったり、鹿を馬だと言ったりする以上にも悪質な意味合いを備えているのだといえる。
あらゆる名辞の乱れの中でも、特に現実問題に即して悪質なのが「刑死しても生き返る」という教条であればこそ、
それが不可能であることを科学的に実証しようなどとする試みが多々為されてきているけれども、本質的には、
当該の教条もまた1+1=3のような原理的な誤謬性を帯びた代物なのであり、だからこそ、それを信奉するものに
致命的な悪為を植え付けてしまうことこそが一番の問題なのである。そこの所をうやむやにしてしまうようなら、
刑死後の復活の不能性の科学的実証なども、かえって邪教の延命に加担してしまうことにすらなりかねないのである。
とにかく論争を続けていられればまだ生き延びられる、それがまた邪宗門にとっての助けとなってしまうのだから。
「徂く攸の民、室家相慶して曰く、予が后を徯つ。后来たらば其れ蘇らん」
「(殷の湯王が、夏の桀王の暴政によって疲弊させられていた天下の平定に臨むや、)
湯王が赴く所の民はみなこぞって大喜びしながら『わが君をお待ちしておりました。
大君が来られましたので、みな生き返るような気持ちでいます。』(聖王賢臣のごとき
権力道徳者こそは民を疲弊から生き返らせるものであるのに、イエスは権力者を端から
『罪人』などと決め付けて名辞をも歪める。そして自分一人の蘇生すら実現できはしな
かった。現実だけを見れば、劣悪至極な惨劇の黄金比以外の何物でもあり得てはいない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・仲虺之誥より)
「(殷の湯王が、夏の桀王の暴政によって疲弊させられていた天下の平定に臨むや、)
湯王が赴く所の民はみなこぞって大喜びしながら『わが君をお待ちしておりました。
大君が来られましたので、みな生き返るような気持ちでいます。』(聖王賢臣のごとき
権力道徳者こそは民を疲弊から生き返らせるものであるのに、イエスは権力者を端から
『罪人』などと決め付けて名辞をも歪める。そして自分一人の蘇生すら実現できはしな
かった。現実だけを見れば、劣悪至極な惨劇の黄金比以外の何物でもあり得てはいない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・仲虺之誥より)
世の中を乱世に陥れるのも治世に導くのも、結局は易の法則の範疇に止まることだが、
個々の人間、個々の部分的集団というのはどこまでも、易の法則の一翼だけを担うものである。
乱世をもたらす個人や部分集団、治世をもたらす個人や部分集団というものも別個のものであるのが
普遍的な事情であり、天下全土全世界を占めるほどもの大局からの乱世や治世をもたらす者である
のなら、それこそ絶対に両者が同一だったり、親和的だったりすることもあり得ないのである。
全世界、全宇宙を司る易の法則が「万物斉同」であるから、万事万物もその内側の部分的存在で
しかあり得ない。全てを超越する絶対者などを気取ってみたところで、所詮は部分的存在としての
宿命から逃れきることもできないのが、すでに量子論の不確定性原理からすらも察知されている。
故に、悪に手を染めた主体が同時に善を司る主体でもあり得たり、その逆だったりすることもない。
善悪をみそくそに扱おうとするものはそれ自体が高度な悪となってしまうだけなのであり、この世に
善悪が現出してしまった以上は、両者がその主体から別個のものとして存在するしかないのである。
善も悪も明瞭でないような状態、真理に即して善悪をも諦観するインド社会や平安時代の日本社会
などもまたあるわけだが、それとはまた別に善悪が分裂しきってしまっているような時代や世の中と
いうものがある。この地球人類社会においては、中国社会や武家時代の日本社会、そして中東社会
などが特に善悪の枝分かれが頻繁であり続けてきた社会だといえる。西洋社会ともなれば、もはや
悪一色に染まりきっていたとすらいえるが、その西洋社会と東洋社会を総合した全地球社会もまた、
やはり相当に善悪が大分裂して鬩ぎ合ってきた社会であるということがいえるわけである。
個々の人間、個々の部分的集団というのはどこまでも、易の法則の一翼だけを担うものである。
乱世をもたらす個人や部分集団、治世をもたらす個人や部分集団というものも別個のものであるのが
普遍的な事情であり、天下全土全世界を占めるほどもの大局からの乱世や治世をもたらす者である
のなら、それこそ絶対に両者が同一だったり、親和的だったりすることもあり得ないのである。
全世界、全宇宙を司る易の法則が「万物斉同」であるから、万事万物もその内側の部分的存在で
しかあり得ない。全てを超越する絶対者などを気取ってみたところで、所詮は部分的存在としての
宿命から逃れきることもできないのが、すでに量子論の不確定性原理からすらも察知されている。
故に、悪に手を染めた主体が同時に善を司る主体でもあり得たり、その逆だったりすることもない。
善悪をみそくそに扱おうとするものはそれ自体が高度な悪となってしまうだけなのであり、この世に
善悪が現出してしまった以上は、両者がその主体から別個のものとして存在するしかないのである。
善も悪も明瞭でないような状態、真理に即して善悪をも諦観するインド社会や平安時代の日本社会
などもまたあるわけだが、それとはまた別に善悪が分裂しきってしまっているような時代や世の中と
いうものがある。この地球人類社会においては、中国社会や武家時代の日本社会、そして中東社会
などが特に善悪の枝分かれが頻繁であり続けてきた社会だといえる。西洋社会ともなれば、もはや
悪一色に染まりきっていたとすらいえるが、その西洋社会と東洋社会を総合した全地球社会もまた、
やはり相当に善悪が大分裂して鬩ぎ合ってきた社会であるということがいえるわけである。
残念ながら、未だ世の中が善悪両極に振れきってしまっているこの地球人類社会において、
最大級の悪の主体たり得ているのはやはり欧米聖書圏であり、欧米人が正義の主体となることも
今後数百年は覚束ないこととなっている。だから、欧米人がこれからまず志すべきなのは、
正義の主体たる以上にも、善悪全体を諦観する仏教徒的なあり方だといえる。一方、
善悪懸隔の中での勧善懲悪を志して来た部類の東洋人は、その志しを貫徹するか、
あるいは善悪全体を諦観する境地の尊崇にも励むなどすればよい。
要は、それぞれに分をわきまえるべきだということであり、そこにしか世の中が改善されて
行く余地もないということである。世の中も宇宙の法則も超越する絶対者など存在し得ない、
そんなものを目指せば目指すだけ余計な負担をかけられた世の中のほうがダメになるのみである
ということをわきまえて、自らの立場に即した振る舞いを誰しもが心がけて行くべきなのである。
「人は以て恥すること無かる可からず。恥ずること無きを之れ恥ずれば、恥無し」
「人は決して恥じぬようなことがあってはならない。恥知らずであることを恥じるぐらいの
恥じらいがあってのみ、初めて恥から遠ざかることができる。(恥知らずはそれだけでも人道に悖る)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上六より)
最大級の悪の主体たり得ているのはやはり欧米聖書圏であり、欧米人が正義の主体となることも
今後数百年は覚束ないこととなっている。だから、欧米人がこれからまず志すべきなのは、
正義の主体たる以上にも、善悪全体を諦観する仏教徒的なあり方だといえる。一方、
善悪懸隔の中での勧善懲悪を志して来た部類の東洋人は、その志しを貫徹するか、
あるいは善悪全体を諦観する境地の尊崇にも励むなどすればよい。
要は、それぞれに分をわきまえるべきだということであり、そこにしか世の中が改善されて
行く余地もないということである。世の中も宇宙の法則も超越する絶対者など存在し得ない、
そんなものを目指せば目指すだけ余計な負担をかけられた世の中のほうがダメになるのみである
ということをわきまえて、自らの立場に即した振る舞いを誰しもが心がけて行くべきなのである。
「人は以て恥すること無かる可からず。恥ずること無きを之れ恥ずれば、恥無し」
「人は決して恥じぬようなことがあってはならない。恥知らずであることを恥じるぐらいの
恥じらいがあってのみ、初めて恥から遠ざかることができる。(恥知らずはそれだけでも人道に悖る)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上六より)
弱小であっても正しき行いに務めている者に報い、強大であっても過てる者には誅罰を下すのが
正しい世の中であり、その逆であるのが間違った世の中である。どんなに絶対的な超越者などと
あがめ立てられているような者であろうとも、邪悪であるようなら天罰を下す、それでこそ正しい世である。
綺麗ごとだどうだという以前に、単なる定義上から自然と導き出されるものとしての、正しい世の中。
そして、そういった世の中を実現して行こうとすることが綺麗ごと止まりになるのかといえば、
決してそんなこともない。世界経済をも先導する今の日本の経済力だとか、中国の人口増大力だとかも、
数百年から数千年に渡る「正しい世の中の希求」としての道徳統治の試みを基盤としてこそ
得られたものである。そんな試みを未だ企てた試しもない、「邪悪な超越者」が絶対神として
君臨することを是とし続けて来た欧米聖書圏たるや、人口面でも経済面でももはや劣勢な
立場に追いやられつつある。これこそは、正しい世の中の希求が国力の増大につながる一方、
間違った世の中の是認が国力の弱体化につながることを示した決定的な証拠ともなっている。
勝つためにこそ、正しい世の中の希求が有効である。
個人や小団体としての勝利なんざより、天下国家規模での勝利こそは、雄大かつ絶対的な勝利ともなるのだから、
真に絶大な勝利を克ち得ようと思うのなら、国力からの増大を決定付ける正しき世の中の追及をも試みて
行かないでいいわけがない。そのためには、破綻した物言いや邪悪な振る舞いに及ぶ部分的強者などの
討伐にも熱心であるべきであり、そんなものを絶対者などとして崇め立てる邪教の廃絶にも専念すべきである。
そもそも、邪悪な強者を絶対神などとして崇めたてるような邪教を好き好んで信仰し続けていたりしたなら、
自業自得での破滅すらもが免れ得なくなるから、そんな邪教を廃絶する他はないという事情もまた別にある。
ただ、そのような邪教の廃絶を済ませて後にも、絶対神とまでは行かない邪悪な強者の跳梁跋扈を容認したり
しているようなら、国家規模での弱小化が顕著化してしまい、最終的な敗亡に見舞われたりすることともなる
だろうから、そのような「人間でありながらの弱肉強食の是認」という性向からの脱却こそを図らねばならない。
正しい世の中であり、その逆であるのが間違った世の中である。どんなに絶対的な超越者などと
あがめ立てられているような者であろうとも、邪悪であるようなら天罰を下す、それでこそ正しい世である。
綺麗ごとだどうだという以前に、単なる定義上から自然と導き出されるものとしての、正しい世の中。
そして、そういった世の中を実現して行こうとすることが綺麗ごと止まりになるのかといえば、
決してそんなこともない。世界経済をも先導する今の日本の経済力だとか、中国の人口増大力だとかも、
数百年から数千年に渡る「正しい世の中の希求」としての道徳統治の試みを基盤としてこそ
得られたものである。そんな試みを未だ企てた試しもない、「邪悪な超越者」が絶対神として
君臨することを是とし続けて来た欧米聖書圏たるや、人口面でも経済面でももはや劣勢な
立場に追いやられつつある。これこそは、正しい世の中の希求が国力の増大につながる一方、
間違った世の中の是認が国力の弱体化につながることを示した決定的な証拠ともなっている。
勝つためにこそ、正しい世の中の希求が有効である。
個人や小団体としての勝利なんざより、天下国家規模での勝利こそは、雄大かつ絶対的な勝利ともなるのだから、
真に絶大な勝利を克ち得ようと思うのなら、国力からの増大を決定付ける正しき世の中の追及をも試みて
行かないでいいわけがない。そのためには、破綻した物言いや邪悪な振る舞いに及ぶ部分的強者などの
討伐にも熱心であるべきであり、そんなものを絶対者などとして崇め立てる邪教の廃絶にも専念すべきである。
そもそも、邪悪な強者を絶対神などとして崇めたてるような邪教を好き好んで信仰し続けていたりしたなら、
自業自得での破滅すらもが免れ得なくなるから、そんな邪教を廃絶する他はないという事情もまた別にある。
ただ、そのような邪教の廃絶を済ませて後にも、絶対神とまでは行かない邪悪な強者の跳梁跋扈を容認したり
しているようなら、国家規模での弱小化が顕著化してしまい、最終的な敗亡に見舞われたりすることともなる
だろうから、そのような「人間でありながらの弱肉強食の是認」という性向からの脱却こそを図らねばならない。
動物界では弱肉強食が当たり前であり、ただ単に強大な動物こそは、食物連鎖の頂点に立つなどして
最強たるわけだけれども、人間にまでそのような動物と同様の法則が通用すると思ったら大間違いである。
人間には動物と違って国家を形成する能力があり、国家単位での公益を企図することを通じて、個人的な
強大さを増進する場合以上もの勢力の底上げというものを実現して行くことができる。そこでこそ、漢帝国が
匈奴を屈服させたような「公の個に対する勝利」が実現できもするわけだから、強者たらんとするもの、決して
国家規模での勢力の底上げや、そのための正しい世の中の追及といった選択肢を無視してはならないのである。
国家規模での政財界の癒着だとか、軍産複合体の肥大化だとかによって、「邪悪なものこそが突出して強大化する」
ということが実際にある。今の資本主義諸国などもそうだし、殷代末期や秦代の中国、織豊時代の日本なども
その内に入るものであるが、むしろそのような政権が瓦解して後、仁徳を保った立場から天下を継ぐものこそが
それ以上の強大さを手に入れることもあり得る。始皇帝の代の秦帝国などは、匈奴からの侵略にもひどく苛まれて
いたのに対し、武帝の代の漢帝国などはもはや匈奴を圧倒し、次代の宣帝の頃には匈奴に朝貢すらさせていた
という記録など、まさに仁義なき皇帝の業を継いだ仁義ある皇帝がより強大たり得た実例を指し示してもいる。
仁徳あるもの、そもそも強大さばかりを追い求めず、まず第一には天下国家の安寧を企図するのが当然である
けれども、その結果として覇者以上にも強大な王者たり、武威でもまた史上空前たり得るような「おまけ」
に与れることもたまにある。故に、ただ精進滅私ばかりが仁政の全てだなどとも言えはしないのである。
「貴くして位无く、高くして民无く、賢人下位に在りて輔くる无し。是れを以て動きて悔い有るなり」
「貴いとしながら正式な位にも就かず、高いとしながらもまともに治めている民があるわけでもなく、
(身分が不審だから)低い身分にある賢人が助けてくれることもない。何をやっても悔いある結果しか招かない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・乾・上九・文言伝より)
最強たるわけだけれども、人間にまでそのような動物と同様の法則が通用すると思ったら大間違いである。
人間には動物と違って国家を形成する能力があり、国家単位での公益を企図することを通じて、個人的な
強大さを増進する場合以上もの勢力の底上げというものを実現して行くことができる。そこでこそ、漢帝国が
匈奴を屈服させたような「公の個に対する勝利」が実現できもするわけだから、強者たらんとするもの、決して
国家規模での勢力の底上げや、そのための正しい世の中の追及といった選択肢を無視してはならないのである。
国家規模での政財界の癒着だとか、軍産複合体の肥大化だとかによって、「邪悪なものこそが突出して強大化する」
ということが実際にある。今の資本主義諸国などもそうだし、殷代末期や秦代の中国、織豊時代の日本なども
その内に入るものであるが、むしろそのような政権が瓦解して後、仁徳を保った立場から天下を継ぐものこそが
それ以上の強大さを手に入れることもあり得る。始皇帝の代の秦帝国などは、匈奴からの侵略にもひどく苛まれて
いたのに対し、武帝の代の漢帝国などはもはや匈奴を圧倒し、次代の宣帝の頃には匈奴に朝貢すらさせていた
という記録など、まさに仁義なき皇帝の業を継いだ仁義ある皇帝がより強大たり得た実例を指し示してもいる。
仁徳あるもの、そもそも強大さばかりを追い求めず、まず第一には天下国家の安寧を企図するのが当然である
けれども、その結果として覇者以上にも強大な王者たり、武威でもまた史上空前たり得るような「おまけ」
に与れることもたまにある。故に、ただ精進滅私ばかりが仁政の全てだなどとも言えはしないのである。
「貴くして位无く、高くして民无く、賢人下位に在りて輔くる无し。是れを以て動きて悔い有るなり」
「貴いとしながら正式な位にも就かず、高いとしながらもまともに治めている民があるわけでもなく、
(身分が不審だから)低い身分にある賢人が助けてくれることもない。何をやっても悔いある結果しか招かない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・乾・上九・文言伝より)
世の中に広く仁政を施すためには、最低でも政商の根絶ぐらいは必須である。
政商が食客(死兵要員)や縦横家(悪徳外交家)までをも駆使することでの権力犯罪こそは、
天災や紛争以上もの仁政にとっての大敵であり、仁政を志す漢や唐のごとき
国家にとっても亡国級の禍いを招く元凶とすらなりかねないものである。
度し難いのは、政商自身が政商であるということを公表もせず、最悪の場合、
自分が政商と化してしまっていることに気づいてすらいない場合があるということである。
唐を滅ぼした黄巣の如きは、塩の密売などのあからさまな悪徳商人としての暗躍によって勢力を付けて
いたわけだからまだ分かりやすいが、後漢を滅ぼした曹家などは純粋な官職者(ただし元下級役人)でいた。
それでいて漢朝における専横の限りを尽くし、賄賂を基調とした政財界の癒着などにも基づく狭隘な
利権の占有によって帝位を奪い取ったわけで(ただし名目上は禅譲)、これなどは政商そのものが曹家を
隠れ蓑として、あまり大きな顔もしないでいるままに仁徳ある国家を滅ぼした事例にも当たっている。
多くの賄賂を役人に贈りすらすれば、営業面や税制面での優遇が得られることに味を占めて、賄賂を
贈っては稼ぎまくり、贈っては稼ぎまくりしていただけで、別に自分が政商犯と化してしまっているなど
とは自覚すらしないままに、政商としての膨大な富に与れていたような商売人などもいたはずなのである。
所詮は政商もまた、無責任極まりない民間からボウフラのように湧いて出てくるものであり、
政商ども自身に自律的な抑制などを期待すべきものでもない。まずは官職者こそが賄賂などによって
政治に取り入ってくる素封家を完全にシャットアウトするなどの修身に勤め、その上で民間に対しても、
腐ったドブからボウフラが湧き出てくるかのような政商の発生を防ぎとめる浄化措置を講じて行くべきである。
政商が食客(死兵要員)や縦横家(悪徳外交家)までをも駆使することでの権力犯罪こそは、
天災や紛争以上もの仁政にとっての大敵であり、仁政を志す漢や唐のごとき
国家にとっても亡国級の禍いを招く元凶とすらなりかねないものである。
度し難いのは、政商自身が政商であるということを公表もせず、最悪の場合、
自分が政商と化してしまっていることに気づいてすらいない場合があるということである。
唐を滅ぼした黄巣の如きは、塩の密売などのあからさまな悪徳商人としての暗躍によって勢力を付けて
いたわけだからまだ分かりやすいが、後漢を滅ぼした曹家などは純粋な官職者(ただし元下級役人)でいた。
それでいて漢朝における専横の限りを尽くし、賄賂を基調とした政財界の癒着などにも基づく狭隘な
利権の占有によって帝位を奪い取ったわけで(ただし名目上は禅譲)、これなどは政商そのものが曹家を
隠れ蓑として、あまり大きな顔もしないでいるままに仁徳ある国家を滅ぼした事例にも当たっている。
多くの賄賂を役人に贈りすらすれば、営業面や税制面での優遇が得られることに味を占めて、賄賂を
贈っては稼ぎまくり、贈っては稼ぎまくりしていただけで、別に自分が政商犯と化してしまっているなど
とは自覚すらしないままに、政商としての膨大な富に与れていたような商売人などもいたはずなのである。
所詮は政商もまた、無責任極まりない民間からボウフラのように湧いて出てくるものであり、
政商ども自身に自律的な抑制などを期待すべきものでもない。まずは官職者こそが賄賂などによって
政治に取り入ってくる素封家を完全にシャットアウトするなどの修身に勤め、その上で民間に対しても、
腐ったドブからボウフラが湧き出てくるかのような政商の発生を防ぎとめる浄化措置を講じて行くべきである。
 今の日本で言えば、地主のドラ息子あたりが地元票や半裏口入学によって政治家や官僚となり、
今の日本で言えば、地主のドラ息子あたりが地元票や半裏口入学によって政治家や官僚となり、 大企業や資産家などからの政治献金や天下り先を提供されるなどして政治腐敗を深刻化
させたりすることが「政商現象」となっている。政商自体であるのは財界人だが、
今の日本などの場合、政治家も官僚も完全な財界の操り人形と化してしまっているわけだから、
政官財ひっくるめての政商現象という深刻な腐敗に苛まれていると考えたほうが、実態が把握しやすい。
単なる財界の操り人形と化してしまっているからこそ、政治家や官僚にとっては、財界こそが頼れる
お母さんとでもいったところである。お金も転職先もいくらでも用意してくれる、甘やかしてくれ放題な
ママンといったもので、為政者たち自身にとってありがたいこと極まりない存在であるには違いない。
しかし、世の中の側からみれば、権力機構の深刻な腐敗の元凶以外の何物でもなく、そんな人間は、
恥部から食物をひり出すオホゲツヒメのごとく、スサノオに斬り殺されてしまえとすら思えるのである。
為政者が素封家(今でいう財界人)などを頼りにはすべきでない、それぐらいは当たり前のことである。
素封家が主、為政者が従というような政治構造も当然厳禁であり(民主主義がそれを正当化してもいる)、
政財が完全に分離された上で、なおかつ素封家を平民以上に賤しむぐらいであって初めて仁政もまた可能となる。
「甘えを断ち切れ」どころの話ですらない。根本的な政治理念からしてひっくり返してしまう必要があるのだ。
「貴きを欲するは人の心を同じくするところなるも、人人己れに貴き者有り。思わざるのみ。
人の貴きとする所は良貴に非ざるなり。趙孟の貴くする所は、趙孟能く之れを賤しむ。
(詩に)云く、既に酒を以って醉い、既に徳を以って飽くとは、仁義に飽くを言うなり。
人の膏粱の味を願わざる所以なり。令聞広誉を身に施す人の文繡を願わざる所以なり」
「みな高貴であることを願う心は同じであるけれども、本当は自分自身の内面にこそ高貴なるものがあって、
にもかかわらずだれもそれを自覚することはない。(みな他人から高貴なものとされることばかりを
願っているが、)常の人の欲する所の高貴さというのは、実はろくな高貴さでもないようなものばかりである。
たとえば(晋の公卿で他人に爵位をやるのを好んでいた)趙孟が高貴な相手だと見なしたものは、
また趙孟が卑賤なものだと見なすことができる。(これこそはろくでもない高貴さの実例である)
詩経(大雅・既酔)に『既に酒に酔い、既に徳に飽く』というが、これなどは己れの内面に湛えられた
仁徳に酔い飽きたことを示している。(つまり、内面からの高貴さを自覚して満足している)
そうなれば他人が美食を食んでいることを羨んだりするようにして他人の高貴さを妬んだりすることも
なくなるし、外面的ないい評判や高い名誉を豪華な衣装ように願い欲したりすることもなくなるのである。
(高貴さを願い欲するはいいが、それは自分以外の誰かから貰い受けたりできるものではない。
あくまで自分自身の修養によって自得するものなのだから、他者に願ったりすべきではないのである。)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・告子章句上・一七より)
人の貴きとする所は良貴に非ざるなり。趙孟の貴くする所は、趙孟能く之れを賤しむ。
(詩に)云く、既に酒を以って醉い、既に徳を以って飽くとは、仁義に飽くを言うなり。
人の膏粱の味を願わざる所以なり。令聞広誉を身に施す人の文繡を願わざる所以なり」
「みな高貴であることを願う心は同じであるけれども、本当は自分自身の内面にこそ高貴なるものがあって、
にもかかわらずだれもそれを自覚することはない。(みな他人から高貴なものとされることばかりを
願っているが、)常の人の欲する所の高貴さというのは、実はろくな高貴さでもないようなものばかりである。
たとえば(晋の公卿で他人に爵位をやるのを好んでいた)趙孟が高貴な相手だと見なしたものは、
また趙孟が卑賤なものだと見なすことができる。(これこそはろくでもない高貴さの実例である)
詩経(大雅・既酔)に『既に酒に酔い、既に徳に飽く』というが、これなどは己れの内面に湛えられた
仁徳に酔い飽きたことを示している。(つまり、内面からの高貴さを自覚して満足している)
そうなれば他人が美食を食んでいることを羨んだりするようにして他人の高貴さを妬んだりすることも
なくなるし、外面的ないい評判や高い名誉を豪華な衣装ように願い欲したりすることもなくなるのである。
(高貴さを願い欲するはいいが、それは自分以外の誰かから貰い受けたりできるものではない。
あくまで自分自身の修養によって自得するものなのだから、他者に願ったりすべきではないのである。)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・告子章句上・一七より)
実際に、実社会に影響を及ぼし得るもののうちで優良であるのは、
王侯将相のごとき正式な位に就いて、仁政のような善良な職務に励むものである。
それとはまた別に、超俗的な神仏が優良で高貴なものとされたりするのは、
あくまで世俗を黙って見守る度量衡的存在である場合に限って可とされるべきことである。
ただの人間が、実社会で正式な地位にも就かずにどんなことをやってみたところで
ろくな結果を挙げられもしないのはもちろんのこと、世俗を超越する神などが、
正式な社会的地位にもないままに何らかの影響を世の中に及ぼすということを想定
してみたとしても、そこに何らかのいい結果を期待できたりすることもないのである。
全国全土を統べる正式な統率者であればこそ、公明正大な仁政を施すことができる。
民たちも彼を天子と仰いで、仁政のための事業であることを了承しつつその命に服するなどする
こともできるようになるわけで、それは決して非正規な立場などから可能となることではない。
たとえば、阿弥陀仏による一切衆生の救済などが実現されるとしたところで、実際には、
阿弥陀仏のような仏性を帯びた正式な為政者が仁政によって「厭離穢土欣求浄土」を
実現して行くなどするのであり、あくまで阿弥陀仏そのものはその仮託対象となるのみである。
(もちろん真諦優位俗諦劣位の仏説に即して阿弥陀仏を真、実社会の為政者を仮と考えてもよい)
正式な位にあるわけでもない超越的な何者か自身が特定の人間を救ったりする、これは結局、
原理的に劣悪であると見なす他ない事案である。実際問題、世の中というのは一定の範囲内に
限られていて、その範囲内で最善を尽くすことが普遍的な最善ともなる。天下国家における
最善の行為は、天下万人を安寧や繁栄へと導く仁政であるわけだけれども、「超越的な何者かが
特定の人間を救う」という事案は、その言語構造上からいって仁政の条件を満たしてはいない。
王侯将相のごとき正式な位に就いて、仁政のような善良な職務に励むものである。
それとはまた別に、超俗的な神仏が優良で高貴なものとされたりするのは、
あくまで世俗を黙って見守る度量衡的存在である場合に限って可とされるべきことである。
ただの人間が、実社会で正式な地位にも就かずにどんなことをやってみたところで
ろくな結果を挙げられもしないのはもちろんのこと、世俗を超越する神などが、
正式な社会的地位にもないままに何らかの影響を世の中に及ぼすということを想定
してみたとしても、そこに何らかのいい結果を期待できたりすることもないのである。
全国全土を統べる正式な統率者であればこそ、公明正大な仁政を施すことができる。
民たちも彼を天子と仰いで、仁政のための事業であることを了承しつつその命に服するなどする
こともできるようになるわけで、それは決して非正規な立場などから可能となることではない。
たとえば、阿弥陀仏による一切衆生の救済などが実現されるとしたところで、実際には、
阿弥陀仏のような仏性を帯びた正式な為政者が仁政によって「厭離穢土欣求浄土」を
実現して行くなどするのであり、あくまで阿弥陀仏そのものはその仮託対象となるのみである。
(もちろん真諦優位俗諦劣位の仏説に即して阿弥陀仏を真、実社会の為政者を仮と考えてもよい)
正式な位にあるわけでもない超越的な何者か自身が特定の人間を救ったりする、これは結局、
原理的に劣悪であると見なす他ない事案である。実際問題、世の中というのは一定の範囲内に
限られていて、その範囲内で最善を尽くすことが普遍的な最善ともなる。天下国家における
最善の行為は、天下万人を安寧や繁栄へと導く仁政であるわけだけれども、「超越的な何者かが
特定の人間を救う」という事案は、その言語構造上からいって仁政の条件を満たしてはいない。
 救済者が超越的かどうか以前に、そもそも特定の人間だけを救おうとすることが仁義に欠けている。
救済者が超越的かどうか以前に、そもそも特定の人間だけを救おうとすることが仁義に欠けている。 だから結局、超越的な何者かによって救われるなどということを以ってして、それを正当化
したりもできはしない。むしろ、「特定の人間が救われる」という事案を正当化できたような
気にさせることがあるぶんだけ、それを実現するなどとする超越者などは、
不正を助長する手先にしかならないとすら考えられるわけである。
世俗の救済を促す神仏が必ずしも正式な為政者の仁政を阻害するとも限らないが、
「正式な位に就いているわけでもないからこそ、特定の人間を救う」などとまで条件が限定
されている神ともなれば、これはもう仁政を阻害する神であることが間違いないから、仁政を
志す以上はそのような邪神への帰依の横行などは当然のこととして根絶していかなければならない。
刑死しても生き返って罪が清められるとか、超越者が非正規な立場から特定の人間を救うとか、
頭の悪い人間には聞こえがよかったりしたところで、そもそもその言語構造上からいって
不正な教義であることが自明である。現実に可能かどうかなど以前に、そんなことが
あり得た所でやはり不正なままである。実現可能であった所で不正でしかないのだから、
そんなものを希求すべきでないし、希求して得られた所でつまらないだけである。
「圭璋特達するは徳なり。天下に貴ばざる莫きは道なり」
「諸侯の国交の際の聘礼では専用の宝玉だけを用い、他の雑多な事物を用いぬことで倹約を尽くす。
天下に何一つとして貴ばざるべきものなどないでいてこそ道であることを示すためである」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・聘義第四十八より)
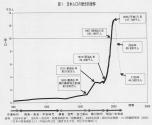 部分の繁栄は、えてして全体の困窮と比例しがちなものである。
部分の繁栄は、えてして全体の困窮と比例しがちなものである。 個人も世の中も共に繁栄できるのは、仁政が大成功している場合に限ったことであり、
別に仁を志しているわけでもない人間が個人的な栄華を極めようとしたりしたなら、そのための
安易な手段としての我田引水に及び、そのせいで社会の側の貧窮を招いてしまうものなのである。
特に、商業権力が体系的に部分の豊満を極めようとしたりしたなら、それが世の中の側に
極度かつ持続的な負担をかけることになる、そしたらどうなるかといえば、人口爆発を招く。
富裕者の非常識な規模の物質的繁栄を実現するために、その下積みを担わされる人間の数も
過度に増大させて行く必要が出てくるから、そのせいで自然と人口が増大して行くこととなる。
徳川綱吉が悪貨を乱造してまで商業を隆盛させた元禄時代など、江戸期でも最も華やかな時代
だったなどとされるが、当時の日本の人口もやはりうなぎ上り状態であった。楽して大金を稼げる
商売に多くの人間が飛びついたせいで、そのような虚業の従事者までをも食わせて行ってやるための
農業人口なども合わせて増大した結果、日本の総人口もまた増加した。しかし、いい加減虚業への
従事人数に対する実業への従事人数が足らなくなって、享保時代には大飢饉を招くことともなった。
分家将軍吉宗による倹約を主体とした政治改革によって危機を免れて後には、日本の人口も
横ばい状態となり、倒幕に至るまでその状態が百五十年以上に渡って続いたのだった。
今の世界などは、まさに享保初期の日本の状態などにも近似したものとなっている。
江戸時代の日本の場合、元禄期の頃にはそれなりの豊かさを保てていたのが、その後の
享保期に至ってついに大飢饉を来たしたわけだが、近代以降の世界はずっとコンスタントに
大量の餓死者や戦死者をはじき出しながら今までやって来ているわけだから、江戸時代の日本
よりもさらにひどい状態となっているといえる。実際、江戸史上最悪の飢饉である天明の大飢饉を
上回る死亡率での餓死者をはじき出し続けており、資本主義国の虚業偏重のしわ寄せとしての
人口爆発もまた、元禄期の日本すらもが遠く及ばないほどもの激甚さとなってしまっている。
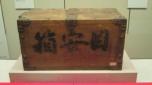 このような事態の打開のために必要となるのも、やはり虚業偏重の風潮の是正であるといえる。
このような事態の打開のために必要となるのも、やはり虚業偏重の風潮の是正であるといえる。 楽して大金を稼ぐことに対する戒めを通じて、誰しもがそのような安易さに流れぬようにする。
したらば全体社会にかける負担も少なくなり、人口を爆発させてまで重労働を担っていく
必要もなくなるわけで、資本主義国の虚業偏重による放辟邪侈が人口爆発を招いている昨今、
この方法以外に人口爆発を抑制して行く手段もないといえる。
虚業による物質的繁栄も元禄期の日本以上だから、その是正も享保の改革以上の厳格さで
なければならない。豪商に対する禁治産などを徳川吉宗が実施したわけでもないが(せいぜい
町代や町名主の員数を減らしたりした程度)、今という時代にはそれすらをも必要としかねない。
目安箱によって下層民の言葉にも耳を傾けるどころか、むしろ下層民の意見こそを優先的に
聞き入れて行くぐらいでなければならない。吉宗以上、劉邦や武帝以上の引き締め改革を心がけて
行く必要があるわけだが、当然それが共産化などであっていいはずもない。問題はあくまで
商業の過度の偏重なのであって、商売自体は都市化した人間社会などにある程度はなくては
ならない必要悪でもあるわけだから、そのあたりのさじ加減を工夫して行くことも必要である。
「四体既に正しく、膚革充盈なるは、人の肥えたるなり。父子篤く、兄弟睦まじく、夫婦和するは
家の肥えたるなり。大臣法あり、小臣廉あり、官職相い序たり、君臣相い正しきは、国の肥えたるなり。
天子徳を以て車と為し、楽を以て御と為し、諸侯礼を以って相い与し、大夫法を以って相い序し、士信を
以って相い考し、(ここから既出)百姓睦を以って相い守るは、天下の肥えたるなり。是れを大順と謂う」
「四体も満足で肌色からいかにも満ちているのは、人が豊かな証拠である。父子夫婦兄弟がお互いに篤く
和睦し合うのは、家が豊かな証拠である。大臣に節度があり、小臣にも清廉さがあり、官職はお互いに
序列を尊重し合い、君臣の関係も正しいのは、国が豊かな証拠である。天子は徳を楽しむことを以って我が
御車とし、諸侯大名も礼節を以って協力し合い、大夫家老も節度を持ってお互いに序列を尊重し、士人も
信頼を以ってお互いを配慮し合い、百姓も和睦によってお互いを守り合うのは、天下が豊かな証拠である。
これこそを大順という。(聖書信仰は、このうちの一番最初『個人の豊かさ』を保証するものでしかない。
故に、個人の豊かさばかりを追い求めすぎた結果、大順を損ねて大逆を招くことともなるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼運第九より)
家の肥えたるなり。大臣法あり、小臣廉あり、官職相い序たり、君臣相い正しきは、国の肥えたるなり。
天子徳を以て車と為し、楽を以て御と為し、諸侯礼を以って相い与し、大夫法を以って相い序し、士信を
以って相い考し、(ここから既出)百姓睦を以って相い守るは、天下の肥えたるなり。是れを大順と謂う」
「四体も満足で肌色からいかにも満ちているのは、人が豊かな証拠である。父子夫婦兄弟がお互いに篤く
和睦し合うのは、家が豊かな証拠である。大臣に節度があり、小臣にも清廉さがあり、官職はお互いに
序列を尊重し合い、君臣の関係も正しいのは、国が豊かな証拠である。天子は徳を楽しむことを以って我が
御車とし、諸侯大名も礼節を以って協力し合い、大夫家老も節度を持ってお互いに序列を尊重し、士人も
信頼を以ってお互いを配慮し合い、百姓も和睦によってお互いを守り合うのは、天下が豊かな証拠である。
これこそを大順という。(聖書信仰は、このうちの一番最初『個人の豊かさ』を保証するものでしかない。
故に、個人の豊かさばかりを追い求めすぎた結果、大順を損ねて大逆を招くことともなるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼運第九より)
大順の反対が大逆、大逆の反対が大順。
何も、主君殺しばかりが大逆行為に当たるわけではない。
君臣父子夫婦の和睦や、それに基づく安寧を損なう行為全般を大逆というのである。
民主主義や個人主義も、大逆行為を正当化したイデオロギーなのである。
何も、主君殺しばかりが大逆行為に当たるわけではない。
君臣父子夫婦の和睦や、それに基づく安寧を損なう行為全般を大逆というのである。
民主主義や個人主義も、大逆行為を正当化したイデオロギーなのである。
信仰が盲目な活動の推進を促すということ自体、常人以下の品性を人々に植え付けるものである。
故に、そのような教義を持つ他力本願系の信教全般(アブラハム教や拝火教や浄土教など)が、
自力作善を促す信教に及ばないのはもちろんのこと、何を信じているというわけでもなく
ただ独立独行を旨とする以上にも拙劣なことであるとすらいえるのである。
信仰に対して一概であろうとすることからして、もはや作為の塊である。
中国浄土教の開祖である曇鸞も、無為自然を貴ぶ道家の書を焼き捨てて浄土信仰に
帰依したというし、良くも悪しくも、信仰こそは旺盛な作為の種子となるものである。
そして悪しき場合には、なにも信仰なんかしないでいたほうがマシなほどにも
劣悪な思考規範や言動規範が信者に植え付けられることにすらなってしまうのである。
だからこそ、「とにかく何かを信じてすらいれば、何も信じていないよりマシ」「何も信じて
いない人間こそは信用が置けない」なんていう思い込みもまた是正されて行かねばならない。
確かに、長きに渡って邪教信仰などに耽溺し続けてきた人間が急激に信仰を破棄したりすると、
そのせいでの虚無感にかられて居ても立ってもいられないような不安に苛まれたりすることにも
なるわけだけれども、べつにそれが無信仰者一般にとってのデフォルトだったりするわけでもない。
邪信に溺れないではいられないような精神薄弱者にとっての特殊なデフォルトに過ぎないのであり、
自力作善に基づく修養によってそれを克服して行くことが可能であるのみならず、そもそも常人に
とってのデフォルトの心理状態自体、そこまでどうしようもなく辛いものだったりもしないのである。
邪信に依存しないではいられないほどにも拙劣な精神薄弱状態に一部の地球人が陥れられた
そもそもの原因は何だったのかといえば、古代のオリエント社会や西洋社会や中国社会などにおける、
政商犯の介入までをも容認しつつの権力腐敗であった。その名残りが数多の遺跡として世界中に
存在していたりするわけだけれども、それ自体は宗教的だったり、そうでもなかったりした。
故に、そのような教義を持つ他力本願系の信教全般(アブラハム教や拝火教や浄土教など)が、
自力作善を促す信教に及ばないのはもちろんのこと、何を信じているというわけでもなく
ただ独立独行を旨とする以上にも拙劣なことであるとすらいえるのである。
信仰に対して一概であろうとすることからして、もはや作為の塊である。
中国浄土教の開祖である曇鸞も、無為自然を貴ぶ道家の書を焼き捨てて浄土信仰に
帰依したというし、良くも悪しくも、信仰こそは旺盛な作為の種子となるものである。
そして悪しき場合には、なにも信仰なんかしないでいたほうがマシなほどにも
劣悪な思考規範や言動規範が信者に植え付けられることにすらなってしまうのである。
だからこそ、「とにかく何かを信じてすらいれば、何も信じていないよりマシ」「何も信じて
いない人間こそは信用が置けない」なんていう思い込みもまた是正されて行かねばならない。
確かに、長きに渡って邪教信仰などに耽溺し続けてきた人間が急激に信仰を破棄したりすると、
そのせいでの虚無感にかられて居ても立ってもいられないような不安に苛まれたりすることにも
なるわけだけれども、べつにそれが無信仰者一般にとってのデフォルトだったりするわけでもない。
邪信に溺れないではいられないような精神薄弱者にとっての特殊なデフォルトに過ぎないのであり、
自力作善に基づく修養によってそれを克服して行くことが可能であるのみならず、そもそも常人に
とってのデフォルトの心理状態自体、そこまでどうしようもなく辛いものだったりもしないのである。
邪信に依存しないではいられないほどにも拙劣な精神薄弱状態に一部の地球人が陥れられた
そもそもの原因は何だったのかといえば、古代のオリエント社会や西洋社会や中国社会などにおける、
政商犯の介入までをも容認しつつの権力腐敗であった。その名残りが数多の遺跡として世界中に
存在していたりするわけだけれども、それ自体は宗教的だったり、そうでもなかったりした。
古代エジプトのピラミッドだとか、秦始皇帝による非常識な規模の王宮や陵墓の建造だとかは、
単なる本人たち自身の自己顕示欲を満たす目的で造られたものだと考えたほうが実に即している。
(もちろんそれを美化するための神託だとかも多々捏造されていたりしたのではある)
精神薄弱者の悪逆非道を信仰によって推進して行くことを理念として体系化までしたのは、
権力腐敗のさ中にある帝王たち自身ではなく、その帝王に取り入った政商犯たちのほうであった。
すなわち、イエスを含む古代ユダヤ人であり、自分たちが古代オリエントや古代ローマの権力者に
取り入って暴利を掠め取ったりしていたこと自体は、本人たちの編纂書である犯罪聖書中に
あからさまに記しているわけではない。しかし、古来からのユダヤ教徒の伝統的な生業が
政商であるのは周知のことであり、政商犯としての性向に根ざして犯罪聖書が編纂された
ことも、当該の聖書の記述が、政商を排することでての仁政を貴ぶ権力道徳聖書——
通称四書五経の記述と決定的に相反していることなどからも察することができるのである。
信教というもの、特に常人以下の退廃を信者に促す邪教こそは、元から権力の腐敗に乗じて
捏造されたものである。母子家庭の環境下での苦学によって孔子が大成させた儒学などとも違い、
ユダヤ教やキリスト教こそは、信徒が権力機構に深く取り入る過程ででっち上げたものである。
その誕生の経緯からして不純であるのが邪教であり、自力作善の信教はもちろんのこと、
無信仰の勉学精進を促す儒学にすら、その起源のまともさで及ばないものとなっている。
だからこそ「神からの啓示」であることなどを標榜して本当の起源を隠蔽しようなどとも
しているわけで、神託であることに依存していること自体、実は発祥が不純な証拠なのである。
神からの啓示であるからこそ嬉しい、そこからもうすでに過ちなのであり、神仏に仮託するので
あっても、その実際的な起源もまた後ろめたくないような信教ですらないことからしておかしい。
精神が強靭である人間ならば、信教がそんな由緒を売りにしたりしている所から嫌悪感を抱くが、
薄弱者にはそれがかえって魅力的に思えたりもする。そこからすでに魔が差しているのである。
単なる本人たち自身の自己顕示欲を満たす目的で造られたものだと考えたほうが実に即している。
(もちろんそれを美化するための神託だとかも多々捏造されていたりしたのではある)
精神薄弱者の悪逆非道を信仰によって推進して行くことを理念として体系化までしたのは、
権力腐敗のさ中にある帝王たち自身ではなく、その帝王に取り入った政商犯たちのほうであった。
すなわち、イエスを含む古代ユダヤ人であり、自分たちが古代オリエントや古代ローマの権力者に
取り入って暴利を掠め取ったりしていたこと自体は、本人たちの編纂書である犯罪聖書中に
あからさまに記しているわけではない。しかし、古来からのユダヤ教徒の伝統的な生業が
政商であるのは周知のことであり、政商犯としての性向に根ざして犯罪聖書が編纂された
ことも、当該の聖書の記述が、政商を排することでての仁政を貴ぶ権力道徳聖書——
通称四書五経の記述と決定的に相反していることなどからも察することができるのである。
信教というもの、特に常人以下の退廃を信者に促す邪教こそは、元から権力の腐敗に乗じて
捏造されたものである。母子家庭の環境下での苦学によって孔子が大成させた儒学などとも違い、
ユダヤ教やキリスト教こそは、信徒が権力機構に深く取り入る過程ででっち上げたものである。
その誕生の経緯からして不純であるのが邪教であり、自力作善の信教はもちろんのこと、
無信仰の勉学精進を促す儒学にすら、その起源のまともさで及ばないものとなっている。
だからこそ「神からの啓示」であることなどを標榜して本当の起源を隠蔽しようなどとも
しているわけで、神託であることに依存していること自体、実は発祥が不純な証拠なのである。
神からの啓示であるからこそ嬉しい、そこからもうすでに過ちなのであり、神仏に仮託するので
あっても、その実際的な起源もまた後ろめたくないような信教ですらないことからしておかしい。
精神が強靭である人間ならば、信教がそんな由緒を売りにしたりしている所から嫌悪感を抱くが、
薄弱者にはそれがかえって魅力的に思えたりもする。そこからすでに魔が差しているのである。
削除(by投稿者)
「儒に貧賤に隕獲せず、富貴に充詘せず、君王に慁められず、長上に累せず、有司に閔しめられざる有り。
故に儒を曰うに、今衆人の儒を命づくるや妄なり、常ら儒を以って相い詬病すと。孔子舍に至りて、哀公之れを館す。
此の言を聞くや、言は信を加え、行いは義を加う、吾が世の終没するまで、敢えて儒を以って戯れと為さずと」
「孔子『儒者のうちには、極度の貧賤に苛まれたり富貴に淫したりすることでも志しを失ったりはせず、
王君に引け目を抱くこともなく、長者や上位者に列したがりもせず、官職者を妬んだりもしない者がいます。
そのため(醜悪なルサンチマンにかられている)大衆の内には、儒者を盲目だなどと決め付ける者もいます。
儒学に耽ってものが見えない病に陥っているというのです』 孔子が学舎に来ると、哀公は食い扶持と官職を
以ってこれを遇し、先ほどの孔子の言葉について返答した。『その言葉には信実さがあり、その行いにも
道義性がある。私の在位中には、決して儒学を衆人の言うような戯れ扱いにすることを許しますまい』
(権力への取り入りも断って物事をしっかと見据えている所にこそ、王侯をも感服させるだけの信実さが備わる。
それでいて、そのような真に信実ある儒者の姿こそを、迷妄な衆人が盲者などと決め付けたりもするのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——儒行第四十一より)
故に儒を曰うに、今衆人の儒を命づくるや妄なり、常ら儒を以って相い詬病すと。孔子舍に至りて、哀公之れを館す。
此の言を聞くや、言は信を加え、行いは義を加う、吾が世の終没するまで、敢えて儒を以って戯れと為さずと」
「孔子『儒者のうちには、極度の貧賤に苛まれたり富貴に淫したりすることでも志しを失ったりはせず、
王君に引け目を抱くこともなく、長者や上位者に列したがりもせず、官職者を妬んだりもしない者がいます。
そのため(醜悪なルサンチマンにかられている)大衆の内には、儒者を盲目だなどと決め付ける者もいます。
儒学に耽ってものが見えない病に陥っているというのです』 孔子が学舎に来ると、哀公は食い扶持と官職を
以ってこれを遇し、先ほどの孔子の言葉について返答した。『その言葉には信実さがあり、その行いにも
道義性がある。私の在位中には、決して儒学を衆人の言うような戯れ扱いにすることを許しますまい』
(権力への取り入りも断って物事をしっかと見据えている所にこそ、王侯をも感服させるだけの信実さが備わる。
それでいて、そのような真に信実ある儒者の姿こそを、迷妄な衆人が盲者などと決め付けたりもするのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——儒行第四十一より)
面白い。。。
率先して重荷を背負って行く者こそは上位者たり、重荷を嫌って易々とした
生き方に逃げたがる者こそは下位に置かれるのが道理というものである。
易行道を奨励する仏門として浄土門などがありもするが、その主な帰依者は一般の
百姓であり、武家や公家のような率先して重荷を背負って行くべき立場の人間は、
むしろ禅や密教のごとき自力作善の聖道門への帰依を主体としていた。だからこそ、
昔の日本の全体規模での仏門帰依なども適正なものであったといえる。重荷を背負う
立場にある人間こそは他力本願でいて、そうでもないような人間ばかりが自力作善を
志してたりするようならば不健全極まりないが、昔の日本はそうではなかったわけで、
自力他力の配分を適正化することに当時の仏教が貢献していたのだともいえるのである。
キリスト教圏などはこの逆で、重荷を背負うべき正規の王侯たちこそは、キリスト
への他力本願を本是とする正統派のキリスト信仰に帰依していた一方、商売人などの
賤しい身分の人間こそが、「キリストの到来もまだ」とするユダヤ教に入信したり、
プロテスタントの異端派として「自力の悪行」に執心するなどして来たのである。
日本で自力他力の配分を適正化した主体も仏教という信教であったし、
キリスト教圏で自力他力の配分を不正化した主体も聖書信仰という信教であった。
儒学や神道や道教のごとき純極東産の教学は、全体社会を体系的に司ることで
自力他力の配分までをも人工的に操作するような試みにまでは及んでいなかった。
(だからこそ為政者を君子扱いしたり、民間人を小人扱いしたりの一方通行でもいた)
そこはコーカソイド圏(インドや古代オリエント)発祥の信教などとは違う部分であり、
全体に対する征服的な姿勢に欠けている点が善い所でも悪い所でもあるといえる。
生き方に逃げたがる者こそは下位に置かれるのが道理というものである。
易行道を奨励する仏門として浄土門などがありもするが、その主な帰依者は一般の
百姓であり、武家や公家のような率先して重荷を背負って行くべき立場の人間は、
むしろ禅や密教のごとき自力作善の聖道門への帰依を主体としていた。だからこそ、
昔の日本の全体規模での仏門帰依なども適正なものであったといえる。重荷を背負う
立場にある人間こそは他力本願でいて、そうでもないような人間ばかりが自力作善を
志してたりするようならば不健全極まりないが、昔の日本はそうではなかったわけで、
自力他力の配分を適正化することに当時の仏教が貢献していたのだともいえるのである。
キリスト教圏などはこの逆で、重荷を背負うべき正規の王侯たちこそは、キリスト
への他力本願を本是とする正統派のキリスト信仰に帰依していた一方、商売人などの
賤しい身分の人間こそが、「キリストの到来もまだ」とするユダヤ教に入信したり、
プロテスタントの異端派として「自力の悪行」に執心するなどして来たのである。
日本で自力他力の配分を適正化した主体も仏教という信教であったし、
キリスト教圏で自力他力の配分を不正化した主体も聖書信仰という信教であった。
儒学や神道や道教のごとき純極東産の教学は、全体社会を体系的に司ることで
自力他力の配分までをも人工的に操作するような試みにまでは及んでいなかった。
(だからこそ為政者を君子扱いしたり、民間人を小人扱いしたりの一方通行でもいた)
そこはコーカソイド圏(インドや古代オリエント)発祥の信教などとは違う部分であり、
全体に対する征服的な姿勢に欠けている点が善い所でも悪い所でもあるといえる。
ただ、そのうちの儒学、特に易の法則に即して、自力作善を旨とするものが尊ばれ、
他力本願を旨とするものが賤しまれることが道理であり、それに反することが
道理に悖るとも判断することもできる。信仰ではなく純粋な学問の見地に即して、
仏教が日本に及ぼした自力他力の配分は適正であった一方、聖書信仰が
欧米などに及ぼした自力他力の配分は不正であったともいえる。
仏教の真理は虚空にこそあり、聖書信仰の真理は超越神にこそあるとされる。
どちらが本物の真理かは一旦おいておくとして、虚空を真理とすることこそは自力の
尊重と他力の賤しみに帰結する一方、超越神を真理とすることは他力の尊重と自力の
賤しみに繋がる。道理に適うのは前者であり、道理に反するのは後者であるから、
無宗教の道理に即して前者を是とし、後者を非として行くべきだともいえる。
世間を虚仮なるものとしながらも、仏教は結局社会的な上位者に自力作善を促し、
下位者に他力本願を奨励している。社会への対応もまた適正であるのが仏教である
一方、そこが不正なのが聖書信仰である。王侯は他力本願、商人は独立独行といった
布教姿勢がすでに社会の退廃を決定付けるものであり、世界のすべてを超越神の配下に
置こうとする宗教的な姿勢からして社会的に悪用されていることが明らかである。
「社会についてどうこうこだわるのは卑俗なことだ」邪教信者はそうほざいたりもする。
そうではなく、邪教こそは世の中の側を決定的に低俗ならしめている元凶なのであり、
そんなものがなければ世の中の側もそれなりに見られたものであり得るのである。そして
そのような世の中での活動を奨励するのが儒学であるし、そのような世の中を信教として
実現して行こうとするのが仏教でもあったりするのだから、邪教ありきなものの考え方に
よってこそ世俗を見るに値しないものだなどと決め付け、実際に世の中の低俗さが深刻化
して行くことを黙認し続けるようなことを可としてやったりしてもならないのである。
他力本願を旨とするものが賤しまれることが道理であり、それに反することが
道理に悖るとも判断することもできる。信仰ではなく純粋な学問の見地に即して、
仏教が日本に及ぼした自力他力の配分は適正であった一方、聖書信仰が
欧米などに及ぼした自力他力の配分は不正であったともいえる。
仏教の真理は虚空にこそあり、聖書信仰の真理は超越神にこそあるとされる。
どちらが本物の真理かは一旦おいておくとして、虚空を真理とすることこそは自力の
尊重と他力の賤しみに帰結する一方、超越神を真理とすることは他力の尊重と自力の
賤しみに繋がる。道理に適うのは前者であり、道理に反するのは後者であるから、
無宗教の道理に即して前者を是とし、後者を非として行くべきだともいえる。
世間を虚仮なるものとしながらも、仏教は結局社会的な上位者に自力作善を促し、
下位者に他力本願を奨励している。社会への対応もまた適正であるのが仏教である
一方、そこが不正なのが聖書信仰である。王侯は他力本願、商人は独立独行といった
布教姿勢がすでに社会の退廃を決定付けるものであり、世界のすべてを超越神の配下に
置こうとする宗教的な姿勢からして社会的に悪用されていることが明らかである。
「社会についてどうこうこだわるのは卑俗なことだ」邪教信者はそうほざいたりもする。
そうではなく、邪教こそは世の中の側を決定的に低俗ならしめている元凶なのであり、
そんなものがなければ世の中の側もそれなりに見られたものであり得るのである。そして
そのような世の中での活動を奨励するのが儒学であるし、そのような世の中を信教として
実現して行こうとするのが仏教でもあったりするのだから、邪教ありきなものの考え方に
よってこそ世俗を見るに値しないものだなどと決め付け、実際に世の中の低俗さが深刻化
して行くことを黙認し続けるようなことを可としてやったりしてもならないのである。
削除(by投稿者)
「君子、重からざれば威あらず」
「君子も重々しさがなければ威厳が備わらない。
(重荷を背負って重々しくあることで威厳を備えよというのだ)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・学而第一・八より)
「君子も重々しさがなければ威厳が備わらない。
(重荷を背負って重々しくあることで威厳を備えよというのだ)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・学而第一・八より)
率先して罪を認めてそこからの救いを請うという点が、いかにもキリスト教の美談めいた点として扱われる。
儒学と言わず仏教と言わずイスラム教と言わず、悪いことはするな、悪いことをするのはよくないとし、
実際に悪いことをすれば罰をあたえるべしという姿勢を基本としている。法家ほどあからさまではなくとも、
信賞必罰を大前提とするのが世界中の主要な教学の本旨であり(ユダヤ教ですらもがそうだが、
トーラーにあるような徒法ばかりを守らせようとするためにいいもの扱いまではできない)、
その点、キリスト教こそは他のいかなる教学と比べても異端であるといえる。
結論からいえば、それも偽善止まりの教条なのである。信賞必罰を絶対化して、
徒法や悪法すらをも頑なに守らせる法家やユダヤ教の姿勢も決してできたものではないが、
かといって罪を罪、徳を徳と分別する正常な判断能力を備えた上で、自らは罪を避け徳を積み、他者にも
なるべくそうあるように促して行ってこそ、本当の善美たり得ることにも変わりはない。にもかかわらず、
キリスト教徒はめくら滅法に誰も彼もを罪人だなどと決め付けて、その内でも率先して罪を認めて神に
救いを請うている自分たちこそは清いとする、そんなことで何らのいい効験が期待できるはずもないのであり、
信者自身の自己陶酔や、誤解に基づく信者への尊崇だとかを生じさせる原因にしかなりはしないのである。
杓子定規に過ぎるような信賞必罰と、キリスト教徒のごときめくら滅法な罪の開き直り、
この二つが避けるべき両極端であり、いずれにも振れ切らない中正こそが人々の目指すべき道である。
そしてその中正を守って行くためには、儒学の勉強や正統な仏教への帰依などに基づいて正しい
善悪の分別を養い、融通の利いた勧善懲悪や断悪修善を実践して行けるようにすればいいのである。
正しい善悪の分別と、それに基づく適度な勧善懲悪や断悪修善という選択肢が拓かれていればこそ、
罪業を開き直るようなことも許されない。少なくとも、罪業を開き直ったりすることを賤しいことと見なせる。
儒学と言わず仏教と言わずイスラム教と言わず、悪いことはするな、悪いことをするのはよくないとし、
実際に悪いことをすれば罰をあたえるべしという姿勢を基本としている。法家ほどあからさまではなくとも、
信賞必罰を大前提とするのが世界中の主要な教学の本旨であり(ユダヤ教ですらもがそうだが、
トーラーにあるような徒法ばかりを守らせようとするためにいいもの扱いまではできない)、
その点、キリスト教こそは他のいかなる教学と比べても異端であるといえる。
結論からいえば、それも偽善止まりの教条なのである。信賞必罰を絶対化して、
徒法や悪法すらをも頑なに守らせる法家やユダヤ教の姿勢も決してできたものではないが、
かといって罪を罪、徳を徳と分別する正常な判断能力を備えた上で、自らは罪を避け徳を積み、他者にも
なるべくそうあるように促して行ってこそ、本当の善美たり得ることにも変わりはない。にもかかわらず、
キリスト教徒はめくら滅法に誰も彼もを罪人だなどと決め付けて、その内でも率先して罪を認めて神に
救いを請うている自分たちこそは清いとする、そんなことで何らのいい効験が期待できるはずもないのであり、
信者自身の自己陶酔や、誤解に基づく信者への尊崇だとかを生じさせる原因にしかなりはしないのである。
杓子定規に過ぎるような信賞必罰と、キリスト教徒のごときめくら滅法な罪の開き直り、
この二つが避けるべき両極端であり、いずれにも振れ切らない中正こそが人々の目指すべき道である。
そしてその中正を守って行くためには、儒学の勉強や正統な仏教への帰依などに基づいて正しい
善悪の分別を養い、融通の利いた勧善懲悪や断悪修善を実践して行けるようにすればいいのである。
正しい善悪の分別と、それに基づく適度な勧善懲悪や断悪修善という選択肢が拓かれていればこそ、
罪業を開き直るようなことも許されない。少なくとも、罪業を開き直ったりすることを賤しいことと見なせる。
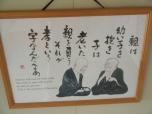 親鸞聖人が、自らが罪悪深重の身であることを自認した時にも、同時に自らが煩悩具縛の
親鸞聖人が、自らが罪悪深重の身であることを自認した時にも、同時に自らが煩悩具縛の 愚夫であることをも認めていた。読経中に美女の姿が頭に思い浮かぶような賤しい身の程であればこそ、
他力本願の浄土門に帰依するしかないとした。その上でなおかつ他者にまで浄土門への帰依を促していたのも、
当時が武家による争いも絶えない乱世であり、自力作善の聖道門への帰依などもなかなか覚束ない時代
であったからだ。自らが弘法大師の如き偉人であり、なおかつ今が平安時代のごとき安寧な時代で
あるというのなら、それこそ真言密教のごとき最難関級の聖道門にでも帰依すればいいわけで、それが
無理だから仕方なく他力本願の念仏者だったりするとしても、決してそれで偉いなんてことはないのである。
自己の賤しさを認めながらの他力本願の徒であることが、マシであるということぐらいなら確かにある。
それこそ、罪を開き直って神に救いを請うている自分たちこそは常人以上にも偉いなどとするほどもの
邪曲が横行しているようであるならば、それよりはまだ自分たちの人並み以上の賤しさを自認しながら
浄土門に帰依している念仏者のほうがまだマシな存在だったりもする。それこそ「最悪かマシか」の
どん尻争いでの辛勝なわけで、そんなこと嬉しがっていたりするのも空しいことだからやめるべきではある。
率先して罪を認めて救いを請うているから人並み以上に偉い、そんな転倒夢想に陥っていればこそ、
人並み以上の賤しさを認めながら他力本願でいる人間にすら及ばない存在ともなってしまうのだから、
そんなことを美学か何かのように勘違いするようなことも決してあってはならないのである。
「舜の天下を棄つるを視るや、猶お敝蹝を棄つるがごときなり。
竊かに負いて逃れ、海浜に遵いて処り、終身訢然として、楽しみて天下を忘れん」
「舜帝にとって天下を捨て去ることは、使い古して破れた草履を捨て去るのも同然なことであった。
密かに老いた親を背負って朝廷を逃げ出し、海浜に沿って人里離れた場所に行き、死ぬまで欣然として
楽しみながら天下のことなど忘れていただろう。(十字架を背負うぐらいなら自分自身の親を背負えよ)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・三五より)
大規模な戦争があろうがなかろうが乱世は乱世であり、そこには何らかの致命的な落ち度があるものである。
始皇帝による法家支配が敷かれた統一秦帝国においても、これといった内戦があったりしたわけでもなく、
せいぜい始皇帝の暗殺未遂事件が散発する程度だったが、それでも当時が極度の乱世であったことにも
間違いはない。秦国は、法家主義を基調とした極度の圧政によって民から暴利を巻き上げることでこそ
突発的な国力を獲得して諸外国を征服し、統一中華帝国をぶち上げたわけだから、中原全土が秦国並みの
圧政下に置かれたことで、かえって人々は春秋戦国時代以上もの被虐下に置かれることになったわけである。
だから、「これなら諸侯が支配していた戦国時代のほうがまだマシだった」というような嘆きが民の間で
囁かれてもいた、これこそは戦争状態以上もの「平和裏の乱世」であった実例だといえ、そんなものの持続を
誰も望みはしなかったから、たった15年の短期間の持続の後に、秦帝国も反乱による崩壊を来たしたのだった。
上記のような事情に即して、平和状態の世の中が戦争状態以上もの乱世たり得るということが、知られて
そうで実は知られていないことである。今の地球社会も、資本主義国の横暴によって年間に1000万人以上
もの人間が餓死し続けている状態であり、これは第二次世界大戦の死亡率にも匹敵する上、毎年ずっとその
程度の死亡率をはじき出し続けているわけだから、今が大戦期以上の乱世であることもまた間違いがない。
にもかかわらず、今という時代が「戦時中よりも平和でいい時代、少なくともマシな時代」として扱われて
いたりするのも「平和状態が戦争状態以上もの乱世たり得る」ということへの察知が全く欠けているからである。
始皇帝による法家支配が敷かれた統一秦帝国においても、これといった内戦があったりしたわけでもなく、
せいぜい始皇帝の暗殺未遂事件が散発する程度だったが、それでも当時が極度の乱世であったことにも
間違いはない。秦国は、法家主義を基調とした極度の圧政によって民から暴利を巻き上げることでこそ
突発的な国力を獲得して諸外国を征服し、統一中華帝国をぶち上げたわけだから、中原全土が秦国並みの
圧政下に置かれたことで、かえって人々は春秋戦国時代以上もの被虐下に置かれることになったわけである。
だから、「これなら諸侯が支配していた戦国時代のほうがまだマシだった」というような嘆きが民の間で
囁かれてもいた、これこそは戦争状態以上もの「平和裏の乱世」であった実例だといえ、そんなものの持続を
誰も望みはしなかったから、たった15年の短期間の持続の後に、秦帝国も反乱による崩壊を来たしたのだった。
上記のような事情に即して、平和状態の世の中が戦争状態以上もの乱世たり得るということが、知られて
そうで実は知られていないことである。今の地球社会も、資本主義国の横暴によって年間に1000万人以上
もの人間が餓死し続けている状態であり、これは第二次世界大戦の死亡率にも匹敵する上、毎年ずっとその
程度の死亡率をはじき出し続けているわけだから、今が大戦期以上の乱世であることもまた間違いがない。
にもかかわらず、今という時代が「戦時中よりも平和でいい時代、少なくともマシな時代」として扱われて
いたりするのも「平和状態が戦争状態以上もの乱世たり得る」ということへの察知が全く欠けているからである。
削除(by投稿者)
「平和」という言葉が英語の「peace」の訳語として用いられるようになってから、日本語としての「平和」
という言葉の意味もずいぶんと劣化してしまった。本来は出典の「礼記」にもあるような「平和で安寧な状態」
こそを「平和」と呼んでいたわけだが、今ではもはや「戦争だけはない状態」という意味で用いられるように
なってしまった。実際、英語の「peace」などはその程度の意味しか持ち合わせていないわけで、peaceという
言葉しか「平和」に当たる言葉が存在しないイギリスなども、万年上層階級が下層階級を経済的に圧迫し続ける
状態でいる。それでも自国で紛争などすらなければ、イギリス人にとってはそれがpeaceとなるわけで、英語圏
こそは、戦争状態以上もの平和裏の乱世という事態を全く察知していない未開社会であることが明らかだといえる。
「戦争状態以上もの乱世である平和状態」などという状態が可とされているようなところでは、漏れなく
権力道徳もまた存在しない。権力道徳が実践されていないのみならず、そんなものの実践が可能であることも、
そもそも権力道徳などというものが存在することすらも見落とされたままでいる。大体の場合、法治主義に
よって世の中の最低限の治安だけは保たれ、下層民に対する経済的な圧迫なども放任されたままでいながら、
紛争レベルの争いだけは徹底して防ぎ止められているような状態がほとんどである。そのような状態でこそ、
人々は戦時中以上もの苦しみに喘がされたりしているわけだが、「戦争だけはない今も戦時中よりはマシな
時代だ」などと思い込まされて、極度の被虐下に置かれ続けることを黙認させられたりもしているわけである。
そんな状態が、戦争状態以上もの乱世であるのは上に述べた通りである。じゃあ、そのまま戦争に突入してしまえば
いいのかといえば、それも違う。戦争状態は戦争状態でろくでもない状態であり、世の中の平和が確立された上で、
なおかつ人々への圧制が緩和された状態こそは真の治世なのだから、それこそを追い求めていくべきなのである。
という言葉の意味もずいぶんと劣化してしまった。本来は出典の「礼記」にもあるような「平和で安寧な状態」
こそを「平和」と呼んでいたわけだが、今ではもはや「戦争だけはない状態」という意味で用いられるように
なってしまった。実際、英語の「peace」などはその程度の意味しか持ち合わせていないわけで、peaceという
言葉しか「平和」に当たる言葉が存在しないイギリスなども、万年上層階級が下層階級を経済的に圧迫し続ける
状態でいる。それでも自国で紛争などすらなければ、イギリス人にとってはそれがpeaceとなるわけで、英語圏
こそは、戦争状態以上もの平和裏の乱世という事態を全く察知していない未開社会であることが明らかだといえる。
「戦争状態以上もの乱世である平和状態」などという状態が可とされているようなところでは、漏れなく
権力道徳もまた存在しない。権力道徳が実践されていないのみならず、そんなものの実践が可能であることも、
そもそも権力道徳などというものが存在することすらも見落とされたままでいる。大体の場合、法治主義に
よって世の中の最低限の治安だけは保たれ、下層民に対する経済的な圧迫なども放任されたままでいながら、
紛争レベルの争いだけは徹底して防ぎ止められているような状態がほとんどである。そのような状態でこそ、
人々は戦時中以上もの苦しみに喘がされたりしているわけだが、「戦争だけはない今も戦時中よりはマシな
時代だ」などと思い込まされて、極度の被虐下に置かれ続けることを黙認させられたりもしているわけである。
そんな状態が、戦争状態以上もの乱世であるのは上に述べた通りである。じゃあ、そのまま戦争に突入してしまえば
いいのかといえば、それも違う。戦争状態は戦争状態でろくでもない状態であり、世の中の平和が確立された上で、
なおかつ人々への圧制が緩和された状態こそは真の治世なのだから、それこそを追い求めていくべきなのである。
権力道徳の実践も察知も覚束ないでいるような状態で、なかなかそんなものを追い求めて行く気にもなれないと
しても無理のない話だが、それはそれはで実現し得るものであり、なおかつ、戦争状態はもちろんのこと、圧政の
敷かれた平和状態なぞ以上もの磐石な安定性が確立すらされ得るものなのであり、「道徳統治など長く続けられる
ものではない」などという、乱世の支配者の全く史実にも即していないような戯れ言などに流されるべきでもない。
「道は爾きに在り、而るに諸れを遠きに求む。事は易きに在り、而るに之れに
難きを求む。人人其の親を親とし、其の長を長とすれば、而うして天下も平らかなり」
「道はごくごく卑近なところにあるというのに、人々はみなそれを高遠なところなどに求めようとする。
それを実行することもさして難しいことではないのに、わざわざ難しいところばかりに実践手段を求める。
ただ誰しもが自らの親を親として尊び、年長者を年長者として尊びすらすれば、それだけで天下全土が平和
にもなるというのに。(過渡的な部分的平和などではなく、最終目的としての天下全土の平安を希求している。
そのための手段こそはかえって素朴なものであり、神聖さを追い求めたりするような無駄なこともしないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句上・一一より)
しても無理のない話だが、それはそれはで実現し得るものであり、なおかつ、戦争状態はもちろんのこと、圧政の
敷かれた平和状態なぞ以上もの磐石な安定性が確立すらされ得るものなのであり、「道徳統治など長く続けられる
ものではない」などという、乱世の支配者の全く史実にも即していないような戯れ言などに流されるべきでもない。
「道は爾きに在り、而るに諸れを遠きに求む。事は易きに在り、而るに之れに
難きを求む。人人其の親を親とし、其の長を長とすれば、而うして天下も平らかなり」
「道はごくごく卑近なところにあるというのに、人々はみなそれを高遠なところなどに求めようとする。
それを実行することもさして難しいことではないのに、わざわざ難しいところばかりに実践手段を求める。
ただ誰しもが自らの親を親として尊び、年長者を年長者として尊びすらすれば、それだけで天下全土が平和
にもなるというのに。(過渡的な部分的平和などではなく、最終目的としての天下全土の平安を希求している。
そのための手段こそはかえって素朴なものであり、神聖さを追い求めたりするような無駄なこともしないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句上・一一より)
始めから世界のごく一部を司る小物然とした神などでいるのならまだしも、「世界の全てを
造った」などと豪語しながら、その内の一部の儲や世界しか救わないとしているものだから、
仁義道徳を決定的に侵害する純度100%の邪神であることまでもが確定しているのである。
一部の事物を司る神であるというのなら、それ相応の扱いによる仁政への
役立てなどもまだ期待ができるのに、わざわざ「世界の全てを司る」などと
したものだから、仁政実現の上では根絶対象となることまでもが避けられない。
そして、そうでありながら一部の人間しか救わないような態度でいる神などを信じようとした
人間たち自身からして、人並み以上の不誠実さを帯びていたことが明らかである。せめてでも、
阿弥陀仏のように「西方浄土において一切衆生を救済の対象とする」と誓約しているような
神仏を信じたりしたのならば、それをして信者たち自身が不誠実である根拠などにはならない
のだが、「全世界を統べながら信じるものだけを救う」などという神を信じたものだから、
それによって自分たち自身の性根からの不誠実さまでをも露呈させてしまったのである。
世界の全てを統べるといいながら、一部の信者しか救わないともする。そこにすでに
歪んだ自己顕示欲が垣間見られる。仁者でもなければ身の程をわきまえた匹夫でもない、
身の程知らずとして世界に大迷惑をかけようとする不埒な小人としての素性が見受けられる。
その立場はといえばやはり、君子でも単なる小人でもない、政商あたりの奇形的な身分で
あっただろうこともうかがえる。君子が小人を治めることで世の中も成り立つわけだから、
君子も小人も世の中にとって欠くべからざる存在であるとはいえるが(昔の薩摩藩のように
藩が裕福だからといって猫も杓子も君子階級である武士になったりするのも考え物である)、
小人身分でありながら上位の君子並みの権限を持つ政商のような身分はといえば、世の中に
とって百害あって一利もない存在なわけだから、そのことからなるコンプレックスにかられての
歪んだ自己顕示欲を抱き、それを形而上の超越神などに偽託しただろうことが察せるのである。
造った」などと豪語しながら、その内の一部の儲や世界しか救わないとしているものだから、
仁義道徳を決定的に侵害する純度100%の邪神であることまでもが確定しているのである。
一部の事物を司る神であるというのなら、それ相応の扱いによる仁政への
役立てなどもまだ期待ができるのに、わざわざ「世界の全てを司る」などと
したものだから、仁政実現の上では根絶対象となることまでもが避けられない。
そして、そうでありながら一部の人間しか救わないような態度でいる神などを信じようとした
人間たち自身からして、人並み以上の不誠実さを帯びていたことが明らかである。せめてでも、
阿弥陀仏のように「西方浄土において一切衆生を救済の対象とする」と誓約しているような
神仏を信じたりしたのならば、それをして信者たち自身が不誠実である根拠などにはならない
のだが、「全世界を統べながら信じるものだけを救う」などという神を信じたものだから、
それによって自分たち自身の性根からの不誠実さまでをも露呈させてしまったのである。
世界の全てを統べるといいながら、一部の信者しか救わないともする。そこにすでに
歪んだ自己顕示欲が垣間見られる。仁者でもなければ身の程をわきまえた匹夫でもない、
身の程知らずとして世界に大迷惑をかけようとする不埒な小人としての素性が見受けられる。
その立場はといえばやはり、君子でも単なる小人でもない、政商あたりの奇形的な身分で
あっただろうこともうかがえる。君子が小人を治めることで世の中も成り立つわけだから、
君子も小人も世の中にとって欠くべからざる存在であるとはいえるが(昔の薩摩藩のように
藩が裕福だからといって猫も杓子も君子階級である武士になったりするのも考え物である)、
小人身分でありながら上位の君子並みの権限を持つ政商のような身分はといえば、世の中に
とって百害あって一利もない存在なわけだから、そのことからなるコンプレックスにかられての
歪んだ自己顕示欲を抱き、それを形而上の超越神などに偽託しただろうことが察せるのである。
超越神の仮面の内側に潜む歪んだ性格が信者たちにも落とし込まれた結果、
救いがたい不誠実さを内面に抱えながら、表向きだけは立派な修辞で取り繕うような、
典型的な偽善者が大勢作り上げられて行くことともなったのだった。
そのような邪教による歪んだ性格の植え付けもなければ、仁義道徳による謹厳さの教示なども
さして施されたことのない、東南アジアの田舎あたりの人間などは、いたって素朴なものである。
現代的な観点からすれば危ういほどにも素直だったりする、そんなままでいられたなら
それでもいいにしろ、案の定、一時はキリスト教圏による侵略などによって極度の疲弊に
晒されたりもしていたわけで(ブラックアフリカなどは今でもそのような状態にある)、
毒を制する薬としての、作為的な仁義道徳の修得なども多少はあってしかるべきことだといえる。
仮に今すぐ、歪んだ性格を信者に植え付けるような邪教がこの世から絶やされたとしても、
その禍根が当分甚だしいままであり続けることも間違いない。そこにプラマイゼロへの回復を
目指した矯正を施す目的で、仁徳の尊重を奨励して行くことなどもそれなりに必要であろう。
仁徳を尊ぶ儒者などもまた、>>294のように傍目には頑迷であるように見られることもあるわけだが、
それも、偽善者や悪人が増え過ぎた世の中における特効薬的な姿勢であるとして、大目に見て行くしかない。
「子張政を問う。子曰く、之れに居りて倦むこと無く、之れを行うには忠を以ってす」
「門弟の子張が政治のあり方を先生にお聞きした。先生は言われた。『任務にあっては決して倦むことなく、
奉行に際しても忠義を尽くすことだ』(難儀な仕事でも決して倦むことなく、忠義を尽くして執り行って
いくことで仁政も実現される。我田引水者はそんなことも始めから倦んで放り投げているのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・顔淵第十二・一四)
救いがたい不誠実さを内面に抱えながら、表向きだけは立派な修辞で取り繕うような、
典型的な偽善者が大勢作り上げられて行くことともなったのだった。
そのような邪教による歪んだ性格の植え付けもなければ、仁義道徳による謹厳さの教示なども
さして施されたことのない、東南アジアの田舎あたりの人間などは、いたって素朴なものである。
現代的な観点からすれば危ういほどにも素直だったりする、そんなままでいられたなら
それでもいいにしろ、案の定、一時はキリスト教圏による侵略などによって極度の疲弊に
晒されたりもしていたわけで(ブラックアフリカなどは今でもそのような状態にある)、
毒を制する薬としての、作為的な仁義道徳の修得なども多少はあってしかるべきことだといえる。
仮に今すぐ、歪んだ性格を信者に植え付けるような邪教がこの世から絶やされたとしても、
その禍根が当分甚だしいままであり続けることも間違いない。そこにプラマイゼロへの回復を
目指した矯正を施す目的で、仁徳の尊重を奨励して行くことなどもそれなりに必要であろう。
仁徳を尊ぶ儒者などもまた、>>294のように傍目には頑迷であるように見られることもあるわけだが、
それも、偽善者や悪人が増え過ぎた世の中における特効薬的な姿勢であるとして、大目に見て行くしかない。
「子張政を問う。子曰く、之れに居りて倦むこと無く、之れを行うには忠を以ってす」
「門弟の子張が政治のあり方を先生にお聞きした。先生は言われた。『任務にあっては決して倦むことなく、
奉行に際しても忠義を尽くすことだ』(難儀な仕事でも決して倦むことなく、忠義を尽くして執り行って
いくことで仁政も実現される。我田引水者はそんなことも始めから倦んで放り投げているのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・顔淵第十二・一四)
 結局、仁政を実現して行く上でも、ある程度は地の利だとか手堅い都市設計だとかに
結局、仁政を実現して行く上でも、ある程度は地の利だとか手堅い都市設計だとかに 頼って行く必要が出てくる場合がある。それは、我田引水を目的とした悪徳商売や権力犯罪を
牽制するためであり、決して為政者たる自分自身が独自にいい思いをしたりするためではない。
昔ながらの王宮や城郭を中心として形成された都市構造などは、その中央部に勝手に立ち入る
ことができない民間の商売人などに身の程を思い知らせると共に、その中央部にどっかりと
居座る王君や重臣が誰しもからの注目対象となって、隠れた不品行などに及べないように
する効果までをも持ち合わせていた。確かに、始皇帝などのように自己顕示欲の過剰によって
人々を重労働で困窮に陥れるほどにも甚大な王宮(阿房宮)を拵えたりすることもあったわけだが、
その逆に、自らは豪華な王宮を造ることなどを拒み通していたにもかかわらず、重臣の蕭何が勝手に
豪壮な王宮(未央宮)を造営したものだから腹を立て、「これぐらいのものがなければ帝王としての
威厳が保てません」となだめられてようやく納得した高祖劉邦のような事例もあるわけであり、後者の
事例などは、本当に必要にかられてやむなく王宮中心の都を構築していった事例であることが確かである。
民主主義の蔓延によって、王君を中心とした制度や都市設計などが軒並み撤廃や有名無実化されて
しまっている現代においては、現存する王宮や城郭といえばただの観光地扱い、金持ちが勝手に王宮をも
上回るような豪華絢爛な自宅を建築したりするのもしたい放題な状態となってしまっている。だからと
いってそのような金持ちが誰しもからの監視対象になったりするわけでもなく、王都の中心にどっかりと
宮殿を据えてそこに居座る王君などよりも遥かに無責任なままでのやりたい放題が可能となっている。
それは結局、封土を責任持って統治する主君の住処こそを中心として都市を設計して行く場合
などと比べても、世の中にかける負担がより大きなものと化す結果を招いてしまっているのである。
素封家が囲い込む富の分量が、世の中で取り回せる富の分量をも上回るような事態と化してしまう
ようならば、自明なこととして世の中のほうが貧困に見舞われることとなる。素封家は基本民間人だから、
「民主主義」の名の下でその主権を尊重される人間の内にも入ることとなる。だからといっていち私人
としての身の程を大きく逸脱するほどもの富を私物化したりしようものなら、そのせいで自分たちが
世の中に対して加える負担が、責任ある王君が年貢や納税によって世の中にかける負担すらをも上回る
ようなことにすらなってしまうわけである。資本主義の民主主義社会ともなればそのような体たらくと
化してしまうのが常套的なことであり、民衆にこそ主権を与えることで、王侯貴族が世の中に加える負担
を最小化ないし抹消しようとした民主化の試みは、完全に本末転倒の結果を来たしてしまったのである。
むろん、民主主義などというもの自体、始めから素封家の独り勝ちこそを真の目的としていたのだとも
言えなくはないわけで、結局のところ、これといった王侯将相の下で全体社会からの統率下に置かれる
ことでのみ、民間人もまた共食い状態などに陥ったりすることなく最善度の豊かさを謳歌して行ける
ように、人間社会の原理的な構造上からしてできているのだと結論付けることもできるわけである。
始皇帝のように、民衆を困窮に陥れるほどもの圧政を敷いたりするわけでもない主君が、素封家の横暴
によって世の中が困窮に陥れられたりすることを抑止するためにこそ全体規模で君臨する世の中こそは、
人々が最大級の豊かさに与れる世の中ともなることを十分に理解して、万端の納得の下に、「民主主義に
よってこそ人々もまた最大級の豊かさに与れる」という事実誤認を払拭して行くようにすべきなのである。
ようならば、自明なこととして世の中のほうが貧困に見舞われることとなる。素封家は基本民間人だから、
「民主主義」の名の下でその主権を尊重される人間の内にも入ることとなる。だからといっていち私人
としての身の程を大きく逸脱するほどもの富を私物化したりしようものなら、そのせいで自分たちが
世の中に対して加える負担が、責任ある王君が年貢や納税によって世の中にかける負担すらをも上回る
ようなことにすらなってしまうわけである。資本主義の民主主義社会ともなればそのような体たらくと
化してしまうのが常套的なことであり、民衆にこそ主権を与えることで、王侯貴族が世の中に加える負担
を最小化ないし抹消しようとした民主化の試みは、完全に本末転倒の結果を来たしてしまったのである。
むろん、民主主義などというもの自体、始めから素封家の独り勝ちこそを真の目的としていたのだとも
言えなくはないわけで、結局のところ、これといった王侯将相の下で全体社会からの統率下に置かれる
ことでのみ、民間人もまた共食い状態などに陥ったりすることなく最善度の豊かさを謳歌して行ける
ように、人間社会の原理的な構造上からしてできているのだと結論付けることもできるわけである。
始皇帝のように、民衆を困窮に陥れるほどもの圧政を敷いたりするわけでもない主君が、素封家の横暴
によって世の中が困窮に陥れられたりすることを抑止するためにこそ全体規模で君臨する世の中こそは、
人々が最大級の豊かさに与れる世の中ともなることを十分に理解して、万端の納得の下に、「民主主義に
よってこそ人々もまた最大級の豊かさに与れる」という事実誤認を払拭して行くようにすべきなのである。
「天下に王有り、地を分け国を建て、都を置き邑を立て、廟祧壇墠を設けて之れを祭り、親疏多少の数を為す」
「天下に帝王があれば、必ず地を諸国に分けて国を立て、都や村も指定して、それぞれに規則に則った祭祀
のため廟壇(日本なら神社に相当)を設置させる。それによって万人の親疎多少を統制して行くようにする。
(このような事業がもたらす効能は上記の通りである。確かな理由があるのだから決して軽んじてはならない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭法第二十三より)
「天下に帝王があれば、必ず地を諸国に分けて国を立て、都や村も指定して、それぞれに規則に則った祭祀
のため廟壇(日本なら神社に相当)を設置させる。それによって万人の親疎多少を統制して行くようにする。
(このような事業がもたらす効能は上記の通りである。確かな理由があるのだから決して軽んじてはならない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭法第二十三より)
ヴァカ。^^
「知る」ということが、人間のあらゆる行為のうちでも第一の自力作善にあたる。
だから「格物致知誠意正心修身斉家治国平天下(大学)」が善行の順序ともなるのである。
実際に仕官して主君に臣従したりするのは「修身」からであり、そこまでの「格物致知誠意正心」
は自学自習によってこそ達成して行くものである。「主君の弟子」たる君子階級としての事業に
取り組むことには多少の他力依存が介在して行くわけだが、それ以前の自学自習にかけては
独立独行を主とし、君子としての事業に望むに際してもあくまで自力本位でいられるようにする。
他者への信用に基づく依頼もあり得るにしろ、あくまで自力で知見を得て独立的な成果を挙げて行く
ことを主体とするのが君子としてのあり方である。だからこそ「仁義礼智信」の優先順位でもある。
信も智もあった上で智のほうが信よりも優位、自力も他力もあった上で自力のほうが他力よりも優位
であるとするのが君子であり、善人たるもの、誰しもが潜在的にその序列をわきまえているものである。
自力と他力、智と信の序列すらをも見損なってしまう所に君子と小人、善人と悪人の決定的な分岐点がある。
孔子は妾腹の私生児でいながら自ら家系を調べ上げて、孔家の正式な跡取りとして学者や君子階級と
しての事績を挙げた。一方、イエスも妾腹の私生児でいたものの、自分の系譜などはろくに調べもせず、
「自分は神の子だ」などとうそぶいての依存心まみれな邪教を触れ回り、いち匹夫小人としての身分の
ままに磔刑に処されてその人生を完全に終え去った。孔子は自己学習を主体として君子となり、イエスは
自学自習を拒んでの依存心まみれによって、小人としての度し難さをかえって深刻化させた。これらの
事例こそは、智と信の優先順位の正誤が、君子と小人を決定的に分断した好例中の好例ともなっている。
信に一辺倒でろくにものも知らないでいる、それなら別に害はないのである。それ以上にも、
信に溺れたままで歪んだ知識を身に付けようとするところにこそ致命的な問題が生ずる。
だから「格物致知誠意正心修身斉家治国平天下(大学)」が善行の順序ともなるのである。
実際に仕官して主君に臣従したりするのは「修身」からであり、そこまでの「格物致知誠意正心」
は自学自習によってこそ達成して行くものである。「主君の弟子」たる君子階級としての事業に
取り組むことには多少の他力依存が介在して行くわけだが、それ以前の自学自習にかけては
独立独行を主とし、君子としての事業に望むに際してもあくまで自力本位でいられるようにする。
他者への信用に基づく依頼もあり得るにしろ、あくまで自力で知見を得て独立的な成果を挙げて行く
ことを主体とするのが君子としてのあり方である。だからこそ「仁義礼智信」の優先順位でもある。
信も智もあった上で智のほうが信よりも優位、自力も他力もあった上で自力のほうが他力よりも優位
であるとするのが君子であり、善人たるもの、誰しもが潜在的にその序列をわきまえているものである。
自力と他力、智と信の序列すらをも見損なってしまう所に君子と小人、善人と悪人の決定的な分岐点がある。
孔子は妾腹の私生児でいながら自ら家系を調べ上げて、孔家の正式な跡取りとして学者や君子階級と
しての事績を挙げた。一方、イエスも妾腹の私生児でいたものの、自分の系譜などはろくに調べもせず、
「自分は神の子だ」などとうそぶいての依存心まみれな邪教を触れ回り、いち匹夫小人としての身分の
ままに磔刑に処されてその人生を完全に終え去った。孔子は自己学習を主体として君子となり、イエスは
自学自習を拒んでの依存心まみれによって、小人としての度し難さをかえって深刻化させた。これらの
事例こそは、智と信の優先順位の正誤が、君子と小人を決定的に分断した好例中の好例ともなっている。
信に一辺倒でろくにものも知らないでいる、それなら別に害はないのである。それ以上にも、
信に溺れたままで歪んだ知識を身に付けようとするところにこそ致命的な問題が生ずる。
キリスト教徒も、そのような歪んだ知識を洋学などとして構築しながら狂信を続けてきたものだから、
それらの知識を実際の世の中に適用しつつ世界を征服して行った結果、自分たちを含む全人類を
滅亡の危機に陥れるほどもの事態を招いてしまっているのである。そんなことは、無知を開き直って
信仰一辺倒でいようとする浄土教あたりなら決して成し得なかったことであり、むしろそんな所業に
までは至り得なければこそ、無知を開き直っての信仰のほうがマシであることまでもが実証されたのである。
ある程度以上の規模の悪逆非道というのはいつも、歪んだ知識に基づく自己正当化や悪行の体系化を
帯びているものであり、そのような知識自体を正当化する最終手段が邪神への信仰であったりもする。
単なる無知でもなければ単なる信仰でもなく、信>智という間違った序列に基づく邪信や歪んだ知識
こそが人類を滅亡の危機に陥れるほどもの大害悪となり得る。今までにも何度か指摘した位相上の
問題であり、故にこそ難解でもあるわけだが、ことは重大であるから、決して軽んじてもならない。
「仁者は憂えず、知者は惑わず、勇者は懼れず」
「(現代語訳は不要だろう。仁徳に基づく上知はむしろ憂いや惑いを排するものである。仁徳の伴わない
歪んだ知識こそは憂いや惑いや懼れを生じさせ、狂信でも抱いていないではいられなくするのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・三〇より)
それらの知識を実際の世の中に適用しつつ世界を征服して行った結果、自分たちを含む全人類を
滅亡の危機に陥れるほどもの事態を招いてしまっているのである。そんなことは、無知を開き直って
信仰一辺倒でいようとする浄土教あたりなら決して成し得なかったことであり、むしろそんな所業に
までは至り得なければこそ、無知を開き直っての信仰のほうがマシであることまでもが実証されたのである。
ある程度以上の規模の悪逆非道というのはいつも、歪んだ知識に基づく自己正当化や悪行の体系化を
帯びているものであり、そのような知識自体を正当化する最終手段が邪神への信仰であったりもする。
単なる無知でもなければ単なる信仰でもなく、信>智という間違った序列に基づく邪信や歪んだ知識
こそが人類を滅亡の危機に陥れるほどもの大害悪となり得る。今までにも何度か指摘した位相上の
問題であり、故にこそ難解でもあるわけだが、ことは重大であるから、決して軽んじてもならない。
「仁者は憂えず、知者は惑わず、勇者は懼れず」
「(現代語訳は不要だろう。仁徳に基づく上知はむしろ憂いや惑いを排するものである。仁徳の伴わない
歪んだ知識こそは憂いや惑いや懼れを生じさせ、狂信でも抱いていないではいられなくするのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・三〇より)
削除(by投稿者)
削除(by投稿者)
歪んだ知識が無知以上の害悪をこの世にもたらす実例の一つとして、
実定法の悪用が無法状態以上もの放辟邪侈を実現するということがある。
ほとんど無法状態だった春秋戦国時代の諸侯による統治以上もの暴政が、
法家支配を主体とした秦始皇帝による統一支配によって中国にもたらされたことなどが
その歴史的な実例である。中国史の場合、法家や名家や縦横家などの劣悪な教学を
宗教的に正当化したりまでしたようなことがほぼ皆無だから、そのあたりが分かりやすい。
西洋史などの場合は、法家にあたる理念を聖書信仰で正当化したり、名家に当たる
理念をイデア主義で正当化したり、縦横家に当たる理念を悪魔崇拝で正当化したりと
いったような不埒な正当化までもが噛まされて来たものだから、中国史よりはずっと
劣悪な異端の教学が世の中に及ぼしていた悪影響の構造が理解しにくい。けれども、
結局のところは、中国の法家や名家や縦横家などが世の中に与えていた悪影響と全く
同じような悪影響を、聖書信仰やイデア主義や悪魔崇拝が及ぼしていたことにも
変わりはないのである。(もちろん、より損害が甚大だったということはある)
邪教邪学による劣悪な教学の正当化の一環として、無為自然の価値を貶めるということがある。
アダムの原罪を根拠として不労を罪とする旧約の教義などがその実例であり、人々に無為自然
の価値を見失わせることで、「悪いことをするぐらいなら何もしないでいたほうがマシ」という
聞いてみれば当たり前な事実関係への誤認をもけしかけるのである。それにより、人々の悪逆非道
への自制心が振り切れて、宗教的な正当化などしない場合以上もの害悪をもたらして来たのである。
(「韓非子」にも不労を罪とするような記述はあるが、宗教的な正当化までは為されていない)
実定法の悪用が無法状態以上もの放辟邪侈を実現するということがある。
ほとんど無法状態だった春秋戦国時代の諸侯による統治以上もの暴政が、
法家支配を主体とした秦始皇帝による統一支配によって中国にもたらされたことなどが
その歴史的な実例である。中国史の場合、法家や名家や縦横家などの劣悪な教学を
宗教的に正当化したりまでしたようなことがほぼ皆無だから、そのあたりが分かりやすい。
西洋史などの場合は、法家にあたる理念を聖書信仰で正当化したり、名家に当たる
理念をイデア主義で正当化したり、縦横家に当たる理念を悪魔崇拝で正当化したりと
いったような不埒な正当化までもが噛まされて来たものだから、中国史よりはずっと
劣悪な異端の教学が世の中に及ぼしていた悪影響の構造が理解しにくい。けれども、
結局のところは、中国の法家や名家や縦横家などが世の中に与えていた悪影響と全く
同じような悪影響を、聖書信仰やイデア主義や悪魔崇拝が及ぼしていたことにも
変わりはないのである。(もちろん、より損害が甚大だったということはある)
邪教邪学による劣悪な教学の正当化の一環として、無為自然の価値を貶めるということがある。
アダムの原罪を根拠として不労を罪とする旧約の教義などがその実例であり、人々に無為自然
の価値を見失わせることで、「悪いことをするぐらいなら何もしないでいたほうがマシ」という
聞いてみれば当たり前な事実関係への誤認をもけしかけるのである。それにより、人々の悪逆非道
への自制心が振り切れて、宗教的な正当化などしない場合以上もの害悪をもたらして来たのである。
(「韓非子」にも不労を罪とするような記述はあるが、宗教的な正当化までは為されていない)
信教それ自体は人々の無知蒙昧をけしかけるものだったりもするわけだが、それと同時に
根本的無知に即した妄動をけしかけたりもする、そのような信教こそは最悪級のカルトであり、
聖書信仰や、日蓮宗やヒンズー教の異端派などがその条件を満たしていたりする一方、
浄土信仰やイスラム教や拝火教などは辛うじてその条件を満たしていない。ここにこそ、
作為的な廃絶すらをも心がけて行くべきか否かの境界線があり、前者はそうしてすら
行かねばならない一方、後者はそこまではする必要がないようになっている。ただ、
両者とも人々の聡明さを積極的に伸ばしていくほどもの良質さは備えていないわけだから、
必要もなく積極的に振興していったりすべきだとまでは言えない点でも共通している。
(最悪級のカルト撃退のために、後者のようなマシな教学の振興が是とされ得る場合はある)
信教が優良な教学のより一層の振興に協力してくれるようならば、そのような信教をも推進
して行くべきだとすらいえるが、そのような信教こそはさしてうまみのないものだったりもする。
信教を儲けのために利用したりすることもなく、厳しい修行に励み続けるものだったりするから、
なかなか従事者を募ることからして難しかったりする。そこではむしろ、世の中の側が家系主義を講じて、
身寄りのない次男三男などを義務的に宗門に入れさせるなどの支援すらもが必要になって行くのであり、
まあ、儲けのための信教を好んでいたような人間が鞍替えしたがれるようなものではないといえる。
それで結局、自分から自主的に信教を好んで行くような人間のほとんどは精神的な堕落や儲けを
期待するものばかりとなるわけだから、信教全般の積極的な推進というものには歯止めをかけて
行くようにすべきだといえる。宗教を信じているからといって偉いなどとは限らない、むしろ
賤しい場合すらある。それぐらいのところに信教の扱いを集約させて、アブラハム教的な
「信教ありき」の姿勢を脱却した、より自由な文化振興を育んでいけるようになればいいのである。
根本的無知に即した妄動をけしかけたりもする、そのような信教こそは最悪級のカルトであり、
聖書信仰や、日蓮宗やヒンズー教の異端派などがその条件を満たしていたりする一方、
浄土信仰やイスラム教や拝火教などは辛うじてその条件を満たしていない。ここにこそ、
作為的な廃絶すらをも心がけて行くべきか否かの境界線があり、前者はそうしてすら
行かねばならない一方、後者はそこまではする必要がないようになっている。ただ、
両者とも人々の聡明さを積極的に伸ばしていくほどもの良質さは備えていないわけだから、
必要もなく積極的に振興していったりすべきだとまでは言えない点でも共通している。
(最悪級のカルト撃退のために、後者のようなマシな教学の振興が是とされ得る場合はある)
信教が優良な教学のより一層の振興に協力してくれるようならば、そのような信教をも推進
して行くべきだとすらいえるが、そのような信教こそはさしてうまみのないものだったりもする。
信教を儲けのために利用したりすることもなく、厳しい修行に励み続けるものだったりするから、
なかなか従事者を募ることからして難しかったりする。そこではむしろ、世の中の側が家系主義を講じて、
身寄りのない次男三男などを義務的に宗門に入れさせるなどの支援すらもが必要になって行くのであり、
まあ、儲けのための信教を好んでいたような人間が鞍替えしたがれるようなものではないといえる。
それで結局、自分から自主的に信教を好んで行くような人間のほとんどは精神的な堕落や儲けを
期待するものばかりとなるわけだから、信教全般の積極的な推進というものには歯止めをかけて
行くようにすべきだといえる。宗教を信じているからといって偉いなどとは限らない、むしろ
賤しい場合すらある。それぐらいのところに信教の扱いを集約させて、アブラハム教的な
「信教ありき」の姿勢を脱却した、より自由な文化振興を育んでいけるようになればいいのである。
「礼は本に反りて古えを修む、其の初めを忘れざるなり。故に凶事には詔せず、朝事には
楽を以てす。醴酒の用ありて、玄酒の尚びあり。割刀の用ありて、鸞刀の貴びあり。莞簟の安ありて、
稿靺の設けあり。是の故に先王の礼を制するや、必ず主有るなり。故に述べて多くを学ぶ可きなり」
「礼はその根本に回帰して古えのあり方をあえて修め、本来のあり方を忘れないようにすることがある。
要人の死などの凶事があれば詔勅を控え、養老養賢などの礼遇に際しては雅楽などの催事を行う。
本物の上等酒を用意しながらも、神前には酒に見立てた水を供えたりする。本当によく切れる刀の
用意がありながらも、鈴を付けた刃のない儀礼用の刀を用いたりする。畳や筵の席も用意しながらも、
藁で拵えた古風な席を用意したりする。これらは先王の礼にまつわる主意に即して執り行われる
ことであり、(表層だけ鑑みてもなかなかその意義が計り知りがたいものであるから、)よく勉強して
その主意までをも計り知れるようにならなければならない。(礼は法律のようにただ規律を忘れずに
いればいいというばかりのものではない。今となっては不可解であるような礼法の主意などまでをも
自らの勉強によって調べ上げ、その根本的な意義までをも忘れないでいられるようにしなければならない。
これこそは、礼が実定法などと違って人々の精神的怠惰を禁じていく材料ともなっている。勉強
への積極性に基づく精神の自由を養生させていく手段として、礼の修得が有効ともなるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼器第十より)
楽を以てす。醴酒の用ありて、玄酒の尚びあり。割刀の用ありて、鸞刀の貴びあり。莞簟の安ありて、
稿靺の設けあり。是の故に先王の礼を制するや、必ず主有るなり。故に述べて多くを学ぶ可きなり」
「礼はその根本に回帰して古えのあり方をあえて修め、本来のあり方を忘れないようにすることがある。
要人の死などの凶事があれば詔勅を控え、養老養賢などの礼遇に際しては雅楽などの催事を行う。
本物の上等酒を用意しながらも、神前には酒に見立てた水を供えたりする。本当によく切れる刀の
用意がありながらも、鈴を付けた刃のない儀礼用の刀を用いたりする。畳や筵の席も用意しながらも、
藁で拵えた古風な席を用意したりする。これらは先王の礼にまつわる主意に即して執り行われる
ことであり、(表層だけ鑑みてもなかなかその意義が計り知りがたいものであるから、)よく勉強して
その主意までをも計り知れるようにならなければならない。(礼は法律のようにただ規律を忘れずに
いればいいというばかりのものではない。今となっては不可解であるような礼法の主意などまでをも
自らの勉強によって調べ上げ、その根本的な意義までをも忘れないでいられるようにしなければならない。
これこそは、礼が実定法などと違って人々の精神的怠惰を禁じていく材料ともなっている。勉強
への積極性に基づく精神の自由を養生させていく手段として、礼の修得が有効ともなるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼器第十より)
487 KB かよ。かきすぎ
500になるまでつかえよ
▲ページ最上部
ログサイズ:696 KB 有効レス数:321 削除レス数:0
不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。
思想・哲学掲示板に戻る 全部 次100 最新50
スレッドタイトル:聖書 Part9
